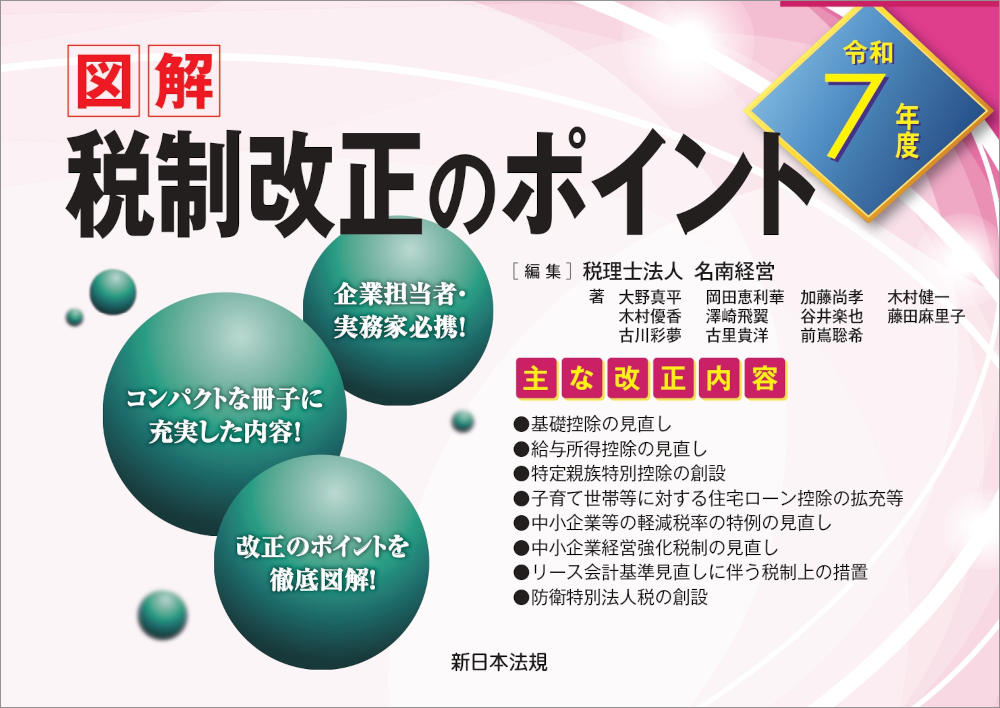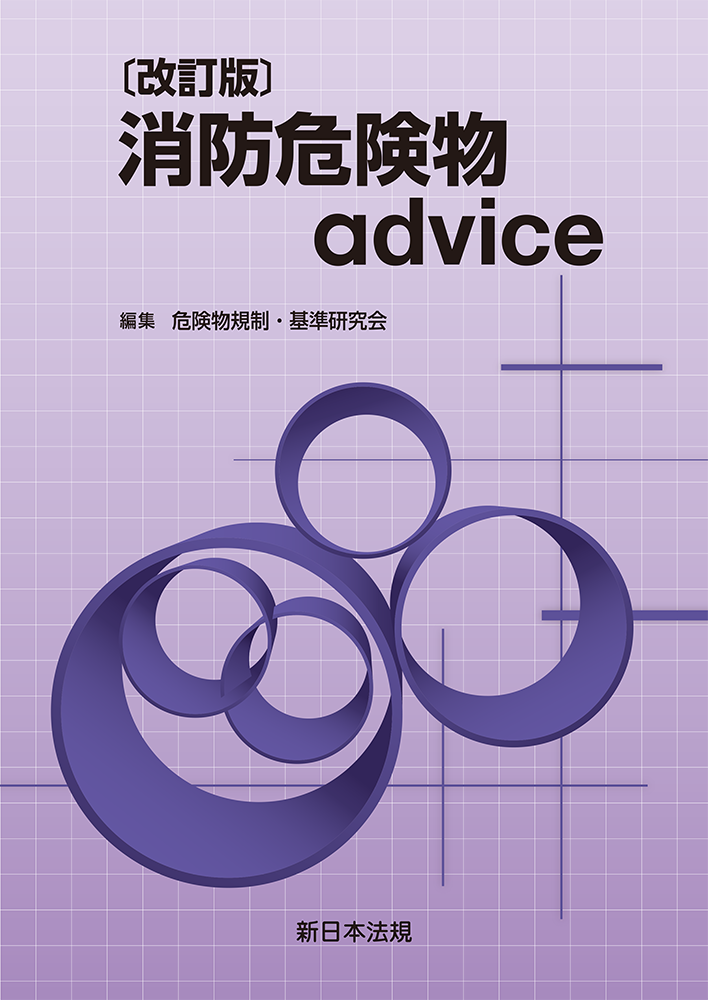解説記事2019年09月23日 未公開判決事例紹介 評価通達6項をめぐる税務訴訟で納税者敗訴(2019年9月23日号・№804)
未公開判決事例紹介
評価通達6項をめぐる税務訴訟で納税者敗訴
通達による評価が著しく不適当と認められる場合は
読者からの反響が大きかった本誌802号(2019.9.9)40頁で紹介した税務訴訟の判決全文について、仮名処理した上で紹介する。
○相続財産の一部の土地及び建物の価額の評価について、課税当局が評価通達6項を適用し、鑑定評価額により評価し更正処分等が行われたことに対する相続税更正処分等取消請求事件。納税者(原告)は評価通達6の「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」場合とは、飽くまで時価評価に影響を及ぼす特別の事情がある場合を指すと解すべきであると主張したが、東京地方裁判所(鎌野真敬裁判長)は、「評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって特定の納税者あるいは特定の財産について評価することが許されるか否かは、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情があるか否かという観点から判断されるべきものである」などとし、納税者の請求を棄却する判決を下した(令和元年8月27日、棄却)。
主 文
1 原告らの請求を、いずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 処分行政庁が平成28年4月27日付けで原告Aに対してした、被相続人B(以下「本件被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
2 処分行政庁が平成28年4月27日付けで原告Cに対してした、本件相続に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
3 処分行政庁が平成28年4月27日付けで原告Dに対してした、本件相続に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
第2 事案の概要
本件は、本件被相続人の相続人である原告らが、本件相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達。ただし、平成25年5月16日付け課評2-18による改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ、処分行政庁から、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして、本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた(以下、本件相続税の各更正処分を総称して「本件各更正処分」といい、過少申告加算税の各賦課決定処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と本件各賦課決定処分を総称して「本件各更正処分等」という。)ため、本件各更正処分等の各取消しを求める事案である。
1 関係法令等の定め
本件に関係する法令等の定めは、別紙1「関係法令等の定め」(編注:略)記載のとおりである(なお、同別紙で定めた略語等は、以下においても用いるものとする。)。
2 前提事実(証拠等を掲記したもののほかは、いずれも当事者間に争いがないか又は当事者が争うことを明らかにしない事実である。)
(1)本件相続の開始等
ア 本件被相続人は、大正7年3月17日に出生した者であり、平成24年6月17日に94歳で死亡し、本件相続が開始した。
イ(ア)本件被相続人の共同相続人は、本件被相続人の妻であるE(以下「訴外E」という。)、長女である原告C、長男である原告A、二男であるF(以下「訴外F」という。)及び養子である原告Dの5名であった(以下、本件被相続人の共同相続人であった上記5名を総称して「本件共同相続人」という。)。
なお、原告Dは、訴外Fの長男であり、平成20年8月19日に本件被相続人と養子縁組をした。
(イ)本件共同相続人は「本件被相続人の平成21年10月16日付け公正証書に係る遺言及び本件共同相続人の間で平成24年10月17日に行った遺産分割に従って、本件相続に係る相続財産を取得した。
ウ G興業株式会社(以下「G興業」という。)は、不動産の売買、賃貸借及び管理等を目的とする株式会社である。本件被相続人は、平成21年6月26日、G興業の代表取締役を辞任し、原告Aが、同日G興業の代表取締役に就任した。
(2)本件相続に係る相続財産等
ア 本件相続に係る相続財産には、東京都杉並区○○○○○○○○の土地(明細は別表1(編注:略)記載のとおり。以下「本件甲土地」という。)及び本件甲土地上に存する家屋番号○○○○○の建物(明細は別表2(編注:略)記載のとおり。以下「本件甲建物」といい、本件甲土地と併せて「本件甲不動産」という。)並びに神奈川県川崎市○○○○○○○○の土地(以下「本件乙土地」という。)及び本件乙土地上に存する建物(以下「本件乙建物」といい、本件乙土地と併せて「本件乙不動産」という。本件乙不動産の明細は別表3(編注:略)のとおり。また、本件甲不動産と本件乙不動産を併せて「本件各不動産」という。)が含まれていた。本件各不動産は、前記(1)イ(イ)の本件被相続人の遺言により原告Dが取得した。
原告Dは、平成25年3月7日付けで、買主であるHに対して本件乙不動産を総額5億1500万円で売却した(以下、同売却額を「本件乙不動産売却額」という。)。
イ(ア)本件甲建物は、JR中央線O駅から徒歩約5分に立地する共同住宅(44戸)及び保育園(1戸)として利用されている建物であり、本件甲土地上に基準容積率をほぼ完全に消化した状態で所在している。(甲5の1)
(イ)本件甲不動産は、本件被相続人が、平成21年1月30日付けで、売主である株式会社Iから総額8億3700万円で購入したものであった(以下、同購入額を「本件甲不動産購入額」という。)。
なお、本件被相続人は、同日付けでM信託銀行から6億3000万円を借り入れており(当該借入れについてG興業、訴外E、原告A及び訴外Fが連帯保証をした。)、同銀行がその際に作成した貸出稟議書(乙9)の採上理由欄には「相続対策のため不動産購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があったもの。」との記載がある。(乙8、9)
ウ(ア)本件乙建物は、JR東海道本線K駅から徒歩約13分に立地する共同住宅として利用されている39個の専有部分からなる建物であり、本件乙土地上に容積率をほぼ完全に消化した状態で所在している。(甲5の2)
(イ)本件乙不動産は、本件被相続人が、平成21年12月25日付けで、売主である株式会社Lから総額5億5000万円で購入したものであった(以下、同購入額を「本件乙不動産購入額」といい、本件甲不動産購入額及び本件乙不動産売却額と総称して「本件各取引額」という。)。
なお、本件被相続人は、同月21日付けで、訴外Eから4700万円を借り入れた。また、本件被相続人は、同月25日付けでM信託銀行から3億7800万円を借り入れており(当該借入れについてG興業、訴外E、原告A及び訴外Fが連帯保証をした。)、同銀行がその際に作成した貸出稟議書(乙14)の採上理由欄には「相続対策のため本年1月に630百万円の富裕層ローンを実行し不動産購入。前回と同じく相続税対策を目的として第2期の収益物件購入を計画。購入資金につき、借入の依頼があったもの。」との記載がある。(乙11、13、14)
(3)本件各更正処分等に至る経緯等
ア 原告らは、平成25年3月11日、別表4(編注:略)の各「申告」欄のとおり、処分行政庁に対して本件相続税の申告(以下「本件申告」という。)をした。
原告らは、本件申告において、評価通達の定める評価方法により、本件甲土地の価額を1億1367万6734円(ただし、租税特別措置法69条の4(平成25年法律第5号による改正前のもの)に規定する特例(以下「小規模宅地等特例」という。)を適用する前の価額)、本件甲建物の価額を8636万4740円(以下、上記の本件甲土地の価額との合計額である2億0004万1474円を「本件甲不動産通達評価額」という。)、本件乙土地の価額を5816万2741円、本件乙建物の価額を7550万2026円(以下、本件乙土地の価額との合計額である1億3366万4767円を「本件乙不動産通達評価額」といい、本件甲不動産通達評価額と本件乙不動産通達評価額を併せて「本件各通達評価額」という。)と評価した。
イ 札幌国税局長は、平成28年2月17日付けで、国税庁長官に対し、本件各不動産について評価通達6を適用し評価通達の定める評価方法によらずに他の合理的な評価方法によって評価することとしたい旨を上申し(以下「本件上申」という。)、国税庁長官は、同年3月10日付けで、札幌国税局長に対し、上記上申について「貴見のとおり取り扱うこととされたい」との指示(以下「本件指示」という。)をした。(乙16の1・2)
ウ 処分行政庁は、本件各不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、原告ら各自に対応した平成28年4月27日付けの各通知書(甲2の1~ 3。以下「本件各通知書」という。)を原告らに対し送達することにより、別表4(編注:略)の各「更正処分等」欄のとおり、本件各更正処分等をした。
本件各更正処分等において、本件甲不動産の価額(ただし、小規模宅地等特例を適用する前の価額)は、株式会社N不動産鑑定事務所の平成27年4月22日付け不動産鑑定評価(甲5の1。以下「本件甲不動産鑑定評価」という。)による鑑定評価額7億5400万円(以下「本件甲不動産鑑定評価額」という。内訳は、本件甲土地が3億0800万円、本件甲建物が4億4600万円である。)であり、本件乙不動産の価額は、P株式会社の同日付け不動産鑑定評価(甲5の2。以下「本件乙不動産鑑定評価」といい、本件甲不動産鑑定評価と併せて「本件各鑑定評価」という。)による鑑定評価額5億1900万円(以下「本件乙不動産鑑定評価額」といい、本件甲不動産鑑定評価額と併せて「本件各鑑定評価額」という。)であった。本件各鑑定評価額は、いずれも、不動産鑑定士により、不動産鑑定評価基準に基づき、本件相続開始時における本件各不動産の正常価格として算定されたものである。(甲5の1・2)
エ 原告らは、平成28年7月27日付けで、本件各更正処分等の全部の取消しを求め、それぞれ審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成29年5月23日付けで、上記の各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。
(4)本件各訴えの提起
原告らは、平成29年11月22日、本件各訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3 本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張
本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記5(1)ないし(3)の各(被告の主張)のほか、別紙2(編注:略)「本件各更正処分等の根拠及び適法性」記載のとおりである。
4 争点
(1)本件相続開始時における本件各不動産の時価(評価通達の定める評価方法によらない評価が許されるための特別の事情の内容及び本件各不動産におけるその有無。争点①)
(2)評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法の有無(争点②)
(3)本件各更正処分等の理由の提示に関する違法の有無(争点③)
5 争点に関する当事者の主張の要旨
(1)争点①(本件相続開始時における本件各不動産の時価)について
(被告の主張)
ア 相続税法22条に規定する時価について
(ア)相続税法22条に規定する時価とは、財産の取得の時における当該財産の客観的な交換価格をいうものと解されているところ、評価通達1(2)は、時価の意義について、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額による旨を定めている。
これは、相続財産の客観的な交換価格を個別に評価する方法を採ると、その評価方法、基礎資料の選択の仕方等によって異なった評価額が生じることが避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどから、あらかじめ定められた評価方法により画一的に財産の評価を行うこととしたものであり、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて合理的であるという理由に基づくものである。
そうすると、特に租税平等主義という観点からして、評価通達の定める評価方法が合理的なものである限り、これが形式的に全ての納税者に適用されることによって租税負担の実質的な公平を実現することができるものと解されるから、特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ評価通達の定める評価方法以外の方法によってその評価を行うことは、たとえその方法による評価額がそれ自体としては相続税法22条に規定する時価として許容できる範囲内のものであったとしても、納税者間の実質的負担の公平を欠くことになり、基本的には許されないものというべきである。
(イ)しかし、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合には、別の評価方法によることが許されるものと解すべきであり、このことは、評価通達6が、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する旨を定めていることからも明らかである。
したがって、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな場合には、評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があるものとして、他の合理的な時価の評価方法によることが認められるものと解すべきである。
イ 本件各不動産について評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があること
本件各不動産の評価においては、以下のとおり、評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情がある。
(ア)本件各通達評価額と本件各不動産の時価との間に著しいかい離があること
a 本件甲不動産について
本件甲不動産通達評価額は、2億0004万1474円であるところ、本件甲不動産鑑定評価額は、7億5400万円であり、本件甲不動産通達評価額は、本件甲不動産鑑定評価額の僅か約26.5%にすぎず、両者には著しい価額のかい離がある。
また、本件甲不動産通達評価額と本件甲不動産購入額を比べてみても、本件甲不動産購入額は、8億3700万円であり、本件甲不動産通達評価額は、本件甲不動産購入額の僅か約23.9%にすぎず、両者には著しい価額のかい離がある。
b 本件乙不動産について
本件乙不動産通達評価額は、1億3366万4767円であるところ、本件乙不動産鑑定評価額は、5億1900万円であり、本件乙不動産通達評価額は、本件乙不動産鑑定評価額の僅か約25.8%にすぎず、両者には著しい価額のかい離がある。
また、本件乙不動産通達評価額と本件乙不動産購入額及び本件乙不動産売却額を比べてみても、本件乙不動産購入額は、5億5000万円、本件乙不動産売却額は、5億1500万円であり、本件乙不動産通達評価額は、これらの僅か約24.3%又は約26%にすぎず、それぞれ著しい価額のかい離がある。
c 小括
以上のとおり、本件各通達評価額と本件各不動産の客観的交換価値を算定したものである本件各鑑定評価額(後記ウ参照)の間のほか、本件各通達評価額と本件各取引額の間には、いずれも著しいかい離が認められ、このような著しいかい離は、単なる評価手法の相違による当然の帰結として許容される範囲にとどまらない。
したがって、本件各通達評価額と本件各不動産の時価との間には著しいかい離が認められるというべきであり、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである。
(イ)本件各不動産に係る本件被相続人及び本件共同相続人による一連の行為について
a 本件被相続人及び本件共同相続人による本件各不動産の取得及び当該取得に伴う資金借入れ等の一連の行為は、原告らが本来負担すべき相続税を免れるという結果をもたらすものであったところ、①本件被相続人が、当時90歳であった平成20年に、M信託銀行に対して、当時代表取締役を務めていたG興業の事業承継について事業経営財務診断を申し込んでいたこと、②本件被相続人による本件各不動産の購入及び購入資金の借入れには、相続税の負担軽減の目的があったこと、③本件被相続人が、G興業の事業承継のための方策の一環として原告Dと養子縁組した時期(平成20年8月19日)と近接した時期に、本件各不動産を取得していること(本件甲不動産につき平成21年1月30日、本件乙不動産につき同年12月25日)等を総合して考慮すれば、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来原告らが負担すべき相続税を免れることになることを認識した上で本件各不動産を取得したと認められ、また、本件被相続人及び本件共同相続人による本件各不動産の取得及び当該取得に伴う資金借入れ等の一連の行為は、専ら相続対策を目的とするものであったと認められる。
本件被相続人は、本件各不動産の購入資金の大半をM信託銀行からの借入金により賄い、その借入金の総額は、本件各通達評価額を上回り、課税価格を圧縮する多額のものであったから、本件相続において、本件各不動産の価額を本件各通達評価額と評価すべきものとすると、原告らが本件各不動産を取得しなかったならば負担していたはずの相続税を免れる利益を享受するという結果を招来する。これは、本件被相続人が相続税の負担の軽減策を採ったことによるものであり、このような事態は、同様の軽減策を採らなかった他の納税者との間の租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる。
以上のとおり、本件においては、本件各不動産の評価について、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである。
b この点につき、原告らは、時価評価に影響を及ぼすことのない、納税者等の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素又は相続開始前後の一連の行為は、評価通達によらないことが許される特別の事情を基礎付けるものではない旨を主張する。
しかし、東京地裁平成5年2月16日判決・判タ845号240頁を始めとする多くの裁判例において、評価通達の定める評価方法による評価額と現実の取引価額との間に生じている開差を利用して相続税の負担の軽減を図る目的で行われた行為を前提とする相続について、評価通達によらないことが許される特別の事情があると判示されているのであって、上記の特別の事情の判断に当たり、節税目的や相続税負担の軽減目的があったことを考慮することが許されるのは明らかである。
ウ 本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的交換価値として適正に算定されたものであり、本件相続開始時における本件各不動産の時価を示すものであること
本件各鑑定評価額は、不動産鑑定士により不動産鑑定評価基準に準拠した方法で算定されたものであって、いずれも原価法による積算価格と収益還元法(DCF法及び直接還元法)による収益価格がそれぞれ試算され、両者が比較検討された上で、最終的には収益還元法による収益価格が重視され算定されたものであって、これらの鑑定評価の手法はいずれも合理性がある。また、本件各取引額は、いずれも、本件各通達評価額と比較して本件各鑑定評価額に近似している。
したがって、本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的交換価値として適正に算定されたものであり、本件相続開始時における本件各不動産の時価を示すものである。
エ 本件各通達評価額と本件各鑑定評価額のかい離の理由について
本件各通達評価額と本件各鑑定評価額の間にかい離が生じている理由については、様々な要因が複合的に影響した結果によるものであり、個別具体的な要因を特定できるものではないが、その要因としては、以下のような事情があると考えられる。
(ア)経済情勢に基づく分析
本件相続開始時の不動産市場の状況についてみると、不動産市場全体は、おおむね平成19年以降、サブプライムローン問題やリーマンショックの影響により価格の下落基調が続いたものの、平成21年以降その下落率が縮小して不動産市場の回復の兆しがみえたが、平成23年に東日本大震災が発生したために、平成25年頃までその回復が妨げられていた。現に、本件各不動産に係る各土地の路線価をみると、いずれも本件相続開始時前後で上昇していない。
他方、投資用不動産については、不動産市場全体とは異なる動きをしており、東日本大震災からの立ち直りが早かった。
しかるところ、本件各不動産は、いずれも投資用不動産に区分され、かつ、首都圏に所在する築浅の不動産であって、最寄り駅からの道程や周辺に生活利便施設が多数存在することなどから、非常に高い収益性が見込まれる投資対象としての価値が高い不動産であった。
したがって、本件各不動産は、本件相続開始時の経済情勢下において、いずれも客観的な交換価値が上昇していたと考えられるが、画一的な評価方法である評価通達の定める評価方法では、個別不動産の収益性を的確に価額へ反映させることが難しかったと想定される。
(イ)路線価方式による評価に関する分析
路線価の評定は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定され、周辺地域における不動産の一般的利用状況を踏まえて行われるが、評価の安全性も考慮した上で路線ごとに一律の金額で評定されるため、その土地の所在における個別の特性や利用状況等の複合的な影響によっては、個々の土地の客観的な交換価値が、路線価に基づく評価額と必ずしも合致しない可能性がある。
本件甲土地及び本件乙土地(以下「本件各土地」という。)は、いずれも高層の賃貸用共同住宅として最有効使用されており、かつ、本件甲建物及び本件乙建物(以下「本件各建物」という。)が容積率をほぼ消化していることなどからすれば、本件各土地の客観的な交換価値が、個々の土地の利用状況によらず路線ごとに一律に設定する路線価に基づく評価額よりも増加する可能性がある。また、本件各土地は、いずれも幹線道路の裏通り沿いに所在し、その路線価は、いずれも幹線道路沿いの路線価よりも低額であるが、不動産鑑定評価においては賃貸用共同住宅としての収益性に着目することになることから、立地の閑静さや固定資産税等の費用負担に照らし、幹線道路沿いにある賃貸用共同住宅よりも収益性において劣らず、むしろ収益性が高い可能性も考えられる。
したがって、本件各土地については、その所在の特性及び利用状況等により評価通達の定める評価方法である路線価方式による評価と客観的な交換価値にかい離が生じた可能性がある。
(ウ)貸家及び貸家建付地の評価に関する分析
本件各不動産は、収益性が顕著に高く投資対象としての価値が高い不動産であり、本件各鑑定評価額においては、建物及び土地が一体として評価され、本件各不動産の個別の用途や高い収益性等の特性が評価に反映されている。他方、本件各通達評価額においては、本件各建物につき、いずれも固定資産税評価額から30%が控除されて算出され、本件各土地につき、路線価方式に基づいて算出した金額(自用地としての価額)から、本件甲土地は21%、本件乙土地は18%がそれぞれ控除されて算出されているところ、これは、評価通達の定める評価方法においては、自家用家屋及び自用地のように権利の付着していない完全所有権の価値を最大とした上で、貸家及び貸家建付地については不動産の収益性にかかわらず一律に借家権の付着による減価額を控除して評価額を算出することとしているためであり、このような評価方法が、本件各不動産の個別の用途や高い収益性等の特性を反映できていないことが、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額のかい離の一因となっている可能性がある。
(エ)本件各鑑定評価における原価法による積算価格の算定に関する分析
本件各鑑定評価においては、原価法による積算価格を求めるに当たって、①Jリート(投資法人)が公表している賃貸用共同住宅取引事例における再調達価格が参考にされており、本件各建物は、投資用不動産としてグレードの高い物件であり、そのグレードの高さによるプレミアムが再調達価格に反映されていること、②本件甲不動産では土地及び建物の積算価格に20%を乗じた額が、本件乙不動産では30%を乗じた額が、それぞれ付帯費用(開発事業者利益のほか、設計管理料、公租公課等のその他費用)として加算されており、これらの事情も、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額のかい離の一因となった可能性がある。
(原告らの主張)
ア 評価通達の定める評価方法による相続財産の評価は、合理性が担保されているものとして久しく実務界において実施されており、評価通達は、行政先例法としての地位を築いているといえる。そして、例外的に上記方法による評価額を否定し、これによらない評価を認める評価通達の制定趣旨は、対象財産につき想定外の時価の下落事情が事後的に生じた場合に、評価通達が形式的に適用され、納税者の担税力が過大に測定されることが、担税力に応じた課税(租税公平主義)に反することに鑑み、このような場合に関する救済措置を設けた点にある。
そうすると、評価通達6に規定する「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」場合とは、飽くまで時価評価に影響を及ぼす特別の事情があり、評価通達の定める評価方法によると実質的な課税の公平を確保できない場合を指すと解すべきである。行政の恣意性を排除し、明確性や予測可能性を担保する観点からも、上記の特別の事情は、災害、地盤沈下、土壌汚染等の客観的事情の発生に限られなくてはならない。したがって、時価評価に影響を及ぼすことのない、納税者等の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素又は相続開始前後の一連の行為は、上記の特別の事情を基礎付けるものではない。
なお、前掲東京地裁平成5年判決等の被告が挙げる裁判例は、いずれも、当時のバブル経済を背景とした右肩上がりの地価上昇局面において、これらを利用した相続税の租税回避が横行し、その問題に対する社会的認識が共有されていた中での事例判決にとどまるものであり、地価が安定しているか、むしろ下落基調にある中での本件において参照されるべきものではない。
イ 本件各更正処分等は、本件各不動産につき想定外の時価の下落事情が事後的に生じた場合ではないにもかかわらず、評価通達6を適用した点で、前記アに述べた評価通達6の制定趣旨に反するものである。また、本件各更正処分等は、本件相続開始前後の本件被相続人及び本件共同相続人の一連の行為について、G興業の事業承継を円滑に進めるという主たる目的を捨象し、本件相続税をゼロにすることを目的とした行為(過度の節税目的による行為)であると決めつけ、評価通達6の適用要件を拡大解釈し、これを恣意的に適用したものである。
したがって、本件各更正処分等は、租税法律主義に反するものであるとともに、評価通達の定める評価方法によって本件各不動産の評価を行い、本件相続税の申告をした原告らの信頼を裏切った点で、法の一般原則たる信頼保護法理にも違反する。
ウ 本件各鑑定評価は、いずれも収益還元法を用いて土地及び建物を一括評価しているから、本件各通達評価額との間にかい離が生じることは、評価手法が異なる以上、当然である。評価通達の定める評価方法、とりわけ路線価方式は、合理性があるものとして広く社会に受け入れられているから、本件のようにその評価額と鑑定評価額に数倍ものかい離がある場合、鑑定評価額の適正さに疑問が呈されるべきである。また、本件各鑑定評価における原価法による積算価格の算定において、付帯費用という名目により根拠不明の金額が加算されている。
そもそも、相続財産の評価は、突然到来した被相続人の死により開始する相続に際してされるものであり、当該財産を不特定多数の者に売却することを前提としていないものであるから、収益の有無あるいは多寡に左右される収益還元法による評価や、経済合理性に基づく取引により形成される取引価額による評価は、その評価手法として著しく妥当性を欠く。
評価手法の妥当性の点をおくとしても、上記のかい離が、想定内のものであり、これをもって評価通達6の適用が肯定される特別の事情に該当しないことは、本件各更正処分等の後に、評価通達や本件各土地の路線価について、評価通達の定める評価方法による評価額を鑑定評価額に近づけるための改定が行われたことがうかがわれないことからも明らかである。そして、評価通達の定める評価方法による評価額と鑑定評価額の開差が著しいと思われる場合はまれではなく、その場合に全て評価通達6が適用されているわけではない。
しかるところ、本件を典型的な節税事案であるとして、例外規定である評価通達6を恣意的に用いて個別評価をすることは、租税公平主義が求める平等取扱原則に反するものである。
エ 以上によれば、本件相続開始時における本件各不動産の相続税法22条に規定する時価を本件各鑑定評価額とすることは許されない。
(2)争点②(評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法の有無)について
(原告らの主張)
評価通達6は、その要件を「国税庁長官の指示を受けて評価する」と定めているが、処分行政庁は、国税庁長官の指示を待たず、本件指示の約1年前に不動産鑑定会社2社に鑑定評価を依頼し、本件各鑑定評価を得た。つまり、処分行政庁は、評価通達6の定める国税庁長官の指示の要件を充足することなく、評価通達の定める評価方法による評価を否定する評価を先行して行っていた。
さらに、本件指示は、本件上申から約20日間という短期間で形式的に下されたものであり、再評価の「指示」ではなく、処分行政庁の評価の「追認」にすぎないものであった。
したがって、本件各更正処分等には、評価通達6の定める要件を満たさなかった点で手続上の瑕疵がある。評価通達は行政先例法としての地位を築いているから、上記の瑕疵は重大な法的瑕疵といえる。
(被告の主張)
ア そもそも、本件各不動産が評価通達6に規定する「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産」に当たるか否かについては、鑑定評価など評価通達の定める評価方法以外の方法により評価額を算定しなければ、これを判断することができず、本件においても、本件各通達評価額が適当であるか否かを確認するために、評価通達の定める評価方法以外の方法により客観的交換価値を調べる必要があったことから、その調査の一環として、本件上申の前に鑑定評価が行われたものである。
その後、札幌国税局長は、本件上申を行い、本件指示を受けたものであるから、本件各更正処分等について、評価通達6の定める国税庁長官の指示に係る手続上の瑕疵は存在せず、原告らの主張には理由がない。
イ 仮に、評価通達6の定める国税庁長官の指示に係る手続に何らかの瑕疵があると評価されたとしても、評価通達6の定める国税庁長官の指示は、行政組織内部における指示、監督に関するものと解すべきであり、この規定に反することが直ちに国民の権利、利益に不利益を与えるものとはいえないから、その指示の有無によって本件各更正処分等の効力が影響を受けるものとは解されない。
したがって、原告らの主張は、この点においても理由がない。
(3)争点③(本件各更正処分等の理由の提示に関する違法の有無)について
(原告らの主張)
本件各更正処分等の理由の提示においては、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額の開差が4倍に上ることが記載されているのみであり、評価通達6の適用が肯定される特別の事情があることの理由が記載されていない。
したがって、本件各更正処分等の理由の提示は、一般の被処分者が理解し、納得できる法的な処分理由が記載されているとはいえない点で、行政手続法14条1項が要求する理由の提示として不十分であり、違法がある。
(被告の主張)
行政手続法14条1項に規定する理由の提示が求められる趣旨は、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあり、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきと解される(最高裁平成21年(行ヒ)第91号同23年6月7日第三小法廷判決・民集65巻4号2081頁参照)。
そして、かかる目的は、処分の理由を具体的に記載して通知すること自体をもってひとまず実現されると解される。
これを本件についてみると、本件各更正処分等の理由の提示においては、処分行政庁が、相続財産の評価に係る法令解釈等を踏まえ、本件各通達評価額と、本件各取引額及び本件各鑑定評価額との間には著しい価額のかい離があり、本件各不動産の価額を評価通達の定める評価方法により評価することは著しく不適当であると認定した上で、国税庁長官の指示に基づいて本件各不動産の価額の評価を行い、本件各更正処分等をした旨が記載されており、これらの処分の理由は、上記の理由提示制度の趣旨及び目的を充足する程度に具体的に示されている。
したがって、本件各更正処分等の理由の提示に行政手続法14条1項に反する点はなく、原告らの主張には理由がない。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(本件相続開始時における本件各不動産の時価)について
(1)相続税法22条は、同法第3章において特別の定めがあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているところ、ここにいう時価とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。
ところで、相続税法は、地上権及び永小作権の評価(同法23条)、定期金に関する権利の評価(同法24条、25条)及び立木の評価(同法26条)を除き、財産の評価方法について定めを置いていないところ、課税実務においては、評価通達において財産の価額の評価に関する一般的な基準を定めて、画一的な評価方法によって相続等により取得した財産の価額を評価することとされている。このような方法が採られているのは、相続税等の課税対象である財産には多種多様なものがあり、その客観的な交換価値が必ずしも一義的に確定されるものではないため、相続等により取得した財産の価額を上記のような画一的な評価方法によることなく個別事案ごとに評価することにすると、その評価方法、基礎資料の選択の仕方等により異なった金額が時価として導かれる結果が生ずることを避け難く、また、課税庁の事務負担が過重なものとなり、課税事務の効率的な処理が困難となるおそれもあることから、相続等により取得した財産の価額をあらかじめ定められた評価方法によって画一的に評価することとするのが相当であるとの理由に基づくものと解される。このような課税実務は、評価通達の定める評価方法が相続等により取得した財産の取得の時における適正な時価を算定する方法として合理的なものであると認められる限り、納税者間の公平、納税者の便宜、効率的な徴税といった租税法律関係の確定に際して求められる種々の要請を満たし、国民の納税義務の適正な履行の確保(国税通則法1条、相続税法1条参照)に資するものとして、相続税法22条の規定の許容するところであると解される。
そして、評価対象の財産に適用される評価通達の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有する場合においては、評価通達の定める評価方法が形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いられることによって、基本的には、租税負担の実質的な公平を実現することができるものと解されるのであって、相続税法22条の規定もいわゆる租税法の基本原則の一つである租税平等主義を当然の前提としているものと考えられることに照らせば、特定の納税者あるいは特定の財産についてのみ、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によってその価額を評価することは、原則として許されないものというべきである。しかし、他方、評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することができないなど、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情(評価通達6参照)がある場合は、他の合理的な方法によって評価することが許されるものと解すべきである。
(2)そこで、本件相続における本件各不動産について、前記(1)に説示した特別の事情があるか否かを検討する。
ア(ア)まず、本件各不動産の各種評価額等についてみると、前提事実(2)アないしウ並びに(3)ア及びウのとおり、①本件甲不動産について、評価通達の定める評価方法による評価額である本件甲不動産通達評価額は、2億0004万1474円である一方、不動産鑑定士により不動産鑑定評価基準に基づき算定された評価額である本件甲不動産鑑定評価額は、7億5400万円であり、本件相続開始時の約3年半前である平成21年1月30日に本件被相続人が購入した価額である本件甲不動産購入額は、8億3700万円であった、②本件乙不動産について、評価通達の定める評価方法による評価額である本件乙不動産通達評価額は、1億3366万4767円である一方、不動産鑑定士により不動産鑑定評価基準に基づき算定された評価額である本件乙不動産鑑定評価額は、5億1900万円であり、本件相続開始時の約2年半前である平成21年12月25日に本件被相続人が購入した価額である本件乙不動産購入額は、5億5000万円、本件相続開始時の約9か月後である平成25年3月7日に原告Dが売却した価額である本件乙不動産売却額は、5億1500万円であったというのである。
このとおり、本件各通達評価額は、それぞれ、本件各鑑定評価額の約4分の1(本件甲不動産につき約26.53%、本件乙不動産につき約25.75%)の額にとどまっている。そして、実際に本件被相続人又は原告Dが本件各不動産を売買した際の価格(本件各取引額)をみると、本件甲不動産に関しては、本件相続開始時から約3年半前の取引であるとはいえ、本件甲不動産鑑定評価額より8300万円高額なものであり、本件甲不動産通達評価額からのかい離の程度は、本件甲不動産鑑定評価額よりも更に大きいものであった。本件乙不動産に関しては、本件相続開始時の約9か月後の取引において、おおむね本件乙不動産鑑定評価額と同程度のもの(本件乙不動産鑑定評価額より400万円安価なもの)であった(本件乙不動産売却額。また、本件相続開始時の約2年半前の取引における本件乙不動産購入額は、本件乙不動産鑑定評価額より3100万円高額なものであり、本件乙不動産通達評価額からのかい離の程度は、本件乙不動産鑑定評価額よりも更に大きいものであった。)。
これらに加え、①本件全証拠によっても、本件被相続人又は原告Dの本件各不動産の売買につき、市場価格と比較して特別に高額又は低額な価格で売買が行われた旨をうかがわせる事情等が見当たらないこと(原告らも、この点につき、特に主張をしていない。)や、②本件各不動産は、いずれも約40戸の共同住宅等として利用されている建物及びその敷地である(前提事実(2)イ(ア)及び同ウ(ア))ところ、本件各鑑定評価は、いずれも、原価法による積算価格を参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標準に鑑定評価額を求めたものである(甲5の1、5の2)こと、③不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき算定する不動産の正常価格は、基本的に、当該不動産の客観的な交換価値(相続税法22条に規定する時価)を示すものと考えられること(地価公示法2条参照)をも勘案すれば、本件各通達評価額が本件相続開始時における本件各不動産の客観的な交換価値を示していること(本件相続開始時における本件各不動産の客観的な交換価値を算定するにつき、評価通達の定める評価方法が合理性を有すること)については、相応の疑義があるといわざるを得ない。
(イ)a この点について、原告らは、評価通達の定める評価方法、とりわけ路線価方式は、合理性があるものとして広く社会に受け入れられており、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額のかい離の程度からすれば、本件各鑑定評価額の適正さに疑問が呈される旨主張する。
しかし、本件各取引額が市場価格と比較して特別に高額又は低額であったことをうかがわせる事情等は見当たらないところ、それが本件各鑑定評価額とおおむね同程度か、又はこれを超えるものであったこと等の前記(ア)に説示したところからすれば、原告らの上記主張は採用することができない。
なお、原告らは、本件各鑑定評価における原価法による積算価格の算定において、付帯費用という名目により根拠不明の金額が加算されている旨指摘するが、前記(ア)に認定及び説示したとおり、本件各鑑定評価は、いずれも、原価法による積算価格を参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標準に鑑定評価額を求めたものであるから、原告らが上記指摘する点について逐一検討するまでもなく、それが直ちに本件各鑑定評価額の適正さに影響を及ぼすものとまでは認め難い。原告らは、上記の他に、本件各鑑定評価額が適正さを欠くものであることについて、具体的な主張をしない。
b 原告らは、相続財産の評価は、当該財産を不特定多数の者に売却することを前提としていないものであるから、収益還元法による評価や、取引価額による評価は、その評価手法として著しく妥当性を欠く旨主張する。
しかし、相続税法22条に規定する時価、すなわち当該財産の客観的な交換価値は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解され(評価通達1(2)も同旨を定めている。)、この価額を収益還元法による評価等により求めることが妥当性を欠くなどと解すべき法的根拠は見当たらない。
したがって、原告らの上記主張は失当である。
イ さらに、本件各不動産が本件相続に係る相続財産に含まれることとなった経緯等についてみると、①本件被相続人は、当時90歳であった平成21年1月、M信託銀行から6億3000万円を借り入れた上で、本件甲不動産を第三者から購入するとともに、当時91歳であった同年12月にも、同銀行から3億7800万円、訴外Eから4700万円を借り入れた上で、本件乙不動産を第三者から購入したものである(前提事実(2)イ(イ)及び同ウ(イ))ところ、②本件各不動産を除く本件相続における財産の価額は6億9787万4456円であり、上記①の各借入れ(以下、総称して「本件各借入れ」という。)に係る本件相続開始時の残債務(合計9億6312万5600円。以下「本件借入金債務」という。)を除く本件相続における債務及び葬式費用の額は3394万1511円にとどまる(甲1)ことから、本件各借入れ及び本件各不動産の購入がなければ、本件相続に係る課税価格は、6億円を超えるものであった(なお、相続税法15条(平成25年法律第5号による改正前のもの)の規定による基礎控除の額は、本件共同相続人が5人であることから、1億円である。)にもかかわらず、③本件各借入れ及び本件各不動産の購入がされたことにより、本件各通達評価額(ただし、本件甲土地につき、小規模宅地等特例を適用した後のもの)と比較して本件借入金債務が多額となることにより、その差額が本件各不動産を除く本件相続における財産の価額から控除されることにより、本件申告による課税価格は、2826万1000円にとどまるものとされ、上記基礎控除により、本件相続に係る相続税は課されないこととされたものである。
上記の経緯等に加え、前提事実(2)イ(イ)及び同ウ(イ)に認定したM信託銀行が本件各借入れに係る貸出しに際し作成した各貸出稟議書(乙9、14)の記載や証拠(甲4の1・2)にもよれば、本件被相続人及び原告らは、本件各不動産の購入及び本件各借入れを、本件被相続人及びG興業の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、それらが近い将来発生することが予想される本件被相続人の相続において原告らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、それを期待して、あえてそれらを企画して実行したと認められ、これを覆すに足りる証拠は見当たらない。
ウ 以上にみた事実関係の下では、本件相続における本件各不動産については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、本件各不動産の購入及び本件各借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許されるというべきである。
そして、本件全証拠によっても本件各鑑定評価の適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないこと(前記ア(イ)参照)に照らせば、本件各不動産の相続税法22条に規定する時価は、本件各鑑定評価額であると認められる。
(3)これに対し、原告らは、評価通達6に規定する「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」場合とは、飽くまで時価評価に影響を及ぼす特別の事情がある場合を指すと解すべきであり、時価評価に影響を及ぼすことのない、納税者等の節税目的や租税回避の目的といった主観的要素又は相続開始前後の一連の行為は、上記の特別の事情を基礎付けるものではないとした上で、本件各不動産につき、想定外の時価の下落事情は事後的に生じておらず、上記の特別の事情を基礎付ける事情はない旨主張する。
しかし、前記(1)に説示したとおり、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって特定の納税者あるいは特定の財産について評価することが許されるか否かは、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである特別の事情があるか否かという観点から判断されるべきものであるから、原告らの上記主張はその前提を異にするものである。
2 争点②(評価通達6の定める国税庁長官の指示に関する手続上の違法の有無)について
原告らは、①処分行政庁が本件指示の約1年前に本件各鑑定評価を得たこと、②本件指示が、本件上申から約20日間で出されたものであり、処分行政庁の評価の「追認」にすぎないといえることから、本件各更正処分等には、評価通達6の定める要件を満たさなかった点で手続上の重大な法的瑕疵がある旨主張する。
しかし、評価通達は税務官庁内部における通達にすぎないから、評価通達6の定める「国税庁長官の指示を受けて評価する」旨の定めが、税務官庁内部における手続という性格を超えて対外的な効果を有し、その違反が、更正処分等の違法を招来するものとは解し難い。
したがって、本件指示に係る手続が評価通達6の定めるところに適合していたか否かについて判断するまでもなく、原告らの上記主張は失当である。
3 争点③(本件各更正処分等の理由の提示に関する違法の有無)について
(1)原告らは、本件各更正処分等の理由の提示は、行政手続法14条1項が要求するものとして不十分である旨主張する。
(2)行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文の規定に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠となる法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである(前掲最高裁平成23年判決参照)。
(3)証拠(甲2の1~ 3)によれば、本件各通知書の「処分の理由」欄には、要旨、①相続税法22条に規定する時価は、原則として、評価通達の定める評価方法により評価した価額によるものの、評価通達6は、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する旨定めている旨、②(ア)本件甲不動産は、本件被相続人が平成21年に8億3700万円(本件甲不動産購入額)で購入したものであり、本件乙不動産は、本件被相続人が同年に5億5000万円(本件乙不動産購入額)で購入し、原告Dが平成25年に譲渡したものであるところ、このとおり、本件相続開始の前後における本件各不動産の購入又は売却の価額(本件各取引額)が明らかとなっており、これらの客観的に相当な取引価額と本件各通達評価額の間に著しいかい離が生じていることから、本件各不動産の価額を評価通達の定める評価方法によって評価することは、相続税法22条の法意に照らし合理性を欠くこと、(イ)本件各鑑定評価額は、本件各不動産の本件相続開始時点における時価を合理的に算定しているものである(本件各鑑定評価額が本件各取引額と近似していることはこれを裏付けるものである。)ところ、本件各通達評価額は、これらとの間においても著しいかい離があることからすれば、本件各不動産の価額を評価通達の定めにより評価することは、著しく不適当であると認められる旨、及び③本件各不動産の価額を本件各鑑定評価額と評価した上での原告らの納付すべき相続税及び過少申告加算税の額の計算過程が記載されていると認められる。
以上によれば、本件各通知書は、原告らの納付すべき相続税及び過少申告加算税の額の計算過程とともに、本件各不動産につき評価通達6に規定する「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる」との判断に至った基礎となる事実関係を記載し、その判断過程を根拠をもって具体的に明らかにしているといえる。
したがって、本件各更正処分等については、処分行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を図るという行政手続法14条1項本文の趣旨が求める程度に理由が提示されているというべきである。
4 その余の原告らの主張について
原告らは、①本件各更正処分等が、評価通達6の適用要件を拡大解釈し、これを恣意的に適用したものであることなどから、租税法律主義に反するものである旨、②本件各更正処分等は、評価通達の定める評価方法によって本件各不動産の評価を行い、本件相続税の申告をした原告らの信頼を裏切った点で、法の一般原則たる信頼保護法理に違反する旨、③本件各土地に適用される路線価や本件各通達評価額の算定に用いられた評価通達の定める評価方法について、本件各通達評価額を時価に近づけるような内容の改定等が行われず、また、評価通達の定める評価方法による評価額と不動産鑑定士等による鑑定評価額の開差が著しいと思われる場合の全てにおいて評価通達6が用いられているわけではないにもかかわらず、処分行政庁が本件各不動産につき評価通達6を用いて個別評価をしたことは恣意的なものであるから、本件各更正処分等は、租税公平主義が求める平等取扱原則に反する旨主張する。
しかし、これまでに説示したとおり、本件相続における本件各不動産については、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許され、その相続税法22条に規定する時価が本件各鑑定評価額であると認められる以上、本件各更正処分等が租税法律主義に反するものではないことは明らかである(上記①)。また、本件の事実関係の下では、本件相続における本件各不動産につき、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであったのであるから、本件各不動産について評価通達の定める評価方法による評価額で課税を受けることに対する原告らの信頼は、保護に値するものとは認め難い(上記②)上、本件各不動産について評価通達の定める評価方法によらず評価を行い相続税等の課税をした本件各更正処分等が恣意的にされたものとは認め難く、本件全証拠によっても他の納税者との関係で原告らが恣意的に取り扱われたことをうかがわせる事情等も見当たらない(上記③)。
したがって、原告らの上記主張はいずれも採用することができない。
5 結論
以上に述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、本件各更正処分等は、別紙2(編注:略)のとおり、いずれも適法なものと認められる。
よって、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.