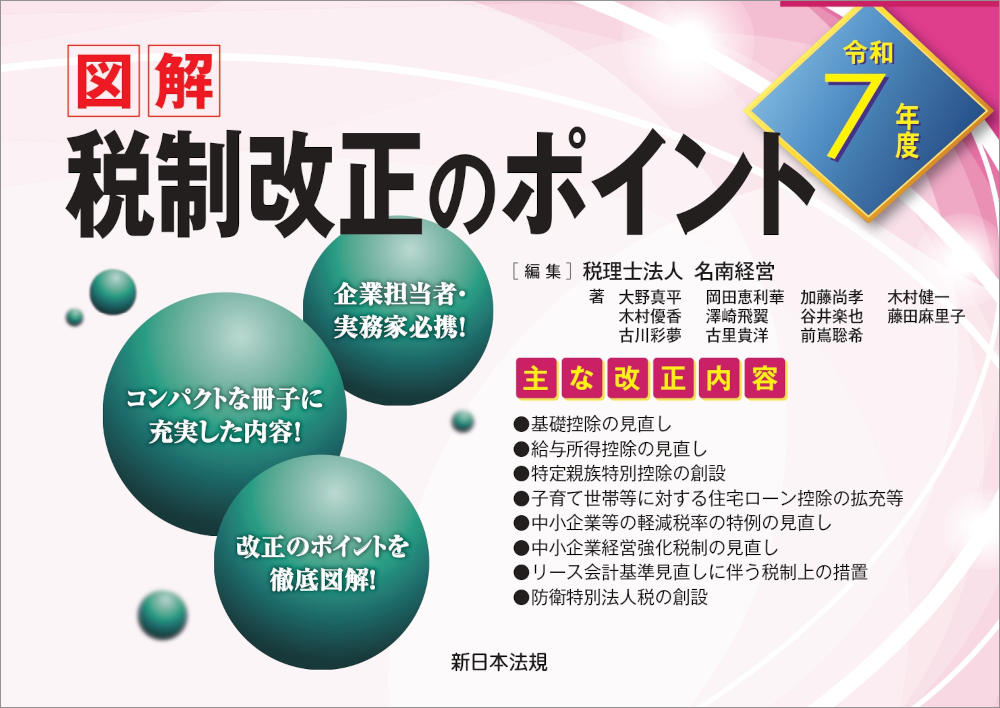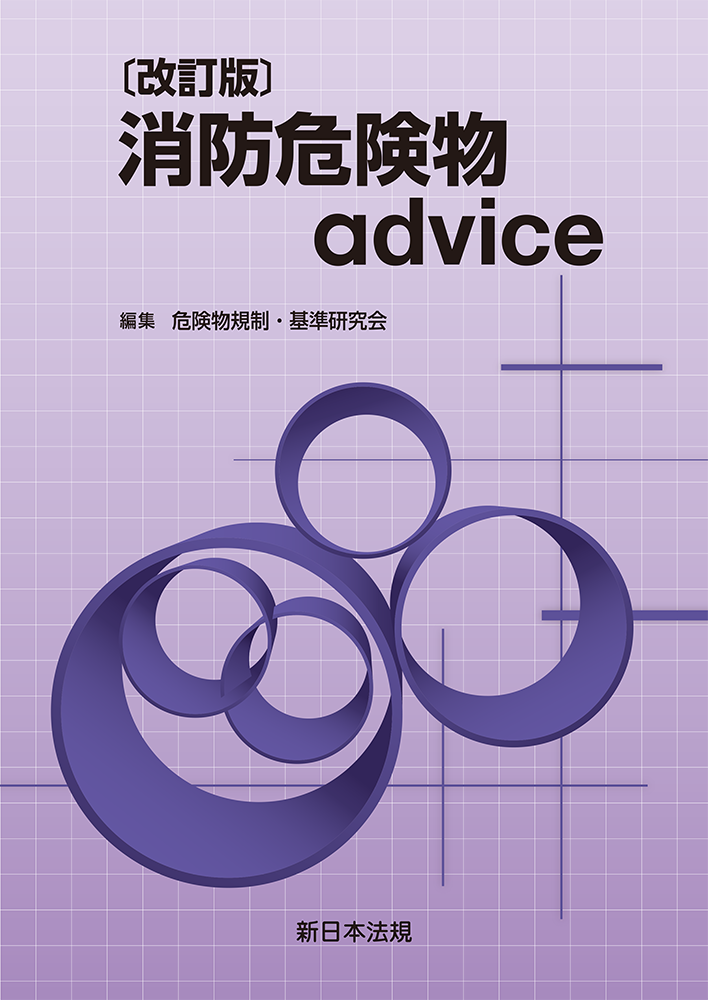解説記事2019年11月04日 巻頭特集 デジタル課税「Pillar1:多国籍企業の利益の配分」のポイントと理論・実務上の問題点(2019年11月4日号・№810)
巻頭特集
デジタル課税「Pillar1:多国籍企業の利益の配分」のポイントと理論・実務上の問題点
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 南 繁樹
はじめに
2019年10月9日、OECD事務局は、経済のデジタル化に対応した新たな国際課税ルールに関し、「第一の柱に関する統合的な提案」(Secretariat Proposal for a“Unified Approach” under Pillar One)を公表した(以下、「統合案」という。)。統合案は、大規模な消費者向け事業(“large consumer-facing businesses”)を行う多国籍企業グループに対し、そのグローバルでの利益のうち、一定の金額を市場国に配分することを提案する。その中核は“Amount A”とされる額であり、物理的拠点の有無を問わず、市場国に新たな課税権を創設し、グループ全体の利益から一定の公式によって算出される部分を市場国に配分するルールを定める。これに加え、物理的拠点のある場合においても一定の固定比率によって市場国に利益を与える簡素化した利益算定のルールも定める(“Amount B”)。従来の国際課税のルールは、納税主体を法人単位とし、その法人の物理的拠点があることを特定の国が課税権を有する根拠としていたが、それに大きな変更が加えられる。
統合案に関しては、2020年1月までに大枠に合意し、2020年末までに最終的な合意に達することが予定されている。
本稿では、統合案の概要を説明するとともに、その問題点を指摘する(脚注1)。
第1 デジタル課税提案に関する背景
1 デジタル課税が必要とされた背景
そもそもデジタル課税がなぜ必要か。課税権は国家主権の中核をなすが、1648年のウェストファリア条約により主権概念が確立して以降、どの国の課税管轄権もその行使は国家主権の及ぶ範囲内に厳しく限定されている(脚注2)。但し、人やモノが当該国家の主権の及ぶ範囲を超えて移動すると、複数の国家がその人やモノへのつながり(nexus)を有するため、それぞれが課税権を主張し、課税権の競合が生じる。そこで、所得を稼得する者が特定の国に「住所(residence)」を有するとの人的なつながり、または所得を産み出す活動が特定の国の物理的拠点において行われるとの物的な関連性が、国家が特定の人またはモノに課税権を行使する条件とされた。後者の物理的拠点は恒久的施設(Permanent Establishment、PE)と呼ばれ、「PEなければ課税なし」の原則が確立している(脚注3)。この考え方は、1920年代の国際連盟の報告書に現れ、国際連盟の租税条約草案を経て、第二次大戦後はOECDのモデル租税条約に引き継がれた(現行OECDモデル租税条約7条1項第1文参照(脚注4))(脚注5)。
しかし、インターネットにより、ある国において物理的拠点を有することなくその国の消費者やユーザーに働きかけて経済活動を行うことが可能となった。このため、統合案は、「デジタル時代において、物理的な存在のみを基準として課税権の配分を限定することはもはや不可能である。1920年代までさかのぼる現行のルールは、一層グローバル化する世界における課税権の公平な配分を確保するにはもはや十分ではない。」(パラ16)と述べ、経済のデジタル化に対応した新たな国家間の課税権の配分を創設するルールが必要であることを宣言し、具体案として、経済活動と国家との間の物的なnexusを見直し、新たな利益配分のルールを創設することを提案している(パラ16)。
2 統合案に至る経緯
経済のデジタル化に関しては、消費課税(消費税・付加価値税)について、1998年OECDオタワ会議報告書を経て、2014年OECD東京会議報告書において商品・サービスが消費される場所で課税を行うとの仕向地・消費地国主義(destination principle)が採用された(脚注6)。これに対し、所得課税(所得税・法人税)に関する進捗は遅く、2015年BEPS行動1最終報告書では結論は先延ばしとなった。その後、2018年3月中間報告、2019年1月ポリシーノート、同年2月公開協議文書を経て、同年5月作業計画(Programme of Work。以下、「作業計画」という。)の形で整理された。今回の統合案は、その作業計画を下敷きにしている。
3 2019年5月作業計画(Programme of Work)
作業計画は、経済のデジタル化に対する対応策を第一の柱(新たな利益源泉と全世界所得配分)と第二の柱(税源浸食対策税制)として整理し、第一の柱について、物理的拠点がないにもかかわらず国家の課税権の根拠となるnexusとして、①「ユーザー参加」(“user participation”)、②「マーケティング無形資産」(“marketing intangibles”)、③「重要な経済的存在」(“significant economic presence”)の3つを挙げた(パラ22)。①「ユーザー参加」案は、SNS、検索エンジンやオンライン市場などの典型的なデジタル企業について当該国家に所在するユーザーが参加することで新たな価値が創造される点に着目し、BEPS行動8ないし10の移転価格税制の考え方と親和性がある。②「マーケティング無形資産」に重要な価値があり、それに課税を行うべきであるとする考え方は、1980年代に遡るので(1988年米国移転価格白書)、従来の移転価格税制の延長にあり、典型的なデジタル企業に限定されない点にユーザー参加案との違いがある。これに対し、③「重要な経済的存在」案は、デジタルによるnexusをそれ自体として承認する点で斬新であるが、従来の租税理論からの乖離は最も大きい(前掲表1参照)。
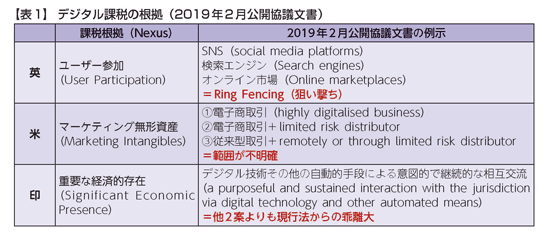
4 各国の単独立法措置
OECDの議論が収束しないうちに、デジタルビジネスに対する課税(Digital Service Tax,DST)を行う国内的立法を単独で行う国が現れている。既にフランスでは本年7月24日にDSTの公布手続を行い、施行された。欧州各国で導入が検討されているデジタル課税は、売上高(グロス)を課税標準とするため(仏は売上高の3%)、所得課税(費用を控除した後の所得(ネット)を課税標準とする)に対して過大になりがちであり、また、所得課税との関係でも外国税額控除などの問題が整理されているとはいえない。そうすると、結果として、デジタルビジネスに対する課税が過大になるおそれがある。米国は自国の有力なデジタル企業に対する課税を許容せず、トランプ米大統領がマクロン仏大統領に対して報復措置を表明したこともあり、米国と欧州の貿易戦争を懸念する声すらあった(脚注7)。このような事態を避けるため、上記3案の差異は捨象して共通点(commonalities)を見出し、Inclusive Framework(OECD参加国を超える多数国の包括的枠組)に参加する134国が合意可能な案として提出されたのが統合案である。
第2 今後の日程
本稿で扱う第一の柱「多国籍企業の利益の配分」に関する統合案については、本年11月21・22日に公聴会が予定されており、コメントが募集されている(11月12日正午(パリ時間)まで)。さらに、第二の柱「税源浸食的な利益移転に対する税」(グローバル・ミニマム・タックス)については、本年11月初旬に公開協議文書(public consultation document)公開、同12月に公聴会が予定されている(本稿は第二の柱は対象としない。)。これらを踏まえ、2020年1月までに大枠(outline)について合意し、2020年末までに最終合意に到達することが想定されている。なお、合意が成立したとしても、各国の国内法で新たな租税法令を制定したうえ、多国間の租税条約を締結することが必要になるから、課税の実現はその先であろう。
第3 統合案の要点
1 統合案の構成
新たな利益配分ルールの対象となるのは大規模な消費者向け事業(“large consumer-facing businesses”)を行う多国籍企業である(パラ20)。典型的なデジタル企業に限定されずに「消費者向け」事業一般が対象とされたのは、「マーケティング無形資産」案に沿ったものである。また、対象は、売上高が一定規模(750 Millionユーロが示唆されている。)を超える多国籍企業グループに限定することが提案されている。対象となる多国籍企業グループの範囲については後述する(第5,1)。
統合案は、対象となる多国籍企業グループに対し、そのグローバルでの利益のうち、下記のAmount A、Amount BおよびAmount Cの3種類の金額を、市場国に配分することを提案する。中核はAmount Aであり、物理的拠点の有無を問わず市場国に新たな課税権を創設し、その市場国への利益配分のルールを定める。これに対しAmount Bは、物理的拠点のある場合に固定比率による利益算定のルールを定めるもので、既存の移転価格税制の簡素化にすぎない。Amount Cは、課税ルールそのものというより、Amount AおよびAmount Bと既存の制度との関係を調整し、実効性を高めるものである。それぞれの概要は、上記表2のとおりである。
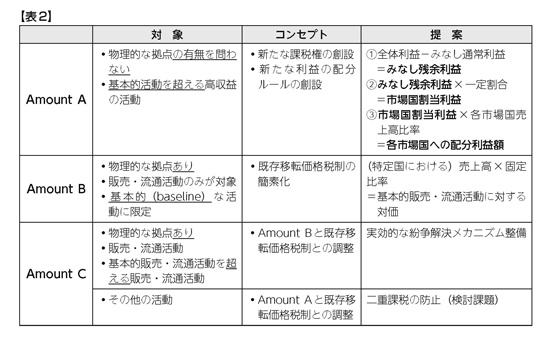
以下、Amount A、Amount BおよびAmount Cのそれぞれを個別に説明する。以下では、統合案のパラグラフを「パラX」として引用する。
2 Amount A(みなし残余利益の市場国への定式配分)
(1)新たな課税根拠(nexus)の創設
Amount Aは、統合案の最重要ポイントであり、多国籍企業が、国境を越えてある国で経済活動を行っているにもかかわらず、その国に物理的拠点(すなわち、子会社または恒久的施設)を有していないためにその国の課税権が及ばないという問題を克服するためのものである(パラ51)。統合案は、物理的拠点なしに行われる経済活動であっても、「消費者との交流や関わりを通じて」(“through consumer interaction and engagement”)、「市場国の経済に対する持続的かつ重要な関与」(“a sustained and significant involvement in the economy of a market jurisdiction”)を有する限り、その国との十分な結び付き(nexus)があり、その活動に対する課税権を有する根拠となるとする(パラ22)。従来のnexusが物理的存在を中核としていたことからすると大きな飛躍であり、国際課税の大きな転換点であるといえる。
但し、ある市場国において「持続的かつ重要な関与」があることが課税根拠になるとしても、物理的存在がない場合には、その認定は困難である。そこで、統合案は、当該市場国における売上高が一定の基準値を超えた場合には、「持続的かつ重要な関与」があるとみなし、物理的拠点の有無を問わず、新たな課税権の対象になるとする(パラ22)。但し、市場規模に応じて、基準額は調整される(市場規模の一定割合を基準値とする趣旨と思われる。)。
(2)利益配分ルールの創設・改定
上記「持続的かつ重要な関与」を新たな課税権の根拠としても、その国に物理的拠点がない場合には、どれだけの利益(課税所得)がその国に帰属するかを決定することは困難である(パラ27)。そこで、統合案は、多国籍企業のグループまたは事業部門(“business line”)の全体の利益の中から、一定割合を「みなし通常利益」(“a deemed routine profit”)とし、それを控除した後に残る利益を「みなし残余利益」(“the deemed residual profit”)とし、これを配分の対象とする(パラ51)。この考え方は、コンセプトにおいて、移転価格税制における残余利益分割法を踏襲している(脚注8)。すなわち、既存の移転価格税制における残余利益分割法は、合算利益のうちから、当事者の通常の機能(同種事業者が通常行うであろう製造活動や販売活動)に対する対価を配分し、その後に残った利益は重要な無形資産による貢献とみなすものであるところ(脚注9)、移転価格税制では、個別の企業について、比較可能な比較対象法人を具体的に選定し、「通常の利益」を算定するが(脚注10)、統合案では、全企業共通または業界別に(後述)基準値を定め、売上高に対する一定比率を自動的に「通常の利益」とみなし、利益のうち当該比率を超える部分のみを新たな課税権の対象とする(パラ54)。このように個別の事実関係によらずに、標準的に定められた比率をもって「みなし通常利益」と「みなし残余利益」に区分する点は、公式に従った計算を行う定式配分法(“the fractional apportionment method(by relying on formula-based calculations)”)であるといえ(パラ52)、既存の移転価格税制と大きく異なる(前掲図1参照)。「みなし通常利益」とされる比率(Step1)は、売上高の10%とする案が検討されている(2019年10月7日読売新聞1面)。つまり、ある企業の売上高営業利益率が25%であれば、売上高の15%(=25%-10%)が新たな課税権の対象として市場国への配分対象となる(Step2)。
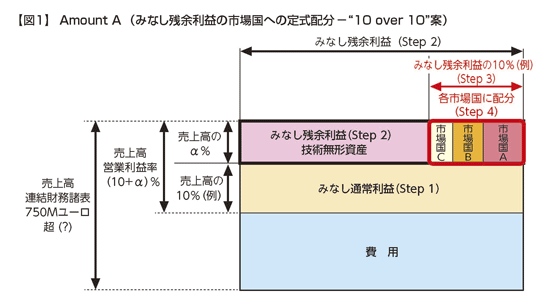
このようにグローバルのグループまたは事業部門単位で合算された利益から、みなし通常利益を控除した後の利益(みなし超過利益)は、①特許権や技術的ノウハウなどの(市場に起因しない)無形資産によるものと、②市場の貢献によるものがありうる。この①と②の配分は、みなし超過利益のうち、②市場の貢献によるものの割合を固定比率で定めることによって決定される(パラ58)。②はさらに、②-1 データなどのデジタル経済によるもの、②-2 マーケティング無形資産によるもの、とコンセプト的には整理されるが(パラ57)、もはや配分計算では区別されない。みなし超過利益のうちの市場の貢献(②の合計)の占める比率に関しては、みなし超過利益のうちの「10%」を市場に配分する案が検討されているようである(Step3)。但し、この比率は、業界や事業部門(“business line”)によって異なる可能性がある(後述)。
そして、このように超過利益のうちで市場国に配分された利益を、さらに各市場国に対して売上高に按分して配分する(パラ60。Step4)。図1は、売上高営業利益率10%を「みなし通常利益」、それを超える部分(売上高営業利益率が25%であれば、売上高の15%)を「みなし残余利益」として、その10%(すなわち売上高の1.5%)を市場国に配分する、いわゆる“10-over-10”案を図示したものである。この場合、利益全体の6%(=1.5/25)が市場国各国に配分されることになる。もちろん、使用される利益指標も、それぞれの数値も、何ら合意されたものではなく、上記は単なる数値例を当てはめたイメージであることに留意されたい。
3 Amount B(基本的販売・流通活動に対する固定比率の対価)
(1)基本的販売・流通機能に対する対価
Amount Bは、市場国において行われる基本的なマーケティングおよび流通機能(“baseline marketing and distribution functions”)に対し、一定比率での固定報酬(“a fixed remuneration”)を与えるものである(前掲図2参照)。
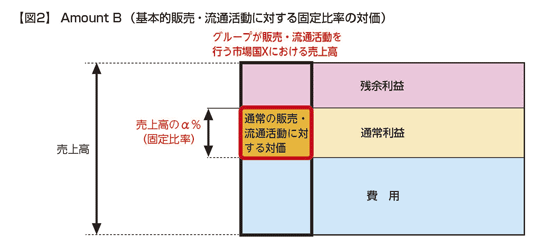
Amount Aは物理的拠点のない市場国での活動が問題とされたが、Amount Bでは、その国において物理的な拠点を有して行う活動が対象であるから、既存のルール(独立企業原則に基づく移転価格税制や、恒久的施設に基づく課税)に従えば足りるはずである。しかし、統合案では、販売・流通機能に関しては、既存の移転価格税制の適用によるだけでは税務当局と納税者との間の対立が無視できないため、二重課税のリスクと、既存の移転価格税制の強硬な執行から生じるコンプライアンス・コストを低下させるために(“reduce the risk of double taxation as well as the substantial compliance costs arising from the aggressive enforcement of current transfer pricing rules”)、固定比率を導入することが有用であるとしている(パラ62)。
デジタル課税に関する改革案において、なぜ通常の販売・流通機能があらためて問題とされているのか、若干分かりにくい面がある。これは、デジタル課税に対する議論において、英仏はユーザー参加を中心としてデジタル企業を中心に据えたが、米国はそのような案を“ring fencing”(狙い撃ち)として批判し、マーケティング無形資産を課税根拠として対象を拡大する方向で議論を構築した。この過程で、Johnson & Johnsonは市場国への配分として、販売・流通機能に対する固定比率での対価の配分が簡素で合理的であると主張したのである(脚注11)。作業計画は、このJohnson & Johnsonの提案に沿って、「簡素化と執行可能性の強い必要性」(“the strong demand for simplicity and administrability”)を理由に「流通ベースのアプローチ」を導入していたが(パラ32~35)、これが踏襲されたものである。
販売・流通の基本的機能に対する対価として割り当てられる固定比率は、今後合意によって決定される(パラ30)。この点は後述する(第5,3)。
4 Amount C(超過機能に対する追加補償と移転価格税制による調整)
(1)Amount Cの位置付け
Amount Cは、Amount AやAmount Bと異なり、それ自体として新たな課税権を創設するものではなく、Amount AおよびAmount Bと既存の移転価格税制との調整をはかったものと考えるのがよい。
(2)Amount BとAmount Cとの関係
上述のとおり、Amount Bは、市場国に実際の物理的な拠点がある場合を対象としているが(この点で、Amount Aと異なる。)、当該市場国内における活動が基本的な活動(“baseline activity”)を超える場合には、その対価は(基本的な活動に対する対価にすぎない)Amount Bでは不足するので、Amount Cとして追加的な対価が支払われる(パラ64)。基本的な活動を超える活動には、販売・流通活動に限られず、それ以外の活動を含む。これは、機能・リスクに応じた対価を支払うべきであるとの移転価格税制の考え方に従うものであり(脚注12)、統合案と既存の移転価格税制の整合性を維持するものにすぎない。むしろ、ポイントは、市場国で生じる紛争に関し、統合案のいかなる要素(“all elements of the proposal”)についても、「紛争解決と二重課税防止の強力な手段」(“robust measures to resolve disputes and prevent double taxation”)が必要であり、具体策として「長期にわたる紛争と二重課税を除去するための義務的で実効性のある紛争防止・解決メカニズム」(“mandatory and effective dispute prevention and resolution mechanisms to ensure the elimination of protracted disputes and double taxation”)を提案している点にある(パラ64)。新興国(特に、インド)は、強制的仲裁制度に反対してきたが、これらの国を「義務的な」紛争解決メカニズムに組み込む意欲が感じられる。
(3)Amount AとAmount Cとの関係
上述のとおり、Amount Aは、コンセプトは移転価格税制を踏襲しているが、具体的な制度としては定式配分法によっている。そこで、Amount BとAmount Cとの関係と同様に、Amount AとAmount Cとの間に二重課税が生じないのかが問題となる。統合案は、Amount Aの対象としての市場国での利益が、当該市場国において(具体的な)機能を果たす活動にも帰着すること(“the profit under Amount A is also in some way referable to the functional activity in the market jurisdiction”)を理由に、当該市場国で二重に計上されることはないこと(“the profit under Amount A could not...... be duplicated in the market jurisdiction”)を確保することが重要であるとしており、二重課税の防止を意図している(パラ65)。この点は後述する(第5,4)。
第4 理論上の問題点
1 新たな課税根拠(nexus)のコンセプトの曖昧さ
統合案は、このように新たなnexusの創設を提案するが、その性格はやや曖昧なものとなってしまっている。そもそもデジタル課税が対象としていたのは、当初は典型的なデジタル企業(“digital centric businesses”)、すなわち、「遠隔地から顧客や顧客以外のユーザーと交流する」(“interact remotely with users, who may or may not be their primary customers”)企業を想定していたはずである。たとえば、X国に設置したインターネットのサーバーからY国の消費者に向けて行う販売活動や、Y国のユーザーが使用するSNSから市場データを得る活動などが想定されていた(ユーザー参加案)。しかし、統合案では、これに加えて、「その他の消費者対象事業」(“other consumer-facing businesses”)であっても、「顧客との関わりや交流、データ収集・利用、販売・ブランディング活動が重要」(“customer engagement and interaction, data collection and exploitation, and marketing and branding is significant”)である限り、「消費者・ユーザーの日常生活に入り込み」(“project themselves into the daily lives of consumers(including users)”)、「市場に伝統的な物理的な存在を有することなしに、消費者層と交流して意味のある価値を創造することができる」(“interact with their consumer base and create meaningful value without a traditional physical presence in the market”)がゆえに、市場国とnexusを有するとされた(パラ19、20)。これはマーケティング無形資産案(米)の影響を受けたものと思われるが、消費者に対する販売・ブランディング活動が重要で新たな課税権の対象となるとしたために、「デジタル課税」であるとの性格が弱まるとともに、どのような企業を対象としているのかが、原理・原則の部分で曖昧になってしまっている。このため、対象になるのか否かの境界線上にある企業について、対象とするのか否かの判断が困難になる場合があるのではないかが懸念される。その実務的な問題点については後述する(第5,1(1))。
2 納税者の特定
統合案は、法人単位または主権の及ぶ範囲内での企業グループ単位での課税という既存の大原則に変更を加え、主権国家の枠を超えて課税主体を把握するものであり、この点においても大変革といえる。では一体誰が申告を行うのか。多国籍企業グループの本社が想定されるところだが、統合案は、そのほかに高い利益率を有する法人、一定の知的財産権を有する法人を例示している(パラ36)。実務上は、どの国で納付するかによって、事務負担も含め、違いが生じるであろう。また、二重課税が生じた場合の紛争解決メカニズムに服するのは、どの国の、どの法人であるかによって、現実的な結果が異なることが考えられる。
3 損 失
統合案はあくまでも所得課税であるから、費用を控除した後のネットの所得を対象とするものである。しかし、Amount Bは売上高に対する固定比率で対価を配分するものであるから、現実にはその国では損失が生じている場合がありうる。また、Amount Aに関し、全体の事業が損失を計上しているにもかかわらず、収益性が高い特定の事業に関しAmount Aの対象になるという問題も生じる。統合案は、新たなルールは損失にも適用されるべきであると述べ(パラ29)、特に、Amount Aに関し“claw-back”や“earn-out”が示唆されている(パラ37、51)。前者は、利益計上後の年度に損失が生じた場合に過去年度に納付した税金を還付する仕組み、後者は、一定条件達成の場合に、追加的に納付する仕組み(価格調整措置)であろうか。あるいは、国家間、事業部門間の調整も意図しているのか。いずれも、みなし計算される利益と現実の所得との乖離を調整する意図であるとは思われるが、ミスマッチは様々な局面で生じうる可能性がある。
第5 実務上の問題点
1 対象となる企業グループの範囲
(1)対象となる企業グループの業種
Amount Aの対象(“Scope”)に含まれる企業について、統合案は「広く定義された大規模な消費者向けビジネス(“consumer-facing businesses”)」であるとしている(パラ19)。
具体的には、第1類型として、「消費者に向き合う要素を有するデジタル・サービスの提供」(“providing digital services that have a consumer-facing element”)を挙げ、その特徴として「遠隔地から主たる顧客であるユーザーや顧客以外のユーザーと交流するデジタルを中心とする事業」(“digital centric businesses which interact remotely with uses, who may or may not be their primary customers”)であると述べている。これは、ユーザー参加案に基づく典型的なデジタル企業であり、国境外から消費者と交流(“interact”)することができることに着目している。
第2類型として、統合案は、「消費者向け製品の供給から収益を生み出す事業」(“businesses that generate revenue from supplying consumer products”)を挙げ、「顧客との関与・交流、データの収集・利用およびマーケティング・ブランディングが重要である事業」(“other consumer-facing businesses for which customer engagement and interaction, data collection and exploitation, and marketing and branding is significant”)であると述べている。これは、マーケティング無形資産案に基づき、消費者への広告宣伝活動によりブランド価値を高めることが重要な企業であり、インターネットによって消費者ベースを拡大することができる点に着目している。
統合案は、上記の定義から、採掘事業(“extractive industries”)や一次産品(“com-modities”)に関する事業は除外(“carve-out”)される旨を示唆する(パラ20)。
上記の第1類型(デジタル・サービス)は比較的明確であるが、第2類型(消費者向け製品)には様々な問題がある。統合案で触れられている点(パラ20)も含め、以下のような事項が挙げられよう。
① 仲介者に対して販売が行われる場合
② 製品が事業者・消費者いずれにも使用される場合
③ 事業者向けと消費者向けで事業部門が区分されていない場合
④ 消費者向け製品の製造者に中間製品・部品を供給している場合
⑤ 消費者向け事業者に対するフランチャイズ・ライセンスを行う場合
⑥ さらなる除外の対象(金融業が示唆されている。)
(2)対象となる企業グループの規模(売上高)
Amount Aの対象(“Scope”)に含まれる企業について、統合案は移転価格税制に関する国別報告書(Country-by-Country Report)の750 Millionユーロを基準とすることを示唆している(パラ20)。その金額となった場合、日本における国別報告事項の提供基準は1,000億円であるから(脚注13)、その額が採用されることになろうか。
2 Amount Aについて
(1)基礎となる財務数値
Amount Aの計算は、米国GAAP又はIFRSに従って作成された本社の連結財務諸表による(パラ53)。IFRSの場合、利益に関しては、純損益、その他の包括利益の合計、当期の包括利益が表示されるうえ、企業に一定の裁量を認めている(脚注14)。また、会計上の利益と各国の税法上の課税所得には差異があるのが一般である。これらの考慮からか、統合案は、利益の適切な指標(“the appropriate measure of profits”)と会計上の利益への標準的な調整(“standardised adjustments to the reported profit”)を検討すべきとされている(同)。たとえば、のれん(goodwill)については会計と各国税法の取扱いに差異があることが多いので、注目しておく必要がある。
(2)算定単位
市場国への配分の対象となる利益の算定に際しては、多国籍企業グループ全体を単位とするのか、事業部門(“business line”)を単位とするのかの問題がある。統合案は、一つの企業が、利益率の低い小売部門と利益率の高いクラウド・コンピューティング部門の両方を有する場合、合算によって(デジタル・サービスである)クラウド・コンピューティング部門が対象から外れると不合理であることを指摘し、事業部門を単位とする案を推進しているように思われる(パラ53)。同様に、地域や市場による区分も示唆されている(同)。
この考え方は理論的には首肯しうるが、グローバル企業の財務諸表を事業部門単位で切り出すのは実務上の困難が予想される。統合案は、既存の会計基準に基づくセグメント情報を基礎とすることを示唆しているが、そのセグメント区分は、“consumer-facing businesses”か否かと整合的であるとは限らず、また、上記パラ53の例によれば、「小売部門」と「クラウド・コンピューティング部門」の両方が“consumer-facing businesses”であったとしても、なお区分が要求されているようにも思われるが、このような区分は曖昧で不明確なものとなりうる。
特に、間接費ないし販売費・一般管理費の配賦については、その方法によって大きく結果が異なりうるという公平性の問題と、各企業に多大なコンプライアンス・コストを強いるという実務上の問題がある。
(3)「みなし通常利益」の水準
新たな課税権の範囲は「みなし通常利益」の水準と、下記(4)の「みなし残余利益」のうちで市場国に配分される比率で決定されることになる。「みなし通常利益」の水準として、一定比率が合意されることが想定されている(パラ54)。現在のところ、売上高の10%が想定されているようである。みなし通常利益の水準を測定する指標として、売上高を分母とする「売上高営業利益率」のほかに、事業資産の価額を分母とする「事業資産営業利益率」など他の指標を使用することも考えられるが、統合案では、具体的な利益指標には言及されていない。また、産業ごとに比率が異なる可能性も示唆されている(同)。
(4) 「みなし残余利益」のうち市場国に配分される比率(市場国の貢献度)の設定
上記(3)の「みなし通常利益」の水準と併せて、「みなし残余利益」のうちで市場国に配分される比率(市場国の貢献度)が非常に重要な問題である。この点は、今後Inclusive Frameworkのメンバーによって合意される(パラ30)。影響を受ける多国籍企業を抱えるOECD諸国は、市場国に配分する金額を押さえるため、売上高のうち「みなし通常利益」とされる比率を高くし、また、「みなし超過利益」の中から市場国に配分する比率を低くすることを志向すると思われるが、それでは市場国ないし新興国の賛成を得られない可能性がある。これらの比率次第で各国の税収や各国企業の業績に影響が生じうるので、この比率の設定は今後さらに議論の対象となる。また、これらの比率は業界によって異なるものとすべきか否かも検討課題とされている(パラ59)。
(5) 二重課税の防止
Amount Aが市場国に配分された場合、本社において外国税額控除または所得免除による二重課税が防止されることが想定されているようである(パラ43)。
3 Amount Bについて
(1)基本的な販売・流通活動の定義
基本的(“baseline”)な販売・流通活動については、売上高をベースに自動的に利益を配分する以上、その定義が明確にされなければならない(パラ63)。たとえば、第三者からライセンスを受けた著名キャラクターを広告・宣伝に使用した場合、売上高は顕著に増加するが、他方でライセンス料の支払も高額になり、ネットの所得はそれほど増加しない場合もありうる(脚注15)。この場合の売上高は「基本的」な販売・流通活動によるものとはいえないのではないか。Amount Bは簡素なルールによって紛争を減少させることが目的であるとされているが(パラ62)、このような考慮をいかに「基本的」な販売・流通活動の定義に反映させるのかが注目される。
(2)基本的な販売・流通活動に配分される利益の水準
Amount Bに関し、売上高に乗じる一定比率の水準については、統合案には何らの示唆がない。業種ごとに変更を加えることは示唆されている(パラ63)。既存の移転価格税制におけるTNMM(取引単位営業利益法)では卸売業・小売業の売上高営業利益率は数パーセントではないかと思われるが(脚注16)、市場国はより高い水準を要求するであろうから、最終的な合意の水準が注目される。
また、グループ全体の利益率が低い場合(例えば、3%)に、それを上回る固定比率(例えば、5%)で基本的な販売・流通活動から利益を先取りすると、本国で損失が生じることが生じうる。このため、この固定比率をグループ全体の利益率の一定割合を上限とすることなども考えられよう。たとえば、Johnson & Johnsonは、地域販売・流通業者(Local Market Distributor)に対する利益は、グループ全体の売上高営業利益率の40%などを上限とすべきとしていた(脚注17)。
4 Amount Cについて
Amount Aは市場国での活動がない場合とある場合のいずれも対象とするのに対し、Amount Cは(既存の移転価格税制によるため)具体的な活動がある場合を対象としているから、両者に重なり合う領域が生じうるので、二重課税防止措置が必要になる。統合案の事例によると、グループXの親会社P社(居住地国1)からストリーミングサービスを市場国2及び市場国3に行った場合、以下のようになる(パラ41~49)。
(1)市場国2(子会社Q社あり)
① 市場国2は、Amount Aに関し、P社に対する直接の課税権とQ社に対する課税権を有し、P社とQ社は連帯責任を負う。P社は居住地国1で外国税額控除または所得免除で二重課税を免れる。
② 市場国2は、固定比率によるAmount Bについて、Q社に対する課税権を有する。
③ 市場国2は、既存の移転価格税制に基づきAmount Cについて、Q社に対する課税権を有する。
前掲図1・図2のとおりAmount AとAmount Bは、コンセプト的には利益の性格が異なるので、その間には二重課税は生じないはずであるが現実の計算上は生じないとは限らない。これに対し、Amount CはAmount Aとの間でも、Amount Bとの間でも二重課税の問題を生じうるので、強力な紛争解決手段が必要となる。
(2)市場国3(物理的拠点なし)
市場国3は、新たな課税権に基づくAmount Aに関し、P社に対する直接の課税権を有する。
第6 今後のポイント
以上から、特に注目を要するポイントは、以下のようになろう。
対象
・「消費者向けビジネス」の定義
・対象となるグループ全体の売上高
Amount A
・みなし通常利益の利益率の水準
・みなし残余利益のうちで市場国に配分される比率(市場国の貢献度)
Amount B
・「基本的な販売・流通活動」の定義
・「基本的な販売・流通活動」に配分される利益の比率(対売上高)
・グループ全体または事業部門の利益率による上限の有無
いずれも理論的な検討もさることながら、各国の税収が関係するので、きわめて政治的な問題である。実務担当者としては、議論の動向を探りつつ、自社に適用される可能性があるか、適用された場合にはどのような実務的な問題が生じるか、シミュレーションを開始しておく必要があろう。
脚注
1 本稿の執筆に際し、キヤノン株式会社理事・経理本部税務担当上席菖蒲静夫氏および東レ株式会社経理部税務室長栗原正明氏から貴重な示唆をいただいた。記して感謝する。もちろん、本稿にありうべき誤りはすべて筆者のみの責任に属する。
2 中里実「BEPS プロジェクトはどこまで実現されるか」ジュリスト1483号26頁。
3 増井良啓・宮崎裕子『国際租税法 第3版』6頁。
4 日本法においては所得税法2条1項8号の4・161条1項1号・164条1項1号イ、法人税法2条12号の19・138条1項1号・141条1号イ。
5 淵圭吾『所得課税の国際的側面』81頁以下。
6 わが国も2015年に消費税を改正し、電気通信利用役務の提供については、原則としての原産地主義(origination principle)に代えて、仕向地主義に基づき「当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所」が国内であれば、わが国消費税が適用されるものと規定された(消費税法2条1項8号の3、4条3項3号)。
7 2019年7月17日Wall Street Journal参照。その後、米仏は合意に達し、OECDが国際的なルールを整備すれば、仏政府は税収の差額分を課税対象のIT企業に還付する方針とのことである(2019年08月27日東京読売新聞朝刊2頁)。その他、EU、英、伊、スペイン、オーストリア等においてデジタル課税の検討が行われている。デジタル課税に関する立法動向全般については、国立国会図書館調査と情報第1064号(2019年7月2日)「デジタル経済の課税をめぐる動向【第2版】」参照。
8 OECD移転価格ガイドライン2017年版パラ2.127~2.129、2.140~2.145参照。
9 本田技研工業事件に関する東京地判平成26年8月28日税務訴訟資料264号順号12520参照)。
10 OECD移転価格ガイドライン2017年版パラ2.127。
11 Josh White, “Johnson & Johnson hatches plan for marketing intangibles”, International Tax Review, March 25, 2019.
12 OECD移転価格ガイドライン2017年版パラ1.51~1.106。
13 租税特別措置法66条の4の4第4項3号
14 IAS第1号「財務諸表の表示」第81A項
15 わが国におけるDisney World事件(東京地判平成29年4月11日・裁判所ウェブサイト・税務訴訟資料267号順号13005)参照。
16 経済産業省平成30年企業活動基本調査速報によると、卸売業の売上高営業利益率は1.9%、小売業は同2.8%となっている。
17 前掲注[11]のJosh Whiteの記事参照。
南 繁樹 (みなみ しげき)
長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士、東京弁護士会:1997年登録(49期)
E-mail: shigeki_minami@noandt.com
1994年東京大学法学部卒業。1997年東京弁護士会登録。2003年New York University School of Law卒業(会社法・租税法LL.M)。東京大学法学部非常勤講師(法と経済学)、神戸大学法科大学院客員教授、上智大学法科大学院非常勤講師、LEC会計大学院客員教授(いずれも租税法)。2017年~2018年IFA(国際租税協会)Asia-Pacific Chair。経済産業研究所「これからの法人に対する課税の方向性」プロジェクトメンバー。専門はM&A及び税務。税務の経験分野は、移転価格税制、国際的組織再編、租税条約、源泉所得税、法人税全般、金融商品、相続税等の全般に及ぶ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.