解説記事2021年03月29日 ニュース特集 Q&Aで読み解くグループ通算制度の税効果(2021年3月29日号・№876)
ニュース特集
ASBJ、実務対応報告の公開草案を公表へ
Q&Aで読み解くグループ通算制度の税効果
企業会計基準委員会(ASBJ)は3月中にも実務対応報告の公開草案となる「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を公表する予定だ。令和2年度税制改正においてグループ通算制度が創設されたことを踏まえ、同制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めたもの。グループ通算制度と連結納税制度は、申告を行うのが親法人か、あるいは各法人かなどで申告手続は異なるものの、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じであることから、基本的には実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(以下「実務対応報告第5号等」という)を踏襲している。
本特集では、公開草案の概要を従来の取扱いと異なる点も含めQ&A形式でお伝えする。なお、公開草案は6月初旬頃まで意見募集し、2022年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する予定。早期適用も認めている。
実務対応報告案公表の経緯
Q
今回、令和2年度税制改正で創設されたグループ通算制度に関する実務対応報告案が公表された経緯を教えてください。
A
令和2年度税制改正により、企業グループ全体を1つの納税単位とし、親法人が一体として計算した法人税額等を申告する現行の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入され、2022年4月1日以後から適用されることになった。これを踏まえ、企業会計基準委員会では、実務対応報告第5号等に関する必要な改廃を行うとしていたものである。
グループ通算制度を含む税制改正法案は、2020年3月27日に成立しているため、本来であれば、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算することとされているため(税効果適用指針第44項)、グループ通算制度を適用する企業は、2020年3月期以降の決算において、グループ通算制度の適用を前提として税効果会計の適用を行う必要があった。
しかし、企業会計基準委員会がグループ通算制度に基づいた税効果会計に関する考え方を整理する際には、政省令や、税務通達に関する情報が必要となる可能性があり、会計上の論点の検討を行うためには一定の時間を要するといった理由から、同委員会は、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「実務対応報告第39号」という)を公表し、実務対応報告第5号等に関する必要な改廃を行うまでの間は、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことを容認する取扱い(以下「特例的な取扱い」という)を示している。
通算税効果額の授受を前提とした会計処理
Q
実務対応報告案の適用範囲について教えてください。
A
実務対応報告案は、グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表並びに連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表に適用することとされている。
通算会社が申告納付を行う税額は、通算前所得に対して通算グループ内の他の通算会社との損益通算や欠損の通算を行った後の課税所得を基に算定されたものであり、当該通算による税額の減少額を通算税効果額として、通算会社間で金銭等の授受を行うことを想定している(ただし、授受を行うか否かは任意)。通算税効果額に関しては、連結納税制度においても個別帰属額の授受を行うことは任意であったものの、大半の企業は授受を行うとの実務が行われてきたようだ。このため、グループ通算制度においても通算税効果額の授受を行うことが想定されるとしている。また、通算税効果額の授受が行われない場合の取扱いを検討することは一定の困難性があることから、実務対応報告案では通算税効果額の授受を行うことを前提として会計処理及び開示を定めている。
なお、通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理及び開示については、連結納税制度における取扱いを踏襲するか否かも含め取り扱われていない。
基本的に実務対応報告第5号等の取扱いを踏襲
Q
現行の実務対応報告第5号と同様の取扱いはありますか。
A
親法人が全体を合算した所得を基に納税申告を行う連結納税制度と、各法人の所得を基にそれらを通算した上で各法人が納税申告を行うグループ通算制度とでは申告手続が異なるものの、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じといえる。このため、今回の実務対応報告案は、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理を除き、連結納税制度における実務対応報告第5号等の会計処理及び開示に関する取扱いを基本的に踏襲することとされている。
なお、踏襲される取扱いは以下のとおりとなっている。
(法人税及び地方法人税に関する会計処理)
・通算税効果額の取扱い
(税効果会計に関する会計処理)
・住民税及び事業税の取扱い
・繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率
・個別財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性
・連結財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性
・未実現損益の消去に係る一時差異の取扱い
・投資簿価修正に関する取扱い
・適用時、加入時及び離脱時の取扱い
(開示)
・法人税及び地方法人税に関する表示
・税効果会計に関する個別財務諸表における表示
・税効果会計に関する連結財務諸表における表示
通算税効果額は個別帰属額と同様、法人税及び地方法人税に
Q
通算税効果額の取扱いについて教えてください。連結納税制度の個別帰属額と異なる点はありますか。
A
連結納税制度では、同制度を適用する各会社の個別帰属額が計算され各社に配分されており、実務対応報告第5号等では、個別帰属額は各社の課税所得に対する法人税及び地方法人税として負担すべき額であることから、個別帰属額を「法人税、住民税及び事業税」と同様に取り扱うこととしている。
グループ通算制度における通算税効果額については、グループ通算制度を適用したことによる税額の減少額であり、法人税に相当する額であるとされている。このため、実務対応報告案では、通算税効果額についても、連結納税制度における個別帰属額の取扱いを踏襲することとしている。したがって、通算税効果額は個別財務諸表における損益計算書において、当事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うことになる。
通算グループ全体が「課税される単位」
Q
連結納税制度では、企業グループ全体をあたかも1つの法人であるかのように捉えて課税が行われており、連結財務諸表においては「課税される単位」を連結納税主体として税効果会計を適用しています。グループ通算制度の場合はどのような取扱いとなりますか。
A
税効果会計を適用する際には、「納税主体」ごとに繰延税金資産及び繰延税金負債の計算を行うことが想定されており、税効果会計適用指針第4項(1)では、「納税主体」を「納税申告書の作成主体をいい、通常は企業が納税主体となる。ただし、連結納税制度を適用している場合、連結納税の範囲に含まれる企業集団が同一の納税主体となる。」と定義している。
連結納税制度の場合は、納税主体が何を指すのかが必ずしも明らかではなかったものの、企業グループの一体性に着目し企業グループ全体をあたかも1つの法人であるかのように捉えて課税が行われており、連結財務諸表においては「課税される単位」を連結納税主体として税効果会計を適用しているものと考えられる。
グループ通算制度においては、各通算会社が納税申告を行うことから、「納税申告書の作成主体」は各通算会社となる。しかし、企業グループの一体性に着目し完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは連結納税制度と同様であるとされており、グループ通算制度を適用する通算グループ全体が「課税される単位」になるとしている。このため、実務対応報告案では、連結財務諸表においては、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を1つに束ねた単位」に対して、税効果会計を適用することとしている。
投資簿価修正の取扱い、一時差異に該当
Q
投資簿価修正に関する取扱いについて教えてください。
A
投資簿価修正は、株式等の売却等を行う時点において税務上の投資簿価を修正するものであり、売却等を行う時点までの間は税務上の帳簿価額が修正されるものではないことから、投資簿価修正による影響は売却等を行う時点までの間は税効果会計適用指針第4項(3)における「一時差異」には該当しないものとされている。
しかし、連結納税制度では、実務対応報告第5号等において、売却等によって解消するときにその期の課税所得を増額又は減額する効果を有することから、一時差異と同様に取り扱うものとしている。グループ通算制度においては、投資簿価修正の方法が税務上の簿価純資産額との差額を加算又は減算する方法に変更されているものの、売却等によってその期の課税所得を増額又は減額する効果を有する点は同様であることから、連結納税制度における取扱いを踏襲することとされている。したがって、期末時点における他の通算会社の株式等の帳簿価額と税務上の簿価純資産額との差額については、一時差異と同様に取り扱うこととしている。
通算税効果額は「未払法人税等」に含めず
Q
通算税効果額の表示方法について教えてください。
A
実務対応報告案では、前述したとおり、グループ通算制度における通算税効果額を法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしているため、連結納税制度における個別帰属額の取扱いを踏襲し、通算税効果額は、法人税、地方法人税を示す科目に含めて損益計算書に表示するとしている。また、法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしても、通算税効果額に係る債権及び債務は通算グループ内の他の会社に対するものであり、連結納税制度における個別帰属額の取扱いと同様に、「未払法人税等」に含めず、他の通算グループ内の他の会社に対する債権及び債務と同様に表示することが適当とされることから、通算税効果額に係る債権及び債務は、未収入金や未払金などに含めて貸借対照表に表示することになる。
通算会社で計上した繰延税金資産と繰延税金負債を相殺
Q
グループ通算制度における繰延税金資産及び繰延税金負債の表示はどのようになりますか。
A
グループ通算制度では、通算会社は異なる納税主体となるが、連結財務諸表においては通算グループ全体に対して税効果会計を適用することとしていることから、連結納税制度における取扱いと同様、法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について、通算会社で計上した繰延税金資産の合計と繰延税金負債の合計を相殺して、連結貸借対照表の投資その他の資産の区分又は固定負債の区分に表示することとしている。
また、個別財務諸表においては、通算会社で計上した繰延税金資産及び繰延税金負債について、税効果会計基準に従って、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示し、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺せずに表示することとしている。
グループ通算制度の適用の有無を注記
Q
連結納税制度の場合と同様、グループ通算制度に関する適用の有無に関する注記は必要になりますか。
A
連結納税制度と同様、グループ通算制度においても、適用開始から取りやめまでの期間において適用していることを示すことが財務諸表利用者にとって有用になると考えられるため、グループ通算制度を適用した場合又は取りやめた場合に加えて、今回の実務対応報告により法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理を行っている場合には、その旨を税効果会計に関する注記の内容とあわせて注記することとしている。
繰延税金資産等の発生原因別内訳は税金の種類ごとの注記の必要なし
Q
グループ通算制度においても、連結納税制度と同様、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等の注記について、その内訳を税金の種類ごとに注記する必要はないと考えてよいですか。
A
実務対応報告案では、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等の注記について、その内訳を税金の種類ごとに注記する必要はないとする連結納税制度における取扱いを踏襲している。したがって、法人税及び地方法人税と住民税と事業税(所得割)を区分せずに、これらの税金全体で注記することになる。
なお、実務対応報告第7号では、連結納税制度における取扱いとして、繰延税金資産から控除された金額(評価性引当額)について、税金の種類によって回収可能性が異なる場合には、税金の種類を示して注記することが望ましいとされている。しかし、この点については、評価性引当額を税金の種類ごとに開示することによる情報の有用性は限定的であると考えられるほか、連結納税制度における実務において、当該定めに基づき注記を行っている企業はごく少数であることから、「注記をすることが望ましい」との記載は踏襲しないこととされている(本誌875号12頁参照)。
ただし、税金の種類によって回収可能性が異なる場合において、評価性引当額について税金の種類を示すことを禁止する趣旨ではないとしている。
繰延税金資産が取り崩される場合の注記は不要
Q
連結納税制度では、連結納税親会社の個別財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の計上額が連結財務諸表における回収可能見込額を大幅に上回り、その上回る金額に重要性がある場合には、連結納税親会社の個別財務諸表に追加情報として注記するとされています。グループ通算制度でも同様の取扱いになりますか。
A
ご質問の注記に関しては、個別財務諸表において計上した繰延税金資産が連結財務諸表において取り崩される場合、個別財務諸表において分配可能額に含まれるものが連結財務諸表では資産性がないものとして取り扱われる点について、連結納税制度導入当初においては財務諸表利用者に十分に認識されていなかったことによるものとされている。
現時点では、連結納税制度の仕組みが理解されていると考えられるため、グループ通算制度においては、当該注記は不要であるとされている(本誌875号12頁参照)。
連帯納付義務に関する偶発債務の注記は不要
Q
グループ通算制度では、連結納税制度と異なり、通算子会社だけではなく通算親会社も連帯納付義務を負っており、また、連帯納付義務の対象となる債務者は通算親会社だけではなく通算グループ内の他の通算子会社も含まれることになると思われますが、連帯納付義務に関する偶発債務の注記は必要ですか。
A
連結納税制度における連帯納付義務については、通常、連結納税子会社が連帯納付義務を履行する可能性は低いと考えられるため、偶発債務の注記は行う必要がないとされている。
連帯納付義務に関しては、連結納税制度では子会社が親会社の債務に対する連帯納付義務を負っているのに対して、グループ通算制度では通算子会社だけではなく通算親会社も連帯納付義務を負っており、また、連帯納付義務の対象となる債務者は通算親会社だけではなく通算グループ内の他の通算子会社も含まれるなどの相違点がある。
しかし、実務対応報告案は基本的に開示も実務対応報告第5号等を踏襲することとしているほか、連帯納付義務は制度に内在する義務でありグループ通算制度を適用していることを注記することとしていることから、別途偶発債務の注記を行う有用性は大きくないとしている。したがって、連帯納付義務について偶発債務の注記は要しないこととしている。
2022年4月1日の期首から強制適用、早期適用も可
Q
実務対応報告案の適用時期はいつからになりますか。また、早期適用も可能ですか。
A
令和2年度税制改正で創設されたグループ通算制度が2022年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、実務対応報告案についてもグループ通算制度の適用時期と同様、2022年4月1日以後に開始する事業年度の期首から強制適用することとしている(図表参照)。また、早期適用については2022年3月31日以後終了する事業年度末から容認する。
ただし、四半期会計期間については、実務対応報告が夏頃に正式決定される見込みであるため、事業年度の途中からの早期適用は認めず、2023年3月期の第1四半期からの適用となる。
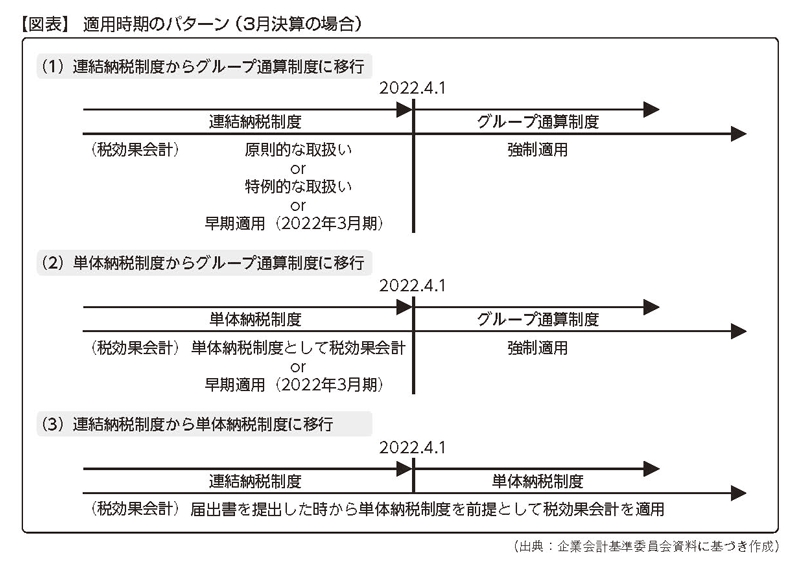
連結納税からグループ通算制度への移行は会計方針の変更に該当せず
Q
連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合、会計方針の変更に該当しますか。
A
連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合においては、実務対応報告案の適用により、税制の変更による影響と会計方針の変更による影響が生じると考えられる。しかし、会計方針の変更による影響については、今回の実務対応報告案は実務対応報告第5号等の会計上の取扱いを踏襲していることから会計方針の変更によって重要な影響は生じないと考えられるとし、会計方針の変更による影響はないものとみなすこととしている。
なお、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「実務対応報告第39号」という)の特例的な取扱いを採用している企業について、実務対応報告案の適用前においては税制の変更による影響が考慮されておらず、実務対応報告案の適用によって考慮することになることから、適用初年度の損益として計上することになるとしている。
経過措置で税制変更による影響のみを損益計上
Q
連結納税制度からグループ通算制度へ移行する際に経過措置は設けられていますか。
A
2022年4月1日より連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合、現時点では多くの企業が実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により、改正前の税法に基づく「特例的な取扱い」により税効果会計を適用していることが想定される。
この場合は、2022年3月期末時点では、実務対応報告第39号における「特例的な取扱い」に従い、連結納税制度の規定に基づき実務対応報告第5号及び第7号により税効果会計を適用することになる。2022年4月1日以後に開始する事業年度の期首では、期首における影響は連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴う税効果会計の影響(税制の変更による影響)のみになり(基本的に新しい実務対応報告は実務対応報告第5号及び第7号の会計上の取扱いを踏襲しているため、会計方針の変更による影響はないものとみなす)、2022年4月1日以後に開始する事業年度で損益として計上するとの経過措置が設けられている。
一方、実務対応報告第39号における「特例的な取扱い」を適用していない企業の場合には、2022年4月1日以後開始事業年度での影響は生じないことになる。
単体納税からグループ通算制度への移行も2022年4月1日から適用
Q
単体納税制度からグループ通算制度へ移行する場合はどのような取扱いとなりますか。
A
単体納税制度からグループ通算制度へ移行する場合については、グループ通算制度を新たに採用することになるため、損益通算や欠損金の通算の影響を考慮して税効果会計を適用することになるが、当該影響は税制上の制度の選択により生じるものであり、当該影響はグループ通算制度を前提として税効果会計を行う最初の期に損益として計上することになる。
この点、3月決算会社の場合であれば、2022年3月期末からグループ通算制度を適用するものとして税効果会計を適用する必要があるが、準備期間が必要であるとの観点から、税法におけるグループ通算制度への移行年度である2022年4月1日以後開始する事業年度からグループ通算制度へ移行する場合に限り、強制適用時期を2022年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとしている(2022年3月31日以後終了する事業年度末からの早期適用は可)(図表参照)。
単体納税への移行は届出書提出事業年度から単体納税前提の税効果
Q
連結納税制度を取りやめて単体納税制度に移行する場合はどのような取扱いになりますか。
A
連結納税制度から単体納税制度に移行するケースも中には想定される。連結納税制度を適用している企業は、2022年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出することにより、当該事業年度から単体納税制度に戻ることができる。このため、税効果会計上は届出書を提出した日の属する会計期間(四半期会計期間を含む)から、単体納税制度を適用する前提で税効果会計を適用することになる(図表参照)。
この場合、税制上の制度の選択は会計方針の変更には該当しないため、移行に伴う税効果会計への影響は適用初年度の損益として計上することになる。
実務対応報告第5号等は廃止に
Q
実務対応報告第5号等はいつ廃止になりますか。
A
実務対応報告第5号等及び実務対応報告第39号については、今回の実務対応報告案の適用により、実務対応報告第5号等及び実務対応報告第39号を適用する企業が存在しなくなった段階で廃止することとされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















