解説記事2019年11月25日 最新判決研究 所得税法における「住所」の判定(2019年11月25日号・№812)
最新判決研究
所得税法における「住所」の判定
東京地裁令和元年5月30日判決(平成28年(行ウ)第434号~第436号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、所得税法上の「非居住者」に該当するという認識のもと、平成21年から平成24年(以下「本件各年」という。)の所得税の申告をしなかったところ、所轄税務署長から同法上の「居住者」に該当するとして期限後申告を勧奨されたため、平成26年12月17日、本件各年分の所得税について期限後申告(各年税額282万円余ないし681万円余)をした上で、平成27年1月16日、平成23年分及び平成24年分所得税について、各年分の所得税額を零とする更正の請求をした。これに対し、所轄税務署長は、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件各通知」という。)をし、更に、本件各年分所得税に係る無申告加算税の賦課決定(以下「本件第1各賦課決定」という。)をした。
また、Xが代表取締役を務めるKR(原告)及び同じくKS(原告)(両社を併せて、以下「原告各社」という。)は、Xに支払った役員報酬について同人が非居住者に当たるということで所得税の源泉徴収をしていたため、平成26年12月5日付で、所轄税務署長から平成21年11月から同24年12月までの各月分の源泉所得税について、居住者としての差額について、納税の告知(以下「本件各納税告知」という。)及び不納付加算税の賦課決定(以下「本件第2各賦課決定」という。)を受けた(上記各処分を一括して以下「本件各処分」という。)。X及び原告各社(以下「Xら」という。)は、本件各処分を不服として、国(被告)に対し、それらの取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)Xは、日本国籍を有する男性である。原告各社は、各種ラジエーターの製造、販売、修理、自動車部品販売等を行う株式会社である。原告各社の関連会社として、日本に本店が所在するKS販売、KKのほか、インドネシアに本店が所在するKJI、アメリカに本店が所在するKOS、シンガポールに本店が所在するKIO及び中国に本店が所在するKHEがある(上記海外会社を総称して以下「本件各海外法人」といい、原告各社、KS販売及びKK社を併せて「本件各社」という。)。
Xは、本件各年を通じて、日本のほか、アメリカ、シンガポール、インドネシア、中国及びその他の国(以下「本件諸外国」という。)に滞在し、その滞在状況は別表のとおりである。Xは、日本滞在時には、名古屋市内に所在する住宅(以下「本件日本居宅」という。)において、アメリカ滞在時には、カリフォルニア州に所在するコンドミニアム(以下「本件アメリカ居宅」という。)において、シンガポール滞在時には、KIOが借り上げた賃貸住宅(以下「本件シンガポール居宅」という。)において、それぞれ生活していた。Xは、本件各年を通じて、上記関連会社の代表者を務めていた。
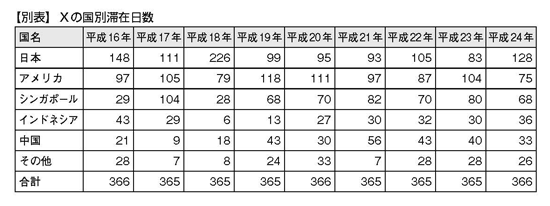
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
(1) Xが本件各年において居住者に該当するか否か。
(2)国税通則法66条1項ただし書及び同法67条1項ただし書に定める「正当な理由」の有無。
2 国の主張
(1)Xは、日本で出生し、日本国籍を有する者である。また、住民登録の状況はそのものの所在や居住に係る客観的事実と併せて重要な判断要素になり得るものであるところ、Xは、昭和35年12月9日に名古屋市に住民登録をし、平成4年4月3日には本件日本居宅が所在する本件日本住所地に住所地を変更した上で、少なくとも平成25年8月13日に至るまでの間に、同所から住所地の登録を異動した事実は認められない。そして、Xは、本件各年を通じて、本件日本居宅を共同所有していたところ、Xが日本に滞在する場合には、本件日本居宅において起居し、妻らと生活を共にしていた。本件各年におけるXの日本国内での滞在日数は、本件諸外国の各国の滞在日数と比較しても、1ないし2番目に多い状況にあった。
以上からすると、本件各年を通じて、Xの住居は本件日本居宅の所在する本件日本住所地にあったと認められる。
(2)Xらは、Xが日本の「居住者」に該当するとの認識を持つことは十分可能であったにもかかわらず、前回調査からXの生活に有意な変化はないとしてXが「非居住者」に該当すると判断した結果、その判断を誤ったものである。Xらの上記判断は、単に税法の不知あるいは法令解釈の誤りによるものというべきであって、国税通則法上の「正当な理由」は、本件において存しない。
3 Xらの主張
(1)本件各年におけるXの日本での滞在日数は、最も多い平成24年でさえ1年の3分の1程度に過ぎず、平成21年~23年においては、1年の4分の1程度でしかない。他方、シンガポールの実質的滞在日数が平成21年144日、同22年144日、同23年165日、同24年152日となり、本件各年を通じて、本件日本居宅を拠点として生活していた日数よりも、本件シンガポール居宅を拠点として生活をしていた日数が多い。
(2)Xは、原告各社の代表取締役であったが、創業者であった父Мが死亡した平成18年頃からは専ら国内向けの事業を営む原告各社の業務については弟Yに任せており、原告各社の業務への関与は極めて限定されていた。そのため、Xは、日本に滞在中であっても原告各社に出勤するのは1週間いた場合には約半分くらいであり、原告各社にいる間も本件各海外法人に関連した業務を行っていた。
したがって、Xが原告各社の業務を行うために本件日本居宅の所在地を生活の拠点とする必要性は低かった。
他方で、Xは、本件各海外法人の中でも特にKIOの業務に注力する必要があった。そして、XがKIOを中心とする本件各海外法人の業務に注力するためには、KIOの本社があり、かつ、KIOの販売先及び支店並びにKIJ及びKHEへのアクセスがよいシンガポールに生活の拠点を置く必要が高かった。
(3)住民票上の住所は、当事者がどのような届出を行ったかによって決まる形式的なものに過ぎないため、それ自体は、その者の全生活の中心たる生活の本拠がどこにあるのかという実質的な判断をする上で重要な要素となるものではない。
(4)本件では、平成21年から平成22年にかけて行われた前回調査において、平成16年から平成20年の各年におけるXの居住者性について調査が行われ、名古屋国税局の担当者が、Xや税理士に対し、前回調査の結果、Xが非居住者であると判断した旨の説明をした。前回調査は、国税局の資料調査課によって5か月にわたり行われ、専らXの居住者性を対象にして行われた調査であることからすれば、Xらは、前回調査における課税庁の判断、すなわち、前回調査の対象となった各年においてXが非居住者であったという判断を正しいものであったと信頼することは通常のことである。そうであれば、Xらが、前回調査における判断に対する信頼に基づいて、Xを非居住者であると判断したことには「正当な理由」が認められる。
三、判決要旨
請求認容。
(1)当裁判所は、Xは本件各年のいずれにおいても所得税法2条1項3号に定める「居住者」に該当するとは認められないから、Xが居住者に該当することを前提としてされた本件各処分はいずれも違法であり、本件各処分の取消しを求めるXらの請求はいずれも理由があるから認容すべきものと判断する。その理由の詳細は、以下のとおりである。
(2)所得税法2条1項3号のいう「住所」とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決・裁判集民事236号71頁参照)。そして、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かは、滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
ア 滞在日数及び住居について
(ア)本件各年においてXが滞在していた各国のうち、Xが自己所有建物又は賃貸建物に居を構え、定住できる態勢の整っていた3か国(日本、アメリカ、シンガポール。以下「居住3国」という。)についてみると、これらの国における滞在日数は、別表のとおりである。そのうち、日本国内における滞在日数と、XらがXの住所があったと主張するシンガポールにおける滞在日数とを比較すると、いずれの年についても、日本国内における滞在日数が上回っていたが、その差は平成21年において11日、平成22年において35日、平成23年において3日、平成24年において60日であり、これらを総じてみると、両国における滞在日数に大きな差があるとはいえない。
(イ)また、Xの滞在国は、居住3国以外にも、インドネシア、中国及びその他の国々に及び、本件各年においてそれぞれ相当数の滞在日数があるところ、シンガポールと地理的距離が近いインドネシアのほか、中国やその他の国(ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オセアニアの国々)にも、世界的なハブ空港があり各国への渡航の利便性が高いシンガポールを起点として渡航していることからすると、中国への渡航には日本を起点とするものが相当数あることを踏まえても、シンガポールが、居住3か国以外の各国へ渡航する際の主な拠点となっていたことは否定し難いものというべきである。そして、これらの渡航先国での滞在が、中国を除いても、平成21年において37日、平成22年において60日、平成23年において58日、平成24年において62日に及ぶことを考慮すると、日本国内における滞在と、シンガポールにおける滞在との間には、量的な観点からみて有意な差があるとはいえない。
(ウ)以上によれば、滞在日数の比較から、Xの生活の本拠が日本国内にあったことを積極的に基礎付けることはできないものというべきである。
イ Xの職業について
Xは、原告各社及び本件各海外法人の代表者の地位にあるが、そもそもは海外進出に強く反対していたMを説得して海外進出の了承を得たという経緯から、本件各海外法人に係る経営判断は専らXが行ってきたものである。そして、これらの海外における事業展開は、①インドネシアに設立したKIJにおいて、ラジエーターの製造工場を設置し、さらに2つの工場を増設し、1000人以上の従業員の労務管理を行いながらこれらの工場を稼働させて製品を製造し、②アメリカに設立したKCSにおいて、アメリカの各地域における販売活動を行い、③さらに、シンガポールに設立したKIOにおいて、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オセアニア等における顧客を獲得して販売地域を広げ、④製品の生産性を増やすため、中国に設立したKHEにおいて、工場を設置し、製品の製造を行うなどというものであり、これらに関する業務の中には、本件各年においてもなお現地の責任者には委ねることができずXが自ら行わなければならないものも多数含まれていた上、顧客と会ったり、工場を視察するなどのために現地へ赴く回数も多数にのぼったことが認められる。他方、日本法人である原告各社については、Xの父であるMが体調を崩してからはXの弟であるYがこれに代わって経営判断を行っていたものである。
そして、Xは、本件各年を通じ、上記①~④のような本件各海外法人の営業活動や工場の管理等の業務のため、年間66~75%程度の期間は、本件諸外国に滞在して業務を行っていたものと認められるところ、このうち、居住3国の一つであるアメリカにおける滞在日数や、日本から渡航することもあった中国の滞在日数の半分を除いても、年間の約4割の日数においてシンガポール又は同国を起点として渡航したインドネシアや中国及びその他の国に滞在していたことになるから、Xの職業活動は、シンガポールを本拠として行われていたと評価することができるものといえる。なお、かかる評価は、X自身、本件各年分についてシンガポールの居住者として同国における納税申告をし、自らがシンガポールに居住しているとの認識を有していたこと(認定事実)とも合致し、また、本件各年においてアメリカに居住していた長男を後にシンガポールに呼び寄せていること(認定事実)とも合致するものということができる。
以上によれば、Xの職業活動は、シンガポールを本拠として行われていたものと認められる。
ウ 生計を一にする配偶者その他の親族の居所について
認定事実のとおり、本件各年を通じて、Xと生計を一にする妻や二女は、本件日本居宅において居住を続けていたことが認められる。これについて、Xは、インドネシアにKJIを設立した平成6年頃から、インドネシアの工場で生産した製品をアメリカの市場で販売するため海外の各地に滞在して業務を行うことが必要となり、妻らがXとともに海外に転居したとしても、Xが不在となることが多々あるため、妻らの生活の便宜や子らの教育上の配慮から、妻らについては従前と同様に日本における居住を継続していたと説明するところ(X本人)、かかる説明は合理的なものである。そうすると、生計を一にする妻らが国内に居住していたことは、Xの生活の本拠が日本国内にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない。
エ 資産の所在について
認定事実キのとおり、Xは、日本国内において原告各社の株式のほか、本件日本居宅の共有持分権、自動車及び多額の預貯金等を有しており、Xが所有する資産の多くは日本に所在していたものと認められる。もっとも、Xは、シンガポールにおいても1700万円以上の預貯金を有しており、当面生活するために十分な額の資産を有していたものといえる。そして日本の預貯金等の資産をシンガポールに移転していないことは、家族を残して海外に赴任する者の行動として不自然なものとはいえないことからすると、その生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない。
オ その他の事情について
(ア)認定事実のとおり、Xは、本件各年を通じ、本件日本住所地における住民登録について転出の届出をしていなかったことが認められるところ、このことについて、Xは、原告各社の借入れに係る個人保証の手続等において印鑑登録証明書を取得する便宜のためであったと説明している。一般に、適切な届出がされないため、住民登録の所在が必ずしも生活の実体を反映したものとなっていない例があること等から、Xが本件日本住所地における住民登録について転出の届出をしていなかったとしても、このことをもって、Xの生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎づけるものとはいえない。
(イ)また、認定事実のとおり、Xは、本件各年を通じて、日本の健康保険組合に加入を継続し、日本国内の病院において、毎年の人間ドックを受診し、おおむね毎月通院していたほか、平成24年には網膜剥離や心臓の手術を受けるために入通院していたこともあったことが認められる。しかしながら、Xのように世界の各地を頻繁に行き来し、一時帰国数も少なくない者であれば、医療水準や保険制度の整備状況、通院や入退院の便宜等に鑑み、一時帰国時に日本の病院に通院等することが不自然であるとはいい難い。そうすると、Xの国内における通院等の状況を踏まえても、このことをもって、Xの生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎づけるものとはいえない。
カ まとめ
以上のとおり、Xは、本件各年を通じて、本件各海外法人の業務に従事し、そのために相応の日数においてシンガポールに滞在し、また、シンガポールを主な拠点としてインドネシアや中国その他の国への渡航を繰り返しており、これらの滞在日数を合わせると年間の約4割に上っていたことなどからすれば、Xの職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められ、他方、日本国内における滞在日数とシンガポールにおける滞在日数とに有意な差を認めることはできず、Xと生計を一にする家族の居所、資産の所在及びその他の事情についても、Xの生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない。これらを総合すると、本件各年のいずれにおいても、Xの生活の本拠が日本にあったと認めることはできないから、Xは所得税法2条1項3号に定める「居住者」に該当するとは認められないというべきである。
(3)したがって、Xが居住者に該当することを前提としてされた本件各処分は、その前提を欠くものとしていずれも違法である。
よって、その余の争点について判断するまでもなく、Xらの請求はいずれも理由があることから、これらを認容することとし、主文のとおり判決する。
四、解説
はじめに
経済のグローバル化が進む中、個人にとっては、その「住所」がどこにあるか、法人にとっては、その「本店所在地」がどこにあるかによって、それらの課税関係を大きく異なることとなり、それらの「住所」等が所在する国の課税権も大きく異なることになる。その中で、個人については、その「住所」の所在地如何によって、所得税又は相続税の課税関係が大きく異なり、特に、所得税については、当該個人に給与等を支払う者(通常、法人)に対しても、所得税の源泉徴収義務にも影響を及ぼすことになる。
本件においては、日本国籍を有し、国内に住民登録をしている会社経営者(X)が、彼が経営する国内の会社等を拠点としながら、数か国に所在する関係会社を経営し、それらの各国に所在する関係会社を渡り歩いてそれらの経営に当たっている場合に、当該会社経営者の所得税法上の「住所」がどこにあるのか、それによって、同法上の「居住者」に該当するか否か等が問題となったものである。また、これに関連し、申告所得税に係る無申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税の賦課を免れる「正当の理由」の存否が問題となったものである。
更に、このような「住所」をめぐる訴訟事件の先例としては、本判決も引用している贈与税に係る最高裁平成23年2月18日第二小法廷判決(裁時1526号2頁、いわゆる武富士事件、以下「最高裁平成23年判決」という。)がある。この武富士事件との関係についても、検討しておく必要がある。
以下、上記各論点について、検討することとする。
1 所得税の納税義務(者)
(1)所得税法は、所得税の納税義務者を、居住者と非居住者に区分し、更に居住者について、非永住者とそれ以外の者に区分し、それぞれの納税義務の範囲を定めている。すなわち、居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある(所法5①)。また、非居住者は、所得税法161条に規定する国内源泉所得を有するとき等には、この法律により、所得税を納める義務がある(所法5②)。そのほか、内国法人及び外国法人に対しても、所定の場合に、所得税の納税義務が課せられている(所法5③、④)。
次いで、課税所得の範囲については、非永住者以外の居住者に対しては、全世界から生じる全ての所得について(所法7①一)、非永住者に対しては、所定の国外所得以外の所定の所得及び所定の国外所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものについて(所法7①二)、非居住者に対しては、所定の国内源泉所得について(所法7①三)、それぞれ所得税が課される。
次に、所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者その他所定の金員の支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき所得税の源泉徴収をする義務がある。この場合、前記(1)で述べたように、給与等の受給者である居住者又は非居住者によって課税所得の範囲が異なることにも対応して、源泉徴収義務者が源泉徴収すべき税率は異なることになる。
すなわち、源泉徴収義務者は、居住者に対して、給与等を支払う場合には、最高40%の税額の徴収を要することになる(所法別表第二、乙欄参照)が、非居住者に対して所定の国内源泉所得を支払う場合には、一律20%の税額を徴収すれば足りることになる(所法161、164、212、213等参照)。
(2)このように、所得税法上、個人が居住者、非永住者又は非居住者に当たるかによって課税所得の範囲が異なることになるが、当該居住者等の区分は、次のように定義づけられている。
まず、居住者とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」(所法2①三)をいい、非永住者とは、「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」をいい(所法2①四)、そして、非居住者とは、居住者以外の個人をいう(所法2①五)。
また、居住者と非居住者の区分については、国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しないもの及び国籍を有する者であっても、現に国外に居住し、かつ、その国外に永住すると認められる者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、所定の条項が適用される(所法3①、所令13)。
なお、所得税法では、所定の場合には、国内に住所を有する者等と推定されるときがある。すなわち、国内に居住することとなった個人が、①その者が国内において継続して1年以上居住することが通常必要とする職業を有すること及び②その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があることに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定され(所令14①)、このように住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他の扶養親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定される(所令14②)。逆に、国外に居住することとなった個人が、国内において同様な事情があれば、その者は、国内に住所を有しない者と推定される(所令15)。
2「住所」の意義と借用概念
(1)以上のように、居住者と非居住者の区分については、原則として、当該個人の「住所」がどこにあるかによって決定されることになる。この「住所」の意義については、所得税法(同じく「住所」の所在によって課税関係を異にしている相続税法)において、その意義を明らかにしているわけではないので、解釈に委ねられることになる。そこで、税務行政の執行上、所得税基本通達2-1では、「法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。(注)国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)及び第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定があることに留意する。」と定めている。
この通達の趣旨について、国税庁の担当者は、次のように説明している(注1)。
「所得税法上個人の「住所」の意義については、特に、定義規定が置かれていないが、一般に「租税法規が、一般私法において使用されていると同一の用語を使用している場合は、特に租税法規が明文をもって他の法規と異なる意義をもって使用することを明らかにしている場合又は法規の体系上他の法規と異なる意義をもって使用されていると解すべき実質的理由がない限り、私法上使用されていると同一の意義を有する概念として使用されているものと解するのが相当である」(昭和34年2月11日東京地裁32(行)38)とされている。
本通達は、所得税法上の「住所」の概念は民法上の住所の概念(「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」(民法22))と同一のものであることを明らかにしたものである。
ただし、民法上「どこが生活の本拠であるか」については、定住の意思を必要とするいわゆる「意思主義」と客観的事実によって決定されるとするいわゆる「客観主義」との2説があるとされているが、意思主義による場合には、本人の意思によって住所の有無、したがって課税所得の範囲が左右される(法7①)ことになるばかりでなく、定住の意思は、通常外部から認め得ない場合が多いことから、本通達では、所得税法上の住所は、客観主義によるものであることを明らかにしている。
本通達でいう「客観的事実」には、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などが挙げられる。」
(2)このように、所得税法又は相続税法における「住所」の意義については、法律上、特段の定めを設けることなく、解釈に委ねているわけであるから、その解釈はいわゆる借用概念としての解釈に委ねられることになる(注2)。
借用概念とは、租税法上用いられている用語のうち、他の法分野で用いられ、既に明確な意味内容が与えられている概念を意味し、他の法分野から借用しているという意味で、そのように呼称される。この点では、「住所」は、民法上、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」(民法21)と定められ、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」(民法22)と定められているところである。そのため、租税法においても、各人の生活の本拠等が住所であると解されている。
そして、このような借用概念の租税法上の解釈については、私法上の概念とは別意に解すべきことが租税法規の明文又はその趣旨から明らかである場合を除き、私法上におけると同じ意義に解するのが法的安定性の見地から望ましいものと解されている(注3)。
このような解釈のうち、「私法上の概念とは別意に解すべきこと」については、本判決が引用する最高裁平成23年判決が判示するところの「反対の解釈をすべき特段の事由はない以上」と考え方を一つにしているものと考えられる。この考え方は、「別異に解すべきこと」又は「特段の事由」が存すれば、「住所」という借用概念であっても、それらの事情を考慮して税法独自の解釈があり得ることを示唆しているものと解される。
3 武富士事件との対比
(1)前述のように、所得税法及び相続税法では、納税者たる個人が国内に「住所」を有するか否かによって、当該個人の課税所得の範囲等が異なることになるが、最近、当該「住所」の意義等が法廷で争われた著名な事件として、本判決も引用している前掲最高裁平成23年判決がある(注4)。同判決の事案では、かつて我が国のサラ金業界の最大手であったT社(注5)の経営者夫妻が、T社の株式を同夫妻が出資しているオランダ法人のY社(外国法人)に取得させ、そのY社の出資口数の90%を平成11年12月当時香港に滞在していた長男Sに贈与したものの、国外財産を相続税法上の制限納税義務者に贈与したということで、Sが贈与税の申告をしなかったため、処分行政庁が贈与税の決定処分をしたので、当該処分の違法性が争われたというものである。
この事件では、Sは、香港に滞在していた期間(平成9年6月から同12年12月までの間において、香港に約65%、杉並区の自宅で約26%、残りを諸外国で過し、香港では、T社の子会社の役員を務めていた、というものである。また、この事件において、平成11年末に贈与が行われたのは、同年12月の税制改正大綱の公表により、翌平成12年から制限納税義務者の範囲が厳しく制限されることが明らかにされたことによるものと推測される。
かくして、一審の東京地裁平成19年5月23日判決(訟務月報55巻2号267頁)は、上記滞在日数の事実を重視し、SとT社等との関係、贈与税回避の目的等の諸事情を考慮してもなお、本件贈与日において、Sが本件杉並自宅に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難である旨判示し、当該処分を取り消した。
これに対し、控訴審の東京高裁平成20年1月23日判決(判例タイムズ1283号119頁)は、①本件杉並自宅のSの居室状況、②Sが同自宅滞在中T社への出勤状況、③SのT社における役員としての重要な地位、④Sが香港滞在居宅には重要な財産を持ち込んでいないこと、等の諸事情の下では香港と日本との形式的な滞在日数の多寡を主要な考慮要素としてSの住所を判断することは相当でないとし、Sの生活の本拠は以前から本件杉並自宅にあった旨判示して、原判決を取り消した。
(2)かくして、上告審の最高裁平成23年判決は、概ね次のように判示して、原判決を破棄した。
「一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり、主観的に贈与税回避の目的があったとしても客観的な生活の実体が消滅するものではないから、Xについて前記事実関係の下で本件香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすることはできない。このことは、相続税法が民法上の概念である「住所」を用いて課税要件を定めているため、本件の争点が上記「住所」概念の解釈適用の問題となることから導かれる帰結であるといわざるを得ず、他方、贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり、このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば、法の解釈では限界があるので、そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。」
以上のように、武富士事件においては、過去3年間において、国内で約26%過し、香港で約65%過していたSの「住所」の判定につき、一審判決と上告審判決が「住所」は香港にあると判断し、控訴審判決が国内にあると判断したものであるが、このような判断の分かれは、民法上の「生活の本拠」の解釈と租税法上の借用概念の解釈における「別意に解すべきこと」又は「特段の事由」をどのように判断したかによって分かれたものと考えられる。もっとも、この事件は相続税に係るものであるが、本件における所得税の場合の異同をどのように考えるかも問題となる。
4 本件における「住所」の判定
(1)本件においては、Xは、国内及び国外に所在する複数会社の経営者として、当該各会社が所在する各国を行き来して、事業活動を行っていたものである。その行き来した結果の各国の滞在日数が別表のとおりとなったものであるが、平均的には国内の滞在日数が最も多くなっている。そうであれば、武富士事件に係る控訴審判決のように当該会社経営者の滞在日数が香港よりも国内の方がはるかに少ないにもかかわらず、国内に住所があると判断した事例があることとその論拠を考えると、本件においても、Xの住所が国内にあると判定することも十分考えられる。
もっとも、同じ「住所」であっても、所得税法と相続税法とで同様に解すべきか否かについては疑問も残る。けだし、所得税法において課税される「所得」のうち、本件で問題となっている「給与所得」又は「事業所得」等は、基本的には、当該個人の役務の提供によって稼得されるものであるから、当該「住所の判定」において、当該役務提供がどの国で行われているかが、重要な判断基準になって然るべきであるとも考えられる。他方、相続税法において課税される「財産」は、相続又は贈与という財産の承継によってもたらされるものであるから、当該「住所」の判定におい
て、それを承継する個人の「終の住処」が一層重視されて然るべきであるとも考えられる。
そのような両者の違いもあってか、所得税法又は相続税法においては、居住者若しくは非居住者の区分又は制限納税義務者若しくは無制限納税義務者の区分について、前述した民法からの借用概念としての「住所」の解釈とは別に、それぞれ別個の規定を設けているところである(所法3①、所令13、14、15等、相法1の3、1の4等参照)。
(2)かくして、本判決は、Xの「住所」の判定(Xが居住者に該当しないこと)について、まず、最高裁平成23年判決を引用し、「「住所」とは、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解する」と判示し、「客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かは、滞在日数、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等を総合的に考慮して判断するのが相当である。」と判示している。
次いで、本判決は、本件各年におけるXの職業活動の事実関係を具さに認定した上で、「Xは、本件各年を通じ、上記①~④のような本件各海外法人の営業活動や工場の管理等の業務のため、年間の66~75%程度の期間は、本件諸外国に滞在して業務を行っていたものと認められるところ、このうち、居住3国の一つであるアメリカにおける滞在日数や日本から渡航することもあった中国の滞在日数の半数を除いても、年間の約4割の日数においてシンガポール又は同国を起点として渡航したインドネシアや中国及びその他の国に滞在していたことになるから、Xの職業活動は、シンガポールを本拠として行われていたと評価することができる」と判示し、更に、「日本国内における滞在日数とシンガポールにおける滞在日数とに有意な差を認めることはできず、Xと生計を一にする家族の居所、資産の所在及びその他の事情についても、Xの生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない。」と判示して、Xがシンガポールで住民届をし、所得税の申告も行っていることも考慮し、Xは所得税法上の「居住者」に該当するとは認められない旨結論づけた。
(3)このような判断については、本判決が判示するように、Xの経済活動の拠点がシンガポールにあるという事実認定が適正なものであれば、一理あるようにも考えられる。しかしながら、日本国内に「住所」があると推認できる事実として、①本件日本居宅に生計を一にする配偶者その他の親族が居住し、Xが係争各年を通じ最も多くそこに滞在していた事実、②Xが所有する資産の大部分が日本に所在していて、シンガポールには1700万円程度の預金しか有していなかった事実、③Xが、本件各年を通じ、本件日本住所地に住民登録をして各国への出国手続に便宜を受け、各国に滞在する際にも転出届をしていなかった事実、④Xが本件各年を通じ、日本の健康保険組合に加入・継続し、日本国内の病院において、毎年人間ドックを受診し、通院・手術等を受けて日本の社会保障制度を利用している事実等については、Xの生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付けるものとはいえない旨一刀両断に切り捨てている。
また、Xの経済活動の中心がシンガポールにあったとする事実認定についても、原告各社及び本件各海外法人の経営基盤となっているラジエーターの製造・販売については、そもそもそれらの起業の源泉が国内に所在する原告各社にあったはずであり、当該各社が経営上重要であるからこそ、Xは代表者の地位に留まり、本件各年の約3割を国内に滞在する理由であったとも推認できる。そうなると、国内に「住所」があったものと推認できる前記①から④までの事実を併せ考慮すると、本判決が必ずしも適正であったとも考えられない。どちらかといえば、本判決の裁判官にとっては、Xの「住所」がシンガポールにあったという先入観の下に、日本国内に「住所」があったと推認できる諸事実を殊更軽視したようにも考えられる。
5 本判決の意義と問題点
(1)前述したように、本件は、日本国籍を有し、生計を一にする配偶者等が居住している本件日本居宅に本件各年を通じて相対的には最も長く滞在しながら、Xが経営する(代表者を務める)本件各海外法人が所在する各国に滞在して経済活動を行っている場合に、当該経営者たるXの所得税法上の「住所」がどこにあったかが争われたものである。本判決は、前述のように、Xの経済活動の拠点がシンガポールにあったと認定し、シンガポールを拠点に経済活動を行っていた各国の滞在日数の合計が相対的に最も多かったと認定した上で、Xの「住所」はシンガポールにあったとし、所得税法上の「居住者」に当たらない旨判示した。
しかし、その判断には、前記4の(3)で述べたように、幾つかの疑問が残るところであるので、控訴審の判断が注目されることになる。いずれにせよ、経済活動のグローバル化が進む中、Xのような経済活動を行う者が多くなっている折、それらの者の「住所」の判定が問題とされることが多くなっているので、本判決は、その一事例として意義がある。
(2)本件においては、上記の「住所」の判定のほか、原告各社に対する不納付加算税等の賦課決定に係る「正当な理由」の存否も争われたが、本税に係る本件各通知と本件各納税告知が取り消されたため、本件の各賦課決定も本件各納税告知等と運命を共し、不問とされた。しかしながら、Xらの主張によると、本件各年分前の平成16年から同20年の各年におけるXの居住地性について、平成21年から同22年にかけて5か月にわたって国税局資料調査課の調査が行われ、その際に、当該調査担当者から、Xが非居住者に当たる旨説明を受けていた旨の事実があったことが認められる。
そうすると、国税通則法において各賦課算税の賦課決定を免れることとなる「正当な理由」の解釈(注6)については、種々の論点があるが、本件に即すると、「納税者の税法の不知もしくは誤解に基づく場合」(注7)は「正当な理由」に当たらないとしても、それが税務職員の誤指導に基づく場合には、「正当な理由」があると解されることが高い(注8)ので、仮に、控訴審において本件第1賦課決定及び本件第2賦課決定についても本案審理を要することになれば、前述した国税局資料調査課の調査の事実関係が問題にされることになるものと考えられる。
(注1)三又修 他編「所得税基本通達逐条解説 平成29年版」(大蔵財務協会 平成29年)21頁。
(注2)金子宏「租税法 第23版」(弘文堂 平成31年)127頁等参照。
(注3)前掲最高裁平成23年判決は、「ここにいう住所とは、反対の解釈をすべき特段の事由はない以上、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である」と判示している。
(注4)同判決の評釈については、品川芳宣・本誌2011年7月18日号24頁、同2011年7月25日号22頁、同「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)706頁等参照。
(注5)T社は、その後、最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決(民集60巻1号1頁)が利息制限法の解釈につき、サラ金業界側に厳しい判断を下したため、更生会社となり、過払金の返還に伴う過年度損失の更正の請求の是非を争ったものの敗訴している(東京地裁平成25年10月30日判決・判例時報2223号3頁及び東京高裁平成26年4月23日判決・訟務月報60巻12号2655頁(詳細については、品川芳宣・本誌2015年2月9日号16頁参照))。
(注6)「正当な理由」の解釈論の詳細については、品川芳宣「附帯税の事例研究 第四版」(財経詳報社 平成24年)64頁等参照。
(注7)東京高裁昭和51年5月24日判決(税資88号841頁)、前出(注6)79頁等参照。
(注8)前出(注6)113頁、申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針、平成12年7月3日)、札幌地裁昭和50年6月24日判決(税資82号238頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















