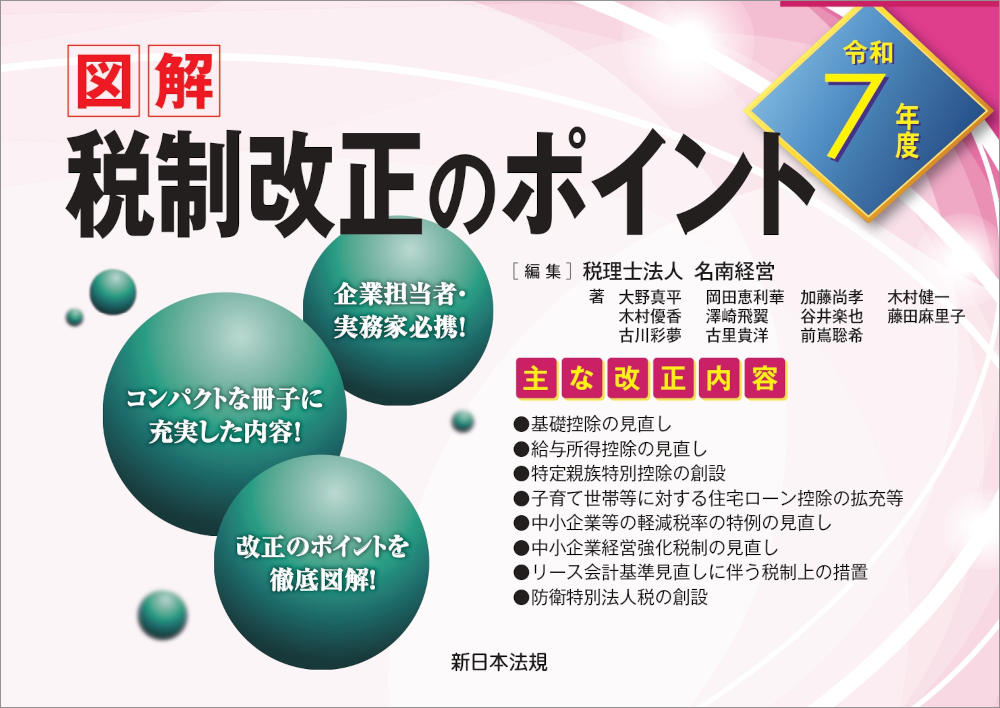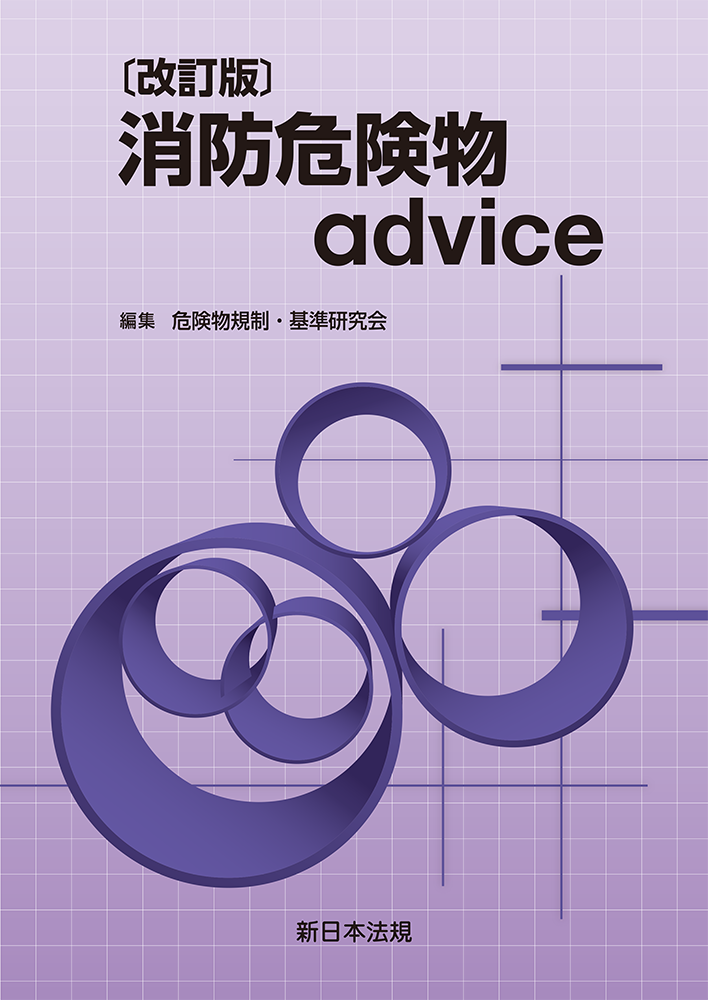解説記事2021年05月24日 判例評釈 自身が代表取締役を務める法人への支出の必要経費性が否定された事例(2021年5月24日号・№883)
判例評釈
自身が代表取締役を務める法人への支出の必要経費性が否定された事例
−大阪高判平成30年11月2日(脚注1)について−
弁護士 福島那央
本判決は、自身が代表取締役を務める法人への支出の必要経費性が否定された事例である。以下では、事案(「1」)及び判旨(「2」)を概観した後、一般的な見解との関係で本判決の特異性を抽出し(「3(1)」)、当該特異性について、先例との比較(「3(2)」)、解釈方法としての体系上の位置付け(「3(3)」)を検討する。さらに、類似事案において所得税法157条1項による処理を行ったものとの関係(「3(4)」)、数量的な必要経費性の判断の可能性(「3(5)」)を検討して、本判決が先例性を持った場合の残された課題や援用可能性等を考える。
1. 事案の概要(脚注2)
Xは、LPガス等の燃料小売業(以下「B商店」という。)を営んでおり、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、同人が代表者を務める株式会社(以下「本件会社」という。)にB商店の業務(LPガスの配達、販売、保守等の業務。以下「本件配達販売等業務」という。)を委託したとして、その外注費(以下「本件外注費」という。)を支払い、自己の事業所得の必要経費に算入して確定申告を行った。兵庫税務署長が、この申告につき、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定をした(脚注3)ため、Xが、異議申立及び審査請求の棄却を経て、同処分のうち各申告額を超える部分及び同賦課決定の取り消しを求めて出訴した。1審は請求棄却。
なお、上記以前の経緯等は次のとおりである。
まず、B商店は、従前Xの父Cが営んでいた。Xは、本件会社の代表取締役就任までの間はCの事業の事業専従者として、本件配達販売等業務を含む同事業の業務全般に従事していた。その後、Xは本件会社の代表取締役就任を機にCの事業の事業専従者から外れたが、この際、Cは、本件会社との間で、本件配達販売等業務を本件会社に委託する取決めを行い、これに基づいてXは本件会社の受託業務として同業務に従事した。ただし、同取決めについては、委託業務の範囲や従事時間、取決めの及ぶ期間等についての明確な合意はなく、書面も作成されなかった。なお、同取決めでは、本件配達販売等業務に従事するのはXのみであり、本件会社の他の従業員らがこれに従事することは予定されておらず、実際にも従事しなかった。さらにその後、Xは、CからB商店を承継し、同取決めの取扱いを継続した。
また、本件会社の目的は、上下水道設備や空調機器等の設計施工等であり、本件配達販売等業務や労働者派遣業務は含まれていない。加えて、本件会社は、本件配達販売等業務に必要な液化石油ガスの販売登録及び保安機関の認定を受けておらず、配達設備であるタンクローリー車についても自社保有はせずにB商店の事業用資産を用いていた(なお、Xは登録及び認定を受けていた。)。
2. 判 旨
1審を引用のうえ本審での主張への判示を行って、控訴棄却。
なお、令和元年7月17日付で上告棄却、上告不受理となった模様(脚注4)。
(1)必要経費該当性の判断基準等(1審を引用)
「必要経費該当性(関連性要件及び必要性要件)の判断に当たっては、投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避けるという必要経費の控除の趣旨に加え、家事上の経費との区別や恣意的な必要経費の計上防止の要請等の観点も踏まえると、関係者の主観的判断を基準とするのではなく、客観的な見地から判断すべきであり、また、当該支出の外形や名目等から形式的類型的に判断するのではなく、当該業務の内容、当該支出及びその原因となった契約の内容、支出先と納税者との関係など個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に判断すべきである。」
(2)あてはめ(1審を引用)
「Xは、本件期間において、自己の個人事業(B商店)に係る業務全般を、自己の保有する設備、車両等や資格を用いて、日常的に、自己の経験と判断に基づき、自己の労力及び経費負担をもって遂行していたものというべきである。」
「Xによる本件委託業務の遂行の実質は、本件会社による役務の提供(業務委託)や労働力の提供(労働者派遣)といったものではなく、正に、Xが自らB商店の事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはない。」
「そうすると、B商店の業務に関し、B商店たるXが本件会社に対し本件配達販売を委託し、本件会社がこれを遂行し、Xから本件会社に対し本件外注費が支払われたという形式及び外観が存在するものの、その実質は、Xが自らB商店の事業主としてその業務を遂行する一方で、本件取決めに基づく取扱いを継続することにより、本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)を、「外注配達費」や「人夫派遣費」という名目で本件外注費として本件会社に支払っていたものといわざるを得ない。」
「以上によれば、本件外注費は、社会通念上、B商店の業務の遂行上必要であるとはいえず、必要経費該当性の判断基準における必要性要件を欠くものと認められるから、Xの事業所得に係る必要経費には該当しないというべきである。」
(3)実質課税ではないかとの主張に対して
ア 1審引用部分
「必要経費該当性(関連性要件及び必要性要件)の判断に当たっては、……、個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に判断すべきであり、このような判断の方法は、所得税法37条1項の文理から離れるものではなく、その解釈として許される範囲を超えるものではない。」
「なお、本件外注費の業務遂行上の必要性(必要性要件)を否定することは、あくまでも必要性の評価の問題であって、本件取決めや本件取引を無効または不存在とみなすものではない」
イ 本審
「なお、ここにおいて、「外注配達費」や「人夫派遣費」という名目で本件会社に支払っていた本件外注費を、本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)と評価したからといって、当事者が選択し、有効に成立している私法上の取引関係の法形式を引き直して認定するものではなく、本件外注費の支払が業務の遂行上必要なかったことの根拠として述べるものに過ぎない。」
3. 検 討
(1)必要経費該当性における必要性要件の判断方法(本判決の特異性の抽出)
ア 必要経費の定義
必要経費の理論的定義については、「所得を得るために必要な支出のことである。」(脚注5)とされ、本判決もこの理解を前提としている。
イ 必要経費該当性の判断基準
また、必要経費該当性の判断基準については、一般に、①必要性、②関連性が求められるとされる(脚注6)。この点も、本判決は踏襲している。
ウ 必要性要件の判断方法
① 学説等
そして、同判断基準該当性の判断方法につき、学説や多くの判例では、「必要性の認定が、関係者の主観的判断を基準としてではなく、客観的基準に則してなされなければならないことは、いうまでもない。」(脚注7)との考え方がとられている。
② 本判決
これに対して、本判決は、①に続けて、「また、当該支出の外形や名目等から形式的類型的に判断するのではなく、当該業務の内容、当該支出及びその原因となった契約の内容、支出先と納税者との関係など個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に判断すべき」とする。
注7で掲げられている例を踏まえると、①は、当該支出と収益との性質上の因果性の有無ないし程度を問題にしているように解される。
これに対して、②は、より個別具体的な事案に踏み込んで、周辺事情を「実質」として考慮して支出の要否の判断を行うことになる点で、特異性を有する。
そして、本判決のみからは、いかなる場合に、どの程度まで、個別具体的な事案への踏み込みを行うのかは、明らかではない(脚注8)。
加えて、これらが「また」で並列されている趣旨も明らかでない(脚注9)。
これらの点については、本判決が先例性を持つとすれば、裁判例の蓄積により明らかになることが期待される。
(2)先例との関係
ア 必要性の判断を「社会通念に従って実質的に行われるべき」とするもの
必要経費性の判断を、「社会通念に従って実質的に行われるべき」等、「客観的」の語でなく、「実質的」の語を用いて行っている裁判例として、次のものがある。そこで、これらの「実質的」の語が担っている意味を検討する(脚注10)。
① 青森地判昭和60年11月5日税資147号326頁(脚注11)
事業用名下の借入金利息の必要経費性につき、借り入れた金員の支出先が子の大学入試に関連していることを指摘して、必要経費性を否定した事例。
支出と収益の因果性を判断する中で、支出の持つ性質の判断を行ったものとみることができる。
② 東京地判平成16年11月30日税資254号順号9839
経営コンサルタント業を営む者による貸し付けの貸倒損失の必要経費性につき、経営コンサルタント業務の業務範囲に含まれないことを指摘して、必要経費性を否定した事例(脚注12)。
通常性の判断を行っているようにもみえるが、支出と収益の因果性を判断する中で、支出の持つ性質の判断を行ったものともみることができる。
③ 千葉地判平成17年11月11日税資255号順号10200(脚注13)
税理士による顧問先への貸し付けや保証をしたことによる損失の必要経費性につき、業務範囲に含まれないことを指摘して、必要経費性を否定した事例。
支出と収益の因果性を判断する中で、支出の持つ性質の判断を行ったものとみることができる。
④ 福岡地判平成22年8月24日税資260号順号11493
土地の賃貸人が、賃貸に際して行った仮設墓地の維持管理、同土地を他の土地と交換するための情報収集、賃貸借契約の条件面に関する情報収集のために行った各支出等の必要経費性につき、家事費該当性や収益との因果性がないことなどを指摘して、必要経費性を否定した事例。
支出と収益の因果性を判断する中で、支出の持つ性質の判断を行ったものとみることができる(脚注14)。
⑤ 福岡地判平成26年4月22日税資264号順号12458
土地の賃貸人が、(i)賃貸借契約の条件面に関する情報収集、(ii)土地の現況確認等のために行った支出の必要経費性につき、支出の周辺事情を指摘して、必要経費性を否定した事例。
(i)については、賃貸借契約が他の土地所有者と同様に定型的に同一の条件で締結されていること等から、契約条件が個別交渉により左右されることが予定されていないことを、(ii)については、賃貸目的物が土地であって建物と異なり損耗等により資産価値の減少や契約条件の悪化がほとんど考えられないことを、それぞれ指摘しており、これらの指摘から支出の必要性の有無という評価を直ちに行ったと読めば、本判決に近いとみることもできる。他方、契約条件の変動可能性に触れていることから、いずれも、あくまで支出と収益の因果性の有無の判断にとどまり、収入と離れた支出自体の要否を評価するものではないとみることもできようか。
イ 小括
上記ア⑤を後者のように理解すれば、先行する裁判例は、必要性の判断として、「実質的に判断」の語を用いていても、収入・収益との関係で当該支出の持つ性質、属性の判断を行って、支出と収入・収益の因果性の有無を判断している点では共通しているということができる。
これに対して、本判決は、「実質的に判断」として、収入と離れた支出自体に対して、支出の周辺事情を評価してそれが不要な状況でなされたものであると評価し、直ちに必要経費該当性を判断している点で、先例との関係で特異性がある。
(3)租税回避の否認、事実認定による否認の概念等との関係
ア 租税回避の否認、事実認定による否認等の概念整理
では、本判決の上記特異性は、解釈方法としての体系上、どのように位置付けられるべきか。
納税者の採用した私法上の法形式に反する形で課税要件の充足判断がされるものとして、本件との関係では、脱税、租税回避の否認、事実認定・私法上の法律構成による否認(以下「事実認定による否認」とする。)が一般に考えられる。以下では、各概念を整理(脚注15)し、本判決との対比を試みる(脚注16)。
① 租税回避の否認
租税回避の否認とは、「私法上一応正当に発生した法律効果を、課税上無視することが許される場合」(脚注17)である。
この場合、私法上有効に生じた法律効果が、課税上は無視され、「通常用いられる法形式に対応する課税関係が充足されたものとして取り扱」(脚注18)われることになる。
そして、租税法律主義との関係で、明文の否認規定が存在しない限り、租税回避の否認は行えないと考えられている(脚注19)。
② 事実認定による否認
事実認定による否認とは、課税要件事実の存否の認定において、「表面上存在する外観と異なる実体を探求するという事実認定・私法上の法律構成の方法」(脚注20)である。
ただし、このような事実認定は、租税法律主義に基づく納税者の予測可能性の確保の観点から、私法上の事実認定・契約解釈の原則に従い、当事者の表示した「表面的な法形式が不存在ないし無効であるような例外的な場合に限られると解すべき」(脚注21)とされる。そして、それは、ほぼ民法上の通謀虚偽表示を意味する仮装行為が存在する場合を指す(脚注22)。
したがって、この例外的場合に限って、「当事者の表示した法形式とは異なるところの私法上の真実の法律関係に基づき課税がなされる」(脚注23)とする。
そして、この操作は、あくまでも私法上の事実認定・契約解釈の原則に従ったものであり、私法上の(真実の)法律関係を尊重するものとしてのみ、行うことができる(脚注24)、と整理される。
③ 脱税(租税逋脱)
これらに対して、脱税(租税逋脱)とは、「課税要件の充足の事実を全部または一部秘匿する行為」(脚注25)である。
イ 各概念と本判決の判断との対比
本判決は、所得税法37条1項該当性を判断したものだから、①租税回避の否認ではない。
そして、Xの本件会社への支払いにつき、その個別具体的な事案における実質から本来支払う必要がないものと「評価」するものであって、Xと本件会社との間の合意が私法上不存在であるとか無効であるとするものではないから、②事実認定による否認でもなく、③脱税を事実認定したものでもない。
このように、本判決の判断は、事実認定の次元の問題ではなく、所得税法37条1項の文言解釈の次元におけるものと位置付けられ、その位置付けにおいて、従前と異なる判断方法を定立したものとして、解釈方法としての体系上位置付けられる。
しかし、これは、私法上有効な法律関係の存在を肯定するにもかかわらず、これと異なる真実の法律関係を探求する法的実質主義を超えて、経済的成果や目的に即して法律要件の存否を判断する経済的実質主義を文言解釈の中で行うことになり、従来の議論では許されていないもの(脚注26)ではないかとの疑問なしとしない(脚注27 28 29)。
本判決の特異性が、今後、先例性を持つのか、それはどのような位置付けでのものか、注視が必要である。
(4)所得税法157条1項による処理を行った事案との関係
本件に類似する事案としては、自己が代表取締役を務める同族会社たる不動産管理会社へ支払った管理委託料と不動産所得の計算(脚注30)、病院経営者による同様の病院建物の管理会社へ支払った委託料と事業所得の計算(脚注31)、税理士による同様の会計管理会社へ支払った経理委託料と事業所得の計算等の事案が考えられる。
これらの事案の処理としては、委託内容等の個別的事情を重視せずに、非同族の同業他社の平均的な委託料等の額との比較によって、「所得税額の負担を不当に減少させる結果」の有無を検討し、所得税法157条1項を適用する実務が固まりつつあるとされる(脚注32)。
本判決は、所得税法37条1項で必要経費性が否定された事案では、所得税法157条1項について「判断する必要がない」とするが、仮に本件につき所得税法157条1項を適用すれば、非同族の同業他社の平均的な委託料の範囲までは必要経費性が肯定されるように思われ、これらの事案との区別は明らかではない(脚注33)。
そもそも、所得税法157条1項と所得税法37条の適用関係については、議論がある。所得税法157条1項を、実体法としての租税回避の否認規定であると理解すれば、論理上、本判決のように所得税法37条1項の判断が先行する(脚注34)(ただし、この中にも、所得税法157条1項に、事実認定による否認の立証上の困難性を緩和するために用いることを肯定する手続ないし証拠法的な内容をも含ませる立場(脚注35)もある。)。他方、法人税法22条2項の規定に関する適正所得計算説の立場から、課税庁による選択的な適用を認める立場(脚注36)も近時あり、この観点からも、本判決がどの程度の先例性を持つのか、注視される(脚注37)。
(5)数量的な必要経費性の判断の可能性
関連して、本判決の示した必要経費性の判断方法によって、支出額の一部のみについて必要経費性が肯定されうるかも今後の課題となる(脚注38)。上記のとおり、所得税法157条1項の判断では、一般的に委託内容の仔細は重視されない傾向であるところ、本判決が行う支出の周辺事情への踏み込みの程度によっては、事案により、所得税法157条1項の適用を受ける場合よりも肯定される必要経費が多額になりえるとも考えられるからである(脚注39)。
日本の所得税法37条1項はアメリカ連邦所得税と異なり、「通常かつ必要」性までは求められていないこと、及び、必要経費として適正な金額を判断することの行政上の作業の困難性から、数量的な必要経費性の判断がどこまで課税実務上実施されるかは議論があるところである(脚注40)。
本判決の判断方法が先例性を有していくとすれば、この意味でも、その作動の要件、作動する際の考慮事情の範囲につき、注視が必要である(脚注41 42)。
福島那央 (ふくしま なお)
森・菊地法律事務所
早稲田大学法学部卒業、一橋大学大学院法学研究科法務専攻(法科大学院)修了。
上場会社からスタートアップまで企業の契約法務、労務対応、訴訟等の紛争対応に加え、事業承継や相続、不動産取引や住宅紛争等の案件も手掛ける。
脚注
1 大阪高判平成30年11月2日税資268号順号13206。同判決の評釈として、司馬えんに「個人事業主が法人に支払った業務委託費は、必要経費に算入されないとした事例」税研JTRI35巻4号107頁(2019)、林仲宣=谷口智紀「同族会社に対する外注費と事業所得の経費性」税務弘報2019年7月号66頁、袴田裕二「所得税法上の必要経費」ジュリスト1553号123頁(2021)、木山泰嗣「同族会社に支払った業務委託費が必要性要件を満たさないとして必要経費の算入が否定された事例」税経通信2021年1月号199頁など。
2 本判決は事実認定につき1審・大阪地判平成30年4月19日税資268号順号13144を引用している。同判決の評釈として、長島弘「個人事業に係る必要経費の必要性が争われた事例」税務事例51巻4号28頁(2019)、山田麻未「同族会社に支払った外注費が所得税法37条1項の必要性要件を満たさないとされた事例」税法学582号193頁(2019)、木山泰嗣「同族会社に対する支払と必要経費の必要性要件」税理2019年8月号152頁など。
3 ただし、このときの更正の根拠は所得税法157条1項だった。
4 袴田・前掲注1)123頁。
5 金子宏『租税法』313頁(弘文堂、第23版、2019)、水野忠恒『体系租税法』311頁(中央経済社、第3版、2021)、谷口勢津夫『税法基本講義』324頁(弘文堂、第6版、2018)など。
なお、水野・前掲311頁は、理論上の必要経費の定義を同様に解したうえで、所得税法37条の「必要経費」の範囲は、同条の解釈問題であることを明示的に指摘する。そのうえで、同315頁は、①支出の実在性、②支出の必要性、③金額の相当性が認められる範囲で、同条の「必要経費」となるとする。
6 金子・前掲注5)314頁「ある支出が必要経費として控除されうるためには、それが事業活動と直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用でなければならない。」など。ただし、このような所謂2要件説には問題があるとするものとして、占部祐典「所得税法における必要経費の概念と判断基準」同志社法学71巻1号113頁以下(2019)(なお、同論文の著者は本件の納税者側代理人であり、本判決についても言及されている。)。
7 金子・前掲注5)314頁。ここでは、不動産賃貸業者の所有地で現に貸付の用に供されていない土地に対する固定資産税の必要経費性につき、それが近い将来確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかである場合か否かにより判断した例、更正処分取消訴訟に勝訴した場合に受ける還付加算金に対する同訴訟での訴訟費用や補佐人への報酬の必要経費性を、同加算金の利息の性質を踏まえて判断する例が挙げられている。
8 袴田・前掲注1)125頁、木山・前掲注1)206頁もこの点を指摘する。
9 木山・前掲注1)205頁は、②を①の考慮事情及び観点と位置付ける。
10 袴田・前掲注1)125頁は、本判決で「社会通念に従って実質的に判断」がなされた場面が、同様のフレーズを用いて必要経費性を判断した他の裁判例(後記③及び④)と異なっていることを指摘している。
11 控訴審・仙台高判昭和61年10月31日税資154号413頁、上告審・最判昭和62年7月7日税資159号31頁も、この判断を維持している。
12 なお、貸付を受けた会社が貸付を受けて再建した後に、同社から顧問収入等を得たとしても、同収入は給与所得又は雑所得となり、問題となった貸倒損失の必要経費算入の前提を欠くとしている。
13 控訴審・東京高判平成18年3月16日税資256号順号10346も、この判断を維持している。
14 ただし、賃貸借契約の条件面に関する情報収集費用については、「原告は、地主会とのかかわりを持っていなければ、本件賃貸借契約上原告が不利に扱われるおそれがある旨主張するが、本件証拠上、その主張を裏付けるような事情は認めがたい」として、周辺事情を認定にするに足りないことを指摘している。
15 用語の厳密な整理を行った中里実「租税法における事実認定と租税回避否認」金子宏編『租税法の基本問題』121頁以下(有斐閣、2007)の整理に依拠した。
16 結論として、あえて支出との関係で敷衍すれば、③支出や支出根拠となる合意の存在を事実認定の結果認めない場合が脱税、②それらは存在するが合意が通謀虚偽表示であって私法上法律効果が発生しないために真実の法律関係たる同支出及び合意の効果がない状態、すなわち支出がされていない状態を事実認定して必要経費性を否定する操作が事実認定による否認、①合意の私法上の法律効果の発生を認めたうえで、明文の規定により、それを課税上無視する操作が租税回避の否認となる。
17 中里・前掲注15)130頁。
18 金子・前掲注5)135頁。
19 中里・前掲注15)127頁。
20 中里・前掲注15)128頁。
21 中里・前掲注15)129頁。
22 中里・前掲注15)131頁。
23 中里・前掲注15)129頁。
24 中里・前掲注15)131頁。
25 中里・前掲注15)130頁、金子・前掲注5)135頁。
26 金子・前掲注5)149頁、谷口勢津夫「『租税回避』の意義と限界」金子宏編『租税法の発展』36頁以下(有斐閣、2010)を参照。
27 なお、裁決平成18年6月13日裁決事例集71巻205頁は、不動産賃貸業を営む者が、同族会社に支払った不動産の管理料の必要経費性の判断において、各支出に対応する委託業務は、別会社が行っていることが認められる一方、支払いを受けた同族会社がそれを行った事実を認めるに足りる証拠がないとして、各業務を委託する客観的必要性を認めることができないとして、必要経費に算入すべき金額を0円とすることが相当とした事例である。
裁決であること、事案の違い、基準が「客観的に必要経費として認識できる」か否かであるなどの違いがあるが、本件に類似する判断という読み方もあり得る。ただし、同族会社が委託を受けたとされる業務を行っていたと認めるに足りない旨の指摘の意味について、事実認定論である(実際に、文面上も評価ではない。)と捉えて、委託関係を通謀虚偽表示等とし、真実の法律関係が贈与等であることを指摘したものとすれば、事実認定による否認を行ったものとして、本判決と区別して考えることもできる。
28 さらに、従来の議論では必要経費性が認められていた違法ないし不法な支出について、本判決のような周辺事情の考慮の取り込み方によって、その必要経費性を否定することも考えられ、理論的に、本判決の射程には慎重な検討が求められる。
29 本判決の射程を限定しようとする立場からは、例えば、二重払い類似の関係の支出の事案のみを対象とすることが考えられるが、本判決のみからは、そのような限定は直ちには読み取れない。
30 東京地判平成元年4月17日訟月35巻10号2004頁など。また、転貸方式につき、最判平成6年6月21日訟月41巻6号1539頁。
31 裁決平成元年4月25日裁決事例集37巻100頁。
32 佐藤英明「所得税法157条(同族会社の行為・計算否認規定)の適用について」税務事例研究21号47頁(1994)。
33 また、本判決を前提とした場合、事後処理としての本件外注費に関する本件会社のXからの売上の益金性も問題である。本判決は所得税法157条1項を適用するものでないため、明文なき対応的調整は困難と思われる。本件会社が、益金性の判断についても本判決類似の実質的判断がなされるとの解釈を主張して、更正の請求を行った場合に、同解釈が受け入れられるかの問題となろうか(さらには、収入金額性についても同様の議論が及ぶことになろうか)。
34 谷口・前掲注5)74頁。なお、上記の租税回避の否認等の概念整理によれば、事実認定による否認は所得税法37条1項該当性の判断の中で行われるものである。
35 水野・前掲注5)699頁。増井・後掲注38)の機能的な立場もこの趣旨を含むか。
36 谷口・前掲注5)73、74頁の整理。佐藤・前掲注32)61頁もこのようにも理解できるか。また、各規定の所得税法上の構造的視角の検討から選択的な適用を認める理解(酒井克彦「所得税法157条は同法37条1項の『別段の定め』か」税務事例52巻4号4頁(2020))も、ここに位置付けうるか。
37 タックスプランニングの視点からは、本判決が先例性を持てば、所得税法157条1項による否認可能性への対応に加えて、所得税法37条1項における必要性判断についても留意する必要が出てくることになる。仮に本件で委託書面や設備等の貸与書面、受託会社の定款などが整備されていれば、あてはめにおいて異なる結論もありえたように思われる。
38 谷口・前掲注5)330頁、増井良啓「所得税法157条を適用して過大不動産管理料の必要経費算入を否定した事例」ジュリスト965号102頁(1990)(東京地判平成元年4月17日訟月35巻10号2004頁の判批)も、一般論として、この必要経費性の数量的判断の可能性を指摘する(ただし、増井は所得税法157条を機能的に同業者比準に基づく更正・決定を承認して立証を緩和するものと位置付ける立場から、同条の37条1項に対する優先(又は選択)的適用を肯定する。)。
39 本件1審は、XがB商店を承継する前のCによる本件会社への本件配達運搬業務にかかる外注費の支払い、同承継後も続いた本件会社従業員であるXの妻によるB商店が本件会社に委託した事務処理にかかる事務費の支払いについて、「判断の基礎となる事情が大きく異なる」として必要経費該当性を肯定し、本判決もこの部分を引用している。ここでは、非同族の同業他社の平均的な委託料等の額との比較等の金額の相当性についての言及はない。
40 水野・前掲注5)317頁。後掲注42)・山口地判平成7年6月27日税資209号1167頁は、ここでの行政上の困難性の程度が小さかった事案と考えることができる。
41 納税者側としては、所得税法157条1項によって否認された事案において、本判決を援用して、所得税法37条1項により必要経費該当性の判断を数量的に行うべきと主張し、より多くの必要経費控除を認めるべきと主張することが考えられる。
42 例えば、山口地判平成7年6月27日税資209号1167頁(広島高判平成9年7月18日税資228号149頁、最判平成10年2月26日税資230号814頁で維持。)は、「客観的に必要経費として認識できる」か否かを基準とするものだが、病院を経営する納税者が、その従兄弟に当たる医師に対して支払った報酬について、当該従兄弟の勤務内容が他の非常勤医師の勤務内容に比して特に異なったものではなかったこと、報酬額が他の非常勤医師に対する報酬額や当該従兄弟の本務の地位で受けていた報酬と比較して著しく高額であること、当該従兄弟の勤務時間の減少が報酬額の決定において考慮されていないことなどから、高額報酬の理由として、従兄弟であるという「実情」を挙げたのち、他の非常勤医師に対する1日当たりの報酬額に対して、当該従兄弟が勤務した日数を乗じた計算した金額のみを、業務の遂行上客観的に必要な報酬として必要経費に算入すべき金額とし、それを超える部分の必要経費該当性を否定しており、参考になりえる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.