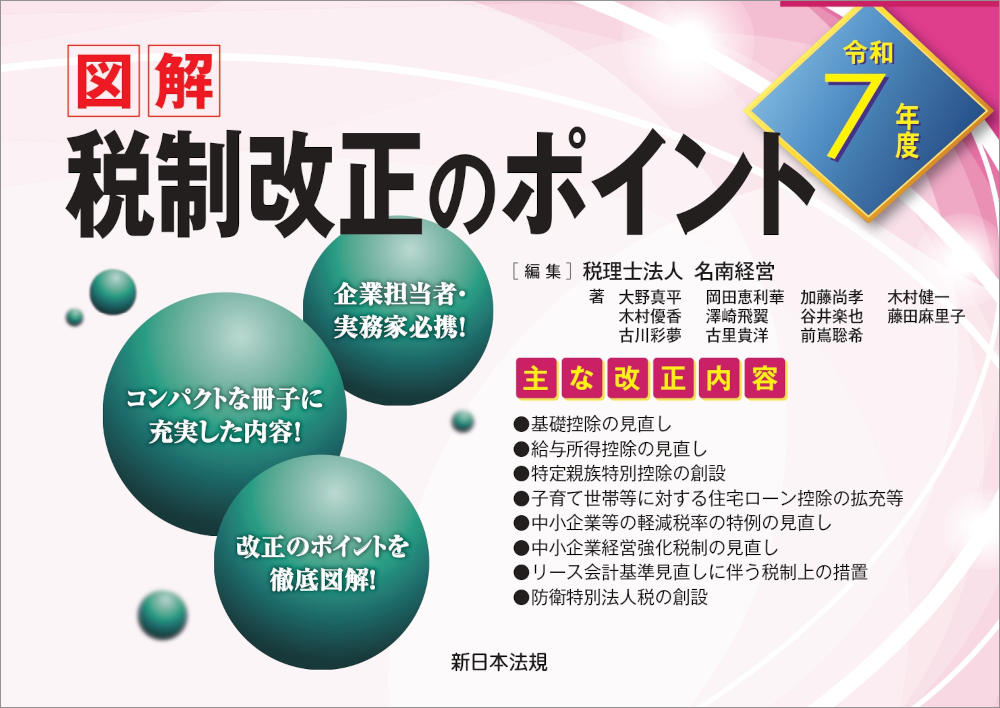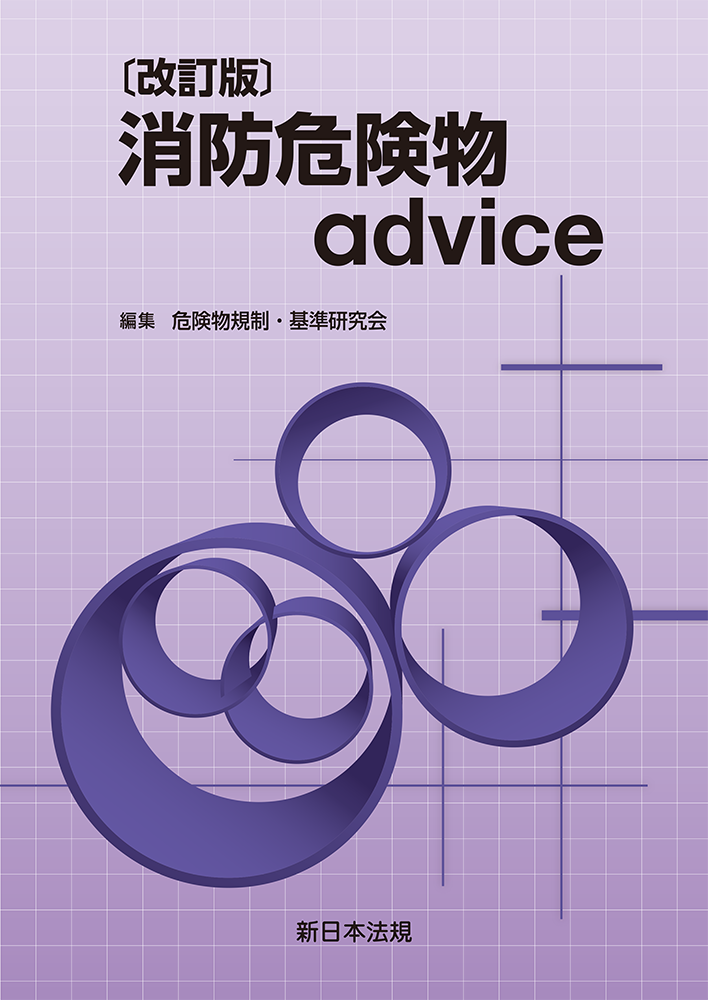解説記事2019年12月02日 解説 「財産評価基本通達総則6項」による評価とその問題点の検証(2019年12月2日号・№813)
解説
「財産評価基本通達総則6項」による評価とその問題点の検証
中央大学名誉教授・税理士 大淵博義
1 はじめに
昭和の後半から平成当初にかけて発生したバブル経済下における異常な土地高騰により、その高騰した実勢価格と財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)、路線価等に基づく評価額(以下「通達評価額」という。)との間で著しい開差が発生した。そこで、相続前の近接した時期に、被相続人が借入金により高騰した土地を取得し(相続開始後に譲渡)、相続税申告に際して、当該土地の高騰した土地等の通達評価額と借入金額との開差(借入金債務超過額)を他の相続財産から減殺して課税価格を引き下げて相続税負担を回避する事例が発生した。後に述べるように、課税庁はかかる租税負担の回避を規制する根拠として、「評価通達総則6項」(以下「総則6項」という。)に規定する評価通達の評価額によらない「特別の事情」があるとして、その取得した価額や相続開始後に譲渡した価額を評価額として課税処分を行った。
かかる事例は、平成3年における法的規制措置や評価額の引き上げ等により対処した結果、その後は総則6項の適用事例は影を潜めていたが、総則6項により収益還元法を基礎とした不動産鑑定評価額を時価とした課税処分を適法とした東京地裁令和元年8月27日判決が言い渡されたのである。
そこで、本稿では総則6項の適用に関する評価論及びその先例判決を分析した上で、本判決を紹介し、その判示内容の問題点、疑問点について検討を加えて、その是非を検証することとしたい。
2 「総則6項」の法的位置付けと運用の実際
(1)「総則6項」の性格
国税庁長官が発遣する評価通達は、相続財産等の評価の統一性と整合性を図り、納税者間の課税の公平を維持し、かつ、これを公開することにより、納税者の申告・納税の便宜に供して公正な課税を実現することを意図している。
その評価通達は、財産の時価の意義につき、「時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」(評価通達「総則1項」(二))とし、この通達評価額が相続税法22条の時価ということを宣明している。
その通達評価額は、「財産の価額に影響を及ぼすすべての事情を考慮すべき」ところ、実際には、その価額に影響を及ぼすすべての事情を調査し把握することには限界があることはいうまでもないことである。
そこで、総則6項において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。このような「著しく不適当と認められる」とは、精通者による調査の際には顕現されていなかった客観的事情、例えば、地盤沈下や液状化被害が報道され、それがその地域の取引価額に影響していることが明らかになった場合等が、「著しく不適当と認められる財産の価額」であると解するのが、この通達の自然な文理解釈である。それが「通達評価額により評価することが著しく不適当」という言葉の意味であると解されるのである。
しかして、本来、①租税負担軽減(租税回避)の意思や目的という主観的意思、②借入金による土地取得という調達資金の相違が、土地等の客観的交換価値(時価)に「影響を及ぼすべき事情」として理解することは当を得ないことである。このことは、独立当事者間の売買において、相手方の主観的意思や相続財産の取得の原資の如何とは無関係に売買価額が決定されるという実際の売買取引に照らしても当然の事理といえよう。
ところが、次に紹介する総則6項適用の先例判決では、実際の取引価額と通達評価額との間で開差が著しい土地を相続により取得した場合で、上記①及び②の事情が認定されて課税庁の実勢価格等による更正処分が判決によりすべて支持されているというのが現実である。
このことは、評価論としての正論はさておき、租税負担が不当に回避される行為を行った納税者に対しては、通達評価額を採用せず、現実に明らかにされている価額を採用して、租税負担の個別的妥当性を重視しているのが、現在の課税実務であり判決であると言えよう。
(2)総則6項適用の先例判決の分析
~相続直前の借入金による不動産の取得と「特別の事情」~
総則6項が適用された最初の判決は、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁、控訴審・東京高裁平成5年2月16日判決・判例タイムズ845号240頁)である。
この事例は、昭和62年12月の相続開始直前の同年10月に借入れを行って7億5,850万円のマンションを取得、相続直後の翌年1月にマンションの購入先の不動産業者との間で本件マンションの売却の媒介契約を締結して、翌年4月から7月にかけて、本件マンションを総額7億7,400万円で売却し、借入金を返済したという事例である。
同判決は、「相続前後を通じて事柄の実質をみると、当該不動産がいわば一種の商品のような形で一時的に相続人及び被相続人の所有に帰属することとなったに過ぎないとも考えられるような場合についても、画一的に評価通達に基づいてその不動産の価額を評価すべきものとすると、他方で右のような取引の経過から客観的に明らかになっているその不動産の市場における現実の交換価格によってその価額を評価した場合に比べて相続税の課税価格に著しい差が生じ、実質的な租税負担の公平という観点からして看過し難い事態を招来することとなる場合があるものというべきであり、そのような場合には、前記の評価通達によらないことが相当と認められる「特別の事情」がある場合に該当する。」と判示し、この場合には、市場における現実の交換価格によって評価されることが許されると判断している。
しかしながら、この判決が、「取引の経過から客観的に明らかになっているその不動産の市場における現実の交換価格によってその価額を評価した場合に比べて相続税の課税価格に著しい差が生じ」るとしているが、そもそも、相続財産であるマンションの評価額は評価通達による路線価及び建物の固定資産税評価額により評価され、市場価格によって評価されることは予定されていないから、相続税の課税価格に著しい差異が生ずることはない。この点の判示は誤りというべきである。
なお、この判決は、「一種の商品のような形で一時的に所有することとなった」本件マンションを評価通達により評価することとすると、棚卸資産の不動産は販売価額を基礎として評価されることから、それとの「実質的負担の公平」を判示したものと考えることもできなくはない。
その後、同種の判決として、①東京地裁平成4年7月29日(行裁例集43巻6・7号999頁、控訴審・東京高裁平成5年3月15日判決・行裁例集44巻3号213頁)、②東京地裁平成5年2月16日判決(判例タイムス845号240頁、控訴審・東京高裁平成5年12月21日判決・税資199号1302頁)が言い渡されている。
これらの判決も相続直後に市場で売却した事例であり、判決は、評価通達による評価額と取引価額との開差の超過借入金債務の額が他の積極財産から控除されて相続税が不当に減少するという点に着目して、「他に多額の財産を保有していないため、右のような方法を採った場合にも結果として他の相続財産の課税価格の大幅な圧縮による相続税負担の軽減という効果を享受する余地のない納税者」との間での実質的な租税負担の公平という観点から看過し難いものといわなければならない、と判示した。
この種の事案の特質は、取得した土地建物等を貸し付けて収益を獲得する本来の事業目的を予定していないために、多額な利息の支払いを継続することが困難なために、取得の時から当該不動産の売却が予定されているという点にある。その点では、前記判示の「一種の商品のようなもの」として棚卸資産と同質という実質的評価により、棚卸資産の評価額である販売価額と同列に評価することが合理的であるという理解もあり得よう。
これらの事例で最も注目すべき事実は、取得した不動産の実勢価格(取得価額)が明確になっていること、相続直後に当該不動産を取得価額とほぼ同額で売却して借入金を返済したという事実である。
ちなみに、上記東京地裁平成5年2月16日判決は、借入金によって不動産を取得したものではなく、他の不動産の売却代金により取得した物件については、その相続財産としての価額を評価通達以外の客観的な交換価格によって評価することを正当化する理由はなく、その評価は、通常の場合と同様に、評価通達に定める方法によって行われるべきである、と判示した。
しかして、この先例判決では、相続税対策として相続直前に現預金で保有することに代えて、評価額の低額なマンションを取得して賃貸し、その貸付事業を将来も継続すると認められる場合には、事業目的のある事業活動であるから、仮に、相続税軽減の意図があるとしても、現預金(流動資産)の保有からマンション(不動産)の保有に保有態様が変質した以上、当該マンションは通達評価額で評価されるし、小規模宅地の特例の適用も可能となる。
しかし、不動産の取得資金が他人資本か自己資本かという資金調達の差異により、客観的交換価値(価格)が変わるという評価論の論理的な矛盾については、先例判決においても、必ずしも理論的一貫性のある説示がなされたわけではない。そこで、この総則6項が適用された最新の東京地裁令和元年8月27日判決を紹介して検討を加えたい。
3 東京地裁令和元年8月27日判決の検証
(1)本判決の概要
<事実の概要>
被相続人は、90才の平成21年1月に甲不動産(甲土地・甲建物)を8億3,700万円で取得、その原資はその4分の3程度の6億3,000万円をM信託銀行からの借入れを主としたものである。また、同年12月、乙不動産(乙土地・乙建物)を総額5億5,000万円で取得したが、その原資は約79%が銀行借入れと妻子からの借入れを主としたものである。
被相続人は平成24年6月に94才で死亡したが、その共同相続人(5人)は両不動産の時価を通達評価額に基づいて相続税申告を行なった。ところが、課税庁は、この申告に対して、通達評価額による申告は「著しく不適当」として、当該評価額を適用しないことによる「特別の事情」があるとして、評価通達総則6項に基づいて、国税庁長官の指示により鑑定評価額を時価とする更正処分を行った。原告主張の通達評価額と被告主張の鑑定評価額の内容は下記のとおりである。
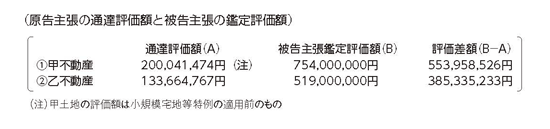
これから分かるとおり、通達評価額と課税庁の認定した時価(鑑定評価額)との差額は9億3,000万円余にも及ぶ。そして、被告主張の時価に対する通達評価額の割合は、甲不動産が26.5%、乙不動産が25.8%と約4分の1程度の評価額であり、これは、被相続人が取得した各不動産の取得価額とも近似したものとなっている。なお、乙不動産を相続した相続人は、平成25年3月に、第三者に同不動産を5億1,500万円で譲渡している。
以上のような価額の実態のもとで、被告は要旨次のとおり主張している。
① 本件各不動産の通達評価額と本件各取引額(買取価額・乙不動産の譲渡価額)の間には、いずれも著しいかい離があり、評価通達の定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかである。
② 被相続人の90才の年に行なわれた養子縁組や両不動産の借入資金による購入の一連の行為は、本来原告が負担すべき相続税を免れる相続税対策を目的としたものであり、このような行為による軽減策を採らなかった他の納税者との間の租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現する相続税の目的に反する著しく不公平なものである。
<判決の要旨>
① 被相続人が取得した本件各不動産の売買価額や乙不動産の相続後の譲渡価額、さらに本件各不動産は、いずれも約40戸の共同住宅等として利用されていることから、本件各鑑定評価は、原価法による積算価格を参考にとどめ、収益還元法による収益価格を標準に鑑定評価額を求めたものであること、不動産鑑定士の不動産鑑定評価基準により算定する不動産の正常価格は、基本的には、当該不動産の客観的交換価値(相続税法22条の時価)を示すものと考えられていることをも勘案すれば、本件通達評価額が本件不動産の客観的な交換価値を示していることについては相応の疑義がある。
② 借入金を原資とする本件不動産の取得は、被相続人及び原告らが、近い将来、被相続人に相続が発生することが予想されることから、本件被相続人の相続において原告等の相続税負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、それらを企画して実行したと認められる。
③ 本件通達の評価額を形式的に、すべての納税者に係るすべての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、本件不動産の購入及び各借入金を行わなかった他の納税者との間で、かえって、相続税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価することが許されるというべきである。そして、本件鑑定評価額の適正性が認められる以上、その鑑定評価額による更正処分は適法である。
(2)本判決に対する素朴な疑問とその検証
本判決を通読して感じた素朴で常識的な疑問とそれに対する所見は以下のとおりである。
① すでに紹介した先例判決等は、相続(直)前に借入金により不動産(相続財産)を取得したものであり、その点では本判決と類似するものであるが、決定的に相違しているのは、先例判決は不動産(マンション)を取得した時に第三者への転売を斡旋することが約定され、現実に相続開始直後に売却されて借入金が返済された事例であり(脚注1)、その実質は、いわば実際の販売価格で評価される棚卸資産(商品)と同列の資産と認定したとしても、現実に譲渡により収益を獲得していることに鑑みれば、かかる評価による現実的な担税力不足という不合理は派生しない事例である。
② 本判決の事例は、乙不動産が取得から3年余、マンションとして貸し付けられ相続開始後に売却されたものであり、その間、賃貸収益を得ているのである。しかして、例えば、被相続人が保有している不動産を相続した相続人が、納税資金を確保するために、これを他に売却して通達評価額の4倍の現金を取得したとしても、その売却価額等又は収益還元価額を評価額とする課税実務は行われていないし、裁判例もかかる事例を否認したものはない。その点では、本件鑑定評価額による課税は不平等課税の謗りを免れないであろう。
③ ところで、相続開始後も40戸の共同住宅として使用収益している甲不動産について同様の収益還元価額を基礎として評価することは、現状の課税実務に違背し、不平等課税の憲法違反の違法性が問題となる(脚注2)。つまり、現行の課税(評価)実務では、本件のように、被相続人が取得した売買価額と通達評価額との間で著しい開差があるとしても、その買取資金が自己資金によるのであれば、否認されないというのが本判決や先例判決の評価ということができる。
そうであれば、自己資金と借入資金の調達資金の差異により相続税の課税額が異なることになるが、それが評価論として当を得ないことは次のことから論証されよう。
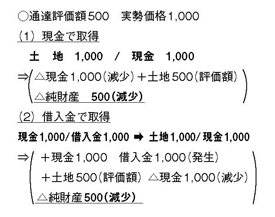
すなわち、(1)の現金で取得した場合には、現金1,000が土地(実勢価格1,000)の保有に変わったのであるから、土地が通達評価額500で評価される結果、その純資産が500減少することになる。それは(2)の借入金による取得も同様である。
つまり、借入金が仮装・架空でなく真実存在する以上、将来に亘り1,000の借入金弁済の債務を負うから、課税価格の計算上他の相続財産の価額から控除されることは当然であり、他方、借入れの現金が土地の保有に変わった結果、(1)の現金による取得と同様に通達評価額(500)により評価され、その差額500の純資産が減少することになる。
かかる通達評価額と実勢価格とのかい離は、評価の安全性からの固め(低め)の評価を意図している相続財産の評価の上で、程度の差はあれ、すでに常態化されているところであり、このことは一義的評価による課税の公平の視点から不自然なことではない。
なお、本判決は、借入れをして不動産を取得した納税者とそれをしなかった納税者との間で、相続税負担の実質的な公平を著しく害することが明らか、と判示しているが、借入れにより不動産を取得した納税者は、将来の借入金弁済の義務を負うものであるから、借り入れをしなかった納税者との間で課税価格が低減することは当然のことであり、その比較論からの判示は当を得ないものである。ここにも、本判決の欠陥が露呈している。なお、総則6項の適用は、相続開始直前に取得した土地等を相続開始直後に売却した場合に限定して適用すべきことにつき後述参照。
④ 本判決は、鑑定評価額と通達評価額との間で著しい開差があるという点を総則6項適用の重要な要因としたものであるが、本件甲及び乙不動産の近隣に位置する不動産についての相続の評価についても、同様の鑑定評価額で評価されることになるのであろうか?という疑問がある。仮に、同様の評価額(本件の様な収益還元価額)で評価するためには、国税庁長官が国税局長(所轄税務署長)に対して、それもその物件の収益状況に応じて個々に評価額が異なる特異な収益還元価額による評価を示達することにより、課税の公平を図るべきである。
⑤ 仮に、本件各不動産の近隣の物件の時価(評価額)も同様に通達評価額ではなく、その4倍の本件鑑定評価額が適用されるというのであれば、従前の評価額を改定して新路線価として、開示して広く納税者に周知する手立てを講ずる必要がある。しかし、本件判決の事実関係から推測するに、この近隣の路線価等が通達評価額から収益還元価額による評価に改訂されて開示されたということを窺うことはできない。
⑥ そうであれば、本件各不動産についてのみ、本件鑑定評価額により相続税が課税されたということが推認されるが、このことは近隣の類似する不動産につき、相続が発生していれば、鑑定評価額の約4分の1程度の価額での相続税が課税されているということであり、明らかに課税平等主義違背の違法な課税ということになろう。
⑦ さらに、毎年公表される路線価の評価額の算定に当って、本件被告(課税庁)が行った収益還元価額に基づく不動産鑑定評価額(時価)は採用されていない。売買取引における売買価額の適正額を算定するためであれば格別、本件のような相続税の資産評価に際しては、納税者の担税力を考慮して(当該相続財産を売却するに際して、常にあるべき時価により売却できる保証はないとして)、固めの評価額(公示価格の80%相当額)により評価の安全性を担保することが必要とされているところであるから、そもそも、収益還元価額を画一的、統一的な時価の評価に採用してこれを公表することは不適切である。その意味からも、本件鑑定評価額を「適切な時価」と認定することは疑問というほかはない。
⑧ さらなる疑問は、不動産鑑定評価の精通者の調査による価額を前提として、その年の路線価が決定されているのであるから、平成20年に行った本件被相続人による本件各不動産の売買取引価額が実例として考慮されているのかは明らかではないものの、買取価額の4分の1が通達評価額とされていることからすれば、本件相続開始前3年余の本件取得取引の価額が考慮されていないと推測される。このことは、そもそも、課税庁による時価評価額の算定の問題であり、そして、それが取得から4年間も通達評価額に反映されず放置されていたということの方が問題であろう。かかる課税庁の過誤を納税者に転嫁するに等しい本件相続財産の鑑定評価額による評価は疑問であり、信義則違背及び不平等課税の違法性が問題とされよう。
(3)結びに代えて
以上、種々の角度から問題点を指摘したところであるが、要するに、この判決は、相続税法上の時価として取り扱う旨公表している通達評価額を否定して、鑑定評価額、それも極めて個別性の強い収益還元価額を重視した鑑定評価額を時価と認定したものであるが、本判決は、いかなる行為を不正義として否認したのか、その否認の理論的な根拠が見えてこない。
本件の場合には、「利害相反する当事者間で通常成立する客観的交換価値」という本来の時価論からすれば、不動産は相続開始3年以上前の不動産の取得から始まり、その間、不動産貸付による収益を生み出し、小規模宅地の評価の特例も受けているマンションであるから、通達評価額により評価されるべきものである。
しかし、当該価額と鑑定評価額又は取得価額とに著しい開差があり、その結果の借入債務超過額による課税価格の減少は、すでに指摘したように、自己資金による不動産の取得の場合と、その資産の時価は何ら変わりがないのであるから、その借入金の存在を根拠として、通達評価額による評価が「著しく不適当」として総則6項を適用することに与することはできない。
そもそも、本件評価は、本来の時価論から外れた論理を前提とした評価であるから、そのことによる矛盾が派生することは当然のことである。すでに論じたように、総則6項の適用は、本来、路線価等の評価に反映されていない客観的事情が事後的に判明したことによる時価の低減を通達評価額に反映させて通達評価額を引き下げるための通達であるから、それを租税回避を規制するために同項を適用するというのは、最初から無理があるということでもある。
しかしながら、現実には、先例判決や本判決の課税庁のような運用がなされているのも事実であるから、そのことも前提として議論する必要があろう。そして、時価評価は通達の世界であり、信義則違背や不平等課税が論証されない以上、判決はかかる課税処分を支持するということが一般化しつつあるというのが現実である。
ところが、従前の先例判決とは異なり、本判決は、相続開始直前ではなく、その3年あまり前の不動産の取得であり、しかも、甲不動産は相続開始後においても売却されずに、貸付に供されて使用収益されていること、すでに論じたように、借入資金か自己資金かの調達原資の相違が、客観的交換価値に影響するはずもないこと、そして、自己資金をどの程度使用して取得した場合には、本判決の評価論が排斥されるのかも全く不明であること、これらの矛盾を考えれば、それを論理的、合理的に説明することは困難であるということでもある。つまり、納税者の予測可能性が担保されていないということであるが、かかる現状を裁判所はどのように理解しているのであろうか。
この点に関しては、先例判決のように、相続の比較的近接した時期に使用収益を目的としていない不要不急の不動産を取得し、かつ、その後も不動産を利用するという本来の事業目的を有せず、そのために、借入金の多額な利息負担を回避するために、当該不動産の売主の業者との間で、他への売却の斡旋等の約定に基づいて、相続開始後の近接した時期に売却して借入金を返済した事例に限定して、「いわば一種商品のようなもの」、つまり、棚卸資産と同視できる場合にはじめて、総則6項を適用して実際の譲渡価額等で評価することが許されると思料する。
このような先例判決のケースを先述した事例で説明すると、次のとおりである。
①現金1,000/借入金1,000
②土地1,000/現金1,000
③総則6項適用による相続財産の評価
・土地1,000 ・借入金(債務)1,000
④相続開始後に土地(1,000)を売却
現金1,000/土地1,000
⑤借入金(1,000)を弁済
借入金1,000/現金1,000
⑥その結果、事後的ではあるが、土地の取得も借入金も存在しない(何もしていない)という、状態に帰着する。かかる場合に、多額な租税負担回避という事態を招来することの不正義を是正するのが、総則6項と解すべきである。
その意味では本件事例につき、総則6項を適用して収益還元価額で評価することは課税の平等原則違反として許されないと思料する。
そして、何よりも、本件のような不動産の取得から約4年もの間、高額な取引事例の時価(売買価額)が、通達評価額に反映されていないという事実こそが問題である。これは課税庁の評価手法自体の問題であり、このような点を反省材料として再検討した上で、通達評価額と実勢価格とのかい離の解消に努めることが先決である。
さらに、本判決は、収益還元価額がいかなる場合に適用されるのか、困難な課題を提供したということができよう。
脚注
1 相続税対策の事案は、租税軽減のみにその目的があり、したがって、相続前に取得した不動産は、その投資額を回収するための使用収益が行われていない事例である。その点で、その取得した不動産は、相続後の近接した時期に他に譲渡することが計画されたものであり、その不動産販売業者が他への譲渡を斡旋するか、それができない場合には買い取ることが推認される事例である。その推認が可能であれば、その取得価額と同様の価額での売戻権(相続財産としての当該債権の評価額は、通達評価額と売戻価額との差額)が相続財産と認定され、通達評価額の当該不動産とともに相続財産を構成することになる。また、当該売戻価額全額を、当該不動産の実質的価値として相続財産を構成するということもできる。そのことにより、かかる相続税対策はシャットアウトすることが可能となる。
2 この収益還元法を基礎とした評価の適法性は被告国側が主張し、判決がこれを支持したものであるから、この判決の確定により、今後の課税実務への影響は避けられないと思われる。そして、このことが、本判決の意義として認識されるべきであろう。その際には、課税庁は、収益還元法による時価評価を評価方法の一つとして認めるべきであり、特に、今後、通達評価額の低減の根拠として、納税者から主張されることは避けられないであろう。
大淵博義 おおふち ひろよし
1970年中央大学商学部卒業。東京国税局直税部訟務官室、東京国税局法人税課審理係、国税庁直税部審理室訟務専門官、税務大学校教授、中央大学教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2015年税理士登録。著書に『法人税法解釈の検証と実践的展開(第Ⅰ巻)改訂増補版、(第Ⅱ巻)、(第Ⅲ巻)』(税務経理協会)、『寄附金課税の実務』(共著)(新日本法規出版)、『最新判例による法人税法の解釈と実務』(大蔵財務協会)ほか多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.