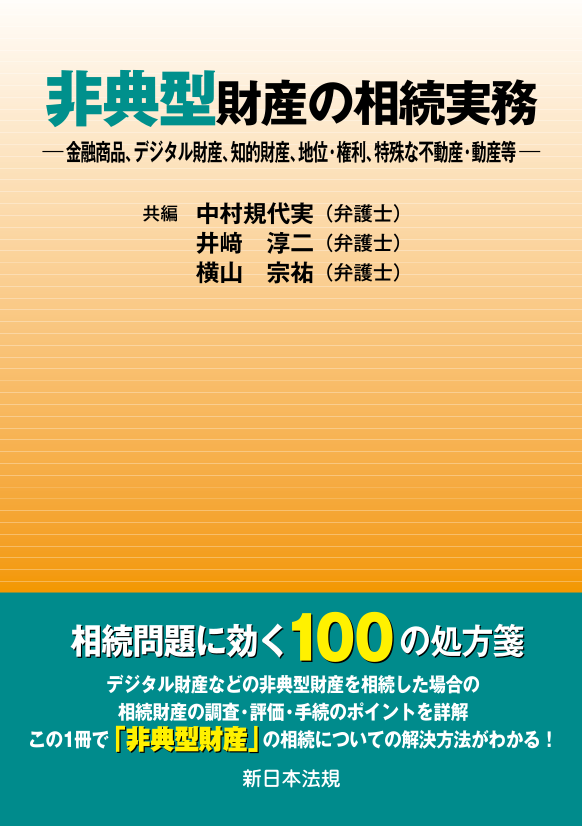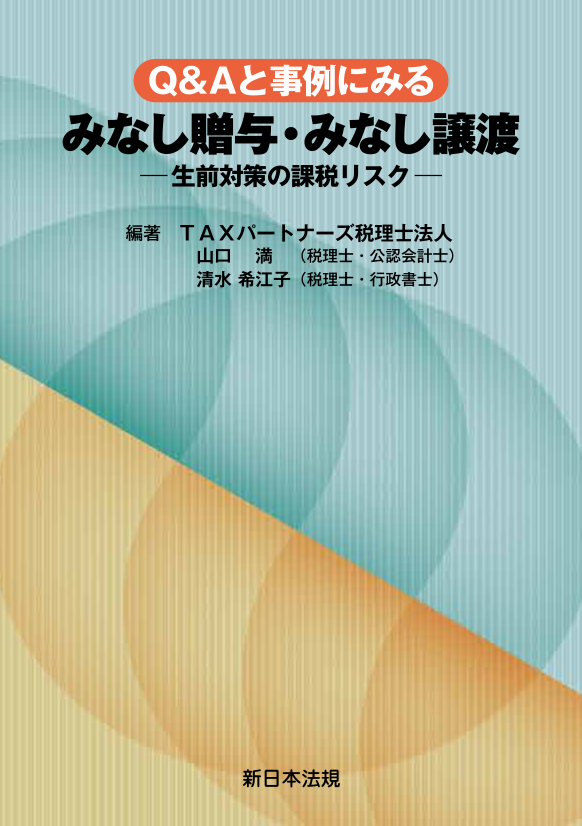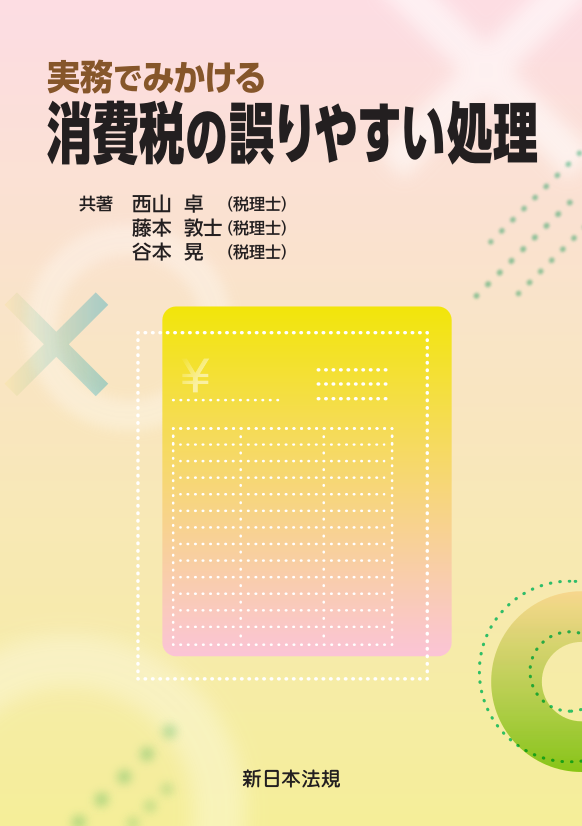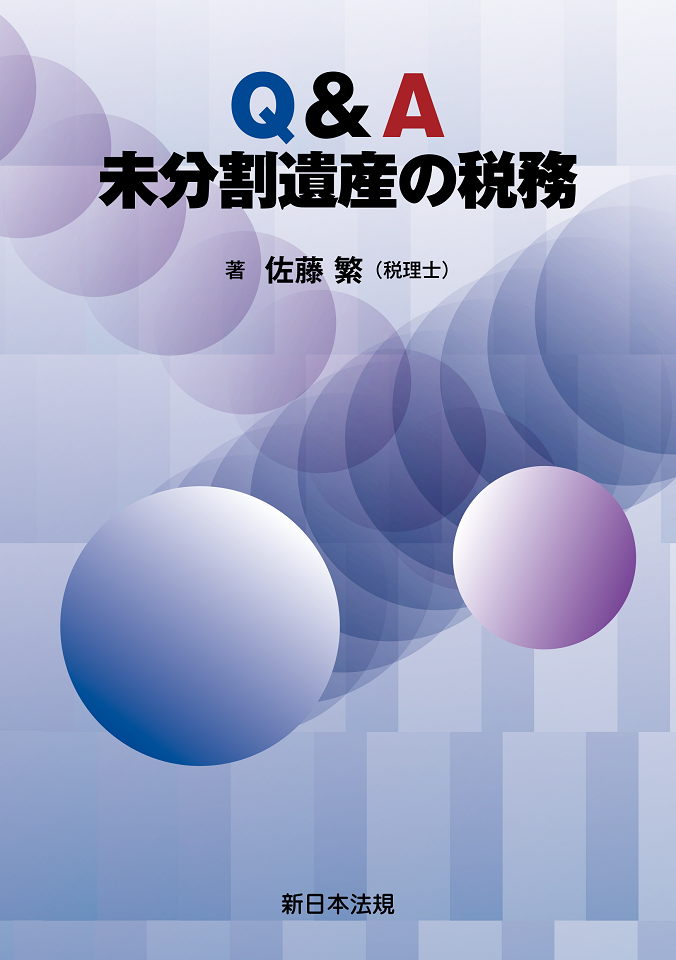解説記事2021年07月05日 ニュース特集 調査怠り通達を誤適用、思い込みで印紙税課税(2021年7月5日号・№889)
ニュース特集
取消裁決に至った原処分時のミス
調査怠り通達を誤適用、思い込みで印紙税課税
本特集では、課税当局が調査・審理担当者向けに作成している取消裁決の原因等を記載した資料の内容を紹介する。最初の事例は、更正の請求事案で価額弁償金の金額に係る調査を怠ったため相続税法基本通達11の2−10の適用を誤ったというもの。2つ目は、消費生活協同組合が作成した課税文書となる領収書の抽出過程において、領収書「作成日」における組合員名データとの照合を行っていなかった事例だ。なお、課税当局は、2つ目の事例において、本件に限らず、調査担当者等の先入観や思い込みから、収集した証拠書類等では課税要件を満たしていないにもかかわらず、課税処分に至る事案が散見されると指摘している。
価額弁償金の金額について引き直し計算をすべきか
1つ目の事例は、原処分庁が、価額弁償金の金額に係る調査を怠ったために相続税法基本通達の適用を誤ったとする事例(令和2年8月11日裁決、裁決事例集No.120)。
被相続人A(平成28年死亡)の相続人は審査請求人X及びその兄Bの2名であり、Aは一切の財産をBに相続させる旨の遺言を残していたが、Aの死亡後、XはBを相手に遺留分減殺請求訴訟を提起。平成30年3月、BがXに対して価額弁償金330,000,000円を支払うことでBと和解した。この和解では、和解時点の相続財産の評価額について合意した上で、これを基礎として価額弁償金の金額を算出していたことから、この金額を相続発生時の相続財産の評価額を基礎とした金額に引き直し計算すべきかが問題となった。
なお、Xは、価額弁償金330,000,000円を取得したとして相続税の申告書を提出。その後、取得した価額弁償金を220,000,000円とする更正の請求を行ったが、原処分庁はXの取得した価額弁償金を当初申告額の330,000,000円とする原処分を行った。一方、Bは、取得財産▲330,000,000円(価額弁償金)とする更正の請求を行い、請求どおりの減額更正処分が行われている(図参照)。
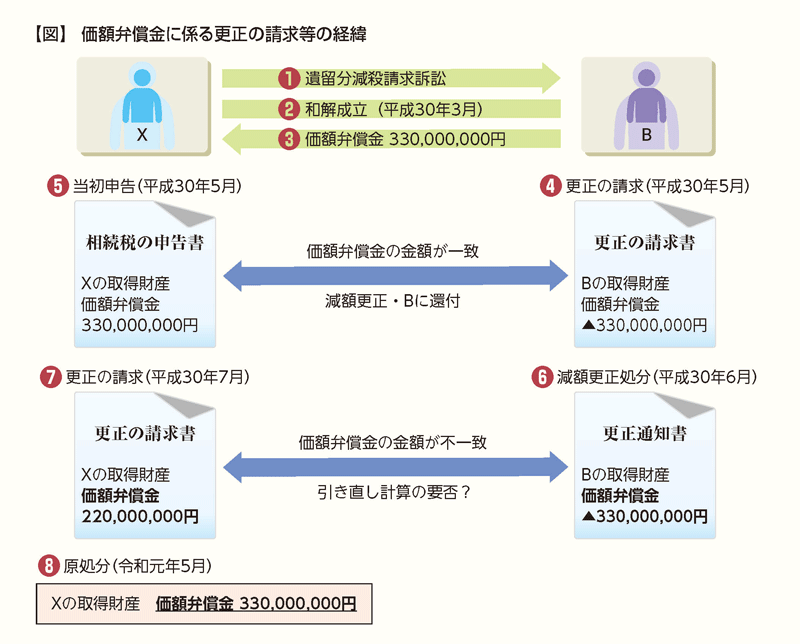
価額弁償金の“申告額”を具体的に協議していない
原処分庁は、当事者間で申告時に価額弁償金の金額に合意があったことから、引き直し計算の必要はない(相基通11の2−10ただし書(1))と主張した。
これに対し、審判所は、XとBとの間で、価額弁償金の申告額を具体的に協議した事実は認められないと指摘。当初申告における価額弁償金の金額は、相基通11の2−10のただし書(1)の場合には該当しないとした。
また、審判所は、価額弁償金の各対象財産の評価額は双方のせめぎ合いの後に合意されたものであり、その合理性を否定すべき事情もないことから、和解時における通常の取引価額であると認定。価額弁償金の金額は、各対象財産の評価額について合意した上で、当該評価額を基礎として、両当事者において歩み寄って合意し、330,000,000円に決まったものであることから、各対象財産の和解時における通常の取引価額を基として決定されたものであると指摘し、価額弁償金は、相基通11の2−10のただし書(2)に定める要件を満たすと判断している。
調査せずに減額更正処分と平仄を合わせた原処分を実施
課税当局は、本事案が取消裁決に至った原因として、以下の点を挙げている。
① 原処分庁は、Bの更正の請求(図④)を受けて、価額弁償金の金額は申告時の合意によるものか、相続発生時の相続財産の評価額と和解時の相続財産の評価額に変動がないのか調査を行う必要があった。
② しかしながら、原処分庁は、このような調査を行うことなく、Bの更正の請求(図④)とXの当初申告(図⑤)における価額弁償金の金額が一致していたことをもって、価額弁償金は、BとXの申告時の合意に基づくものとして、Bに減額更正処分(図⑥)を行った。
③ また、Xの更正の請求(図⑦)に対しても同様に、必要な調査を行うことなく、Bへの減額更正処分と平仄を合わせたところで、Xに原処分(図⑧)を行った。
十分調査し通達の適用関係を検討
その上で、今後の調査に向けた教訓として、(1)更正の請求事案であっても、認定に必要な事実関係については、調査で必ず確認する必要がある、(2)更正の請求で代償分割における代償財産や遺留分減殺請求による価額弁償金(遺留分侵害額)の金額がある場合には、必ず事実関係を十分に調査して、相基通11の2−10の適用関係を検討することが必要であるとしている。
運営する病院等で作成・交付した領収書の印紙税課否が争点に
次の事例は、消費生活協同組合が作成した各領収書の一部は課税文書に該当しないとして、印紙税の過怠税賦課決定処分の一部が取り消された事例(令和2年3月2日裁決、裁決事例集No.118)。
事案の概要は、消費生活協同組合法(生協法)に基づき設立された組合である審査請求人がその運営する病院等で作成・交付した各領収書のうち、請求人の非出資者であった者に対して交付した各領収書(本件各領収書)について、原処分庁が印紙税法に規定する課税文書に該当するとして過怠税の各賦課決定処分を行ったもの。
「営業」に該当しないなどと主張
請求人は、本件各領収書の一部は、①請求人の行う事業が印紙税法別表第一の第17号の「非課税物件」欄2(本件非課税規定)に規定する「営業」に該当しないこと、②仮に、本件各領収書が課税文書に該当するとしても、本件各領収書には、本件各領収書の各作成日において請求人の出資者であった者に対して交付したものが含まれていることから、課税文書に該当しないとして、原処分の一部の取消しを求めた。
原処分庁、出資者・非出資者の別が入力されたデータと照合
原処分庁は、請求人が非出資者に対して行った事業に係る本件各領収書は、印紙税法別表第一の第17号の1文書に該当する課税文書であるとして原処分を行っている。その際、課税文書に該当する領収書を抽出するため、出資者と非出資者の別が入力された組合員名データと請求人が作成した領収書を照合することにより本件各領収書を特定した。
作成日のデータでは一部が出資者
一方、審判所は、本件各領収書の宛名と本件各領収書の各作成日における請求人の組合員名データを照合した結果、一部の者は本件各領収書の各作成日において請求人の出資者であったことを確認。本件出資者宛名領収書(本件各領収書のうち、本件各領収書の各作成日において請求人の出資者であった者に対して交付されたもの)は、請求人が出資者に対して行う事業において作成し、交付したものであり、課税文書ではないと判断した(上掲・裁決要旨参照)。
〇令和2年3月2日裁決の要旨
| (1)生協法及び請求人の定款により、請求人は剰余金の分配等をすることができる旨規定等をしていることから、請求人がその出資者に対して行う事業は、本件非課税規定に規定する「営業」に該当しないが、出資者以外の者に対して行う事業は、たとえ営利を目的としないものであったとしても全て「営業」に該当することになる。 したがって、本件各領収書のうち、本件各領収書の各作成日において請求人の非出資者に対して行う事業において作成して交付したもの(本件非出資者宛名領収書)については、当該事業が本件非課税規定に規定する「営業」に該当するから、課税文書であると認められる。 (2)しかし、本件各領収書の宛名と本件各領収書の各作成日における請求人の組合員名データを照合したところ、一部の者は請求人の出資者であったことから、本件各領収書のうち、本件各領収書の各作成日において請求人の出資者であった者に対して交付されたもの(本件出資者宛名領収書)は、本件非課税規定に規定する「営業に関しない受取書」といえるため、課税文書ではないと認められる。 |
課税要件について理解はしているものの……
いつの時点での状況か確認不十分
課税当局は、本事案が取消裁決となった原因として、本件各領収書を抽出する過程において照合した請求人の組合員名データが、いつの時点での組合員の状況であるかを十分に確認していなかった点を挙げている。
収集した証拠書類等を十分に精査
上記を踏まえ、課税当局は、調査担当者等に対し、以下の事項を指摘。調査においては、収集した証拠書類等が課税要件を満たすものとして担当者の意図するものとなっているかどうか十分精査した上で、課税処分を行うよう促している。
① 印紙税法8条1項は、課税文書の作成者は、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書に貼り付ける方法により、印紙税を納付しなければならない旨規していることから、本件においても、領収書の作成日において、当該領収書の交付を受けた者が出資者であったか否かが、課税文書に当たるか否かの判断基準となる。
② 本件に限らず、課税要件について理解はしているものの、収集した証拠書類等に対する担当者の先入観や思い込みから、当該証拠書類等では課税要件を満たしていないにもかかわらず、課税処分に至る事案が散見される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.