解説記事2022年06月20日 SCOPE 一括譲渡土地建物、固定資産税評価額でなく鑑定評価額で按分(2022年6月20日号・№935)
地裁、消費税更正処分等の大部分を取消し
一括譲渡土地建物、固定資産税評価額でなく鑑定評価額で按分
それぞれの対価の額が合理的に区分されていない一括譲渡された土地、建物について、消費税の課税標準の計算上、その按分に用いられる価額が争われた事件で、東京地裁民事51部(岡田幸人裁判長)は令和4年6月7日、国の主張する固定資産税評価額比率による按分法ではなく、裁判所が行った鑑定評価額比率による按分法によるべきとして、原処分の大部分を取り消した。
国にとっては、類似事案(令和2年9月1日東京地裁判決)に続き、固定資産税評価額による按分が否定されるという厳しい結果となり、鑑定評価が必要とされることによる実務負担への懸念も主張したものの、認められなかった。
固定資産税評価額は、適正な時価を上回るものでないことの推認にとどまる
本件は、土地建物が一括譲渡された場合における「課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないとき」(消令45③)に当たるものについて、その按分に用いられる価額(按分比率)が争われたもの。
国は、固定資産税評価額比率による按分法によるべきと主張したが、東京地裁は、原告の鑑定の申出を採用して行った鑑定評価額によるべきとの判断を下した(本件土地と建物の固定資産税評価額比率55.51対44.49に対して、鑑定評価額比率は77.30対22.70)。
その理由として東京地裁は、類似事案の令和2年9月1日東京地裁判決(本誌856号)と同様に、最高裁判決を引用して、以下の考えを示した。
固定資産評価基準の定める評価方法が、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであるとしても、この評価方法に従って決定された価格は、特段の事情のない限り当該資産の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないことが推認されるにとどまるものというべきである(最高裁平成24年(行ヒ)第79号同25年7月12日第二小法廷判決)。また、地方税法が、固定資産税の課税標準に係る固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を総務大臣の告示に係る評価基準に委ねている(388条1項)のは、固定資産税の賦課期日における土地課税台帳等の登録価格が同期日における当該資産の客観的な交換価値を上回らないようにすることのみならず、全国一律の統一的な評価基準による評価によって、各市町村全体の評価の均衡を図り、評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消することをも目的とするものであり、かかる目的の下に行われる評価は、適正な鑑定の評価の過程において考慮の対象とされるような当該資産の個別的な事情については、ある程度捨象されることも前提としているものということができる。
その上で、「消費税の課税標準の額を計算するために、一括して譲渡された土地及び建物の対価の額を按分する方法として、固定資産評価額による価格比を用いることは、一般的には、その合理性を肯定し得ないものではないが、当該資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、価額比においても実質的な差異が生じた場合には、もはや固定資産税評価額による価額比を用いて按分する合理性を肯定する根拠は失われ、適正な鑑定に基づく評価額による価額比を用いて按分するのがより合理的になるというべきである。」と判示した。
地裁、納税者の主張する按分計算も否定
そして、国の「消費税法施行令45条3項が規定する『価額』について、土地の価額と建物の価額がそれぞれ適正な時価といえるだけでなく、課税標準を算定するに当たり合理的な比率となる価額の組み合わせとなるものでなければならない」との主張に対しては、「同項の文言から直ちに導くことはできず、明文にない要件を加重するものとして採用することは困難」とした。また、国は「事後的に行われた鑑定評価等によって一義的な時価に基づく価額比が判明したことを理由に当該処分が違法であると評価することは、納税者(事業者)及び課税庁に対し逐一鑑定評価等を実施して納税申告や更正処分等の内容の適否を検証する必要を迫るものになりかねない」などとも主張したが、その主張も斥けられた。
一方、本件代金総額は消費税等相当額を含むものであったため、東京地裁は、納税者の主張する、本件建物鑑定評価額に消費税等相当額を加算しない場合の比率で按分する方法についても、「本件代金総額に含まれる消費税等相当額の一部が本件土地の譲渡の対価の額に上乗せされてしまうことになり、本来あるべき本件建物の譲渡の対価の額より過少となる。」として斥けている(図参照)。
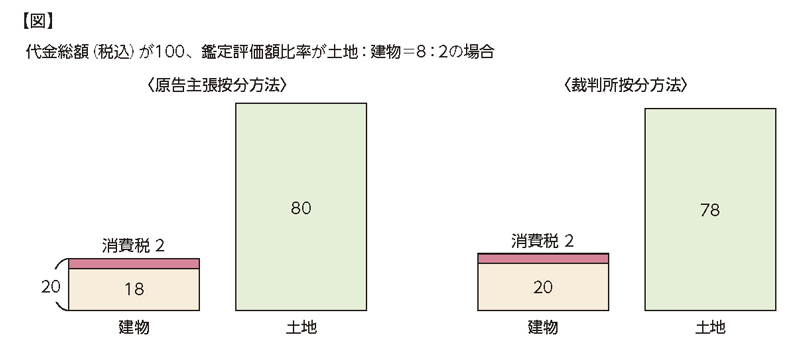
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























