解説記事2022年09月19日 実務解説 大口株主の判定に関する改正について(2022年9月19日号・№947)
実務解説
大口株主の判定に関する改正について
税理士 竹内陽一
税理士 阿部隆也
令和4年度税制改正により、上場株式等の配当等に係る課税における、大口株主の判定に関する改正が行われている。今回は、この大口株主の判定に関する改正の内容と、実務上のポイントを確認する。
Ⅰ 制度の概要
保有する株式等の数の発行済株式等の総数等に占める割合(「株式等保有割合」)が3%未満である個人(いわゆる小口株主)が、支払を受ける上場株式等の配当等については、支払時に20.315%(所得税15.315%と住民税5%)の税率で源泉徴収(措法9の3、9の3の2)され、下表の3つの課税方式を選択することが可能とされている。
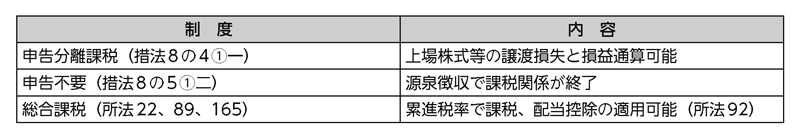
一方、株式等保有割合が3%以上である個人(いわゆる大口株主)が支払を受ける上場株式等の配当等については、支払時に20.42%の税率で源泉徴収(所法181、182)され、総合課税による確定申告をすることとされている(所法22、89、165)(図表1参照)。
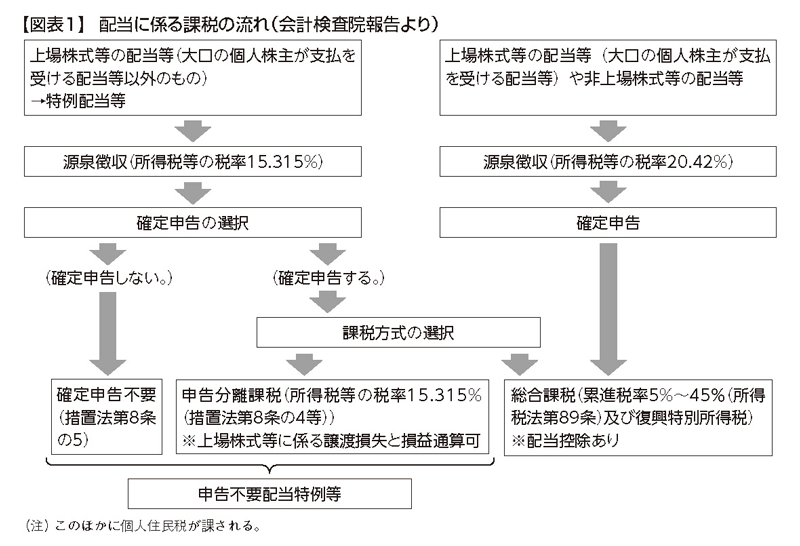
このような小口株主に対する申告分離課税、申告不要の特例制度は、「貯蓄から投資へ」という政策的要請を受けた「金融所得課税の一体化」に沿って、個人投資家に対する課税の簡素化や投資リスクの軽減を目的に、平成15年度税制改正において、申告不要制度が導入され、平成20年度税制改正において、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算制度と共に、申告分離課税制度が創設された。
一方、大口株主については、事業参加的側面が強いことを勘案し、上記特例の対象外とし、総合課税により課税することとされている。その要件は、制度創設当初、株式等保有割合が5%以上とされていたが、平成23年度税制改正において、所得再分配機能の回復の観点や会社法における少数株主権の制度との整合性を図るためとして、株式等保有割合が3%以上へ引き下げされた経緯があり、今回、議決権の過半数を保有して支配している法人を通じるなどして持株割合が実質的に3%以上となっている個人株主と、分離課税を選択できない大口株主との間での課税の公平性が保たれていないなどとする会計検査院の指摘を契機として、令和4年度税制改正において、大口株主の3%以上の判定において同族会社を含むこととされた。
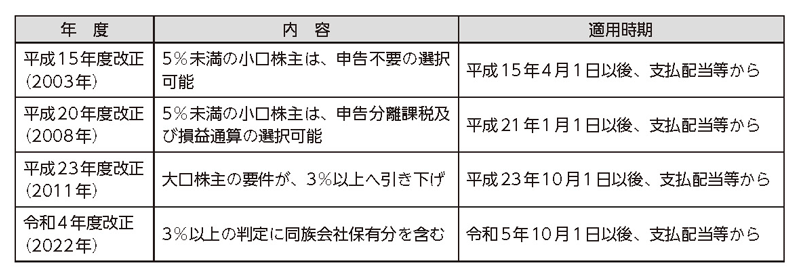
Ⅱ 改正の内容
改正のポイントは、以下である。
(1)大口株主3%以上の判定に同族会社保有分を含む
(2)申告分離課税と申告不要が適用不可
(3)譲渡損失との損益通算も適用不可
(4)年間10万円以下であれば引き続き申告不要
(5)源泉徴収は変更なし
(6)報告書提出制度の創設
(1)大口株主3%以上の判定に同族会社保有分を含む
内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその株式等保有割合が、100分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるものが、総合課税の対象とされた(措法8の4①一)。
この改正は、居住者等が令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用し、居住者等が同日前に支払を受けるべき配当等については従前どおりとされている(改正法附則23①)。
(2)申告分離課税と申告不要が適用不可
上記(1)の改正は、同族会社と合算して株式等保有割合が3%以上となる個人株主における申告分離課税の選択を不可とするものであるが、申告不要(措法8の5①二)は、申告分離課税(措法8の4①一)を参照しているため、同族会社と合算して株式等保有割合が3%以上となる個人株主は、申告不要の選択も同時に不可となる。
(3)譲渡損失との損益通算も適用不可
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算(措法37の12の2①)は、申告分離課税を選択した配当所得等の金額を対象としているため、同族会社と合算して株式等保有割合が3%以上となる個人株主は、上場株式等に係る譲渡損失が発生した場合であっても、この申告分離課税を選択不可とされる上場株式等の配当等との損益通算ができないこととなる。
(4)年間10万円以下であれば引き続き申告不要
上場株式等の配当等で、1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下であるものについては、仮に同族会社と合算して株式等保有割合が3%以上となる個人株主であっても、引き続き申告不要を選択することができる(措法8の5①一、税制改正の解説193頁(注1))。
(5)源泉徴収は変更なし
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例(措法9の3)、及び、これを参照する上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例(措法9の3の2)の大口株主等の要件は、改正されていないため、同族会社との合算は考慮せずに、従前どおり、株式等保有割合を個人の保有分のみで算出し、株式等保有割合が3%以上であれば20.42%、3%未満であれば20.315%の源泉徴収を行うこととなる(税制改正の解説193頁(注2))。
(6)報告書提出制度の創設
上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が100分の1以上となるその支払を受ける居住者等の氏名、個人番号その他の事項を記載した「上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書」を、その支払の確定した日から1月以内に、その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされた。
Ⅲ 改正の影響
個人保有分のみでは株式等保有割合が3%未満であるが、同族会社と合算すると株式等保有割合が3%以上となる個人株主は、今回の改正で、総合課税が適用されることとなる。
今回の改正で、大口株主に該当することとなる個人は、その多くが高額所得者であることが想定されるため、改正前は20.315%の源泉徴収のみで課税関係が終了していたのに対し、総合課税となることにより最高49.44%(所得税(税率45%、配当控除5%)、住民税(税率10%、配当控除1.4%)で課税されることとなり、多くのケースで税負担が増加することとなることが想定される(図表2参照)。
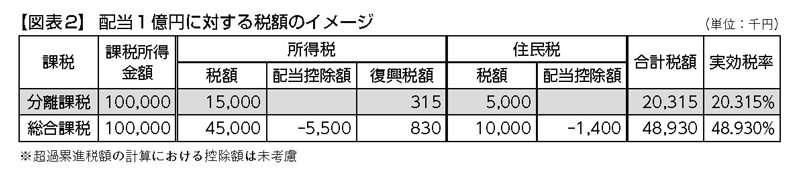
大口株主ファミリーが、その親族に上場株式等を保有させているケースも想定されるが、その親族が今回の改正により大口株主に該当することとなる場合に、仮にその親族の所得が上場株式等の配当等のみであるときは、図表3のとおり、配当額が約1,300万円を超えると、実効税率が申告不要若しくは申告分離課税の場合の20.315%を超えることとなるため、改正前に比べて不利になると考えられる。一方、配当額が約1,200万円を超えない場合には、今回の改正前より総合課税を選択することが有利であり、今後も総合課税を選択すると想定されることから、改正の影響はないということになる。
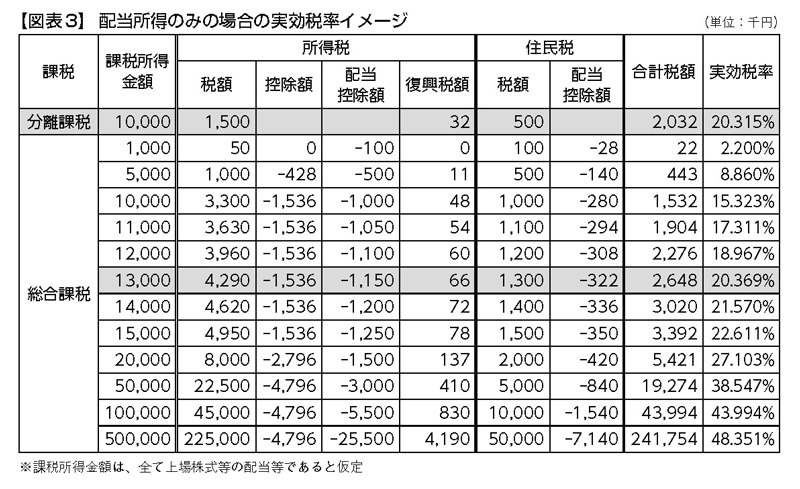
Ⅳ 判定の実務
1 大口株主の判定
その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける者と、その者を判定の基礎となる株主として選定した場合に、法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなる法人が、保有する株式等を合算して株式等保有割合が100分の3以上となるときは、その者は大口株主に含まれることとされた(措法8の4①一)。
同族会社(法法2十)は、次の会社である。
「株主等の三人以下」並びに「これらと政令で定める特殊の関係のある個人」及び「法人」がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社
特殊の関係のある個人(法令4①)は、次の者である。
① 株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
② 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 個人である株主等の使用人
④ 上記①から③に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
⑤ 上記②から④に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
特殊の関係のある法人(法令4②)は、次の会社である。
① 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(判定会社株主等)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと特殊の関係のある個人)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
② 判定会社株主等の一人及びこれと上記①に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
③ 判定会社株主等の一人及びこれと上記①及び②に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
2 大口株主の判定例
事例として、次のような資本関係を前提として検討する(図表4参照)。
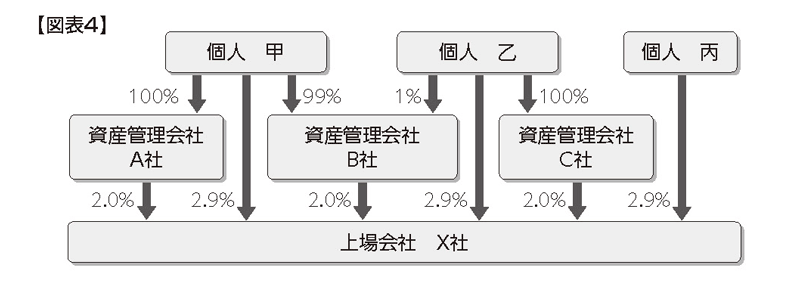
① 個人甲、個人乙、個人丙は、上場会社X社の株式を、各2.9%保有している。
② 資産管理会社A社の株式は、個人甲が100%保有している。
③ 資産管理会社B社の株式は、個人甲が99%、個人乙が1%保有している。
④ 資産管理会社C社の株式は、個人乙が100%保有している。
⑤ 資産管理会社A社とB社とC社は、上場会社X社の株式を、各2.0%保有している。
判定結果は、以下のとおりである。
(1)個人甲の判定…大口株主に該当する。
(2)個人乙の判定…大口株主に該当する。
(3)個人丙の判定…大口株主に該当しない。
(1)個人甲の判定……大口株主に該当する。
① 同族会社の判定
・資産管理会社A社……個人甲が100%を有する会社であり、株主等の3人以下がその会社の発行済株式総数の50%超を有する会社であることから、同族会社に該当する(法法2十)。
・資産管理会社B社……個人甲が99%、個人乙が1%を有する会社であり、株主等の3人以下がその会社の発行済株式総数の50%超を有する会社であることから、同族会社に該当する(法法2十)。
・資産管理会社C社……個人乙が100%を有する会社であり、株主等の3人以下がその会社の発行済株式総数の50%超を有する会社であることから、同族会社に該当する(法法2十)。
② 株主の選定
・資産管理会社A社……個人甲は、資産管理会社A社の株式を保有していることから、A社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することが可能であり、かつ、A社は、個人甲1人で50%超を有するため、同族会社に該当し、個人甲はその判定の基礎となっている。
・資産管理会社B社……個人甲は、資産管理会社B社の株式を保有していることから、B社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することが可能であり、かつ、B社は、個人甲と個人乙の2人で50%超を有するため、同族会社に該当し、個人甲はその判定の基礎となっている。
・資産管理会社C社……個人甲は、資産管理会社C社の株式を保有していないことから、C社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することができない。
仮に、個人甲が、個人乙と特殊の関係のある個人に該当する場合でも同様である。
③ 大口株主の判定
この場合、大口株主の判定は、(イ)個人甲が保有する2.9%(配当等の支払を受ける者の保有する株式等)と、(ロ)資産管理会社A社が保有する2.0%(個人甲を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当することとなる法人の保有する株式等)、(ハ)資産管理会社B社が保有する2.0%(個人甲を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当することとなる法人の保有する株式等)を合算して判定する(措法8の4①一)。
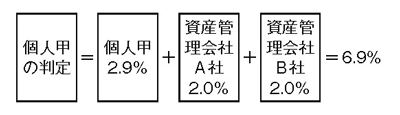
したがって、個人甲、資産管理会社A社及び資産管理会社B社が保有する株式等を合算した株式保有割合は6.9%となり、その割合が3%以上となることから、個人甲は大口株主に該当する。
(2)個人乙の判定……大口株主に該当する。
① 同族会社の判定
上記(1)のとおりである。
② 株主の選定
・資産管理会社A社……個人乙は、資産管理会社A社の株式を保有していないことから、A社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することができない。
仮に、個人乙が、甲と特殊の関係のある個人に該当する場合でも同様である。
・資産管理会社B社……個人乙は、資産管理会社B社の株式を保有していることから、B社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することが可能であり、かつ、B社は、個人甲と個人乙の2人で50%超を有するため、同族会社に該当し、個人乙はその判定の基礎となっている。
・資産管理会社C社……個人乙は、資産管理会社C社の株式を保有していることから、C社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することが可能であり、かつ、C社は、個人乙1人で50%超を有するため、同族会社に該当し、個人乙はその判定の基礎となっている。
③ 大口株主の判定
この場合、大口株主の判定は、(イ)個人乙が保有する2.9%(配当等の支払を受ける者の保有する株式等)と、(ロ)資産管理会社B社が保有する2.0%(個人乙を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当することとなる法人の保有する株式等)、(ハ)資産管理会社C社が保有する2.0%(個人乙を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当することとなる法人の保有する株式等)を合算して判定する(措法8の4①一)。
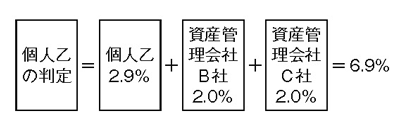
したがって、個人乙と資産管理会社B社及び資産管理会社C社が保有する株式等を合算した株式保有割合は6.9%となり、その割合が3%以上となることから、個人乙は大口株主に該当する。
(3)個人丙の判定……大口株主に該当しない。
① 同族会社の判定
上記(1)のとおりである。
② 株主の選定
個人丙は、資産管理会社A社、B社及びC社の株式を保有していないことから、A社、B社及びC社の同族会社判定における基礎となる株主として、「選定」することができない。
仮に、丙が、甲又は乙と特殊の関係のある個人に該当する場合でも同様である。
③ 大口株主の判定
この場合、大口株主の判定は、個人丙が保有する2.9%(配当等の支払を受ける者の保有する株式等)のみで判定する(措法8の4①一)。
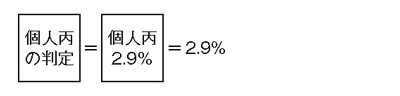
したがって、個人丙が保有する株式保有割合は2.9%であり、その割合が3%未満となることから、個人丙は大口株主に該当しない。
Ⅴ 参考 法人税の取扱い
1 関連法人株式等、その他の株式等の判定
令和2年度税制改正において、連結納税制度の見直しに伴うグループ法人税制等の見直しが行われ、受取配当等の益金不算入の改正が行われた。
この改正により、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等(並びに、これらのいずれにも該当しない株式等(その他の株式等))の判定は、内国法人との間に完全支配関係がある法人が有する株式等を含めて判定することとされた(法法23④⑥)。
完全支配関係は、一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係を含み(法法2十二の七の六)、一の者が個人である場合には、その者と特殊の関係のある個人を含むこととされている(法令4の2②)(次頁表参照)。
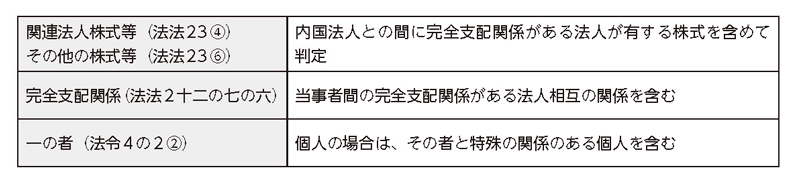
したがって、法人税における完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等の判定は、特殊関係のある個人が保有する会社の持分を含めて判定することとなる。
2 その他の株式等の判定例
事例は、上記Ⅳ2の事例と同様とする(図表5参照)。
① 個人甲、個人乙、個人丙は、上場会社X社の株式を、各2.9%保有している。
② 資産管理会社A社の株式は、個人甲が100%保有している。
③ 資産管理会社B社の株式は、個人甲が99%、個人乙が1%保有している。
④ 資産管理会社C社の株式は、個人乙が100%保有している。
⑤ 資産管理会社A社とB社とC社は、上場会社X社の株式を、各2.0%保有している。
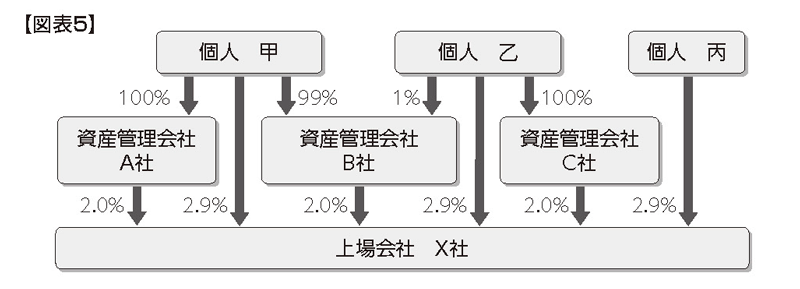
(1)完全支配関係の判定
この事例において、仮に個人甲と個人乙が特殊の関係(例えば親族など)にある場合、個人甲と個人乙は一の者(法令4の2②)となることから、資産管理会社A社、資産管理会社B社及び資産管理会社C社は、完全支配関係があることとなる。
(2)その他の株式等の判定
資産管理会社A社、資産管理会社B社及び資産管理会社C社に完全支配関係がある場合、A社、B社及びC社における上場会社X社株式の「その他の株式等」の判定は、それぞれが有する株式を含めて判定する(法法23⑥)。
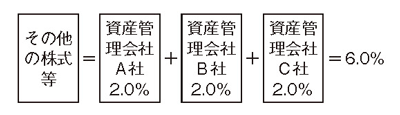
したがって、A社、B社及びC社が有する株式等を合算した株式保有割合は6.0%となり、5%を超えることから、上場会社X社株式は「その他の株式等」に該当する。
(3)所得税との違い
所得税における「大口株主の判定」においては、個人甲と個人乙に特殊の関係がある場合にも、資産管理会社A社と資産管理会社C社の株式等保有割合を合算することはないが、法人税における「その他の株式等の判定」においては、個人甲と個人乙に特殊の関係がある場合には、資産管理会社A社と資産管理会社C社の株式等保有割合を合算することとなる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























