解説記事2022年10月10日 SCOPE 1株利益計算上、均等取崩額は非経常的利益としての除外不可(2022年10月10日号・№949)
延払基準の廃止による評基通株価への影響は
1株利益計算上、均等取崩額は非経常的利益としての除外不可
平成30年度法人税法改正による長期割賦販売等における延払基準の廃止による繰延割賦利益額の10年均等取崩額については、財産評価基本通達における取引相場のない株式に係る類似業種比準価額の1株当たりの利益金額の計算上、その発生原因が法人側の任意の事情ではなく税制改正によるものであることから、旧法人税法第54条第2項に規定する退職給与引当金の取崩額と同様に「非経常的な利益」の金額として除外することができるのではないかとの意見が実務家から聞かれる。
しかし、この点について編集部が課税当局に取材したところ、負債である退職給与引当金とは異なり、その性質が本業から生じた利益と考えられる繰延割賦利益については、「非経常的な利益」として1株当たりの利益金額の計算から除かれるとは考えられないとの回答を得た。
繰延割賦利益の性質はあくまで本業から生じた経常的な利益
長期割賦販売等に該当する資産の販売等については、平成30年度税制改正により、延払基準により収益の額及び費用の額を計算する法人税法上の選択制度が廃止されたのは周知のとおり。当該改正には経過措置が講じられており、2018年4月1日以前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人については、2023年3月31日までに開始する各事業年度までは改正前の規定を適用することができる。ただし、従前どおり、延払基準の方法による経理が要件となっている。
経過措置事業年度中に延払基準の方法により経理しなかった場合には、一括で益金の額及び損金の額に算入するのが原則的な処理とされているが(改正法附則28②)、激変緩和の観点から、2018年4月1日以後に終了する事業年度において、延払基準の方法により経理しなかった場合の長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る未計上収益額及び未計上費用額(繰延割賦利益額がある場合に限る)については、その経理しなかった事業年度以後の各事業年度に10年間で均等に計上する等の措置が講じられている(改正法附則28③ 図表1参照)。
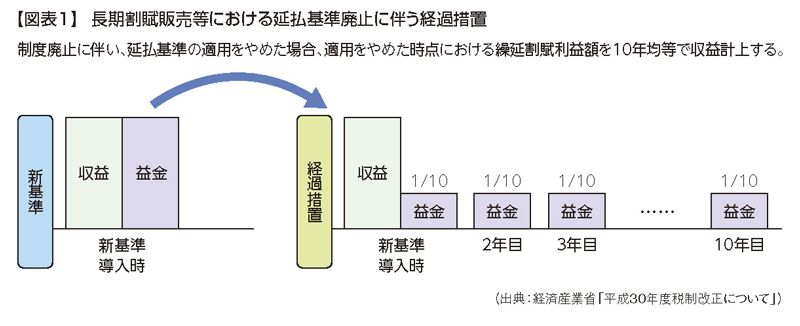
退職給与引当金と同様の取扱いにはならず
ところで、従前引き当てていたものが税制改正により取り崩すことが強制され、かつ、激変緩和の観点から段階的に取り崩すことが認められたものとして、旧法人税法第54条第2項に規定する退職給与引当金がある。この益金算入される取崩額については、取引相場のない株式に係る類似業種比準価額の算定(評基通183)において、1株当たりの利益金額の計算上、いわゆる非経常的な利益の金額として除外することができる旨が、図表2のとおり課税当局の資料で解説されている。
| 旧法人税法第54条第2項に規定する退職給与引当金制度は、平成14年7月の税制改正で廃止されたが、激変緩和の観点から、引当金の取崩しを段階的に行う経過措置が設けられている。この場合、退職給与引当金は段階的に取り崩されて益金に算入されるが、評基通183(評会社の1株当たりの配当金額等の計算)の「1株当たりの利益金額《C》」の計算上においては、その段階的取崩額が、激変緩和の観点から4年間(大法人)又は10年間(中小法人)にわたって法人の各期の益金に算入されるものの、その発生原因は法人側の任意の事情によるものではなく、税制改正による制度の廃止にあり、その実質は臨時偶発的な性格を有するものと認められることになるので、その段階的取崩額は、固定資産売却益等と同様、「非経常的な利益」として1株当たりの利益金額の計算から除くのが相当である。 |
そこで専門家の間では、上記の繰延割賦利益の10年均等取崩額についても、「法人の各期の益金に算入されるものの、その発生原因は法人側の任意の事情によるものではなく、税制改正による制度の廃止」という同様の理由があることから、「非経常的な利益」として1株当たりの利益金額の計算から除かれるのではないかとの意見が聞かれる。
しかし、この点について編集部が課税当局に取材したところ、退職給与引当金と同様の取扱いとはならない、つまり、「非経常的な利益」として1株当たりの利益金額の計算から除かれることはないと考えるとの回答を得た。これは、退職給与引当金は負債であるのに対し、繰延割賦利益はほぼ本業から生じた利益であると考えられること、つまり、平成30年改正で講じられた措置は、益金算入のタイミング(時点)の問題であり、利益の発生原因、性質としては、経常的な利益であることは変わらないという理由によるとのことだ。
実務家の意見は、「評基通の趣旨からすれば、類似業種比準方式における比準要素としての利益金額は、評価会社の経常的な収益力を表すものでなければならず、経常的な収益力を表すためには上記取崩額は除かれなければならない」というものであるが、課税当局が示した見解はこれとは正反対のものであるだけに注意したい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























