解説記事2022年11月21日 ニュース特集 インサイダー情報伝達で課徴金、東京高裁も取消し(2022年11月21日号・№955)
ニュース特集
証券監視委調査官の違法性はなし、国への賠償は取消し
インサイダー情報伝達で課徴金、東京高裁も取消し
インサイダー情報を友人に伝えたとして金融庁から351万円の課徴金納付命令を受けた上場会社の元取締役がその取消しなどを求めた裁判で、東京高等裁判所(増田稔裁判長)は令和4年10月13日、原審の東京地裁に引き続き、課徴金納付命令を取り消した(令和4年(行コ)第4号、同49号)(確定)。元取締役は公認会計士の資格を有し、同社の最高財務責任者であった者。今回、課徴金納付命令は取り消されたわけだが、元取締役は証券取引等監視委員会の勧告を受けると同時に取締役を辞任しており、その代償はあまりにも大きい。公認会計士がスタートアップ企業のCFOに就任するケースも多いだけにコンプライアンス意識の共有など、インサイダー取引関連については改めて注意しておきたい点といえよう。
なお、東京地裁では、「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていなかった」として証券取引等監視委員会の調査官2人の行為について国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの判断を示し、国に対して120万円の損害賠償請求を認容していたが、この点については一転して取り消されることになった。
同窓会で友人に情報伝達、重要事実であったか否かが問題に
本件は、インサイダー情報を友人に伝えたとして金融庁から351万円の課徴金納付命令を受けた被控訴人が、課徴金納付命令は違法であるとしてその取消しを求めるとともに、その処分及びこれに至る手続が国家賠償法(国賠法)1条1項の適用上違法であるとして、約500万円の損害賠償請求を行った事件である。
被控訴人はマザーズ(現在はプライム市場)に上場するSHIFTの取締役であった者である。同社が平成27年10月8日に公表した直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値において重要な差異が生じた旨の重要事実を公表する前に、被控訴人が同年12月30日開催の高校時代の友人たちとの同窓会の際に友人Aに対してその旨を伝達したとし、金融庁は平成29年4月11日、351万円の課徴金納付命令を行ったもの(図表1参照)。なお、金融庁は、友人Aに対しては被控訴人からの情報に基づき同社の株式を売買したとして平成28年4月22日付けで1,380万円の課徴金納付命令を行っており、決定している。
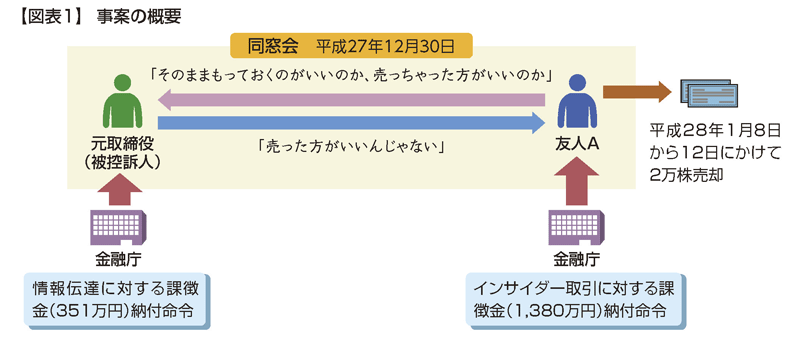
国側は被控訴人による友人Aに対する重要事実の伝達行為が平成27年12月30日にあったと主張。具体的には12月22日の取締役会における業績予想修正の了承により重要事実が発生したか否かが問題となった。事件の経緯は図表2のとおりである。
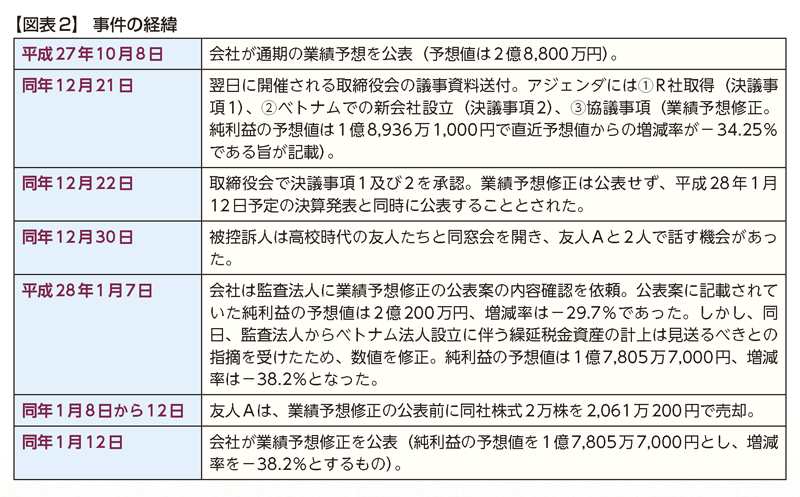
東京地裁、国賠法上違法と判断し国に120万円の賠償命令
原審の東京地裁では、原告(元取締役である被控訴人)に対する課徴金納付命令を取り消すとともに、証券取引等監視委員会の調査官2人の行為について国賠法1条1項の適用上違法であるとの判断を示し、国に対して120万円の損害賠償請求を認容している(平成29年(行う)第192号)。課徴金を巡る調査官の調査で違法性が認められたのは初めてのケースという。
増減率が基準値以上となることについて具体的な根拠が必要
東京高裁の判断も、原審と同様、平成27年12月30日以前に重要事実が発生した事実は認められないとして課徴金納付命令を取り消している。
東京高裁は、上場会社等において増減率が基準値以上となる純利益の予想値を「新たに算出した」場合に該当する実質的な意思決定がされたといえるためには、純利益の予想値に係る業績予想修正についての意思決定が、単に増減率が基準値以上となる抽象的な可能性の下に行われたというだけでは足りず、少なくとも、増減率が基準値以上となることにつき具体的な根拠に基づいて行われたと認められることを要するべきであると指摘。その上で本件では、取締役会においては、その前日に算定された予想数値に基づき、純利益の予想値に係る増減率が−29.73%であることを前提に協議がされ、すでに基準値を超え上方修正の適時開示を要することが確実となっていた売上高の予想値と併せて、決算発表と同時に公表する旨が了承されたことが認められ、この時点において増減率につき−30%以上の具体的な数値をもって公表する旨の了承がされた事実は認められないとの判断を示した。
なお、取締役会において説明に用いられたベトナム資料には、販管費等のコストにつき精査中である旨が付記されており、この点のベトナム予算(修正後ベトナム予算)にはなお修正の余地があったとみることもできるが、東京高裁は、書面決議までの間にベトナム予算に係る修正が行われるか否かについては取締役会時点においては必ずしも明らかであったとはいえず、実際には取締役会の後もベトナム予算の修正は行われず、書面決議直前の平成28年1月7日に公表案の確認をした監査法人からベトナム法人につき繰延税金資産の計上を見送るべきである旨の指摘を受けて修正をした結果、増減率が−38.21%となり基準値を超えることになったものであるとした。
取締役会時点では抽象的な可能性
このため東京高裁は、取締役会後におけるベトナム予算の修正の余地を考慮に入れるとしても、取締役会時点では、増減率が基準値以上となる抽象的な可能性があったと認められるにとどまり、増減率が基準値以上となる具体的な根拠に基づいた意思決定が行われたと認めることはできないから、取締役会において、増減率が基準値以上となる純利益の予想値を「新たに算出した」場合に該当する実質的な意思決定がされたということはできないとし、取締役会時点では重要事実が発生したとは認められないとの判断を示し、控訴人である国の請求を棄却した。
コラム 未公表の重要事実の伝達等の禁止
上場会社等又はその属する企業集団の純利益に係る新予想値について、直近予想値を基準とした増減率が±30%(基準値)以上である場合で、かつ、変動幅基準を満たす場合に、直近予想値と新予想値との間にそのような差異が生じたことをもって金商法166条1項に定める重要事実とし、これを職務に関し知った上場会社等の役員が、重要事実の公表前に他人に利益を得させ又は損失の発生を回避させる目的をもってこれを伝達することを禁止している(金商法167条の2第1項、166条2項3号、取引府令51条3号)。これは、純利益に係る直近予想値と新予想値との間に差異が生じたとの事実が投資者の投資判断に及ぼす影響に鑑み、上場会社等の役員に対し、かかる事実に関する公表前の伝達行為を禁止することによって、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の取引の公正や、投資者の保護を図ろうとするものであるとともに、課徴金納付命令や刑事罰の対象とされる違反行為の内容を、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものに限定したものであると解されている。
金商法167条の2第1項等の趣旨に鑑みると、上場会社等において増減率が基準値以上となる純利益の予想値を「新たに算出した」(同法166条2項3号)といえるためには、当該予想値に係る業績予想修正につき上場会社等にける正式な決定を必ず経なければならないものではなく、上場会社等における実質的な意思決定がされれば足りるというべきであるとされている。
増減率の修正過程の更なる調査を行うまでの義務は負わず
本件では、もう1つの注目すべき論点がある。証券取引等監視委員会の調査官らの調査が国賠法1条1項の適法上違法であるか否かという点である。公務員による公権力の行使に当たる行為が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるのは、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認め得るような事情がある場合に限られると解するのが相当であるとされている(最高裁平成元年(オ)第930号等)。
東京地裁では、基本的な資料で確認の必要性が高く、容易に確認し得る書面決議資料について、通常払うべき注意をもって確認すれば、注記部分に記載された監査法人の指摘による予想値の修正という重要事実の発生に重大な疑義を生じさせる事情を発見することができたにもかかわらず、その注意を怠って漫然とこれを看過したものであるから職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていなかったとし、国に対して120万円の賠償責任を認めていた。
被控訴人が自己に不利益な内容を供述
この点、東京高裁では、証券調査官らは会社に対する所要の調査等を実施することによって、取締役会時点における増減率が−29.73%であったことや、監査法人の指摘を受けて初めて増減率が−38.2%となったことを把握できた可能性があったことは否めず、証券調査官らにおいて、そのような調査等を実施することが望ましかったということができると指摘。しかし、増減率の算定や修正、重要事実の公表等に関しても最も詳しいはずの被控訴人が自己に不利益な内容の供述等を行い、これに沿う客観的な証拠等も収集される状況の中で、証券調査官らが、敢えて被控訴人の供述等の信頼性に疑いを持つなどして、その信用性の有無を裏付けるとともに事案を解明するため、増減率の修正過程について更なる調査を行うまでの義務を負っていたと認めることはできず、証券調査官らにおいて職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていなかったと認めることはできないとの判断を示し、認容した原審の判断を取り消した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























