解説記事2022年11月28日 ニュース特集 住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償責任(2022年11月28日号・№956)
ニュース特集
修正申告すればダブル適用できるとアドバイスするも
住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償責任
修正申告すれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と住宅ローン控除の適用が可能であるとして新居を購入したものの、修正申告が認められず、住宅ローン控除の適用を受けることができなかったため、委任契約を締結した税理士に対し損害賠償請求を行った事件で、東京地方裁判所(品田幸男裁判長)は令和4年5月16日、税理士の委任契約に係る債務不履行がなければ、原告は住宅ローン控除満額の適用を受けるため、物件の購入を見送ったなどとし、税理士側に対して235万3,289円の損害賠償請求を認めた(令和2年(ワ)第11869号)。
修正申告業務で委任契約締結も結果的に修正申告できず
本件は、弁護士である原告が新居の購入に当たり、税理士から過去の所得税等の確定申告について修正申告をすれば、新居の購入のための住宅ローン控除の適用を受けることができる旨の助言を受けたことから、税理士との間で修正申告業務について委任契約を締結(報酬3万円)したもの。しかし、新居を購入したものの、結果的に修正申告が認められず、住宅ローン控除の適用を受けることできなかったため、特別控除額相当の損害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償請求を行ったものである。なお、税理士が訴訟提起後に死亡したことにより、損害賠償請求は相続人である配偶者及び子(被告)に対し行われている。
原告はマンション売却を平成30年分で申告
原告は、委任契約に先立つ平成29年9月20日、自宅として所有していたマンションを、購入価額を上回る金額で第三者に売却し、平成30年1月30日に買主への引渡しを行ったところ、売却に係る譲渡所得について、売買契約の効力発生の日の属する平成29年分の所得としてではなく、物件を引き渡した日の属する平成30年分の所得として確定申告をし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(以下「売却時控除」)の適用を受けていた。
なお、確定申告において、譲渡所得は資産を譲渡した日の属する年の所得として扱われる。資産を譲渡した日とは、原則として、売買などの譲渡契約に基づいて資産を買主等に引き渡した日をいうが、同契約の効力発生の日に譲渡があったものと扱うこともできるとされており、平成30年分の確定申告はこれに沿った適正なものであった。
原告は修正申告不可の通達前に物件購入
その後、原告は、税理士に対し、新居の購入を検討するに当たり、住宅ローン控除の適用を受けることができることが可能か問い合わせたところ、税理士は、原告に対し、①売却時控除の適用を受けた年から2年以内に新居の引渡しを受ける場合には住宅ローン控除の適用は受けられない、②原告は自宅の売却に係る譲渡所得について平成30年分の所得として売却時控除の適用を受けているものの、同譲渡所得については平成29年分の所得としても申告が可能であったため、平成30年分の所得としていた税務申告を平成29年分の所得として申告をし直すことが可能である、③修正申告をすることにより、令和2年に新居の引渡しを受けるのであれば、住宅ローン控除と売却時控除の両方の適用を受けることができると回答。原告は、税理士との間で修正申告に係る申告業務を報酬3万円で委任する旨の委任契約を締結。税理士は平成29年分の所得として確定申告をする旨の修正申告をしたが、税務署は、税理士に対し、修正申告の要件(修正申告をすることができる場合とは、①記載した税額に不足額があるとき、②純損失等の金額が過大であるとき、③税額が過大であるとき、④納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるときとされている(通則法19条①))を満たしていないため、修正申告は認められないと通達。しかし、原告は税務署からの通達の前に物件の購入を行っていた。
なお、事案の経緯は表1のとおりである。
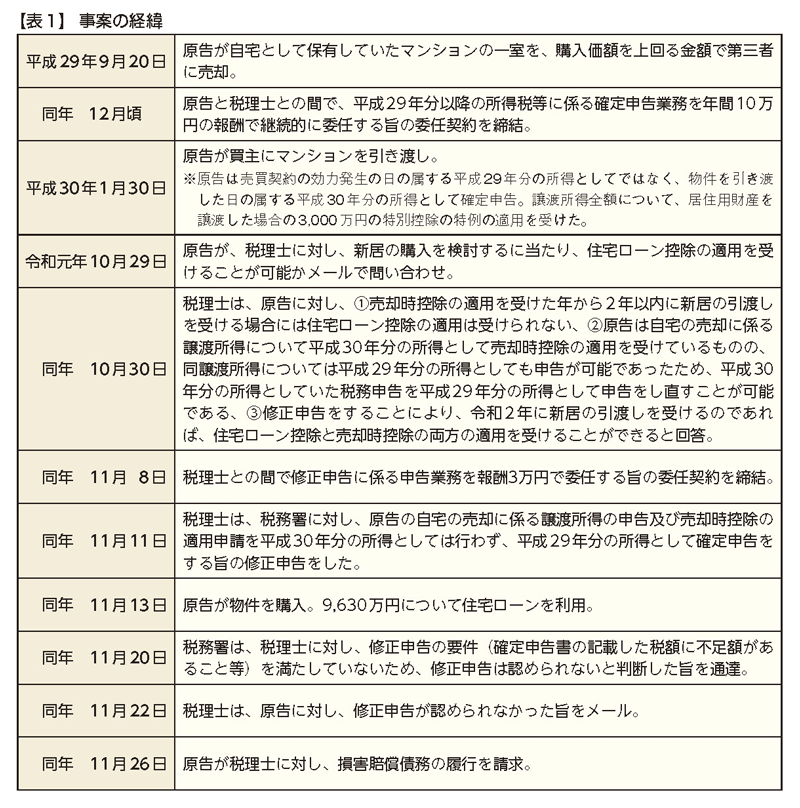
修正申告の可否を確認し報告する義務あり
原告は、税理士は修正申告が認められない可能性に備え、物件の購入を修正申告の受理まで待つべきことを原告に助言するか、契約締結後、直ちに法令・通達等を調査し、又は管轄の税務署に問い合わせた上で、修正申告が認められるか否かについて確認し、その結果を原告に対して報告する義務を負っていたなどと主張した(表2参照)。
【表2】当事者の主な主張
| 原 告 | 被 告 |
| ・税理士は、税務の専門家として高度の注意義務を負っているところ、契約の締結経緯に照らせば、契約に基づく税務申告業務(修正申告)を行うに当たり、①修正申告が認められない可能性に備え、物件の購入を修正申告の受理まで待つべきことを原告に助言するか、②契約締結後、直ちに法令・通達等を調査し、又は管轄の税務署に問い合わせた上で、修正申告が認められるか否かについて確認し、その結果を原告に対して報告する義務を負っていた。それにもかかわらず、税理士は原告に何の注意喚起もせず、また、法令・通達等を誤認して修正申告が認められると考えたまま、注意義務を尽くすことなく漫然と修正申告をしたものである。 ・税理士は、原告が税理士から修正申告が認められない旨の連絡を受けていれば、令和元年中に物件は購入することを見送り、住宅ローン控除の適用を受けられる条件で、翌令和2年に同等物件を購入することとしたことを認識しており、又は予見することができた。したがって、原告の損害は、税理士の本件契約に係る債務不履行と相当因果関係がある。 |
・原告において税理士に不履行があったと主張する債務は、いずれも本件契約の内容に含まれるものではない。すなわち、①本件修正申告が認められない可能性に備えて本件物件の購入を待つか否かは原告自身が判断すべき事柄であって、あえて税理士が助言するほどのことではないし、②そもそも本件契約は修正申告に係る申告業務をすること自体であって、税理士は、原告が主張するような確認、調査をする義務を負っていない。そのため、税理士がした助言に何らかの問題があったとしても、そのことを理由に本件助言の後に締結された本件契約に係る債務不履行責任を問うことはできない。 ・原告は、令和2年1月に入居できる物件を購入する意向を示していたのであるから、税理士から修正申告が認められない旨の連絡を受けていたとしても、令和元年中に物件を購入することを見送り、住宅ローン控除の適用を受けられる条件で、翌令和2年に同等物件を購入することとしたとはいえない。したがって、仮に原告に損害が生じていたとしても、その損害は税理士の本件契約に係る債務不履行と相当因果関係がない。 |
住宅ローン控除の適用を受けるため物件購入を見送ると判断
裁判所は、原告は物件を購入するに当たり、住宅ローン控除満額の適用を受けられることを重視していたと認められるところ、税理士の本件契約に係る債務不履行がなければ、原告において住宅ローン控除満額の適用を受けるため、物件の購入を見送った上で、遅くとも令和3年12月末までに入居するとの条件で同等物件を購入したと認められるのが相当であるとの判断を示し、原告は、同等物件を購入する際に利用したはずの住宅ローン控除額相当の損害が生じたものと認められるとした。
10年間の控除は予見可能
また、税理士は、原告において修正申告が認められず、令和元年に購入して令和2年に入居する新居の購入に際して利用する住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けられなかった場合には、物件の購入を見送った上で、遅くとも令和3年12月末までに入居するとの条件で新居を購入したことを予見することができたと認められるとした。その上で、税理士は、原告の平成30年当時の所得水準(約1,500万円)を把握していたことが認められ、原告の自宅の売却(売却代金約6,000万円)に係る譲渡所得の申告にも関与していたことも併せて考慮すれば、税理士は本件契約に係る債務不履行があった令和元年11月当時、少なくとも、原告が通常の住宅ローン控除(限度額を40万円とするもの)の満額である40万円の特別控除の適用を通常の控除期間である10年間受けることができたことについては予見することができたと認められるとした。
コロナによる期間延長は予見できず
ただし、裁判所は、税理士において原告が認定長期優良住宅を購入することや、住宅ローン控除の控除期間の延長に係る特例措置が、新型コロナウイルス感染症の影響により本来の期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、令和2年11月末までに分譲住宅を取得して令和3年12月31日までに引渡しを受けた場合には適用されることになるといった事柄についてまで、相当程度具体的に予見できたとは認められないとの判断を示し、令和元年11月に生じた税理士の本件契約に係る債務不履行と相当因果関係のある住宅ローン控除額相当の損害は、令和3年12月末日以降、10年間にわたって毎年40万円ずつ発生するものに限られることになるところ、中間利息5%を控除すると、294万1,600円になるとした。
原告に慎重さを求めて過失相殺は2割
過失相殺の可否について裁判所は、原告は物件の購入に当たり、住宅ローン控除の適用を重視していたものであるところ、物件の金額に照らせば住宅ローン控除の税務上の効果は大きく、また、住宅ローン控除の適用を受けるためにする本件修正申告の内容はいささか技巧的なものといえ、そのような修正申告が認められるか否かは住宅ローン控除の適用の可否に直結する重大事であることからすれば、一定の調査能力及び実務経験を有する弁護士である原告には、物件の購入に当たり、相応の慎重さが求められたというべきであると指摘した。
原告は、修正申告が認められたことを確認することなく、税理士から修正申告をしたとの連絡を受けてからわずか5日後に物件を購入するに至っているのであって、このような経過に照らせば、過失相殺による減額は避けられないとし、裁判所は、総合考慮して損害額から2割の過失相殺をした235万3,289円の法定相続分(2分の1)に当たる117万6,640円の限度で、それぞれ原告に対する損害賠償責任を負うとの判断を示した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























