解説記事2023年01月23日 ニュース特集 新たな猶予措置を恒久化する電子帳簿等保存制度の見直し(2023年1月23日号・№963)
ニュース特集
検索機能の確保の要件が大幅に緩和
新たな猶予措置を恒久化する電子帳簿等保存制度の見直し
電子帳簿等保存制度における電子取引データの保存については、令和4年度税制改正により、令和5年12月31日までの2年間の宥恕措置が講じられたところだが、令和5年度税制改正では、新たな猶予措置が講じられることになった(本誌957号5頁参照)。システム対応を「相当の理由」により行うことができなかった事業者については、現行の出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータ保存が可能になる。新たな猶予措置は経過措置ではなく、本則として恒久化されることになる。また、検索機能の確保の要件を緩和。ダウンロードの求めへの対応を前提にすべての検索機能の確保が不要となる売上高基準を現行の「1千万円以下」から「5千万円以下」に大幅に引き上げるなどの見直しを行う。システム対応が難しい事業者だけではなく、電子取引のデータ保存を規定通り行う企業にとっても朗報といえよう。
そのほか、スキャナ保存制度では、入力者等情報の確認要件やスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件を廃止する。また、過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲を合理化・明確化する。対象となる帳簿を絞り込み、法人については「賃金台帳」が除外される点が注目される。
本特集では、令和5年度税制改正における電子帳簿等保存制度の見直しの概要を解説する。
新たな猶予措置は令和6年1月1日以後適用
令和3年度税制改正では電子帳簿保存法が改正され、出力書面の保存をもって電子データに代えることができるとの取扱いが廃止され、令和4年1月1日から適用されることになっていた。しかし、システム対応が遅れている企業の状況を踏まえ、一転して令和4年度税制改正では、「やむを得ない事情」があれば、従前と同様、出力書面による保存を可能とする宥恕措置が設けられることになった。
この宥恕措置は令和5年12月31日までの2年間とされているが、令和5年度税制改正では、宥恕措置が廃止された後の新たな猶予措置が講じられることになった(令和6年1月1日以後適用)。具体的には、システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、従前行われていた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータの保存を可能とする。
「システム対応が間に合わず」でOK
現行の宥恕措置では、税務署長が「やむを得ない事情」があると認める場合とされているが、事業者による手続は不要となっている。仮に税務調査等の際に確認があった場合には各事業者における対応状況や今後の見通しなどを口頭で回答すればよいこととされている。国税庁によれば、例えば、電子データの保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった事情も含め、準備を整えることが困難であれば、宥恕措置の「やむを得ない事情」に該当するとしている。一方、新しい猶予措置も税務署長が「相当の理由」があると認められる場合とされ、やはり事業者による手続は不要となっている。宥恕措置と同様、システム対応が間に合わなかったという理由のみで新しい猶予措置も適用できる方向となっている。
ただし、宥恕措置は出力書面の提示・提出の求めに応じることができることが要件となっているが、新しい猶予措置については、これに加えて、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておく必要がある点に留意したい。また、出力書面及びデータの双方について、事実上、税務調査期間の保存が必要となる。
なお、今回の新しい猶予措置は経過措置ではなく、本則として規定されることとされているため、これは同措置が恒久化されたことを意味することになる。
検索機能の確保の要件を大幅に緩和
電子データ取引の要件の1つである検索機能の確保の要件が令和6年1月1日以後から大幅に緩和される。まず、ダウンロードの求めへの対応を前提にすべての検索機能の確保の要件が不要となる売上高基準を現行の「1千万円以下」から「5千万円以下」に大幅に引き上げる。また、データを出力することにより作成した書面(整然として形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る)の提示・提出の求め及びそのデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは、検索機能の確保の要件を充足しているものとする。
今回の見直しにより、新しい猶予措置の適用者に加え、売上高が「5千万円以下」の事業者(ダウンロードの求めに応じることが必要)及び出力書面の提示・提出の求め及びデータのダウンロードの求めに応じることができる事業者については検索機能の確保の要件が不要となる(図表1参照)。
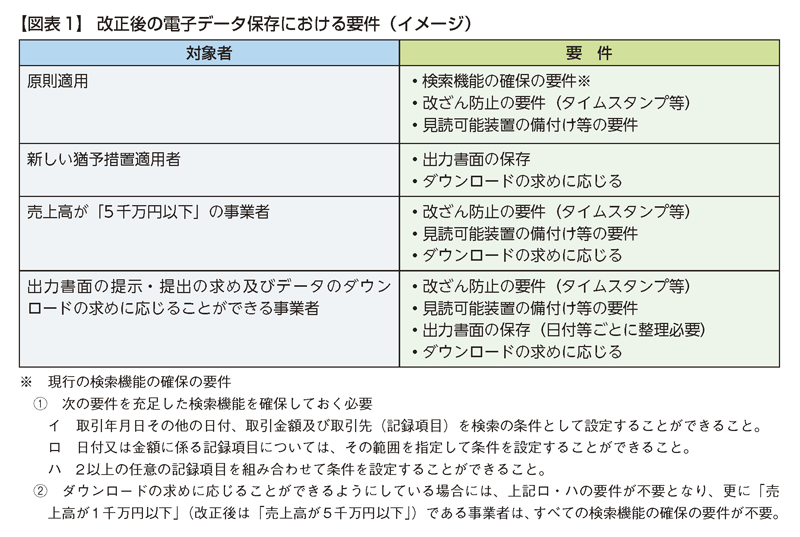
入力者等情報の確認など、スキャナ保存制度の要件を見直し
令和3年度税制改正で大幅な見直しが行われたスキャナ保存制度だが、制度の利用促進を図る観点から、更なる要件緩和措置が講じられることになった(本誌957号7頁参照)。現行のスキャナ保存制度の主な要件は図表2のとおりとなっているが、このうち、「入力者等情報の確認」及び「スキャナで読み取った際の情報(解像度・階調・大きさ)の保存」を不要とする(図表3参照)。
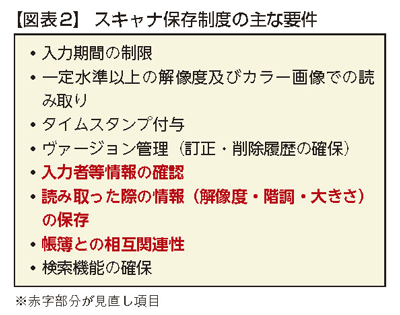
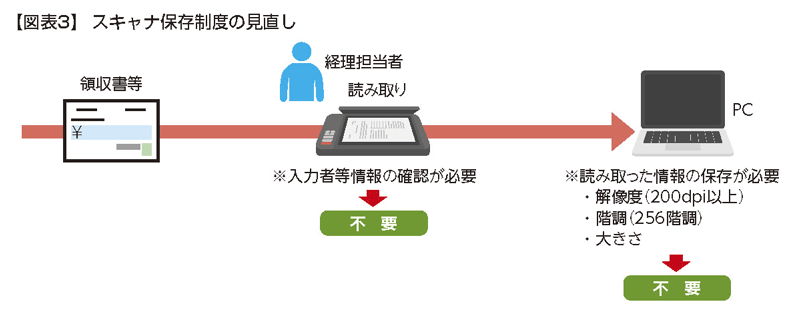
また、現行ではすべての保存書類と帳簿との相互関連性が必要とされているが、相互関連性を求める書類を「重要書類」に限定する。重要書類とは、資金や物の移動に直結・連動する書類のこと。具体的には、契約書、領収書、納品書、請求書などが該当し、見積書、注文書、検収書などは該当しない。
優良な電子帳簿、所得税の場合は「賃金台帳」も対象
令和3年度税制改正で導入された優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置。同措置は、記帳水準の向上に資する観点から、事後検証可能性の高い電子帳簿保存法の要件を満たす電子帳簿については、あらかじめ届出書を所轄税務署長に提出することにより、仮に優良な電子帳簿に記載された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税を5%軽減するというもの。令和5年度税制改正では、この優良な電子帳簿の範囲の合理化・明確化が行われることになった。
現行制度では、「仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(すべて)」とされているが、「その他必要な帳簿」については、図表4に掲げた補助帳簿に限定される。注目すべきは「賃金台帳」は不要となる点だ。賃金台帳のような人事データは経理部の統制の及ばないところであるため、対象から外れることになった(本誌958号8頁参照)。ただし、賃金台帳が除外されるのは法人税の場合のみ。所得税の場合は必要となるので留意したい。
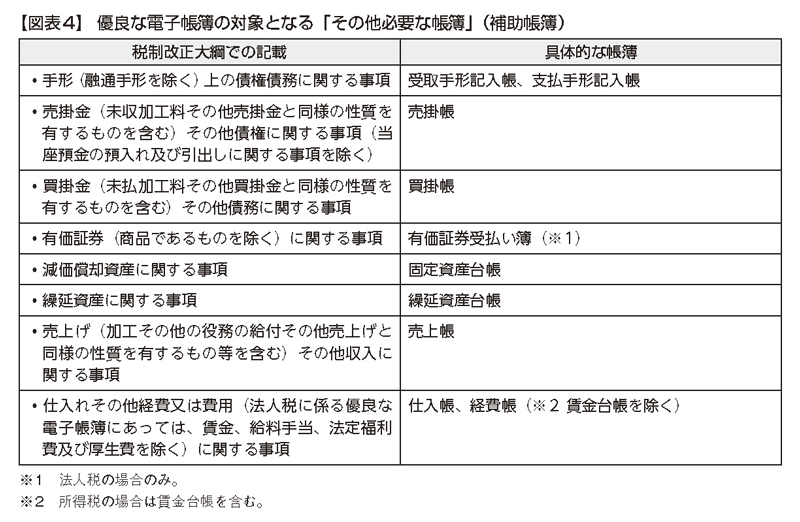
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置適用の手続
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の5%軽減の適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、所轄の税務署長に当該措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出する必要がある。なお、所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合も同様だ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























