解説記事2023年03月20日 第2特集 障害者の生産活動に係る工賃は「役務の提供の対価」か否か(2023年3月20日号・№971)
第2特集
障害者に支払った工賃を巡る争いが訴訟に
障害者の生産活動に係る工賃は「役務の提供の対価」か否か
障害福祉サービスを利用して生産活動を行う障害者に対して支払った工賃が、消費税の課税仕入れに係る支払対価(消法30条①)に該当するか否かが争点となった事件が名古屋地裁で争われている。原告である社会福祉法人は、国税不服審判所に審査請求したものの、「障害福祉サービス(就労継続支援B型)における生産活動の従事者への工賃の支払は、障害福祉サービスの一環として行ったものと認められるから、利用者に対する工賃は、当該利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められない」と棄却されたため、訴訟の提起に踏み切っている。同法人は、「障害福祉サービスの利用者が従事した生産活動は社会的に有用な労働であることなどから、役務の提供であるとし、支払った工賃は消費税の仕入税額控除の対象になる」などと主張。障害者の就労に関する税法上の取り扱いを巡る裁判は珍しく、その行方が注目される。
社会福祉法人と利用者が利用契約を締結、事業収入から工賃を支払い
原告は、就労継続支援B型事業など、複数の障害福祉サービス事業(以下、「各福祉サービス」)を提供する社会福祉法人だ。就労継続支援事業とは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する福祉サービスであり、比較的障害の程度が軽く、雇用契約に基づく就労が可能な「A型」事業と、比較的重度の障害を持っており、雇用契約に基づく就労が困な障害者を支援する「B型」事業に分かれている。
本件各福祉サービスでは、社会福祉法人は、利用者(障害者)と利用契約を締結した上で、利用者ごとに個別の支援計画を作成。その上で、利用契約に基づき就労訓練や生産活動の機会の提供、必要な福祉サービスの提供などを行うことになっており、利用者はそれらの福祉サービスに対して所定の負担額を支払うことになっている。また、「B型」では雇用契約を締結しないことから、生産活動に従事した利用者に対して、給与ではなく、生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う契約となっている(図表1参照)。
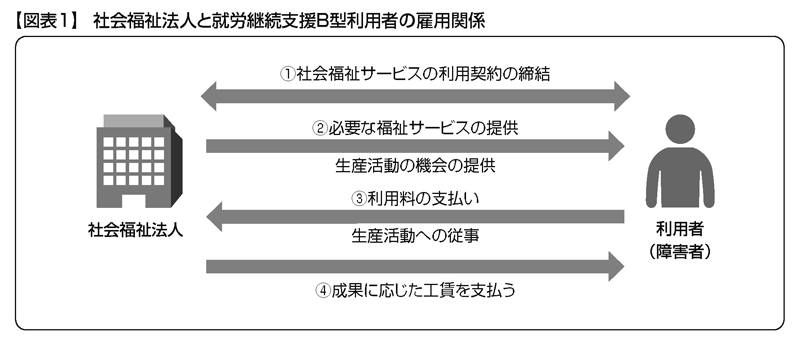
社会福祉法人は、提供する障害福祉サービスを利用して生産活動に従事した障害者に対して支払った工賃については、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に該当するとして、平成26年分から平成29年分の課税期間の消費税額について更正の請求を行ったが、原処分庁が更正をすべき理由がない旨を通知したため、審査請求に至っている(名裁(諸)令3−25)。
審判所、工賃の支払は障害福祉サービスの一環で行ったものと判断
社会福祉法人(請求人)は、「各福祉サービスの利用者が、サービスとして利用した指定生活介護事業、指定就労継続支援B型事業又は指定就労移行支援事業における生産活動に係る作業は、社会的に有用な労働であるから、障害福祉サービスに伴うものであっても、通常の取引と同様に、役務の提供である」などと主張(図表2参照)。一方、原処分庁は、「障害福祉サービスの利用者が生産活動を行った場合に支払われる工賃は、生産活動に係る事業で得た収入から当該事業に直接必要な経費を差し引いた残りを利用者の人数で割った金額で支払うものであり、作業量や作業時間で異なることはなく、収入金額から経費を差し引いた残りを利用者で分配するものである」などと主張した。
【図表2】当事者の主な主張(本件工賃が課税仕入れに係る支払い対価に該当するか)
| 請求人 | 原処分庁 |
| 本件工賃は、以下の理由により消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する。 ○請求人と各福祉サービスの利用者の間で締結される利用契約が混合契約であることは明らかであるから、各福祉サービスの利用者が行う生産活動は、別個に評価が必要な「役務提供」というべきである。 ○利用者の「B型」における生産活動に係る作業は、社会的に有用な労働であるから、障害福祉サービスに伴うものであっても、通常の取引と同様に、役務の提供であるといえる。 ○本件工賃は、生産活動に従事した利用者の能力や就労時間等によって、支給額が決定されている。 ○総合支援法事業基準の規定は、各福祉サービス事業について、事業者は生産活動に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した金額を賃金又は工賃として支払うという同一の文言で規定していることからすれば、「A型」事業に係る労働の対価としての賃金と「B型」事業に係る工賃とを別異に扱うことは不合理である。 |
本件工賃は、以下の理由により、消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。 ○「B型」の利用者が、生産活動を行った場合に支払われる工賃は、法令に定められている通り、生産活動に係る事業で得た収入から当該事業に直接必要な経費を差し引いた残りを利用者の人数で割った金額で支払うものであり、作業量や作業時間で異なることはなく、収入金額から経費を差し引いた残りを利用者に分配するものであるから、賃金や報酬には該当しない。 ○本件工賃も、本件各福祉サービス事業において、本件各福祉サービスの利用者が生産活動に従事することにより、請求人から障害福祉サービスの一環として支払われる金員であって、当該生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除したものである。 ○本件工賃は、生産活動に係る役務の提供に対する対価ではなく、本件各福祉サービスの利用者に対する障害福祉サービスの一環として、生産活動の事業収入から経費を控除した差額が配分されたものである。 |
審判所は、金銭等の支払が課税仕入れに係る支払対価の額に該当するといえるためには、資産の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供の反対給付として支払うことが必要であり、その反対給付としての性質を有さない場合には、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと解されるとした。
その上で審判所は、障害福祉サービス(就労継続支援B型)の利用者は、生産活動の機会の提供を含む一連のサービスに対して利用料を支払うこととされ、生産活動に当たって雇用契約等は締結せず、工賃は生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額とされていたことに加え、障害福祉サービスが利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とするものであることを併せ考えると、就労継続支援B型における生産活動の従事者への工賃の支払は、生産活動の機会の提供と併せて、福祉目的を実現するために、請求人が就労継続支援B型という障害福祉サービスの一環として行ったものと認めるのが相当であると指摘。就労継続支援B型の利用者に対する工賃は、利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められないとし、本件工賃は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価には該当しないとの判断を示した。
生産活動への従事は福祉サービス利用で実現
そのほか、請求人は、各利用契約は混合契約であり、各福祉サービスの利用者が従事した生産活動は、社会的に有用な労働であることなどから、障害福祉サービスとは別個に評価が可能な役務の提供というべきであり、サービスの一環であるという形式論理で判断すべきではないと主張したが、審判所は、生産活動への従事は各福祉サービスを利用することにより初めて可能となるものであり、生産活動への従事のみを形式的に各利用契約から切り離して評価することは適切でないとした。
利用者の作業量等は無視すべきでない
審査請求が棄却された社会福祉法人はこれを不服として提訴し、現在、名古屋地裁で争われている。原告の社会福祉法人は、総合支援法事業基準192条3項(就労継続支援A型)及び201条(就労継続支援B型)では「利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」とされており、就労支援事業経費として支給される訓練等給付費を工賃に充ててはならないという規定(総合支援法事業基準192条6項)を併せみると、生産活動収益はすべて工賃として支払い、就労支援事業経費に充ててはならないとする解釈が正解であり、利用者の作業量や作業時間を無視し、すべて均等に作業従事障害者の人員で割って支払う解釈は誤りであるなどと主張している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























