解説記事2023年05月15日 税務マエストロ インボイスQ&A~令和5年4月改訂を検証する!(2023年5月15日号・№978)
税務マエストロ
インボイスQ&A~令和5年4月改訂を検証する!(1)
#286
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)が令和5年4月14日に改訂された。令和4年11月25日の改訂から5か月も経たずしての再改訂である。令和5年度の税制改正法案の成立を受け、一日も早く情報をアップして令和5年10月から始まるインボイス制度に備えてほしいということなのであろう。
改訂されたインボイスQ&Aが公表された日には、国税庁動画チャンネルに「フワちゃんと学ぼう!インボイス制度」がアップされた。経済評論家の岸博幸氏とフワちゃんの対談によるインボイスの解説動画はなかなかに面白いので、是非ご視聴いただきたい。また、「お問合せの多いご質問」も同日付で更新されている。
財務省では、インボイス制度のPRのため、民間企業や日税連が主催する座談会やwebセミナーを精力的にこなし、インボイス制度の普及に努めているようだ。また、法案の成立前であるにも係わらず、「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問と回答」なるものを公表し、2割特例を中心とした令和5年度改正に関する情報発信をした。
これらの仕事は本来、国税庁がすべきことなのだが、法案が成立しない状態では、立場上、国税庁は動くことができない。そこで、財務省がなりふり構わずインボイスの普及活動のために奔走したということなのであろう。
本稿では、改訂されたQ&Aについて、特に留意すべき改訂事項をピックアップするとともに、新たに追加された15問のQ&Aについてコメントを付すこととした。
改訂されたQ&Aのポイントチェック
1 Q&Aの改訂箇所
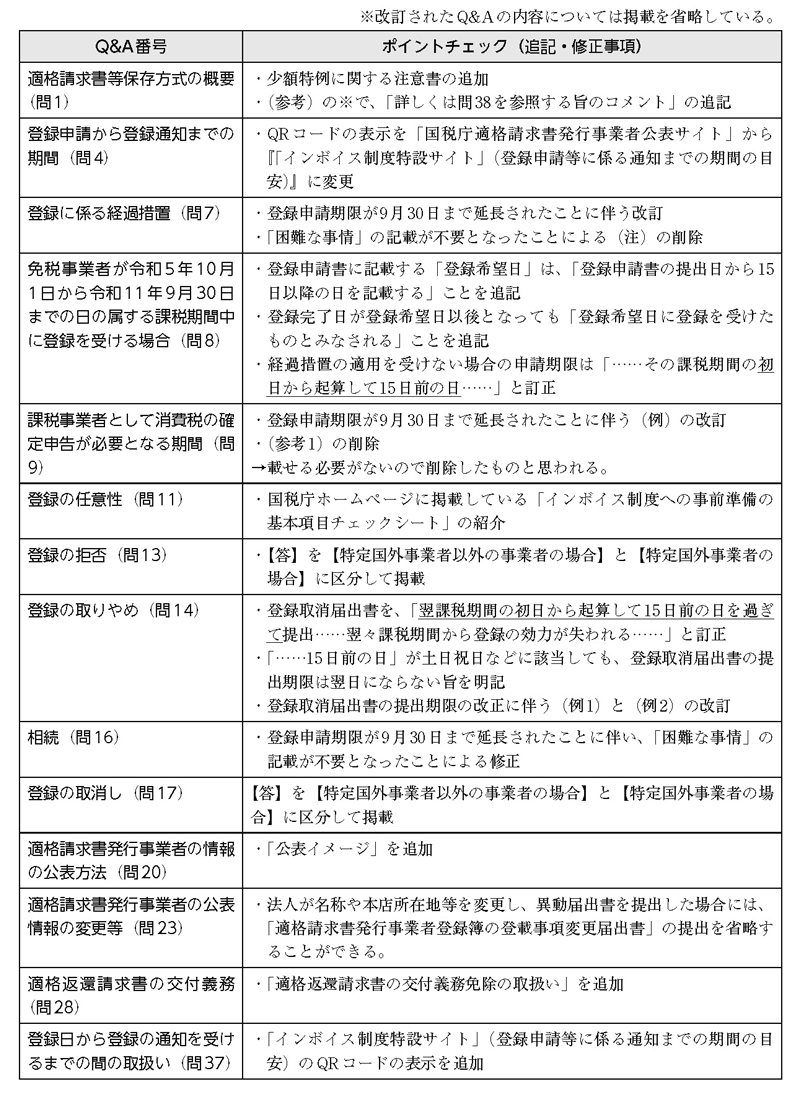
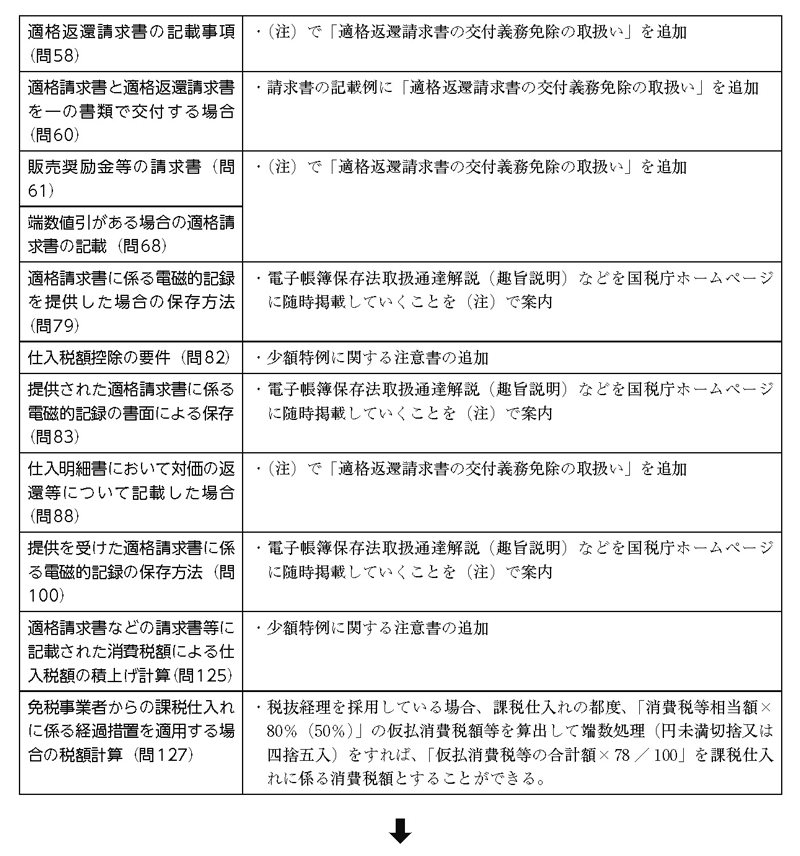
改訂により問127に追加された文章は、令和5年2月28日付で「お問合わせの多い質問」に掲載された下記の問を文章で簡記したものである(上表の文章は、筆者が一部アレンジして掲載した)。
法令に定められているからといって、取引の都度、7.8%(国税)部分を算出してから経過措置の対象となる80%相当額を計算するのはナンセンス極まりない。そこで、まずは80%経過措置を適用後の仮払消費税額等を算出し、その合計額を基に7.8%(国税)部分を算出してもよいこととしたものである。
この問は、改訂Q&Aに掲載されたことにより「お問合わせの多い質問」からは削除されているのだが、改訂Q&Aの問127では、「お問合わせの多い質問」に掲載されていた算式が省略されている。算式があればわかりやすいのに、なぜ算式を省略してしまったのだろう……。
以下のQ&Aは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和4年11月改訂)」の公表後、お問合せの多い事項について、追加問として整理し、集約したものです。
(税抜経理を採用し、積上げ計算を行っている場合における適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算)
問 当社は、適格請求書等保存方式の下では、売上税額の計算は積上げ計算方式によることとし、税抜経理を採用していることから、仕入税額の計算については帳簿積上げ計算方式を採用する予定です。
また、令和8年9月30日までの間に行った経過措置の適用を受ける適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る消費税額については、仕入税額の計算方法が積上げ計算方式であることから、
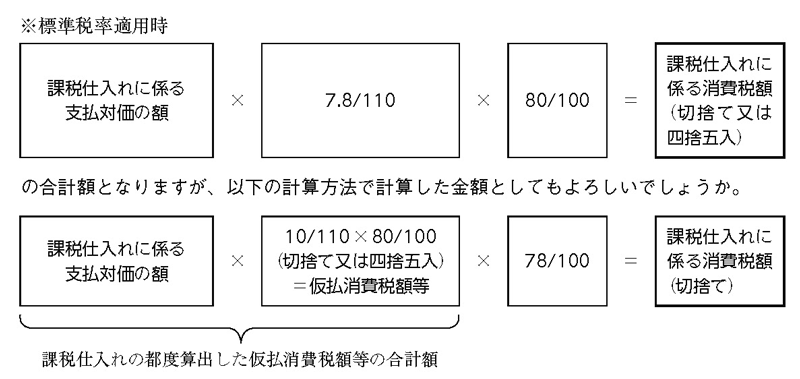
【答】
ご質問の計算方法については、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額等相当額の100分の80)の仮払消費税額等を算出し、端数処理がなされています。
したがって、当該計算方法により算出した金額を当該経過措置の適用を受けた課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません。
なお、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の具体的な控除割合や計算方法については、「消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関するQ&Aの問112」をご参照ください。
Q&Aの問127は、令和4年4月改訂で追加されたものであるが、「また、税抜経理を……」と追加された文章の上に、「なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。」という実に難解な解説が書かれている。
ここに書かれている「……区分して管理……」という文章を「集計」と解釈すると、経過措置の適用を受ける課税仕入れについては事実上割戻し計算ができるようにも思えるのだが、実際はこのような計算は認められないようである。
改正法施行規則では、経過措置の適用を受ける課税仕入れの場合、課税仕入れの都度、消費税額まで求めることを要求している。ただ、現実的に消費税の計算は期末に行うことから、課税仕入れの都度、消費税額を計算しても意味がないことになる。そこで、インボイスのある課税仕入れと合わせて、期末に計算する、あるいは期間短縮を行っているのであれば、3か月又は1か月ごとに計算することを認めるという意味になるようだ。
ただし、計算方法としては、課税仕入れごとに改正法施行令附則によりその都度計算することになるものと思われる。ソフト会社からすれば、経過措置の適用を受ける課税仕入れについて、計算式さえプログラミングしておけば、課税仕入れごとに積上げ計算を行ったとしても、おそらくは大した問題ではない(逐条放談 消費税のインボイスQ&A第2版334頁より抜粋)。
他のQ&Aは算式や図表を使って丁寧に説明がされているのに、この問127だけは、【答】の解説が極めて不親切という印象を受ける。Q&Aの作成者によって出来映えが異なるのは致し方ないとしても、もう少しわかりやすい解説を心掛けて戴きたいものである。
2 登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する改正事項・留意点
○免税事業者が登録申請するケース
免税事業者がインボイスの登録申請をする場合には、「適格請求書発行事業者」になろうとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない(消法57の2②、消令70の2)。
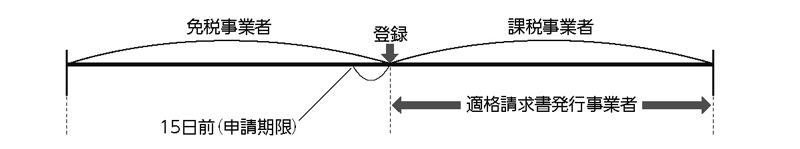
期限までに申請書を提出した場合において、実際の登録日がその課税期間の初日後にずれこんだ場合には、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされるので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになる。
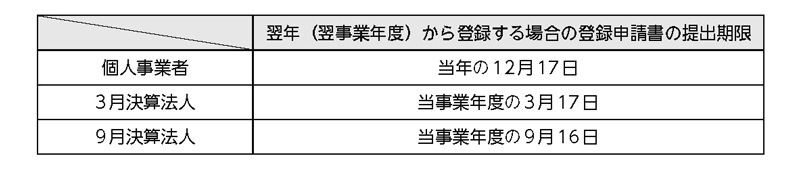
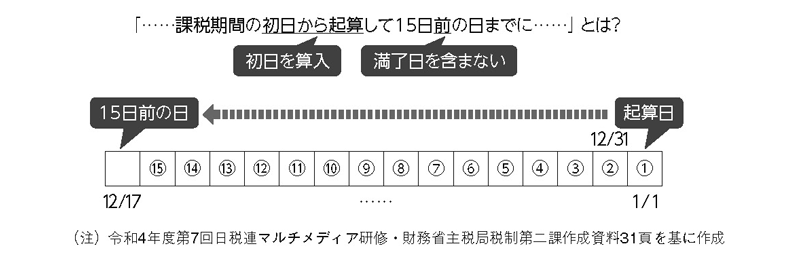
○令和5年10月1日から登録する場合の申請期限(問7関係)
令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、令和5年3月31日(申請期限①)までに登録申請書を税務署長に提出する必要がある。ただし、特定期間中の課税売上高等が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる事業者の場合には、①の期限までに登録申請書を提出することができないケースが想定される。
そこで、特定期間中の課税売上高等により納税義務を判定した結果、課税事業者となる事業者が、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、登録申請書の提出期限を令和5年6月30日(申請期限②)まで延長していた(平成28年改正法附則44①)。
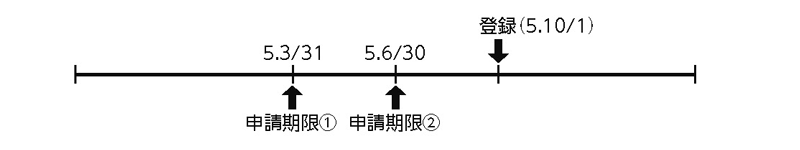
上記①又は②の期限までに登録申請書を提出することにつき、困難な事情がある場合には、困難の度合いを問わず、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなすこととされている(インボイス通達5-2)。
そこで、あえて申請書に困難な事情を記載しなくても、令和5年9月30日までの登録申請で、令和5年10月1日からの登録ができることとなった(平成30年改正令附則15①)。
※申請書の記載箇所については23頁を参照
なお、実際の登録日が令和5年10月1日後にずれこんだ場合には、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされるので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになる(平成28年改正法附則44③)。
言い換えれば、令和5年10月1日以後に発行する請求書等は、インボイスの通知が届くまでの間は登録番号を記載することはできないということである。
法人の登録番号は法人番号であることをもって、インボイスの通知が届く前に法人番号を登録番号として請求書等に記載することは認められないので注意が必要だ。
○免税事業者が令和5年10月1日から登録する場合
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「課税事業者選択届出書」の提出は不要とされている。
例えば、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日より「適格請求書発行事業者」となる場合には、上記の期限までに登録申請書を提出することにより適格請求書発行事業者としてインボイスを発行することができる。
この場合において、令和5年1月1日~令和5年9月30日の間は免税事業者として納税義務はないことから、登録開始日である令和5年10月1日以後の期間についてのみ、課税事業者として申告義務が発生することになる(平成28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。
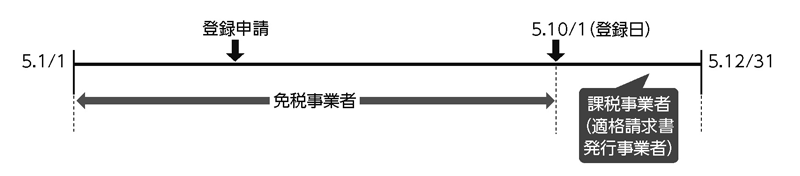
また、登録日以後の期間(令和5年10月1日~令和5年12月31日)について簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和5年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税により仕入控除税額を計算することができる(平成30年改正令附則18)。
つまり、「簡易課税制度選択届出書」は登録日の属する課税期間の末日までに提出すればよいということである。
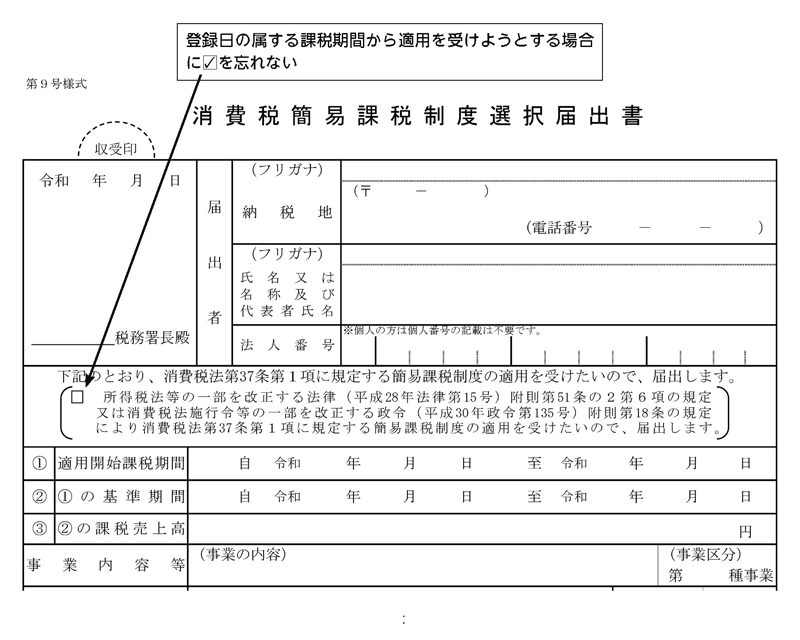
○免税事業者の登録手続に関する経過措置の延長(令和4年度改正)
1 登録手続に関する経過措置の延長と課税期間の中途からの登録
免税事業者はインボイスの発行ができないため、取引先からの要請により、インボイスの登録申請をして適格請求書発行事業者となることが予想される。
この場合、適格請求書発行事業者になると消費税の申告義務が生ずるため、納付消費税額をコストとして負担しなければならない。
そこで、免税事業者のような適格請求書発行事業者でない「非登録事業者」からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間については課税仕入高の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間については、課税仕入高の50%を仕入控除税額の計算に取り込むことができる(平成28年改正法附則52、53)。
免税事業者は、この経過措置も考慮に入れながら、登録の必要性と資金繰りを天秤にかけ、取引先との価格交渉に当たらなければならない。つまり、登録の是非を慎重に判断する必要があるということである。
令和4年度改正では、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、令和5年10月1日の属する課税期間だけでなく、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、「課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録申請書を提出することにより、適格請求書発行事業者となることを認めることとした。また、登録申請書を提出することにより、年または事業年度の中途から登録をすることもできる(平成28年改正法附則44④)。
簡易課税制度についても、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者については、登録日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から簡易課税により仕入控除税額を計算することができる。
<具体例>
個人事業者であれば、登録申請書を提出することにより、令和5年から令和11年分までの任意の年(課税期間)について適格請求書発行事業者になることができる。また、令和6年10月1日といったように、年の中途からの登録も認められる。
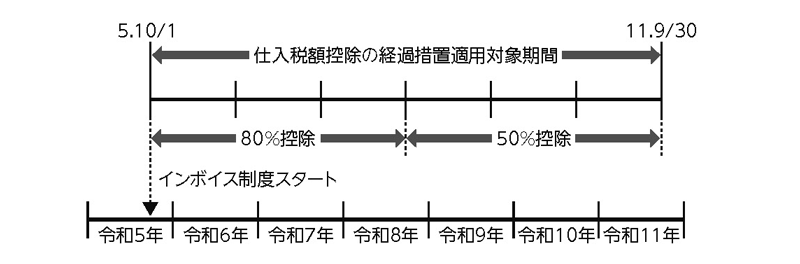
2 免税事業者が登録した場合の課税事業者としての拘束期間
令和4年度改正では、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者とのバランスに配慮し、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において登録する免税事業者は、令和5年10月2日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者として申告義務を課することとしている(平成28年改正法附則44⑤)。
注意したいのは、上記1により、令和5年10月1日の属する課税期間において登録する免税事業者は、いわゆる2年縛りの規定がないということである。
したがって、個人事業者(免税事業者)が令和5年10月1日に登録した場合には、令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者となることができるのに対し、令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)は、登録開始日(令和6年1月1日)から2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間(令和7年)までの間は課税事業者として申告義務があるので、結果、令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として拘束されることとなるのである。
3 登録希望日(問8関係)
登録申請書の「登録希望日」に記載した日から登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書の提出日から15日を経過する日以後の日を記載しなければならない(平成30年改正令附則15②③)。この場合において、実際の登録日が登録希望日後にずれこんだ場合には、その登録希望日に登録を受けたものとみなすこととされているので、登録通知を受け取った後に登録番号を取引先に通知すれば、通知前に交付した請求書等はインボイスとしての効力を有することになる。
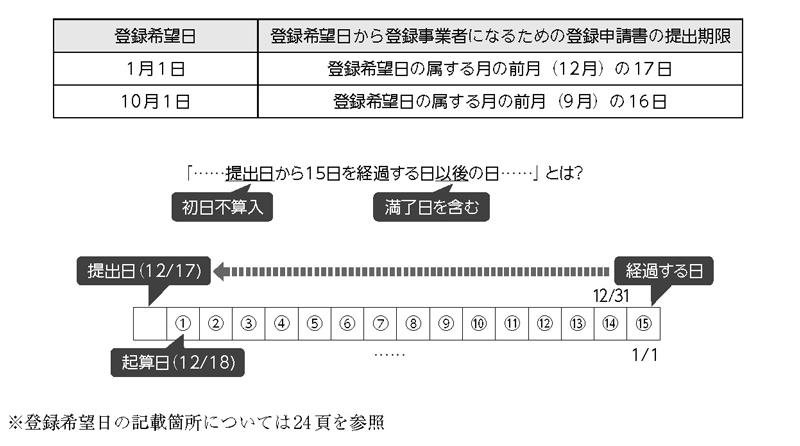
○登録の取消し(問12関係)
インボイスの登録を受けた適格請求書発行事業者は、登録取消届出書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(25頁参照))を提出しない限り、課税事業者として申告義務が発生する。
適格請求書発行事業者が登録取消届出書を税務署長に提出した場合には、インボイスの登録が取り消され、インボイスの効力が失効する(消法57の2⑩一)。
適格請求書発行事業者が翌年又は翌事業年度から登録を取り止めようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録取消届出書を提出しなければならない(消法57の2⑩一、消令70の5③)。
なお、登録取消届出書については、提出期限を定めたものではないため、国税通則法10条2項(期限の特例)の規定は適用されない。よって、課税期間の初日から起算して15日前の日が土日祝日などであったとしても、届出書の提出期限はその翌日に延長されない(インボイスQ&A問14)。
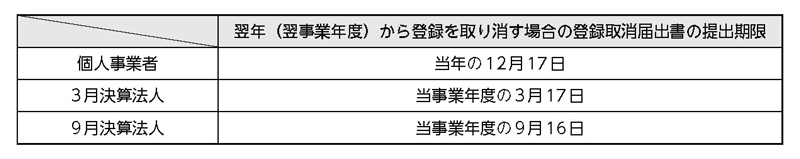
この場合において、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、「登録取消届出書」だけでなく、「課税事業者選択不適用届出書」も提出しないと免税事業者になることはできない。「ダブルロック」により課税事業者として拘束されているということに注意する必要がある。
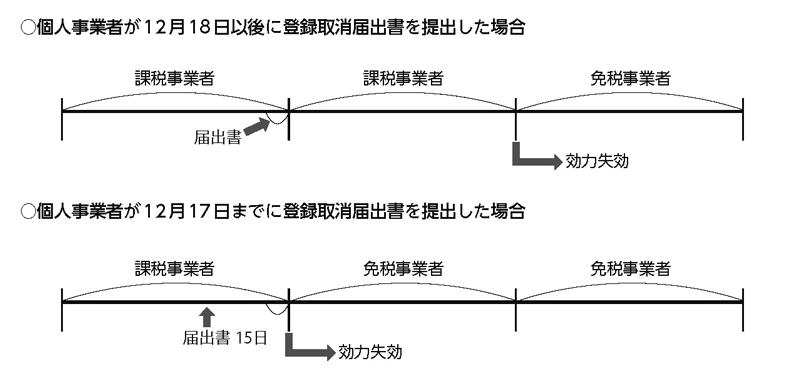
○登録事項の変更(問23関係)
適格請求書発行事業者は、「適格請求書発行事業者登録簿」に登載された事項に変更があった場合には、速やかに「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」(26~27頁参照)を提出することとされている(消法57の2⑧)。
なお、法人税と消費税で兼用となっている「異動届出書」(28頁参照)に必要事項を記載した上で「消費税」の□に✔︎印を付して提出すれば、納税地の異動があったときに提出する「法人の消費税異動届出書」や「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要はない。
(注)個人事業者などが、旧姓・屋号・事務所等の所在地を公表したり変更するような場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要がある(インボイスQ&A問20・22)。
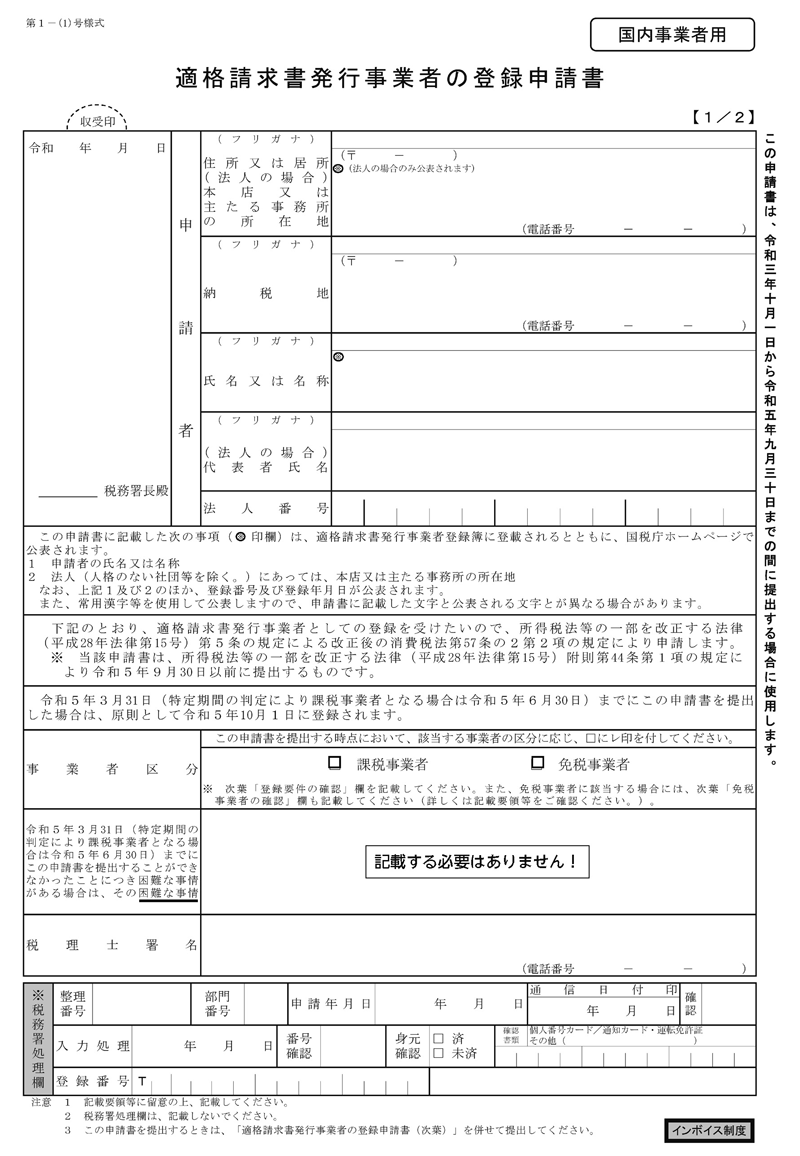
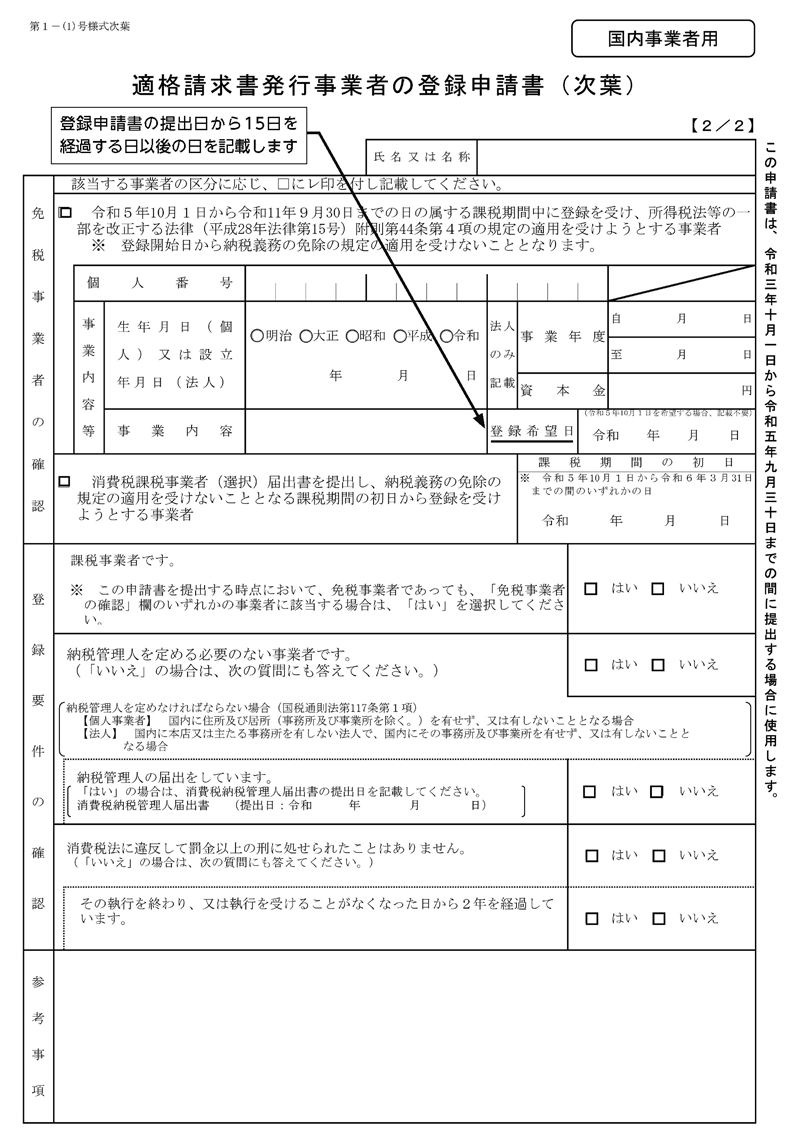
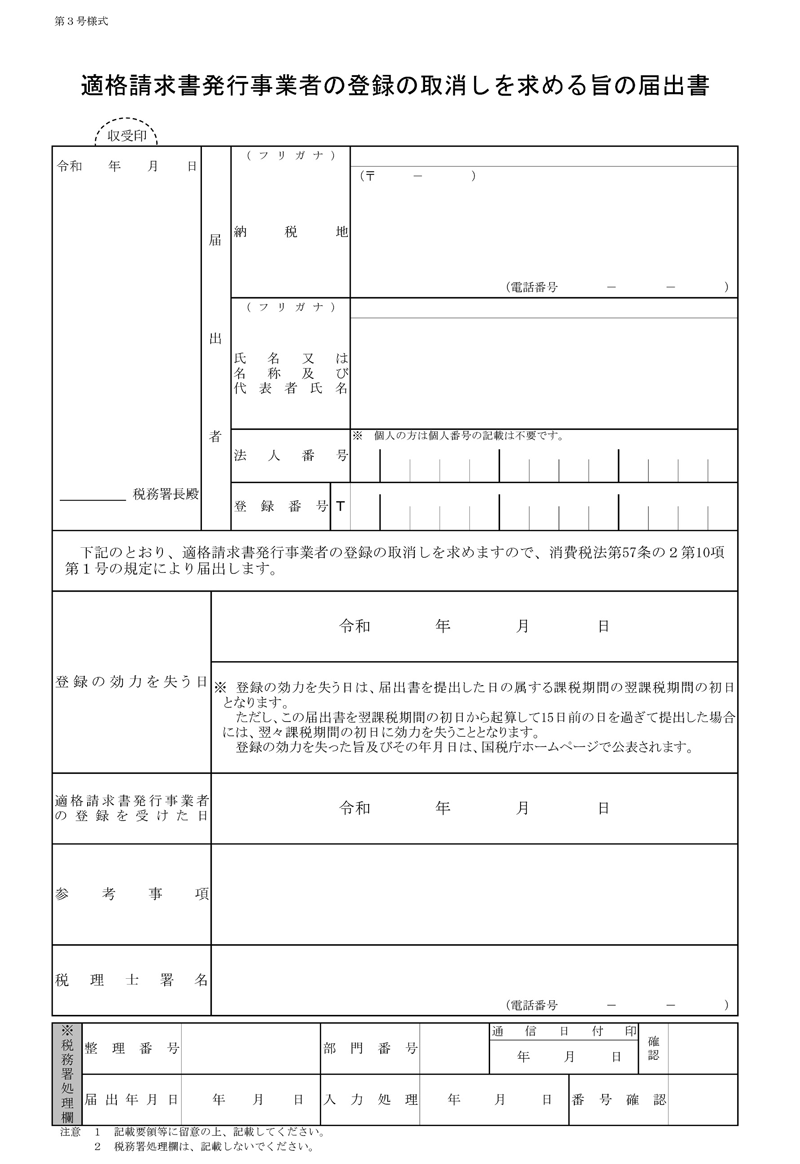
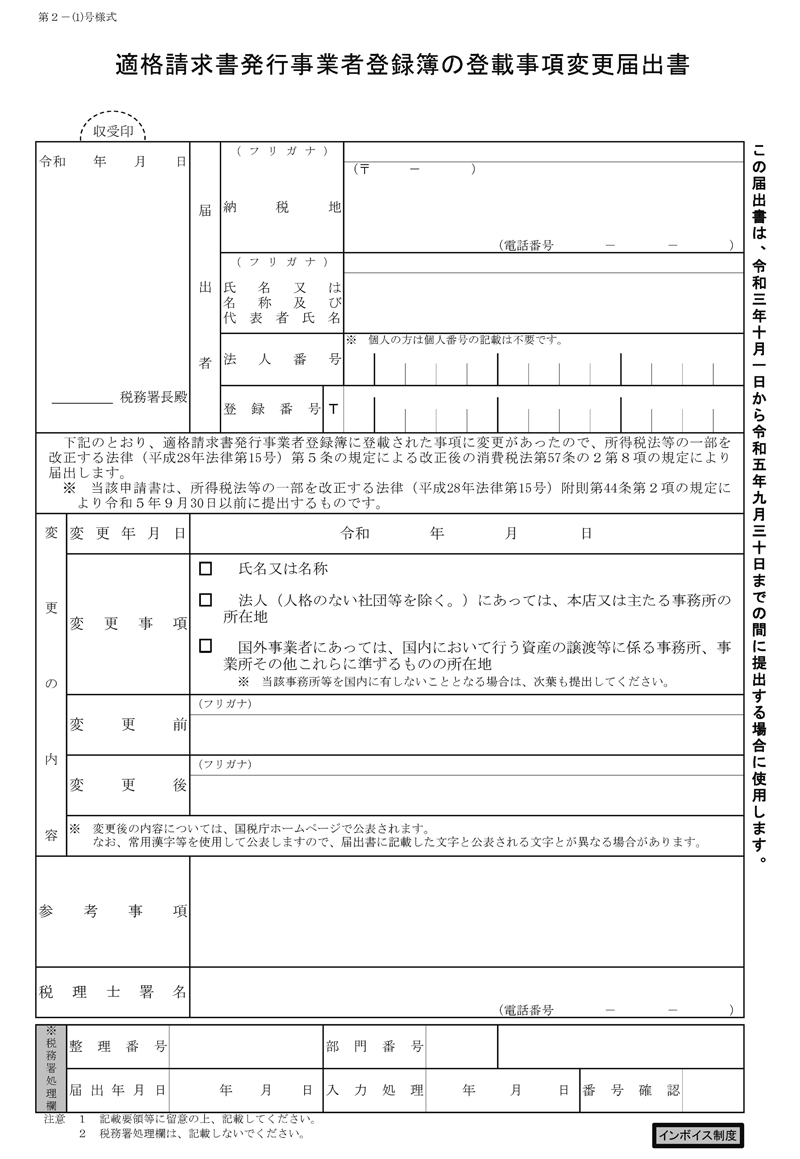
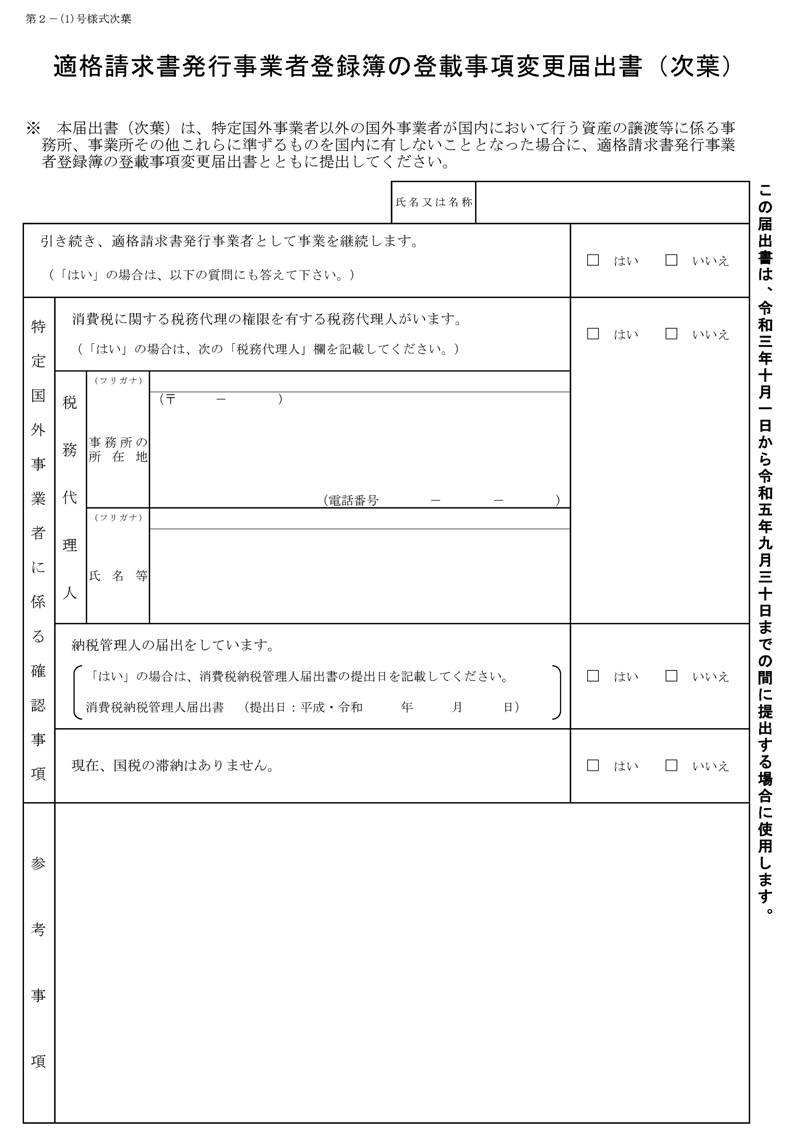
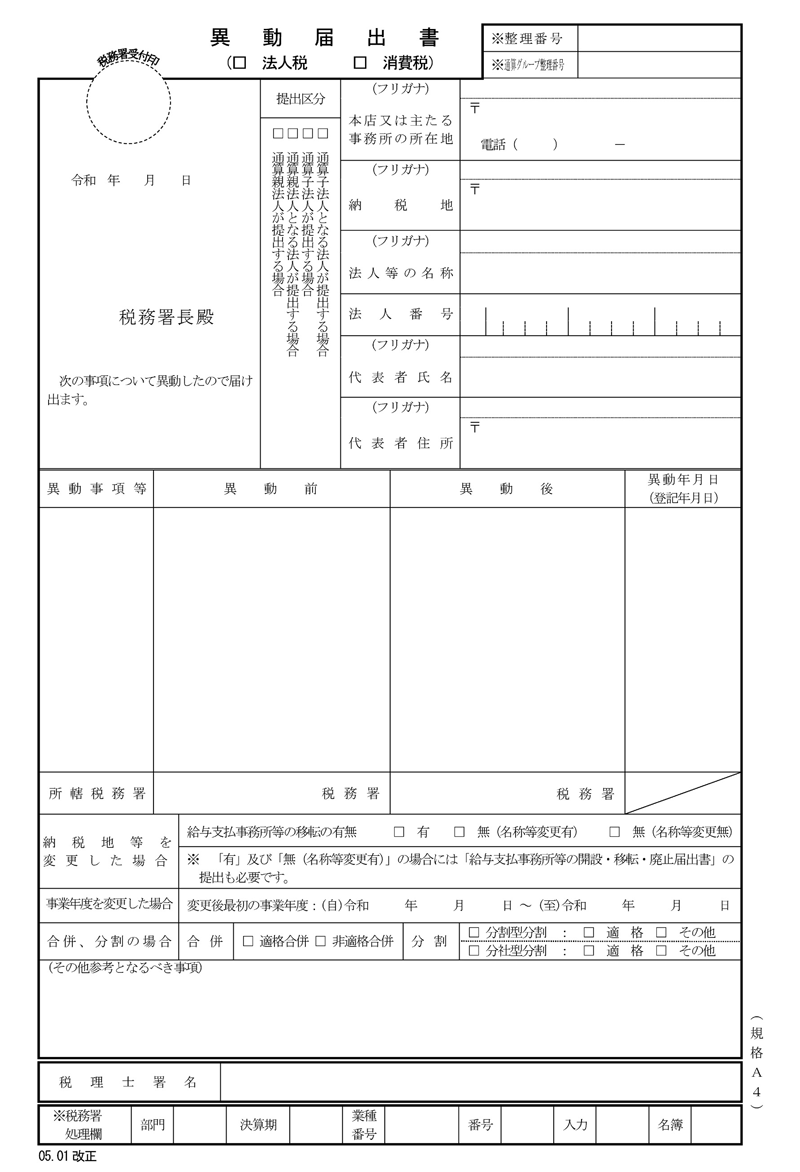
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















