解説記事2023年07月24日 SCOPE 外国籍不動産関連法人株式の相続・贈与は「国外財産」扱い(2023年7月24日号・№988)
非居住者間等での移転であれば課税対象外
外国籍不動産関連法人株式の相続・贈与は「国外財産」扱い
外国人富裕層を中心に、非居住者による国内不動産への投資が増加しているが、所得税法又は法人税法上は不動産関連法人に該当する外国法人の株式まで相続税法上の国外財産として扱ってしまってよいのか、との疑問が生じている。
この点、本誌が課税当局に取材したところ、そのような場合であっても、「相続税法上、有価証券の内外判定の方法は同法10条にのみ規定されているため、同条に基づき、その本店又は主たる事務所の所在地で判断する」ということが確認された。
譲渡時は非居住者に申告納税義務、相続・贈与時の扱いは
海外の富裕層等、日本国籍を有さない非居住者による国内不動産への投資は、個人で直接当該不動産を保有するほか、自身が保有する外国法人を経由して行われるケースがある。
所得税法又は法人税法上は、法人の有する資産の価額の総額のうちに占める国内不動産の割合が50%以上である場合、通常その法人は「不動産関連法人」に該当する。要件を満たす限り、内国法人・外国法人の区別なく不動産関連法人に該当し得ることになり、保有株式数が少数(非上場株であれば発行済株式等の2%以下)でなければ、その株式の譲渡益について、日本に恒久的施設を有していない非居住者であっても申告納税が必要な国内源泉所得として扱われる(所令281条①五、法令178条①五)。
有価証券として相続税法10条で内外判定
一方、相続又は贈与により株式を含む資産が移転する場合は、相続税法上、「日本国籍を有さず、国内に住所も有していない非居住者」から、同様に「日本国籍を有さず、国内に住所も有していない他の非居住者」に対して資産が移転した場合等には、国内財産に対してのみ相続税又は贈与税が課されることになる。そのため、不動産関連法人株式が国内財産と国外財産のいずれとして扱われるかによって、課税関係が大きく異なるケースがある。相続税法上、国内財産に該当するかどうかの判定は、相続税法10条に従って行われるが、現物不動産については同条1項1号に基づきその所在地が国内であれば国内財産として扱われ、株式を含む有価証券については同項8号に基づき「発行法人の本店又は主たる事務所の所在地」により判定される。つまり、株式については、発行した法人の本店等所在地が日本国外であれば、国外財産として扱われることになる。
所得税又は法人税法上、不動産関連法人に該当する外国法人の株式については、実質的には国内不動産を保有している状態であるため、外国籍の不動産関連法人の株式まで、相続税法10条に基づき本店等所在地が国外であることを理由に国外財産として扱ってしまってよいのかとの疑問が、税理士等の間で生じている。
この点について本誌が課税当局に取材したところ、不動産関連法人に該当する外国法人の株式であっても、「相続税法上、有価証券の内外判定の方法は同法10条にのみ規定されているため、同条に基づき、その本店又は主たる事務所の所在地で判断する」ということで差し支えないことが確認された。
したがって、日本国籍・住所のいずれも有していない非居住者である個人が、不動産関連法人株式に該当する外国法人の株式を譲渡により移転した場合には、所得税の申告納税が必要となるが、同株式を、相続または贈与により同じく日本国籍・住所のいずれも有していない他の非居住者に移転する場合等には、国外財産として、相続税・贈与税の対象外として扱われることになる(図表参照)。外国人富裕層を顧問先に持つ税理士等は、保有・売却時のみならず、相続・贈与時の課税関係までを視野に入れた総合的なアドバイスが必要となるケースがあるだろう。
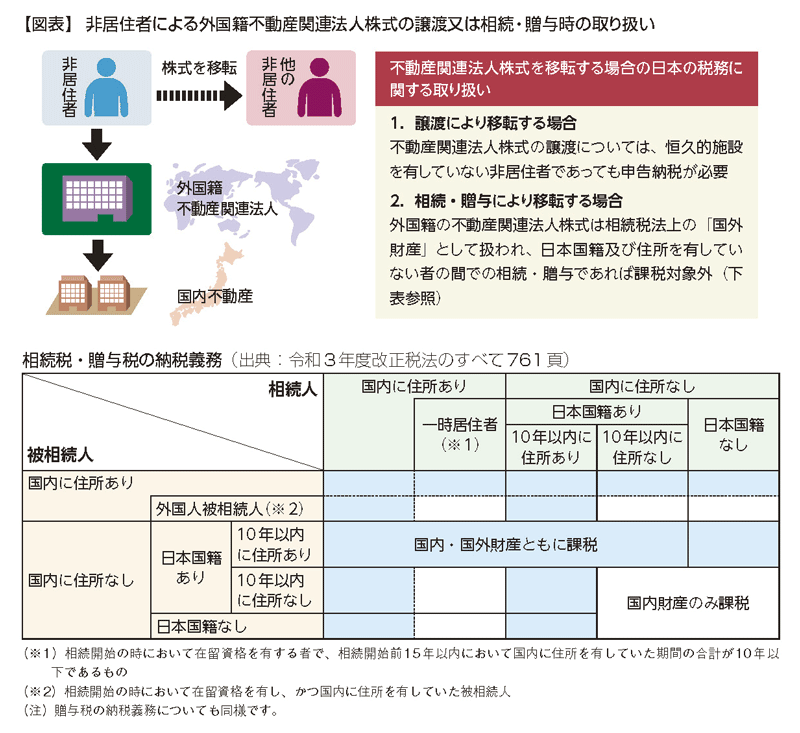
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















