解説記事2023年09月25日 税務マエストロ 国税庁の質疑応答事例とインボイスの関係(2023年9月25日号・№996)
税務マエストロ
国税庁の質疑応答事例とインボイスの関係
#291
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
今回は、国税庁の質疑応答事例に掲載されている事例について、インボイスとの関係を考察する。
Ⅰ 会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却(資産の譲渡の範囲 2)
【照会要旨】
会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。
消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。
照会の余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。
したがって、照会のように、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。
(注)会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
1 解説と疑問点
【回答要旨】によれば、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象とはならないとしている。
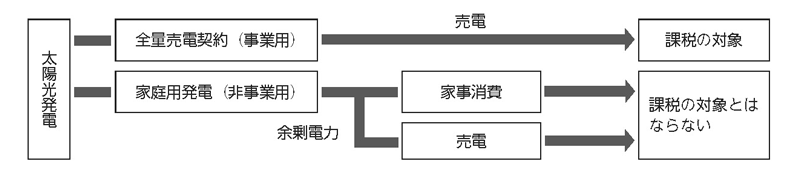
余剰電力の販売が課税の対象になるかどうかの判断は、売手が事業者かどうかで取扱いが異なってくると説明がされているのであるが、この場合において、売手が個人事業者の場合には、「事業として」に該当するかどうかはどのように判断したらよいのであろうか……?
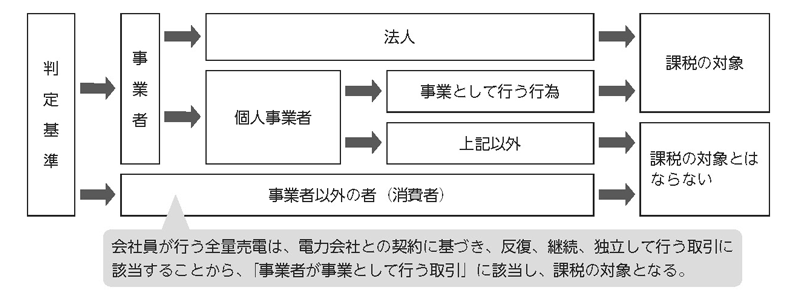
【回答要旨】には、「……事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。」と書かれているので、文字面だけ読むと、個人が行う余剰電力の売却は課税の対象とはならないようにも思える。
その一方で、国税庁質疑応答事例では、「会社員が行う建物の貸付けの取扱い(資産の譲渡の範囲1)」について、次のような事例も掲載している。
【照会要旨】
会社員が行う建物の貸付けは、課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですから、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。
なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。
この事例に書いてある「会社員」とは、事業者ではない者を想定しているものと思われるが、この事業者ではない会社員が、反復、継続、独立して建物を貸し付ける場合には、その行為は、事業者が事業として行ったものとして課税の対象に組み込まれることとなる。そうすると、個人事業者が行う余剰電力の売却は、反復、継続、独立して行われる限りは課税の対象となるようにも思えるのである。
2 インボイスとの関係
東京電力エナジーパートナー株式会社では、電力の買取先である発電事業者(課税事業者)に対し、DMによりインボイスの登録をお願いしているようである。
<参考>
インボイス登録番号のご登録のお願い
2023年4月17日
東京電力エナジーパートナー株式会社
平素は、当社事業に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2023年10月1日より、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度の導入に際し、インボイス発行事業者として登録された事業者さまにおかれましては、税務署から届く登録通知書に記載されている「登録番号」について、以下の通り登録サイトよりご登録をお願いいたします。
また、インボイス発行事業者として未登録の事業者さま、消費税を申告・納付していない事業者さま(免税事業者)におかれましても、登録していない旨のご登録をお願いいたします。
1.ご登録方法
当社と電力受給契約を締結されている事業者さまを対象に、2023年5月下旬より、順次、QRコード付きのダイレクトメールをお送りいたします。
ダイレクトメールに印字されたQRコードを読み取りますと、ご契約毎の登録サイトにアクセスできますので、表示されるご契約情報に誤りが無いかご確認の上、インボイス登録状況をご登録ください。
2.登録受付期間
QRコードからのご登録は2023年6月1日(木)から2023年9月27日(水)までとなります。
2023年9月28日(木)以降のご登録、および登録番号の変更等につきましては、2023年9月以降、当社ホームページ等にてご案内させていただきます。
3.インボイス制度開始後の電力購入単価について
(1)再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となるご契約
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)にもとづき既にFIT認定を受けているご契約については、インボイス登録の有無により調達価格が変更されることはございません。
(2)再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象とならないご契約
インボイス登録の有無によらず、従来通りの買取単価を適用いたします。
買取単価を変更する場合には、ホームページ等により、予めお知らせいたします。
4.免税事業者におけるインボイス制度への対応について
消費税を申告・納付していない事業者さま(免税事業者)におかれましてはインボイス制度に関する対応はございませんが、各事業者さまのインボイス登録状況を把握するため、登録していない旨を「1.ご登録方法」記載の方法でご登録ください。
:
(以下省略)
上記の案内文に先駆け、同社は同年2月1日に「インボイス発行事業者の登録申請に関するお願い」として、下記のような案内文(抜粋)を公表している。
:
2.電力受給契約におけるインボイスの交付について
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者であるインボイス発行事業者が交付するインボイス等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、電力受給契約においては、全てのインボイス発行事業者よりインボイスの交付を受けることが困難なため、当社が交付する仕入明細書(「購入料金等のお知らせ」を指します)による対応を予定しております。
3.インボイス登録番号のご連絡について
インボイス発行事業者として登録された際に通知される「登録番号」については、当社が発行する仕入明細書に記載が必要なため、当社へご連絡頂く必要がございます。
「登録番号」のご連絡方法等につきましては、2023年4月以降、当社ホームページ等にてご案内させていただきます。
:
すべての発電事業者にインボイスを発行してもらうことは事実上不可能である。よって、実際には仕入明細書(購入料金等のお知らせ)で対応することとなることから、仕入明細書に記載する「登録番号」のご連絡をお願いしたいという趣旨の文面となっている。実務上は登録番号さえ把握できれば買手である「東京電力エナジーパートナー株式会社」は仕入明細書の作成ができるのであり、4月17日のお願い文では仕入明細書に関する説明はすべて省略されているようだ。
また、インボイスの登録をしない場合であっても従来通りの買取単価を適用することとしているので、外税で支払っている消費税相当額について、「東京電力エナジーパートナー株式会社」が仕入税額控除ができない2割部分を負担するということなのだと思われる。
インボイスの登録をしない小規模事業者が取引から排除されることを避けるために設けられた経過措置が、悪戯にインボイス登録を阻害しているだけでなく、小規模事業者との価格交渉の足かせになっているというのが現実である。取引先の顔色を伺いながら、また、世論の動向にも気を遣いながら価格交渉をしなければならないというジレンマが暫くの間は続くのであろう……。
(注)令和5年10月1日〜令和8年9月30日においては、非登録事業者からの課税仕入れについても80%を課税仕入れ等の税額に加算することが認められている(平成28年改正法附則52)。
Ⅱ 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡(資産の譲渡の範囲 3)
【照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(消基通5−1−1(注)1)。
1 解説と疑問点
本照会事例には、「個人事業者が所有するゴルフ会員権はそもそもが事業用ではなく、生活用資産である。」という固定概念があるようだ。しかし、この考え方からすれば、個人事業者が取引先との接待ゴルフのためにゴルフ会員権を取得した場合には、そのゴルフ会員権は全額が仕入税額控除の対象とすることはできないことになってしまう。
個人事業者が家事共用資産を取得した場合には、使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により課税仕入れに係る支払対価の額を計算することとされている(消基通11−1−4)。よって、事業用にも使用する目的でゴルフ会員権を取得した場合には、事業使用割合を合理的に見積もって、事業用部分は課税仕入れとして取り扱うべきである。そうすると、事業用と家事用に兼用していたゴルフ会員権を譲渡した場合にも、その譲渡対価を合理的に区分したうえで、事業用の部分(対価)を課税の対象に取り込むことになろう(消基通10−1−19)。
ところで、ゴルフ会員権のような資産の場合には、事業使用割合が年によって異なることがあり、上記通達に定める「合理的に区分する方法」が、必ずしも明らかにされていないのが実情である。
この点について、「平成30年版 消費税法基本通達逐条解説616頁・大蔵財務協会」では、「家事共用資産を譲渡した場合の譲渡対価の区分については、譲渡時の使用割合ではなく、原則として当該資産の取得時の区分による」との解説がされている。
この取扱いは、仕入税額控除の対象とした部分を譲渡時に課税し、帳尻を合わせるという発想なのだと思われる。そうすると、例えば取得時の使用割合が10%、譲渡時の使用割合が100%の資産であっても、譲渡対価の10%だけを売上高にカウントすればよいということになる。また、これとは逆に、取得時の使用割合が100%で、譲渡時の使用割合が10%の資産は、譲渡対価の全額を売上高に計上しなければいけないことになってしまう。
このような取扱いは、法令や通達からはいっさい読み取ることができない。よって、私見としては、家事共用資産を譲渡した場合には、取得時の使用割合ではなく、譲渡時の使用割合により、譲渡対価をあん分するべきではないかと考えている。
2 インボイスとの関係
(1)家事共用資産の譲渡
個人事業者が家事共用資産を譲渡する場合には、事業用部分を合理的に区分したうえで、事業用部分の取引金額を基にインボイスに記載すべき金額等を計算することとされている(インボイス通達3−4)。
<計算例>
事業共用割合が90%の中古車両を20万円で売却する場合には、適格請求書に記載すべき金額は次のように計算する。
200,000円×90%=180,000円
180,000円×10/110≒16,363円
この場合に発行するインボイスとしては、右のような雛形になるものと思われる。
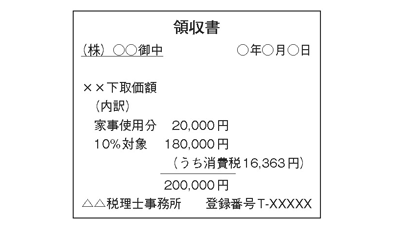
ところで、古物商(中古車買取業者など)が適格請求書発行事業者でない他の者から買い受けた販売用の古物(中古自動車)については、帳簿の保存のみにより、仕入税額控除を認めることとしている(消令49①一ハ(1))。上記の<計算例>は、適格請求書発行事業者である個人事業者が課税資産を譲渡するのでこの取扱いはない。結果、中古車買取業者は、下取先が適格請求書発行事業者かどうかを買い取りの都度確認しなければいけないことになるのであろうか?
また、中古資産を売却するような場合には、要求されなければインボイスを発行しないこともあろうかと思われるので、現実の実務においては、適格請求書発行事業者かどうかに関係なく、仕入税額控除を認めるような取扱いが必要ではないかと思われる。
(2)家事共用資産の取得
個人事業者が家事共用資産を取得した場合には、使用率、使用面積割合等の合理的な基準により消費税額又は課税仕入高を区分したうえで、事業用部分だけが仕入控除税額の計算に取り込まれることとなる(インボイス通達4−1)。
<計算例>
車両を220万円(うち消費税20万円)で取得した場合の課税仕入れ等の税額は次のように計算する(事業共用割合90%)。
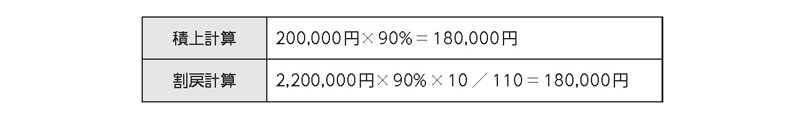
Ⅲ 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係(資産の譲渡の範囲 5)
【照会要旨】
個人事業者が所有する資産で、事業と家事の用途に共通して使用されるものを売却した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
(例)
1.店舗兼住宅の1階部分を店舗又は工場に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物
2.昼は事業用、夜は家庭用として使用している電話に係る電話加入権
なお、所得税法の計算上は、家事関連費であっても業務の遂行上必要であること等の一定の要件に該当するものについては、必要経費に算入されます(所法45、所令96)。
【回答要旨】
事業と家事の用途に共通して使用される資産であっても、譲渡すれば事業用の部分については課税の対象となります(按分)。
ただし、例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。
1 解説と疑問点
(例)の1.については、次頁のように計算することになる。
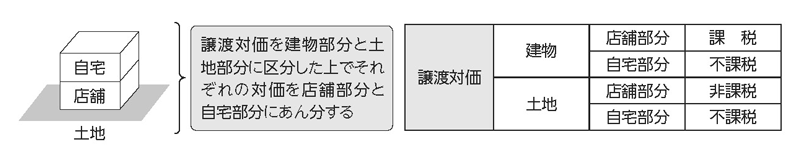
<計算例>
個人事業者が、2階建の店舗兼用住宅を4,400万円で取得し、1階を店舗、2階を住居として使用する場合の課税仕入れに係る支払対価の額は次のように計算する。
なお、床面積は、1階の店舗部分が120㎡、2階の住居部分が80㎡、玄関や廊下などの共用部分が20㎡となっている(延床面積220㎡)。
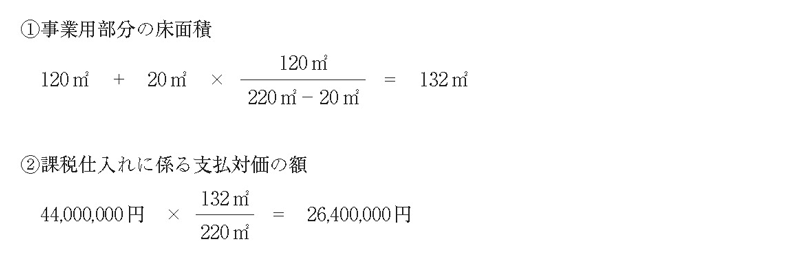
(例)の2.については、電話加入権の売却代金の全額が課税の対象となる根拠を国税庁に問いたい。昼は事業用で夜は家庭用ということなので、「基本的に事業用資産である」という前提での説明なのだと思われるが、個人事業者の実務については、昼にプライベートな電話がかかってくることもあり、夜中に仕事の電話がかかってくることもある。「昼はどうで夜はこう」などといった杓子定規的な判断はできないのである。
「個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡(資産の譲渡の範囲3)」でも解説したように、電話加入権の譲渡時における使用割合、すなわち、所得税の申告における電話使用料金の必要経費への算入割合を電話加入権の売却金額に乗ずることにより、課税の対象となる事業用の譲渡対価を算出すればよいものと思われる。
2 インボイスとの関係
個人事業者が家事共用資産を取得した場合には、使用率、使用面積割合等の合理的な基準により消費税額又は課税仕入高を区分したうえで、事業用部分だけが仕入控除税額の計算に取り込まれることとなる(インボイス通達4−1)。よって、(例)の1.については、交付されたインボイスの保存を条件に、上記<計算例>により計算した金額を仕入控除税額の計算に取り込むことができる。
(例)の2.については、【回答要旨】には電話代の取扱いが書かれていないものの、所得税法施行令96条(家事関連費)に掲げる経費については、消費税においても課税仕入れとして処理することが認められている(消基通11−1−5)。よって、NTTなどの通信会社から交付されたインボイスに記載された電話代を合理的な基準により区分した上で、事業用部分だけが仕入控除税額の計算に取り込まれることとなる。
3 個人名義の経費を法人の損金に計上した場合の取扱い
自宅と会社が兼用となっている同族法人などでは、自宅の電話代や水道代などの一部を会社の経費として計上していることがある。このようなケースでは、個人から法人へ立替金精算書を発行することにより、法人サイドで仕入税額控除ができるものと思われる(インボイス通達4−2、インボイスQ&A問92)。
ところで、自動車保険が安いなどの理由で個人名義で自動車を購入し、法人で資産計上して減価償却費を損金計上しているようなケースでは、個人名義の自動車の購入費は仕入税額控除の対象とすることができるのであろうか?
減価償却費相当額については、法人から個人への車両の賃借料と認識すれば、損金処理も可能ではないかと思われる(個人は減価償却費相当額で賃貸したこととなるので所得は発生しない)。
また、個人名義でなければ入会できないような規約のあるゴルフ場の会員権などであれば、個人名義でも会費は法人の損金として何ら問題はない。ただ、このような個人名義のゴルフ会員権を法人の資産として計上したからといって、消費税の世界で仕入税額控除の対象とすることができるのであろうか……?
私見ではあるが、個人名義の資産を取得した際に、立替金の精算という理屈は通じないように思えるのである……。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























