解説記事2023年12月18日 SCOPE 固定資産税の負担調整措置は令和8年度まで存続決定(2023年12月18日号・№1007)
土地取得に係る不動産取得税の特例も3年延長
固定資産税の負担調整措置は令和8年度まで存続決定
令和6年度は固定資産税の評価替えの年となっているが、与党の税制調査会は、宅地等及び農地の負担調整措置については、令和6年度から令和8年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続することを決めた。また、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置等の適用期限も3年間延長する。
条例減額制度も含め令和8年度まで延長
令和6年度は固定資産税の評価替えの年にあたるが、令和6年度税制改正では、土地に係る固定資産税等の負担調整措置(税負担急増土地に係る条例減額制度及び商業地等に係る条例減額制度を含む)については、令和8年度まで3年間適用期限が延長される。
現行、固定資産税については、商業地等について、負担水準(=前年度の課税標準額÷今年度の評価額)をもとに、今年度課税標準額を決定し、評価替えによる価格の上昇に伴う税負担を調整する措置が講じられている。例えば、負担水準が70%以上の場合は、今年度の評価額の70%に引き下げ、負担水準が60%以上70%未満の場合には、前年度課税標準額と同額に据え置かれることになる。また、地方公共団体の条例により課税標準額の上限を評価額の60~70%未満の範囲で定める値に引き下げることなどができる条例減額制度が設けられている。ただ、令和6年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年にあたり、現行の負担調整措置及び条例減額制度が存続するかどうか注目されていた。
この点、令和6年度評価替えに係る地価の状況を見ると、大都市を中心とした地価上昇と地方における地価下落が混在する状況が継続しており、今回の評価替えにおいては、大都市を中心に、引き続き負担水準が据置きゾーンを下回る土地が生ずるなど負担水準のばらついた状態が続くことが見込まれている。このため、税負担の公平性等の観点から、現行の負担調整措置を継続することにより、まずはこのような土地の負担水準を据置きゾーン内に再び収斂させることが必要と判断したものだ。
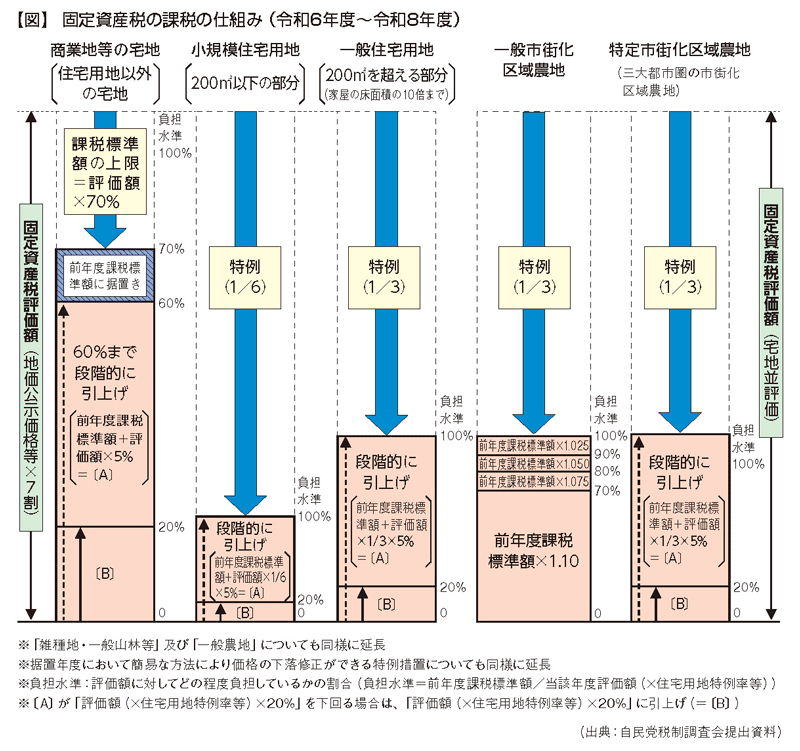
また、併せて住宅及び土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例(本則4%から3%)及び宅地評価土地(住宅用地・商業地等)に係る不動産取得税の課税標準の特例(評価額を2分の1に圧縮)も令和9年3月31日まで3年間延長する。土地の購入者の多くは個人や資本金1億円未満の中小企業であり、特例措置による負担軽減効果が大きいほか、取得時の負担を軽減することで土地等に対する需要を喚起するとしている。
不動産関係の税制措置は軒並み期限延長、居住用財産の買換え特例は2年間
国土交通省などが要望していた不動産関係の税制措置については軒並み適用期限が延長されることになった。住宅価格の高騰により住宅取得環境が悪化していることなどを踏まえたもの。例えば、①新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置、②既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修に係る固定資産税の減額措置、③新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、令和8年3月31日まで2年間延長される。また、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度についても令和7年12月31日まで2年間延長されることになった。そのほか、工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置については、令和9年3月31日まで3年間延長されることになっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























