解説記事2024年06月03日 特別解説 IFRS第17号「保険契約」の適用(2024年6月3日号・№1029)
特別解説
IFRS第17号「保険契約」の適用
はじめに
IFRS第17号「保険契約」が2023年1月1日以後に開始する事業年度から適用開始された(3月決算の企業の場合には、2024年3月期から適用開始)。IASB(国際会計基準審議会)の前身であるIASC(国際会計基準委員会)で保険会計のプロジェクトが開始されたのが1997年であることから、最終的な基準の適用開始まで、実に四半世紀以上の期間を要したことになる。
いわゆる「会計ビッグバン」以降の動きを見ても分かるように、極めて流れが速い会計基準策定の世界において、この検討期間の長さは極めて異例であり、それだけ、この保険契約や保険業界という世界が特殊かつ複雑で、関係する利害関係者の合意を得ることが困難であったことを物語っているといえよう。
IFRS第4号とIFRS第17号
IFRS第17号が公表される以前、保険契約についてはIFRS第4号という基準書(2004年3月公表)が存在していた。
しかしながらこの基準書は、標題とは相違して保険契約の会計処理を具体的に示す完全な基準書ではなかった。公表された時期からも推察されるように、EUにおける2005年からのIFRS強制適用開始に間に合わせるための「仮の基準書」という位置づけであったと言える。IFRS第4号の目的は、完全な保険契約に係る会計基準ができるまで、保険契約に関する会計について、限定的な改善を加えるものの、保険負債の計測など重要な部分については、現行の実務を継続することをIFRSにおいて認めることを明確にするためのものであった。
IFRS第4号の大きな特徴は第13項(他のIFRSからの一時的な適用除外)にある。すなわち、
IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の第10項から第12項は、ある会計項目に具体的に適用すべきIFRSが存在しない場合に、企業が当該会計項目に関する会計方針を策定する際に用いるべき要件を明記している。しかし、本基準では、保険者に対して、次に関する既存の会計方針については、そのような要件の適用を免除している。
(a)保険者が自ら発行した保険契約(第31項及び第32項に記載するような、関連する新契約費及び無形資産を含む)
(b)保険者が保有する再保険契約
その結果、保険者はIFRS第4号を遵守していれば、各企業がそれぞれの法域で利用していた会計基準をほぼそのまま適用して、しかも、それをIFRSに従って作成した財務諸表であるとして対外公表できるようになっていた。これは、本来のIFRSの目的からは大きくかけ離れた妥協であったといえよう。このことは、IFRS第4号の公表を承認する際の議決に加わったIASBのメンバー14名のうち、実に6名ものメンバーが反対票を投じていることからも伺える。14名中8名の賛成というのは、公開草案、基準及び解釈指針を可決できる最低ラインであり、それだけ、IFRS第4号の議決公表は、IASBにとって不本意であったことが分かる。
IFRS第4号がこのような、「欧州におけるIFRSの2005年からの一斉適用を最優先として問題を先送りしたに過ぎない仮の基準」であったことはほぼすべての関係者が認め、理解していたにもかかわらず、「正式な基準書」であるIFRS第17号が公表されるまでにはそれからさらに13年、適用開始までには20年近い年月が必要とされた。
保険業の会計とIFRS第17号のアプローチ
保険会社は免許事業であり、多くの法域における保険業会計の目的は、企業の期間業績を表すことに重点が置かれているのではなく、ソルベンシー・マージン比率といった指標に代表されるように、保険会社が保険契約者に対して約束した保険金を支払う能力を担保しているかを、監督当局等が確認することにあった。そして、そのような支払い能力を担保するための法律や規制が法域によって異なるために、保険会計もそれに合わせて法域によって異なるローカル色の強いものにならざるを得なかった。こういった事情の積み重ねによって、保険会社の財務諸表は地域間の比較も、他業種との比較もできないものとして、個別の発展を遂げることとなったと考えられる。
我が国において保険業は財務諸表等規則の別記に掲げられているいわゆる「別記事業」であり、保険業法等に基づく財務諸表による開示をもって金融商品取引法上の開示として認められている。一般に保険会社に投資する投資家は、保険会社同士の比較はするものの、保険会社とそれ以外の業界に属する企業とを比較して投資判断をすることはあまりないと考えられていたからであると考えられる。
これに対し、IFRSは「情報提供を企業に対して直接要求することが出来ず、必要とする財務情報の多くを一般目的財務諸表に依拠しなければならない者」を一般目的財務諸表の主要な利用者として想定し、そのような利用者の意思決定に資するように会計基準が策定されている。また、よく知られているように、IFRSはすべての法域のすべての産業分野に属する企業が適用できるように基準が出来ており、特定の業種を想定した解釈指針やガイドライン、例外規定等は極力排除されている。すなわち、IFRSでは、保険業に限らず、一般の企業が保険契約の定義を満たすものを保有していれば、どのような会計基準を適用するのが妥当であろうか、という発想を基に基準が構築されている。
このように、IFRSが目指す方向性と、従来の保険業の会計が指向してきた方向性は正反対といってもよいくらい異なっている。この隔たりを埋めるために、四半世紀近い時間が費やされたのだとも言えよう。
次項では、IFRS第17号の考え方やこれまでの我が国の伝統的な保険会計との相違点等を中心に、特徴的な会計処理等をみていくこととしたい。
IFRS第17号の特徴的な会計処理
わが国の伝統的な保険会計では、保険契約者が死亡して保険金が支払われるか、満期が来て保険金の支払いがないと確定して初めて純利益が計上できる仕組みとなっている。このような仕組みとなっている理由は、会計の目的が保険契約者を保護することを目的とした規制監督会計と親和的であるためである。保険契約者を保護する観点からは、確定していない利益を見積りに基づいて計上することは健全ではないと考えられ、発生主義会計に基づいて保険会社の期間業績を把握することよりも、保険契約者の保護が優先されることになる。
一方IFRS第17号は、保険会社の期間業績を他の産業分野の一般の企業と同じコンセプトで計測しようとしており、比較可能性を重視している。計測の方法を検討するにあたってIASBは、計測の対象期間に保険金の支払いや満期の到来が全くなかったとしても、その期間に保険会社が何もしていなかったわけではなく、いつでも保険金を支払える状態で待機しているというサービスを行っていると考えて、そのサービスの提供に応じて利益の計上が可能となる、契約上のサービスマージン(CSM)という仕組みを作った。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」における、履行義務の充足に伴って収益を認識するという原則に基づいたもので、これにより、保険会社の期間業績について、一般の企業との比較可能性がもたらされることになる。なお、CSMは契約を開始する当初時点で保険会社が見積っている利益に基づいて計測され、それがカバー期間にわたって償却される。
次に、保険収益(グロス)については、我が国の伝統的な保険会計では、原則として保険料の受け取りを、現金主義の考え方で、そのまま保険収益(グロス)として計上する。一方、IFRS第17号では、我が国のように保険料の受け取りを保険収益(グロス)として計上するのではなく、保険料の支払いがなければ、CSMの償却額がそのまま保険収益(グロス)になる。保険料の支払いがあった場合には、保険会社の活動の規模感を示すために、保険料支払額を収益と費用に同額計上する。
また、わが国の伝統的な保険会計の場合は、当初に想定した死亡率や金利の変動等が事後的にあったとしても、それに応じて保険負債を再測定することがないのに対して、IFRS第17号では、毎期基礎率を見直して保険負債を再測定(事後測定)し、その差額を主に純損益に反映させるという違いがある。
例えば、死亡率が事後的に変動した場合、IFRS第17号では最新の死亡率に基づいて将来キャッシュ・フローを測定するとともに、生じた差額をCSMで調整する。死亡率が契約獲得時に想定していたものよりも低下した場合にはCSMの金額が増加し(償却して計上される保険収益の額も増加する)、上昇した場合にはCSMの金額と保険収益の額が減少することになる。
また、金利が変動した場合には、金利の変動によって変化した将来キャッシュ・フローについては、CSMで調整することは行われずに、会計方針の選択によって純損益又はその他の包括利益に反映される(金利が低下した場合には損失の方向、上昇した場合には利益の方向となる)。
このようにしてみていくと、IFRS第17号が保険会社に与える影響は非常に大きいことが分かる。特に金利変動が保険負債に与える影響を毎期の損益として認識することは、経営上大きな影響があると考えられる。
我が国企業の開示(楽天、ライフネット生命保険)
わが国で保険業務を大規模に展開しているIFRS任意適用企業は、楽天(12月決算)とライフネット生命保険(3月決算)である。楽天が2024年3月28日付で公表した有価証券報告書では、以下の6つの区分に分けてIFRS第17号に基づく会計方針が記載されているが、合計すると5ページ分ほどあるため、見出しの紹介のみにとどめることとしたい。
【楽天の有価証券報告書の保険契約に係る重要な会計方針(会計方針の変更)の見出し】
(1)保険契約の分類及び集約
(2)保険契約の認識及び測定
① 保険料配分アプローチ(PAA)を適用せずに測定している保険契約の当初測定
a. 履行キャッシュ・フロー
b. 契約上のサービス・マージン(CSM)
② PAAを適用せずに測定している保険契約の事後測定
a. 履行キャッシュ・フロー
b. CSM
(3)契約の境界線
(4)PAAの適用
(5)表示
① 保険収益
a. PAAを適用せずに測定している契約
b. PAAを適用して測定する契約
② 保険サービス費用
③ 損失要素
④ 保険金融収益又は費用
(6)経過措置
なお、楽天の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、IFRS第17号の新規適用をKAMとはしなかった。
ライフネット生命保険は2022年4月1日からIFRSに移行し、2023年8月14日に公表した四半期報告書において、IFRS第17号に基づく開示をはじめて実施した。これも楽天と同様に、重要な会計方針は保険契約に関連する部分だけで6ページにわたる。本稿では、IFRSの初度適用において開示が求められる調整表における開示(日本基準とIFRSとの相違点が開示される)の一部(「保険収益及び保険サービス費用」の部分のみ)を抜粋して紹介することとしたい。
【ライフネット生命保険の四半期報告書における開示】
(保険収益及び保険サービス費用)
日本基準において、保険料及び保険料等支払金については、保険業法及び保険業法施行規則に基づき、以下のとおり計上しています。
・保険料
契約応当日が到来している契約のうち、保険料の収納があったものについて、当該金額により計上。
・保険料等支払金
保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上。
IFRSでは、保険契約に基づいてカバーを提供するにつれて、保険契約グループごとに保険収益を認識しています。
保険約款に基づき支払事由が発生している保険金請求金額(まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生していると認められるものを含む)及び発生したその他の関連費用を保険サービス費用として認識しています。
また、当社グループは、保険料のうちの契約獲得キャッシュ・フローの回収に関連する部分を、時の経過に基づいて規則的な方法で各期間に配分しています。当社グループは、配分した金額を保険収益として認識し、同額を保険サービス費用として認識しています。
欧州の保険会社の監査報告書における監査上の主要な検討事項(KAM)の開示
12月決算が多い欧州の保険会社は、2023年度のアニュアル・レポートの公表が終わり、IFRS第17号に基づく情報開示も出揃った。保険会社の監査を実施する会計監査人にとっても、2023年度の監査は特別な対応や追加的な監査手続の実施を迫られたに違いない。
本稿では最後に、各社の監査報告書に記載された監査上の主要な検討事項(KAM)の項目を列挙するとともに、会計監査人の対応の一部を紹介することとしたい。
欧州の主要な保険会社と、監査報告書においてKAMとして記載された標題の一覧は表のとおりである。なお、欧州の主要な保険会社は、FTSE100の構成銘柄に選定されている企業(英国の企業が中心)とSTOXX600の構成銘柄に選定されている企業(独仏等、欧州大陸の企業が中心)から抽出した。なお、KAMは、IFRS第17号という用語やIFRS第17号における特有の用語が含まれている項目のみを抽出しており、「保険負債の評価」といった一般的な標題のKAMにもIFRS第17号に対する対応が記載されていることにご留意頂きたい。
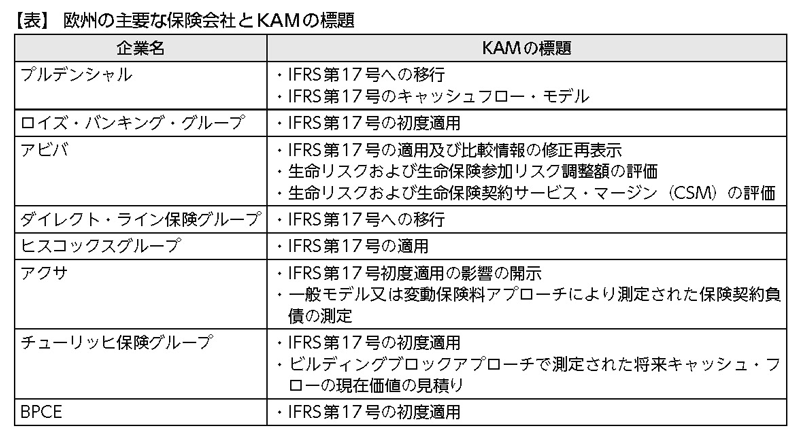
本稿では、アビバ(Aviva)社の監査報告書に記載されたKAMのうち、「生命リスク及び生命保険契約サービス・マージンの評価」のリスクの内容と監査上の対応を和訳して紹介することとしたい。
(リスクの内容)
CSM(Contractual Service Margin)は、一般的測定モデルにより測定される保険契約グループの資産または負債の帳簿価額の構成要素であり、当グループが将来保険契約サービスを提供する際に認識する前受収益である。
CSMエンジンは複雑な計算と微妙な前提条件によって計算されており、手作業による調整と相まって計算の誤謬のリスクを高めている。
特に、当グループがリスクを特定した主な分野は以下の通りである:
・CSM計算エンジンにおける経営者の方法論の適用、および
・経営者が計算結果に対して行う手作業による調整。
(監査上の対応)
生命リスクと生命保険契約CSMの評価に関して、当法人は以下の手続を実施した。
−プロセスおよび適用されている内部統制の整備と適用状況について理解し、評価した。
これには、適用されている関連する内部統制の整備および運用の有効性、ならびに使用されたデータの完全性および正確性のテストが含まれる。
−独立したCSMモデルにより作成されたものとアウトプットサンプルを比較することにより、CSM計算エンジンの正確性及び経営者の判断の適用を検証した。
−2023年12月31日現在のCSMの算定に使用したモデルの正確性に関する経営者のテストについて、監査手続を実施して検証した。
−経営者が行った手作業による調整について、監査手続を実施して検証した。
−再実施および独立した監査手続を通じて、CSM評価に関する経営者の主要なレビュー統制に対して監査手続を実施して検証した。
実施した監査手続および入手した証拠に基づき、当監査法人は参加型CSMが適切であると判断した。
終わりに
本稿の前段部分でも紹介したとおり、IFRS第17号は、従来からの保険契約者保護・当局による監督のための会計と、一般投資者を主要な利用者として想定し、異業種間の企業比較を重視した会計とを融合させるという大きなチャレンジを行った基準書である。本稿ではごく一部しか取り上げられなかったが、これまでの保険会計のルールを大きく変更する可能性がある革新的な規定が数多く盛り込まれている。
欧州の保険会社では、すでにIFRS第17号適用2年目に入っているが、保険会社の財務諸表の作成者、会計監査人の双方ともに、適用初年度の経験や知見を活かして、実務を改善してゆくものと思われる。
本稿の前段でもたびたび引用させて頂いたが、これまで保険会計にほとんどなじみがなかった筆者にとって、IFRS第17号の基準作成に直接携わられた鶯地氏の手による解説記事は大変分かりやすく、有用であった(「参考文献」を参照)。基準書の条項を逐一説明するのではなく、保険会計の特徴をその成り立ちから説き起こした内容は大変興味深く、理解が深まったと感じている。また、IFRSを適用することによって、このようなチャレンジングな基準書の適用にあえて挑んだライフネット生命保険や楽天の関係者各位にも改めて敬意を表したい。
参考文献
鶯地隆継 国際会計基準(IFRS)−つくり手の狙いと監査 第32回~第38回(有限責任監査法人トーマツ「会計情報」2023年3月号~2023年12月号)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























