解説記事2024年09月09日 実務解説 半期報告書 作成上の留意点半期報告書(2024年9月期提出用)(2024年9月9日号・№1042)
実務解説
半期報告書 作成上の留意点半期報告書(2024年9月期提出用)
(前)企業会計基準委員会 専門研究員 傳田陽一
《まとめ》
・四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備を行うため、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正が行われている。当該改正は、従来の第2四半期報告書と半期報告書が同程度の記載内容となることを方針としている。
・「中間財務諸表に関する会計基準」等は、改正後の金融商品取引法の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用するとされている。比較情報や会計方針の変更等について留意が必要である。
・改正「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用とされている。一部については適用初年度の経過措置がある。
・このほか、「期中レビュー報告書」、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」についても留意が必要である。
Ⅰ はじめに
本稿は、2024年9月期の半期報告書における作成上の留意点についてまとめたものであり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)の改正に伴う留意点、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から改正・公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説する。
なお、文中において意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えておく。
Ⅱ 令和5年金融商品取引法改正に伴う内閣府令の改正に係る留意点
令和5年金融商品取引法改正に伴い、四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備を行うため、開示府令の改正が行なわれており、2024年4月1日から施行されている。
当該改正は、従来の第2四半期報告書と半期報告書が同程度の記載内容となることを方針としており、四半期報告書の様式(第4号の3様式)については、四半期に係る財務情報の開示を不要とする等の所要の改正を行った上で、上場会社等(銀行等の特定事業会社を含む)が提出する半期報告書の様式に改正されている。
また、四半期に関連する規則やガイドラインは第1、第3四半期特有のものを除いて、基本的に内容を変えずに、四半期を中間という用語に変更した上で、第1種中間連結財務諸表、第1種中間財務諸表として、連結財規や財規、連結財規ガイドライン、財規ガイドラインなどに集約される形で改正が行われている。
Ⅲ 中間財務諸表に関する会計基準等に係る留意点
(1)概要
ASBJは、2024年3月に企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「中間会計基準」という。)等を公表している。中間会計基準等は、改正後の金融商品取引法の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用することとされている。
中間会計基準等においては、中間財務諸表の記載内容が従前の第2四半期報告書と同程度の記載内容となるように、基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継いでいる。四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合と、期首から6か月間を1つの会計期間、すなわち中間会計期間とした場合とで差異が生じる可能性がある項目については、企業の実務負担が生じないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱いを定めている。その詳細は、山田正顕「企業会計基準第33号『中間財務諸表に関する会計基準』等の概要」(No.1029)を参照いただきたい。
(2)2024年9月期の半期報告書に関するポイント
① 比較情報
中間会計基準等において基本的に四半期会計基準の会計処理を継続することが可能となるため、前第2四半期連結累計期間と同一の会計処理を継続していれば、前第2四半期連結累計期間の情報を修正することなく比較情報として記載することが可能である。
② 会計方針の変更等
中間会計基準等の適用初年度においては、従来作成していた四半期財務諸表とは異なる種類の中間財務諸表を新たに作成することになると考えられるため、従前の四半期財務諸表において採用していた会計方針と異なる会計方針を採用した場合であっても、それが年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針でないものであれば、会計方針の変更には該当しないと考えられる。
なお、その場合、開示対象期間の中間財務諸表等について遡及適用することとされており、当中間連結会計期間への影響が大きい場合には、会計方針の変更に関する注記に準じて税金等調整前中間純損益金額に対する前中間連結会計期間における影響額などを追加情報として記載することが考えられる。
Ⅳ 2022年改正「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等に係る留意点
(1)概要
ASBJは、2022年10月28日に企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)の3つの会計基準等を改正している。
この改正により税引前当期純利益と税金費用の対応関係を図る目的で、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとされた。また、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いに関する改正として、グループ法人税制が適用される場合で、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い売却元企業で生じた売却損益を税務上繰り延べたことで繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合に、当該売却に係る連結財務諸表上の税引前当期純利益と税金費用との対応関係の改善を図る観点から、連結決算手続上、当該繰延税金資産又は繰延税金負債を消去することとされた。
適用時期は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用とされている。その詳細は、花澤徳裕「改正企業会計基準第27号『法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準』等の概要」(No.961)を参照いただきたい。
(2)主要な経営指標等の推移
「第1 企業の概況」の「主要な経営指標の推移」について、記載事例1に記載している。
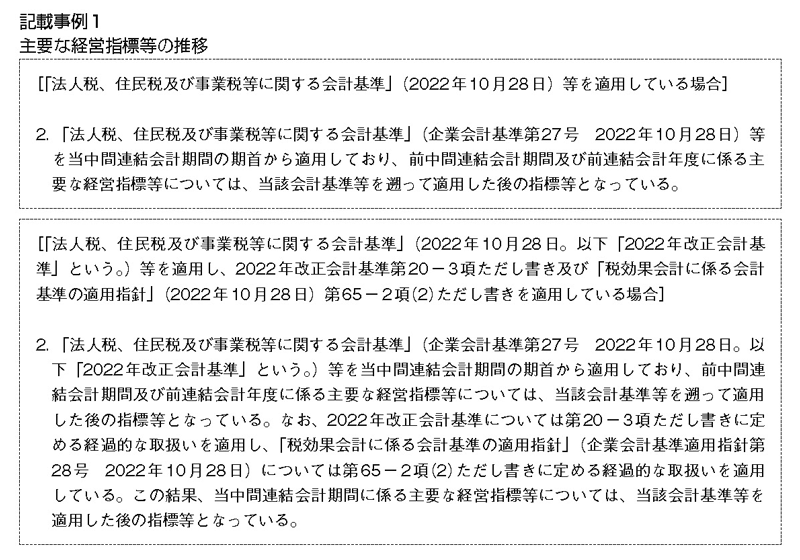
今回改正された法人税等会計基準等は、遡及適用に関して、経過的な取扱いが認められている。そのため、全て遡及適用を行う場合の記載事例を上段に、経過的な取扱いを行った場合の記載事例を下段に記載している。経過的な取扱いを適用している下段の記載事例については、4行目の「なお、」以降に経過的な取扱いについて具体的に記載している。
(3)会計方針の変更に関する注記
法人税等会計基準等を適用し、法人税等会計基準の第20−3項ただし書きに定める経過的な取扱い、及び税効果適用指針の第65−2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを適用する場合について記載事例2に記載している。
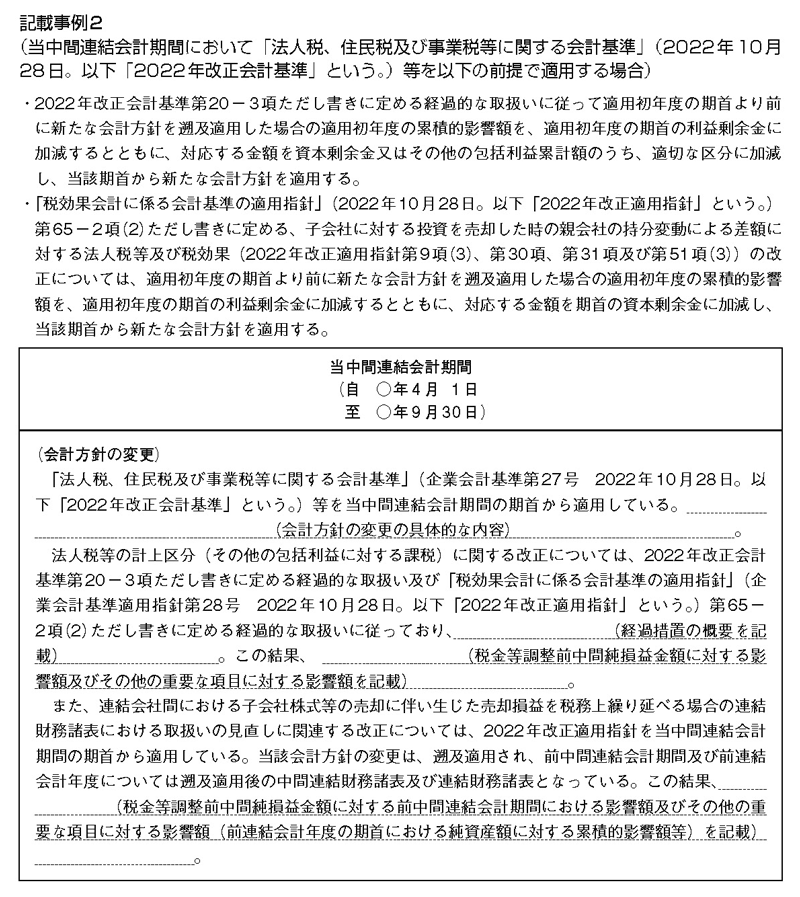
今回の会計方針の変更の記載事例は、会計基準等の改正等に伴うものであり、連結財規第102条、財規第131条を準用に基づいて注記を行っている。
記載事例2では、冒頭に該当する会計基準等の名称(法人税等会計基準等)を適用していることを明記した後、カッコに記載しているとおり、会計方針の変更の具体的な内容を記載するようにしている。続いて、経過措置に従って会計処理を行った旨を記載し、その後、経過措置の概要を記載、そして、「この結果」の箇所に、税金等調整前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額を記載することを想定している。
なお、「連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正」については、税効果適用指針において経過的な取扱いが定められていないため、「また」に続く箇所で、税金等調整前中間純損益金額に対する前中間連結会計期間における影響額やその他重要な項目に対する影響額を記載している。
記載事例のカッコ書きの記載は、連結財規等に定められている記載すべき事項を記載しているものであり、各企業の状況を踏まえ、記載することになると考えられる。
Ⅴ 期中レビュー報告書に係る留意点
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)から、2024年3月に四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」が改正され、期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」が公表されている。
これに伴い、レビュー報告書については、報告書の名称の変更や用語の置換えなどが行われている。
Ⅵ その他の留意点
(1)「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等に係る留意点
2024年3月22日にASBJから実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等が公表された。当該実務対応報告は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされている。その詳細は、大竹勇輝「実務対応報告第46号『グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い』等の概要」(No.1028)を参照いただきたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























