解説記事2025年02月24日 第2特集 複合構造家屋の固定資産評価、地方自治体の低層階方式は適法(2025年2月24日号・№1064)
第2特集
最高裁、床面積方式とすべきとの納税者の主張を斥ける
複合構造家屋の固定資産評価、地方自治体の低層階方式は適法
ホテルなど、低層階と高層階の構造が異なる複合構造家屋の固定資産の評価を巡る3件の裁判で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は令和7年2月17日、地方自治体が採用した低層階方式は固定資産評価基準上許容されるとの判断を示し、納税者の主張を斥けた。
裁判では、納税者は床面積方式により評価すべきと主張。原審の高裁レベルでは判断が分かれていたが、最高裁は、複合構造家屋であっても、使用に耐えなくなったものとしてこれを取り壊すかどうかについては、基本的に一棟単位で判断されることになるため、低層階を構成する構造のうち所定経過年数の最も長いものに応じた経年減点補正率によることも合理性を欠くものとはいえないとした。
現在、多くの地方自治体においては、複合構造家屋の評価は低層階方式ではなく、床面積方式が採用されている。今回の裁判の対象となった大阪市及び広島市も例外ではないだけに、当事者の納税者だけでなく、同市内で以前から複合構造家屋を所有する納税者にとっては非常に酷な判決となった。
低層階は鉄骨鉄筋コンクリート造で、それ以外は鉄骨造の複合構造家屋
本件は、家屋の所有者であり固定資産税の納税義務者である大手金融機関が、家屋課税台帳に登録された平成30年度の価格に不服があるとして、固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、棄却する等の決定を受けたことから、訴訟に至ったもの。今回の最高裁では、同じ大手金融機関が大阪市を相手取った2件(事件①及び②)及び広島市(事件③)を相手取った1件の訴訟で判決が言い渡された。
問題となったのは、いずれの家屋もホテルやオフィスビルとなっている複合構造家屋であり、低層階が鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であり、それ以外が鉄骨造(S造)となっている。地方自治体側は、低層階方式に従い、低層階を構成するSRC造に係る構造別区分の経年減点補正率によって家屋を評価。一方、大手金融機関は、低層階方式ではなく、床面積方式に従いS造に係る構造別区分の経年減点補正率を適用すべきとしている。
なお、低層階方式とは、家屋自体の荷重を支え基礎と一体となっている地下階又は低層階を構成する最も耐用年数の長い構造をもって主たる構造ととらえ、これに対応した経年減点補正率を適用する方法のこと。また、床面積方式とは、家屋を占める最も大きな床面積割合を占める構造をもって主たる構造と捉え、これに対応した経年減点補正率を適用する方法のことである。
同じ築年数でも評価額はSRC造が一番同じ築年数でも評価額はSRC造が一番
固定資産評価基準は、非木造家屋の評点数は非木造家屋の再建築費評点数を基礎として、これに損耗の状況による減点補正率を乗じて付設するものとした上で、非木造家屋の損耗の状況による減点補正率は、原則として経過年数に応ずる減点補正率(経年減点補正率)によるものとされている。経年減点補正率は、通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定めたものであって、非木造家屋の構造区分に従い、非木造家屋経年減点補正率基準表に示されている非木造家屋の経年減点補正率によって求めることになる。
なお、同基準表は、家屋の用途の別に従い、①鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造(SRC造等)、②煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造、③鉄骨造(S造)(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの)、④S造(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの)、⑤S造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの)の5つの構造別区分ごとに、それぞれ経過年数に応じた経年減点補正率が定められている。耐用年数は①の構造が一番長く、⑤の構造が一番短く設定されている。このため、同じ築年数であっても、再建築評点数に乗じる経年減点補正率が異なることになる。例えば、S造よりも、SRC造と判定された場合の方が減価の程度が小さくなるため、評価額はSRC造の方が高くなり、当然のことながら固定資産税も高くなる。
高裁判決では判断が分かれる
原審の高裁の判断は分かれている(次頁表参照)。令和4年12月13日の大阪高裁判決(令和4(行コ)66)(事件①)及び令和5年3月9日の広島高裁判決(令和3(行コ)17)(事件③)は、床面積方式により評価すべきとの判断を示し、納税者(大手金融機関)が勝訴。一方、令和5年1月26日の大阪高裁判決(令和4(行コ)67)(事件②)は、低層階方式に一般的合理性があると判断し、納税者が敗訴している。
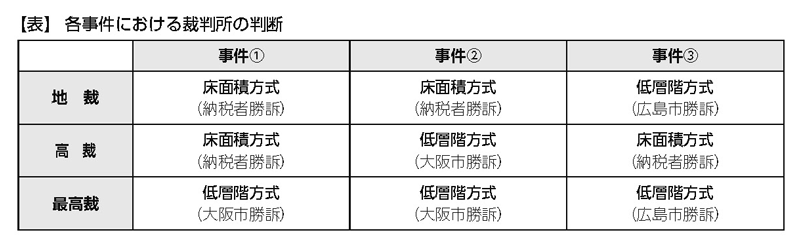
例えば、納税者が勝訴した大阪高裁判決(事件①)では、低層階方式は、構造ごとの構造耐力に応じた各構造の損傷、損耗等による価値減少を、減価補正の程度に可能な限り反映するものとはいえず、経年減点補正率に係る評価基準の定めの内容、趣旨に沿ったものとはいえないとしたほか、大阪市は、平成18年改正の固定資産評価実施要領によって、大阪市に所在する複合構造家屋に適用する経年減点補正率の求め方を、基本的に床面積方式に統一しているにもかかわらず、本件各建物と、床面積方式を採用した複合構造家屋との間で、経年減点補正率の求め方に関して異なる取扱いをし、かつ、平成18年改正の下においても継続したことは、大阪市内における評価の統一性の要請からみて、もはや合理的とは言えないとの判断を示していた。
一方、地方自治体が勝訴した大阪高裁判決(事件②)では、高層建築物等の複合構造家屋について、家屋の荷重を支える低層階の構造部分が維持されている限りは、上層階部分については構造体以外の外装、窓といった建物各部分について補修等で対応することにより、建物一棟全体の存続を図ることが可能であり、低層階の構造部分が傷んだ場合に家屋全体を取り壊すのが一般的であることなどから、低層階方式に一般的な合理性があるとの判断を示している。
最高裁、建物を取り壊すかどうかは一棟単位で判断
最高裁は、固定資産評価基準は非木造家屋の評価に当たり適用すべき経年減点補正率につき、非木造家屋の構造区分に従い、非木造家屋経年減点補正率基準表に示されている非木造家屋の経年減点補正率によって求めるものとされているが、非木造家屋が複合構造家屋である場合に適用すべき経年減点補正率の具体的な求め方を定めていないとした上で、低層階がSRC造でそれ以外の高層階がS造といった複合構造家屋であっても、使用に耐えなくなったものとしてこれを取り壊すかどうかについては、基本的に一棟単位で判断されることになると指摘。低層階を構成する構造のうち耐用年数が最も長いものの耐用年数が経過しない限り、その余の構造の部分の補修等によってなおその建物としての効用の維持を図ることができるものと考えられることからすれば、低層階を構成する構造のうち所定経過年数の最も長いものに応じた経年減点補正率によることも、評価基準の定める経年減点補正率の趣旨に照らして合理性を欠くものとはいえず、評価基準上許容されるものというべきであるとの判断を示した。したがって、低層階を構成する構造であるSRC造等の経年減点補正率を適用したことは、評価基準に反するものということはできないとし、納税者の主張を斥けている。
また、改訂された実施要領では、複合構造家屋に適用すべき経年減点補正率は原則として床面積方式に従って求めるべきとしているが、実施要領では、複合構造家屋が在来分家屋である場合について特別の定めを置いていないところ、この場合にまで適用すべき経年減点補正率の求め方を一律に床面積方式に改めなければならないものとすれば、地方自治体における固定資産の評価事務に大きな負担が生ずることが想定されることなどから、一律に床面積方式に従って適用すべき経年減点補正率を求めるものとすることを定めたものではないと解するのが相当とした。
裁判官1人から登録価格は違法との反対意見
なお、草野耕一裁判官は、穏やかな低層階方式(低層階の方が高層化よりも損耗の進行を抑える上で重要であることを斟酌した上で計算を簡素化した算定方式)に基づいてなされた価格決定が適法といえるためには、税務当局がその具体的算定方式をあらかじめ公表していることが必要条件であり、地方自治体は複合構造家屋に用いる低層階方式が具体的にいかなるものであるかを納税者に一切公表していないことから、その登録価格の決定は違法であるとし、反対意見を述べている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























