解説記事2025年06月23日 巻頭特集 要件事実論の租税実務への活かし方(前編)(2025年6月23日号・№1079)
巻頭特集
対談
要件事実論の租税実務への活かし方(前編)
−具体的裁判事例を元に
北海道大学大学院法学研究科教授 元国税審判官 佐藤修二
弁護士・元国税審判官 向笠太郎
民事訴訟では、主張・立証責任の分配ルールである「要件事実論」が紛争の適正迅速な解決を目的として活用されている。租税訴訟も民事訴訟の一類型である以上、要件事実論は問題となり得るが、課税要件に該当する事実の立証責任は基本的にすべて国側が負うため、通常の民事訴訟に比べて活躍の場がないようにも見える。
しかし、租税訴訟においても、納税者は、自らに有利な事情等の主張立証責任を負っており、そのことを認識していないと、主張立証が足りないまま裁判が終了し、納税者の反論が認められずに敗訴となってしまうリスクがある。また、税務調査の段階でも、課税庁が納税者に主張立証責任を押し付けていると思われるケースや、納税者に有利な事実があるにもかかわらず納税者が主体的に主張立証しないといったケースがあるように思われる。このような場合に、要件事実を踏まえた適切な反論や主張立証を行うことで、課税庁に課税処分を断念させ、税務トラブルの早期解決につながる可能性がある。つまり、要件事実論の知識は、租税訴訟のみならず、租税実務レベルでも有益であるといえる。
そこで、本特集では、ともに元国税審判官である北海道大学大学院法学研究科の佐藤修二教授と向笠太郎弁護士に、租税実務において要件事実論が具体的にどのように役立つのかを、対談を通じて紐解いていただく。前編となる今回は、「租税実務における要件事実論の意義」を、国(課税庁)と納税者のどちらが立証責任を負うのかという観点から、分かりやすい事例も用いながら明らかにする。
はじめに
佐藤:今回は、弁護士法人日本クレアス法律事務所の向笠太郎先生に、要件事実論の租税実務への活かし方について伺います。向笠先生は、企業法務の名門である岡村綜合法律事務所で正統的な修業時代を過ごされた後、国税審判官を経て、現在は、日弁連税制委員会委員・第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第一部会(税務部会)副部会長を務められるなど税務に造詣の深い弁護士です。分担執筆された最新の著作として、弁護士に必要な税務のトピックを語った書籍があり(脚注1)、また、一昨年には、要件事実と相続税法に関する浩瀚な書籍(脚注2)も分担執筆されていることから、今回のテーマを伺うには最適の方と思います。まず、向笠先生から、自己紹介をお願いします。
向笠:弁護士法人日本クレアス法律事務所の向笠太郎でございます。佐藤先生におかれましては、過分なご紹介をくださいまして誠にありがとうございます。私は、2018年から2022年まで東京国税不服審判所において国税審判官として勤務し、弁護士に復帰してからは、一般民事や企業法務といった、いわゆる通常の弁護士業務とともに、審判官としての経験を生かし、税務調査対応や租税訴訟といった租税法案件にも携わっております。
佐藤先生も国税審判官のご経験がおありで、また、ご紹介いただいたとおり、現在、私は第一東京弁護士会の税務部会で副部会長を務めておりますが、佐藤先生もかつてその部会で副部会長を務めておられ、こういったご縁もあってか、佐藤先生には色々な場面でお引き立ていただいております。今回も、このような対談の機会を頂戴しまして、心から御礼申し上げます。
租税実務において要件事実論がどのように役立つのかについて、先生との対話を通して紐解いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1.租税実務における要件事実論の意義
佐藤:それでは早速中身に入ってまいります。まず、そもそも要件事実論とはどのようなものかについて、民事裁判を念頭に、簡単にご説明いただけますでしょうか。
向笠:要件事実とは、法律効果、すなわち、権利の発生という効果や、権利発生の障害、消滅、阻止という効果を発生させる法律要件に該当する具体的事実、などと説明されています(脚注3)。そして、この要件事実を明らかにしようとする理論体系を要件事実論といいます。
要件事実は、民事裁判における紛争の適正迅速な解決を目的としているものですので、あまり聞き馴染みのない方も多く、抽象的な説明では分かりにくいかと思います。そこで、「AとBとの間で、△月△日、AがBに対して動産甲を1万円で売却することとし、Bに動産甲を引き渡した。ところが、Bが代金をなかなか支払わないので、AがBに支払うよう求めたところ、Bは、代金は●月●日に既に支払済みである、と反論している。」という設例(図1参照)を用いて具体的に説明したいと思います(脚注4)。
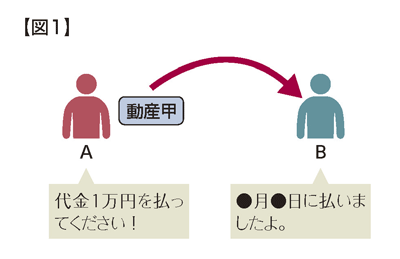
この場合、Aとしては、売買契約に基づく代金支払請求権という「法律効果」の発生、つまり、請求権が発生していることを主張する必要があります。そして、そのためには、この請求権の発生に必要な「法律要件」を主張する必要があります。この例でいう「法律要件」は、要するに、売買契約の成立ということですが、正確には、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約すること」となります(民法555条)。
この「法律要件」を満たしていることを示すための具体的事実が要件事実であり、先ほどの例では、AB間で動産甲を1万円で売却する旨の合意を△月△日に取り交わしたこと、となります。
民事裁判では、Aが原告となってこの代金支払請求権の法律要件を満たすための要件事実を主張立証する必要がありますが、このように、原告が、その主張する権利を発生させるために立証すべき必要十分な事実を「請求原因」とか「請求原因事実」といいます。
次に、「代金は支払済みである」というBの反論を検討したいと思います。Bのこの反論は、Aが主張立証する請求原因事実を前提とし、かつ両立する事実であり、請求原因から生じる効果を覆す効果を持ちます。このような効果のある事実を「抗弁」とか「抗弁事実」といいます。
Bが抗弁事実として代金を支払済みであることを主張立証すると、「債務者が債権者に対して債務の弁済をした」(民法473条)という弁済の法律要件を具備することになります。そうすると、Aが主張する代金支払請求権の消滅という法律効果が発生します(以上、図2参照)。
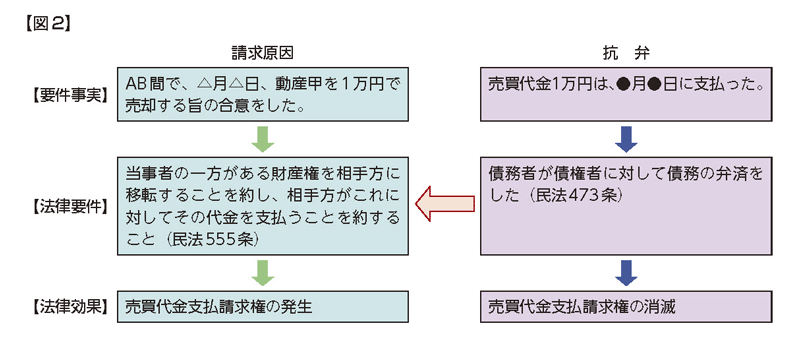
なお、仮にBが弁済をしたという反論ではなく、「動産甲はAからもらったもので、Aから買ったわけではない。」という反論をしていた場合、この反論は、動産甲を売却する旨の合意を取り交わしたというAの主張立証する事実と両立しません。このような事実の主張は「否認」と呼ばれ、抗弁とは異なり、Bはその否認内容を立証する必要はなく、否認されたAにおいて、売買契約を締結した事実を主張立証する責任を負うことになります。
また、民事裁判では、抗弁事実を前提とし、かつ両立する事実で抗弁から生じる効果を覆し、請求原因の効果を復活させる事実として再抗弁が主張立証されたり、さらにその再抗弁を前提とし、かつ両立する事実で再抗弁から生じる効果を覆し、抗弁の効果を復活させる事実として再々抗弁が主張立証されたりする、ということもあります。
ある要件事実について、誰が立証責任を負っているのかという立証責任の分配基準は重要で、自分が立証責任を負っている要件事実について立証ができなかった場合、その事実は存在しなかったものとして扱われてしまいます。先ほどの売買の例で、BがAから受け取った領収証を紛失していて、他に弁済を裏付けるものが何もなく、弁済の事実について立証が足りていないと判断された場合、弁済の抗弁はなかったものとして扱われてしまいます。そうすると、Aの主張が認められ、BはAに対して1万円を支払え、という結論になるのです。
このような要件事実をしっかりと把握するには、その法律要件を満たしているといえるために必要最小限の事実が何かを検討することになるのですが、その必要最小限の事実が立証のポイントになり、これを明確にすることで効率的かつ迅速な審理を行うことができるのです。
佐藤:このように民事訴訟で活用される要件事実論ですが、裁判実務上、租税訴訟も民事訴訟の一類型と整理されますので、租税訴訟でも、要件事実論は問題となり得ることになります。ただ、租税訴訟では、課税要件に該当する事実の立証責任は基本的にすべて、国側が負うものと解されているので、主張・立証責任の分配のルールともいえる要件事実論は、租税訴訟ではそれほど活躍の場が無いように何となく思っておりました。そこで、租税訴訟で要件事実論がどのように活きてくるのか、ご説明いただけますでしょうか。
向笠:佐藤先生がおっしゃるとおり、租税訴訟においては課税要件に該当する事実の立証責任は国側が負っていると思われます。そのため、租税訴訟における要件事実論の意義が分かりにくいのですが、やはり、租税訴訟においても、要件事実論を理解しておくことは重要であると考えます。
そのことをご説明するに当たり、租税訴訟における立証責任の分配基準についてまずご説明します。
先ほど、民事訴訟における要件事実の立証責任の分配基準について少し触れましたが、そもそも、分配基準については、民事訴訟法の分野において様々な学説があり、租税訴訟、あるいはより広い視点で行政訴訟の分野と考えた場合でも、やはり様々な学説があります。ただ、そこに立ち入ると非常に細かく、また専門的になり過ぎてしまいますので、下表のように考えておけばよいと思います(脚注5)。
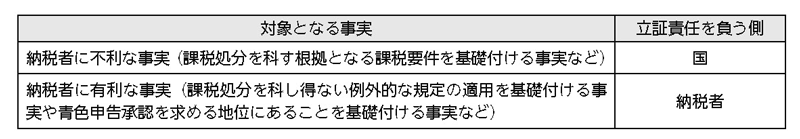
また、これも先ほどご説明しましたとおり、民事裁判では、請求原因、抗弁、再抗弁、再々抗弁、といった形で事実が細かく分類されます。租税訴訟でもそれは同じですので、厳密には、課税処分取消訴訟において、納税者は請求原因と再抗弁のどちらの段階で主張立証責任を負っているのか、といった検討も必要となります。しかし、ここでは、そこまで細かい検討は行わず、先ほどのとおり国と納税者のどちらが立証責任を負うのか、という観点で検討を行いたいと思います。
前置きが長くなりましたが、租税訴訟における要件事実論の意義について説明したいと思います。まず、課税要件に該当する事実は、納税者に不利な事実ですから、先生のおっしゃるとおり、国側が立証責任を負うと考えられます。これに対し、青色申告承認を求める地位にあることを基礎付ける事実、雑損控除(所得税法72条)を基礎付ける事実(脚注6)や過少申告加算税が課されない「正当な理由」(国税通則法65条5項1号)の根拠となる事実(脚注7)などは、納税者に有利な事情ですので、納税者側が主張立証責任を負っていると考えられます。このような事実を国側が積極的に主張立証してくれるとは限らないですし、むしろ、そのような期待はできませんので、納税者側で積極的に主張立証していく必要があります。
租税訴訟についても要件事実論を踏まえた分析を行いますと、納税者側が主張立証責任を負っているものが意外と多いことが分かります。今挙げた例以外にも、庭内神しの敷地部分が「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」(相続税法12条1項2号)であることを基礎付ける事実(東京地判平成24年6月21日税資262号順号11973)、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等(租税特別措置法69条の4)であることを基礎付ける事実、といったものが挙げられます(脚注8)。なお、小規模宅地等の特例については、政令(租税特別措置法施行令40条の2)により詳細な要件も定められていますが、このような場合には、政省令の定める要件を満たすための具体的事実も主張立証する必要がありますのでご注意ください。
このように、租税訴訟においても納税者側に有利な事情は、納税者側に主張立証責任があることを認識していないと、主張立証が足りていないまま裁判が終了してしまい、反論が認められずに納税者敗訴となってしまう、というリスクがあります。
また、要件事実というのは、法律要件を具備していることを示すためのものです。そうすると、「この法律要件を満たすための具体的な事実は何か。」という視点が備わることとなり、どのような事実を主張すればよいのか、そしてそれを裏付ける証拠として、どのようなものを収集すればよいのか、ということが見えてきます。これは、租税訴訟に限った話ではないかもしれませんが、裁判、正確には裁判に向けた準備というのは、限られた時間の中で、多くの資料から有益な事情をピックアップして効果的な反論を組み立てていく必要がありますので、自分たちが、今、何をすべきかを正しく把握するためにも、要件事実論に基づく分析、検討は、租税訴訟においても重要であると考えます。
佐藤:納税者は、自らに有利な事実について主張立証責任がある、ということですが、最判昭和38年3月3日税資37号171頁は、必要経費についても国側が主張立証責任を負うかのような判示をしています。そうだとすると、国側が、納税額を押し下げる要因であり、納税者側に有利な事実である必要経費について主張立証責任を負うということにならないでしょうか。
向笠:非常に鋭いご指摘です。おっしゃるとおり、必要経費は、納税額を押し下げる要因ですが、課税所得を決めるファクターでもあります。つまり、課税要件の一部ということですので、国側が主張立証責任を負う、ということになります。
もっとも、どのような必要経費があるのかを一番分かっているのは納税者自身であり、主張立証も容易といえます。また、納税額を押し下げるという観点からすれば、ご指摘のように納税者側にとって有利な事情です。このようなことから、ご紹介いただいた判例以降の下級審裁判例は、国は必要経費について一応の主張立証を行えば足り、それ以上の必要経費があるというのであれば、納税者においてその主張立証を行うべき、というスタンスを採用しています(脚注9)。
このように、多少技巧的ではありますが、要するに、納税者として、必要経費として認めてもらいたいものについては主張立証責任を負っている、ということですから、やはり、「納税者に不利な事実=国側、納税者に有利な事実=納税者側」という視点で理解しておけばよいように思います。
【租税訴訟における要件事実論の意義】
1 納税者が主張立証すべき事実の把握が可能となる。
2 1の事実の裏付けとなる証拠の適切な取捨選択を行い得る。
佐藤:ありがとうございました。租税訴訟における要件事実論の意義が良く分かりました。次に、訴訟よりも前の、日常の税務の実務の中で、要件事実論がどのように活用できるか、教えていただければ幸いです。
向笠:日常の税務実務における要件事実論の意義として、まず、税務トラブルの早期解決ということが挙げられます。
一般的に、裁判を利用した事件の解決には、どうしても時間がかかります。これは租税訴訟も例外ではなく、裁判所の統計資料によりますと、令和5年の租税訴訟を含む行政訴訟の一審での平均審理期間は17.3月とのことですし(脚注10)、高裁や最高裁まで争われれば、結論が出るまでに更に時間がかかります。また、租税訴訟の場合、審査請求前置主義が採用されており(国税通則法115条1項)、課税処分に不服があるからといって直ちに取消訴訟を提起できるわけではありません。
このようなことから、税務トラブルについて訴訟を利用して解決しようとなると、かなりの時間がかかることとなります。例えば、ユニバーサルミュージック事件(最判令和4年4月21日税資272号順号13707)は、最も古い平成20年12月期の確定申告から考えますと、納税者勝訴が確定するまでに約13年かかっています(下表参照)。
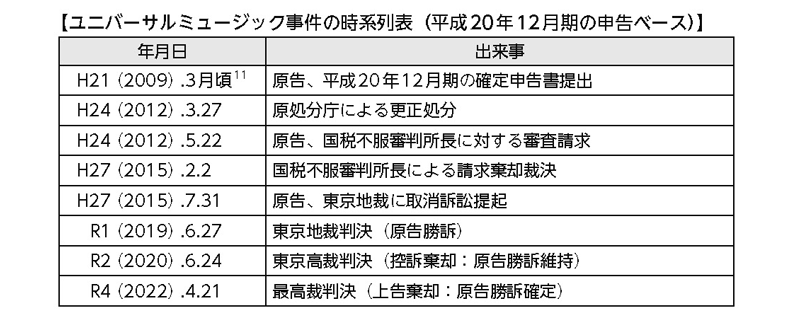
ユニバーサルミュージック事件は、直接的には要件事実に関する事件ではありませんが、ここでお伝えしたいのは、裁判となると、最終的に勝訴できたとしても長い期間闘う必要がありますし、また、確実に勝訴できるか不明というリスクもある、ということです。したがいまして、裁判になる前に解決できれば、それに越したことはありません。
ではどうすればよいのかといいますと、私は、税務調査段階において要件事実論を踏まえた主張立証を行うことが1つのポイントであると考えています。
すなわち、国側は、課税要件を基礎付ける事実について主張立証責任を負っていますので、税務調査段階でも、課税庁は、そのことを意識した調査を行うのが一般的であると思われます。ところが、実際には、税務調査担当者から、課税要件を基礎付ける事実が存在しないことを立証できなければ課税要件を基礎付ける事実が存在するとみなす、などと言われたりすることがあるようです。これは、課税庁側が、いわば納税者に主張立証責任を押し付けている格好であり、立証責任の分配基準に照らすとおかしいことになります。また、調査をしても実情が不明確なままであるにもかかわらず、憶測に基づいて課税を試みようとする場合もあるようですが、これも、課税庁側がしっかりと主張立証責任を行っていない状況といえます。
一方、税務署は、申告漏れがないか、更正処分や賦課決定処分を行う必要がないか、という観点で税務調査を行うのが通常ですので、納税者に有利な事実を積極的に集めることはあまりないように思われます。そのため、有利な事実があることは、税務調査段階でも納税者側から主体的に主張していくべきですが、特に納税者がご自身で対応されているような場合、税務署が指摘してこないことについて主張していいのかが分からず、結局主張しないままとなっていることもあるようです。
このように、税務調査段階では、必ずしも主張立証責任を意識したやり取りがされていない場合があるようなので、課税当局による課税要件についての立証が不十分であると主張する、納税者に有利な事実をしっかりと立証するといった要件事実を踏まえた適切な反論や主張立証を行うのが重要となります。これを行うことで、税務調査担当者に、課税処分を課しても後になって裁判等で取り消されてしまうのではないか、という疑念を抱かせ、課税処分を断念させることに繋がり、訴訟に発展する前に解決できる可能性があるのです。この税務トラブルの早期解決が、日常税務実務における要件事実論の意義と考えます。
そして、それをより可能にさせるために重要となるのが、証拠作りです。
先ほど、税務調査段階での説得的な主張立証が必要と伝えましたが、そのためには、どうしても客観的な証拠が必要となります。ただ、証拠というのは、一朝一夕に出来上がるものではありませんので、普段から、証拠として役立ちそうなことは客観化、記録化しておくことが大事になります。もっとも、日常の税務業務全てを記録化するのは大変ですし、税理士の皆様が顧客に対し、関係しそうなことは全て記録化しておいてほしい、と伝えるのも困難であろうかと思います。
そのような場合に、要件事実論に対する理解があれば、万一、税務調査となった場合に、どのような反論ができるか、どのような事実を主張立証すべきかをあらかじめ想定し、最低限、そのために必要十分な事実を裏付けるものを証拠化しておく、ということが可能となると考えます。
必要十分な事実の裏付け部分を証拠化、というと、少し大袈裟に聞こえますが、例えば、納税者側が主張立証責任を負う事実で、その根拠として当事者間のやり取りがあるとした場合、やり取りを口頭で行うのではなくあえてメールで行ったり、会議の議事録にしっかりと残したりしておく、ということです。もちろん、契約や合意をした場合には、契約書なり覚書なりをしっかり作成しておく、というのも重要です。そして、このような証拠化をしておけば、万一、税務調査段階で解決しなかったとしても、後の審査請求や取消訴訟で改めて証拠として提出することも可能となります。
弁護士として仕事をしていると、こちらが主張立証責任を負っている事実について裏付けとなるものを確認すると、口頭のやり取りしかない、周辺部分についてのメールはあるのに核心部分については何故かメールが存在しない、といったことがよくあります。日常の税務業務においても、将来の税務調査に備え、主張立証責任を負う事実の裏付けとなるものについては、是非とも証拠化を意識していただければと思います。
【租税実務における要件事実論の意義】
1 税務トラブルの早期解決に繋がり得る。
2 主張立証責任を負っている事実を証拠化することへの認識、理解が高まる。
佐藤:詳細にありがとうございました。ユニバーサルミュージック事件は、2012年の課税処分が報道されたのを記憶しており、それから今年でちょうど13年ほどで、ずいぶん長い時間がかかった事件ですね。私が東京大学法科大学院で授業をしていたころの教え子である吉沢健太郎さん(東京大学助教)が最近、その締めくくりと言えるような詳細な評釈を発表されており(脚注12)、私も改めて感慨深く思っていたところです。
(後編に続く)
脚注
1 山下眞弘=堀田善之編著『国税組織の実務経験者が説く 弁護士として気付きたい 法律相談事案の隠れた税務問題』(第一法規、2025)。
2 伊藤滋夫=岩崎政明=河村浩=向笠太郎『要件事実で構成する相続税法』(中央経済社、2023)。
3 司法研修所編『改訂 新問題研究 要件事実』(法曹会、2022年)5頁。
4 本対談では、要件事実論について可能な限り簡潔な説明を試みているが、初学者、非法曹向けのより詳しい解説として、伊藤滋夫名誉教授の「基礎の基礎から始める要件事実・事実認定の徹底的入門」(ビジネス法務2025年6月号~(隔月での連載))がある。関心のある方は、そちらも併せてお読みいただきたい。
5 ここで紹介する考え方は、「侵害処分・授益処分説」と呼ばれるものである。同説の詳細については、前掲注2・17頁以下、伊藤滋夫=岩崎政明『租税訴訟における要件事実論の展開』(青林書院、2016年)19頁以下等をご参照いただきたいが、簡単に説明すると、以下のとおりである。すなわち、まず、課税処分の場合、この処分は国民の財産権を制限する典型的な侵害処分であるから、国側において課税処分の適法要件を基礎付ける要件事実の主張立証責任を負うと考える。次に、青色申告の承認のように、国民が本来有する利益・地位に比して特別な利益を付与する授益処分については、納税者が授益処分を受け得ることを基礎付ける事実の主張立証責任を負い、国側において、納税者が当該授益処分を受けることができない例外的事実の主張立証責任を負うと考える。
6 大阪地判昭和62年10月23日税資160号228頁(控訴審である大阪高判昭和63年3月30日税資163号1044頁も大阪地裁判決を支持している。上告棄却により確定(最判昭和63年10月18日税資166号182頁))参照。なお、雑損控除を基礎付ける事実について納税者が主張立証責任を負うとする裁判所の考えには、異論もある(伊藤滋夫=岩崎政明=河村浩『要件事実で構成する所得税法』(中央経済社、2019)183頁〔伊藤〕)。
7 最判平成11年6月10日税資243号250頁参照。
8 ここで挙げた例については、前掲注2・107頁〔岩崎〕及び254頁〔向笠〕参照。
9 例えば、大阪高判昭和46年12月21日税資63号1233頁は、「必要経費の点を含め、課税所得の存在については、課税庁たる被控訴人に立証責任があることは、さきに述べたとおりであるが、必要経費の存在を主張、立証することが納税者にとつて有利かつ容易であることに鑑み、通常の経費についてはともかくとして、控訴人らの主張する利息のような特別の経費については、その不存在について事実上の推定が働くものというべきであり、その存在を主張する納税者は、右推定を破る程度の立証を要するものと解するのが公平である。」と判示する。
10 裁判所「裁判所データブック2024」73頁(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/databook2024/db2024_all.pdf) 最終閲覧日:2025年6月18日。
11 向笠が判決文から推測したものであり、正確な提出日は不明である。
12 吉沢健太郎「判批」法学協会雑誌142巻5・6号所収。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業。2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授。2022年~現在 北海道大学大学院法学研究科教授。著書に、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、 『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『対話でわかる租税「法律家」入門』(編著、中央経済社、2024)など。
向笠太郎 (むかさ たろう)
2009年上智大学法科大学院修了。10年弁護士登録。18年から22年まで東京国税不服審判所において任期付公務員(国税審判官)として勤務し、現在は、弁護士法人日本クレアス法律事務所所属。最近の著書、論文としては、本文掲記のもののほか、「名義株の判断方法−裁判例の分析を中心に」税経通信2025年7月号28頁、『景品表示法の法律相談』(共著、青林書院、2025年)、「グループ通算制度についての一考察−個別的否認規定の不当性要件を考える−」本誌1067号17頁(2025年)、「租税分野における私法関係(契約関係)の重要性−南御堂参道事件を題材に−」本誌1026号12頁(2024年)等がある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























