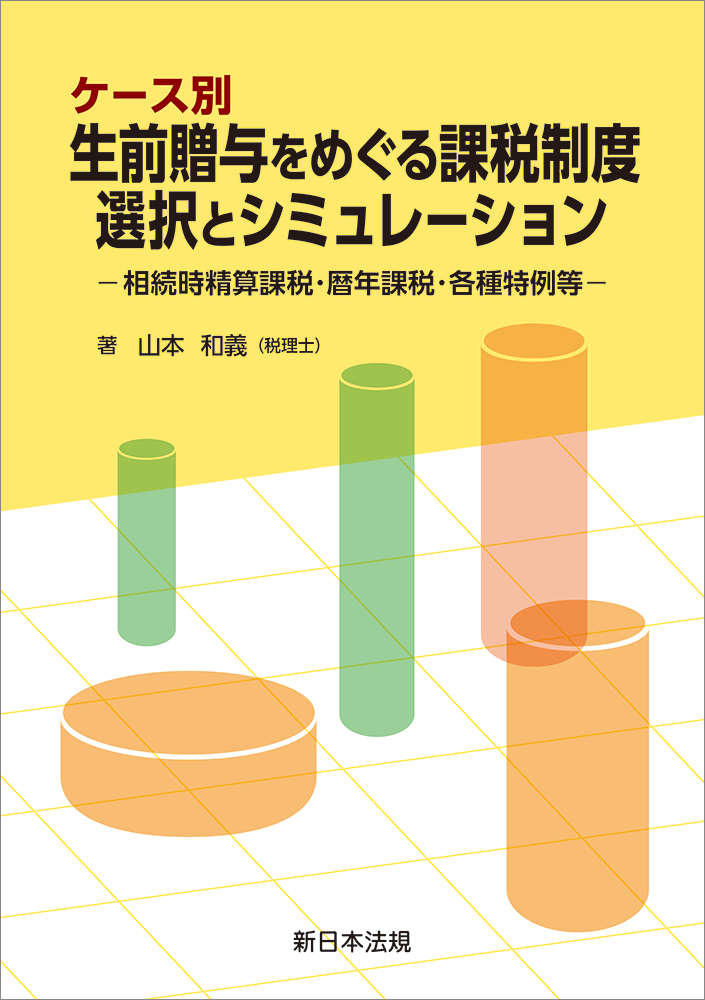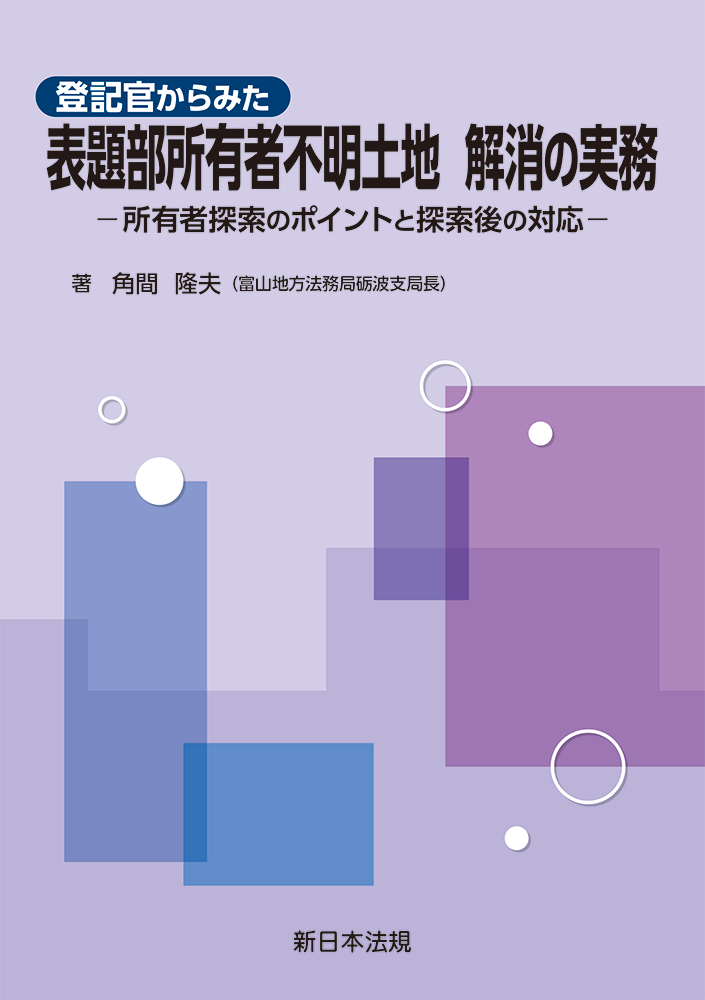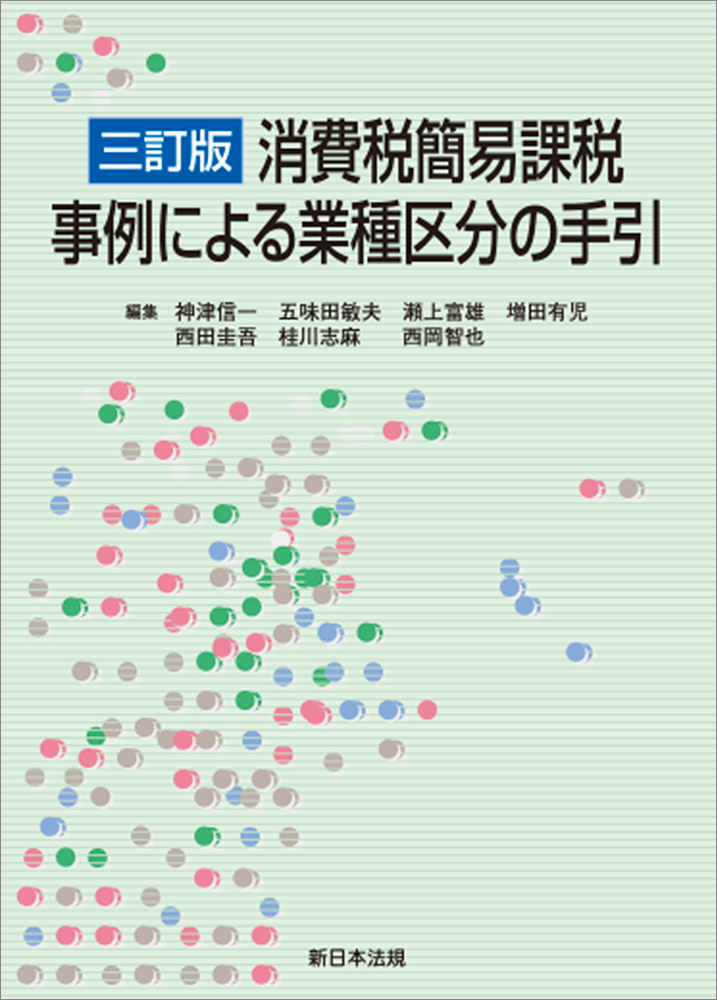会計ニュース2025年10月10日 のれん非償却で監査工程数増えコストも(2025年10月13日号・№1094) ASBJ、第4回のれんに関する公聴会を開催
企業会計基準委員会(ASBJ)は10月7日、のれんに関する公聴会を開催した。4回目となる今回は、有限責任あずさ監査法人、EY新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、PwC Japan有限責任監査法人からパートナーが参加し、個人的な立場として意見聴取が行われている(公聴会の模様は、同委員会のHPから閲覧可)。
まず、のれんの非償却化について、トーマツの東川裕樹氏は、仮に導入する場合には減損会計の見直しもセットで行うべきとした。毎期減損テストを実施することなどにより監査工程数が増えることでコストも増加することになるほか、取得対価配分(PPA)や割引率の算定など、企業側においても専門家が必要であるとの認識を示した。EY新日本の齊藤直人氏についても、IFRSと同様の減損テストは導入すべきであるとした上、特にスタートアップ企業においては現状でも内部管理体制が十分でないケースが多いため、専門性のある人材を増やす必要があるとしたが、その確保が難しいとの課題も指摘している。PwC Japanの加藤正英氏は、償却とするか非償却とするかは経営判断になるとした上で、非償却化した場合にはコストが増加するのも事実であるとした。また、あずさの阿部博氏は、のれんの非償却化のモデルに関しては減損損失計上のタイミングが遅れるなどの構造的な欠陥があるとし、慎重な検討が必要とした。
のれんの償却・非償却との選択制については、4人とも財務諸表の比較可能性の観点から導入に反対している。また、日本基準に2種類の減損会計が混在し、財務諸表利用者をミスリードするとの指摘もあった。なお、仮に日本基準にのれんの非償却化が導入された場合には、のれんの減損テストの実務上の負担を避けるため、未上場企業などに限り選択制を導入することは検討の余地があるとの意見があった。
そのほか、計上区分の変更についても、変更する正当な理由を見出すことは難しいなど、賛同する意見はなかったが、仮に変更する場合には、「営業外費用」や「特別損失」などの定義の説明も併せて開示すべきとの指摘があった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -