解説記事2025年10月13日 税務マエストロ 民泊用の建物は居住用賃貸建物に該当するか?(2025年10月13日号・№1094)
税務マエストロ
民泊用の建物は居住用賃貸建物に該当するか?
#311
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
消費税法30条10項では、居住用賃貸建物について「……住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物……」と定義しているのであるが、そもそも居住用賃貸建物とは、未来永劫住宅家賃が発生しない建物を意味するのだろうか……。それとも、賃貸する時点において、店舗や事務所など、住宅家賃が発生しない状態の建物を意味するのであろうか……?
筆者は十数年にわたり、東京税理士会と東京地方税理士会の税務相談員を担当しているが、実務の現場では、分譲マンションを取得し、事務所として使用したり賃貸した場合の取扱いが所轄税務署により異なっているようだ。
構造がマンション(居住用)だから居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除はできないと回答した税務署がある。その一方で、決算までに事務所として賃貸することを契約書により明らかにしているならば、たとえ構造が居住用でも居住用賃貸建物には該当しないと回答した税務署があったようだ。
居住用賃貸建物に該当するとした場合、賃貸物件であれば第3年度の課税期間において加算調整(取戻し控除)が可能となるのでトータルの仕入控除税額は変わらない。しかし、取得時に控除できるのか第3年度の課税期間における税額調整になるのかが所轄税務署により異なるなどということは、本来あってはならない異常事態なのである。
この、最も重要であるはずの居住用賃貸建物の定義であるが、困ったことに、法令からは、はっきりと読み取ることができない。本稿では、法令や通達、市販されている書籍などを参考に、まずはこの居住用賃貸建物の定義について考えてみたい。その上で、近年増加している民泊事業と居住用賃貸建物の関係について検討する。
Ⅰ 居住用賃貸建物とは?
「居住用賃貸建物」とは、次の①と②のいずれにも該当するものをいう。また、「建物」にはその附属設備が含まれる(消法30⑩)。
① 事業者が国内において行う住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であること
② 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当する建物であること
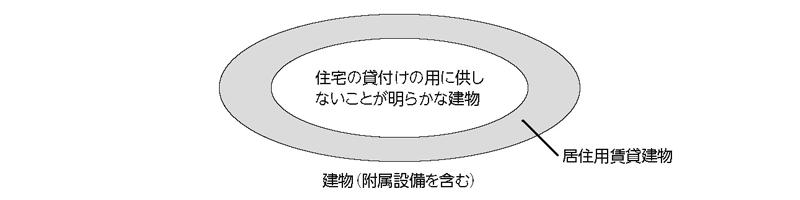
上図のように、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」以外の建物が居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除が制限されることとなる。
「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」については、「建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいう」とした上で、消費税法基本通達では次のような建物を具体的に例示している(消基通11−7−1)。
(1)建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
(2)旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
(3)棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの
1 判断基準はどこにあるのか?
居住用賃貸建物に該当するかどうかの判断に当たっては、建物の用途と構造のどちらを基準にすればいいのだろうか……。消費税法基本通達11−7−1の例示であれば、(1)は構造、(2)と(3)は用途で判断するように読めるのであるが、その明確な判断基準(境界線)がわからない。
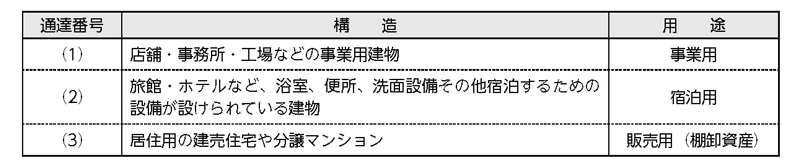
建物の構造や設備の状況などを勘案して判断するとした場合、店舗や工場のような事業用施設であれば居住用賃貸建物に該当しないことは明白であるが、事務所として賃貸する目的で取得する物件などはどうやって判断すればいいのだろう……?
居住用賃貸建物の判定に建物の構造や設備の状況などを勘案するとした場合、分譲マンションの一室を購入して事務所として賃貸するケースでは、その用途に関係なく、居住用賃貸建物に該当することになるのだろうか……?
消費税法30条10項では、居住用賃貸建物について「……住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物……」と定義している。この条文を読む限り、住宅の貸付けの用に供しないかどうかの判断は、取得時点でするのか、将来にわたる用途まで視野に入れて判断するのかがわからない。
取得したときは事務所として賃貸したとしても、構造が居住用であれば将来的に住宅として賃貸する可能性がないわけではない。そうすると、未来永劫住宅家賃が発生しない建物とは言えないことから居住用賃貸建物に該当し、家賃収入が課税されるにも関わらず仕入税額控除が制限されてしまうのであろうか? それとも、「居住用として貸すつもりはない!」と固く心に誓っておけば、居住用賃貸建物には該当しないことになるのだろうか? 居住用賃貸建物に該当するかどうかの判断は、気持ちの持ちようによって変わり、仕入控除税額も変わってくるということなのであろうか……???
また、居住用の物件かどうかの判断は、なにを基準に決めるのであろう……。バスタブやキッチンの有無、畳部屋の有無や間取り、収納スペースの大小や床面積などを総合勘案して判断するのだろうか……もしそうだとしたならば、その判断基準(境界線)はどこにあるのだろう……?
2 国税庁の見解やいかに?
週刊税務通信3863号(2025年8月18日)では、国税庁に確認した居住用賃貸建物の取扱いについて、Q&A形式による記事を掲載した。この記事のQ3では、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」の判定要素として次のような解説がされている。
:
Q3 居住用賃貸建物に該当しない「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、「建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなもの」とあります(Q1)。建物の構造及び設備の状況から、住宅と認められる建物は、全て居住用賃貸建物に該当することになりますか。
A 建物の構造及び設備の状況からみて、「住宅」(人の居住の用に供する家屋)と認められる建物であっても、その建物の取得時において、契約書その他の書類等から、「(消費税が非課税となる)住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなもの」といえるケースもあります。
例えば、建物の構造及び設備の状況に照らして「住宅」と認められる建物であっても、自己が事務所用として使用することが建物の取得時点で契約書やその他の書類等から客観的に明らかであれば、「住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなもの」として居住用賃貸建物に該当しないことになります。
なお、「客観的に明らか」といえるかどうかは個々の事実関係を踏まえて判断することになります。例えば、自社事務所として取得するものの将来的に居住用賃貸に供する可能性があることが否定できないようなケースは、「住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなもの」とはいえず、居住用賃貸建物に該当することになります。
:
このQ&AのAnswerに「例えば……」と前置きして書かれている「建物の構造及び設備の状況に照らして「住宅」と認められる建物であっても、自己が事務所用として使用することが建物の取得時点で契約書やその他の書類等から客観的に明らかであれば、「住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなもの」として居住用賃貸建物に該当しないことになります。」という例示については、2024年9月24日に発行された「令和6年版消費税法基本通達逐条解説/大蔵財務協会」の703頁にもほぼ同一の文言による解説がされている。
そうすると、これらの雑誌や書籍では直接の解説はないものの、自己使用の建物だけでなく、「建物を取得した課税期間の末日までに事務所として賃貸することが契約書やその他の書類等から客観的に明らかな場合」についても、居住用賃貸建物に該当しないものとして問題なさそうである。
気になるのは、Answerのなお書に書かれている下線の箇所である。「……将来的に居住用賃貸に供する可能性があることが否定できないようなケース……」とは、どのようなケースを想定しているのだろうか……。分譲マンションのように、そもそもの構造が居住用になっている場合には、いつでも居住用賃貸に供する可能性があることになるのでは……。そうすると、そもそもの構造が居住用の場合には、いつでも居住用賃貸に供する可能性があるので居住用賃貸建物に該当することになるのだろうか……。それとも、「居住用として貸すつもりはない!」と固く心に誓っておけば、居住用賃貸建物には該当しないことになるのだろうか……?
3 国税庁の質疑応答事例(社宅に係る仕入税額控除)
【照会要旨】
社宅や従業員寮の使用料は住宅家賃として非課税になるとのことですが、社宅や従業員寮の取得費、借上料や維持等に要する費用に係る仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか。
【回答要旨】
住宅家賃については非課税とされていますが、社宅や従業員寮も住宅に該当します。また、その建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃及びこれを他の者に転貸した場合の家賃ともに住宅家賃に該当します。
したがって、会社が住宅の所有者から従業員の社宅又は従業員寮用に借り上げる場合の借上料及び借り上げた住宅又は従業員寮を従業員に貸し付ける場合の使用料ともに非課税となる住宅家賃に該当します。
これらの社宅や従業員寮の取得費、借上料又は維持等に要する費用に係る仕入税額控除の取扱いは次のようになります。
1 自己において取得した社宅や従業員寮の取得費
使用料を徴収する社宅や従業員寮は、居住用賃貸建物に該当しますので、事業者が、国内において行う社宅や従業員寮の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません。
なお、従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
……(以下省略)……
<解説>
【照会要旨】にもあるように、従業員から社宅使用料を徴収する場合の社宅の取得費は居住用賃貸建物に該当する。これに対し、無償による社宅の貸付けはそもそもが対価を得ていないことから資産の譲渡等には該当せず、結果として取得する建物は居住用賃貸建物には該当しないことになる。
●消費税法2条1項8号
資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
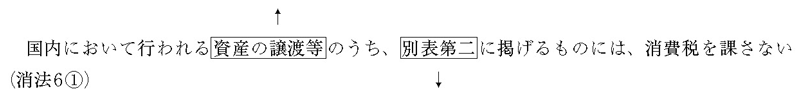
:
●消費税法別表第二13号
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
個別対応方式を適用する場合、社宅の取得費は、無償による貸付けであれば共通対応分、有償であれば従業員から収受する社宅使用料収入が非課税売上げになることから非課税売上対応分に区分することになる。この考え方は、改正により居住用賃貸建物に対する仕入税額控除が制限された後でも何ら変わるものではない。
気になるのは、質疑応答事例において、「……従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しない……」としている件である。
国内取引については、対価を得て行うものだけを課税の対象とする一方で、課税対象取引であっても、別表第二に掲げるものについては非課税として消費税を課さないこととしている。したがって、非課税となる住宅の貸付けについては結果として有償取引に限られることとなるのであるが、このような文理解釈による判断で、無償により貸し付けられる社宅や従業員寮はすべて居住用賃貸建物に該当しないものと整理してよいのだろうか?
居住用賃貸建物については、本法で曖昧な定義をした傍らで、無償による貸し付けはすべて無罪放免で仕入税額控除を認めるという質疑応答事例の解説には違和感を禁じざるを得ない。
不動産業や医療業など、経常的に非課税売上げが発生する事業者を除き、一般事業会社では預金利息くらいしか非課税売上げは発生しないのであるから、課税売上割合は限りなく100%に近い数値が算出されることになる。結果、社宅の取得費を共通対応分に区分したとしても、ほぼ全額に近い仕入税額控除ができることを考えると、居住用賃貸建物の定義そのものに法令上の欠陥があるように思えてならないのである。
Ⅱ 居住用賃貸建物の判定時期
居住用賃貸建物に該当するかどうかについては、課税仕入れを行った日の状況により判定することとされており、取得の時点において用途が未定であるなどの理由により、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかでない建物は、居住用賃貸建物に該当することとなる。
つまり、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物でない限りは居住用賃貸建物から除外することはできないということである。
なお、消費税法基本通達11−7−2(居住用賃貸建物の判定時期)によれば、取得時に用途未定の物件であっても、課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日において住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとすることができるとのことであるが、本通達の取扱いは、どのようなケースを想定しているのだろう……?
物件の用途に関係なく、取得時に建物の構造や設備の状況などを勘案して判断するとしたならば、取得時に判定が確定するのであるから、課税期間の末日において住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされることなどあり得ない。言い換えれば、取得時に用途が未定の建物とは、すなわち、分譲マンションのような居住用の構造になっている建物しかないように思えるのである。
Ⅲ 合理的に区分する方法
賃貸マンションやアパートなど、居住用の賃貸物件は居住用賃貸建物に該当する。
1階が貸店舗で2階が居住用の貸室となっているような物件は、1階から発生する家賃は消費税が課税されるものの、2階部分が居住用貸室となっていることから「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」には該当しないため、物件全体が居住用賃貸建物に該当することになる。
なお、居住用賃貸建物を、建物の構造や設備の状況・その他の状況により、商業用部分(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分)と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、居住用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除を制限することとしている(消令50の2①)。
具体的には、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物などについて、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分することになる(消基通11−7−3)。
Ⅳ 住宅宿泊事業(民泊)
いわゆる「民泊」は旅館業法に規定する旅館業に該当することとされている。したがって、たとえ貸付期間が1か月以上になるとしても非課税とはならず、利用料金には消費税が課税されることになる(消基通6−13−4(注))。
1 住宅宿泊事業法による民泊営業
住宅宿泊事業法では、第2条第1項において「当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして……設備が設けられていること」と「住宅」を定義し、同条第3項において、「住宅宿泊事業」とは、「……宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業……」と定義している。
住宅宿泊事業法(抄)
:
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
2 この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
:
住宅宿泊事業法の「住宅」という文言に着目した場合、民泊用の建物は居住用賃貸建物に該当するように思えなくもない。しかし、消費税法では、「住宅」について「人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。」と定義しているのであり、住宅宿泊事業法の「住宅」の定義は援用していないのである(消法別表第二13)。
また、民泊営業については、国土交通省住宅局・観光庁等が策定した住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において詳細な解説がされており、このガイドラインを読む限り、民泊営業と下宿営業とのさしたる違いはないように思えるのである。
民泊法の第2条第3項では、「住宅宿泊事業」について、「……宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として……算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。」と規定している。
よって、民泊用の建物は180日という利用制限があるので、180日を超えて民泊として賃貸することはできない。物件の所有者は、利用制限期間を経過した後の期間をマンスリーマンションとして賃貸するなど、その利用方法を工夫する必要がある。言い換えれば、180日を超えてからは住宅として貸付けることも可能ということになる。そうすると、民泊用の建物は構造や用途から判断するのではなく、民泊法の利用制限(180日ルール)の規定から居住用賃貸建物に該当するものと整理するべきではないだろうか?
2 旅館業法と国家戦略特区法による民泊営業
民泊制度ポータルサイトによると、民泊事業を行う場合、下記①~③のいずれかの方法によることとなるようである。
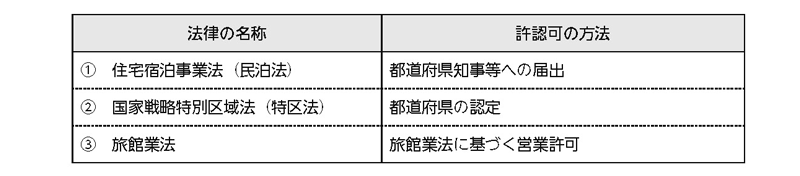
これについて、週刊税務通信(3637号2021年1月11日10頁)では、上記①~③のいずれの制度に基づく届出等をした住宅であっても、建物の構造等から判断すれば住宅であることに変わりはないため、「居住用賃貸建物」に該当し、建物取得時には仕入税額控除が適用できないと解説されている。
しかし上記②の「国家戦略特区法の認定」と③の「旅館業法の許可」を受けて民泊事業を行う場合には、いわゆる利用日数の制限(180日ルール)はないのであるから、取得した建物は居住用賃貸建物には該当しないものと考えるべきではないだろうか? 民泊営業を一括りにして居住用賃貸建物に該当するかどうかを判断すべきではないと思うのである。
3 民泊業者が建物を転貸する場合
消費税法別表第二13号と関連する消費税法基本通達では、非課税となる住宅の貸付けについて次のように定義している。
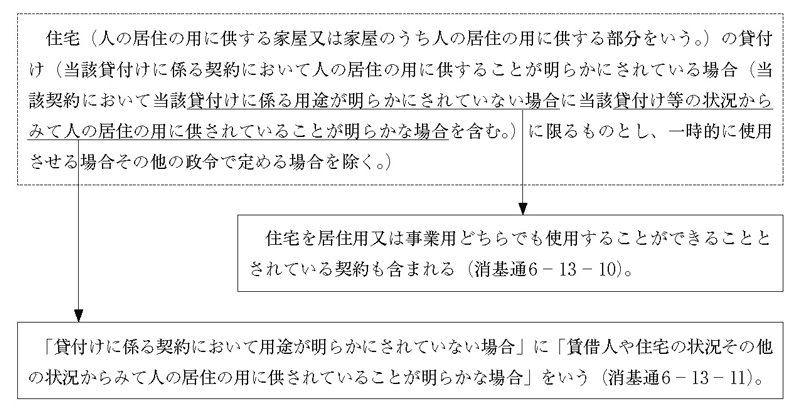
上記消費税法基本通達6−13−11では、(1)~(3)の具体的な例示を示しているので、その内容を【具体例1】~【具体例3】で確認するとともに、民泊事業との関係を検討する。
【具体例1】通常の賃貸借契約
賃貸人と賃借人との契約において物件の用途が明らかにされておらず、賃借人(個人)が物件を事業用に使用していることを賃貸人が把握していない場合には、その物件の貸付けは非課税となる(消基通6−13−11(1))。
ただし、契約書で物件の用途が明らかにされていない場合であっても、賃借人が物件を事業用に使用することを賃貸人が把握(承諾)している場合には、単に事実を書面にしていないというだけのことであり、その事実に基づき、課税されることになる。
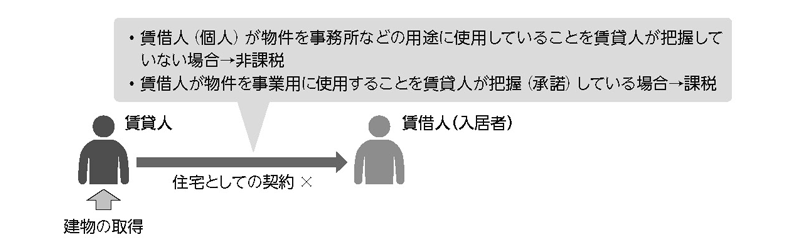
この場合において、賃貸人が民泊運営サイトを経由して、所有物件を民泊として利用させる場合には、2で説明したように、民泊法に基づくものだけが居住用賃貸建物に該当するものと思われる。
また、賃借人が物件を事業用に使用することを賃貸人が把握(承諾)している場合には、非課税となる住宅の貸付けには該当しないわけであるから、取得物件は居住用賃貸建物には該当しないものと思われる。ただし、課税側とのトラブルを未然に防ぐためにも契約書は作成しておくべきである。
【具体例2】サブリース契約(その1)
サブリース契約において、賃貸人と賃借人との契約においては物件の用途が明らかにされていないものの、賃借人と転借人(入居者)との間で住宅用としての契約がされている場合には、入居者が住宅として使用することが明らかなので、賃借人から転借人(入居者)への転貸だけでなく、賃貸人から賃借人への賃貸についても非課税となる(消基通6−13−11(2))。
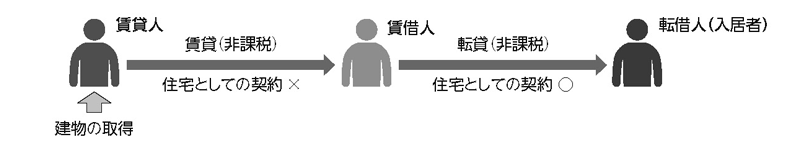
よって、取得物件は居住用賃貸建物に該当し、仕入税額控除の対象とすることはできない。
【具体例3】サブリース契約(その2)
サブリース契約において、賃貸人と賃借人との契約においては物件の用途が明らかにされておらず、賃借人と転借人(入居者)との間でも物件の用途が明らかにされていない場合において、転借人(個人)が物件を事務所などの用途に使用していることを賃貸人が把握していない場合には、その物件の貸付けは非課税となる(消基通6−13−11(3))。
したがって、契約書で物件の用途が明らかにされていない場合であっても、転借人が物件を事業用に使用することを賃貸人が把握(承諾)している場合には、その事実に基づき、課税されることになる。
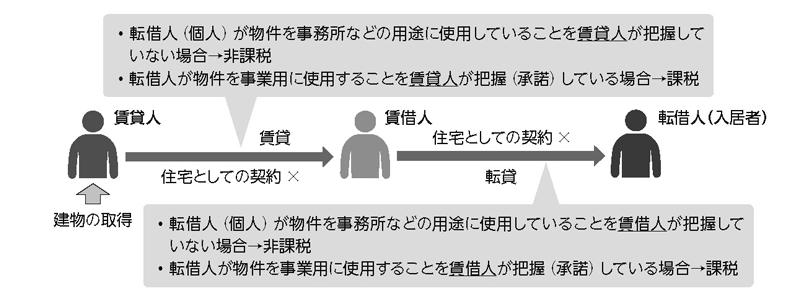
この場合において、賃貸人と賃借人との間で民泊利用を目的とした建物の賃貸借契約を締結する場合には、賃貸人が民泊事業を営むわけではないことから、取得物件は居住用賃貸建物に該当しないことになり、仕入税額控除の対象とすることができるのだろうか?
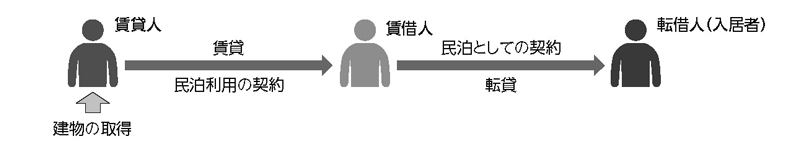
4 福利厚生施設を民泊に利用した場合
事業者が福利厚生施設を取得した場合には、その建物は住宅として貸し付けるものではないので居住用賃貸建物には該当しない。では、福利厚生目的で取得した建物につき、未利用期間を有効活用するために、民泊法による届出をした上で民泊事業としても利用する場合には、その建物は居住用賃貸建物に該当するのだろうか……?
福利厚生目的で取得した建物につき、仕入税額控除の対象とした翌課税期間において民泊法による届出書を提出し、民泊事業を開始する場合はどうだろう……。いずれの場合にしても、建物はあくまでも福利厚生目的で取得するわけであるから、結果的に民泊事業に利用したとしても、居住用賃貸建物には該当しないものとしてよいのだろうか……?
5 個人事業者の取扱い
リゾート地で分譲マンションを購入し、セカンドハウスとして利用しながら民泊事業を営むケースが増えているようだ。札幌などの行楽地では不動産価格の高騰とともにホテル価格も上昇傾向にあることから、首都圏の富裕層を中心に、札幌でのセカンドハウス需要が拡大している。道内の宿泊施設は繁閑の差が大きいので、繁忙期に営業日を集中させれば高単価が期待できることから、大和ハウスは今後も札幌駅近くと千歳市で分譲マンションの供給を計画しているとのことである(2025.8.30日経夕刊2面)。
では、個人がセカンドハウスとして利用するために分譲マンションを取得し、副業として民泊事業を営む場合の消費税の課税関係はどうなるのだろうか……。消費税には所得税のような事業の規模に関する要件はない。よって、民泊による利用料収入は、不定期かつ少額ではあるものの、反復、継続、独立して行われることから課税の対象になるものと思われる。
ところで、個人事業者が事業用の自動車を家事のためにも利用する場合には、家事使用の部分を明確に区分できないことからみなし譲渡の規定は適用しないこととしている(消基通5−3−2)。また、個人事業者が家事共用資産を取得した場合には、その取得金額を合理的な基準により区分した上で、事業用部分だけを仕入控除税額の計算に取り込むこととする一方で、事業用の部分(課税仕入れに係る資産)を一時的に家事使用したとしても、その行為はみなし譲渡の対象とはならないこととしている(消基通11−1−4)。
そうすると、個人事業者が民泊事業を営むために分譲マンションを取得し、空室の時にプライベートで利用したとしても、そもそも物件の取得時に家事使用の頻度(日数)はわからないのであるからその取得金額を合理的に区分することはできないことになる。
結果、利用頻度に関係なく、その行為についてみなし課税がされることはないものと理解してよいのだろうか?
民泊法は、所有する家屋を自らが使用しない期間のみ民泊として有効利用することを目的に立法されたものである。こういった理由から、対象となる建物は少なくとも年1回以上は使用している家屋でなければ民泊として利用することはできないため、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションについては民泊法の適用はできないこととされている(民泊制度ポータルサイト→民泊を行う方→対象となる住宅→居住要件とは→◆対象となる家屋(3))。
そうすると、個人事業者が民泊法の届出をして民泊営業を営む場合には、まず家事用資産として家屋を取得するわけであるから、取得した家屋は仕入税額控除の対象とすることはできないことになる。家事用資産を事業用に転用した場合であっても「みなし仕入れ」のような規定は存在しないことから、個人がセカンドハウスとして利用するために分譲マンションを取得し、副業として民泊事業を営む場合には、取得時の仕入税額控除も第3年度の課税期間における加算調整(取戻し控除)もできずに利用料収入についてだけ消費税が課税されることになりそうだ。
もっとも、民泊の利用者からインボイスの交付を求められることは実務上ほぼないであろうから、自営業者でないサラリーマンが副業で民泊事業を営む場合には、民泊事業の年間利用料収入が1,000万円以下であれば免税事業者となることができる。
Ⅴ おわりに
居住用賃貸建物を調整期間中に課税賃貸用に供した場合には、下記の算式により計算した仕入税額を加算調整(取戻し控除)することが認められている(消法35の2①③)
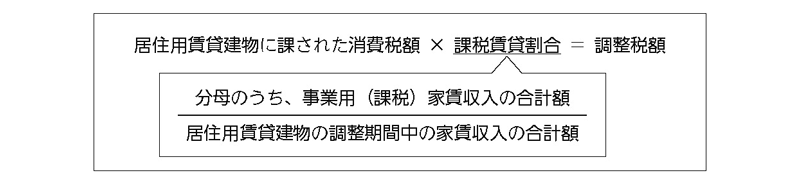
これに対し、居住用賃貸建物を合理的な基準により区分し、課税賃貸部分を仕入税額控除の対象とした後に居住賃貸用に転用したとしても、仕入税額を減算調整するという規定は存在しない。
建物に課される消費税は相対的に高額になることを思料すると、居住用賃貸建物の定義と仕入控除税額に関する取扱いについては抜本的な治療が必要ではないかと感じている。
記事に関連するお問い合わせ先
記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























