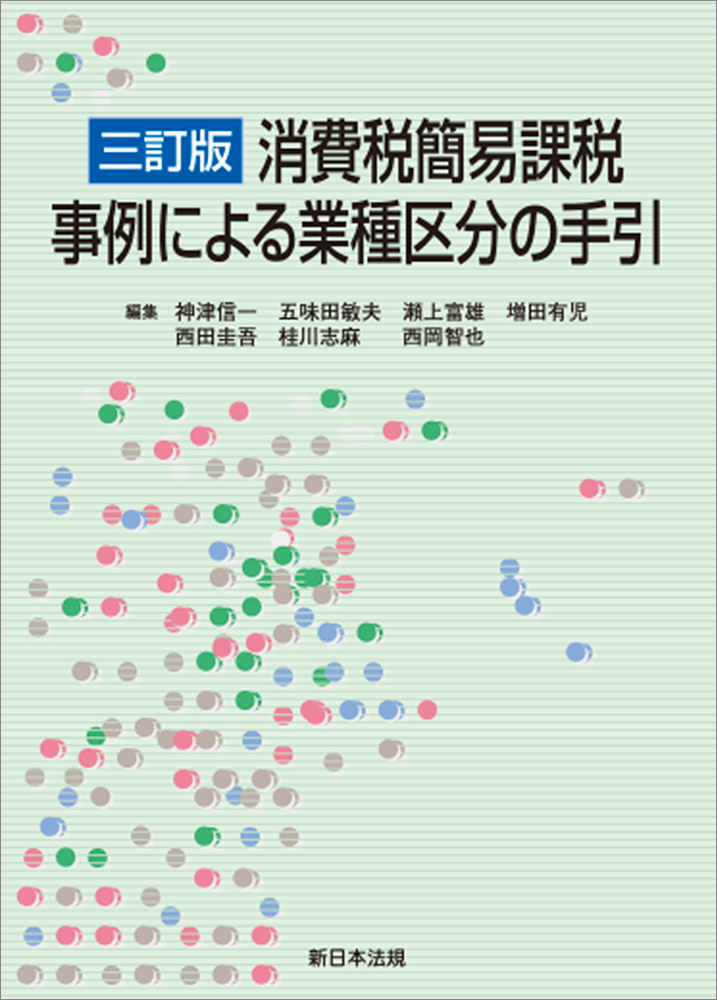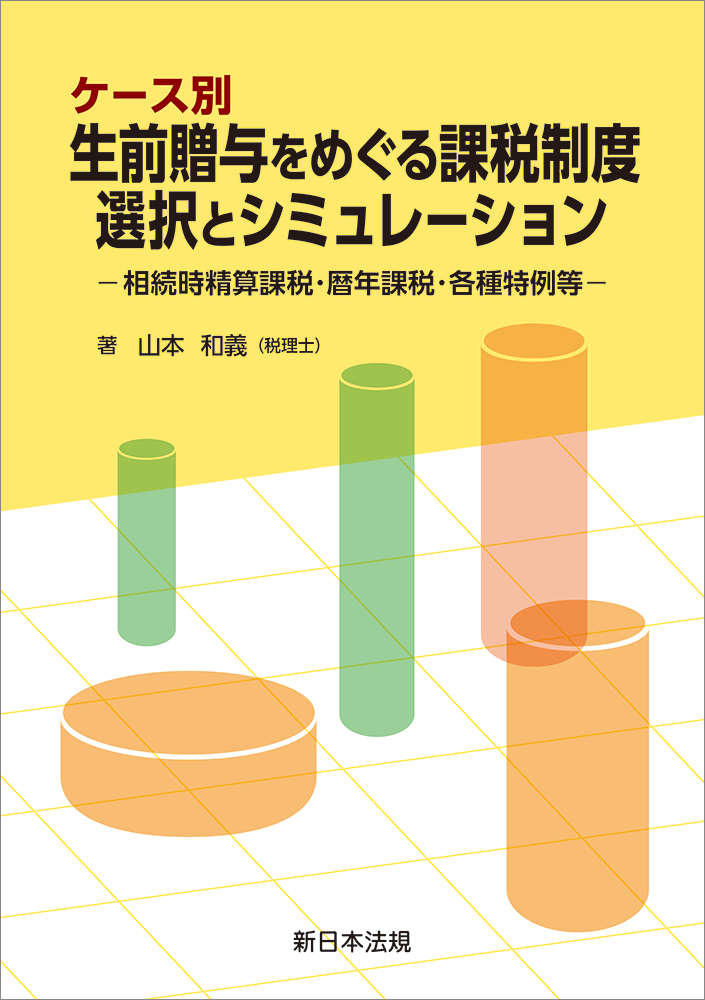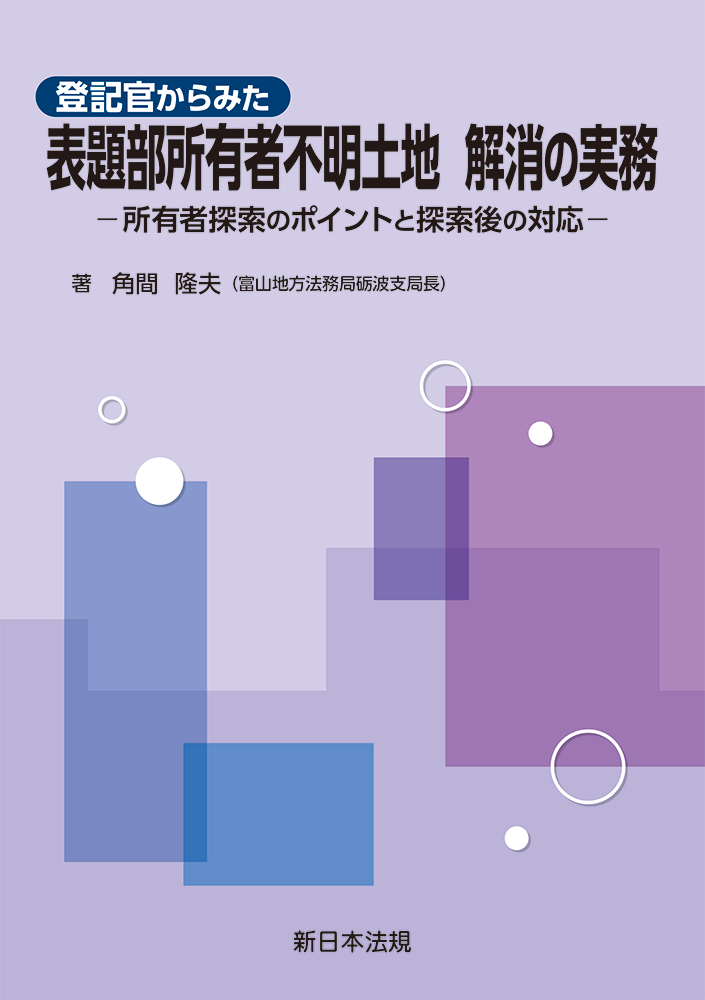解説記事2025年10月13日 論考 ステーブルコインの課題と展望(2025年10月13日号・№1094)
論考
ステーブルコインの課題と展望
神奈川大学名誉教授 葭田英人
1 はじめに
ステーブルコインは、金や法定通貨(ドルや円)などの価値と連動し、利便性と安定性を兼ね備えた仮想通貨(暗号資産)である。ビットコインなどの暗号資産は、市場の需要と供給により価格が決まるため価格変動幅が大きく、決済手段や資産運用として活用することが難しい。その点、ステーブルコインは価値が安定していることから実用性が高く、決済手段や資産運用として活用されている。
日本でのステーブルコインに関する規制は、2023年6月の「改正資金決済法」により整備されている。同法によりステーブルコインは他の暗号資産と区別され、電子決済手段として法的に規定された。発行及び償還は、銀行・資金移動業・特定信託会社のみが認められている。アメリカ合衆国では、2025年7月にジーニアス法(GENIUS法、正式名称はGuiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)が成立し、ステーブルコインを規制している。
日本においては、JPYC株式会社が資金移動業者の登録を金融庁で済ませ、日本円に連動したステーブルコインを発行する国内初のスタートアップ企業である。その後、マネックスグループもステーブルコインを発行することを検討していることを発表した。また、三井住友銀行もSBIホールディングスの子会社であるSBI VCトレードと共同でステーブルコイン発行に向けた検討を開始すると表明するなど、ステーブルコインに関する動きが活発化している。
ステーブルコインの発行体は、保有する裏付け資産から利子収入を得ることができることから、ユーザーの手数料を抑えることができ、銀行の送金やクレジットカード決済の取引量を上回る可能性がある。
そこで、本稿において、ステーブルコイン誕生の経緯やステーブルコインの特徴と仕組みを概観し、従来の仮想通貨の違いやメリットについて検討する。さらに、ステーブルコインに関する課題や今後の展望について考察する。
2 ステーブルコイン誕生の経緯
ビットコインなどの従来の仮想通貨は、価格の変動幅が大きいため、それを解消する目的でステーブルコインが誕生した。従来の仮想通貨は価格の上下が大きく投機的な利益を上げられるため、投資する者が増えた。しかし、決済や資産として安定性を欠くことから、安定した法定通貨や現物資産の価格と連動して、価値を一定に保つ目的でステーブルコインが導入された。
2023年6月1日に施行された「改正資金決済法」は、日本での法定通貨である円や日本国債、金を裏付けとするステーブルコインの発行と流通を明確に規定した。
アメリカ合衆国においては、ステーブルコインに関する規制がなかったため、2025年7月18日、ステーブルコインに関する包括的な法律であるジーニアス法が成立した。ドルに連動したステーブルコインの国際決済での利用を促し、ドルへの信頼性を高め、ドルの基軸通貨としての地位の維持を目的としている。
同法では、ドルやアメリカ国債などの資産を、ステーブルコインの発行量に応じた準備資産として保有することを義務付け、発行体は、ステーブルコインの準備資産の詳細を、毎月開示することが義務付けられている。また、マネーロンダリング防止法にも従わなければならない。
3 ステーブルコインの特徴と仕組み
ステーブルコインの主な特徴は、ドルや円といった法定通貨や現物資産の価格に連動する暗号資産であり、ビットコインのような変動の激しい暗号資産と異なり、価格が安定している点である。仕組みは担保の種類によって、法定通貨担保型ステーブルコイン、暗号資産担保型ステーブルコイン、コモディティ型ステーブルコイン、無担保型(アルゴリズム型)ステーブルコインの4種類に分類される。この安定性により、決済手段や、暗号資産取引における価値の保存手段としても利用されている。
ステーブルコインは、ブロックチェーン技術を使い、裏付け資産と価値を連動させていることから、金融機関を経由しないで低い手数料で送金や決済が可能である。ブロックチェーン技術とは、取引データを「ブロック」という単位でまとめ、暗号技術でチェーンのように連結して保管・共有する技術である。この技術により、データの改ざんを防止することができ、特定の管理者がいなくても、データを分散的に管理・共有することができるため、高い透明性、信頼性を確保することが可能である。
さらに、ステーブルコインと法定通貨との交換比率を固定化することで、特定の条件を満たせば、ドルや円などの法定通貨と交換して入手することもできる。
4 ステーブルコインと従来の仮想通貨の違い
ステーブルコインとビットコインなどの従来の仮想通貨の違いは価格の安定性である。ステーブルコインは円やドルなどの法定通貨や国債、金に価値が連動するため、価格変動が小さく、送金や決済に適している。
一方、ビットコインのような従来の仮想通貨は、法定通貨に裏付けがなく、市場の需要と供給により価格が大きく変動し、リスクが高い金融商品であり、投機対象としての役割が中心となる。
また、ビットコインなどの多くの仮想通貨は発行体や管理者が存在せず、その価値を誰かが保証するわけでもない。ユーザー同士が直接取引を行うことから分散管理されているため、トラブルが発生した場合、責任の所在が曖昧になる可能性がある。これに対し、ステーブルコインは、特定の企業が管理しているため、責任の所在が不明確になることはない。
5 ステーブルコインの種類
ステーブルコインは、裏付け資産の有無と担保方法によって、次の4種類に分類することができる。
(1)法定通貨担保型ステーブルコイン
法定通貨担保型ステーブルコインとは、円やドルなどの法定通貨を担保としてステーブルコインを発行し、法定通貨との一定の交換比率を設定し、それを固定化することにより通貨の変動率を抑制し、価格を安定化させているステーブルコインをいう。
(2)暗号資産担保型ステーブルコイン
暗号資産担保型ステーブルコインとは、ビットコインなど他の暗号資産を担保として価格を連動させる方式である。ただし、価格が安定しない他の暗号資産を担保にしても価格の安定化を図ることは難しいため、発行の際に、担保とする暗号資産を増やすなどの方策が必要である。
(3)コモディティ型ステーブルコイン
コモディティ型ステーブルコインとは、金や商品などの現物資産を担保とする方式である。金の価値は安定しているが、商品などの現物資産の価格に連動しているため、ステーブルコインの価格を安定化させるには、どんな商品を担保とするかが重要となり、相応の商品保有が必要となる。一方、金利の上昇やインフレにより担保となる現物資産の目減りが生ずるリスクがある。
(4)無担保型(アルゴリズム型)ステーブルコイン
無担保型(アルゴリズム型)ステーブルコインとは、法定通貨や他の暗号資産などを担保としないで、発行体が、ステーブルコインの供給量を増減させることにより調整し、価格の変動幅を縮小させ、ステーブルコインの価格を安定化させる方式である。
6 ステーブルコインのメリット
ステーブルコインのメリットとして、次の5つを挙げることができる。
(1)価格の安定
ステーブルコインは裏付けとしての準備資産と連動しているため、価格が安定していることから、変動幅が小さく価値を維持できるというメリットがある。ただし、担保資産の価値が暴落した場合、ステーブルコインの価格も暴落することになる。
(2)リスクの分散
ステーブルコインの担保資産として、円やドル、ユーロなどの法定通貨に分散することにより、為替の暴落など予期せぬ将来のリスクに備えることができる。さらに、ビットコインなどの価格変動が大きい暗号資産をステーブルコインに退避させることにより、暴落から資産を保護することができる。
(3)低コスト・迅速な国際送金や決済
ステーブルコインのブロックチェーン技術を活用することにより、為替手数料や中継銀行手数料もかからないことから、銀行送金に比べ安価で迅速に国際送金や決済が可能である。
(4)法定通貨の代替機能
ステーブルコインは法定通貨と連動しているので、担保通貨の代替機能があることから、海外旅行などでは、ドルと連動したステーブルコインであればドルを保有していると同じ効果があり、利用できる場所においては、両替なく決済が可能である。
(5)資産運用
ドルを裏付け資産としたステーブルコインに円を変えておけば、円安ドル高の際には、為替変動により利益を得ることができる。また、所有するステーブルコインを貸し出すことで貸出料を受け取ることもできる。
7 ステーブルコインの課題
ステーブルコインの課題として、次の4つを挙げることができる。
(1)裏付け資産の価格変動
ステーブルコインの価値は裏付け資産によって決まるため、裏付け資産の価格自体が、為替変動やインフレーションにより下落すれば、価値の維持は難しくなるというリスクがあることから、発行体は十分な裏付け資産を保有することが必要となる。また、無担保型(アルゴリズム型)ステーブルコインは、裏付け資産がないため、需給バランスが崩れると暴落する可能性があり、発行体は慎重に需給調整する必要がある。
(2)信用上の問題
ステーブルコインの発行は、民間企業が発行体となって行うため、発行体や関連企業の信用力や経営状況が悪化したり、破綻したりすることになると、裏付け資産自体を失うリスクがあり、発行体や関連企業の裏付け資産の保全状況に注意する必要がある。
(3)ハッキングやマネーロンダリング
ステーブルコインのシステムがハッキングされた場合、ユーザーは取引が困難になったり、資産を失ったりするおそれがある。また、ステーブルコインを利用したマネーロンダリングや脱税、詐欺行為に利用されるリスクがある。今後、これらを規制するための対策が必要不可欠となる。
(4)世界各国の法規制や税制
世界各国でのステーブルコインに関する法規制は整備途上であり、国によっては、ステーブルコインの発行や流通が制限されたり、禁止されたりしている可能性がある。このようにステーブルコインに関する世界規模の法構築が国ごとに異なるため、ビジネスや運用に支障をきたす可能性がある。
また、ステーブルコインに関する税制もリスク要因であり、課税強化されれば、ステーブルコインによる運用は難しくなる。各国のコンセンサスが一致した実効性のある法規制や税制は最も重要な課題であり、今後の各国の動向に注視する必要がある。
8 ステーブルコインの今後の展望
ステーブルコインは、他の仮想通貨が持つ不安定性を軽減することから誕生した。発行体は、法定通貨、国債、金などの担保資産を裏付けとし、ブロックチェーン技術を基盤としたステーブルコインを発行・運用することで、裏付け資産から得られる運用益や手数料収入を得ることができる。
ユーザーは、ビットコインなどの暗号資産と異なり、法定通貨に連動し、価格変動が少なく、安定した決済手段や送金手段として利用することができる。つまり、ブロックチェーン技術を活用するため、銀行の営業時間や国際送金ネットワークに影響されず、リアルタイムで低コストな送金が可能となる。
さらに、保有するステーブルコインを一時的に第三者(取引所や企業、個人など)に貸し出すことで、貸出料を得ることができ、保有するステーブルコインを運用して収益を得ることも可能である。また、為替変動に対応することにより、ステーブルコインは安定した価値の保存手段として機能することもできる。
このように、ステーブルコインは、低コスト・高効率な決済システムとしての利用拡大や国際送金への活用など、将来性は非常に高く、特に、企業間取引や貿易へ活用する動きが進んでおり、より多様な分野で社会インフラとして浸透していくものと考えられる。
一方、ステーブルコインの利用が拡大されれば、銀行送金やクレジットカードでの決済が減少し、銀行の手数料収入が減少し、収益が圧迫されることから、銀行と非銀行間(ステーブルコインの発行体)での競争激化が予想される。
ステーブルコインは、投資より資産を守る使い方が中心となるであろうが、金融システムに革命的変革をもたらすことになり、新たな金融サービスの構築と業務効率化に大きく貢献することになると考えられる。一方、リスクや弊害もあることから、法令遵守、信頼性の維持などの国際的な規制の適切な整備とサイバー攻撃や情報漏洩リスクから情報資産を守るセキュリティの確保が必要不可欠な課題となる。
葭田英人 よしだ ひでと
筑波大学大学院修了。神奈川大学名誉教授、YAP代表。専門分野は、会社法・税法。近著は『コーポレートガバナンスと社外取締役・社外監査役』(三省堂・2020)、『会社法入門(第六版)』(同文舘出版・2020)、『合同会社の法制度と税制(第三版)』(税務経理協会・2019)など他多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -