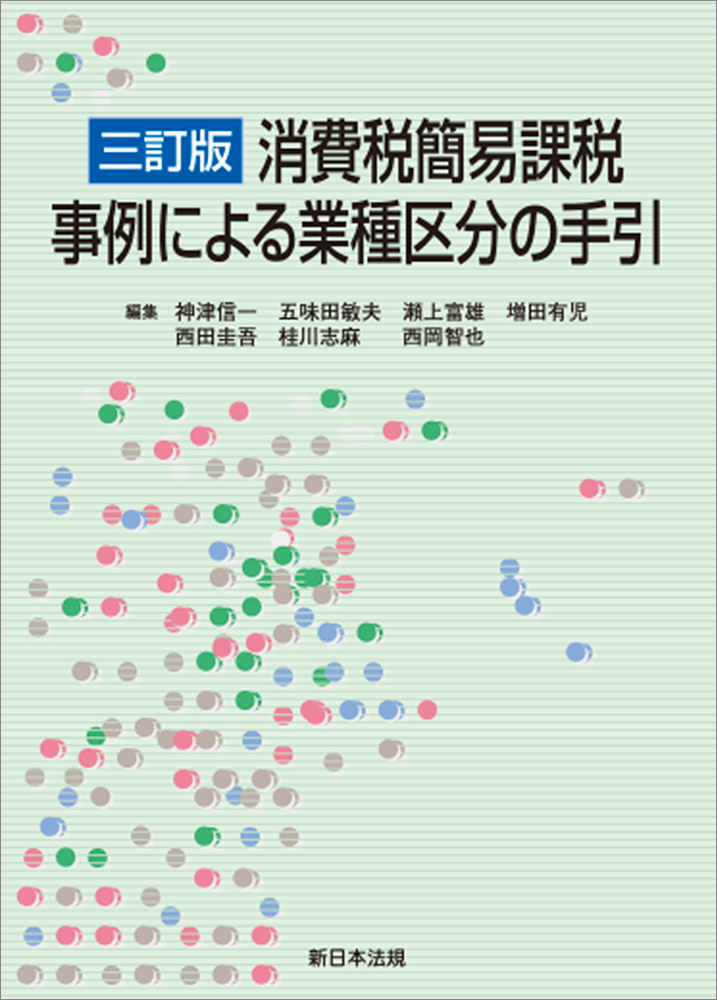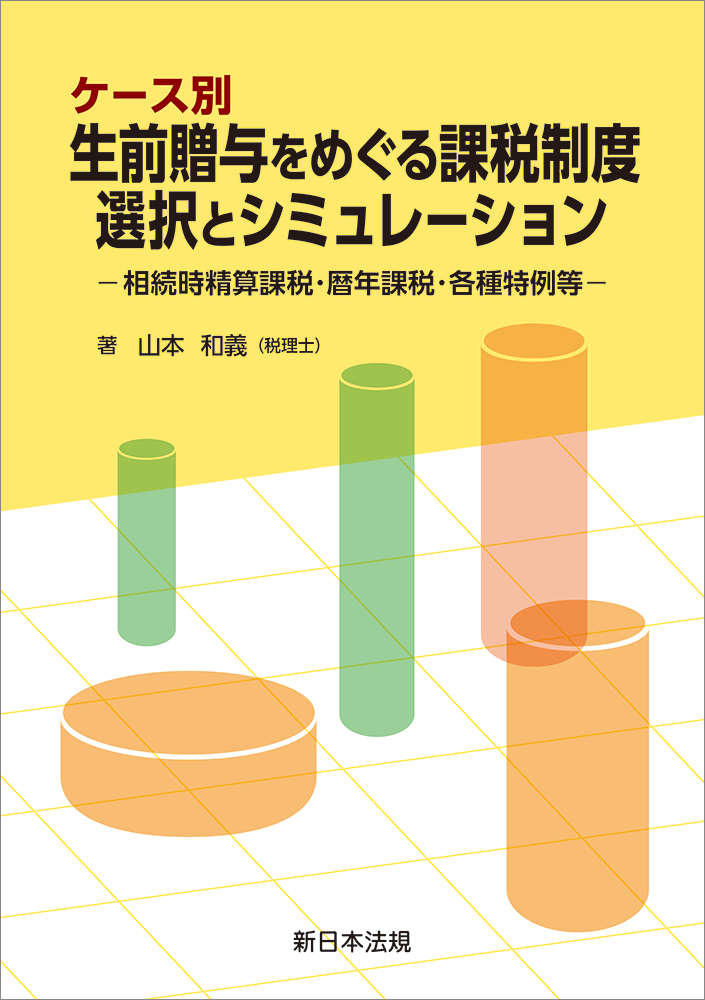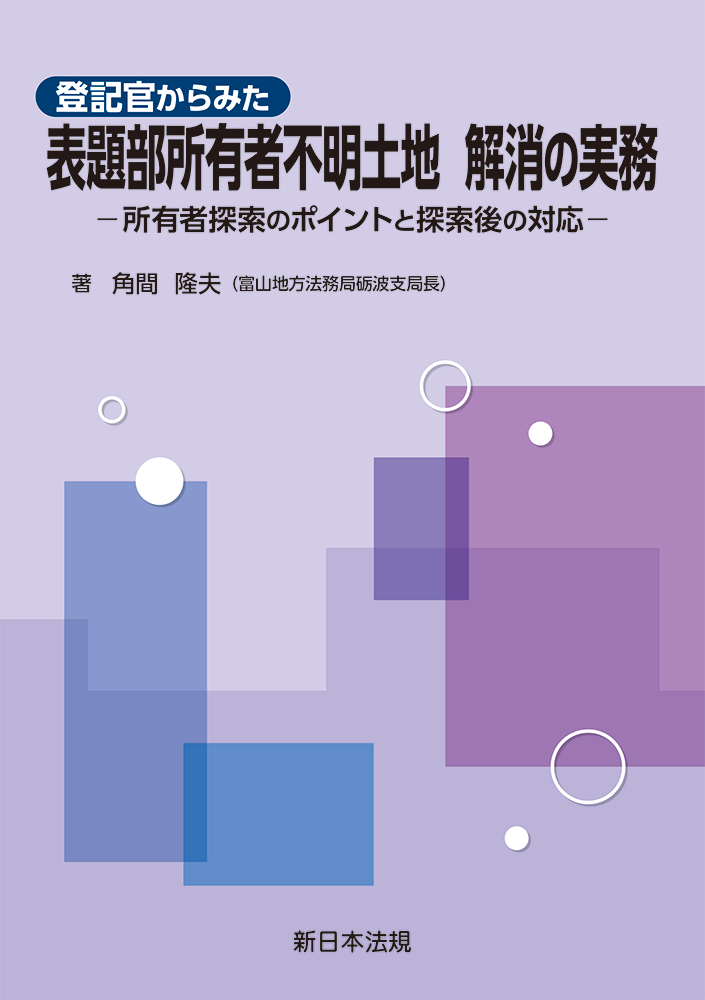解説記事2025年10月13日 SCOPE 東京高裁も原判決支持、保険外交員は個人事業税の対象(2025年10月13日号・№1094)
代理権のない媒介業務も「代理業」に該当
東京高裁も原判決支持、保険外交員は個人事業税の対象
既報の通り、保険外交員の業務が個人事業税の課税対象となる「代理業」に該当するか否かが争われた事案の一審では納税者側が敗訴したところ(本誌1067号参照)。地方税法が「代理業」の定義を規定していないことから「代理業」の意義が争われたが、納税者側の『代理権を有しない者が行う取引の「媒介」業務は「代理業」に該当しない』との主張に対し東京地裁は、商法27条が定義する「代理商」の業務の内容に基づき、「媒介」も含まれるとの解釈を示していた。
東京高裁も原判決を支持し、令和7年10月2日、納税者の控訴を棄却した。
使用人が行う取引の媒介業務も「代理業」に該当
本件では、個人事業税の課税対象となる「代理業」(地方税法72条の2⑧二十三)の意義、具体的には、代理権を有しない者が行う取引の媒介業務が「代理業」に当たるか否かが争点となった。
一審の東京地裁は、「代理業」の意義について、反対の解釈をすべき特段の事由がない限り、商法(同条1条)の規定と整合的に解釈することが相当との考えを示した。その上で、個人事業税に係る規定の内容や趣旨、事業税の性格等に照らしても、「代理業」の意義について、商法27条(表1参照)が定義する「代理商」の業務の内容と異なる解釈をすべき特段の事由は見当たらないとした。
(通知義務)
|
さらに東京地裁は、所得税法上の事業所得に関する解釈も踏まえて、「代理業」とは「自己の計算と危険において独立して反復継続的に営まれる事業であって、手数料等の報酬の収得を目的として、一定の商人のために、その平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をするもの」との解釈を示した。
原判決を不服とした原告は控訴し、表2のとおり補充主張を行った。
| ① | ・地方税法は「代理業」の別段の定義を置いていないから、その文言を離れずに解釈すれば代理権を有して行う業務と解するほかない。 ・代理権がなくとも「代理業」に含まれるのは、その旨の別段の定義規定が置かれた場合に限られる。(例:銀行法、旅館業法) ・地方税法が課税客体となる事業を限定列挙した趣旨からすれば、法定事業の要件を拡張的に解釈することは許されず、「代理業」を「代理又は媒介」を行う「業」と拡張的に解釈することは許されない。 |
| ② | ・「代理業」の意義を商法と整合的に解釈するのであれば、「代理」に代理権のない場合を含まない同法504条と整合的に解釈すべき。 ・仮に同法27条を参酌するとしても、同法は、その文言上、代理権を有して行う「取引の代理」と代理権を有しないで行う「取引の……媒介」とが区別されることを前提としているから、「取引の代理」を参酌すべき。 |
| ③ | ・控訴人らは、本件生命保険会社の使用人であり、商法27条によれば、使用人が行う業務は「代理商」ではないとされている以上、「代理業」ではないと解釈するほかない。 |
これに対し東京高裁は、まず控訴人の表2①の主張に対しては、①関連する商法27条の「代理商」の業務の内容に照らして取引の代理又は仲介をする事業と解したからといって、許されない拡張解釈をするものとはいえない、②控訴人らが指摘する銀行法や旅館業法は、それぞれの趣旨・目的を踏まえた定義規定を置く事により当該法律における「代理業」の範囲を画しているにすぎず、定義規定がない他の法律における「代理業」の解釈について一定の方向性を示唆するものとはいえない、③地方税法が個人事業税の課税客体を限定列挙したのは課税技術上の観点によるものと解され、限定列挙されていることから「代理業」について代理権を有する場合に限られるとの解釈が導かれるものではないとして、その主張を排斥した。
また、控訴人の表2②の主張に対しては、①商法504条は、商行為の代理について民法100条のいわゆる顕名主義の特則としてその効果帰属の関係を規定したものであり、「代理業」の解釈において参酌すべきものとはいえない、②商法27条の「代理商」は、その業務の内容として代理と媒介の双方を含むものとされている以上、「代理業」の業務内容を解釈するに当たって、その一方のみを参酌すべきとする合理的な理由はないとして、この主張も排斥した。
さらに、控訴人の表2③の主張についても、「『代理業』の意義を解釈するに当たって商法27条の『代理商』の定義のうち業務の内容に係る部分とは整合的に解釈すべきであるが、人的要素に係る部分すなわち『その商人の使用人ではない』ことと整合させる必要はなく、個人の事業が『代理業』に当たるか否かは当該個人が使用人であるか否かとは関係なく判断されるべきものであり、商人の使用人が使用人として行う業務が『代理業』に当たる場合があるとしても、文理解釈として不合理とはいえない」として排斥した。
なお、補足的な検討として、控訴人らの業務の実態等から、控訴人らの業務は使用人として行う業務とは認められないとの考えが既に原判決で示されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -