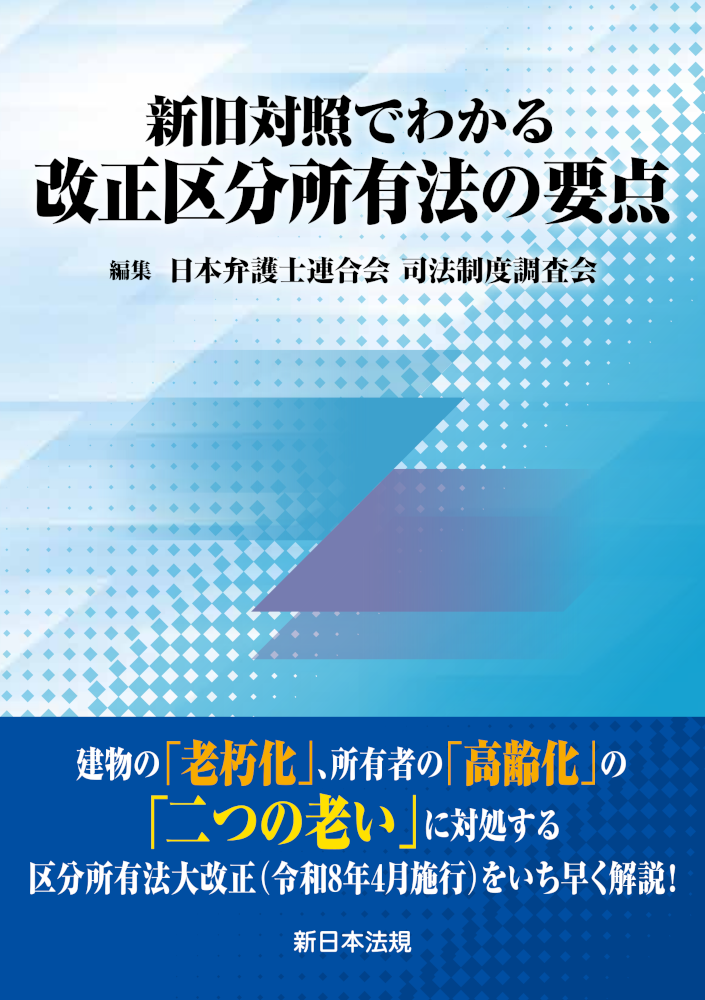解説記事2020年05月04日 税務マエストロ 非上場株式に係るみなし譲渡課税における時価(1)(2020年5月4日号・№833) -令和2年3月24日最高裁判決に敷衍して-
税務マエストロ
非上場株式に係るみなし譲渡課税における時価(1)
-令和2年3月24日最高裁判決に敷衍して-
#246
税理士 梶野研二
略歴
国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長などを経て、平成25年6月税理士登録。現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。○主な著書 「ケース別相続土地の評価減」、「非公開株式評価実務マニュアル」(新日本法規)、「判例・裁決にみる非公開株式評価の実務」(共著)(新日本法規)、「株式・公社債評価の実務」、「土地評価の実務」(共著)(大蔵財務協会)
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
今回のテーマ
個人株主が法人に対して、譲渡所得の基因となる資産である株式を無償又は時価の2分の1未満の対価の額で譲渡した場合には、所得税法第59条第1項の規定により、その株式を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得課税が行われる。譲渡資産が非上場会社の株式である場合には、時価の把握は容易ではなく、したがって、「時価の2分の1未満の対価の額」で行われた譲渡であるかどうかの判断は難しいが、実務上、所得税基本通達の定めに従ってその判定がされているところである。
この通達の適用について争われた事件について、このほど最高裁判所の判決があったので、本稿ではこの事件について紹介するとともに、あらためて同通達の定めについて検討することとする。
マエストロの解説
1 みなし譲渡課税
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属することとなった増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するものである(昭和43年10月31日最高裁第一小法廷判決、昭和47年12月26日最高裁第三小法廷判決など)。したがって、この譲渡所得に対する課税においては、本来、譲渡が有償で行われたものであるか無償で行われたものであるか、また、有償で行われた場合にその譲渡価額が時価相当額であるか時価よりも低額であるかどうかを問わないはずである。しかしながら、所得税法においては、譲渡所得金額を計算する場合の収入金額は、別段の定めがある場合を除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることとされている(所法36①)ため、所得税法等に特段の定めがない限り、無償の移転である相続、遺贈又は個人間の贈与による資産の移転については、原則として、移転を契機とした譲渡所得に対する課税は行われず(脚注1)、また、時価よりも低い価額の対価で譲渡が行われた場合には当該時価よりも低い対価の額を収入金額として譲渡所得金額の計算を行うこととなる。
このような譲渡所得の原則的な課税方法の例外として設けられた別段の定めの一つが、所得税法第59条第1項の規定である。同条第1項は、次のとおり定め、法人に対して行われた対価の授受が行われない無償の譲渡(贈与及び遺贈)や対価の額がその財産の譲渡時の時価に比して著しく低額である一定の譲渡があった場合に、譲渡時の時価に相当する金額を対価の額として譲渡があったものとみなして譲渡所得課税を行うこととしている。
○ 所得税法
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第59条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2 (省略)
○ 所得税法施行令
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
第169条 法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。
この規定の適用に当たって問題となるのが、譲渡した資産の「譲渡の時における価額」である。これについては、譲渡所得の基因となる資産の移転の事由が生じた時点における時価、すなわち、その時点における当該資産の客観的交換価値を指すものと解すべきであり、この交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であると解されている(平成26年4月23日東京高裁判決、平成28年9月8日東京高裁判決など)。
しかしながら、取引相場のない株式については、そもそも自由な取引市場が存在しないため、自由な取引を前提とする客観的交換価値の把握は極めて困難であって、でき得る限り合理的な方法によってこれを推認せざるを得ない(脚注2)。このため、実務上、次のとおり相続税及び贈与税における財産評価のための通達である財産評価基本通達の定めを一部修正して、所得税法第59条第1項における「譲渡の時の価額」の算定が行われているところである。
○ 所得税基本通達
(株式等を取得する権利の価額)
23~35共-9 令第84条第2項第1号及び第2号に掲げる権利の行使の日又は同項第3号に掲げる権利に基づく払込み若しくは給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同条第2項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。
(1)これらの権利の行使により取得する株式が金融商品取引所に上場されている場合当該株式につき金融商品取引法第130条の規定により公表された最終の価格(同日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)とする。
(2)これらの権利の行使により取得する株式に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合において、当該株式が上場されていないとき当該旧株の最終の価格を基準として当該株式につき合理的に計算した価額とする。
(3)(1)の株式及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該株式又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額とする。
(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ 売買実例のあるもの最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
ロ 公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。)金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの当該価額に比準して推定した価額
ニ イからハまでに該当しないもの権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)この取扱いは、令第354条第2項((新株予約権の行使に関する調書))に規定する「当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の1株当たりの価額」について準用する。
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23〜35共−9に準じて算定した価額による。この場合、23〜35共−9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189−7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。
(1)財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2)当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189−3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3)当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4)財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
この所得税基本通達59−6中に、「原則として」との文言があるように、この通達の定めによって算定された価額が、常に唯一絶対の時価とされるわけではなく、利害が相対立する当事者の間で種々の経済性を考慮して決定された価額であれば、この通達の定めにかかわらず、それが時価と認められる(脚注3)(この点については、後述する。)。
なお、法人税基本通達においても同様の定めが設けられている(脚注4)が、本稿では、所得税基本通達を前提として説明し、必要に応じて、法人税基本通達について言及することとする。
2 所得税基本通達59−6の適用方法が争点となった裁判例
次に紹介する事件は、この所得税基本通達59−6の適用及び非上場株式の株式の時価について争われた事件である。
本事件は、T社の代表取締役であった被相続人Kが、自身の有していたT社の株式のうち72万5000株(以下「本件株式」という。)を、平成19年8月1日、S社に対して譲渡(以下「本件株式譲渡」という。)したことにつき、その相続人らが、その株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ金額(配当還元方式により算定した価額)として、被相続人の所得税の申告(準確定申告)をしたところ、所轄税務署長が、本件株式の譲渡対価はその時における本件株式の価額(類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから、本件株式譲渡は所得税法第59条第1項第2号の低額譲渡に当たるとして、所得税の更正処分をしたことから、相続人である納税者らが、これらの処分の取消しを求めた事件である。
所得税基本通達59−6は、非上場会社の株式を譲渡した場合の所得税法第59条第1項の規定を適用する際の当該株式の価額の評価方法について定めているところ、この通達では4項目の条件を付したうえで、譲渡した非上場会社の株式の価額を、財産評価基本通達の定めの例により評価した価額とする旨を定めている。この事件は、この4項目の条件のうちの「(1)財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」を巡って争われたものである(脚注5)。第一審東京地裁判決は、譲渡所得課税の趣旨から課税庁の主張を認めたのに対し、第二審東京高裁判決は通達の文言を重視して納税者らの主張を認めた。最高裁判所は、原審判決には所得税法第59条第1項の解釈適用を誤った違法があるとして、原審判決を破棄し、本件株式の価額についてさらに審理をつくさせるべく原審に差し戻した。
(1)事実関係(脚注6)
イ 関係者
(イ)T社(本件株式の発行会社)
T社は、昭和25年9月に設立された、金属製品及び消防器材の製造及び販売等を業とする資本金4億6,000万円の株式会社である。T社の販売主力商品は、ハンドル・取手、錠前・ファスナー、蝶番・ステー等であり、本件株式譲渡の直前の事業年度である平成19年1月期の売上金額は約236億5,000万円、平成19年1月現在の従業員数は449人である。本件株式譲渡の時点(平成19年8月1日)において、T社の発行済株式総数は920万株であり、T社の株主は、1株につき1個の議決権を有する。また、T社においては、定款においてその株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めている。本件株式譲渡の時点において、T社は、評価通達178に規定する「大会社」に、T社の株式は、所得税基本通達23〜35共−9の(4)ニの株式及び評価通達における「取引相場のない株式」に、それぞれ該当する。
なお、本件株式譲渡前後のT社の株主構成は後記ハのとおりである。
(ロ)S社(本件株式の譲受会社)
S社は、平成16年2月に金銭の貸付業、株式投資業等を目的として設立された会社であり、設立時以降の株主は、全てT社の役員又は従業員である(S社は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行前の有限会社であるが、以下では、その社員を「株主」と表記する。)。
(ハ)K(本件株式の譲渡者)
Kは、本件株式譲渡の当時(平成19年8月1日)、T社の代表取締役社長の地位にあった者であり、平成19年12月○日死亡した。
ロ 本件株式の譲渡について
Kは、平成19年8月1日、S社に対し、自己が有するT社の株式146万700株のうち72万5,000株(本件株式)を、1株当たり75円、合計5,437万5,000円で譲渡した(以下「本件譲渡」という。)。1株当たり75円という譲渡価額は、本件株式を配当還元方式により評価して得た金額と同額である。本件株式譲渡について、Kは、自身の相続に係る相続税対策という目的を有していた(第一審認定事実)。
ハ 本件譲渡前後におけるT社の株主構成
T社の株主構成及び各株主の議決権割合は次頁図表1、図表2のとおりである。
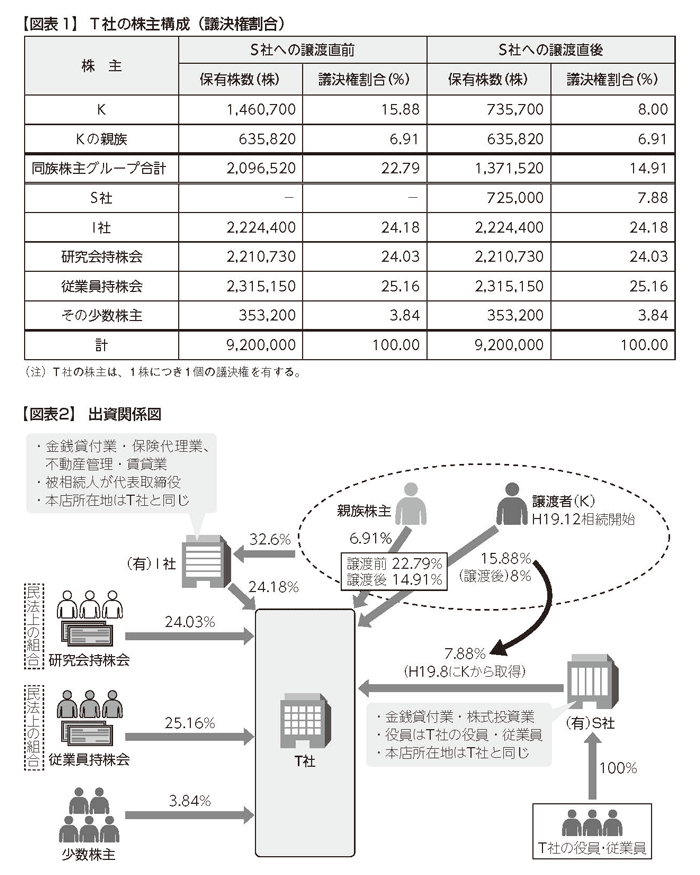
(2)本事件の争点
本事件の争点は、本件株式譲渡が所得税法第59条第1項第2号に規定する低額譲渡に該当するかどうかであるが、この争点は、さらに①所得税基本通達59−6(1)の条件下における評価通達188の議決権割合の判定(争点①)、及び②本件株式譲渡における譲渡代金額をもって時価といえるかどうか(争点②)の2つの争点に分けることができる。
(3)当事者の主張(次頁図表3、図表4参照)
【図表3】争点①(所得税基本通達59−6(1)の条件下における評価通達188の議決権割合の判定方法)について
| 納税者らの主張 | 課税庁の主張 |
| 1 所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式の価額につき、一定の条件の下で評価通達の例により算定すべきものと規定し、その条件としての(1)は、評価通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権の数により判定すると規定している。他方で、同様の条件は評価通達188の(2)〜(4)については規定されていない。そうすると、評価通達188の(3)のうち、「同族株主のいない会社」であるかどうかの判定は、所得税基本通達59−6の(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行うことになるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定は、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当である。このような評価通達の文言に忠実な解釈は、実務上、通達も法律に準じ広く一般に周知され、納税者の指針となっていることに鑑みれば、租税法律主義の下で課税に関する予測可能性を保障するという要請に適うものといえる。また、所得税法第59条第1項の趣旨は、譲渡人に帰属するキャピタル・ゲインの清算課税を行うというものであるが、このことから直ちに株式の価額の評価を譲渡人の議決権割合に基づいてすべきということにはならず、清算すべき「その時における価額」、すなわち客観的交換価値の評価の在り方が問題となる。取引相場のない株式の売買を行う場合には、譲受人が取得株式に期待するものが何かという譲受人側の事情が、取引価額の決定要素となり、譲受人が少数株主となる場合には配当を期待して売買価額を決定することになるため、配当還元方式により評価することが合理的である。以上によれば、評価通達188の(3)における株主区分の判定は、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うべきである。 | 1 所得税基本通達59−6(1)は、取引相場のない株式について、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権割合により、評価通達188の定めに基づき、当該株式が「同族株主以外の株主等が取得した株式」に当たるか否かを判断すべきことを定めたものである。これは、譲渡所得課税制度の趣旨が、譲渡人に帰属する資産の保有期間中の増加益を所得として課税する点にあることからすれば、その増加益は株式の譲渡人の譲渡直前の議決権割合により判定することが最も合理的といえるためである。 |
| 2 本件株式譲渡の直前において、T社には、自己及びその同族関係者が30%以上の議決権を有する株主がいないから、T社は「同族株主のいない会社」である。そして、S社の本件株式取得後の議決権割合は、7.88%であり、S社には同族関係者がおらず、その議決権割合は15%未満にとどまる。したがって、本件株式は、評価通達188の(3)の株式に該当するから、評価通達188− 2に従い、配当還元方式により評価すべきことになる。 | 2 本件株式譲渡の直前において、自己及びその同族関係者の有するT社の議決権の合計数が同社の議決権総数の30%以上である株主(同族株主)はいないから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式に該当しない。また、本件株式譲渡の直前において、K及びその同族関係者は、T社の議決権総数の15%以上(22.79%)の議決権を有し、かつ、K個人も、T社の議決権総数の5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。したがって、本件株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないから、評価通達178本文、179の(1)により、原則的評価方法である類似業種比準方式により評価すべきことになる。 |
| 3 よって、本件株式譲渡の時における本件株式の価額は、1 株当たり75円と評価され、本件株式譲渡の対価はこれと同額であるから、本件株式譲渡は、所得税法第59条第1 項第2 号の低額譲渡には当たらない。 | 3 よって、本件株式譲渡の時における本件株式の価額は、1株当たり2,505円であり、本件株式譲渡は、この価額の2分の1に満たない金額によるものであるから、所得税法第59 条第1項第2号の低額譲渡に当たる。 |
【図表4】争点②(本件株式譲渡における譲渡代金額をもって時価といえるか)について
| 納税者の主張 | 課税庁の主張 |
| 1 所得税法上の低額譲渡の場合における適正価額 の認定は、動態的評価の場面である。資産を売買する場合のような動態的評価の場面では、同じ資産であっても、売買に至る経緯や事情等の主観的要因により成立する取引価額は異なるから、当該取引の売買価額が適正であるかどうかの判断は、相当な幅をもって弾力的に行うべきである。そして、市場が形成されていない非上場株式等の動態的評価の場合には、客観的な市場価額が存在しないことに加え、当該株式の議決権の程度等の経営参画の法的度合いが異なるなど売買価額の形成に影響を及ぼす個別的要因を考慮する必要がある点で、適正価額の認定には極めて困難を伴う。そのため、利害相反する第三者間で成立した売買価額は、税務上、原則として正常な取引条件で成立した適正価額(時価)と取り扱われることになる。 |
|
| 2 本件の場合、S社は、既存のT社の持株会を補完するものとしてT社の役員や従業員の福利厚生を目的に設立され、現に株主の負担においてS社への出資がされており、S社から株主への配当もされている等、S社は、Kとは独立した第三者であり、本件株式譲渡は、利害相反する第三者間で行われたものである。そして、T社の少数株主となるにすぎないS社にとって、本件株式の実質的な経済的価値は配当への期待のみであり、このような買主の主観的事情を考慮すれば、本件株式を配当還元方式により評価することは当然であるから、本件株式譲渡は「時価」によりなされたものである。 | 1 Kは、T社の株主でもあるI社及びT社の役員らがKの実効支配下にあったことなどから、T 社のみならず、T社の役員らが株主であるS 社においても極めて強い権限を有しており、これらの会社では、本件株式譲渡の前後を通じて株主総会や取締役会が開催されたことはなく、株式の移動や人事、報酬などの株主総会や取締役会で決定される事項は、全てKが意思決定をするというKによる実効支配体制が確立していた。そして、本件株式譲渡の譲渡価額を決定するに当たり、KやS社において合理的な検討はされておらず、本件株式譲渡は、K一族が有するT社の議決権割合を15%未満にして相続税負担を軽減させることを目的に行われたものである。以上によれば、本件株式譲渡における譲渡価額は、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して算定されたものではなく、時価であるとはいえない。 |
| 3 よって、本件株式譲渡は、時価による譲渡であるため、評価通達の解釈を論ずるまでもなく、所得税法第59条第1項第2号の低額譲渡には当たらない。 | 2 よって、本件株式譲渡は、時価による取引であるとはいえず、前記のとおり、譲渡の時の価額の2分の1に満たない金額によるものであるから、所得税法第59条第1項第2号の低額譲渡に当たる。 |
(4)平成29年8月30日東京地裁判決(平成24年(行ウ)185号)(税資13045順号)
イ 所得税基本通達59−6の規定
所得税基本通達59−6が評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の一定の条件として規定した内容の合理性について検討すると、そもそもそのような一定の条件を設けたのは、評価通達が本来的には相続税や贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであって、譲渡所得の収入金額の計算とは適用場面が異なることから、評価通達を譲渡所得の収入金額の計算の趣旨に則して用いることを可能にするためであると解される。
すなわち、相続税や贈与税が、相続や贈与による財産の移転があった場合にその財産の価額を課税価格としてその財産を取得した者に課される税であるのに対し、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算してその譲渡人である元の所有者に課税する趣旨のものと解されるのであって、そのような課税の趣旨からすれば、譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当であるから、評価通達188の(1)~(4)の定めを取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算上当該株式のその譲渡の時における価額の算定に適用する場合には、各定め中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株主の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当であり、また、各定め中のそれぞれの議決権の数も当該株式の譲渡直前の議決権の数によることが相当であると解される。
所得税基本通達59−6(1)が、評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権の数により判定する旨を定めているのは、上記の趣旨を「同族株主」の判定について確認的に規定したものであり、上記の読替え等をした上で評価通達188の(1)から(4)の定めを適用すべきであることを当然の前提とするものと解されるから、この規定もまた一般的な合理性を有すると認められる。
ロ 所得税基本通達59−6の文理解釈について
納税者らは、所得税基本通達59−6の(1)が評価通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかの判定に限り、譲渡直前の議決権の数による旨定めていることの文理解釈によれば、評価通達188(3)の株主区分の判定においては、所得税基本通達59−6(1)は適用されず、譲渡後の譲受人の議決権割合により判定すべきであるとも主張する。
しかしながら、評価通達188(3)が一文で定める株式の要件に関して納税者らが主張するような異なる判断基準を混在させることに合理的な理由は見出し難く、譲渡所得に対する課税の趣旨に鑑みれば、上記イのとおりに解釈するのが相当である。譲渡所得に対する課税の趣旨から上記のような解釈を導き出すことはさほど困難なことではないから、このように解しても課税に関する予測可能性を損なうとはいえない。
ハ 本件株式の時価
本件株式譲渡直前の時点において、T社には合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がおらず、T社は「同族株主のいない会社」に当たるから、本件株式は、評価通達188(1)及び(2)の株式には該当しない。また、本件株式譲渡直前の時点において、譲渡人であるK及びその同族関係者であるKの親族らは、合計して15%以上(22.79%)の議決権を有し、K個人も5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188(3)及び(4)の株式にも該当しない。よって、本件株式は、評価通達188の株式のいずれにも該当しないから、評価通達178本文、179の(1)により類似業種比準方式により評価すべきこととなる。そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、その評価額は1株当たり2,505円となることが認められる。
ニ 特別の事情の有無
本件株式の譲渡人であるKの側から見れば、Kは、本件株式譲渡前には、単独でも15.88%の議決権割合となる株式を有していたものであり、これを一括して他に譲渡するか、又はその一部に限って譲渡するとしても、その譲渡する議決権を合わせたT社での議決権割合が15%以上となるような株主に対してこれを譲渡していれば、本件株式譲渡の譲渡対価(1株当たり75円)よりも高額の類似業種比準方式による評価額(1株当たり2,505円)に相当する金額程度の対価を得られる可能性があり、また、Kが株主としての会社支配力の低下等を懸念してそのような譲渡を望まず、あるいはそのような譲渡に応じる者がいないというのであれば、譲渡しないこともできたのに、あえてその有する株式のうちの一部のみをS社に対して譲渡したことによって、本件株式が事業経営への影響力が著しく減退した少数株式となり、配当還元方式による評価額相当の低額な対価を得るにとどまったものである。このような譲渡をしたことの目的としては、Kの側では、自己が代表取締役社長を務めるT社の役員及び従業員が株主になっていて、平時においては敵対的な議決権行使等をしないことが一般的に期待できるS社に本件株式のみを譲渡することによって、T社における経営の安定を一定程度保持しつつ、本件株式の譲渡による対価収入を減らしてでも、自身の相続人の相続税の負担を軽減するということ以外には考え難く、譲渡対価による収益を目的とする通常の取引としての合理性には乏しいものといわざるを得ない。また、本件株式譲渡において、Kの有する資産としての価値が真摯に検討されて、S社との交渉を経るなどして本件株式の譲渡価額が決定されたといった事情も認められない。
以上のような本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡を納税者らのいう利害相反する第三者間の取引(正常な株式の売買)とみることはできず、その対価をもって本件株式の時価(客観的交換価値)ということはできない。その他、本件の全証拠によっても、類似業種比準方式によっては本件株式の客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情があるとは認められない。
ホ 結論
以上によれば、所得税法第59条第1項第2
号の適用に当たって、本件株式の譲渡の時における本件株式の価額は1株当たり2,505円であると認められ、本件株式の譲渡の対価である1株当たり75円はその2分の1に満たないから、本件株式の譲渡は、同号の低額譲渡に当たる。
(5)平成30年7月19日東京高裁判決(平成29年(行コ)第283号)(税資13172順号)
イ 所得税基本通達59−6
本件では、所得税基本通達59−6の定める(1)から(4)までの条件のうち、(1)が妥当する範囲とその合理性の有無が問題となる。すなわち、所得税基本通達59−6の(1)は、評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の条件として、「財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」と定めている。これは、評価通達188の(1)は、「同族株主」につき、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上等である場合におけるその株主及びその同族関係者としているところ、その文理解釈だけでは、30%以上等である場合が、株式譲渡前の議決権について述べているのか、譲渡後の議決権について述べているのかは必ずしも明らかではないため、譲渡所得に対する課税が、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するという趣旨から、30%以上等という基準は、株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権割合により判定すべきことを定めたということができ、このこと自体の合理性は認めることができる。
ところが、被控訴人(国)は、更に進んで、譲渡所得に対する課税の上記の趣旨から、評価通達188の(2)から(4)までに係る株主区分の判定についても、譲渡人の株式譲渡直前の議決権割合により判定する旨を主張している。評価通達188の(2)及び(4)には、「株式取得後」と、同(2)から(4)までには「取得した株式」との文言があり、その文理からすると、株式譲渡後の譲受人の議決権割合を述べていることが明らかであるから、被控訴人(国))主張のように理解するためには、同(2)及び(4)の「株式取得後」との文言を「株式譲渡前」と、同(2)から(4)までの「取得した株式」との文言を「譲渡した株式」と、それぞれ読み替えることを要し、所得税基本通達59−6の(1)は、そのような読み替えを定めたものと理解することが必要となる。
ロ 通達の解釈
租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うことは許されないと解されるところ、所得税基本通達及び評価通達は租税法規そのものではないものの、課税庁による租税法規の解釈適用の統一に極めて重要な役割を果たしており、一般にも公開されて納税者が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば、課税に関する納税者の信頼及び予見可能性を確保する見地から、上記各通達の意味内容についてもその文理に忠実に解釈するのが相当であり、通達の文言を殊更に読み替えて異なる内容のものとして適用することは許されないというべきである。本件においては、本件株式が評価通達188(3)の株式に該当するかどうかが争われているところ、上記のとおり、所得税基本通達59−6(1)が、評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかについて株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権の数により判定する旨を定める一方で、同(2)から(4)までについて何ら触れていないことからすれば、同(3)の「同族株主のいない会社」に当たるかどうかの判定(会社区分の判定)については、それが同(1)の「同族株主のいる会社」の対概念として定められていることに照らし、所得税基本通達59−6(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行われるものと解されるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定(株主区分の判定)については、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により判定されるものと解するのが相当である。
ハ 所得税基本通達59−6の解釈
被控訴人(国)は、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税するという趣旨から、評価通達188(2)から(4)までについて、譲渡人の株式譲渡直前の議決権割合により判定する旨を主張している。
しかし、そのような解釈をするためには、上記のような「読み替え」が必要となるが、所得税基本通達59−6(1)の文言は、評価通達188(1)の「同族株主」について述べているのであるから、評価通達188(2)から(4)までの「同族株主」以外の部分までが上記のように読み替えられて適用される旨を読み取ることは、一般の納税者にとっては困難である。
しかも、被控訴人(国)の主張する譲渡所得に対する課税の趣旨から、上記「読み替え」を導き出すこと自体、所得税基本通達59−6の(1)があっても無理があるといわなければならない。すなわち、所得税法第59条第1項にいう「その時における価額」は、譲渡の時における資産の客観的交換価値で、不特定多数の独立当事者間の自由な取引において通常成立すると認められる価額(時価)を意味するのであり、譲渡人が会社支配権を有する多数の株式を保有する場合には、当該株式は議決権行使に係る経営的支配関係を前提とした経済的価値を有するものと評価され得る一方、当該株式が分割して譲渡され、譲受人が支配権を有しない少数の株式を保有するにとどまる場合には、当該株式は配当への期待に基づく経済的価値を有するにすぎないものとして評価されることとなるから、その間の自由な取引において成立すると認められる価額は、譲渡人が譲渡前に有していた支配関係によって決定されるのか、譲渡後に譲受人が取得することになった支配関係のどちらかで決定されるのかは一概に決定することはできず、双方の会社支配の程度によって結論を異にする事柄であるというべきである。被控訴人(国)の主張する譲渡所得課税の趣旨(所有者に帰属していた増加益を清算して課税する。)といっても、上記のように成立した価額を基準に、所有者の有していた増加益を判断して課税することになるのであるから、上記譲渡所得課税の趣旨に反するということまではできない。そのため、議決権割合の判定基準時を文理解釈で決定できない評価通達188(1)について、上記譲渡所得課税の趣旨に基づく条件(所得税基本通達59−6(1))を定めてその解釈を明確化することには、一定の合理性が認められるものの、株式取得後の議決権割合で判定する旨を定めていることが文理上明らかな評価通達188(2)から(4)までについてまで、明文の定めもなく、上記譲渡所得課税の趣旨によって読み替えることは、所得税基本通達59−6(1)があっても無理があるといわなければならない。そうすると、評価通達188(2)から(4)までについては、上記の自由な取引において成立すると認められる価額について、譲渡人と譲受人の双方の会社支配の程度を考慮して規定された合理的な内容を有するものとして、これを読み替える明文の規定がない場合には、「同族株主のいない会社」の部分を除き、そのまま譲渡所得課税にも適用するのが相当である(所得税基本通達59−6は、このことを定めたものとして合理性を有する。)。仮に、所得税基本通達59−6(1)の適用範囲について、評価通達188(2)から(4)までについてまで被控訴人が主張するような解釈をとろうとするのであれば、上記に説示したような通達の重要性及び機能に照らし、その旨を通達上明確にしておくべきであって、通達の改正等を経ることなく解釈によりその実質的内容を変更することは、通達の定めを信頼して取引等について判断をした納税者に不測の不利益を与えるものであり、相当でないというべきである。
ニ 本件における所得税基本通達59−6の当てはめ
以上によれば、本件株式が評価通達188の(3)の株式に該当するかどうかについて、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定については、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により判定されるものと解するのが相当である。
ホ 本件株式の評価額
T社の株式は、評価通達における「取引相場のない株式」に当たり、かつ、同社には、本件株式譲渡の直前において、議決権総数の30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者は存在しなかったから、同社は「同族株主のいない会社」に当たる。そして、S社の本件株式取得後の議決権割合は7.88%であり、S社には同族関係者がおらず、その議決権割合はT社の議決権総数の15%未満にとどまる。したがって、本件株式は、評価通達188(3)の株式に該当するから、所得税基本通達59−6、評価通達188−2に従い、配当還元方式によって評価すべきこととなり、配当還元方式による本件株式の1株当たりの評価額は、75円であると認められる。
ヘ 結論
本件全証拠によっても、配当還元方式によっては本件株式の客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情があるとは認められないから、配当還元方式による本件株式の1株当たりの評価額は、本件株式譲渡の時点における本件株式の客観的交換価値として適正なものであると認められる。そうすると、本件株式譲渡における譲渡価格はこれと同額であるから、本件株式譲渡は、争点②について判断するまでもなく、所得税法第59条第1項第2号の低額譲渡には当たらないというべきである。
なお、Kが、S社に対し強い権限を有し、また、本件株式の譲渡が相続税負担の軽減させることを目的して行われたとしても、1株当たり75円という譲渡価額が、前記のとおり合理性が認められる所得税基本通達59−6、評価通達188(3)、188−2に従って算定された価額と一致する以上、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して算定された価額とは異なるということはできず、ほかに同事実を認めるに足る証拠はない。
(6)令和2年3月24日最高裁第三小法廷判決(平成30年(行ヒ)第422号)(最高裁判所ウェブサイト掲載)
イ 所得税法第59条第1項の趣旨
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものである。すなわち、譲渡所得に対する課税においては、資産の譲渡は課税の機会にすぎず、その時点において所有者である譲渡人の下に生じている増加益に対して課税されることとなるところ、所得税法第59条第1項は、同項各号に掲げる事由により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に当該資産についてその時点において生じている増加益の全部又は一部に対して課税できなくなる事態を防止するため、「その時における価額」に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなすこととしたものと解される。
ロ 所得税法第59条第1項における時価評価の場合における評価通達の適用
所得税法第59条第1項所定の「その時における価額」につき、所得税基本通達59−6は、譲渡所得の基因となった資産が取引相場のない株式である場合には、同通達59−6(1)から(4)によることを条件に評価通達の例により算定した価額とする旨を定める。評価通達は、相続税及び贈与税の課税における財産の評価に関するものであるところ、取引相場のない株式の評価方法について、原則的な評価方法を定める一方、事業経営への影響の少ない同族株主の一部や従業員株主等においては、会社への支配力が乏しく、単に配当を期待するにとどまるという実情があることから、評価手続の簡便性をも考慮して、このような少数株主が取得した株式については、例外的に配当還元方式によるものとする。そして、評価通達は、株式を取得した株主の議決権の割合により配当還元方式を用いるか否かを判定するものとするが、これは、相続税や贈与税は、相続等により財産を取得した者に対し、取得した財産の価額を課税価格として課されるものであることから、株式を取得した株主の会社への支配力に着目したものということができる。
これに対し、本件のような株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、当該譲渡における譲受人の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を及ぼすものではないのであって、前記の譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される。
そうすると、譲渡所得に対する課税の場面においては、相続税や贈与税の課税の場面を前提とする評価通達の前記の定めをそのまま用いることはできず、所得税法の趣旨に則し、その差異に応じた取扱いがされるべきである。所得税基本通達59−6は、取引相場のない株式の評価につき、少数株主に該当するか否かの判断の前提となる「同族株主」に該当するかどうかは株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること等を条件に、評価通達の例により算定した価額とする旨を定めているところ、この定めは、上記のとおり、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株式を譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる。
ハ 結論
原審は、本件株式の譲受人であるS社が評価通達188の(3)の少数株主に該当することを理由として、本件株式につき配当還元方式により算定した額が本件株式譲渡の時における価額であるとしたものであり、この原審の判断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。
((2)に続く)
脚注
1 相続、遺贈及び個人間の贈与にあっては、取得価額を引き継ぐことによりこれらの理由により資産を取得した者が譲渡を行った際に、従前の所有者に帰属していた増加益を併せて譲渡所得課税が行われることとされている(所法60)。
2 平成11年11月30日東京地裁判決。
3 「当然のことながら、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額により取引されたと認められる場合など、この取扱いを形式的に当てはめて判定することが相当でない場合もあることから、この取扱いは原則的なものとしている。」(平成29年版「所得税基本通達逐条解説」718頁。)。
4 法人税基本通達2−3−4、4−1−5、4−1−6、9−1−13、9−1−14。
5 本事件の譲渡者を被相続人とする相続税に関し、本事件におけるT社の株式の評価方法が争点とされた裁判例がある。興味のある方は本事件の判決と同日に出された平成29年8月30日東京地裁判決(平成24年(行ウ)184号)(判例タイムズ1464号106頁)を確認いただきたい。なお、この相続税事件に係る裁決(平成23年9月28日裁決・裁決事例集No.84)も興味深い裁決である。
6 この事件の事実関係の説明については、相続税の課税処分について争われた平成29年8月30日東京地裁判決(平成24年(行ウ)184号)及び平成23年9月28日裁決(裁決事例集No.84)も参考にしている。
この記事に関するご意見・お問合せはta@lotus21.co.jpにお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.