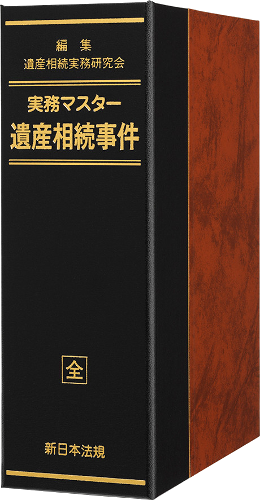相続・遺言2014年03月24日 相続法を理解するためのポイント 執筆者:仲隆
相続事件は感情的な対立の解消という点で面倒な分野であるが、相続法の理論的な側面は簡単なものと誤解している方も少なくないのでないかと思う。私自身20年ほど前はそう思っていた。だが、何かで理論的な問題にぶつかると相続法の難しさが身に染みてくるようになった。考えてみれば、相続法は、財産法に身分法(家族法)の修正を加えたようなものであるし、その解決には家庭裁判所だけでなく地方裁判所も登場したりするから、実は大変難しいのである。
相続法を理解するための私なりのポイントを挙げてみたい。
1つ目のポイントは相続人を重視すべきか、被相続人を重視すべきかという点である。「相続と遺言」という言い方がある。しかし、民法は第五編「相続」と題し、その中の第七章に「遺言」を置いているから、並列的な表現には違和感がある。そこで、私は理解をし易くするため、あえて「法定相続」と「遺言相続」という用語を好んで使う。相続(財産承継)が法律を原因とするのか、遺言を原因とするのか、ということである。では、民法は法定相続を原則としているのか、遺言相続を原則としているのか。このことは、共同相続人間の公平(あるいは各相続人の期待権)を重視するのか、被相続人の意思を重視するのかの問題であろう。たとえば、遺留分制度は、被相続人の意思実現を制限し、共同相続人間の公平を企図するものであり、推定相続人廃除の制度は被相続人の意思を尊重して特定の相続人の権利を剥奪するものである。そして、このいずれを重視するかによって具体的な解釈や事案処理に影響を与えることになるのである。この視点は常に念頭に置く必要がある。
2つ目は、遺産共有の性質である。これについて昔から最高裁は物権法上の共有であると明言する。さりとて、遺産たる不動産について共有物分割請求をすることは認めない。調停制度が現に存するからである。ところが、銀行預金などの可分債権は被相続人死亡と同時に各共同相続人に法定相続分に応じて当然承継される、したがって、遺産分割の対象とはならないというのが最高裁である。たとえば、預貯金しか遺産がない場合には原則として調停申立ても認められないことになる。また、各共同相続人は、特定の不動産の共有持分権を第三者に譲渡することができる。その第三者と他の共同相続人との共有関係の解消方法は共有物分割である。これに対し遺産全体に対する共有持分(つまり相続分)を第三者に譲渡した場合は当該第三者は相続人の地位を取得するのである。このように遺産共有の性質論は一本の筋が通っていない感じで、これが相続法の理解を難しくさせている。
3つ目は、相続させる遺言である。平成3年4月19日の最高裁判決以降、完全に定着した遺言事項である。特定の相続人に特定の遺産を相続させる旨の遺言があるとき、それは遺産分割の方法を指定したものであるが、原則として、当該相続人は遺産分割手続を経ずして、当然に当該遺産を取得するというのである。遺贈については遺産分割を経ずして当然に受遺者が権利を取得する。しかし、遺贈ではなく、遺産分割の方法の指定であるのに同じ結論になっている。たとえば、遺贈の場合、受遺者が遺言者より先に死亡したときは遺贈の効力は失う旨の規定があるが、相続させる遺言ではどうか。下級審は分かれていたが、最高裁は遺贈と同様の結論を導いたのである。法的性格は相続による承継(遺産分割の方法を指定したもの)であるが、効力は遺贈のようである。しかも、不動産の場合、遺贈による名義移転手続は共同申請であるが、相続させる遺言では単独申請が認められ、しかも、受遺者は登記なくして第三者に対抗できないが、相続させる遺言における受益者は登記なくして対抗できるという。何か虫がいいように感ずる。さらに、相続させる遺言では遺言執行の余地もないと言われ、原則として遺言執行者の権限の範疇ではない(仕事とならない)ことになる。これも大変難しい問題である。
間違った法律相談をしないために、実務家としては、かように相続法が難解であることを十分認識しておくことが大切であるように思う次第である。
(2014年3月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.