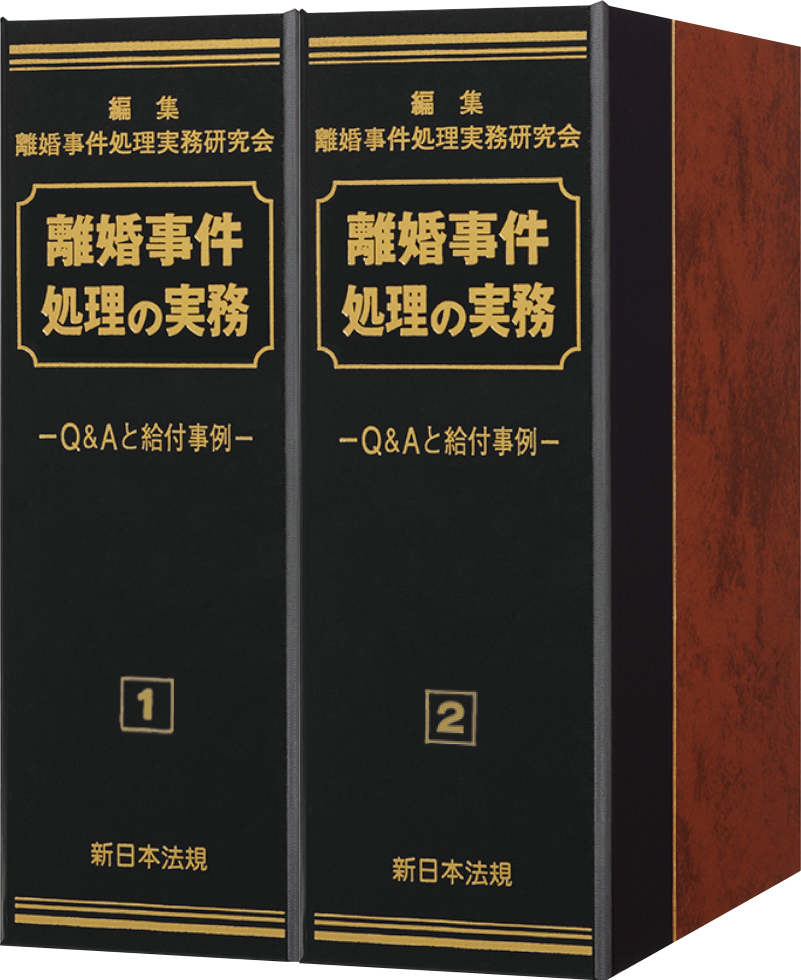民事2013年11月27日 ハーグ条約についての所感 執筆者:冨永忠祐
ハーグ条約は、今から30年以上も前の1980年(昭和55年)に、オランダで開催されたハーグ国際私法会議で採択された条約で、正式名称を「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」といいます。この正式名称からわかるとおり、この条約は、子どもが国外に連れ去られた場合などにおいて、子どもを元の国に戻して保護するための国際協力を定めた条約です。
ハーグ条約は、アメリカやEU加盟国などのほとんどの先進国で批准されていましたが、わが国は長い間、これを批准しませんでした。そのため、国際結婚した夫婦が不仲となり、一方の親が勝手に子どもを連れて日本に帰ってしまうと、ハーグ条約が日本では適用されないので、子どもを元の国に戻すことが容易ではありませんでした。
ハーグ条約を締約しないわが国は、外国から強い批判を受けてきましたが、ようやく2013年5月になって、国会でハーグ条約が承認され、翌6月には、条約を実施するための国内法も制定されました。
ハーグ条約では、子どもの返還を求める親が、①子どもが連れ去られる直前に、条約の締約国内に子どもの常居所(生活の本拠)があったこと、②当該常居所地国の法令では、当該連れ去りが監護権の侵害になること、③連れ去りの時に、監護権を現実に行使していたこと、または連れ去りがなかったならば現実に行使していたであろうことを立証しなければなりません。
そして、子どもの返還の申立てを受けた裁判所は、①ないし③が認められ、かつ連れ去りから1年を経過していない場合には、原則として、子どもを常居所地国に返還することを命じなければなりません。
この手続の特徴は、監護権については議論せずに、「まずは元の国に戻す」ことが最優先とされていることです。すなわち、子どもを元の国に戻してから、子どもの監護権については、別途、審理するのです。
しかし、子どもは、日々、自分が現在置かれている生活環境の中で成長していきます。連れ去られた子どもも同じです。時が経てば、地元の学校に通い、友人を作って、自分の世界を築いていくのです。したがって、子どもの生活環境をコロコロと変えることは好ましいことではありません。
そうだとすると、「まずは元の国に戻す」という法律の仕組みは、両親の紛争に子どもが巻き込まれて、かえって子どもの福祉に反する結果にならないでしょうか。今後の実務の中で、子どもを主人公とした運用がなされるよう注視する必要があります。
(2013年11月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -