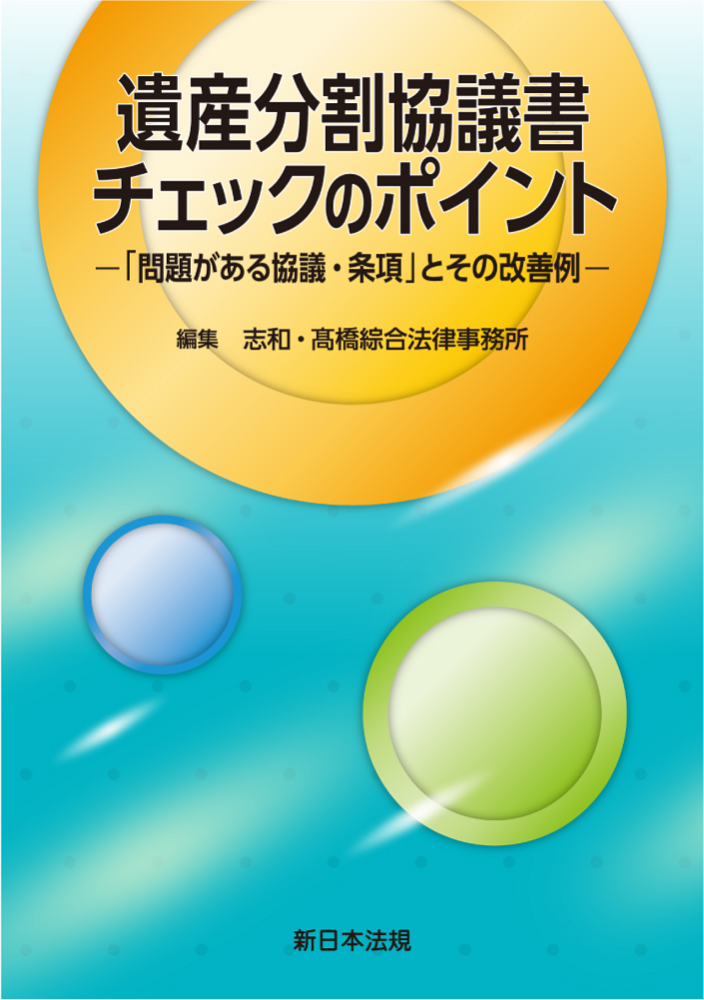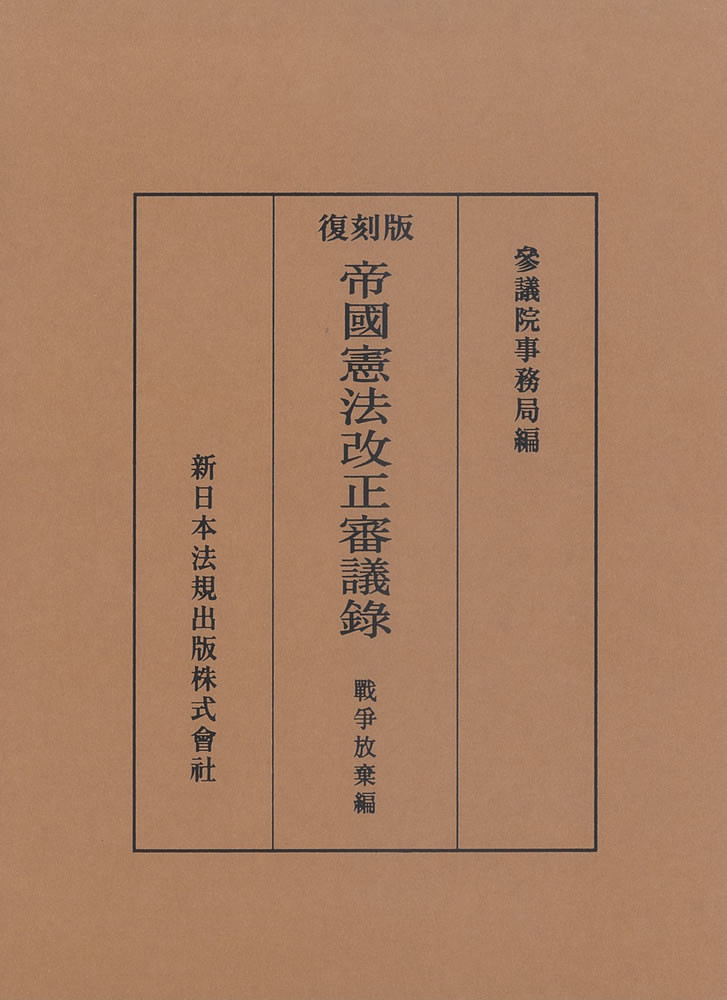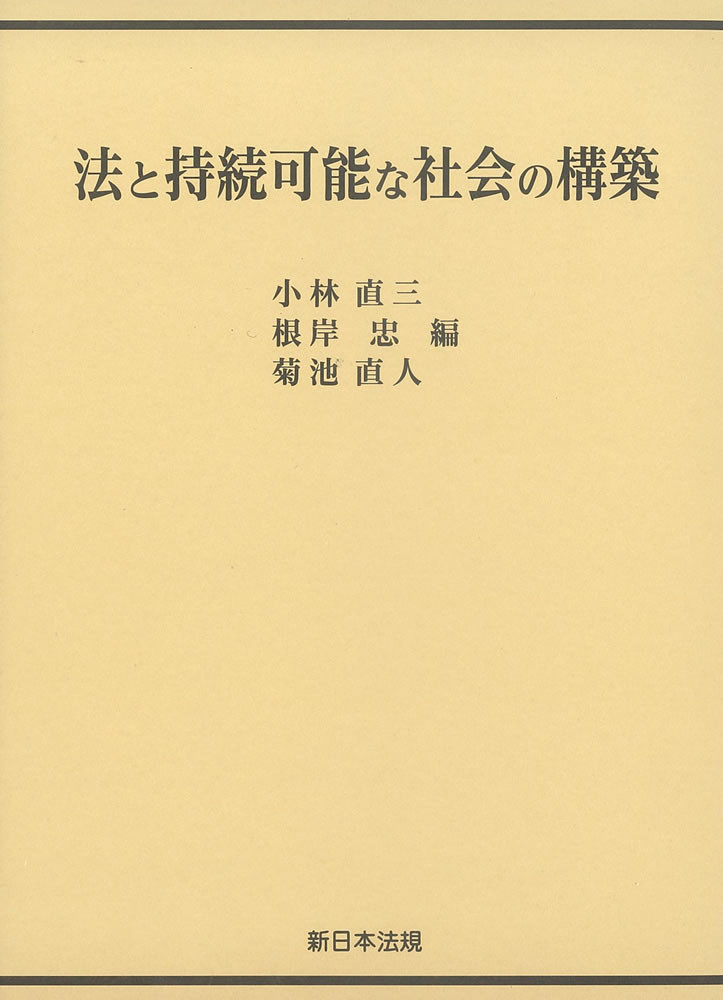一般2025年04月27日 インタビュー「憲法とあした 施行78年」 提供:共同通信社

性教育、人権尊重に不可欠 教育評論家の尾木直樹さん
日本の中学生が受ける性教育は年間で3時間にも満たないという民間の調査があります。自身の記憶をたどっても学生や教員時代、「性」について学ぶ機会はほとんどありませんでした。こうして多くの人が性に関する教育を受けないまま大人になり、子どもたちに、どう伝えるべきか分からないでいます。
国連教育科学文化機関(ユネスコ)が提唱する「包括的性教育」は生殖に関すること以外にも、対等な人間関係や性の多様性など幅広い内容を扱います。自分の性や、他者の性を大切にすることは憲法が求める基本的人権の尊重の根幹部分。子どもたちが自分の人生を決定していく上でも欠かせない知識です。
日本で性教育が進まない要因の一つは中学の学習指導要領にある「妊娠の経過を取り扱わない」とする歯止め規定です。今も授業では性交や避妊、中絶については教えない傾向があります。2003年に都立七生養護学校(当時)の性教育が批判され、教員らが処分されたことも学校現場を萎縮させてしまいました。
しかし性交が何かを知らなければ子どもが性暴力に気づくことはできず、避妊方法を知らなければ予期せぬ妊娠を防ぐこともできません。生きる上で必要な知識を教えないことは憲法が保障する教育を受ける権利の侵害に当たります。時代遅れの考えや規定を早急になくすべきです。
性教育を「寝た子を起こす」と批判する人もいます。しかしインターネットの普及により性に関する情報が簡単に入手できてしまう時代。既に子どもたちは寝ていません。むしろ誤った性の知識やゆがんだ考えに触れ、子どもが加害者になってしまう事態も既に発生しています。
21年に北海道旭川市で女子中学生が自殺した問題で再調査委員会の委員長を務めました。報告書では深刻な性的いじめを認定し、全ての子どもが包括的性教育を受ける必要があることを提言しました。子どもを被害者にも加害者にもしないため、国はしっかりと国際基準にのっとったカリキュラムを作成し、性教育について専門知識を持つ教員の養成や学び直しができる仕組みを整備してほしいと思います。
× ×
おぎ・なおき 1947年、滋賀県生まれ。法政大名誉教授。「尾木ママ」の愛称で知られる。
× ×
憲法施行から78年。国際情勢は混迷し「平和」が揺らいでいる。インターネット上の言論が影響力を強める中で、未来を担う子どもの意思決定は保障されているか―。憲法を軸に私たちの暮らしと明日を考えたい。3組の識者に話を聞いた。
憲法26条
教育を受ける権利を保障している。特に子どもは発達に応じて平等に学ぶ権利を持ち、大人は子どもに教育を受けさせる義務を負う。国際的には「性に関する人権」の一つとして包括的性教育を受ける権利が挙げられている。
中傷対策で表現の自由守れ 水谷瑛嗣郎慶応大准教授
インターネット、とりわけ交流サイト(SNS)は、現代の「言論空間」になっています。多くの人が表現の自由を行使できる一方で、誹謗(ひぼう)中傷やヘイトスピーチ、フェイクニュースなどが問題になっています。
憲法が保障する表現の自由は、検閲など国家による制約を受けない自由として議論されてきました。SNSでは一般の人同士で中傷などの問題が起きます。裁判などで個人対個人の争いとみるだけでは、問題の本質を見誤る可能性があります。SNSを運営するプラットフォーム(PF)企業の存在が大きいのです。
X(旧ツイッター)や、フェイスブック、インスタグラムのMeta(メタ)などは、言論空間をデザインします。利用者に「おすすめ」や「トレンド」を提示するアルゴリズム(計算手法)で目に入る情報を操作し、独自のルールに基づき違反する投稿を削除する「コンテンツモデレーション」を行っています。
昨年11月の兵庫県知事選で、落選した稲村和美(いなむら・かずみ)氏の後援会が運営するXのアカウントが、選挙期間中に凍結されました。稲村氏側は何者かが虚偽の通報をしたとして刑事告訴しましたが、最終的に凍結を判断したのはXです。PF企業が言論空間のルールを決め、時に選挙運動にすら影響を与えます。マスメディアと異なるその力は「新たな統治者」と評されています。総務省の誹謗中傷対策ワーキンググループでは、PF企業の社会的責務に見合うガバナンスが必要だと議論を重ねてきました。
4月1日に施行された「情報流通プラットフォーム対処法」は、誹謗中傷投稿などへの対応の迅速化や透明化が柱。PF企業に通報窓口の整備や、削除基準の明示を義務付けました。ただ、もっと積極的な削除を求める声がある一方、違反ではないものまで過剰に削除してしまう懸念もあり、両立する必要があります。
この法律は「言論統制だ」との批判もありますが、誹謗中傷を放置すると、被害を受けた人は言論を萎縮させてしまいかねません。それは言論空間や民主主義にとってマイナスです。PF企業に対する適切なガバナンスは、より多様な意見が流通する言論空間を実現することにもつながるのです。
× ×
みずたに・えいじろう 1986年、大阪府生まれ。専門は憲法。編著に「リーディング メディア法・情報法」。
憲法21条
集会、結社、言論など表現の自由を保障し、検閲を禁止する。国民それぞれが自分の考えを表明し、議論のやりとりで世論を形成し国政を決めることは民主主義国家の基礎。インターネットの普及は、個人による発信を容易にした。
9条は私たちの生活に直結 弁護士コンビ「四谷姉妹」
お笑いコンビ「阿佐ケ谷姉妹」にちなみ、弁護士2人が結成した「四谷姉妹」。憲法を題材にした漫才が人気で、再生回数が1万回近くに上るユーチューブ動画もある。
× ×
岸松江(きし・まつえ)さん 憲法が書いてある「六法全書」は、何の役に立つでしょうか。①私たちの暮らしと平和を守っている②お昼寝の枕③漬物石の代わり④ダンベル。
青龍美和子(せいりゅう・みわこ)さん ①しかないじゃない。
岸 正解は全部。
青龍 どひゃー。と、こんなふうに漫才をしています。以前は憲法の講演会で話しても、護憲派層にしか届いていない実感があり、広く憲法を知ってほしいと2018年に四谷姉妹を結成しました。権力は暴走します。憲法に人権規定を並べ、権力を制限する考え方が「立憲主義」です。
岸 立憲主義は憲法の一番大きな役割。そして、二つの世界大戦を経てつくられた憲法には、二度と戦争はしないとの思いが込められています。先進性があり、今読んでも古くないと感じます。
青龍 権力者は自分たちの都合がいいように解釈を緩めます。「戦争の放棄、戦力の不保持」を定めた9条の存在は「自衛隊に予算をかけるのはおかしいのでは」と声を上げる根拠になります。
岸 武力による抑止は、相手国にピストルを突きつけながら仲良くしようといっているようなもの。9条ができた当時を知って、今こそ原点に戻るべきです。
青龍 政府は防衛力強化に向け22年に安保3文書を策定しましたが、四谷姉妹は「対案」を考えました。平和外交で日本の安全を守ること、私たちを「9条大使」として9条を世界に広げるアイデアも盛り込みました。
岸 文化や豊かな自然の存在を発信することも、戦争をしないために有効だと思う。戦争が起きたら、世界で人気がある日本の漫画も読めなくなるかもしれない。
青龍 一見、市民に関係がなさそうな9条は私たちの生活に直結しています。憲法は身近なものであると知ってほしい。
岸 言論の自由があり、権力の批判ができるのも憲法で保障されているから。失ってから大切さが分かるのではだめだと思います。
× ×
きし・まつえ 岡山県出身。せいりゅう・みわこ 東京都出身。岸さんは2005年、青龍さんは11年に弁護士登録。
憲法9条
「国民主権」「基本的人権の尊重」と並び、憲法の三大原則を構成する「平和主義」を規定。戦争放棄、戦力不保持・交戦権否定を定める。安倍政権は2014年に憲法解釈を変更し、集団的自衛権の一部行使を容認。15年に安保関連法を成立させた。
(2025/04/27)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.