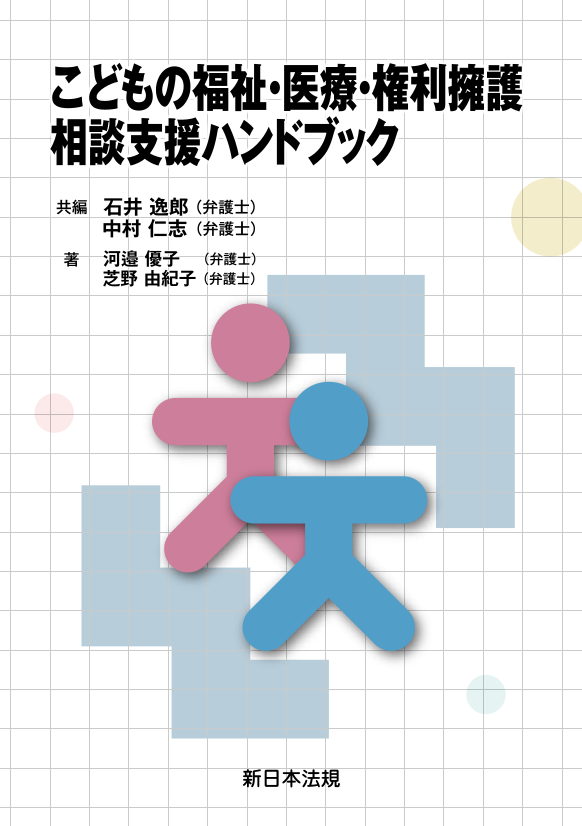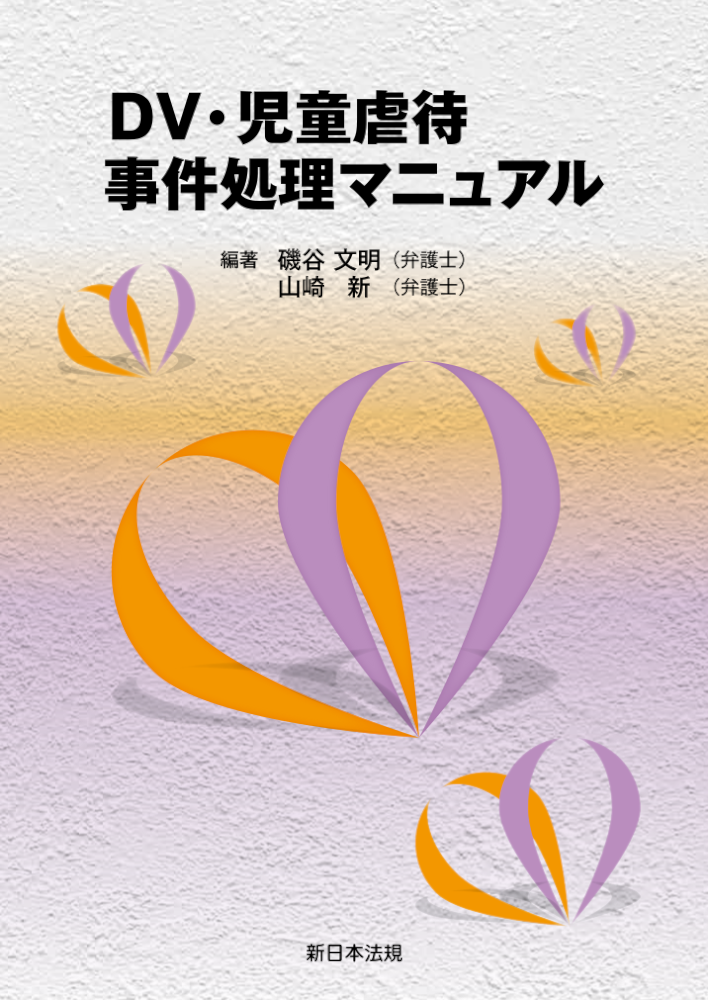一般2025年05月20日 子どものケア「継続を」 新型コロナ、心身に影響か 増え続ける不登校や暴力 提供:共同通信社

新型コロナウイルス流行による初の緊急事態宣言は一斉休校のさなかだった。それから5年が過ぎ、5類移行からも2年がたった。コロナ禍が終わり、学校は日常に戻ったように見えるが、不登校は増え続け、特に小学生で暴力行為が増加するなど、子どもの心身の変化を指摘する声は少なくない。専門家は「ケアの視点を持ち続ける必要がある」と訴える。
サイン
九州地方の公立小で2年生の担任をしている40代の男性教諭は、ここ数年の子どもの変化を感じている。「入学してくる子がおとなしくなった」。給食の時間に周囲と活発に話す児童や、昼休みに外遊びをしたがる児童が減ったという。
その一方で、友人とのトラブルなど困りごとに直面すると、突然手が出たり、物を壊したりする子が増えた。「子どもの出すサインが、このごろはややつかみにくい」と打ち明ける。
2020年春に突如として始まった小中高校などの一斉休校は、地域によって6月ごろまでの約3カ月に及び、保育所や幼稚園も休園や受け入れ縮小に追い込まれた。その後も修学旅行や運動会の中止・縮小が相次ぐなど、活動の制限が続いた。学校は繰り返される緊急事態宣言に振り回され、なかなか通常モードに戻れなかった。
文部科学省の調査によると、不登校の小中学生は過去最多を更新し続け、23年度に暴力行為をした小学生は5年前の1・7倍に増えた。
抑うつ傾向も
「子どもは大人に比べ、厳しい行動制限による心身への影響が長く続く傾向にある」。国立成育医療研究センターの児童精神科医の石塚一枝(いしつか・かずえ)さんは、子どもの診療やカウンセリングに当たった経験からそう指摘する。
同センターがコロナ禍に小中高の児童生徒とその保護者に実施した調査によると、受診が望ましい中等度以上の抑うつ傾向が見られた子どもの割合は、20年6%、21年11%、22年13%と増えていった。
子どもの場合、不調が数年後に現れるケースも多いといい、石塚さんは「小さな変化を見逃さないよう気を配り続けることが重要。いろいろな人に気にかけてもらうことが安心につながり、不調の予防になる」と語る。
子どもの心のケアなどに詳しい東海学院大の高橋智(たかはし・さとる)教授(特別支援教育)は「教育機関でのマスク着用や給食の黙食は、特に低年齢児の言葉の発達やコミュニケーション能力に影響を及ぼした可能性が高く、不登校や暴力行為の増加の一因になっていると考えられる」と指摘する。
コロナ禍は地域や年齢に関係なく誰しもが当事者だったため、子どものケアが議論の焦点になりにくかった。「国は責任を持って子どもへの継続的な実態調査を実施し、経過をしっかり見ていくべきだ」と強調した。
問題行動・不登校調査
いじめや暴力行為、不登校の実態を把握し、子どもの指導に生かすため文部科学省が毎年度実施する調査。2023年度に全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒は11年連続で増加し、全体の3・7%に当たる34万6482人となり過去最多を更新した。小中高校が把握した児童生徒の暴力行為も、過去最多の10万8987件を記録。特に小学校での増加が顕著で、加害児童数は新型コロナウイルス禍前の18年度から1・7倍に増えた。
(2025/05/20)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.