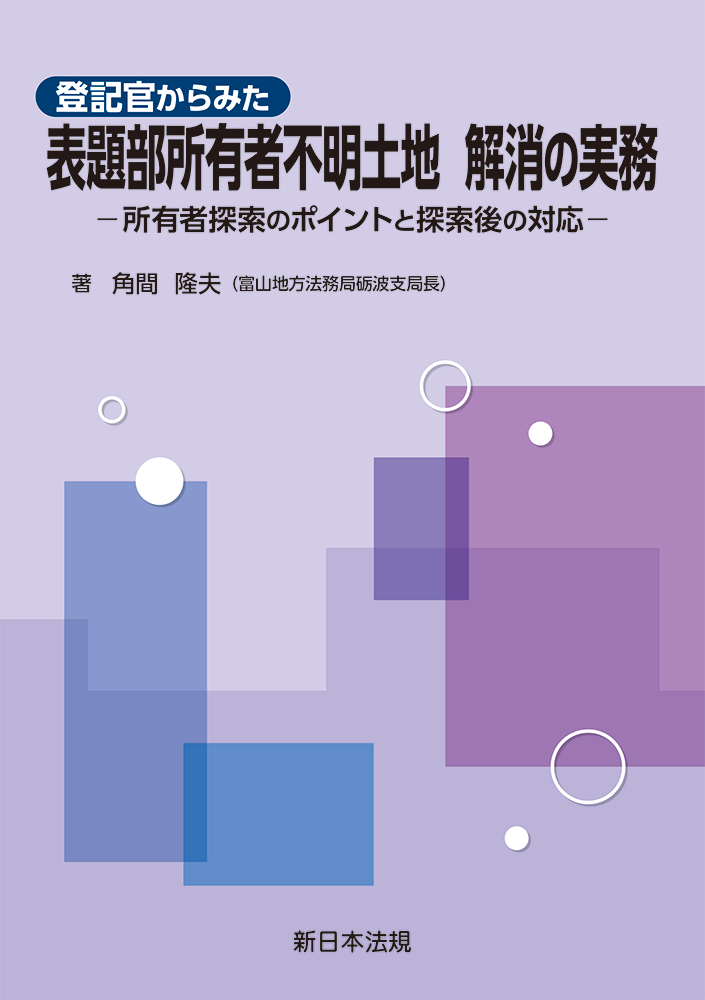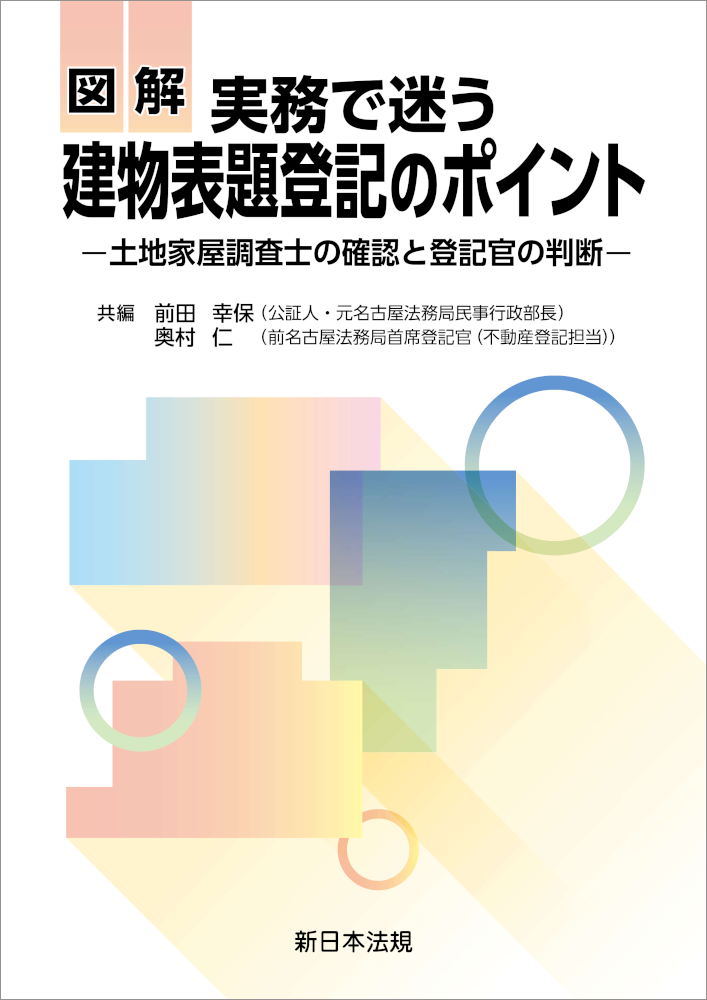不動産登記2025年10月07日 所有者不明土地の解消作業 実務で役立つ!ベテラン登記官の知恵袋 執筆者:角間隆夫
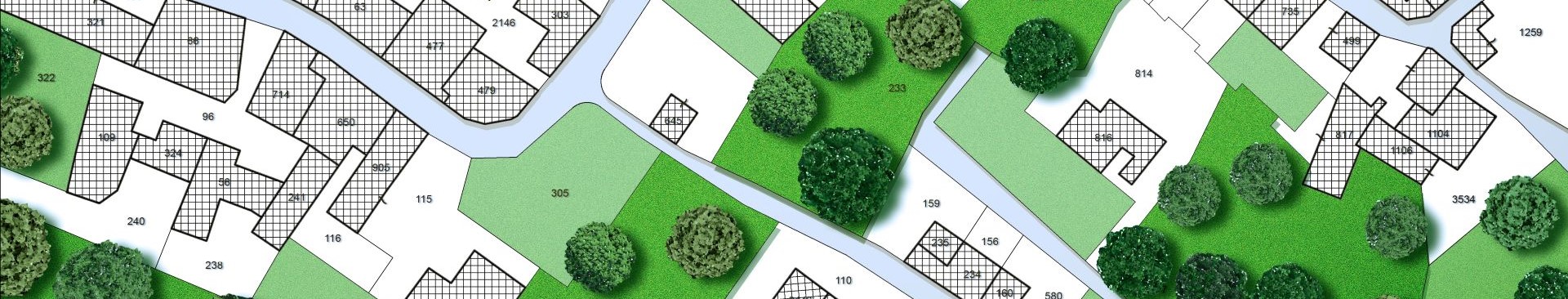
ご承知のとおり、令和6年4月から相続登記が義務化され、令和8年4月からは不動産について所有権の登記名義人の住所又は氏名変更の登記が義務化されます。
司法書士の方の中には、これらのうち相続登記の申請を依頼された不動産に所有者不明土地が含まれているケースや、所有者が不明の空き地・空き家に遭遇した経験がある方もあると思います。
また、所有者不明土地について、自らが所有する土地であることから所有者又は登記名義人として登記をする方法を相談されたことがある司法書士や土地家屋調査士の方も多いと思います。
所有者不明土地の登記記録に登記されている所有者又は登記名義人を現地における所有実態に合わせるには、表題部所有者欄の所有者又は所有権の登記名義人の氏名等の更正登記を申請する必要がありますが、これらの更正登記を申請する際には、次の添付情報を提供する必要があります。
・表題部の所有者欄に登記されている所有者の更正の登記
更正後の所有者について当該土地の所有権を有することを証する情報(不動産登記令7①六 別表の4の項添付情報欄ハ)
・所有権の登記名義人の住所等を更正する登記
登記原因情報として更正前と更正後の登記名義人が同一人であることを証する情報(不動産登記令7①五)
しかしながら、ご承知おきのことと思いますが、所有者不明土地については、所有者を直接的に示す資料のないことが多く、添付情報を取得して、登記申請手続により所有者不明土地を解消することは容易ではありません。
また、これまで所有者不明土地について所有者の更正登記等による解消事例が十分に積み上げられてこなかったこと、また、所有者不明土地の態様は個別の事情によることなどから、所有者不明土地を解消するための登記について具体的な所有者の探索及び特定方法並びに添付情報を明確に示すことが難しく、登記官と司法書士又は土地家屋調査士において共通の認識を有することも少なかったものと思われます。
例えば、所有者として氏名だけが登記されている場合は、個人が所有していた土地であることが推測されるので、まずは、戸籍や除かれた戸籍を調査して所有者を探索することになります。
一方、所有者として「大字○」や「共有惣代○」、「某ほか○名」と登記されている土地については、過去の所有実態を把握した上で、所有を主張する者との関係や所有の変遷について調査し、その調査結果を踏まえて、所有者又は登記名義人の住所等の更正登記のほか、必要に応じて所有権の移転登記を申請することになるものと思われます。
しかしながら、所有者として「大字○」などと登記された土地について登記官が直接調査をすることが少ないこともあってか、ポツダム政令により所有権の帰属が判断できる場合以外は、「大字〇」と登記された当時の所有実態や登記された経緯などに基づき所有者を調査する方法や所有者の特定方法が明確ではなかったことから、所有者不明土地の解消が困難とされていたものと思われます。
ところで、全国の法務局及び地方法務局では、令和元年度から表題部所有者不明土地解消作業を実施しています。
この作業では、特定が難しいとされる変則型登記の所有者を探索するための調査を登記官が行っていることから、変則型登記がされた土地について所有者の特定に係る登記官による判断事例が、特定のための調査や調査に必要な資料の収集及びその評価とともに積み上げられています。
この作業は、令和元年度から各法務局又は地方法務局において約170筆の土地を選定して実施されていることから、これまでに数万筆の所有者不明土地が解消されており、これら登記官が積み上げてきた事例は、表題部のみならず、権利部における所有者の特定にも応用できることがあると思料します。
しかしながら、表題部所有者不明土地解消作業は、各法務局等において数名の職員が担当して実施されており、司法書士や土地家屋調査士も所有者探索委員として任命・指定されていますが、所有者探索の調査に関与された方は少ないものと思われます。
また、個々の所有者特定事例は、所有者特定書により確認できるものの写しを取得することができる者は、利害関係を有する者に限られていることから、表題部所有者不明土地解消作業における所有者を探索するための資料や調査方法、所有者の特定方法は、作業の担当者を経験した法務局職員と所有者探索委員に任命・指定されたことのある司法書士又は土地家屋調査士に限られているものと思われます。
それでは、表題部所有者不明土地解消作業における基本的な所有者探索のための調査について説明します。
まずは、探索に必要な資料についてです。
登記記録、閉鎖登記簿及びその附属書類、地図又は地図に準ずる図面(閉鎖されているものを含みます。)、旧土地台帳、旧家屋台帳、共有者連名簿など、登記所内にある資料を収集します。
また、所有者等の探索のために必要な程度で、道路台帳や路線図、地籍調査票など、地方公共団体等にある資料のほか、対象土地が農地の場合には農地台帳や農業委員会が保管している耕作者名簿、ため池の場合はため池データベースなど、土地の地目又は利用状況に応じた特有の資料も収集して所有者を調査します。
次に、実地調査と立入調査です。
実地調査では、対象土地や周辺の土地の現況などにより現地における大まかな位置とともに所有者等の特定について参考となる情報を把握するほか、寺院が保管している過去帳や歴史的文献等、参考となる資料について調査し、収集及び調査を行います。
また、資料等だけでは所有者を特定することができない場合には、資料による調査を踏まえて現地の住民等から所有者の特定に役立つ情報について聴取を行うほか、必要に応じて他人の土地に立入調査を行います。
これらの調査は、必要に応じて複数回行うことも可能です。
登記官は、収集した資料と現地における調査結果を踏まえて所有者を特定するのですが、所有者の特定には、所有者不明土地がある周辺地域の成り立ちや、所有者不明土地に登記されている所有者が登記された経緯も踏まえる必要があります。
登記官による所有者の特定は、基本的にこのような調査に基づく探索により行っています。
これら表題部所有者不明土地解消作業における所有者の探索に必要な資料や現地における調査及び所有者特定の方法は、所有者不明土地の所有者の探索や、探索結果に基づいて登記官と協議を行い、所有者不明土地を解消するための登記を申請するときの参考となることから、司法書士及び土地家屋調査士の皆さんの業務において所有者不明土地の解消に繋がる登記に役立てていただければ幸いです。
(2025年9月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
執筆者

執筆者の記事
執筆者の書籍
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -