コラム2006年01月09日 【SCOPE】 公開買付WGのTOB見直しに関する報告書を読み解く(2006年1月9日号・№145)
SCOPE
大量保有報告の特例は2週間ごとの基準日に短縮
公開買付WGのTOB見直しに関する報告書を読み解く
金融審議会金融分科会第一部会の公開買付制度等ワーキング・グループは12月21日、「公開買付制度等のあり方について」と題する報告書をとりまとめた(28頁参照)。公開買付期間については、営業日ベースに変更するほか、公開買付けの撤回や条件変更を認める。また、問題視されていた大量保有報告の特例制度については、2週間ごとの基準日における保有状況を5営業日以内に報告するなど、大幅な短縮を図ることが明記された。金融庁は1月下旬からの通常国会に証券取引法の改正案を提出する考えだ。
公開買付期間は営業日ベースで
今回の公開買付制度等の見直しは、自民党の企業統治委員会が7月7日にまとめた「公正なM&Aルールに関する提言」を受けてのもの(本誌No.123参照)。提言では、①経営方針の開示とTOB期間の伸長、②TOB条件の柔軟化(TOBの撤回と価格の下方修正)、③買収者間の公平性確保のための買付ルール整備、④大量保有報告制度の特例の見直しが盛り込まれていた。
3分の1ルールを見直し
まず、3分の1ルール(買付け後の株券等保有割合が3分の1を超える場合に公開買付規制を適用するもの)については、現行制度を維持するものの、例えば、32%の株式を市場外で買付け、その後、市場内で2%の株式を買い付けるようなケースについては、公開買付規制の対象とすることを明確化する。また、種類株式については、今年5月施行予定の会社法において、その設計が柔軟化されることに伴い、公開買付制度を適用する規定を整備する。
公開買付届出書等の開示の拡充へ
公開買付制度の透明性を図る観点の施策として、まず、公開買付届出書等の情報開示を拡充する。具体的には、公開買付価格の決定プロセスや買付け後における対象会社の経営への関与の具体的内容などを開示させる。また、MBO(経営陣による株式買取り)や親会社による子会社株式の買取りについては、経営陣等が買付者となるため、例えば、公開買付価格の妥当性や利益相反を回避するためにとられている方策等を開示させる。
一方、対象会社については、株主等の投資判断の的確性を高める観点から意見表明を義務付けることとされている。意見表明については、公開買付けへの賛否のみならず、併せて①その意見の理由、②買収防衛策発動予定の有無、③賛成・反対等の結論に至ったプロセス等を開示させる。加えて、公開買付者に対し、対象会社から質問する機会を付与する。質問については、意見表明の際に行うこととする。
買収者が設定する公開買付期間については、現行20日以上60日以内とされているが、これは実日数ベースとなっているため、営業日ベース(20営業日以上60営業日以内)に改めることにする。ただし、買付期間が30営業日未満に設定され、対象会社が公開買付けに対して、反対意見を述べる場合には、30営業日を上限として公開買付期間を伸長することができるようにする。
買収防衛策の発動で公開買付けの撤回が可能
公開買付けの撤回については、現行、対象会社の株式交換、合併、破産など、法令で限定列挙されている事由などでしか認められていない。しかし、買収防衛策を導入する企業も増える中、公開買付けの撤回が一切認められないとすると、公開買付者に不測の損害を与えるおそれがある。 このため、例えば、①株式分割、株式の無償割当が決定された場合、②新株・新株予約権の発行が決定された場合、③重要な資産の売却がなされた場合には、公開買付けの撤回を認める。また、買収防衛策が解除されないことが確実な場合にも、公開買付けの撤回を認める。
買付条件の変更については、現行、買付価格の引き下げなど、応募株主に明らかに不利となる条件変更は禁止されている。しかし、対象会社による株式分割、株式の無償割当等により株価が希釈化された場合については、その希釈分に対応した公開買付価格の引き下げを認めるとしている。
その他、公開買付け後における株券等所有割合が3分の2を超える場合には、会社法上、特別決議に対する買付者以外からの拒否権が基本的になくなるため、公開買付者に全部買付義務を課すとしている。
将来発行される株券も公開買付規制の対象
ある者が公開買付けを実施している期間中に、株券等所有割合が既に3分の1超となっている別の者が更なる買付けを行う場合などに限り、公開買付けを義務付ける。
また、株式分割により将来発行される新株や発行決議に基づき将来発行される新株、新株予約権などについては、公開買付規制の対象とする。
 通常国会に証取法の改正案を提出へ
通常国会に証取法の改正案を提出へ
特例制度・最短では1週間後の開示
大量保有報告制度は、上場株券等の保有割合が5%を超える保有者に対して、5%を超えることとなった日から原則5営業日以内、以後1%以上の変動があった場合に情報を開示させるもの(いわゆる5%ルール)。
しかし、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社等の機関投資家については、特例が認められている。具体的には、「当該基準日の属する月の翌月十五日まで」(※基準日とは「特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう」)に情報を開示すればよいことになっている。今回の見直しでは、2週間ごとの基準日における保有状況を5営業日までに短縮を図ることになる。このため、最短では、1週間後の開示が実現することになる。
その他、保有割合が10%を上回る取引については、特例対象者でも一般の報告と同じく、提出事由発生から5営業日以内の開示が義務付けられているが、10%超保有の状態から保有割合が10%を下回る取引を行った場合には一般の報告が求められていない。このため、下回る場合でも一般の報告を求めることにする。
保有目的などを開示
大量保有報告書に関しては、保有目的や株券賃借の状況などについて、詳細な開示を求めることやEDINETによる提出の義務付けを行うとしている。
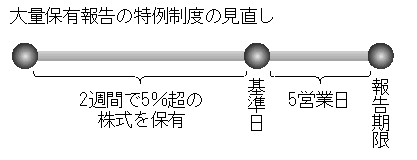
大量保有報告の特例は2週間ごとの基準日に短縮
公開買付WGのTOB見直しに関する報告書を読み解く
金融審議会金融分科会第一部会の公開買付制度等ワーキング・グループは12月21日、「公開買付制度等のあり方について」と題する報告書をとりまとめた(28頁参照)。公開買付期間については、営業日ベースに変更するほか、公開買付けの撤回や条件変更を認める。また、問題視されていた大量保有報告の特例制度については、2週間ごとの基準日における保有状況を5営業日以内に報告するなど、大幅な短縮を図ることが明記された。金融庁は1月下旬からの通常国会に証券取引法の改正案を提出する考えだ。
公開買付期間は営業日ベースで
今回の公開買付制度等の見直しは、自民党の企業統治委員会が7月7日にまとめた「公正なM&Aルールに関する提言」を受けてのもの(本誌No.123参照)。提言では、①経営方針の開示とTOB期間の伸長、②TOB条件の柔軟化(TOBの撤回と価格の下方修正)、③買収者間の公平性確保のための買付ルール整備、④大量保有報告制度の特例の見直しが盛り込まれていた。
3分の1ルールを見直し
まず、3分の1ルール(買付け後の株券等保有割合が3分の1を超える場合に公開買付規制を適用するもの)については、現行制度を維持するものの、例えば、32%の株式を市場外で買付け、その後、市場内で2%の株式を買い付けるようなケースについては、公開買付規制の対象とすることを明確化する。また、種類株式については、今年5月施行予定の会社法において、その設計が柔軟化されることに伴い、公開買付制度を適用する規定を整備する。
公開買付届出書等の開示の拡充へ
公開買付制度の透明性を図る観点の施策として、まず、公開買付届出書等の情報開示を拡充する。具体的には、公開買付価格の決定プロセスや買付け後における対象会社の経営への関与の具体的内容などを開示させる。また、MBO(経営陣による株式買取り)や親会社による子会社株式の買取りについては、経営陣等が買付者となるため、例えば、公開買付価格の妥当性や利益相反を回避するためにとられている方策等を開示させる。
一方、対象会社については、株主等の投資判断の的確性を高める観点から意見表明を義務付けることとされている。意見表明については、公開買付けへの賛否のみならず、併せて①その意見の理由、②買収防衛策発動予定の有無、③賛成・反対等の結論に至ったプロセス等を開示させる。加えて、公開買付者に対し、対象会社から質問する機会を付与する。質問については、意見表明の際に行うこととする。
買収者が設定する公開買付期間については、現行20日以上60日以内とされているが、これは実日数ベースとなっているため、営業日ベース(20営業日以上60営業日以内)に改めることにする。ただし、買付期間が30営業日未満に設定され、対象会社が公開買付けに対して、反対意見を述べる場合には、30営業日を上限として公開買付期間を伸長することができるようにする。
買収防衛策の発動で公開買付けの撤回が可能
公開買付けの撤回については、現行、対象会社の株式交換、合併、破産など、法令で限定列挙されている事由などでしか認められていない。しかし、買収防衛策を導入する企業も増える中、公開買付けの撤回が一切認められないとすると、公開買付者に不測の損害を与えるおそれがある。 このため、例えば、①株式分割、株式の無償割当が決定された場合、②新株・新株予約権の発行が決定された場合、③重要な資産の売却がなされた場合には、公開買付けの撤回を認める。また、買収防衛策が解除されないことが確実な場合にも、公開買付けの撤回を認める。
買付条件の変更については、現行、買付価格の引き下げなど、応募株主に明らかに不利となる条件変更は禁止されている。しかし、対象会社による株式分割、株式の無償割当等により株価が希釈化された場合については、その希釈分に対応した公開買付価格の引き下げを認めるとしている。
その他、公開買付け後における株券等所有割合が3分の2を超える場合には、会社法上、特別決議に対する買付者以外からの拒否権が基本的になくなるため、公開買付者に全部買付義務を課すとしている。
将来発行される株券も公開買付規制の対象
ある者が公開買付けを実施している期間中に、株券等所有割合が既に3分の1超となっている別の者が更なる買付けを行う場合などに限り、公開買付けを義務付ける。
また、株式分割により将来発行される新株や発行決議に基づき将来発行される新株、新株予約権などについては、公開買付規制の対象とする。
 通常国会に証取法の改正案を提出へ
通常国会に証取法の改正案を提出へ特例制度・最短では1週間後の開示
大量保有報告制度は、上場株券等の保有割合が5%を超える保有者に対して、5%を超えることとなった日から原則5営業日以内、以後1%以上の変動があった場合に情報を開示させるもの(いわゆる5%ルール)。
しかし、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社等の機関投資家については、特例が認められている。具体的には、「当該基準日の属する月の翌月十五日まで」(※基準日とは「特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう」)に情報を開示すればよいことになっている。今回の見直しでは、2週間ごとの基準日における保有状況を5営業日までに短縮を図ることになる。このため、最短では、1週間後の開示が実現することになる。
その他、保有割合が10%を上回る取引については、特例対象者でも一般の報告と同じく、提出事由発生から5営業日以内の開示が義務付けられているが、10%超保有の状態から保有割合が10%を下回る取引を行った場合には一般の報告が求められていない。このため、下回る場合でも一般の報告を求めることにする。
保有目的などを開示
大量保有報告書に関しては、保有目的や株券賃借の状況などについて、詳細な開示を求めることやEDINETによる提出の義務付けを行うとしている。
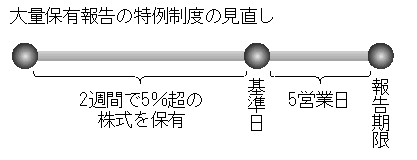
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























