解説記事2006年12月11日 【ニュース特集】 留保金課税は撤廃の方向も特殊支配同族会社には触れず(2006年12月11日号・№190)
ニュース特集
政府税調が平成19年度税制改正に関する答申を提出
留保金課税は撤廃の方向も特殊支配同族会社には触れず
政府税制調査会(本間正明会長)は12月1日、安倍首相に平成19年度の税制改正に関する答申を提出した(27頁参照)。約3週間と短期間でまとめた今回の答申は、減価償却制度における残存価額、償却可能限度額の撤廃、同族会社の留保金課税の撤廃に向けたスタンスの提示など、企業減税が中心の内容となっている。なお、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」については、答申で一切触れられていない。また、来年度中に期限切れとなる証券優遇税率については、留意事項を付して、撤廃を提言。三角合併、信託税制では、租税回避への対応措置の検討が盛り込まれている。
自民党税調が大綱を取りまとめる予定の12月15日まで残りわずか。政府税調の答申がどこまで影響を与えるのか予断を許さない状況だ。

1 特殊支配同族会社に係る見直し論は封印
減価償却見直しで自民税調と足並み揃う
平成19年度の税制改正に関する答申は、安倍政権の「成長なくして財政再建なし」の理念のもと、経済成長路線が重視され、企業減税が中心の内容となった。
減価償却制度における残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)の撤廃の提言は、企業の国際競争力の強化を狙ったものだ。現在、大綱の取りまとめに向けて議論を進めている自民党税制調査会(津島雄二会長)においても、撤廃の方向で意見が集約されており、平成19年度税制改正で実現することが確実な情勢となっている。今後、残存価額の撤廃による償却率の変更(新規取得資産から)が行われることになる。
なお、固定資産税の償却資産について答申は、法人税の減価償却と趣旨が異なるとしたうえで、評価方法の検討を今後の課題としている。自民党税調では、固定資産税についても減免するかどうかが最大の論点となる。最終的には政治的な決着となりそうだ(今号8頁参照)。
特定同族会社の留保金課税は撤廃が濃厚
特定同族会社の留保金課税(図表1参照)については、中小企業の資本蓄積の促進、ベンチャー企業の支援の観点から、見直しが提言された。しかし、留保金課税については平成18年度税制改正で大幅な要件緩和がなされており、今回の答申における「見直し」は、「撤廃」の意味合いを多分に含んだものだ。安倍首相への答申提出後、記者会見した本間会長は、留保金課税の「見直し」との表現について、「撤廃に向けてのスタンスを提示した」と述べるとともに、19年度改正での課題になると明言している。
自民党税調の議論でも、同族会社の留保金課税については撤廃論(大企業については存続論も)が主流となっており、平成19年度税制改正で撤廃される可能性が高くなっている。
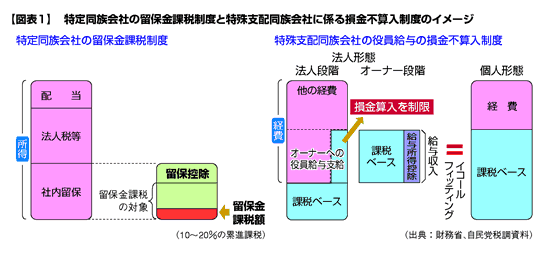
特殊支配同族会社については適用状況待ち?
同族会社に関する税制措置では、平成18年度改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」(図表1参照)に対する風当たりが強くなっている。たとえば、自民党の財務金融部会、経済産業部会などが廃止、見直しを要望しているほか、政府税調の第2回グループ・ディスカッション(11月15日開催)においても委員から、見直しを求める意見が出された。
しかし、今回の答申では、同制度については一言も触れられておらず(答申に付された「その他の主な意見」にも明記なし)、見直し論は封印された状況だ。また、財務省は平成19年度改正での見直しについて「あり得ない」とコメントしている。
だが、平成19年3月決算での適用状況によっては、平成20年度税制改正議論の焦点の1つになる可能性がある。
2 三角合併では、外国子会社合算税制の見直しへ
100%親会社の株式交付でも適格要件に
三角合併は来年5月から可能となるが、答申では、現行の組織再編税制における譲渡損益の課税の繰延べと同様の考え方で対応すべきとしている。
具体的には、現行の適格要件(図表2参照)を見直し、合併対価について合併法人株式以外に合併法人の100%親会社の株式についても認めることとし、そのうえで合併当事者間の要件を緩和するかどうかが検討されることになる模様だ。
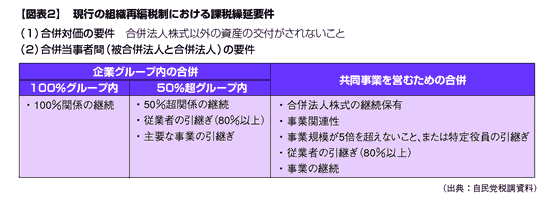
この合併当事者間の要件緩和では、2通りの案が考えられる。
① 従来どおり合併法人と被合併法人との間で判断し、親会社については判断の対象に加えない。
→合併法人がペーパーカンパニーの場合、事業関連性等が認められず非適格になる。
② 合併法人と被合併法人の間のみでなく、親会社やそのグループ子会社等も含めて判断する。
→合併法人(親会社)がペーパーカンパニーであっても一定の場合には適格となる。
なお、上記のとおり、親会社の範囲については、「100%の親子関係」を求めることになりそうだ。
外国法人株主への旧株譲渡益課税を検討
三角合併では、合併対価として外国親会社株式の交付が可能となり、クロスボーダーの組織再編が起こることになる。答申では、「内外無差別を原則とすべき」としており、被合併法人株主が非居住者・外国法人である場合、非居住者・外国法人が外国法人株式を取得することになるため、繰り延べられた譲渡益に対する課税権が及ばなくなる問題への対応も指摘している。
ここでは、適格組織再編成において日本に課税権のある株式を有する非居住者・外国法人株主が外国親法人株式を受け取る場合は、合併時に旧株譲渡益への課税を行うことが検討されることになる。
また、外国法人株主が日本支店で保有する株式は課税を繰延べとするが、日本支店から移管した場合の手当てついても検討される模様だ。
外国子会社合算税制では議決権を考慮へ
答申では、タックス・ヘイブンを利用した三角合併により租税回避を容易にする組織形態(コーポレート・インバージョン)への対応にも言及している。まず、タックス・ヘイブンにある実体のない外国法人子会社となった場合は、当該外国法人の所得を株主である居住者の所得に合算(組織再編成前に内国法人を少数株主が支配し、再編成後、その株主が外国法人親会社を支配する場合に限定)することが検討課題となる(図表3参照)。
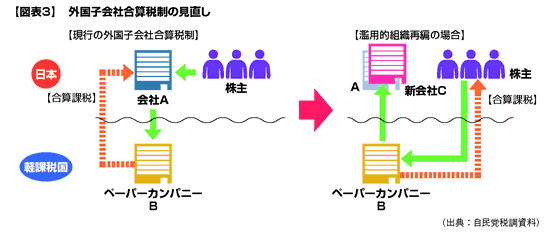
さらに、現行の外国子会社合算税制での計算方法を見直し、合算所得金額を5%以上保有の場合の配当請求権のみでの計算に議決権を考慮した計算方法を加えることなどが検討されるようだ。
「必要な場合」には信託段階課税
信託法の改正については、「我が国経済における事業形態の多様化がさらに進み、経済活性化にも資すると期待される。」としている。そのうえで、信託の利用実態に対応した税制上の検討の必要性を提起している。
具体的には、新たな制度を利用した租税回避行為の懸念が指摘されているとして、必要な場合に信託段階課税を行うなど、適切な措置を講ずることを求めている。しかし、答申にはこの「必要な場合」についての例示はなく、どのようなケースで課税するかについては明らかにされていない。
なお、これまでの議論からすれば、自己信託(法人同様の事業を行う信託が創設された場合の法人税の回避)、目的信託(受益者の定めがなく相続税を課税できず)について、信託段階での課税が検討されることになりそうだ。
3 相互協議中の納税猶予で企業負担を軽減
海外に進出している企業への更正処分の増加から、移転価格税制の見直し論が高まっている。答申においても、企業の予測可能性を高めるための適用基準の明確化、手続の改善、相互協議体制を強化することによる事前確認制度の迅速化などが求められた。
また、二重課税に伴う企業負担を軽減するため、二国間協議で合意が得られるまでの間、納税を猶予する制度(図表4参照)の導入を提言している。同制度については、自民党の経済産業部会、厚生労働部会が重点的に要望しており、平成19年度税制改正で導入される可能性が高くなっている。
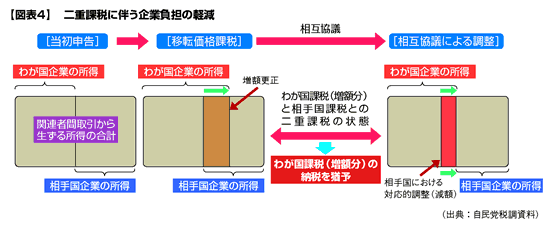
4 証券優遇税制では廃止を提言も、留意事項を付す
自民党税調では「現状維持」が圧倒的
来年度中に期限切れとなる上場株式等の譲渡益、配当に対する軽減税率(10%)については、期限到来とともに廃止することを答申している。また、軽減税率の廃止にあたっては、株式市場への変動要因にならない工夫が必要とし、激変緩和措置の必要性にも言及している。
この証券優遇措置の存廃については、今後、自民党税調での議論が激化しそうだ。答申提出と同じ12月1日午前の正副会長・顧問・幹事会議では、圧倒的に10%の税率維持を求める意見が強かった。しかし、会議後の町村小委員長のコメントは、「幹部の意見であり、尊重される」としながら、「今後の議論で詰めていく」と言葉を濁している。同日午後の小委員会でも同様に、10%の税率維持が圧倒的に多かったが、最終的な結論にまでは至っていない(8頁参照)。
最終的には激変緩和措置で調整か
自民党税調の議論で「現状維持」が大多数を占めるにもかかわらず、結論を出せない背景には、政府の見解との調整を図りたい意向が伺える。12月15日をめどに取りまとめられる大綱では、廃止を前提に何らかの激変緩和措置の導入がなされることが予想される。
執行面で資料情報制度の強化を提言
そのほか、答申では税務執行面に関して、主に以下の提言が行われている。
① 金融所得課税の一体化では、源泉徴収制度、資料情報制度、金融番号制度等の環境整備について議論
② 国税納付におけるコンビニ納付の実現
③ 電子申告の手続の簡素化など普及のための方策の検討
④ 税務当局が差し押さえた動産等を売却する公売の売却手続の円滑化
⑤ 源泉徴収、支払調書の提出の対象となる報酬範囲の見直し
⑥ 投資ファンドから分配される損益に関する資料情報制度の改善(図表5参照)
特に、③については、国税庁が平成22年度までにe-Tax普及率を50%とする目標を掲げており、e-Taxで申告した場合の費用等に対して税額控除が認められるかが注目される(9頁参照)。
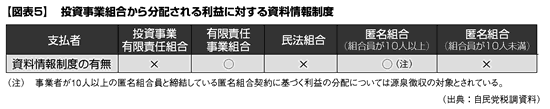
政府税調が平成19年度税制改正に関する答申を提出
留保金課税は撤廃の方向も特殊支配同族会社には触れず
政府税制調査会(本間正明会長)は12月1日、安倍首相に平成19年度の税制改正に関する答申を提出した(27頁参照)。約3週間と短期間でまとめた今回の答申は、減価償却制度における残存価額、償却可能限度額の撤廃、同族会社の留保金課税の撤廃に向けたスタンスの提示など、企業減税が中心の内容となっている。なお、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」については、答申で一切触れられていない。また、来年度中に期限切れとなる証券優遇税率については、留意事項を付して、撤廃を提言。三角合併、信託税制では、租税回避への対応措置の検討が盛り込まれている。
自民党税調が大綱を取りまとめる予定の12月15日まで残りわずか。政府税調の答申がどこまで影響を与えるのか予断を許さない状況だ。

1 特殊支配同族会社に係る見直し論は封印
減価償却見直しで自民税調と足並み揃う
平成19年度の税制改正に関する答申は、安倍政権の「成長なくして財政再建なし」の理念のもと、経済成長路線が重視され、企業減税が中心の内容となった。
減価償却制度における残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)の撤廃の提言は、企業の国際競争力の強化を狙ったものだ。現在、大綱の取りまとめに向けて議論を進めている自民党税制調査会(津島雄二会長)においても、撤廃の方向で意見が集約されており、平成19年度税制改正で実現することが確実な情勢となっている。今後、残存価額の撤廃による償却率の変更(新規取得資産から)が行われることになる。
なお、固定資産税の償却資産について答申は、法人税の減価償却と趣旨が異なるとしたうえで、評価方法の検討を今後の課題としている。自民党税調では、固定資産税についても減免するかどうかが最大の論点となる。最終的には政治的な決着となりそうだ(今号8頁参照)。
特定同族会社の留保金課税は撤廃が濃厚
特定同族会社の留保金課税(図表1参照)については、中小企業の資本蓄積の促進、ベンチャー企業の支援の観点から、見直しが提言された。しかし、留保金課税については平成18年度税制改正で大幅な要件緩和がなされており、今回の答申における「見直し」は、「撤廃」の意味合いを多分に含んだものだ。安倍首相への答申提出後、記者会見した本間会長は、留保金課税の「見直し」との表現について、「撤廃に向けてのスタンスを提示した」と述べるとともに、19年度改正での課題になると明言している。
自民党税調の議論でも、同族会社の留保金課税については撤廃論(大企業については存続論も)が主流となっており、平成19年度税制改正で撤廃される可能性が高くなっている。
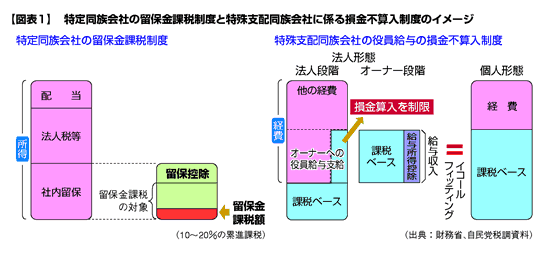
特殊支配同族会社については適用状況待ち?
同族会社に関する税制措置では、平成18年度改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」(図表1参照)に対する風当たりが強くなっている。たとえば、自民党の財務金融部会、経済産業部会などが廃止、見直しを要望しているほか、政府税調の第2回グループ・ディスカッション(11月15日開催)においても委員から、見直しを求める意見が出された。
しかし、今回の答申では、同制度については一言も触れられておらず(答申に付された「その他の主な意見」にも明記なし)、見直し論は封印された状況だ。また、財務省は平成19年度改正での見直しについて「あり得ない」とコメントしている。
だが、平成19年3月決算での適用状況によっては、平成20年度税制改正議論の焦点の1つになる可能性がある。
2 三角合併では、外国子会社合算税制の見直しへ
100%親会社の株式交付でも適格要件に
三角合併は来年5月から可能となるが、答申では、現行の組織再編税制における譲渡損益の課税の繰延べと同様の考え方で対応すべきとしている。
具体的には、現行の適格要件(図表2参照)を見直し、合併対価について合併法人株式以外に合併法人の100%親会社の株式についても認めることとし、そのうえで合併当事者間の要件を緩和するかどうかが検討されることになる模様だ。
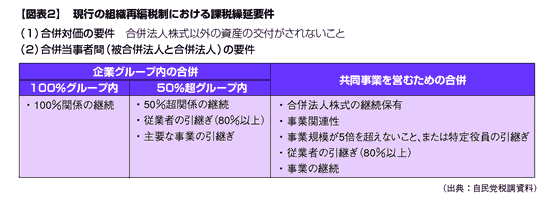
この合併当事者間の要件緩和では、2通りの案が考えられる。
① 従来どおり合併法人と被合併法人との間で判断し、親会社については判断の対象に加えない。
→合併法人がペーパーカンパニーの場合、事業関連性等が認められず非適格になる。
② 合併法人と被合併法人の間のみでなく、親会社やそのグループ子会社等も含めて判断する。
→合併法人(親会社)がペーパーカンパニーであっても一定の場合には適格となる。
なお、上記のとおり、親会社の範囲については、「100%の親子関係」を求めることになりそうだ。
外国法人株主への旧株譲渡益課税を検討
三角合併では、合併対価として外国親会社株式の交付が可能となり、クロスボーダーの組織再編が起こることになる。答申では、「内外無差別を原則とすべき」としており、被合併法人株主が非居住者・外国法人である場合、非居住者・外国法人が外国法人株式を取得することになるため、繰り延べられた譲渡益に対する課税権が及ばなくなる問題への対応も指摘している。
ここでは、適格組織再編成において日本に課税権のある株式を有する非居住者・外国法人株主が外国親法人株式を受け取る場合は、合併時に旧株譲渡益への課税を行うことが検討されることになる。
また、外国法人株主が日本支店で保有する株式は課税を繰延べとするが、日本支店から移管した場合の手当てついても検討される模様だ。
外国子会社合算税制では議決権を考慮へ
答申では、タックス・ヘイブンを利用した三角合併により租税回避を容易にする組織形態(コーポレート・インバージョン)への対応にも言及している。まず、タックス・ヘイブンにある実体のない外国法人子会社となった場合は、当該外国法人の所得を株主である居住者の所得に合算(組織再編成前に内国法人を少数株主が支配し、再編成後、その株主が外国法人親会社を支配する場合に限定)することが検討課題となる(図表3参照)。
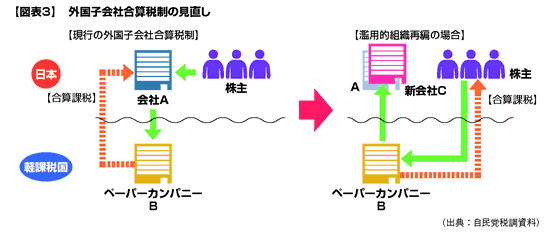
さらに、現行の外国子会社合算税制での計算方法を見直し、合算所得金額を5%以上保有の場合の配当請求権のみでの計算に議決権を考慮した計算方法を加えることなどが検討されるようだ。
「必要な場合」には信託段階課税
信託法の改正については、「我が国経済における事業形態の多様化がさらに進み、経済活性化にも資すると期待される。」としている。そのうえで、信託の利用実態に対応した税制上の検討の必要性を提起している。
具体的には、新たな制度を利用した租税回避行為の懸念が指摘されているとして、必要な場合に信託段階課税を行うなど、適切な措置を講ずることを求めている。しかし、答申にはこの「必要な場合」についての例示はなく、どのようなケースで課税するかについては明らかにされていない。
なお、これまでの議論からすれば、自己信託(法人同様の事業を行う信託が創設された場合の法人税の回避)、目的信託(受益者の定めがなく相続税を課税できず)について、信託段階での課税が検討されることになりそうだ。
3 相互協議中の納税猶予で企業負担を軽減
海外に進出している企業への更正処分の増加から、移転価格税制の見直し論が高まっている。答申においても、企業の予測可能性を高めるための適用基準の明確化、手続の改善、相互協議体制を強化することによる事前確認制度の迅速化などが求められた。
また、二重課税に伴う企業負担を軽減するため、二国間協議で合意が得られるまでの間、納税を猶予する制度(図表4参照)の導入を提言している。同制度については、自民党の経済産業部会、厚生労働部会が重点的に要望しており、平成19年度税制改正で導入される可能性が高くなっている。
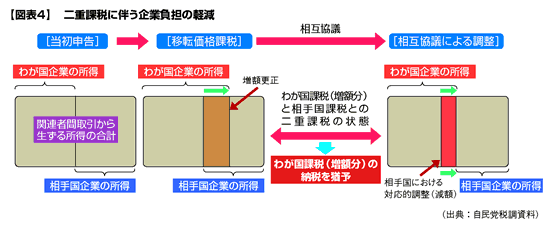
4 証券優遇税制では廃止を提言も、留意事項を付す
自民党税調では「現状維持」が圧倒的
来年度中に期限切れとなる上場株式等の譲渡益、配当に対する軽減税率(10%)については、期限到来とともに廃止することを答申している。また、軽減税率の廃止にあたっては、株式市場への変動要因にならない工夫が必要とし、激変緩和措置の必要性にも言及している。
この証券優遇措置の存廃については、今後、自民党税調での議論が激化しそうだ。答申提出と同じ12月1日午前の正副会長・顧問・幹事会議では、圧倒的に10%の税率維持を求める意見が強かった。しかし、会議後の町村小委員長のコメントは、「幹部の意見であり、尊重される」としながら、「今後の議論で詰めていく」と言葉を濁している。同日午後の小委員会でも同様に、10%の税率維持が圧倒的に多かったが、最終的な結論にまでは至っていない(8頁参照)。
最終的には激変緩和措置で調整か
自民党税調の議論で「現状維持」が大多数を占めるにもかかわらず、結論を出せない背景には、政府の見解との調整を図りたい意向が伺える。12月15日をめどに取りまとめられる大綱では、廃止を前提に何らかの激変緩和措置の導入がなされることが予想される。
執行面で資料情報制度の強化を提言
そのほか、答申では税務執行面に関して、主に以下の提言が行われている。
① 金融所得課税の一体化では、源泉徴収制度、資料情報制度、金融番号制度等の環境整備について議論
② 国税納付におけるコンビニ納付の実現
③ 電子申告の手続の簡素化など普及のための方策の検討
④ 税務当局が差し押さえた動産等を売却する公売の売却手続の円滑化
⑤ 源泉徴収、支払調書の提出の対象となる報酬範囲の見直し
⑥ 投資ファンドから分配される損益に関する資料情報制度の改善(図表5参照)
特に、③については、国税庁が平成22年度までにe-Tax普及率を50%とする目標を掲げており、e-Taxで申告した場合の費用等に対して税額控除が認められるかが注目される(9頁参照)。
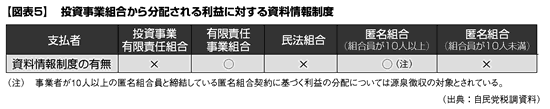
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























