解説記事2007年08月27日 【会計基準等解説】 「過年度遡及修正に関する論点の整理」について(2007年8月27日号・№224)
実務解説
「過年度遡及修正に関する論点の整理」について
企業会計基準委員会 研究員 玄蕃進吾
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準で見られるような、会計方針の変更や表示方法の変更が行われた場合などの財務諸表の過年度遡及修正に関する取扱いについての検討を行い、ひととおりの整理が終了したことから、平成19年7月9日に、これを「過年度遡及修正に関する論点の整理」(以下、本論点整理という。)として公表した(脚注1)。ASBJでは今後、本論点整理に寄せられた意見も参考に、財務諸表の過年度遡及修正の取扱いに関する取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。
本稿は、本論点整理の概要を解説するものであるが、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ.本論点整理公表の経緯
財務諸表の過年度遡及修正に関しては、これまで、商法や税法の制約から過年度財務諸表を遡って修正することはできないという考え方もあったが、平成18年5月に施行された会社法により、過年度事項の修正を前提とした当期計算書類の作成及び修正後の過年度事項の参考情報としての提供が妨げられないことが明確化されるなど、会計基準開発を巡る環境が大きく変わりつつある。
また、平成16年9月以降、ASBJと国際会計基準審議会(IASB)との間で行われている我が国の会計基準と国際財務報告基準との差異の縮小を目的とした両会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおいても過年度遡及修正は、特に優先して取り組むべき項目の1つとして位置付けられている。
このような状況に鑑み、当委員会では、学識経験者を含むワーキング・グループを平成18年12月に立ち上げ、さらに平成19年3月には過年度遡及修正専門委員会を設置し、過年度遡及修正に関する論点について検討を重ねてきたものである。
なお、本論点整理では、具体的な項目の論点に入る前に、財務諸表の過年度遡及修正の取扱いを定める必要性についての包括的な論点を掲げている(論点1)。
ここでは、こうした取扱いを求める必要性として、以下の3点を挙げている。
① 比較可能で意思決定に有用な過年度の情報を、原則として財務諸表本体で提供
② 過年度遡及修正の実施に向けた条件が会社法で整備されたことへの対応
③ 国際財務報告基準(及び米国会計基準)との会計基準のコンバージェンスの促進
ただし、実務負担の増加を懸念する指摘、裁量的な会計処理が行われる可能性を懸念する指摘など、過年度遡及修正の導入によるデメリットについての指摘もあり、過年度遡及修正を実際に導入するにあたっては、コスト・ベネフィットの観点等も考慮した検討が必要と考えられる。遡及修正された過年度財務諸表の取扱いについては、誤謬に関する事項も含め、会社法及び証券取引法(金融商品取引法)に基づく監査も含めた開示制度との関係など、関連法制度との関係の整理も不可欠であると考えられる。
Ⅱ.会計方針の変更(論点3)及び表示方法の変更(論点4)に係る過年度遡及修正
国際財務報告基準及び米国会計基準では、自発的な会計方針の変更は過去の財務諸表に遡及適用することが求められており、新たに適用された会計基準の適用による会計方針の変更の場合でも、その会計基準に特段の経過措置が定められていないときには、同様の取扱いをすることが求められている。一方で、我が国における会計方針の変更に関する現行の取扱い(財務諸表等規則等)では、国際的な会計基準とは異なり、過年度財務諸表への遡及適用はせず、その影響額の開示のみが求められている。さらにここで開示される影響額とは、前期と同様の会計方針を当期においても適用した場合の営業損益等に関する差額である。
このため、会計方針の変更を行った場合に過年度財務諸表に遡及適用を行うことにより、特定の項目だけではなく、財務諸表全般についての比較可能性が高まり、さらに、比較のベースが旧基準ベースから新基準ベースへと変わることによっても、情報の有用性がより高まる効果も期待できるため、今後は国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表への遡及適用による対応への転換を検討していくことが考えられる。
ただし、当期に行われた会計方針の変更は、前期の時点では会計方針の変更に至るまでの正当な理由がなかったと考えられるが、それにもかかわらず当期の会計方針を前期に遡及適用し、遡及適用後の情報を提供することがすべての場合において有用であるといえるかどうか、例えば過去に情報が収集されておらず、遡及適用による再計算ができない場合などの取扱いをどう定めるのかといった点については、今後も検討を続けていく必要があるものと考えられる。
また、国際的な会計基準においては、表示方法の変更が行われた場合には会計方針の変更と同様、財務諸表の比較可能性を確保するための遡及的な組替えが求められている。我が国における現行の取扱い(財務諸表等規則等)においても比較可能性を確保するための注記による開示は行われているが、遡及的な組替えは求められていない。会計方針の変更について遡及適用を求める場合には、表示方法の変更に関しても、現行の注記による対応から、国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表の組替えによる対応へと転換する方向で検討することが考えられる。
Ⅲ.会計上の見積りの変更に係る取扱い(論点5)
会計上の見積りの変更について、過年度財務諸表に遡って修正を行わないという点に関しては、我が国における現行実務と、国際財務報告基準及び米国会計基準の定めの間に相違はないものと思われる。また、会計上の見積りの変更は、新しい情報(事実)によってもたらされるものであることに着目すれば、その変更による影響額は、過年度よりもむしろ当年度以降に帰属すべき損益であると考えられる。したがって、会計上の見積りの変更については、現行の取扱いを踏襲し、過年度財務諸表に遡って修正を行わない方向で検討することが考えられる。
ただし、固定資産の減価償却方法や耐用年数の変更の取扱いに関連し、後述の[各論1]から[各論3]で説明するような論点がある。また、会計上の見積りの変更と誤謬の訂正との境界や、見積りの変更時期のあり方についても、合わせて検討することが必要と考えられる。
Ⅳ.固定資産の減価償却方法の変更及び耐用年数の変更に関する取扱いについての個別論点(論点3及び5に関連する各論)
1 減価償却方法の変更の取扱い[各論1] 我が国においては、減価償却方法は、会計方針のひとつとされており、その変更は会計方針の変更として取り扱うことになっている。すなわち、我が国では減価償却方法について、固定資産の取得原価を各年度に配分する方法として、定率法や定額法などの一定の計画的・規則的な配分法があることを所与とし、そうした既成の会計方針の選択の問題として捉えているものと考えられる。一方、国際的な会計基準では、減価償却方法の変更の実質を、資産に具現化される経済的便益の費消パターンに関する見積りの変更として捉えている。
減価償却方法の変更を、国際財務報告基準のように、資産に具現化される経済的便益の費消パターンに関する見積りの変更として第一義的にとらえるのが妥当であれば、会計処理についてもこれを見積りの変更と同様に処理することが考えられる。
その一方、固定資産の経済的便益の費消パターンはそもそも見積りが不可能であるからこそ、計画的・規則的な償却を行っていると考えるのが歴史的な経緯であるとの指摘もある。このように、減価償却方法と見積りの要素との関係を切り離し、固定資産に係る計画的・規則的な費用配分方法として捉えるのであれば、我が国の現行の取扱いのとおり、会計方針の変更として捉えることになるものと考えられる。なお、このように考える場合には、減価償却方法の変更についても、会計方針の変更と区別することなく、遡及適用の対象とすべきかどうかということも論点となる。
2 見積りの変更(耐用年数の変更)に関する会計処理の考え方[各論2] 会計上の見積りの変更について、過年度財務諸表に遡って修正を行わないという点に関しては、我が国における現行実務と、国際財務報告基準及び米国会計基準の定めの間に相違はないものと思われる。しかしながら、見積りの変更のひとつと考えられる耐用年数の変更に関しては、修正額を変更期間及びそれ以降の期間で認識する「プロスペクティブ方式」もしくは、修正額を変更期間で一時に認識する「キャッチ・アップ方式」の2つの考え方がとり得るものと思われる(次頁参照)。
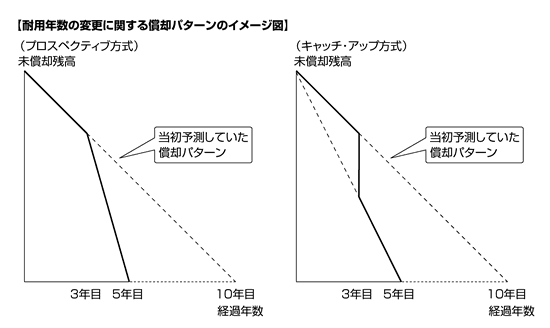
国際財務報告基準や米国会計基準では、固定資産の耐用年数の変更を見積りの変更と捉え、プロスペクティブ方式を採用しているものと通常解釈されている。我が国においても、固定資産の耐用年数の変更をプロスペクティブ方式によって処理する実務が一般的ではあるものの、減価償却計算に適用されている耐用年数(又は残存価額)が、予見することのできなかった原因等により著しく不合理となった場合に、耐用年数の短縮や残存価額の修正に基づいて一時に減価償却累計額の修正を行う場合(臨時償却)もある。
これらの2つの方法について検討するにあたっては、見積りの変更による費用配分パターンの変動に関する実態解釈という切り口のほか、こうした見積りの変更が、固定資産に関するストック評価額の見積額に与える影響という側面に着目する切り口もあるものと考えられる。このような点に着目した場合、当期の見積りの変更をまずもって当期の貸借対照表価額に反映すること、すなわち固定資産のストック評価額に反映させ、その影響額をすべて当期の損益として認識する方法が妥当であるとも考えられる(脚注2)。
3 減損処理と臨時償却の関係[各論3] 固定資産の減損処理を行う際、臨時償却による損失も、減損による損失も、認識された年度の損失とされる点では同じであることから、回収を見込めない帳簿価額を一纏めにして、減損の会計処理を適用することとされている。しかしながら、従前より両者の関係のあり方には議論のあるところであり、過年度遡及修正の導入や見積りの変更に関する取扱いの検討に合わせ、一度整理をしておく必要があるものと考える。
Ⅴ.セグメントの区分方法の変更に係る具体的な取扱い(論点6)
我が国の現行の取扱いでも、前期のセグメント情報を変更後のセグメントの区分方法等により遡及して作り直したものと比較して開示することは認められているが、国際的な会計基準とは異なり、その採否は企業の裁量に委ねられているため、会計方針の変更について過年度遡及修正を求める場合には、セグメントの区分方法の変更についても、国際的な会計基準と同様の遡及適用を求めていくことを検討していくことが考えられる。
ただし、セグメント情報の開示に関しては、別プロジェクトにおいてマネジメント・アプローチの採用に関する検討が進められており、求められる開示の内容が変わることも想定されるため、セグメントの区分方法等の変更に係る取扱いに関しては、セグメント情報の開示全般の議論と並行して、今後の開示のあり方について検討を続けていくことが考えられる。
Ⅵ.誤謬に係る過年度遡及修正(論点7)
我が国においては現在、誤謬に関する会計上の取扱いとしては、前期損益修正項目として当期の損益で修正する方法のみが示されている。一方、国際的な会計基準では、すでに公表済の財務諸表について誤謬が発見された場合、過年度財務諸表を修正再表示することとされている。
この点に関しては、会計上の誤謬の取扱いとして、国際的な会計基準と同様に、重要な誤謬を修正再表示する考え方を導入することは、期間比較が可能な情報を開示するという観点からも有用であり、会計基準のコンバージェンスを図るという観点からも望ましいという考え方がある。また、そもそも誤謬のある過年度財務諸表を修正再表示することは、会計方針の変更に関する遡及適用等とは性格が異なっており、比較可能性の確保や会計基準のコンバージェンスの促進という観点からではなく、当然の要請として会計基準に定めておくべきであるとの指摘がある。さらに、すべての会社に対して誤謬による修正再表示を求めるのであれば、現行の会計上の誤謬の取扱いを変更することが必要であるという指摘もある。
こうした指摘がある一方、我が国においては、財務諸表に重要な影響を及ぼすような誤謬が発見された場合、当該誤謬が訂正報告書の提出事由に該当するときには、修正再表示が行われることになるため、修正再表示の枠組みは開示制度において手当て済みであるという考え方がある。
会計上の誤謬の取扱いに関しては、前述の開示制度との関係を考慮しつつ、国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表の修正再表示による対応を求めることとするかどうかも含め、検討を進めていく必要があるものと考えられる。
なお、誤謬のうち、重要なものについての会計処理を定めるとした場合、何をもって「重要な誤謬」とするのかが重要な論点となる(脚注3)。この点については、実務上の混乱を招かないように、会社法及び証券取引法(金融商品取引法)に基づく開示制度との関係などについても、十分な整理が必要であるものと考えられる。
Ⅶ.四半期(中間)財務諸表開示に固有の遡及修正(論点8)
平成19年3月にASBJが公表した企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」では、第2四半期以降に会計方針の変更を行った場合、年度の期首に遡って修正した四半期財務諸表を開示することは求めていないが、年度の財務諸表における会計方針の変更について遡及適用を求める場合には、国際的な会計基準と同様に、四半期(中間)財務諸表開示においても、現行の注記による対応から、それ以前の四半期会計期間への遡及的な適用による対応へと、原則的には転換する方向で検討することが考えられる。
また、四半期(中間)財務諸表の遡及修正に固有の問題としては、会計方針に関する会計年度全体での首尾一貫性の問題がある。国際的な会計基準においては、会計年度の中途で行う会計方針の変更に関する遡及適用を求める際には、同一の会計年度中のそれより前の中間期間すべてに遡及適用することを定めている。ただし、この点については、遡及修正できないことが、会計方針の変更の制約となるのは問題があるのではないかという指摘もあり、さらなる検討を進めていく必要がある。
Ⅷ.廃止事業の報告に係る過年度遡及修正(論点9)
我が国では廃止事業に関する取扱いは定められていないが、国際的な会計基準では、財務諸表の報告企業において処分済み又は処分が予定されている事業(廃止事業)がある場合には、損益計算書上、継続事業に係る損益と区分し、廃止事業に係る損益を独立項目で表示し、過年度の損益計算書において遡及的に修正することが求められており、我が国において廃止事業の報告が行われることとなった場合には、国際的な会計基準と同様に、過年度の損益情報を遡及的に修正するという方向で検討していくことが考えられる。
ただし、廃止事業の報告に関しては、過年度の損益計算書の遡及的な修正が重要な論点の1つではあるものの、国際的な会計基準においては売却目的で保有する非流動資産(及び処分グループ)の減損に関連して設けられた定めであり、廃止事業の定義の設定いかんでは実務が非常に煩雑となるという指摘があることなどから、廃止事業の報告に関しては、別プロジェクトでその取扱いを議論した後、改めて過年度遡及修正に係る論点について検討を行うことも考えられる。
Ⅸ.個別財務諸表における過年度遡及修正の適用上の論点(論点2)
過年度遡及修正を求めることにより、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることができるという点については、連結財務諸表だけでなく、個別財務諸表についても同様であるものと考えられる。我が国においては上場会社が個別財務諸表のみを公表している場合に限らず、連結財務諸表を公表する場合でも個別財務諸表をあわせて公表しているため、これらの会社が公表する個別財務諸表についても連結財務諸表と同様に、過年度遡及修正によって期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることが期待されるものと考えられる。
しかしながら、非上場会社の場合、個別財務諸表上も一律に過年度遡及修正を求めるか否かについては、コスト・ベネフィットの観点から、適用上の問題に関する検討が必要ではないかという指摘がある。この点に関しては、非上場会社の個別財務諸表については、遡及修正された過年度の情報に関するニーズは、上場会社の連結財務諸表ほどには高くないとも考えられるため、例えば遡及修正に係る影響額を当期の期首の剰余金に含めるのか、それとも当期の損益計算に含めるのかといった問題と、遡及修正後の過年度財務諸表の開示の問題に分け、その各々について適用上の論点を整理することが考えられる。
なお、この点に関連し、連結財務諸表で過年度遡及修正を行うこととする場合、連結財務諸表は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない(連結財務諸表原則第二2)とされていることから、非上場会社であっても上場会社の子会社にあたる場合には、その個別財務諸表にも当然に過年度遡及修正を求めることになるのではないかとの考え方がある。しかし、親会社の連結決算手続上利用するために内部的に作成された情報により、こうした点が担保されると考えることができるのであれば、当該子会社が法的に求められる個別財務諸表で過年度遡及修正を行うべきかどうかについては、コスト・ベネフィットの観点から、連結財務諸表上での取扱いとは別途のものとする場合も考えられる(脚注4)。その一方、非上場会社の場合でも、会計監査人を設置する会社であるときには、従来の考え方との整合性を踏まえ、上場会社において過年度遡及修正が求められるのであれば、これに準じた取扱いにすることが適切であるとする考え方もあり、これらの観点も含め、引き続き検討を行っていく必要があるものと思われる。
Ⅹ.その他の論点(論点10)
1 報告事業体の変更 米国の会計基準においては、特定の子会社の変動など報告事業体の変更があった場合、新しい報告事業体の財務諸表を示すために、その変更を財務諸表に遡及適用しなければならないとされている。ただし、仮に米国と同様のこの定めを設けたとしても、設立や買収などによる子会社の変動はこれに該当しないものとされていることなどから、この定めが適用される局面は限定されるものと考えられる。
2 既存の会計基準との整合性 我が国の既存の会計基準は、過年度遡及修正が認められないことを前提に構築されているため、本論点整理でとりあげた四半期会計基準やセグメント情報の開示に関する取扱いのほかにも、既存の会計基準全般に及ぼす影響も視野に入れ、検討を進めていく必要がある。
3 過年度遡及修正の考え方を導入する際の適用時期等に関する留意点 過年度遡及修正の適用は我が国にとって新しい考え方の導入であり、関連法制度との関係の整理が不可欠であるため、その適用時期の設定等については、この点を十分に考慮することが必要と考えられる。(げんば・しんご)
脚注
1 ASBJのホームページ、(http://www.asb.or.jp/html/documents/summary_issue/retro/)を参照。
コメントの締切りは平成19年9月26日(水)である。
2 国際財務報告基準においても、固定資産に関連する見積り以外の見積りの変更、例えば不良債権の金額の見積りの変更などは、このように考えることで、その処理方法をプロスペクティブ方式のなかに包含して解釈しているようである。
3 米国においては現在、誤謬の重要性に関して、ロールオーバー法(損益計算書に与える影響度合いにより重要性を判定)及びアイアン・カーテン法(貸借対照表に与える影響度合いにより重要性を判定)の両方を用い、誤謬の程度を測定しその重要性を評価する方法が提案されている。
4 実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」では、在外子会社の財務諸表には、所在地国で法的に求められるものや外部に公表されるものに限らず、連結決算手続上利用するために内部的に作成されたものを含むとしている取扱いがある。
「過年度遡及修正に関する論点の整理」について
企業会計基準委員会 研究員 玄蕃進吾
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準で見られるような、会計方針の変更や表示方法の変更が行われた場合などの財務諸表の過年度遡及修正に関する取扱いについての検討を行い、ひととおりの整理が終了したことから、平成19年7月9日に、これを「過年度遡及修正に関する論点の整理」(以下、本論点整理という。)として公表した(脚注1)。ASBJでは今後、本論点整理に寄せられた意見も参考に、財務諸表の過年度遡及修正の取扱いに関する取りまとめに向けた検討を続けていく予定である。
本稿は、本論点整理の概要を解説するものであるが、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅰ.本論点整理公表の経緯
財務諸表の過年度遡及修正に関しては、これまで、商法や税法の制約から過年度財務諸表を遡って修正することはできないという考え方もあったが、平成18年5月に施行された会社法により、過年度事項の修正を前提とした当期計算書類の作成及び修正後の過年度事項の参考情報としての提供が妨げられないことが明確化されるなど、会計基準開発を巡る環境が大きく変わりつつある。
また、平成16年9月以降、ASBJと国際会計基準審議会(IASB)との間で行われている我が国の会計基準と国際財務報告基準との差異の縮小を目的とした両会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおいても過年度遡及修正は、特に優先して取り組むべき項目の1つとして位置付けられている。
このような状況に鑑み、当委員会では、学識経験者を含むワーキング・グループを平成18年12月に立ち上げ、さらに平成19年3月には過年度遡及修正専門委員会を設置し、過年度遡及修正に関する論点について検討を重ねてきたものである。
なお、本論点整理では、具体的な項目の論点に入る前に、財務諸表の過年度遡及修正の取扱いを定める必要性についての包括的な論点を掲げている(論点1)。
ここでは、こうした取扱いを求める必要性として、以下の3点を挙げている。
① 比較可能で意思決定に有用な過年度の情報を、原則として財務諸表本体で提供
② 過年度遡及修正の実施に向けた条件が会社法で整備されたことへの対応
③ 国際財務報告基準(及び米国会計基準)との会計基準のコンバージェンスの促進
ただし、実務負担の増加を懸念する指摘、裁量的な会計処理が行われる可能性を懸念する指摘など、過年度遡及修正の導入によるデメリットについての指摘もあり、過年度遡及修正を実際に導入するにあたっては、コスト・ベネフィットの観点等も考慮した検討が必要と考えられる。遡及修正された過年度財務諸表の取扱いについては、誤謬に関する事項も含め、会社法及び証券取引法(金融商品取引法)に基づく監査も含めた開示制度との関係など、関連法制度との関係の整理も不可欠であると考えられる。
Ⅱ.会計方針の変更(論点3)及び表示方法の変更(論点4)に係る過年度遡及修正
国際財務報告基準及び米国会計基準では、自発的な会計方針の変更は過去の財務諸表に遡及適用することが求められており、新たに適用された会計基準の適用による会計方針の変更の場合でも、その会計基準に特段の経過措置が定められていないときには、同様の取扱いをすることが求められている。一方で、我が国における会計方針の変更に関する現行の取扱い(財務諸表等規則等)では、国際的な会計基準とは異なり、過年度財務諸表への遡及適用はせず、その影響額の開示のみが求められている。さらにここで開示される影響額とは、前期と同様の会計方針を当期においても適用した場合の営業損益等に関する差額である。
このため、会計方針の変更を行った場合に過年度財務諸表に遡及適用を行うことにより、特定の項目だけではなく、財務諸表全般についての比較可能性が高まり、さらに、比較のベースが旧基準ベースから新基準ベースへと変わることによっても、情報の有用性がより高まる効果も期待できるため、今後は国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表への遡及適用による対応への転換を検討していくことが考えられる。
ただし、当期に行われた会計方針の変更は、前期の時点では会計方針の変更に至るまでの正当な理由がなかったと考えられるが、それにもかかわらず当期の会計方針を前期に遡及適用し、遡及適用後の情報を提供することがすべての場合において有用であるといえるかどうか、例えば過去に情報が収集されておらず、遡及適用による再計算ができない場合などの取扱いをどう定めるのかといった点については、今後も検討を続けていく必要があるものと考えられる。
また、国際的な会計基準においては、表示方法の変更が行われた場合には会計方針の変更と同様、財務諸表の比較可能性を確保するための遡及的な組替えが求められている。我が国における現行の取扱い(財務諸表等規則等)においても比較可能性を確保するための注記による開示は行われているが、遡及的な組替えは求められていない。会計方針の変更について遡及適用を求める場合には、表示方法の変更に関しても、現行の注記による対応から、国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表の組替えによる対応へと転換する方向で検討することが考えられる。
Ⅲ.会計上の見積りの変更に係る取扱い(論点5)
会計上の見積りの変更について、過年度財務諸表に遡って修正を行わないという点に関しては、我が国における現行実務と、国際財務報告基準及び米国会計基準の定めの間に相違はないものと思われる。また、会計上の見積りの変更は、新しい情報(事実)によってもたらされるものであることに着目すれば、その変更による影響額は、過年度よりもむしろ当年度以降に帰属すべき損益であると考えられる。したがって、会計上の見積りの変更については、現行の取扱いを踏襲し、過年度財務諸表に遡って修正を行わない方向で検討することが考えられる。
ただし、固定資産の減価償却方法や耐用年数の変更の取扱いに関連し、後述の[各論1]から[各論3]で説明するような論点がある。また、会計上の見積りの変更と誤謬の訂正との境界や、見積りの変更時期のあり方についても、合わせて検討することが必要と考えられる。
Ⅳ.固定資産の減価償却方法の変更及び耐用年数の変更に関する取扱いについての個別論点(論点3及び5に関連する各論)
1 減価償却方法の変更の取扱い[各論1] 我が国においては、減価償却方法は、会計方針のひとつとされており、その変更は会計方針の変更として取り扱うことになっている。すなわち、我が国では減価償却方法について、固定資産の取得原価を各年度に配分する方法として、定率法や定額法などの一定の計画的・規則的な配分法があることを所与とし、そうした既成の会計方針の選択の問題として捉えているものと考えられる。一方、国際的な会計基準では、減価償却方法の変更の実質を、資産に具現化される経済的便益の費消パターンに関する見積りの変更として捉えている。
減価償却方法の変更を、国際財務報告基準のように、資産に具現化される経済的便益の費消パターンに関する見積りの変更として第一義的にとらえるのが妥当であれば、会計処理についてもこれを見積りの変更と同様に処理することが考えられる。
その一方、固定資産の経済的便益の費消パターンはそもそも見積りが不可能であるからこそ、計画的・規則的な償却を行っていると考えるのが歴史的な経緯であるとの指摘もある。このように、減価償却方法と見積りの要素との関係を切り離し、固定資産に係る計画的・規則的な費用配分方法として捉えるのであれば、我が国の現行の取扱いのとおり、会計方針の変更として捉えることになるものと考えられる。なお、このように考える場合には、減価償却方法の変更についても、会計方針の変更と区別することなく、遡及適用の対象とすべきかどうかということも論点となる。
2 見積りの変更(耐用年数の変更)に関する会計処理の考え方[各論2] 会計上の見積りの変更について、過年度財務諸表に遡って修正を行わないという点に関しては、我が国における現行実務と、国際財務報告基準及び米国会計基準の定めの間に相違はないものと思われる。しかしながら、見積りの変更のひとつと考えられる耐用年数の変更に関しては、修正額を変更期間及びそれ以降の期間で認識する「プロスペクティブ方式」もしくは、修正額を変更期間で一時に認識する「キャッチ・アップ方式」の2つの考え方がとり得るものと思われる(次頁参照)。
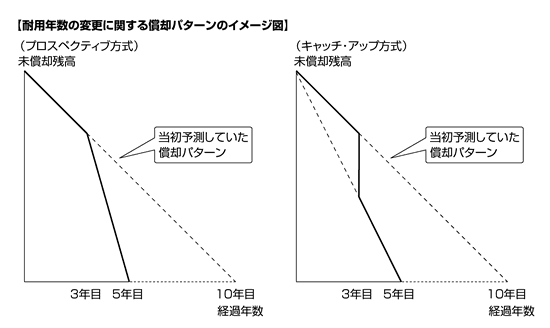
国際財務報告基準や米国会計基準では、固定資産の耐用年数の変更を見積りの変更と捉え、プロスペクティブ方式を採用しているものと通常解釈されている。我が国においても、固定資産の耐用年数の変更をプロスペクティブ方式によって処理する実務が一般的ではあるものの、減価償却計算に適用されている耐用年数(又は残存価額)が、予見することのできなかった原因等により著しく不合理となった場合に、耐用年数の短縮や残存価額の修正に基づいて一時に減価償却累計額の修正を行う場合(臨時償却)もある。
これらの2つの方法について検討するにあたっては、見積りの変更による費用配分パターンの変動に関する実態解釈という切り口のほか、こうした見積りの変更が、固定資産に関するストック評価額の見積額に与える影響という側面に着目する切り口もあるものと考えられる。このような点に着目した場合、当期の見積りの変更をまずもって当期の貸借対照表価額に反映すること、すなわち固定資産のストック評価額に反映させ、その影響額をすべて当期の損益として認識する方法が妥当であるとも考えられる(脚注2)。
3 減損処理と臨時償却の関係[各論3] 固定資産の減損処理を行う際、臨時償却による損失も、減損による損失も、認識された年度の損失とされる点では同じであることから、回収を見込めない帳簿価額を一纏めにして、減損の会計処理を適用することとされている。しかしながら、従前より両者の関係のあり方には議論のあるところであり、過年度遡及修正の導入や見積りの変更に関する取扱いの検討に合わせ、一度整理をしておく必要があるものと考える。
Ⅴ.セグメントの区分方法の変更に係る具体的な取扱い(論点6)
我が国の現行の取扱いでも、前期のセグメント情報を変更後のセグメントの区分方法等により遡及して作り直したものと比較して開示することは認められているが、国際的な会計基準とは異なり、その採否は企業の裁量に委ねられているため、会計方針の変更について過年度遡及修正を求める場合には、セグメントの区分方法の変更についても、国際的な会計基準と同様の遡及適用を求めていくことを検討していくことが考えられる。
ただし、セグメント情報の開示に関しては、別プロジェクトにおいてマネジメント・アプローチの採用に関する検討が進められており、求められる開示の内容が変わることも想定されるため、セグメントの区分方法等の変更に係る取扱いに関しては、セグメント情報の開示全般の議論と並行して、今後の開示のあり方について検討を続けていくことが考えられる。
Ⅵ.誤謬に係る過年度遡及修正(論点7)
我が国においては現在、誤謬に関する会計上の取扱いとしては、前期損益修正項目として当期の損益で修正する方法のみが示されている。一方、国際的な会計基準では、すでに公表済の財務諸表について誤謬が発見された場合、過年度財務諸表を修正再表示することとされている。
この点に関しては、会計上の誤謬の取扱いとして、国際的な会計基準と同様に、重要な誤謬を修正再表示する考え方を導入することは、期間比較が可能な情報を開示するという観点からも有用であり、会計基準のコンバージェンスを図るという観点からも望ましいという考え方がある。また、そもそも誤謬のある過年度財務諸表を修正再表示することは、会計方針の変更に関する遡及適用等とは性格が異なっており、比較可能性の確保や会計基準のコンバージェンスの促進という観点からではなく、当然の要請として会計基準に定めておくべきであるとの指摘がある。さらに、すべての会社に対して誤謬による修正再表示を求めるのであれば、現行の会計上の誤謬の取扱いを変更することが必要であるという指摘もある。
こうした指摘がある一方、我が国においては、財務諸表に重要な影響を及ぼすような誤謬が発見された場合、当該誤謬が訂正報告書の提出事由に該当するときには、修正再表示が行われることになるため、修正再表示の枠組みは開示制度において手当て済みであるという考え方がある。
会計上の誤謬の取扱いに関しては、前述の開示制度との関係を考慮しつつ、国際的な会計基準と同様に過年度財務諸表の修正再表示による対応を求めることとするかどうかも含め、検討を進めていく必要があるものと考えられる。
なお、誤謬のうち、重要なものについての会計処理を定めるとした場合、何をもって「重要な誤謬」とするのかが重要な論点となる(脚注3)。この点については、実務上の混乱を招かないように、会社法及び証券取引法(金融商品取引法)に基づく開示制度との関係などについても、十分な整理が必要であるものと考えられる。
Ⅶ.四半期(中間)財務諸表開示に固有の遡及修正(論点8)
平成19年3月にASBJが公表した企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」では、第2四半期以降に会計方針の変更を行った場合、年度の期首に遡って修正した四半期財務諸表を開示することは求めていないが、年度の財務諸表における会計方針の変更について遡及適用を求める場合には、国際的な会計基準と同様に、四半期(中間)財務諸表開示においても、現行の注記による対応から、それ以前の四半期会計期間への遡及的な適用による対応へと、原則的には転換する方向で検討することが考えられる。
また、四半期(中間)財務諸表の遡及修正に固有の問題としては、会計方針に関する会計年度全体での首尾一貫性の問題がある。国際的な会計基準においては、会計年度の中途で行う会計方針の変更に関する遡及適用を求める際には、同一の会計年度中のそれより前の中間期間すべてに遡及適用することを定めている。ただし、この点については、遡及修正できないことが、会計方針の変更の制約となるのは問題があるのではないかという指摘もあり、さらなる検討を進めていく必要がある。
Ⅷ.廃止事業の報告に係る過年度遡及修正(論点9)
我が国では廃止事業に関する取扱いは定められていないが、国際的な会計基準では、財務諸表の報告企業において処分済み又は処分が予定されている事業(廃止事業)がある場合には、損益計算書上、継続事業に係る損益と区分し、廃止事業に係る損益を独立項目で表示し、過年度の損益計算書において遡及的に修正することが求められており、我が国において廃止事業の報告が行われることとなった場合には、国際的な会計基準と同様に、過年度の損益情報を遡及的に修正するという方向で検討していくことが考えられる。
ただし、廃止事業の報告に関しては、過年度の損益計算書の遡及的な修正が重要な論点の1つではあるものの、国際的な会計基準においては売却目的で保有する非流動資産(及び処分グループ)の減損に関連して設けられた定めであり、廃止事業の定義の設定いかんでは実務が非常に煩雑となるという指摘があることなどから、廃止事業の報告に関しては、別プロジェクトでその取扱いを議論した後、改めて過年度遡及修正に係る論点について検討を行うことも考えられる。
Ⅸ.個別財務諸表における過年度遡及修正の適用上の論点(論点2)
過年度遡及修正を求めることにより、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることができるという点については、連結財務諸表だけでなく、個別財務諸表についても同様であるものと考えられる。我が国においては上場会社が個別財務諸表のみを公表している場合に限らず、連結財務諸表を公表する場合でも個別財務諸表をあわせて公表しているため、これらの会社が公表する個別財務諸表についても連結財務諸表と同様に、過年度遡及修正によって期間比較可能性及び企業間の比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性を高めることが期待されるものと考えられる。
しかしながら、非上場会社の場合、個別財務諸表上も一律に過年度遡及修正を求めるか否かについては、コスト・ベネフィットの観点から、適用上の問題に関する検討が必要ではないかという指摘がある。この点に関しては、非上場会社の個別財務諸表については、遡及修正された過年度の情報に関するニーズは、上場会社の連結財務諸表ほどには高くないとも考えられるため、例えば遡及修正に係る影響額を当期の期首の剰余金に含めるのか、それとも当期の損益計算に含めるのかといった問題と、遡及修正後の過年度財務諸表の開示の問題に分け、その各々について適用上の論点を整理することが考えられる。
なお、この点に関連し、連結財務諸表で過年度遡及修正を行うこととする場合、連結財務諸表は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない(連結財務諸表原則第二2)とされていることから、非上場会社であっても上場会社の子会社にあたる場合には、その個別財務諸表にも当然に過年度遡及修正を求めることになるのではないかとの考え方がある。しかし、親会社の連結決算手続上利用するために内部的に作成された情報により、こうした点が担保されると考えることができるのであれば、当該子会社が法的に求められる個別財務諸表で過年度遡及修正を行うべきかどうかについては、コスト・ベネフィットの観点から、連結財務諸表上での取扱いとは別途のものとする場合も考えられる(脚注4)。その一方、非上場会社の場合でも、会計監査人を設置する会社であるときには、従来の考え方との整合性を踏まえ、上場会社において過年度遡及修正が求められるのであれば、これに準じた取扱いにすることが適切であるとする考え方もあり、これらの観点も含め、引き続き検討を行っていく必要があるものと思われる。
Ⅹ.その他の論点(論点10)
1 報告事業体の変更 米国の会計基準においては、特定の子会社の変動など報告事業体の変更があった場合、新しい報告事業体の財務諸表を示すために、その変更を財務諸表に遡及適用しなければならないとされている。ただし、仮に米国と同様のこの定めを設けたとしても、設立や買収などによる子会社の変動はこれに該当しないものとされていることなどから、この定めが適用される局面は限定されるものと考えられる。
2 既存の会計基準との整合性 我が国の既存の会計基準は、過年度遡及修正が認められないことを前提に構築されているため、本論点整理でとりあげた四半期会計基準やセグメント情報の開示に関する取扱いのほかにも、既存の会計基準全般に及ぼす影響も視野に入れ、検討を進めていく必要がある。
3 過年度遡及修正の考え方を導入する際の適用時期等に関する留意点 過年度遡及修正の適用は我が国にとって新しい考え方の導入であり、関連法制度との関係の整理が不可欠であるため、その適用時期の設定等については、この点を十分に考慮することが必要と考えられる。(げんば・しんご)
脚注
1 ASBJのホームページ、(http://www.asb.or.jp/html/documents/summary_issue/retro/)を参照。
コメントの締切りは平成19年9月26日(水)である。
2 国際財務報告基準においても、固定資産に関連する見積り以外の見積りの変更、例えば不良債権の金額の見積りの変更などは、このように考えることで、その処理方法をプロスペクティブ方式のなかに包含して解釈しているようである。
3 米国においては現在、誤謬の重要性に関して、ロールオーバー法(損益計算書に与える影響度合いにより重要性を判定)及びアイアン・カーテン法(貸借対照表に与える影響度合いにより重要性を判定)の両方を用い、誤謬の程度を測定しその重要性を評価する方法が提案されている。
4 実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」では、在外子会社の財務諸表には、所在地国で法的に求められるものや外部に公表されるものに限らず、連結決算手続上利用するために内部的に作成されたものを含むとしている取扱いがある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















