コラム2008年03月31日 【SCOPE】 自民党が内部統制報告制度で関係者からヒアリング(2008年3月31日号・№252)
日本経団連は負担軽減を求める
自民党が内部統制報告制度で関係者からヒアリング
自民党の金融調査会企業会計に関する小委員会(小委員長:後藤茂之衆議院議員)が3月13日に開催され、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用される内部統制報告制度について、金融庁、日本公認会計士協会、日本経済団体連合会からヒアリングを行った。日本経団連からはIT統制、評価対象の選定、文書化のレベルなどで監査人から保守的な対応を求められるケースがあることが報告され、企業の負担が重くならないよう求めている。なお、3月18日には自民党の国際競争力調査会経済安全保障に関するワーキングチーム(座長:棚橋泰文衆議院議員)でも同様の内容のヒアリングが行われている。
企業側に配慮も一部には監査法人からの過度な要求も 会合では、まず、金融庁から内部統制報告制度の概要についての説明が行われている。金融庁は、米国の企業改革法とは異なり、ダイレクト・レポーティング(直接報告業務)の不採用や内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施など、企業に配慮した仕組みを講じていることを説明した(下表参照)。
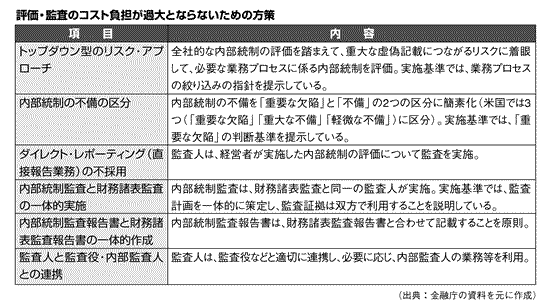
また、実施基準では、評価の絞り込みについて、売上高等の概ね3分の2程度をカバーする事業拠点の3勘定科目(売上、売掛金、棚卸資産)をベースにするなど、90~95%の事業拠点において、90~95%の勘定科目について業務プロセスの評価を行う米国と比べてかなりの緩和が行われているとしている。
そのほか、3月11日には「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表している旨を説明した(本誌251号参照)。
実務上の取扱いは基準の範囲内 また、日本公認会計士協会からは、昨年10月に公表した「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」についての説明が行われた。実務上の取扱いが厳しいとの指摘に対しては、企業会計審議会が定めた「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」や実施基準に基づいて策定したものであるとしている。
監査時間が2~3倍となるケースも! 一方、日本経済団体連合会では、内部統制報告制度導入への準備は順調に進んでいるとの認識を示すも、一部には企業と監査法人との間で解釈の違いや監査法人からの過度な要求もあると指摘している。
また、監査時間が2倍から3倍に増える旨の提示が監査法人から企業にされている事例が報告されていると指摘。四半期レビューも導入されるため、監査時間が増えることは当然だが、企業が納得のいくような説明をしてほしいと要望している。
出席した議員からは、適正な監査報酬や監査時間とはどの程度なのかなどの質問が出されている。日本経済団体連合会からは、現状より1割から2割程度の増加はあると回答。また、日本公認会計士協会は、業種、規模、内部統制の構築度合いによって異なるとしている。
内部統制監査等で監査時間の見積りは約8,000時間超に このように監査時間がどの程度になるか注目されるなか、日本公認会計士協会は3月19日、内部統制監査や四半期財務諸表のレビューが導入されることを踏まえ、監査時間の見積り例を示した「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」(公開草案)を公表している(4月9日まで意見募集)。
モデルとなる被監査会社を想定して監査作業に必要な時間を見積った結果では、8,042時間と平成18年9月に公表した見積り時間と比べ約1.8倍に増加している。
同協会では、あくまでも設定した前提条件のもとで監査時間を見積ったものであり、標準時間を示すものではないとしているが、企業側としては、驚くべき数字となっているといえよう。
なお、モデルは、連結上の売上高および資産総額が2千億円程度、本社以外に支店10箇所、工場6箇所、国内子会社10社、海外子会社4社、持分法適用会社3社、物流センター1箇所を持つ上場企業を想定している。
MEMO
制度導入後のレビューで実施基準の見直しも 金融庁では、内部統制報告制度の内容を明確化するため、内部統制報告制度Q&Aを追加公表するとしている。「内部統制報告制度に関する11の誤解」については、制度に関する共通の質問を集めたものとなっているが、追加Q&Aは技術的な質問を集めたものとなりそうだ。
また、制度導入後については、適時にレビューを行い、その結果を踏まえ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」や実施基準の見直しなどを検討するとしている。この点、3月18日の国際競争力調査会経済安全保障に関するワーキングチームにおいても、経済産業省からフォローアップを要請する意見があった。
自民党が内部統制報告制度で関係者からヒアリング
自民党の金融調査会企業会計に関する小委員会(小委員長:後藤茂之衆議院議員)が3月13日に開催され、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用される内部統制報告制度について、金融庁、日本公認会計士協会、日本経済団体連合会からヒアリングを行った。日本経団連からはIT統制、評価対象の選定、文書化のレベルなどで監査人から保守的な対応を求められるケースがあることが報告され、企業の負担が重くならないよう求めている。なお、3月18日には自民党の国際競争力調査会経済安全保障に関するワーキングチーム(座長:棚橋泰文衆議院議員)でも同様の内容のヒアリングが行われている。
企業側に配慮も一部には監査法人からの過度な要求も 会合では、まず、金融庁から内部統制報告制度の概要についての説明が行われている。金融庁は、米国の企業改革法とは異なり、ダイレクト・レポーティング(直接報告業務)の不採用や内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施など、企業に配慮した仕組みを講じていることを説明した(下表参照)。
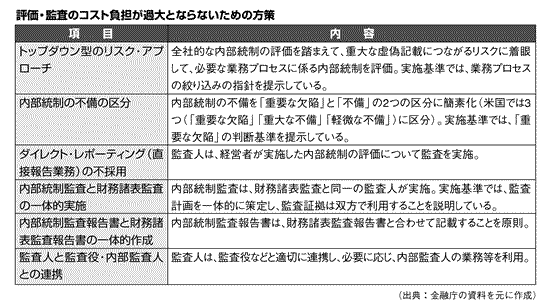
また、実施基準では、評価の絞り込みについて、売上高等の概ね3分の2程度をカバーする事業拠点の3勘定科目(売上、売掛金、棚卸資産)をベースにするなど、90~95%の事業拠点において、90~95%の勘定科目について業務プロセスの評価を行う米国と比べてかなりの緩和が行われているとしている。
そのほか、3月11日には「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表している旨を説明した(本誌251号参照)。
実務上の取扱いは基準の範囲内 また、日本公認会計士協会からは、昨年10月に公表した「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」についての説明が行われた。実務上の取扱いが厳しいとの指摘に対しては、企業会計審議会が定めた「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」や実施基準に基づいて策定したものであるとしている。
監査時間が2~3倍となるケースも! 一方、日本経済団体連合会では、内部統制報告制度導入への準備は順調に進んでいるとの認識を示すも、一部には企業と監査法人との間で解釈の違いや監査法人からの過度な要求もあると指摘している。
また、監査時間が2倍から3倍に増える旨の提示が監査法人から企業にされている事例が報告されていると指摘。四半期レビューも導入されるため、監査時間が増えることは当然だが、企業が納得のいくような説明をしてほしいと要望している。
出席した議員からは、適正な監査報酬や監査時間とはどの程度なのかなどの質問が出されている。日本経済団体連合会からは、現状より1割から2割程度の増加はあると回答。また、日本公認会計士協会は、業種、規模、内部統制の構築度合いによって異なるとしている。
内部統制監査等で監査時間の見積りは約8,000時間超に このように監査時間がどの程度になるか注目されるなか、日本公認会計士協会は3月19日、内部統制監査や四半期財務諸表のレビューが導入されることを踏まえ、監査時間の見積り例を示した「監査時間の見積りに関する研究報告(中間報告)」(公開草案)を公表している(4月9日まで意見募集)。
モデルとなる被監査会社を想定して監査作業に必要な時間を見積った結果では、8,042時間と平成18年9月に公表した見積り時間と比べ約1.8倍に増加している。
同協会では、あくまでも設定した前提条件のもとで監査時間を見積ったものであり、標準時間を示すものではないとしているが、企業側としては、驚くべき数字となっているといえよう。
なお、モデルは、連結上の売上高および資産総額が2千億円程度、本社以外に支店10箇所、工場6箇所、国内子会社10社、海外子会社4社、持分法適用会社3社、物流センター1箇所を持つ上場企業を想定している。
MEMO
制度導入後のレビューで実施基準の見直しも 金融庁では、内部統制報告制度の内容を明確化するため、内部統制報告制度Q&Aを追加公表するとしている。「内部統制報告制度に関する11の誤解」については、制度に関する共通の質問を集めたものとなっているが、追加Q&Aは技術的な質問を集めたものとなりそうだ。
また、制度導入後については、適時にレビューを行い、その結果を踏まえ、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」や実施基準の見直しなどを検討するとしている。この点、3月18日の国際競争力調査会経済安全保障に関するワーキングチームにおいても、経済産業省からフォローアップを要請する意見があった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























