解説記事2008年08月11日 【ニュース特集】 平成21年度税制改正での税体系の抜本的改革は困難?(2008年8月11日号・№270)
大山鳴動鼠一匹! 財政再建重視シフトも打つ手なし!
平成21年度税制改正での税体系の抜本的改革は困難?
福田改造内閣は8月2日、認証式を行い、正式に発足した。税制および道路特定財源の一般財源化を担当する伊吹文明財務大臣、与謝野馨経済財政政策担当大臣、谷垣禎一国土交通大臣、町村信孝官房長官(留任)の顔ぶれからすると、福田改造内閣は、財政再建を重視する姿勢が窺えるが、消費税の税率アップについては、「2009年度は困難」との町村官房長官の認識が示されている。
経済環境・政治環境からすると当然の(やむを得ない?)認識といえそうだが、平成21年度における基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げなど財政需要は厳しさを増している。2011年度単年度における基礎的財政収支(プライマリー・バランス)の黒字化の目標についても、見直しを求める声があがってきた。消費税の税率アップが困難となれば、税体系の抜本改革もまた、困難(先送り)となりそうだ。
平成21年度税制改正は、事業承継税制の抜本拡充など、所定の見直しは行われることになるものの、法人税・所得税・消費税の主要税目では、抜本的改革とはかけ離れたものとなりそうだ。
「財政再建重視」シフトだが、消費税率アップの政治判断は困難 福田改造内閣の税制担当の閣僚(国土交通大臣は、道路特定財源の一般財源化を所管する)について、その主な経歴をみてみると、政府(財務省)または自民党の税制調査会において、要職を経てきたことがわかる。
自民党内においては、いわゆる「上げ潮派」と「財政再建重視派」が対立するとされているが、下記(表1参照)の大臣は、いずれも財政再建重視派と目されている。したがって、消費税の税率引上げの議論には理解を示すものとみられるが、サブプライム問題等を基因とする不透明な経済環境・ネジレ現象で衆議院の解散(総選挙)まで時間的な余裕のない政治環境からすると、このような財政再建重視シフトをしいたとしても、消費税の税率引上げの政治判断は容易ではない。
福田首相も町村官房長官も2009年度税制改正における消費税率引上げの判断は困難との意向を示している。
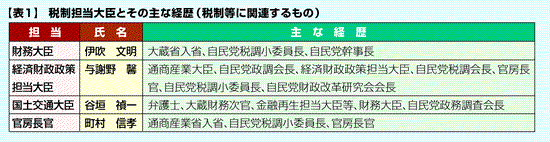
「消費税率の引上げ」と「法人税率の引下げ」は共倒れ 消費税率の引上げが困難となることで、国際的動向に照らして引下げの必要があるとする意見が多かった法人税率の引下げもまた困難な状況だ。財源の手当てのつかない減税措置として見送られる可能性が高い。もっとも、財源的に「消費税率の引上げ」と「法人税率の引下げ」がセットになりうるとしても、衆議院議員の残りの任期が1年程度となり、選挙を意識した状況においては、個人増税と法人減税とを組み合わせることは政治的に困難である。政府税調の「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」(平成19年11月)においても、「法人実効税率の引下げについては、〈中略〉今後、厳しい財政事情の下、課税ベースの拡大を含めて対応する必要がある。」とされてきた。このような認識のもとで、法人税率の引下げの財源を、法人税の課税ベースの拡大により手当てすることが経済産業省の研究会(「経済社会の持続的発展のための企業税制に関する研究会」)で検討されてきた。
しかしながら、法人税の課税ベースの拡大については、意見の集約が困難な状況である。すでに、賞与引当金・退職給与引当金については、法人税法上損金算入が認められていない。これ以上の法人税課税ベースの拡大は、さらなる会計と税務の分離を意味することになる。平成19年度税制改正で採用された250%定率法などの加速償却を廃止したり、支払利子の損金算入を制限することなどが検討されたりもしているが、上記(表2参照)の問題点などが指摘され、容易に意見が集約できない状況となっている。
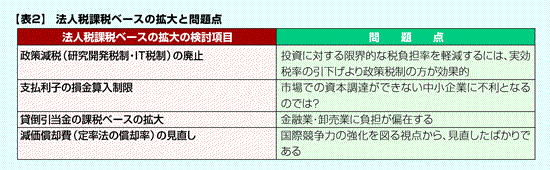
また、租税特別措置などの取りやめにより、法人税率引下げの財源に充てようとする検討も行われているが、国際競争力確保のための法人税率の引下げが、逆に国際的に競争に面している法人の納付法人税額を増やしてしまう結果となるようなジレンマが生じることになる。結果として、平成21年度税制改正における法人税制の見直しは、海外利益に対する国外所得免除制度の導入などの国際課税での見直しが中心とならざるをえない。
中小企業税制の見直しも合意は困難 法人税制の見直しの一環として中小企業税制についても検討されているが、こちらも意見の集約が困難な状況だ。日本版LLCともいわれる合同会社制度が導入されたことで、米国におけるチェック・ザ・ボックス規則のようなパス・スルー課税方式を容認する仕組みを求める要望もある一方で、現行の法人成りにより法人課税となる仕組みはすっきりした仕組みとも評価されている。
同族会社の役員給与課税の見直しを要望する声も上がっているが、すでに、実質的に損金算入制限の効果は、基準所得金額の1,600万円以下への引上げにより、大きな効果は生じないとの見方もある。いずれにしても、赤字法人が2/3を占める状況においては、税制による支援は限定的なものであり、社会保険料負担の軽減など、中小企業経営への支援(配慮)が求められる。
政治決断の見送りで社会福祉財源も地方税制の改革も期待できず 消費税の税率アップの政治判断は困難であるとしても、消費税の社会保障財源化、複数税率の採用、インボイス方式の導入、地方消費税との税率配分など、現行消費税については、税率アップ時に検討を要する項目が数多くある。医療や学校などの消費税法上の非課税売上を収益の柱とする業種においては消費税の税率アップのタイミングで損税防止のための0(ゼロ)税率の採用を働きかけることになる。
一方、政治的には、税率アップの決断なしに、消費税の制度設計の真剣な議論は不可能であろう。消費税の税率引上げは、年を経るごとにその影響範囲を拡大させて、いまや単に財政再建の問題ではなく、「社会保障給付との一体性」「地方税として偏在性の少ない安定的な基幹税目」などの視点から注目されている。消費税の税率引上げが困難とされることで、社会福祉や地方税制のあり方を含めて、平成21年度税制改正における抜本的な改革は掛声倒れに終わりそうな状況だ。
「給付つき税額控除」と「買換え等」期限切れ税制の取扱いが焦点 法人税制の改革が限定的とならざるを得ないのに対し、個人所得課税の見直しについては、今後の議論により、改革のスピードが変わってくる状況だ。すなわち、これまでに、問題点などを掘り起こして検討したような形跡が窺えない。
経済財政諮問会議の「経済財政改革の基本方針2008」では、「税制と社会保障給付を一体的に切れ目なく設計し、必要な人に必要な支援をきめ細かく行うため、控除制度の在り方や既存施策との関連など、その課題の検討に着手する。」としている。消費税の問題も含めて、社会保障と税について一体的に改革する必要を記述しており、個人所得課税においては、いわゆる「給付つき税額控除」(税制を活用した給付措置)の議論が本格化される。「給付つき税額控除」については、執行面への懸念もありうるため、平成21年度税制改正での実現は難しいのでは(消費税の議論と併せて実現を目指すのでは)ないかと考えられる。
また、後期高齢者医療制度の年金からの天引き問題などから、保険料に係る社会保険料控除の取扱いが明確化されている。税制としても同居老親等の扶養控除額(現行は老人扶養親族の扶養控除額+10万円)を拡大して、高齢者を子が同居して扶養することを推進する施策が検討されている。
個人所得税の基本的な仕組みの見直しが流動的であるのに対し、実務家からは、時限立法の延長問題に関心が高まっている。なかでも注目しておきたいのは、住宅ローン減税(措置法41条)と、長期(10年超)保有土地等の国内資産への買換え(措置法37条1項16号)である。長期保有土地等に係る買換え特例については、平成19年度改正で平成20年末までの見直しを検討事項として明記したうえで延長が認められたものだけに、その動向は予断を許さないものとなっている。
相続税の課税方式の見直しの論点を整理中 事業承継税制では、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を平成21年度税制改正において、創設することとされている。また、「この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討し、その際、格差の固定化の防止、老後不要の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」としている。
財務省主税局においては、相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点を税理士会などと意見交換し、整理を始めている。平成21年度税制改正の中心的な項目は、相続税の課税方式の見直しということになろう。
また、事業承継税制についても、その骨子は定まっているものの、生前贈与・相続時精算課税制度との適用関係などについて、使い勝手を求める立場からの要望が明確化され、議論されることが予想されている。
このほか、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等に遡って適用することの、適用関係(不利益不遡及の取扱い)なども制度設計上の注目事項となる。
省エネ促進税制・環境税の取扱いも大きなテーマ 平成21年度税制改正では、上記のほか、固定資産税の評価替えの年度に該当することから、負担水準の調整が検討課題となる。
道路特定財源の一般財源化・環境税の取扱いを含め、低炭素化促進の観点から税制全般の横断的見直しを行うこととされている。省エネルギー促進税制の拡充なども検討されよう。
平成21年度税制改正での税体系の抜本的改革は困難?
福田改造内閣は8月2日、認証式を行い、正式に発足した。税制および道路特定財源の一般財源化を担当する伊吹文明財務大臣、与謝野馨経済財政政策担当大臣、谷垣禎一国土交通大臣、町村信孝官房長官(留任)の顔ぶれからすると、福田改造内閣は、財政再建を重視する姿勢が窺えるが、消費税の税率アップについては、「2009年度は困難」との町村官房長官の認識が示されている。
経済環境・政治環境からすると当然の(やむを得ない?)認識といえそうだが、平成21年度における基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げなど財政需要は厳しさを増している。2011年度単年度における基礎的財政収支(プライマリー・バランス)の黒字化の目標についても、見直しを求める声があがってきた。消費税の税率アップが困難となれば、税体系の抜本改革もまた、困難(先送り)となりそうだ。
平成21年度税制改正は、事業承継税制の抜本拡充など、所定の見直しは行われることになるものの、法人税・所得税・消費税の主要税目では、抜本的改革とはかけ離れたものとなりそうだ。
「財政再建重視」シフトだが、消費税率アップの政治判断は困難 福田改造内閣の税制担当の閣僚(国土交通大臣は、道路特定財源の一般財源化を所管する)について、その主な経歴をみてみると、政府(財務省)または自民党の税制調査会において、要職を経てきたことがわかる。
自民党内においては、いわゆる「上げ潮派」と「財政再建重視派」が対立するとされているが、下記(表1参照)の大臣は、いずれも財政再建重視派と目されている。したがって、消費税の税率引上げの議論には理解を示すものとみられるが、サブプライム問題等を基因とする不透明な経済環境・ネジレ現象で衆議院の解散(総選挙)まで時間的な余裕のない政治環境からすると、このような財政再建重視シフトをしいたとしても、消費税の税率引上げの政治判断は容易ではない。
福田首相も町村官房長官も2009年度税制改正における消費税率引上げの判断は困難との意向を示している。
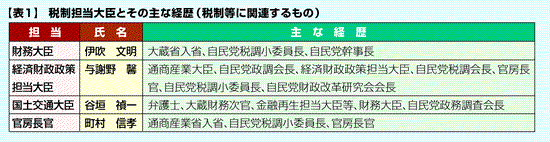
「消費税率の引上げ」と「法人税率の引下げ」は共倒れ 消費税率の引上げが困難となることで、国際的動向に照らして引下げの必要があるとする意見が多かった法人税率の引下げもまた困難な状況だ。財源の手当てのつかない減税措置として見送られる可能性が高い。もっとも、財源的に「消費税率の引上げ」と「法人税率の引下げ」がセットになりうるとしても、衆議院議員の残りの任期が1年程度となり、選挙を意識した状況においては、個人増税と法人減税とを組み合わせることは政治的に困難である。政府税調の「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」(平成19年11月)においても、「法人実効税率の引下げについては、〈中略〉今後、厳しい財政事情の下、課税ベースの拡大を含めて対応する必要がある。」とされてきた。このような認識のもとで、法人税率の引下げの財源を、法人税の課税ベースの拡大により手当てすることが経済産業省の研究会(「経済社会の持続的発展のための企業税制に関する研究会」)で検討されてきた。
しかしながら、法人税の課税ベースの拡大については、意見の集約が困難な状況である。すでに、賞与引当金・退職給与引当金については、法人税法上損金算入が認められていない。これ以上の法人税課税ベースの拡大は、さらなる会計と税務の分離を意味することになる。平成19年度税制改正で採用された250%定率法などの加速償却を廃止したり、支払利子の損金算入を制限することなどが検討されたりもしているが、上記(表2参照)の問題点などが指摘され、容易に意見が集約できない状況となっている。
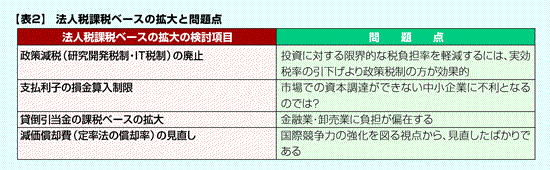
また、租税特別措置などの取りやめにより、法人税率引下げの財源に充てようとする検討も行われているが、国際競争力確保のための法人税率の引下げが、逆に国際的に競争に面している法人の納付法人税額を増やしてしまう結果となるようなジレンマが生じることになる。結果として、平成21年度税制改正における法人税制の見直しは、海外利益に対する国外所得免除制度の導入などの国際課税での見直しが中心とならざるをえない。
中小企業税制の見直しも合意は困難 法人税制の見直しの一環として中小企業税制についても検討されているが、こちらも意見の集約が困難な状況だ。日本版LLCともいわれる合同会社制度が導入されたことで、米国におけるチェック・ザ・ボックス規則のようなパス・スルー課税方式を容認する仕組みを求める要望もある一方で、現行の法人成りにより法人課税となる仕組みはすっきりした仕組みとも評価されている。
同族会社の役員給与課税の見直しを要望する声も上がっているが、すでに、実質的に損金算入制限の効果は、基準所得金額の1,600万円以下への引上げにより、大きな効果は生じないとの見方もある。いずれにしても、赤字法人が2/3を占める状況においては、税制による支援は限定的なものであり、社会保険料負担の軽減など、中小企業経営への支援(配慮)が求められる。
政治決断の見送りで社会福祉財源も地方税制の改革も期待できず 消費税の税率アップの政治判断は困難であるとしても、消費税の社会保障財源化、複数税率の採用、インボイス方式の導入、地方消費税との税率配分など、現行消費税については、税率アップ時に検討を要する項目が数多くある。医療や学校などの消費税法上の非課税売上を収益の柱とする業種においては消費税の税率アップのタイミングで損税防止のための0(ゼロ)税率の採用を働きかけることになる。
一方、政治的には、税率アップの決断なしに、消費税の制度設計の真剣な議論は不可能であろう。消費税の税率引上げは、年を経るごとにその影響範囲を拡大させて、いまや単に財政再建の問題ではなく、「社会保障給付との一体性」「地方税として偏在性の少ない安定的な基幹税目」などの視点から注目されている。消費税の税率引上げが困難とされることで、社会福祉や地方税制のあり方を含めて、平成21年度税制改正における抜本的な改革は掛声倒れに終わりそうな状況だ。
「給付つき税額控除」と「買換え等」期限切れ税制の取扱いが焦点 法人税制の改革が限定的とならざるを得ないのに対し、個人所得課税の見直しについては、今後の議論により、改革のスピードが変わってくる状況だ。すなわち、これまでに、問題点などを掘り起こして検討したような形跡が窺えない。
経済財政諮問会議の「経済財政改革の基本方針2008」では、「税制と社会保障給付を一体的に切れ目なく設計し、必要な人に必要な支援をきめ細かく行うため、控除制度の在り方や既存施策との関連など、その課題の検討に着手する。」としている。消費税の問題も含めて、社会保障と税について一体的に改革する必要を記述しており、個人所得課税においては、いわゆる「給付つき税額控除」(税制を活用した給付措置)の議論が本格化される。「給付つき税額控除」については、執行面への懸念もありうるため、平成21年度税制改正での実現は難しいのでは(消費税の議論と併せて実現を目指すのでは)ないかと考えられる。
また、後期高齢者医療制度の年金からの天引き問題などから、保険料に係る社会保険料控除の取扱いが明確化されている。税制としても同居老親等の扶養控除額(現行は老人扶養親族の扶養控除額+10万円)を拡大して、高齢者を子が同居して扶養することを推進する施策が検討されている。
個人所得税の基本的な仕組みの見直しが流動的であるのに対し、実務家からは、時限立法の延長問題に関心が高まっている。なかでも注目しておきたいのは、住宅ローン減税(措置法41条)と、長期(10年超)保有土地等の国内資産への買換え(措置法37条1項16号)である。長期保有土地等に係る買換え特例については、平成19年度改正で平成20年末までの見直しを検討事項として明記したうえで延長が認められたものだけに、その動向は予断を許さないものとなっている。
相続税の課税方式の見直しの論点を整理中 事業承継税制では、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を平成21年度税制改正において、創設することとされている。また、「この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討し、その際、格差の固定化の防止、老後不要の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」としている。
財務省主税局においては、相続税の課税方式の見直しに伴う主な法制的・実務的論点を税理士会などと意見交換し、整理を始めている。平成21年度税制改正の中心的な項目は、相続税の課税方式の見直しということになろう。
また、事業承継税制についても、その骨子は定まっているものの、生前贈与・相続時精算課税制度との適用関係などについて、使い勝手を求める立場からの要望が明確化され、議論されることが予想されている。
このほか、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等に遡って適用することの、適用関係(不利益不遡及の取扱い)なども制度設計上の注目事項となる。
省エネ促進税制・環境税の取扱いも大きなテーマ 平成21年度税制改正では、上記のほか、固定資産税の評価替えの年度に該当することから、負担水準の調整が検討課題となる。
道路特定財源の一般財源化・環境税の取扱いを含め、低炭素化促進の観点から税制全般の横断的見直しを行うこととされている。省エネルギー促進税制の拡充なども検討されよう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























