解説記事2010年05月03日 【ニュース特集】 国際会計基準でも退職給付信託は年金資産(2010年5月3日号・№353)
退職給付信託でIASBスタッフが回答
国際会計基準でも退職給付信託は年金資産
わが国の退職給付会計基準で年金資産として認められている退職給付信託だが、国際会計基準(IAS)においても年金資産と認められることが本誌の取材で明らかとなった。企業会計基準委員会(ASBJ)が窓口となって、国際会計基準審議会(IASB)に対して退職給付信託がIAS第19号「従業員給付(改訂)」において年金資産に該当するか否かを照会。IASBのスタッフは、日本公認会計士協会の実務指針の4つの要件を満たす退職給付信託については、年金資産として認めて差し支えないといった旨の回答を行ったものである。IASBの公式の見解ではないものの、これまで、日本独自の制度である退職給付信託がIASでも年金資産に該当するかどうかは不明確であっただけに、企業にとっては朗報といえそうだ。
退職給付信託がIASでも年金資産に該当するかどうかは不明確 現行、わが国において、退職給付信託については、①当該信託が退職給付に充てられるものであることが退職金規程等により確認できること、②当該信託は信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること、③当該信託は事業主から法的に分離されており、信託財産の事業主への返還および受益者に対する詐害行為が禁止されていること、④信託財産の管理・運用・処分については、受託者が信託契約に基づいて行うことの4つのすべての要件を満たした場合には、年金資産に該当することとされている(上掲参照)。
しかし、退職給付信託については、わが国独自の制度であるため、国際会計基準においても、年金資産として認められるかどうかが不明確であった。
ASBJを窓口に実務上の問題について照会 わが国でも平成22年3月期から、国際会計基準の任意適用がスタートした。国際会計基準はプリンシプル・ベース(原則主義)のため、わが国や米国の会計基準とは異なり、細かなルールがあるわけではない。
このため、わが国では、企業会計基準委員会を窓口に、実務上の問題をIASBに照会することにより、当該問題への対応を行っている。
具体的には、IFRS導入準備タスクフォース(日本経団連企業会計部会のメンバーをはじめとする主要企業21社や監査法人で構成)で実務上の問題を抽出。抽出した問題については、企業会計基準委員会内に設置された国際会計基準実務対応グループで議論し、国際会計基準の具体的な適用に関して確認が必要な論点については、同委員会を窓口としてIASBのスタッフに相談・照会を行っている。
今回の退職給付信託の取扱いについても、企業会計基準委員会を窓口としてIASBのスタッフに照会したものである。
実質的にはIASBの公式見解!?
照会内容は、わが国の退職給付信託(日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」第7項に規定する退職給付信託)がIAS第19号においても年金資産に該当するかどうかというもので、平成21年11月に照会。これに対して、IASBのスタッフは、照会のあった日本公認会計士協会の実務指針に該当する退職給付信託であれば、IAS第19号の年金資産に該当する旨の回答を今年に入ってから行っている。
IASBは、現在、新たなIFRIC解釈指針をできるだけ取りまとめない方針を示している。会計基準で不明な点があれば、会計基準自体を直そうとしている状況だ。
このため、今回のIASBのスタッフが行った回答は、IASBとしての公式の見解ではないものの、わが国でしか退職給付信託という制度がないという状況を考えれば、実質的な公式見解であるといえそうだ。
信託した株式を入れ替えるケースも
なお、企業会計基準委員会が3月18日に公表した退職給付に関する会計基準の適用指針(案)では、前述の4つの要件を満たし、そのうえで、退職給付信託の設定時における考え方など(適用指針(案)第83項~第93項)に沿うことが必要であることを明確化した(上掲参照)。退職給付信託契約が適用指針(案)に従っていないと認められる場合、拠出した資産は会計上の年金資産に該当しないと明記している。
現行の実務では、特別の事由がないにもかかわらず、退職給付信託の資産の入替えが行われているケースもなかにはあるようだ。今後はこのようなケースなどでの退職給付信託は、年金資産として認められないことになろう。
COLUMN
退職給付信託は年金資産の積立不足解消を目的に導入 平成13年3月期より導入された退職給付に関する会計基準では、年金資産の積立額が従業員に対する将来の年金支払いに満たない場合については、その差額分を貸借対照表上、負債に計上することになった。
当時は、企業の年金資産の積立不足が問題となっており、これを解消するため、当時の経済団体連合会と日本公認会計士協会が協議。退職給付目的で保有株式を信託銀行に拠出した場合、当該信託が退職給付に充てられるものであることが退職金規程等により確認できることなどの4つの要件をすべて満たせば、企業会計上、年金資産と認めることとし、日本公認会計士協会では、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」において、退職給付信託の取扱いを明記することになった。退職給付信託のメリットとしては、年金資産の積立不足を解消する手段の1つとなるほか、議決権については、年金を受け取る従業員の利益に反しない範囲で企業が信託銀行に指図できる。
このため、現在では、上場企業の1,000社以上が退職給付信託を活用しているといわれている。
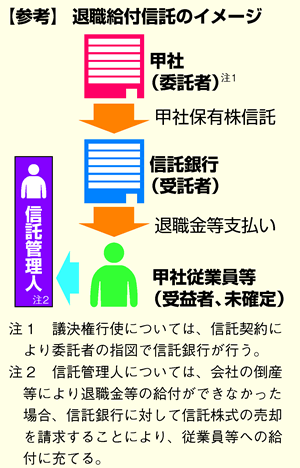
国際会計基準でも退職給付信託は年金資産
わが国の退職給付会計基準で年金資産として認められている退職給付信託だが、国際会計基準(IAS)においても年金資産と認められることが本誌の取材で明らかとなった。企業会計基準委員会(ASBJ)が窓口となって、国際会計基準審議会(IASB)に対して退職給付信託がIAS第19号「従業員給付(改訂)」において年金資産に該当するか否かを照会。IASBのスタッフは、日本公認会計士協会の実務指針の4つの要件を満たす退職給付信託については、年金資産として認めて差し支えないといった旨の回答を行ったものである。IASBの公式の見解ではないものの、これまで、日本独自の制度である退職給付信託がIASでも年金資産に該当するかどうかは不明確であっただけに、企業にとっては朗報といえそうだ。
退職給付信託がIASでも年金資産に該当するかどうかは不明確 現行、わが国において、退職給付信託については、①当該信託が退職給付に充てられるものであることが退職金規程等により確認できること、②当該信託は信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること、③当該信託は事業主から法的に分離されており、信託財産の事業主への返還および受益者に対する詐害行為が禁止されていること、④信託財産の管理・運用・処分については、受託者が信託契約に基づいて行うことの4つのすべての要件を満たした場合には、年金資産に該当することとされている(上掲参照)。
| 日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(抜粋) (信託を用いる場合の年金資産) 7.退職給付(退職一時金及び退職年金)目的の信託(以下「退職給付信託」という。)を用いる場合、退職給付に充てるために積み立てる資産は、下記のすべての要件を満たしているときは、前項の年金資産に該当するものとする。 なお、退職給付信託を設定した場合、退職給付信託から厚生年金基金制度及び適格退職年金制度へ直接拠出ができると解されており、それを前提として、本報告は作成してある。 ① 当該信託が退職給付に充てられるものであることが退職金規程等により確認できること 年金資産は退職給付制度を前提として退職給付債務に対応するものである。したがって、信託から支払われる退職給付も退職給付制度の枠組みの中にあることが退職金規程等により確認できれば、当該信託財産と退職給付債務との対応関係が認められることになる。 ② 当該信託は信託財産を退職給付に充てることに限定した他益信託であること 信託財産を複数の退職給付に充てることとする場合には、信託受益権の内容等により支払の対象となる退職給付や処理方法の明確化が必要である。 ③ 当該信託は事業主から法的に分離されており、信託財産の事業主への返還及び受益者に対する詐害行為が禁止されていること 事業主の倒産時において、事業主の債権者に対抗できること及び信託財産の信託の目的に従った処分が実行できる仕組みとなっていることが必要である。 ④ 信託財産の管理・運用・処分については、受託者が信託契約に基づいて行うこと ア.事業主との分離の実効性を確保するため、例えば、信託管理人を置く方法があるが、その場合は、当該信託管理人が事業主から独立するための措置が必要である。 イ.信託財産の管理・運用・処分について事業主と分離することが必要であり、したがって、信託の設定に伴い、信託財産の所有権は受託者に移転すること(信託財産が株式の場合、その名義も受託者に移転すること)及び受託者は事業主からの信託財産の処分等の指示について拒否できないような内容を含まないこと、などの契約であることが必要である。 ウ.信託は退職給付に充てる目的で設定されるものであり、信託した資産を事業主の意思により、基本的に、事業主の資産と交換することはできないことが必要である。 なお、退職給付信託は、退職一時金及び退職年金制度における退職給付債務の積立不足額を積み立てるために設定するものであり、資産の信託への拠出時に、退職給付信託財産及び年金資産の合計額が対応する退職給付債務を超える場合には、当該退職給付信託財産は本報告における年金資産として認められないことに留意すべきである。 |
ASBJを窓口に実務上の問題について照会 わが国でも平成22年3月期から、国際会計基準の任意適用がスタートした。国際会計基準はプリンシプル・ベース(原則主義)のため、わが国や米国の会計基準とは異なり、細かなルールがあるわけではない。
このため、わが国では、企業会計基準委員会を窓口に、実務上の問題をIASBに照会することにより、当該問題への対応を行っている。
具体的には、IFRS導入準備タスクフォース(日本経団連企業会計部会のメンバーをはじめとする主要企業21社や監査法人で構成)で実務上の問題を抽出。抽出した問題については、企業会計基準委員会内に設置された国際会計基準実務対応グループで議論し、国際会計基準の具体的な適用に関して確認が必要な論点については、同委員会を窓口としてIASBのスタッフに相談・照会を行っている。
今回の退職給付信託の取扱いについても、企業会計基準委員会を窓口としてIASBのスタッフに照会したものである。
| 退職給付信託の主な考え方 ●1つの退職給付信託を複数の退職給付制度に対して設定する場合には、各退職給付制度との対応関係を明確にして、退職給付制度ごとに対応する退職給付信託の年金資産額を区分計算することが必要となる。 ●収益(配当)を事業主に帰属させる自益信託は認められない。 ●退職給付信託方式での株式について議決権行使の指示権が事業主に残されたとしても、信託として拠出した株式を退職給付会計上、年金資産としても差し支えない。 ●「いかなる指示も拒否できない」と明示された信託財産は、退職給付会計上の年金資産として認められない。 ●退職給付信託は、事業主との間で現金による入替えまたは時価が同等の他の資産との入替えは通常生じない。 ●土地などの有形固定資産については、退職給付信託に拠出できる資産として適当ではない。 ●連結対象である子会社の株式を信託した場合には、連結決算上、信託への拠出に伴い発生した退職給付信託設定損益はなかったものとする。 |
IASBは、現在、新たなIFRIC解釈指針をできるだけ取りまとめない方針を示している。会計基準で不明な点があれば、会計基準自体を直そうとしている状況だ。
このため、今回のIASBのスタッフが行った回答は、IASBとしての公式の見解ではないものの、わが国でしか退職給付信託という制度がないという状況を考えれば、実質的な公式見解であるといえそうだ。
信託した株式を入れ替えるケースも
なお、企業会計基準委員会が3月18日に公表した退職給付に関する会計基準の適用指針(案)では、前述の4つの要件を満たし、そのうえで、退職給付信託の設定時における考え方など(適用指針(案)第83項~第93項)に沿うことが必要であることを明確化した(上掲参照)。退職給付信託契約が適用指針(案)に従っていないと認められる場合、拠出した資産は会計上の年金資産に該当しないと明記している。
現行の実務では、特別の事由がないにもかかわらず、退職給付信託の資産の入替えが行われているケースもなかにはあるようだ。今後はこのようなケースなどでの退職給付信託は、年金資産として認められないことになろう。
COLUMN
退職給付信託は年金資産の積立不足解消を目的に導入 平成13年3月期より導入された退職給付に関する会計基準では、年金資産の積立額が従業員に対する将来の年金支払いに満たない場合については、その差額分を貸借対照表上、負債に計上することになった。
当時は、企業の年金資産の積立不足が問題となっており、これを解消するため、当時の経済団体連合会と日本公認会計士協会が協議。退職給付目的で保有株式を信託銀行に拠出した場合、当該信託が退職給付に充てられるものであることが退職金規程等により確認できることなどの4つの要件をすべて満たせば、企業会計上、年金資産と認めることとし、日本公認会計士協会では、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」において、退職給付信託の取扱いを明記することになった。退職給付信託のメリットとしては、年金資産の積立不足を解消する手段の1つとなるほか、議決権については、年金を受け取る従業員の利益に反しない範囲で企業が信託銀行に指図できる。
このため、現在では、上場企業の1,000社以上が退職給付信託を活用しているといわれている。
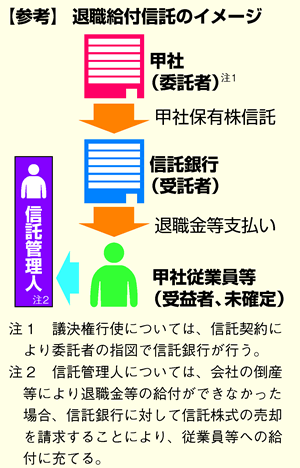
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























