解説記事2011年03月14日 【実務解説】 税制から見た新公益法人制度の留意点(5)(2011年3月14日号・№394)
実務解説
税制から見た新公益法人制度の留意点(5)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅳ.法人区分の移行に伴う課税問題(承前)
7.移行時点以降の各事業年度の課税
(1)公益目的支出超過額の損金不算入 営利型法人である移行法人(普通法人)は全所得課税である。したがって、会費収入や資産の譲渡収入、寄附金も含めて全て課税対象となる。ところで、Ⅳ3、4(第4回、本誌393号参照)で述べた移行に伴う累積所得金額の課税を受けたので、移行後は普通法人と同じ課税方式で済むかというと、そうではないので留意が必要である。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く)の公益目的支出の額(実施事業に係る事業費の額、特定寄付の額及び実施事業に係る経常外費用の額の合計額)が実施事業収入の額(実施事業に係る収益の額と実施事業資産から生じた収益の額の合計額)を超えるときは、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされ(法令131の5⑤)(図表1参照)、実施事業収入の額が公益目的支出を超えるときは、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)。
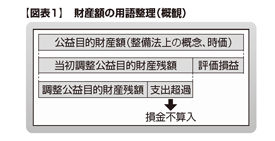
「調整公益目的財産残額」とは、Ⅳ5(第4回、本誌393号参照)で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、零)とされている(法令131の5⑦)(図表2参照)。
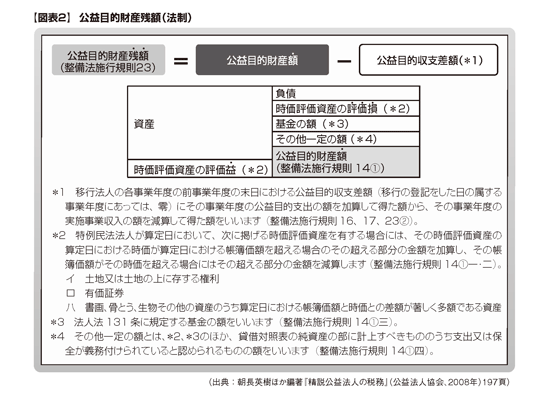
なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのか。これはⅣ3、4で示したとおり、普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」が零になればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、それまでの期間はこの法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があり、公益目的支出計画実施中の各事業年度では継続して申告書作成に留意が必要である。
(2)累積所得金額の益金算入事例 移行法人が普通法人に該当することとなった場合の累積所得金額の益金算入計算は、具体的には、別表十四(六)の「Ⅱ 移行法人が普通法人に該当することとなった場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金または損金算入等に関する明細書」にて当初調整公益目的財産残額の計算を行い、調整後の累積所得金額又は累積欠損金額の益金算入額又は損金算入額を記載することとなる。
簡単な計算を試みると事例1のとおりである。
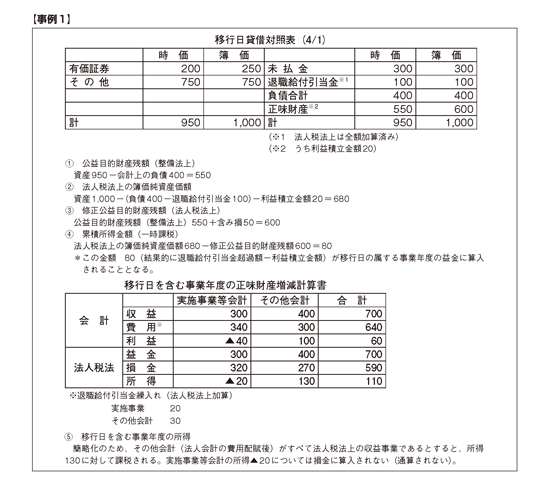
法人税別表十四(七)の記載事例及び「記載の仕方」は書式1のとおり。
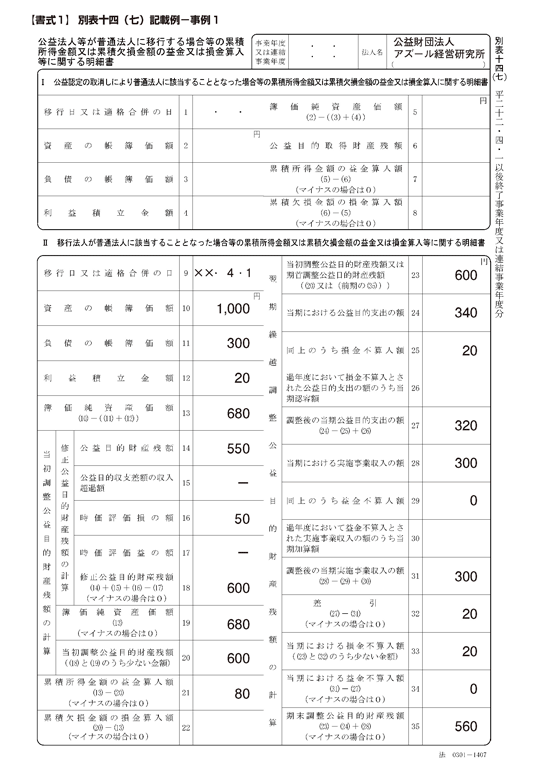
(3)公益目的支出計画期間の法人税法上の留意点 公益目的財産残額にはいくつかの申告調整要因がある。まず、整備法上の「公益目的財産残額」は時価概念であり、法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して「修正公益目的財産残額」を算定している。そして、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させている。また、整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制を継続している。
以上から、含み損があれば法人税法上の調整公益目的財産残額が残り、含み益があれば公益目的支出計画完了前に調整公益目的財産残額が零になってしまう。
次の事例2は、含み損が大きいので、公益目的支出計画が1年目で完了する場合である。
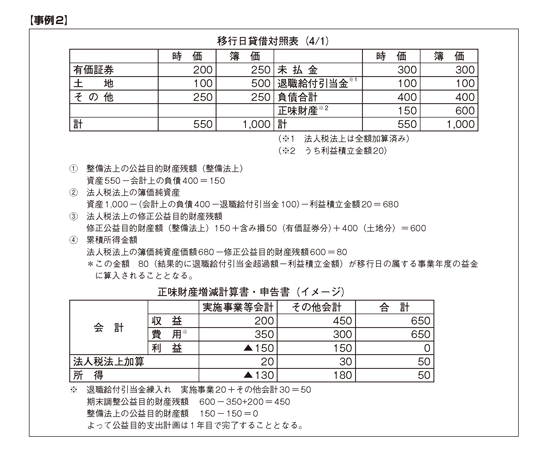
この場合の法人税別表十四(七)の記載事例及び「記載の仕方」は書式2のとおり。
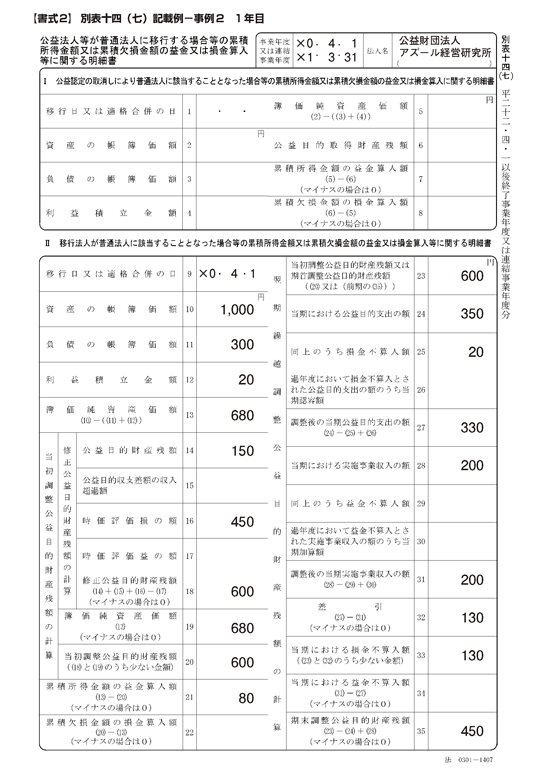
公益目的支出計画の実施期間(事例2では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額が零になる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額が零ではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。
この場合、期末調整公益目的財産残額の記載(事例2では450)はいつまで、何のために続けるのだろうか。公益目的支出超過額(事例2では130)を損金の額に算入しない規制は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度以後は発生しない(法令131の5⑤)。このため、2年目からは支出超過額は損金算入できる上に、確認後は行政庁の監督もなくなり、整備法上の義務を離れた単純な法人法上の一般社団・財団法人として存続するので、2年目以降の記載は不要と考える。
逆に含み益がある場合には、期末調整公益目的財産残額は零になっていたとしても、公益目的支出超過額を損金の額に算入しない規制(法令131の5⑤)は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度まで継続すると考えられる。
Ⅴ.公益目的支出計画と法人税課税
1.トレードオフ関係の危険性 一般社団・財団法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならない(整備法119①)(図表3参照)。
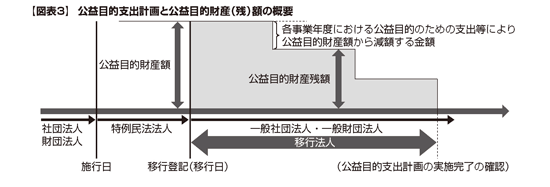
公益目的支出計画を早期に完了させるため、移行法人は勢い実施事業等会計の赤字を拡大するために、法人会計に属する管理費をできるだけ実施事業等に配賦計算したり、金融資産運用益を法人会計に属させようとする。しかし、このことは結果として法人税課税を一時的に大きくする危険性がある。公益目的支出計画と法人税課税は一時的にトレードオフの関係にあることに留意が必要である。
2.収益・費用の配分の留意点 非営利型の移行法人が、合理的な論理構成をして特定資産運用収益を実施事業等会計以外へ、管理費を実施事業等会計へ移したとすると次のように計算できる(事例3参照)。
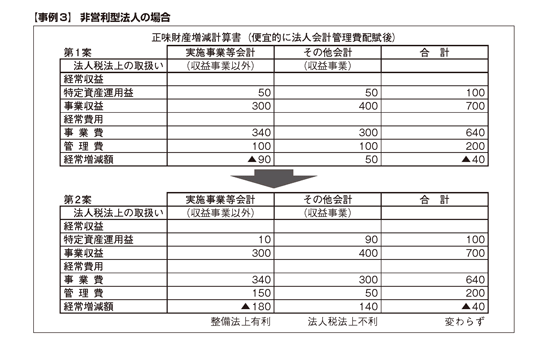
簡略化のために、その他会計を法人税法上、収益事業とすると、実施事業等会計の赤字が増えて公益目的支出計画の実施期間が短縮される(整備法上有利)が、法人税課税が増える(法人税法上不利)結果となる。もっとも法人税法上の収益事業か否かと、整備法上の実施事業会計、その他会計の区分は整合的である必要はないのですべてトレードオフの関係となるわけではない。
公益目的支出計画の実施期間に制限はないので、充分にシミュレーションをすべきである。
営利型法人の場合には全所得課税でありながら、実施事業等会計の公益目的支出計画支出超過額は損金不算入(法令131の5⑤)であるので、やはり一時的に法人税法上不利となる。
なお、有価証券等の運用益が法人税法上の収益事業等に含まれるかについて、収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる(脚注1)。
3.事業区分の留意点 公益目的支出計画の実施事業については、整備法の規定に反しない限り、法人が任意に選択できる。
営利型法人である移行法人の場合、Ⅲ2、3(第3回、本誌391号参照)記載のとおり、全部課税であるにもかかわらず、実施事業等の「支出超過額」を損金の額に算入できないために、赤字を大きくしても収益事業の所得の圧縮には直接はつながらない。
この場面においても、公益目的支出計画と法人税課税は一時的にはトレードオフの関係にあることに留意が必要である(事例4参照)。ただし、公益目的支出計画における公益目的財産額が損金不算入の総額であるので、長期的に見れば課税所得総額は第1案も第2案も同額である。
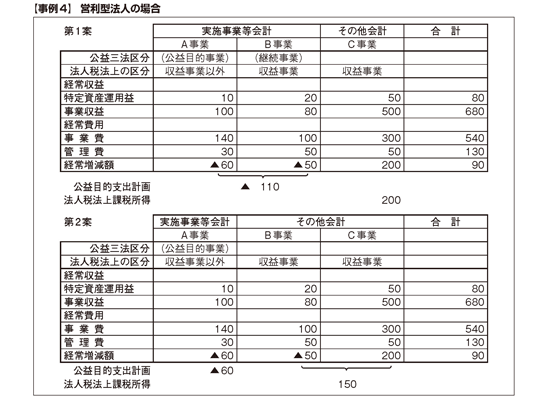
なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、事例4が非営利型法人の場合には、B事業とC事業(収益事業)が課税対象となるため、第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。
脚注
1 【法人税基本通達15-1-7(収益事業の所得の運用)(抜粋)】
公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。
【法人税基本通達15-1-6(付随行為)】
収益事業の範囲に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。
(1)~(4)略
(5)公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為
(6)公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為
税制から見た新公益法人制度の留意点(5)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅳ.法人区分の移行に伴う課税問題(承前)
7.移行時点以降の各事業年度の課税
(1)公益目的支出超過額の損金不算入 営利型法人である移行法人(普通法人)は全所得課税である。したがって、会費収入や資産の譲渡収入、寄附金も含めて全て課税対象となる。ところで、Ⅳ3、4(第4回、本誌393号参照)で述べた移行に伴う累積所得金額の課税を受けたので、移行後は普通法人と同じ課税方式で済むかというと、そうではないので留意が必要である。
移行法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならないこととされている(整備法119①)。
法人税法では、移行日の属する事業年度以後の各事業年度(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度を除く)の公益目的支出の額(実施事業に係る事業費の額、特定寄付の額及び実施事業に係る経常外費用の額の合計額)が実施事業収入の額(実施事業に係る収益の額と実施事業資産から生じた収益の額の合計額)を超えるときは、その超える部分の金額(「支出超過額」)を損金の額に算入しないこととされ(法令131の5⑤)(図表1参照)、実施事業収入の額が公益目的支出を超えるときは、その超える部分の金額(「収入超過額」)を益金の額に算入しないこととされている(法令131の5⑥)。
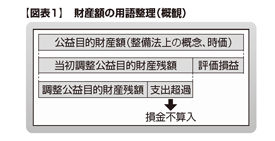
「調整公益目的財産残額」とは、Ⅳ5(第4回、本誌393号参照)で計算した当初調整公益目的財産残額から、過年度の支出超過額の合計額を減算し、過年度の収入超過額の合計額を加算した金額(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認に係る事業年度後の事業年度にあっては、零)とされている(法令131の5⑦)(図表2参照)。
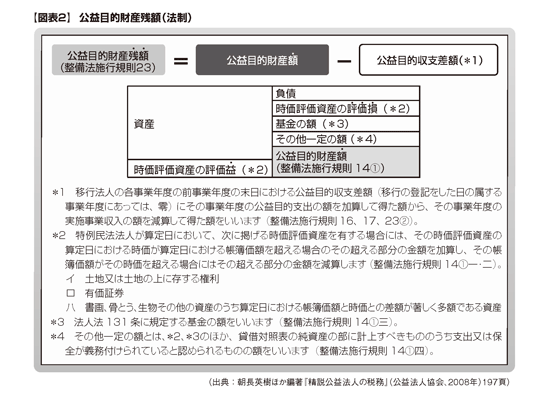
なぜ「支出超過額」を損金に算入できないのか。これはⅣ3、4で示したとおり、普通法人(全所得課税法人)に移行したときの累積所得金額の計算時に、「修正公益目的財産残額」を一括して控除(損金算入と同じ効果)しているためである。
「調整公益目的財産残額」が零になればその後の各事業年度においてこのような調整計算からは解放されるが、それまでの期間はこの法人税法上の「調整公益目的財産残額」を計算する必要があり、公益目的支出計画実施中の各事業年度では継続して申告書作成に留意が必要である。
(2)累積所得金額の益金算入事例 移行法人が普通法人に該当することとなった場合の累積所得金額の益金算入計算は、具体的には、別表十四(六)の「Ⅱ 移行法人が普通法人に該当することとなった場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金または損金算入等に関する明細書」にて当初調整公益目的財産残額の計算を行い、調整後の累積所得金額又は累積欠損金額の益金算入額又は損金算入額を記載することとなる。
簡単な計算を試みると事例1のとおりである。
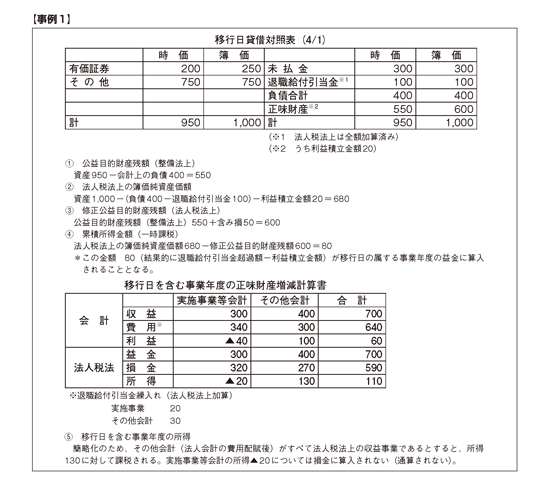
法人税別表十四(七)の記載事例及び「記載の仕方」は書式1のとおり。
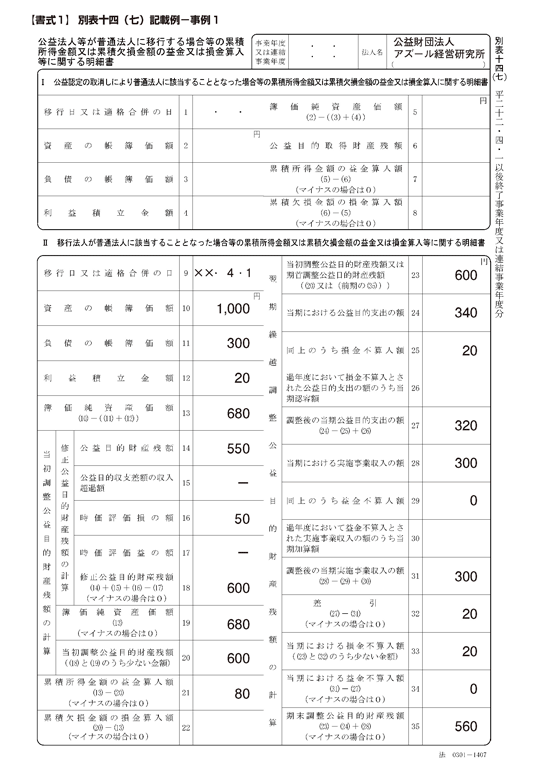
(3)公益目的支出計画期間の法人税法上の留意点 公益目的財産残額にはいくつかの申告調整要因がある。まず、整備法上の「公益目的財産残額」は時価概念であり、法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して「修正公益目的財産残額」を算定している。そして、その後は、法人税法上も整備法上の公益目的支出超過額を共通の減少額として期末調整公益目的財産残額を減少させている。また、整備法上の「公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度」を共通の指標とし、法人税法上の損金不算入規制を継続している。
以上から、含み損があれば法人税法上の調整公益目的財産残額が残り、含み益があれば公益目的支出計画完了前に調整公益目的財産残額が零になってしまう。
次の事例2は、含み損が大きいので、公益目的支出計画が1年目で完了する場合である。
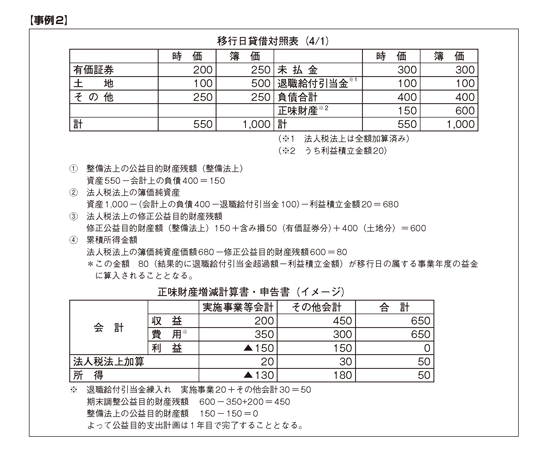
この場合の法人税別表十四(七)の記載事例及び「記載の仕方」は書式2のとおり。
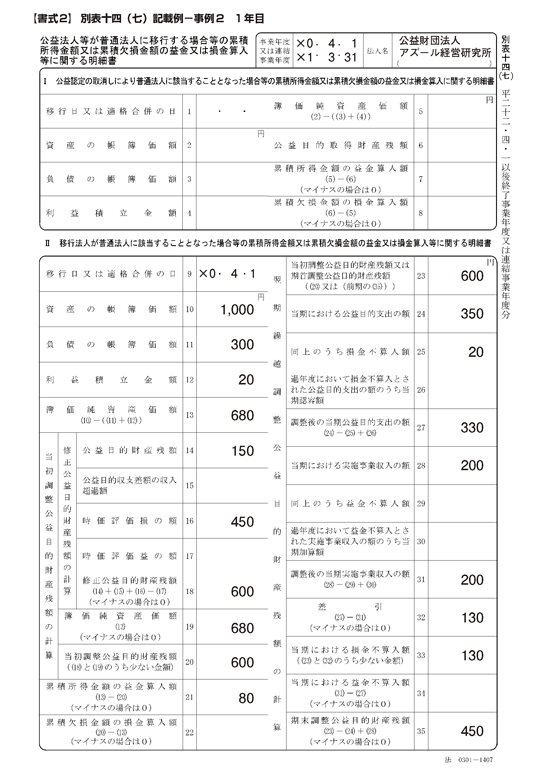
公益目的支出計画の実施期間(事例2では1年間)と法人税法上の調整公益目的財産残額が零になる期間(1年超)が異なる。スタートになる金額が相違することから、法人税法上の調整公益目的財産残額が零ではないのに、公益目的支出計画の実施が完了してしまい、齟齬が生じている。
この場合、期末調整公益目的財産残額の記載(事例2では450)はいつまで、何のために続けるのだろうか。公益目的支出超過額(事例2では130)を損金の額に算入しない規制は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度以後は発生しない(法令131の5⑤)。このため、2年目からは支出超過額は損金算入できる上に、確認後は行政庁の監督もなくなり、整備法上の義務を離れた単純な法人法上の一般社団・財団法人として存続するので、2年目以降の記載は不要と考える。
逆に含み益がある場合には、期末調整公益目的財産残額は零になっていたとしても、公益目的支出超過額を損金の額に算入しない規制(法令131の5⑤)は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認事業年度まで継続すると考えられる。
Ⅴ.公益目的支出計画と法人税課税
1.トレードオフ関係の危険性 一般社団・財団法人は、「公益目的財産額」がある場合には、公益目的財産額に相当する額を公益目的のために支出して零とするための「公益目的支出計画」を作成しなければならない(整備法119①)(図表3参照)。
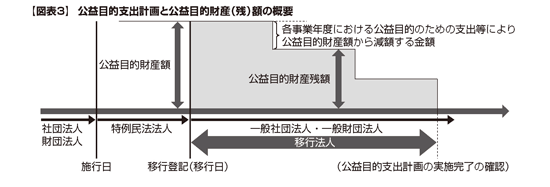
公益目的支出計画を早期に完了させるため、移行法人は勢い実施事業等会計の赤字を拡大するために、法人会計に属する管理費をできるだけ実施事業等に配賦計算したり、金融資産運用益を法人会計に属させようとする。しかし、このことは結果として法人税課税を一時的に大きくする危険性がある。公益目的支出計画と法人税課税は一時的にトレードオフの関係にあることに留意が必要である。
2.収益・費用の配分の留意点 非営利型の移行法人が、合理的な論理構成をして特定資産運用収益を実施事業等会計以外へ、管理費を実施事業等会計へ移したとすると次のように計算できる(事例3参照)。
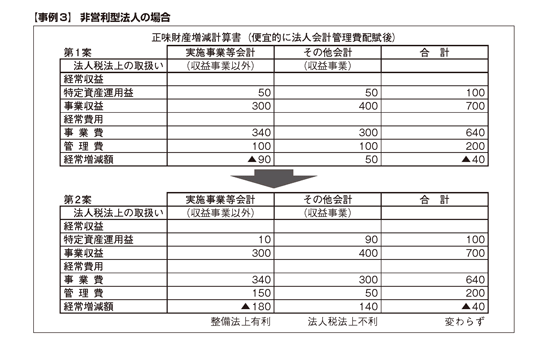
簡略化のために、その他会計を法人税法上、収益事業とすると、実施事業等会計の赤字が増えて公益目的支出計画の実施期間が短縮される(整備法上有利)が、法人税課税が増える(法人税法上不利)結果となる。もっとも法人税法上の収益事業か否かと、整備法上の実施事業会計、その他会計の区分は整合的である必要はないのですべてトレードオフの関係となるわけではない。
公益目的支出計画の実施期間に制限はないので、充分にシミュレーションをすべきである。
営利型法人の場合には全所得課税でありながら、実施事業等会計の公益目的支出計画支出超過額は損金不算入(法令131の5⑤)であるので、やはり一時的に法人税法上不利となる。
なお、有価証券等の運用益が法人税法上の収益事業等に含まれるかについて、収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる(脚注1)。
3.事業区分の留意点 公益目的支出計画の実施事業については、整備法の規定に反しない限り、法人が任意に選択できる。
営利型法人である移行法人の場合、Ⅲ2、3(第3回、本誌391号参照)記載のとおり、全部課税であるにもかかわらず、実施事業等の「支出超過額」を損金の額に算入できないために、赤字を大きくしても収益事業の所得の圧縮には直接はつながらない。
この場面においても、公益目的支出計画と法人税課税は一時的にはトレードオフの関係にあることに留意が必要である(事例4参照)。ただし、公益目的支出計画における公益目的財産額が損金不算入の総額であるので、長期的に見れば課税所得総額は第1案も第2案も同額である。
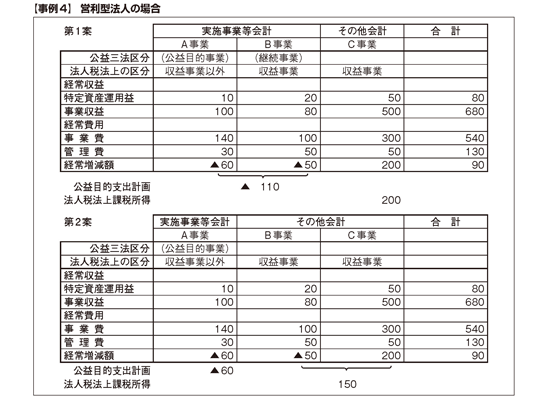
なお、非営利型法人の場合には、収益事業課税であるので、事例4が非営利型法人の場合には、B事業とC事業(収益事業)が課税対象となるため、第1案でも第2案でも同じ課税所得金額となる。
脚注
1 【法人税基本通達15-1-7(収益事業の所得の運用)(抜粋)】
公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。
【法人税基本通達15-1-6(付随行為)】
収益事業の範囲に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。
(1)~(4)略
(5)公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為
(6)公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























