解説記事2011年04月25日 【法令解説】 四半期会計基準等の公表に伴う四半期連結財務諸表規則等の改正の要点(2011年4月25日号・№400)
法令解説
四半期会計基準等の公表に伴う四半期連結財務諸表規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 徳重昌宏
金融庁総 務企画局企業開示課 開示企画第一係長 神保勇一郎
Ⅰ はじめに
平成23年3月31日に「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第10号。以下「改正府令」という)が公布され、また、関係ガイドラインについて、改正ガイドラインが公表されている。
本改正は、昨年6月に閣議決定された「新成長戦略」のなかで、四半期報告の大幅簡素化について2010年度中に行うものとされたことを受け、金融庁および企業会計基準委員会において、四半期報告における財務情報および非財務情報の簡素化についての検討が開始されたものである。
その結果、四半期報告に係る財務情報に関して、平成23年3月25日付で企業会計基準委員会から「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という)等が公表され、これを踏まえ、四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則について改正が行われた。また、財務情報・非財務情報の記載内容の簡素化に伴い、四半期報告書の様式を改正するため、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)について改正が行われた。併せて、関係ガイドラインについても改正が行われた。
また、平成21年12月4日付で企業会計基準委員会から「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「過年度遡及会計基準」という)が公表され、これを受けて平成22年6月30日付で「四半期会計基準」等が公表されている。改正府令では、平成22年6月30日付で改正された「四半期会計基準」等を踏まえて、四半期連結財務諸表規則および中間連結財務諸表規則においても、財務諸表等規則と同様に比較情報の考え方を導入するとともに会計方針の変更に関する注記等の規定の整備が行われ、また、併せて関係ガイドラインについても改正が行われた。
本稿では、四半期報告の簡素化に係る改正を中心に解説を行うこととするが、意見にわたる部分はすべて私見であることをお断りしておく。
Ⅱ 四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則の改正
四半期連結財務諸表規則における改正は、主に①四半期連結キャッシュ・フロー計算書の簡素化、②四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書の簡素化、③注記の簡素化の3つに分けることができる。
なお、四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則において、同様の改正を行っていることから、四半期連結財務諸表規則の規定を引用することとし、四半期連結財務諸表規則の規定が四半期財務諸表等規則の規定を準用している場合には、四半期財務諸表等規則の規定を引用することとする。
1.四半期連結キャッシュ・フロー計算書の簡素化(図表1参照)

(1)四半期連結キャッシュ・フロー計算書(四半期連結財務諸表規則5条の2、四半期財務諸表等規則4条の2)
5条の2は、四半期会計基準第5-2項および第36-2項を踏まえて、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の取扱いについて規定している。
すなわち、同条1項において、四半期連結財務諸表提出会社に作成が義務付けられるのは、第2四半期に係るもののみであることを明確にしている。さらに、同条2項および3項において、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、作成を要しないが、任意で第1四半期に係るものを作成する場合には、第3四半期に係るものも作成しなければならないことを規定している。
これは、同一年度内における四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成については、企業のディスクロージャーに関する方針に基づいて予め決められると考えられることなどを踏まえ、基本的に首尾一貫していることが求められたものと考えられる。
また、一般に作成の負担が重いといわれているキャッシュ・フロー計算書について、第3四半期において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難な場合があることを認め、第1四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成した場合でも、第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しないことを規定している。ただし、作成しない場合にはその旨およびその理由を注記することが必要とされている(同条4項)。
なお、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書について、作成自体が任意となったことから、年度間における継続性までは求められていないが、みだりに変更することは継続性の観点から望ましくないものと考えられる(3月31日付公表「『四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」という)2・3参照)。
(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記(四半期連結財務諸表規則27条の2、改正府令附則2条5項、四半期財務諸表等規則22条の3、改正府令附則3条5項)
27条の2は、四半期会計基準第19項(20-2)を踏まえて、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合に求められる注記について規定している。
すなわち、四半期報告の大幅簡素化の要請から前述のとおり、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成は任意とされたが、作成しない場合には、四半期連結財務諸表の利用者がキャッシュ・フローの状況についての概算額を知ることができるよう、四半期連結財務諸表から直接知ることが困難と考えられる減価償却費やのれんの償却額の注記を求めることとされた。
また、四半期会計基準第19項(20-2)において、のれんの償却額には、負ののれんの償却額も含まれているが、償却の会計処理については、過年度(平成22年4月1日前)の企業結合等により生じた負ののれんにしか認められていないことから、負ののれんの償却額の注記については、改正府令の附則に規定されている。
2.四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結損益計算書の簡素化(四半期連結財務諸表規則64条、四半期財務諸表等規則56条)(図表1参照)
64条2項~4項は、四半期会計基準第7項(2)、第7-2項および第7-3項を踏まえて、四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書の取扱いについて規定している。
すなわち、同条2項において、四半期連結財務諸表提出会社に作成が義務付けられるのは、四半期連結累計期間に係るもののみであることを明確にしている。
四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書については、作成を要しないが、任意で作成する場合には、第2四半期および第3四半期に係るものをともに作成する必要があり(同条3項・4項)、年度内における首尾一貫性を求めていること、また、年度間の継続性は義務付けられていないが、みだりに変更することは継続性の観点から望ましくないことは、前述の四半期連結キャッシュ・フロー計算書と同様である。
なお、四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結包括利益計算書(四半期連結財務諸表規則83条の2)についても同様の改正が行われている。
3.比較情報(レビュー) 前述したとおり、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書ならびに四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書について、年度間の継続性は求められていないため、前連結会計年度に属する四半期に作成していない場合であっても、当連結会計年度に属する第1四半期から作成することは可能である。
この場合、当四半期においては、比較情報の記載は要しないものと考えられる。ただし、前連結会計年度の対応する四半期連結財務諸表を作成し、公認会計士または監査法人によるレビューを受けたうえで比較情報を記載することは可能である(パブコメ回答5・10、四半期会計基準第7-4項、第37-3項)。
4.注記の簡素化 注記についても簡素化が行われており、①規定自体が削除されたもの、②注記内容が簡素化されたもの(図表2参照)および③科目表示に関する注記が削除されたものに分けることができる。本稿では、②に関して主な事項を説明することとしたい。
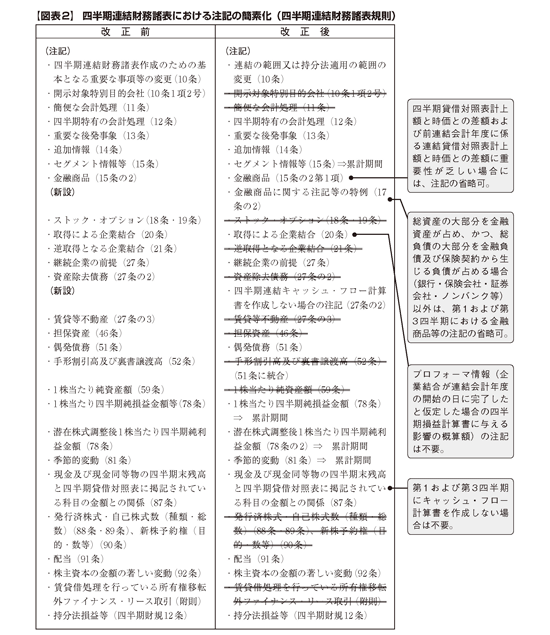
(1)金融商品に関する注記の簡素化(四半期連結財務諸表規則15条の2第1項ただし書、四半期財務諸表等規則8条の2第1項ただし書)
従前においては、金融商品が企業集団の事業運営において重要であり、かつ、四半期連結貸借対照表計上額が前期の連結貸借対照表計上額と比較して著しく変動している場合には、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額について注記することが求められていたため、金融商品の金額が前期末に比較して、四半期末に著しく変動した場合、時価と簿価が同額かほとんど差がない場合であっても、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額が注記されていた。
これらについては、四半期連結貸借対照表計上額を参照すれば足り、改めて注記を行う必要性に乏しいと考えられることから、見直しが行われている。
すなわち、15条の2第1項ただし書は、四半期会計基準適用指針第112項を踏まえて、金融商品の四半期連結貸借対照表計上額が前連結会計年度末に比して著しく変動した場合であっても、四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額の注記を省略できるものと規定されている。
また、当該金融資産の前連結会計年度末における簿価と時価との差額に重要性がある場合には、時価の変動は有用な情報と考えられることから、改めて四半期においても注記を求めることとし、「連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合」という要件も合わせて規定されたものと考えられる。
(2)金融商品に関する注記等の特例(四半期連結財務諸表規則17条の2、四半期財務諸表等規則10条の2)
従前においては、金融商品について、すべての連結財務諸表提出会社に、四半期連結貸借対照表の科目ごとの注記(15条の2)に加え、有価証券については保有目的ごとの注記(16条)およびデリバティブ取引に関する注記(17条)が求められていたが、一般事業会社については、利用者のニーズが高くないものと考えられ、見直しが行われている。
すなわち、17条の2は、四半期会計基準適用指針第80項(3)ただし書の規定を踏まえ、「企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除」き、連結財務諸表提出会社は、第1四半期および第3四半期において、金融商品(15条の2)、有価証券(16条)およびデリバティブ取引(17条)に関する注記を省略できるものと規定されている。
「企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める」企業は、銀行、保険会社、証券会社、ノンバンク等の金融機関等が想定されている(四半期会計基準適用指針第113項)。
金融商品に関する注記等が重要と考えられる金融機関等については、これまでどおりこれらの注記を求める一方、上記の要件を満たさないと考えられる一般事業会社について、注記の簡素化が行われている。
5.適用時期 簡素化に係る上記改正は、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間および四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表、同日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間および四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用される(改正府令附則2条1項、3条1項)。
Ⅲ 開示府令の改正
1.四半期報告書の簡素化に係る改正の概要 前述したような四半期報告書における財務情報の簡素化とともに、四半期報告書に記載すべき非財務情報の記載内容の簡素化に伴い、四半期報告書等の様式の改正が行われた。改正のポイントは次の3つである。
(イ)「経理の状況」に記載する四半期連結財務諸表は、原則、四半期連結累計期間に係るもののみを記載すればよいこととされたことに伴い、「経理の状況」以外の非財務情報の記載内容についても、基本的に、四半期連結累計期間についての情報を記載する。
(ロ)「生産、受注及び販売の状況」等の記載内容については、生産、受注および販売の実績等が四半期連結累計期間において著しく変動した場合に「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(いわゆる「MD&A」)に集約して記載することとし、記載項目としては削除する。
(ハ)「株価の推移」は他の情報源から取得が可能であるため削除され、「保証会社情報」における「継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」については、四半期報告書提出会社が提出した有価証券報告書を参照することを可能とする。
(1)四半期報告書 四半期報告書の様式(開示府令第4号の3様式)の具体的な改正内容は、次のとおりである(図表3参照)。
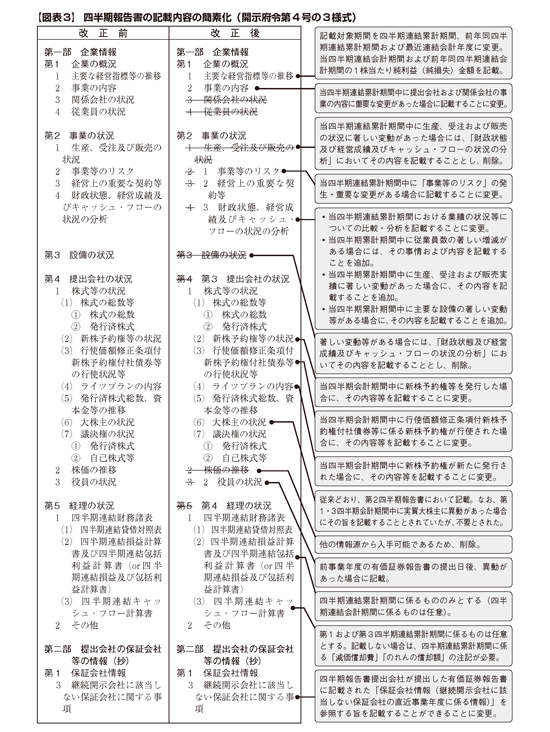
① 「企業の概況」の記載 (i)「主要な経営指標等の推移」(いわゆる「ハイライト情報」)については、基本的に、当四半期連結累計期間(前年同四半期連結累計期間を含む)および最近連結会計年度に係るものを記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)a)。
たとえば、第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書では、図表4のように記載することが考えられ、前年同四半期連結累計期間(第Y-1期第2四半期連結累計期間)、当四半期連結累計期間(第Y期第2四半期連結累計期間)および直近の連結会計年度(第Y-1期)の順に記載することとなる。なお、「1株当たり純資産額」および「従業員数」の記載は不要とされている。
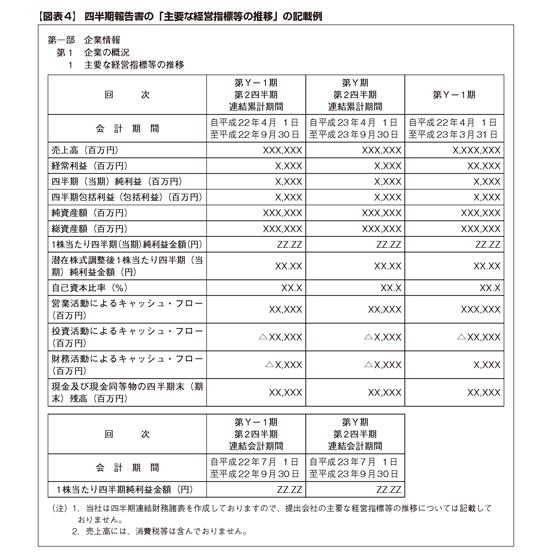
また、「売上高」「四半期純利益金額」「1株当たり四半期純利益金額」については、「経理の状況」において、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書または四半期連結損益および包括利益計算書(以下「四半期連結損益計算書等」という)を記載する場合に、四半期連結会計期間に係る数値をかっこ書で四半期連結累計期間に係る数値に併せて記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)a本文ただし書)。
他方、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」は、投資者の投資判断に重要な情報であると考えられることから、「経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等が記載されず、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」が、上記のようにかっこ書で記載されない場合には、図表4における下の表のように記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)b)。
(ⅱ)「事業の内容」については、四半期連結累計期間において提出会社および関係会社の事業の内容に重要な変更があった場合にその内容を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(6))。
(ⅲ)「関係会社の状況」の記載項目が削除されたほか、「従業員の状況」については、当四半期連結累計期間において連結会社または提出会社の従業員数に著しい増加または減少があった場合に「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の欄に記載することとし、記載項目としては削除された。
② 「事業の状況」の記載
(i)「生産、受注及び販売の状況」については、当四半期連結累計期間において生産、受注および販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において記載することとされ、記載項目としては削除された。なお、その内容の記載にあたっては、改正前と同様、業種・業態によっては定性的に記載することも可能である。
(ⅱ)「事業等のリスク」については、当四半期連結累計期間において、事業等のリスクが発生した場合または有価証券報告書に記載した事業等のリスクに重要な変更があった場合に記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(7))。
(ⅲ)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」については、セグメント情報ごとの業績の状況およびキャッシュ・フローの状況の前年同期との比較・分析、対処すべき課題の重要な変更等の対象期間が四半期連結累計期間に改正されるとともに(第4号の3様式・記載上の注意(9)a(a)・(b))、前述のとおり、「従業員数」「生産、受注及び販売の実績」および「主要な設備」について当四半期連結累計期間において著しい変動があった場合に、その内容を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(9)a(d)~(f))。
③ 「設備の状況」の記載 「設備の状況」については、「主要な設備」について当四半期連結累計期間において著しい変動等があった場合に、その内容を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において記載することとされ、記載項目としては削除された。
④ 「提出会社の状況」の記載 (i)「新株予約権等の状況」については、記載内容を簡素化する観点から、当四半期会計期間において新株予約権等を発行した場合に、当該新株予約権等の発行に係る決議年月日、発行時の新株予約権の数、目的となる株式の種類および株式数、行使時の払込金額、行使期間、株式の発行価格および資本組入額、行使の条件等に関する事項を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(11))。
(ⅱ)「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」については、当四半期会計期間において行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が行使された場合にその状況を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(12))。
(ⅲ)「ライツプランの内容」については、当四半期会計期間において新株予約権を発行した場合に記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(13))。
(ⅳ)「大株主の状況」については、当四半期会計期間が第2四半期会計期間である場合にのみ、当四半期会計期間末現在の大株主の状況を記載すればよいこととされた(第4号の3様式・記載上の注意(15))。
(ⅴ)「株価の推移」については、その株価について四半期報告書に記載を求めなくても、投資者は株価を他の情報源から入手することが容易であるため、記載項目から削除された。
(ⅵ)「役員の状況」については、前事業年度に係る有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員に異動があった場合について記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(17))。
⑤ 「経理の状況」の記載 四半期報告書に記載すべき四半期連結財務諸表等については、前述のとおり、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等の記載は任意とされたほか、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載についても任意とされた(第4号の3様式・記載上の注意(21)・(23)等)。
なお、提出会社の判断により、任意で四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等または第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載する場合には、「経理の状況」の冒頭にその旨を記載しなければならないことが開示ガイドラインにおいて明確化された(企業内容等開示ガイドライン24の4の7-9、24の4の7-10)。
⑥ 「提出会社の保証会社等の情報」等の記載 「提出会社の保証会社等の情報」の「保証会社情報」のうち、「継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」については、四半期報告書提出会社が既に提出した有価証券報告書に記載されているため、記載内容の簡素化の一環として、当該有価証券報告書に記載された保証会社に関する情報を参照する旨、記載することができることとされた(第4号の3様式・記載上の注意(33)d)。
(2)有価証券届出書等 有価証券届出書の提出会社が四半期報告書を提出している場合には、当該有価証券届出書の提出時期によって、当該有価証券届出書に係る最近連結会計年度の次の連結会計年度における四半期連結累計期間に関する業績等の概要、四半期連結財務諸表等を当該有価証券届出書に記載することとされているが、今般の四半期報告書の記載内容の簡素化に伴い、これらの記載内容について改正が行われた。
(i)有価証券届出書(開示府令第2号様式)の記載内容のうち、「業績等の概要」については、業績およびキャッシュ・フローの状況を記載することとなるが、当該有価証券届出書の「経理の状況」において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げていない場合には、キャッシュ・フローの状況についての記載は不要とされた。
(ⅱ)「生産、受注及び販売の状況」および「主要な設備の状況」については、「経理の状況」において、四半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間において、「生産、受注及び販売の状況」および「主要な設備の状況」に著しい変動があった場合に、その内容を記載することとされた(第2号様式・記載上の注意(31)・(38))。
(ⅲ)有価証券届出書の提出者が四半期報告書を提出した場合には、「経理の状況」・「連結財務諸表」の「その他」において、「最近連結会計年度における四半期情報」として各四半期連結会計期間に係る「売上高」「税金等調整前四半期純利益金額」「四半期純利益金額」および「1株当たり四半期純利益金額」を記載することとされていた。
改正後は、四半期報告書に記載されるこれらの金額は四半期連結累計期間に係るものに改正されることから、有価証券届出書に記載すべきこれらの金額について、各四半期連結累計期間および最近連結会計年度に係る金額を記載することとされた。
なお、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」については、投資情報として重要な情報であると考えられることから、最近連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額(各四半期連結累計期間に係る項目の金額に準じて算出したもの)」についても記載することとされた(第2号様式・記載上の注意(66)c・d、第2号の4様式・記載上の注意(10-3)c・d等)。
(3)適用時期 上記(1)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する事業年度における四半期会計期間に係る四半期報告書から適用される。
(2)の改正については、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成23年4月1日以後に開始する事業年度のものである場合における有価証券届出書から適用される。
2.比較情報等に係る改正 四半期連結財務諸表規則および中間連結財務諸表規則等の改正により、新たに四半期連結財務諸表および中間連結財務諸表等に「比較情報」が含まれることとなったことに伴い、四半期報告書および半期報告書等の様式が改正された。
(1)四半期報告書 前述のように、四半期連結財務諸表には、「比較情報」(当四半期連結会計期間または当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に記載された事項に対応する前連結会計年度および前連結会計年度における当四半期連結会計期間または当四半期連結累計期間に対応する四半期連結会計期間または四半期連結累計期間に係る事項(四半期連結財務諸表規則5条の3))が含まれることになる。
したがって、四半期報告書の「経理の状況」において、従来のように、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表および前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表を記載した場合には、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表の比較情報と前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表が併記され、前連結会計年度に係る情報が重複することになる。同様に、四半期連結損益計算書等および四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、前年同四半期連結会計期間または前年同四半期連結累計期間に係る情報が重複することとなる。
このため、四半期報告書の「経理の状況」に記載する四半期連結財務諸表に係る「記載上の注意」では、「当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表」「四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書等」「四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書」等を記載する旨を規定することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(19)~(23))。
四半期報告書の「経理の状況」に記載する四半期財務諸表についても、同様である(第4号の3様式・記載上の注意(25)~(28))。
(2)半期報告書 中間連結財務諸表に含まれることとなる「比較情報」は、当中間連結会計期間に係る当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応する前連結会計年度および前中間連結会計期間に係る事項である(中間連結財務諸表規則4条の2)。
したがって、半期報告書の「経理の状況」において、従来のように、当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表および前中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を記載した場合には、当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の比較情報と前中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表が併記され、前中間連結会計期間に係る情報が重複することになる。
このため、半期報告書の「経理の状況」に記載する中間連結財務諸表に係る「記載上の注意」では、「当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表」を記載する旨を規定することとされた(第5号様式・記載上の注意(25)~(29))。
半期報告書の「経理の状況」に記載する中間財務諸表についても、同様である(第5号様式・記載上の注意(31)~(35))。
(3)適用時期 上記(1)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する事業年度における四半期会計期間に係る四半期報告書から適用される。
(2)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る半期報告書から適用される。
四半期会計基準等の公表に伴う四半期連結財務諸表規則等の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 徳重昌宏
金融庁総 務企画局企業開示課 開示企画第一係長 神保勇一郎
Ⅰ はじめに
平成23年3月31日に「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第10号。以下「改正府令」という)が公布され、また、関係ガイドラインについて、改正ガイドラインが公表されている。
本改正は、昨年6月に閣議決定された「新成長戦略」のなかで、四半期報告の大幅簡素化について2010年度中に行うものとされたことを受け、金融庁および企業会計基準委員会において、四半期報告における財務情報および非財務情報の簡素化についての検討が開始されたものである。
その結果、四半期報告に係る財務情報に関して、平成23年3月25日付で企業会計基準委員会から「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「四半期会計基準」という)等が公表され、これを踏まえ、四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則について改正が行われた。また、財務情報・非財務情報の記載内容の簡素化に伴い、四半期報告書の様式を改正するため、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)について改正が行われた。併せて、関係ガイドラインについても改正が行われた。
また、平成21年12月4日付で企業会計基準委員会から「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「過年度遡及会計基準」という)が公表され、これを受けて平成22年6月30日付で「四半期会計基準」等が公表されている。改正府令では、平成22年6月30日付で改正された「四半期会計基準」等を踏まえて、四半期連結財務諸表規則および中間連結財務諸表規則においても、財務諸表等規則と同様に比較情報の考え方を導入するとともに会計方針の変更に関する注記等の規定の整備が行われ、また、併せて関係ガイドラインについても改正が行われた。
本稿では、四半期報告の簡素化に係る改正を中心に解説を行うこととするが、意見にわたる部分はすべて私見であることをお断りしておく。
Ⅱ 四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則の改正
四半期連結財務諸表規則における改正は、主に①四半期連結キャッシュ・フロー計算書の簡素化、②四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書の簡素化、③注記の簡素化の3つに分けることができる。
なお、四半期連結財務諸表規則および四半期財務諸表等規則において、同様の改正を行っていることから、四半期連結財務諸表規則の規定を引用することとし、四半期連結財務諸表規則の規定が四半期財務諸表等規則の規定を準用している場合には、四半期財務諸表等規則の規定を引用することとする。
1.四半期連結キャッシュ・フロー計算書の簡素化(図表1参照)

(1)四半期連結キャッシュ・フロー計算書(四半期連結財務諸表規則5条の2、四半期財務諸表等規則4条の2)
5条の2は、四半期会計基準第5-2項および第36-2項を踏まえて、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の取扱いについて規定している。
すなわち、同条1項において、四半期連結財務諸表提出会社に作成が義務付けられるのは、第2四半期に係るもののみであることを明確にしている。さらに、同条2項および3項において、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、作成を要しないが、任意で第1四半期に係るものを作成する場合には、第3四半期に係るものも作成しなければならないことを規定している。
これは、同一年度内における四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成については、企業のディスクロージャーに関する方針に基づいて予め決められると考えられることなどを踏まえ、基本的に首尾一貫していることが求められたものと考えられる。
また、一般に作成の負担が重いといわれているキャッシュ・フロー計算書について、第3四半期において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難な場合があることを認め、第1四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成した場合でも、第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しないことを規定している。ただし、作成しない場合にはその旨およびその理由を注記することが必要とされている(同条4項)。
なお、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書について、作成自体が任意となったことから、年度間における継続性までは求められていないが、みだりに変更することは継続性の観点から望ましくないものと考えられる(3月31日付公表「『四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」という)2・3参照)。
(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記(四半期連結財務諸表規則27条の2、改正府令附則2条5項、四半期財務諸表等規則22条の3、改正府令附則3条5項)
27条の2は、四半期会計基準第19項(20-2)を踏まえて、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合に求められる注記について規定している。
すなわち、四半期報告の大幅簡素化の要請から前述のとおり、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成は任意とされたが、作成しない場合には、四半期連結財務諸表の利用者がキャッシュ・フローの状況についての概算額を知ることができるよう、四半期連結財務諸表から直接知ることが困難と考えられる減価償却費やのれんの償却額の注記を求めることとされた。
また、四半期会計基準第19項(20-2)において、のれんの償却額には、負ののれんの償却額も含まれているが、償却の会計処理については、過年度(平成22年4月1日前)の企業結合等により生じた負ののれんにしか認められていないことから、負ののれんの償却額の注記については、改正府令の附則に規定されている。
2.四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結損益計算書の簡素化(四半期連結財務諸表規則64条、四半期財務諸表等規則56条)(図表1参照)
64条2項~4項は、四半期会計基準第7項(2)、第7-2項および第7-3項を踏まえて、四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書の取扱いについて規定している。
すなわち、同条2項において、四半期連結財務諸表提出会社に作成が義務付けられるのは、四半期連結累計期間に係るもののみであることを明確にしている。
四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書については、作成を要しないが、任意で作成する場合には、第2四半期および第3四半期に係るものをともに作成する必要があり(同条3項・4項)、年度内における首尾一貫性を求めていること、また、年度間の継続性は義務付けられていないが、みだりに変更することは継続性の観点から望ましくないことは、前述の四半期連結キャッシュ・フロー計算書と同様である。
なお、四半期連結会計期間(3か月)に係る四半期連結包括利益計算書(四半期連結財務諸表規則83条の2)についても同様の改正が行われている。
3.比較情報(レビュー) 前述したとおり、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書ならびに四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書について、年度間の継続性は求められていないため、前連結会計年度に属する四半期に作成していない場合であっても、当連結会計年度に属する第1四半期から作成することは可能である。
この場合、当四半期においては、比較情報の記載は要しないものと考えられる。ただし、前連結会計年度の対応する四半期連結財務諸表を作成し、公認会計士または監査法人によるレビューを受けたうえで比較情報を記載することは可能である(パブコメ回答5・10、四半期会計基準第7-4項、第37-3項)。
4.注記の簡素化 注記についても簡素化が行われており、①規定自体が削除されたもの、②注記内容が簡素化されたもの(図表2参照)および③科目表示に関する注記が削除されたものに分けることができる。本稿では、②に関して主な事項を説明することとしたい。
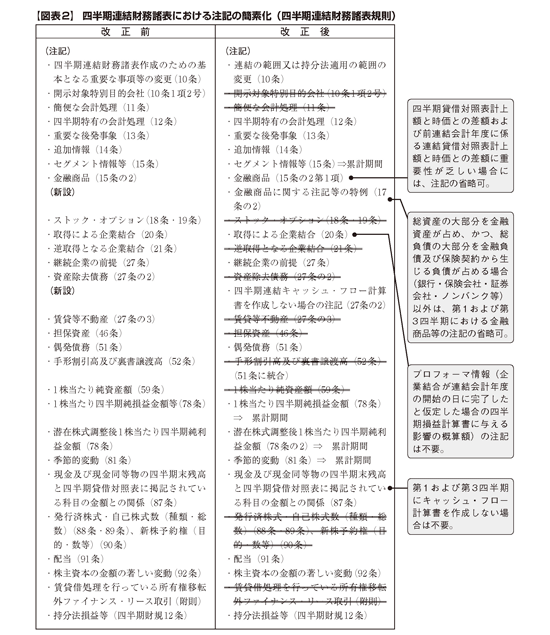
(1)金融商品に関する注記の簡素化(四半期連結財務諸表規則15条の2第1項ただし書、四半期財務諸表等規則8条の2第1項ただし書)
従前においては、金融商品が企業集団の事業運営において重要であり、かつ、四半期連結貸借対照表計上額が前期の連結貸借対照表計上額と比較して著しく変動している場合には、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額について注記することが求められていたため、金融商品の金額が前期末に比較して、四半期末に著しく変動した場合、時価と簿価が同額かほとんど差がない場合であっても、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額が注記されていた。
これらについては、四半期連結貸借対照表計上額を参照すれば足り、改めて注記を行う必要性に乏しいと考えられることから、見直しが行われている。
すなわち、15条の2第1項ただし書は、四半期会計基準適用指針第112項を踏まえて、金融商品の四半期連結貸借対照表計上額が前連結会計年度末に比して著しく変動した場合であっても、四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、四半期連結貸借対照表計上額、時価およびその差額の注記を省略できるものと規定されている。
また、当該金融資産の前連結会計年度末における簿価と時価との差額に重要性がある場合には、時価の変動は有用な情報と考えられることから、改めて四半期においても注記を求めることとし、「連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合」という要件も合わせて規定されたものと考えられる。
(2)金融商品に関する注記等の特例(四半期連結財務諸表規則17条の2、四半期財務諸表等規則10条の2)
従前においては、金融商品について、すべての連結財務諸表提出会社に、四半期連結貸借対照表の科目ごとの注記(15条の2)に加え、有価証券については保有目的ごとの注記(16条)およびデリバティブ取引に関する注記(17条)が求められていたが、一般事業会社については、利用者のニーズが高くないものと考えられ、見直しが行われている。
すなわち、17条の2は、四半期会計基準適用指針第80項(3)ただし書の規定を踏まえ、「企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除」き、連結財務諸表提出会社は、第1四半期および第3四半期において、金融商品(15条の2)、有価証券(16条)およびデリバティブ取引(17条)に関する注記を省略できるものと規定されている。
「企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める」企業は、銀行、保険会社、証券会社、ノンバンク等の金融機関等が想定されている(四半期会計基準適用指針第113項)。
金融商品に関する注記等が重要と考えられる金融機関等については、これまでどおりこれらの注記を求める一方、上記の要件を満たさないと考えられる一般事業会社について、注記の簡素化が行われている。
5.適用時期 簡素化に係る上記改正は、平成23年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間および四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表、同日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間および四半期累計期間に係る四半期財務諸表について適用される(改正府令附則2条1項、3条1項)。
Ⅲ 開示府令の改正
1.四半期報告書の簡素化に係る改正の概要 前述したような四半期報告書における財務情報の簡素化とともに、四半期報告書に記載すべき非財務情報の記載内容の簡素化に伴い、四半期報告書等の様式の改正が行われた。改正のポイントは次の3つである。
(イ)「経理の状況」に記載する四半期連結財務諸表は、原則、四半期連結累計期間に係るもののみを記載すればよいこととされたことに伴い、「経理の状況」以外の非財務情報の記載内容についても、基本的に、四半期連結累計期間についての情報を記載する。
(ロ)「生産、受注及び販売の状況」等の記載内容については、生産、受注および販売の実績等が四半期連結累計期間において著しく変動した場合に「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(いわゆる「MD&A」)に集約して記載することとし、記載項目としては削除する。
(ハ)「株価の推移」は他の情報源から取得が可能であるため削除され、「保証会社情報」における「継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」については、四半期報告書提出会社が提出した有価証券報告書を参照することを可能とする。
(1)四半期報告書 四半期報告書の様式(開示府令第4号の3様式)の具体的な改正内容は、次のとおりである(図表3参照)。
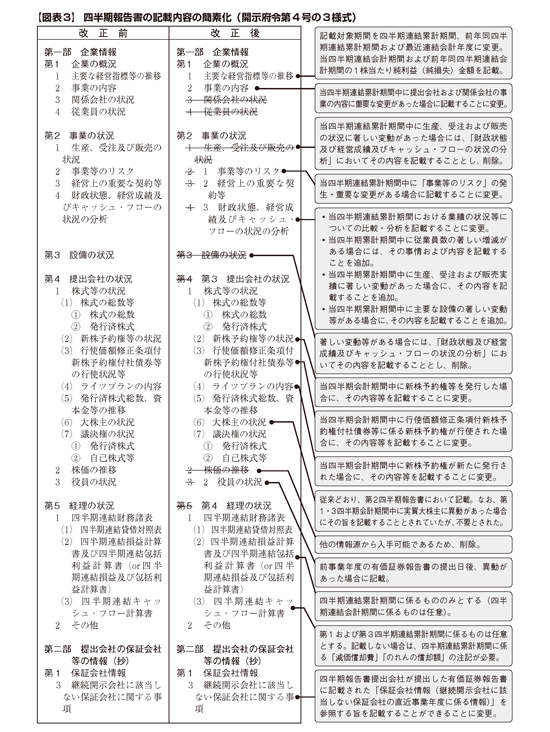
① 「企業の概況」の記載 (i)「主要な経営指標等の推移」(いわゆる「ハイライト情報」)については、基本的に、当四半期連結累計期間(前年同四半期連結累計期間を含む)および最近連結会計年度に係るものを記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)a)。
たとえば、第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書では、図表4のように記載することが考えられ、前年同四半期連結累計期間(第Y-1期第2四半期連結累計期間)、当四半期連結累計期間(第Y期第2四半期連結累計期間)および直近の連結会計年度(第Y-1期)の順に記載することとなる。なお、「1株当たり純資産額」および「従業員数」の記載は不要とされている。
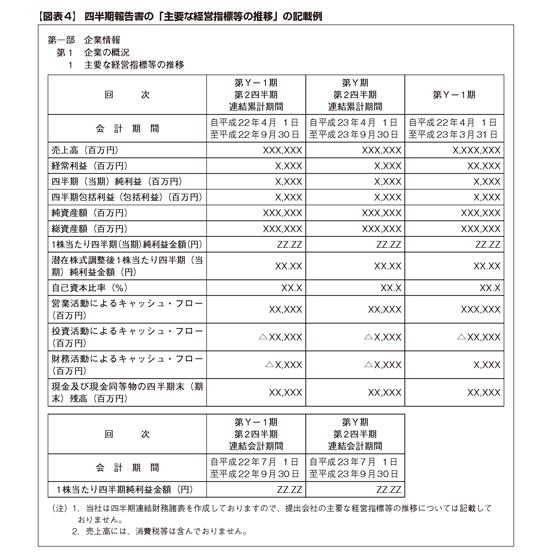
また、「売上高」「四半期純利益金額」「1株当たり四半期純利益金額」については、「経理の状況」において、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書または四半期連結損益および包括利益計算書(以下「四半期連結損益計算書等」という)を記載する場合に、四半期連結会計期間に係る数値をかっこ書で四半期連結累計期間に係る数値に併せて記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)a本文ただし書)。
他方、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」は、投資者の投資判断に重要な情報であると考えられることから、「経理の状況」において当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等が記載されず、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」が、上記のようにかっこ書で記載されない場合には、図表4における下の表のように記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(5)b)。
(ⅱ)「事業の内容」については、四半期連結累計期間において提出会社および関係会社の事業の内容に重要な変更があった場合にその内容を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(6))。
(ⅲ)「関係会社の状況」の記載項目が削除されたほか、「従業員の状況」については、当四半期連結累計期間において連結会社または提出会社の従業員数に著しい増加または減少があった場合に「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の欄に記載することとし、記載項目としては削除された。
② 「事業の状況」の記載
(i)「生産、受注及び販売の状況」については、当四半期連結累計期間において生産、受注および販売の実績について著しい変動があった場合には、その内容を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において記載することとされ、記載項目としては削除された。なお、その内容の記載にあたっては、改正前と同様、業種・業態によっては定性的に記載することも可能である。
(ⅱ)「事業等のリスク」については、当四半期連結累計期間において、事業等のリスクが発生した場合または有価証券報告書に記載した事業等のリスクに重要な変更があった場合に記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(7))。
(ⅲ)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」については、セグメント情報ごとの業績の状況およびキャッシュ・フローの状況の前年同期との比較・分析、対処すべき課題の重要な変更等の対象期間が四半期連結累計期間に改正されるとともに(第4号の3様式・記載上の注意(9)a(a)・(b))、前述のとおり、「従業員数」「生産、受注及び販売の実績」および「主要な設備」について当四半期連結累計期間において著しい変動があった場合に、その内容を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(9)a(d)~(f))。
③ 「設備の状況」の記載 「設備の状況」については、「主要な設備」について当四半期連結累計期間において著しい変動等があった場合に、その内容を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において記載することとされ、記載項目としては削除された。
④ 「提出会社の状況」の記載 (i)「新株予約権等の状況」については、記載内容を簡素化する観点から、当四半期会計期間において新株予約権等を発行した場合に、当該新株予約権等の発行に係る決議年月日、発行時の新株予約権の数、目的となる株式の種類および株式数、行使時の払込金額、行使期間、株式の発行価格および資本組入額、行使の条件等に関する事項を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(11))。
(ⅱ)「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等」については、当四半期会計期間において行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が行使された場合にその状況を記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(12))。
(ⅲ)「ライツプランの内容」については、当四半期会計期間において新株予約権を発行した場合に記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(13))。
(ⅳ)「大株主の状況」については、当四半期会計期間が第2四半期会計期間である場合にのみ、当四半期会計期間末現在の大株主の状況を記載すればよいこととされた(第4号の3様式・記載上の注意(15))。
(ⅴ)「株価の推移」については、その株価について四半期報告書に記載を求めなくても、投資者は株価を他の情報源から入手することが容易であるため、記載項目から削除された。
(ⅵ)「役員の状況」については、前事業年度に係る有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員に異動があった場合について記載することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(17))。
⑤ 「経理の状況」の記載 四半期報告書に記載すべき四半期連結財務諸表等については、前述のとおり、当四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等の記載は任意とされたほか、第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載についても任意とされた(第4号の3様式・記載上の注意(21)・(23)等)。
なお、提出会社の判断により、任意で四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書等または第1四半期および第3四半期に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載する場合には、「経理の状況」の冒頭にその旨を記載しなければならないことが開示ガイドラインにおいて明確化された(企業内容等開示ガイドライン24の4の7-9、24の4の7-10)。
⑥ 「提出会社の保証会社等の情報」等の記載 「提出会社の保証会社等の情報」の「保証会社情報」のうち、「継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項」については、四半期報告書提出会社が既に提出した有価証券報告書に記載されているため、記載内容の簡素化の一環として、当該有価証券報告書に記載された保証会社に関する情報を参照する旨、記載することができることとされた(第4号の3様式・記載上の注意(33)d)。
(2)有価証券届出書等 有価証券届出書の提出会社が四半期報告書を提出している場合には、当該有価証券届出書の提出時期によって、当該有価証券届出書に係る最近連結会計年度の次の連結会計年度における四半期連結累計期間に関する業績等の概要、四半期連結財務諸表等を当該有価証券届出書に記載することとされているが、今般の四半期報告書の記載内容の簡素化に伴い、これらの記載内容について改正が行われた。
(i)有価証券届出書(開示府令第2号様式)の記載内容のうち、「業績等の概要」については、業績およびキャッシュ・フローの状況を記載することとなるが、当該有価証券届出書の「経理の状況」において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げていない場合には、キャッシュ・フローの状況についての記載は不要とされた。
(ⅱ)「生産、受注及び販売の状況」および「主要な設備の状況」については、「経理の状況」において、四半期連結貸借対照表を掲げた場合にあっては、当該四半期連結貸借対照表に係る四半期連結累計期間において、「生産、受注及び販売の状況」および「主要な設備の状況」に著しい変動があった場合に、その内容を記載することとされた(第2号様式・記載上の注意(31)・(38))。
(ⅲ)有価証券届出書の提出者が四半期報告書を提出した場合には、「経理の状況」・「連結財務諸表」の「その他」において、「最近連結会計年度における四半期情報」として各四半期連結会計期間に係る「売上高」「税金等調整前四半期純利益金額」「四半期純利益金額」および「1株当たり四半期純利益金額」を記載することとされていた。
改正後は、四半期報告書に記載されるこれらの金額は四半期連結累計期間に係るものに改正されることから、有価証券届出書に記載すべきこれらの金額について、各四半期連結累計期間および最近連結会計年度に係る金額を記載することとされた。
なお、四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額」については、投資情報として重要な情報であると考えられることから、最近連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る「1株当たり四半期純利益金額(各四半期連結累計期間に係る項目の金額に準じて算出したもの)」についても記載することとされた(第2号様式・記載上の注意(66)c・d、第2号の4様式・記載上の注意(10-3)c・d等)。
(3)適用時期 上記(1)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する事業年度における四半期会計期間に係る四半期報告書から適用される。
(2)の改正については、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成23年4月1日以後に開始する事業年度のものである場合における有価証券届出書から適用される。
2.比較情報等に係る改正 四半期連結財務諸表規則および中間連結財務諸表規則等の改正により、新たに四半期連結財務諸表および中間連結財務諸表等に「比較情報」が含まれることとなったことに伴い、四半期報告書および半期報告書等の様式が改正された。
(1)四半期報告書 前述のように、四半期連結財務諸表には、「比較情報」(当四半期連結会計期間または当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表に記載された事項に対応する前連結会計年度および前連結会計年度における当四半期連結会計期間または当四半期連結累計期間に対応する四半期連結会計期間または四半期連結累計期間に係る事項(四半期連結財務諸表規則5条の3))が含まれることになる。
したがって、四半期報告書の「経理の状況」において、従来のように、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表および前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表を記載した場合には、当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表の比較情報と前連結会計年度に係る要約連結貸借対照表が併記され、前連結会計年度に係る情報が重複することになる。同様に、四半期連結損益計算書等および四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、前年同四半期連結会計期間または前年同四半期連結累計期間に係る情報が重複することとなる。
このため、四半期報告書の「経理の状況」に記載する四半期連結財務諸表に係る「記載上の注意」では、「当四半期連結会計期間に係る四半期連結貸借対照表」「四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書等」「四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書」等を記載する旨を規定することとされた(第4号の3様式・記載上の注意(19)~(23))。
四半期報告書の「経理の状況」に記載する四半期財務諸表についても、同様である(第4号の3様式・記載上の注意(25)~(28))。
(2)半期報告書 中間連結財務諸表に含まれることとなる「比較情報」は、当中間連結会計期間に係る当該中間連結財務諸表に記載された事項に対応する前連結会計年度および前中間連結会計期間に係る事項である(中間連結財務諸表規則4条の2)。
したがって、半期報告書の「経理の状況」において、従来のように、当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表および前中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表を記載した場合には、当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の比較情報と前中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表が併記され、前中間連結会計期間に係る情報が重複することになる。
このため、半期報告書の「経理の状況」に記載する中間連結財務諸表に係る「記載上の注意」では、「当中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表」を記載する旨を規定することとされた(第5号様式・記載上の注意(25)~(29))。
半期報告書の「経理の状況」に記載する中間財務諸表についても、同様である(第5号様式・記載上の注意(31)~(35))。
(3)適用時期 上記(1)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する事業年度における四半期会計期間に係る四半期報告書から適用される。
(2)の改正については、平成23年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る半期報告書から適用される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























