解説記事2017年02月13日 【税理士のための相続法講座】 遺産分割(5)-遺産分割の効力(2)(2017年2月13日号・№678)
税理士のための相続法講座
第24回
遺産分割(5)-遺産分割の効力(2)
弁護士 間瀬まゆ子
前回に引き続き、遺産分割協議の効力がテーマです。
3 遺産分割協議の無効(承前) 前回も述べたとおり、当事者の意思表示に瑕疵がある場合にも、遺産分割協議の効力に影響が及びます。意思表示の瑕疵としては、民法95条の錯誤無効や民法96条の詐欺・強迫による取消の主張が考えられますが、中でも、遺産分割協議に係る紛争の中でよく出されるのが、民法95条の錯誤無効の主張です。
裁判例でも、遺言の存在、遺産の範囲、遺産の評価などに錯誤があった場合に要素の錯誤があると認められた例があります(最一小判平成5年12月16日集民170号757ページほか。ただし、要素の錯誤があっても、表意者に重過失があったとして、錯誤無効の主張が認められないこともあります。)。
また、他の相続人から、翌日が申告期限でありこれを過ぎると数千万円の無申告加算税を課せられるなどと説明され、それを誤信してしまったというケースで、動機の錯誤ではあるもののその動機は他の相続人に表示されていたとして、錯誤無効が認められた例もあります(東京地判平成11年1月22日判時1685号51ページ)。
さらに、税との関係でいうと、遺産分割協議後に想定外の税を課されてしまった相続人が、当該協議が錯誤により無効になると主張した場合に、これが認められるかという問題もあります。
このように想定外の税が課されることが後に判明するというのはあり得ることですが、税負担に関する錯誤無効の主張は認められないのが大原則です(高松高判平成18年2月23日訟月52巻12号3672ページほか参照)。というのも、納税義務の発生原因となる私法上の法律行為に関する課税負担の錯誤の主張を認めていたのでは、申告納税方式が成り立たないからです。
しかし、例外的に、錯誤無効の主張を認めた下級審の裁判例があります。それが、上記の事例に係る判決です。
東京地裁平成21年2月27日判タ1355号123ページは、Bらが、更正の請求の期間内に、課税庁の指摘等によらず、自ら間違いに気付いて再度の遺産分割協議と更正の請求をした点を捉え、「申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合」に該当するとして、Bらの錯誤無効の主張を認めました。
相続税の負担額の差額が合計5億円余りであったといいますから、当事者はもちろん、税理士も胸を撫で下ろしたことでしょう。ただ、これはあくまで例外事例ですので、税負担に係る錯誤無効の主張は認められないと思っていた方が安全です。
4 一部分割 実務上、遺産の一部のみを対象とする分割協議が行われることは珍しくありません。例えば、相続税の納期限が迫っているため、納税資金に充てるため、一部の預金を分割して払戻しを受けるような場合です。このような一部分割も、原則として有効と解されています。
ただし、残余の遺産の分割に当って一部分割による取得分を考慮するか否かについて、予め当事者間で合意しておくことは必須です。
また、寄与分や特別受益が主張されていて、それが具体的相続分に大きく影響することが見込まれる場合には、相続財産の多くを占める財産について一部分割してしまうことは避けた方が無難です。後の残余の相続財産の分割により取得した分を合わせても、具体的相続分に相当する財産を取得できない相続人が出てしまう可能性があり、そのような場合に、残余についての分割協議がまとまらなくなってしまう恐れがあるためです。
5 相続分なきことの証明書 遺産分割協議に関する紛争としては、遺産分割協議の効力が争われる場合の他に、遺産分割がそもそも存在したのかが争われる場合があります。
具体的な場面としていちばんに想定されるのは、相続人の一人が遺産分割協議書を偽造したような場合ですが、その他に、相続分なきことの証明書(相続分不存在証明書)を用いて相続登記を経た事例でも、遺産分割協議がそもそも成立していないと争われることがあります。
相続分なきことの証明書は、相続分を超える特別受益を受けている相続人がいる場合に用いられるもので、そのような相続人が作成した相続分なきことの証明書(相続分不存在証明書)を添付することにより、当該相続人を除外した簡易な方法による相続登記の申請が可能になります。現在でも長子相続の慣習が残っている地域で、よく用いられているなどと聞くことがあります。
しかし、このような相続分なきことの証明書を偽造されたとして、遺産分割協議の存否が争われることがあります。また、実際には特別受益を受けていないにもかかわらず証明書を交付した場合、相続分の贈与または有効な遺産分割協議があったとして、登記は有効と解されていますが、詐欺や強迫によって証明書を書かされたとして、遺産分割協議の不存在を争われてしまうこともあり得ます。
簡易な方法ではありますが、無用な紛争を招いてしまっては元も子もありませんので、相続分なきことの証明書を用いてよい事案かどうか、慎重に見極める必要があるように思います。
《預貯金債権に関する最高裁判決》 以前から触れていた預貯金債権が遺産分割の対象になるかについて争われた事例について、最高裁大法廷が昨年12月19日に判決を出しました。
預貯金債権が「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とするもので、預貯金債権が相続開始と同時に各共同相続人に法定相続分に応じて当然に分割されるとしていた従前の判例を変更しました(なお、判決で言及されているのは、普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権です。当該案件で問題とならなかったため、定期預金債権については触れられていませんが、判旨からして、今回判示された内容は定期預金債権にも妥当すると解されます。)。
この判例変更により、様々な実務上の影響が想定されています。その中の一つが、相続開始後に急な資金が必要となった場合でも、遺産分割がまとまらない限り預貯金を払い戻すことができないという問題です。
これまでは、遺産分割で揉めてしまったような場合に自己資金で相続税の納税が出来ないとしても、預金債権のうち自らの法定相続分に相当する分を金融機関に支払ってもらって(容易に支払ってもらえないという実態はありましたが、その場合でも、訴訟を提起すれば支払いを受けることはできました。)、納税資金に充てるということが可能でした。しかし、今回の判例変更により、今後はそのようなことが出来なくなります。
その代替措置としては、審判前の保全処分(家事事件手続法200条)の一つである仮分割の仮処分を用いることが考えられます。「審判前」の保全処分と言っても、家事事件手続法制定の際に要件が緩和されて調停申立段階でも申立てが可能となり、以前より使いやすい制度となっています。しかし、遺産分割調停と仮処分の申立てを裁判所に対して行う必要があるわけですから、相続人にとって大きな負担であることは間違いありません。
なお、以前、判決の理由如何によっては、他の可分債権にも影響が及ぶことになるのではとの見解を述べましたが、今回の判決理由を読むと、預貯金債権の可分債権性を否定する内容ですので(多数意見の中では明示されていませんが)、損害賠償請求権等の可分債権については、これまで同様、法定相続分に応じて当然に分割されるとの解釈が妥当するものと思われます。
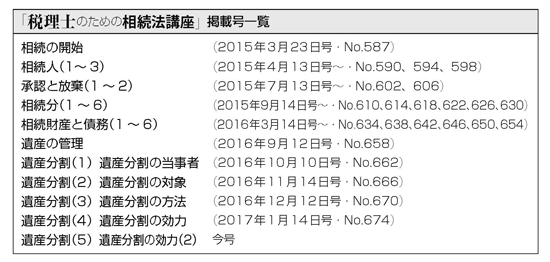
第24回
遺産分割(5)-遺産分割の効力(2)
弁護士 間瀬まゆ子
前回に引き続き、遺産分割協議の効力がテーマです。
3 遺産分割協議の無効(承前) 前回も述べたとおり、当事者の意思表示に瑕疵がある場合にも、遺産分割協議の効力に影響が及びます。意思表示の瑕疵としては、民法95条の錯誤無効や民法96条の詐欺・強迫による取消の主張が考えられますが、中でも、遺産分割協議に係る紛争の中でよく出されるのが、民法95条の錯誤無効の主張です。
裁判例でも、遺言の存在、遺産の範囲、遺産の評価などに錯誤があった場合に要素の錯誤があると認められた例があります(最一小判平成5年12月16日集民170号757ページほか。ただし、要素の錯誤があっても、表意者に重過失があったとして、錯誤無効の主張が認められないこともあります。)。
また、他の相続人から、翌日が申告期限でありこれを過ぎると数千万円の無申告加算税を課せられるなどと説明され、それを誤信してしまったというケースで、動機の錯誤ではあるもののその動機は他の相続人に表示されていたとして、錯誤無効が認められた例もあります(東京地判平成11年1月22日判時1685号51ページ)。
さらに、税との関係でいうと、遺産分割協議後に想定外の税を課されてしまった相続人が、当該協議が錯誤により無効になると主張した場合に、これが認められるかという問題もあります。
| 被相続人Aが亡くなった。相続人であるAの妻Bと子・孫らは、Bが取得する取引相場のない株式を配当還元方式で評価することを前提として、遺産分割協議を行い、相続税の申告をした。しかし、株式の評価につき税理士の誤解があり、本来は類似業種比準価額方式で評価すべきであったことが判明したため、Bらは、改めて、配当還元方式を用いることができるように株数を調整して遺産分割協議をし直した。その上で、税務署長に対して、更正の請求の期間内に、相続税の更正の請求をした。 |
しかし、例外的に、錯誤無効の主張を認めた下級審の裁判例があります。それが、上記の事例に係る判決です。
東京地裁平成21年2月27日判タ1355号123ページは、Bらが、更正の請求の期間内に、課税庁の指摘等によらず、自ら間違いに気付いて再度の遺産分割協議と更正の請求をした点を捉え、「申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合」に該当するとして、Bらの錯誤無効の主張を認めました。
相続税の負担額の差額が合計5億円余りであったといいますから、当事者はもちろん、税理士も胸を撫で下ろしたことでしょう。ただ、これはあくまで例外事例ですので、税負担に係る錯誤無効の主張は認められないと思っていた方が安全です。
4 一部分割 実務上、遺産の一部のみを対象とする分割協議が行われることは珍しくありません。例えば、相続税の納期限が迫っているため、納税資金に充てるため、一部の預金を分割して払戻しを受けるような場合です。このような一部分割も、原則として有効と解されています。
ただし、残余の遺産の分割に当って一部分割による取得分を考慮するか否かについて、予め当事者間で合意しておくことは必須です。
また、寄与分や特別受益が主張されていて、それが具体的相続分に大きく影響することが見込まれる場合には、相続財産の多くを占める財産について一部分割してしまうことは避けた方が無難です。後の残余の相続財産の分割により取得した分を合わせても、具体的相続分に相当する財産を取得できない相続人が出てしまう可能性があり、そのような場合に、残余についての分割協議がまとまらなくなってしまう恐れがあるためです。
5 相続分なきことの証明書 遺産分割協議に関する紛争としては、遺産分割協議の効力が争われる場合の他に、遺産分割がそもそも存在したのかが争われる場合があります。
具体的な場面としていちばんに想定されるのは、相続人の一人が遺産分割協議書を偽造したような場合ですが、その他に、相続分なきことの証明書(相続分不存在証明書)を用いて相続登記を経た事例でも、遺産分割協議がそもそも成立していないと争われることがあります。
相続分なきことの証明書は、相続分を超える特別受益を受けている相続人がいる場合に用いられるもので、そのような相続人が作成した相続分なきことの証明書(相続分不存在証明書)を添付することにより、当該相続人を除外した簡易な方法による相続登記の申請が可能になります。現在でも長子相続の慣習が残っている地域で、よく用いられているなどと聞くことがあります。
しかし、このような相続分なきことの証明書を偽造されたとして、遺産分割協議の存否が争われることがあります。また、実際には特別受益を受けていないにもかかわらず証明書を交付した場合、相続分の贈与または有効な遺産分割協議があったとして、登記は有効と解されていますが、詐欺や強迫によって証明書を書かされたとして、遺産分割協議の不存在を争われてしまうこともあり得ます。
簡易な方法ではありますが、無用な紛争を招いてしまっては元も子もありませんので、相続分なきことの証明書を用いてよい事案かどうか、慎重に見極める必要があるように思います。
《預貯金債権に関する最高裁判決》 以前から触れていた預貯金債権が遺産分割の対象になるかについて争われた事例について、最高裁大法廷が昨年12月19日に判決を出しました。
預貯金債権が「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当」とするもので、預貯金債権が相続開始と同時に各共同相続人に法定相続分に応じて当然に分割されるとしていた従前の判例を変更しました(なお、判決で言及されているのは、普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権です。当該案件で問題とならなかったため、定期預金債権については触れられていませんが、判旨からして、今回判示された内容は定期預金債権にも妥当すると解されます。)。
この判例変更により、様々な実務上の影響が想定されています。その中の一つが、相続開始後に急な資金が必要となった場合でも、遺産分割がまとまらない限り預貯金を払い戻すことができないという問題です。
これまでは、遺産分割で揉めてしまったような場合に自己資金で相続税の納税が出来ないとしても、預金債権のうち自らの法定相続分に相当する分を金融機関に支払ってもらって(容易に支払ってもらえないという実態はありましたが、その場合でも、訴訟を提起すれば支払いを受けることはできました。)、納税資金に充てるということが可能でした。しかし、今回の判例変更により、今後はそのようなことが出来なくなります。
その代替措置としては、審判前の保全処分(家事事件手続法200条)の一つである仮分割の仮処分を用いることが考えられます。「審判前」の保全処分と言っても、家事事件手続法制定の際に要件が緩和されて調停申立段階でも申立てが可能となり、以前より使いやすい制度となっています。しかし、遺産分割調停と仮処分の申立てを裁判所に対して行う必要があるわけですから、相続人にとって大きな負担であることは間違いありません。
なお、以前、判決の理由如何によっては、他の可分債権にも影響が及ぶことになるのではとの見解を述べましたが、今回の判決理由を読むと、預貯金債権の可分債権性を否定する内容ですので(多数意見の中では明示されていませんが)、損害賠償請求権等の可分債権については、これまで同様、法定相続分に応じて当然に分割されるとの解釈が妥当するものと思われます。
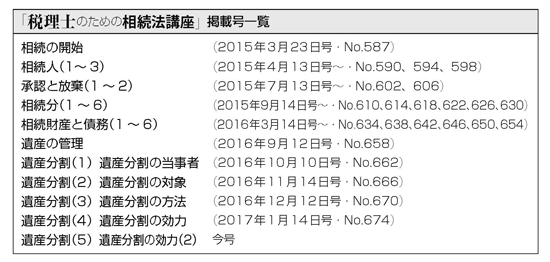
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















