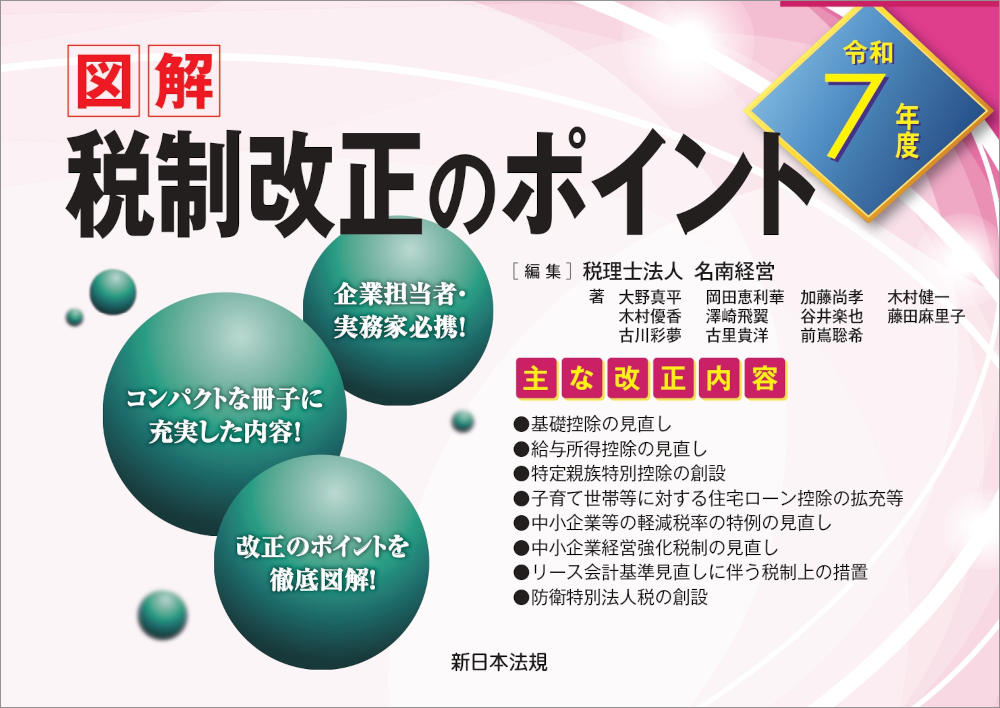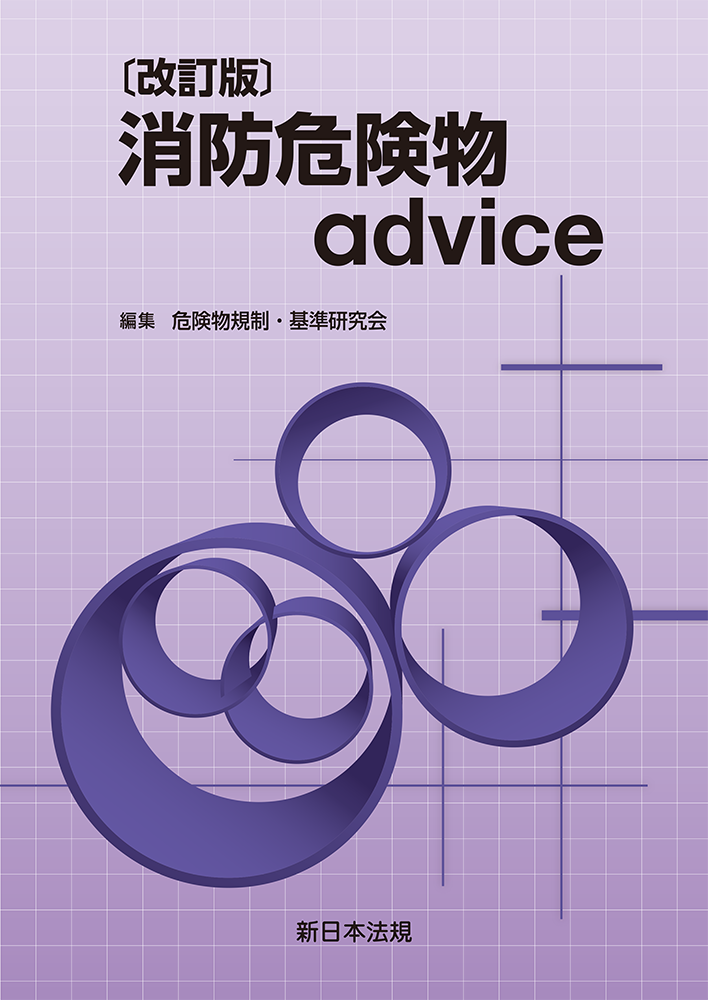解説記事2018年04月30日 【税務マエストロ】 タックスヘイブン対策税制関連のQ&Aについて①(2018年4月30日号・№737)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
タックスヘイブン対策税制関連のQ&Aについて①
#212 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#213
免税(1)
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制ともいわれる)は、昨年度(平成29年度)税制改正において、その制度の基本構造を含め、大幅な変更がされたところである。この改正による新制度が適用されるのは、原則として、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額等についてであり、今般の適用開始にあわせ、国税庁より、重要な改正点についてのQ&Aが公表された。具体的には、その改正点のうち、「特定外国関係会社の判定」、「対象外国関係会社の判定における経済活動基準」、および「部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲等」について、具体的な観点からの説明がされている。以下、その内容を解説する。
1 タックスヘイブン対策税制の改正点 タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度である。この税制は、平成29年度改正で大幅に改正されたところであるが、改正前のタックスヘイブン対策税制では、「外国子会社の租税負担割合が20%以上であれば、実体がない場合であっても、制度が適用されない一方、租税負担割合が20%未満であれば、実体のある事業を行っている場合であっても、その所得が、親会社の所得に合算されてしまう場合がある、といった問題があった」と説明されている。しかしながら、そもそも、「租税負担割合が20%未満であれば、実体のある事業を行っている場合であっても、その所得が、親会社の所得に合算されてしまう場合がある」というのは、制度矛盾と言えるのではないだろうか。つまり、実体がある場合には、合算課税の対象とならないようにするために「適用除外基準」が定められているわけであり、当該制度を的確に執行しているのであれば、こうした課税は起きないはずである。かつて議論となった「来料加工貿易」に対する本税制による課税や「レンタルオフィス事件」がそうした制度矛盾をあらわしているといえよう。
また、当該改正は、「具体的には、租税回避リスクを、改正前の外国子会社の租税負担割合により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改め」るとされている。これにより、従来は制度の対象外であった租税負担割合20%以上の外国子会社について、「一見して明らか」に、利子・配当・使用料等の「受動的所得」しか得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられるペーパーカンパニー等である場合には、外国子会社合算税制の対象とされている。他方で、「経済活動の実体のある事業から得られた、いわゆる「能動的所得」は、外国子会社の租税負担割合にかかわらず合算対象外」とされている。しかしながら所得の種類のみで、租税回避か否かの判定を行うのは困難であり、また、議論されている租税回避の範囲も不明確である。「特定の資産性所得は、常に日本で課税する。」と言っているようなものであり、いわゆる日本国内に源泉があるという所得のとらえ方の問題ではないだろうか。
2 特定外国関係会社の判定
(1)ペーパーカンパニー等について 改正後のタックスヘイブン対策税制では、次に掲げる外国関係会社は受動的所得しか得ていないような「租税回避リスクの高い」外国関係会社であるとされ、これらを「特定外国関係会社」と定義し、会社単位で合算課税の対象とすることとしている。ただし、この類型に該当する場合であっても、租税負担割合が30%以上であるときには、適用除外とされている。つまり30%の租税負担割合を基準として合算課税される対象とされている。
イ)活動の実体がない外国関係会社(ペーパーカンパニー)
ロ)総資産に比して「受動的所得」の占める割合が高い外国関係会社(事実上のキャッシュ・ボックス)
ハ)情報交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国等(ブラック・リスト国)に所在する外国関係会社
このうち、イ)のペーパーカンパニーについては、「実体基準(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している外国関係会社)」及び「管理支配基準(その本店所在地国においてその事業の管理・支配等を自ら行っている外国関係会社)」のいずれも満たさない外国関係会社と定義されている。
(2)ペーパーカンパニーにおける実体基準 この実体基準の内容は、対象外国関係会社を判定する際の経済活動基準(改正前の適用除外基準)における実体基準と同様の概念であり、独立した企業としての活動の実体を有するのかを判定する基準とされている。これは、外国関係会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設の存在という物的な側面から、独立した企業としての活動の実体を有するのかを判定するもので、この固定施設とは、単なる物的設備ではなく、そこで人が活動することを前提とした概念と説明されている。例えば、外国関係会社が主たる事業として不動産賃貸業を行っている場合における賃貸用の不動産は、小売業における棚卸資産と同様の位置づけに該当し、外国関係会社が事業活動を行うためのものではないため、実体基準における固定施設には該当しないと考えられる。つまり、不動産賃貸業の場合には、外国関係会社が賃貸借契約の締結等といった事業活動を行う事務所等が、実体基準における固定施設に該当すると考えられる。
また、外国関係会社が有する固定施設が主たる「事業を行うに必要」と認められるか否かは、主たる事業の業種や業態に応じて考える必要がある。例えば、小売業なら店舗、製造業なら工場などが一般的には該当すると考えられる一方で、それ以外の事業についてどのような機能・用途を有する固定施設を要するのか、あるいはどの程度の規模の固定施設を要するのかは、その主たる事業の内容、その事業に係る活動の内容などから個別に判断するべき内容とされている。なお、実体基準は、主たる事業を行うために必要と認められる固定施設が「有る」か「無い」かによって判定するため、外国関係会社が固定施設について所有権を有するか否かは、固定施設の有無に影響しないこととなる。
また、より重要な論点として、実体基準では、外国関係会社が主たる「事業を行うに必要と認められる固定施設」を有しているかどうかにより判定をすることとなるため、外国関係会社の有する固定施設が、
① 主たる事業に使用されていない場合
② 主たる事業を行うために必要と認められないものである場合
には、実体基準を満たさないこととなる。したがって、そもそも主たる事業が人の活動を要しない事業である場合には、主たる事業を行うに必要と認められる固定施設は有していないこととされる。
(3)実体基準に関するQ&A
Q1:子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合 商社を営む内国法人P社は、F国に、その外国関係会社であるS社を設立した。このS社は、現地F国において発電事業を営むA社を子会社とし、当該A社の事業の管理等を行うことを事業としている。S社は、単にA社の株式を保有するだけでなく、F国において事務所を賃借し、その役員及び使用人はその事務所においてA社の行う設備投資や事業の進捗への関与、A社に提供する資金の調達や他の株主との調整等に従事している。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) S社の役員及び使用人がA社の行う設備投資や事業の進捗への関与等の業務に従事するために、賃借した事務所を使用しているとのことであるため、その賃借した事務所は、S社の主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当し、S社は実体基準を満たすものと考えられると説明されている。
実体基準の判定において、単なる物的施設の存在の有無ではなく、外国関係会社の事業に即して、当該施設の機能、用途の観点から、事業を行うために必要か否かの検討を示したQ&Aであり、結論も妥当と言えよう。
Q2:関係会社の事務所の一室を賃借して子会社の事業への関与等を行っている場合 上記ケースにおいて、S社はその業務にS社の役員及び使用人を従事させるため、F国に所在し、P社の外国関係会社に該当するB社の事務所の一室を賃借しており、S社の役員及び使用人はその事務所の一室においてA社の行う設備投資や事業の進捗への関与、A社に提供する資金の調達や他の株主との調整等に従事している。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) S社が事務所として使用するのは、B社の事務所の一室であるということであるが、A社の行う設備投資や事業の進捗への関与等の業務を行うのにその一室で十分であり、S社の役員及び使用人がこれらの業務等に従事するためにその一室を使用しているのであれば、その事務所
の一室は主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当し、実体基準を満たすものと説明されている。
さらに、外国関係会社の中には、事務所の一室の中の一画を使用して事業活動を行うといった場合もありえ、このような場合であっても、その事業活動を行うのにその一画で十分であり、その一画を使用して役員又は使用人が主たる事業に係る活動を行っているという実態があるのであれば、その一画は主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当すると考えられると説明されている。
このQ&Aは、外国関係会社の主たる事業を行うに必要な規模の固定施設か否かを例示したものであろう。結論も妥当と言えよう。
Q3:主たる事業を行うに必要な固定施設を有していると認められない場合 製造業を営む内国法人P社は、かねてからF国において工業所有権を保有しているS社(外国関係会社に該当)の株式を保有している。S社はF国にあるビルの一室を事務所用に賃借しているが、S社の主たる事業はその保有する工業所有権に係る使用料を得ることのみであり、S社の銀行口座に使用料が振り込まれるだけであるため、S社の役員及び使用人はその一室を使用して主たる事業に係る活動を行っている実態はない。なお、S社はこの一室以外の固定施設を有していない。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) 本件については、「S社の主たる事業は工業所有権に係る使用料を得ることであり、その使用料はS社の銀行口座において収受することとなっています。S社はビルの一室を賃借しているとのことですが、S社はその一室を使用して、主たる事業に係る活動を行っているという実態がないということですので、その一室は主たる事業を行うに必要な固定施設には該当しないと考えられます。なお、仮に、ビルの一室を使用していたとしても、その主たる事業が工業所有権に係る使用料を得ることのみであって、その事業活動にその一室を使用する必要もないと認められる場合には、その一室はその主たる事業に必要な固定施設には該当しないものと考えられます。」と回答されている。
このQでは、S社は工業所有権を得るために、全く事業活動を行っていないことが前提とされている。「使用料を得ることのみが主たる事業」であり、それには実態的な活動が全く必要ないとの設定である。しかしながら、現実社会においては、使用料の基因となる無形資産の維持、管理は重要な業務であろう。無許可でブランドや特許、意匠が使用されていないか、支払使用料の計算が正しいかどうか等、多くの必要な業務が考えられるところである。こうした活動をどう評価するのかについても説明が欲しいところである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
タックスヘイブン対策税制関連のQ&Aについて①
#212 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#213
免税(1)
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説
タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制ともいわれる)は、昨年度(平成29年度)税制改正において、その制度の基本構造を含め、大幅な変更がされたところである。この改正による新制度が適用されるのは、原則として、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額等についてであり、今般の適用開始にあわせ、国税庁より、重要な改正点についてのQ&Aが公表された。具体的には、その改正点のうち、「特定外国関係会社の判定」、「対象外国関係会社の判定における経済活動基準」、および「部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲等」について、具体的な観点からの説明がされている。以下、その内容を解説する。
1 タックスヘイブン対策税制の改正点 タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を、日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度である。この税制は、平成29年度改正で大幅に改正されたところであるが、改正前のタックスヘイブン対策税制では、「外国子会社の租税負担割合が20%以上であれば、実体がない場合であっても、制度が適用されない一方、租税負担割合が20%未満であれば、実体のある事業を行っている場合であっても、その所得が、親会社の所得に合算されてしまう場合がある、といった問題があった」と説明されている。しかしながら、そもそも、「租税負担割合が20%未満であれば、実体のある事業を行っている場合であっても、その所得が、親会社の所得に合算されてしまう場合がある」というのは、制度矛盾と言えるのではないだろうか。つまり、実体がある場合には、合算課税の対象とならないようにするために「適用除外基準」が定められているわけであり、当該制度を的確に執行しているのであれば、こうした課税は起きないはずである。かつて議論となった「来料加工貿易」に対する本税制による課税や「レンタルオフィス事件」がそうした制度矛盾をあらわしているといえよう。
また、当該改正は、「具体的には、租税回避リスクを、改正前の外国子会社の租税負担割合により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改め」るとされている。これにより、従来は制度の対象外であった租税負担割合20%以上の外国子会社について、「一見して明らか」に、利子・配当・使用料等の「受動的所得」しか得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられるペーパーカンパニー等である場合には、外国子会社合算税制の対象とされている。他方で、「経済活動の実体のある事業から得られた、いわゆる「能動的所得」は、外国子会社の租税負担割合にかかわらず合算対象外」とされている。しかしながら所得の種類のみで、租税回避か否かの判定を行うのは困難であり、また、議論されている租税回避の範囲も不明確である。「特定の資産性所得は、常に日本で課税する。」と言っているようなものであり、いわゆる日本国内に源泉があるという所得のとらえ方の問題ではないだろうか。
2 特定外国関係会社の判定
(1)ペーパーカンパニー等について 改正後のタックスヘイブン対策税制では、次に掲げる外国関係会社は受動的所得しか得ていないような「租税回避リスクの高い」外国関係会社であるとされ、これらを「特定外国関係会社」と定義し、会社単位で合算課税の対象とすることとしている。ただし、この類型に該当する場合であっても、租税負担割合が30%以上であるときには、適用除外とされている。つまり30%の租税負担割合を基準として合算課税される対象とされている。
イ)活動の実体がない外国関係会社(ペーパーカンパニー)
ロ)総資産に比して「受動的所得」の占める割合が高い外国関係会社(事実上のキャッシュ・ボックス)
ハ)情報交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国等(ブラック・リスト国)に所在する外国関係会社
このうち、イ)のペーパーカンパニーについては、「実体基準(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している外国関係会社)」及び「管理支配基準(その本店所在地国においてその事業の管理・支配等を自ら行っている外国関係会社)」のいずれも満たさない外国関係会社と定義されている。
(2)ペーパーカンパニーにおける実体基準 この実体基準の内容は、対象外国関係会社を判定する際の経済活動基準(改正前の適用除外基準)における実体基準と同様の概念であり、独立した企業としての活動の実体を有するのかを判定する基準とされている。これは、外国関係会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設の存在という物的な側面から、独立した企業としての活動の実体を有するのかを判定するもので、この固定施設とは、単なる物的設備ではなく、そこで人が活動することを前提とした概念と説明されている。例えば、外国関係会社が主たる事業として不動産賃貸業を行っている場合における賃貸用の不動産は、小売業における棚卸資産と同様の位置づけに該当し、外国関係会社が事業活動を行うためのものではないため、実体基準における固定施設には該当しないと考えられる。つまり、不動産賃貸業の場合には、外国関係会社が賃貸借契約の締結等といった事業活動を行う事務所等が、実体基準における固定施設に該当すると考えられる。
また、外国関係会社が有する固定施設が主たる「事業を行うに必要」と認められるか否かは、主たる事業の業種や業態に応じて考える必要がある。例えば、小売業なら店舗、製造業なら工場などが一般的には該当すると考えられる一方で、それ以外の事業についてどのような機能・用途を有する固定施設を要するのか、あるいはどの程度の規模の固定施設を要するのかは、その主たる事業の内容、その事業に係る活動の内容などから個別に判断するべき内容とされている。なお、実体基準は、主たる事業を行うために必要と認められる固定施設が「有る」か「無い」かによって判定するため、外国関係会社が固定施設について所有権を有するか否かは、固定施設の有無に影響しないこととなる。
また、より重要な論点として、実体基準では、外国関係会社が主たる「事業を行うに必要と認められる固定施設」を有しているかどうかにより判定をすることとなるため、外国関係会社の有する固定施設が、
① 主たる事業に使用されていない場合
② 主たる事業を行うために必要と認められないものである場合
には、実体基準を満たさないこととなる。したがって、そもそも主たる事業が人の活動を要しない事業である場合には、主たる事業を行うに必要と認められる固定施設は有していないこととされる。
(3)実体基準に関するQ&A
Q1:子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合 商社を営む内国法人P社は、F国に、その外国関係会社であるS社を設立した。このS社は、現地F国において発電事業を営むA社を子会社とし、当該A社の事業の管理等を行うことを事業としている。S社は、単にA社の株式を保有するだけでなく、F国において事務所を賃借し、その役員及び使用人はその事務所においてA社の行う設備投資や事業の進捗への関与、A社に提供する資金の調達や他の株主との調整等に従事している。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) S社の役員及び使用人がA社の行う設備投資や事業の進捗への関与等の業務に従事するために、賃借した事務所を使用しているとのことであるため、その賃借した事務所は、S社の主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当し、S社は実体基準を満たすものと考えられると説明されている。
実体基準の判定において、単なる物的施設の存在の有無ではなく、外国関係会社の事業に即して、当該施設の機能、用途の観点から、事業を行うために必要か否かの検討を示したQ&Aであり、結論も妥当と言えよう。
Q2:関係会社の事務所の一室を賃借して子会社の事業への関与等を行っている場合 上記ケースにおいて、S社はその業務にS社の役員及び使用人を従事させるため、F国に所在し、P社の外国関係会社に該当するB社の事務所の一室を賃借しており、S社の役員及び使用人はその事務所の一室においてA社の行う設備投資や事業の進捗への関与、A社に提供する資金の調達や他の株主との調整等に従事している。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) S社が事務所として使用するのは、B社の事務所の一室であるということであるが、A社の行う設備投資や事業の進捗への関与等の業務を行うのにその一室で十分であり、S社の役員及び使用人がこれらの業務等に従事するためにその一室を使用しているのであれば、その事務所
の一室は主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当し、実体基準を満たすものと説明されている。
さらに、外国関係会社の中には、事務所の一室の中の一画を使用して事業活動を行うといった場合もありえ、このような場合であっても、その事業活動を行うのにその一画で十分であり、その一画を使用して役員又は使用人が主たる事業に係る活動を行っているという実態があるのであれば、その一画は主たる事業を行うに必要と認められる固定施設に該当すると考えられると説明されている。
このQ&Aは、外国関係会社の主たる事業を行うに必要な規模の固定施設か否かを例示したものであろう。結論も妥当と言えよう。
Q3:主たる事業を行うに必要な固定施設を有していると認められない場合 製造業を営む内国法人P社は、かねてからF国において工業所有権を保有しているS社(外国関係会社に該当)の株式を保有している。S社はF国にあるビルの一室を事務所用に賃借しているが、S社の主たる事業はその保有する工業所有権に係る使用料を得ることのみであり、S社の銀行口座に使用料が振り込まれるだけであるため、S社の役員及び使用人はその一室を使用して主たる事業に係る活動を行っている実態はない。なお、S社はこの一室以外の固定施設を有していない。このような場合において、S社は実体基準を満たすことになるか。
(回答) 本件については、「S社の主たる事業は工業所有権に係る使用料を得ることであり、その使用料はS社の銀行口座において収受することとなっています。S社はビルの一室を賃借しているとのことですが、S社はその一室を使用して、主たる事業に係る活動を行っているという実態がないということですので、その一室は主たる事業を行うに必要な固定施設には該当しないと考えられます。なお、仮に、ビルの一室を使用していたとしても、その主たる事業が工業所有権に係る使用料を得ることのみであって、その事業活動にその一室を使用する必要もないと認められる場合には、その一室はその主たる事業に必要な固定施設には該当しないものと考えられます。」と回答されている。
このQでは、S社は工業所有権を得るために、全く事業活動を行っていないことが前提とされている。「使用料を得ることのみが主たる事業」であり、それには実態的な活動が全く必要ないとの設定である。しかしながら、現実社会においては、使用料の基因となる無形資産の維持、管理は重要な業務であろう。無許可でブランドや特許、意匠が使用されていないか、支払使用料の計算が正しいかどうか等、多くの必要な業務が考えられるところである。こうした活動をどう評価するのかについても説明が欲しいところである。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.