解説記事2018年06月18日 【法令解説】 経営承継円滑化法施行規則の改正について(2018年6月18日号・№743)
法令解説
経営承継円滑化法施行規則の改正について
中小企業庁 事業環境部財務課 田沢大地
1.事業承継税制改正の背景
人口の高齢化とともに、中小企業経営者の高齢化が進んでいる。1995年には経営者の年齢のピークは47歳だったが、2015年には66歳にまで高齢化した。今後10年間で、平均引退年齢とされる70歳を越える経営者の数は、約245万人にのぼると推計される。中小企業の数が現在約380万者であるところ、実にその約2/3の会社の経営者が引退年齢を迎える計算だ。それにもかかわらず、経営者の約半数が事業承継の準備を終えていない、という調査もある。現状を放置すれば、日本経済の基盤である中小企業の多くが円滑な事業承継を行うことができず、廃業の危機に瀕する恐れがある。
事業承継において経営者が直面する問題は様々だ。会社の経営状態を改善することはもちろん、状況によってはM&Aを検討することもあるだろう。一方、親族内承継を検討する企業における、「事業承継を行う上での課題」についてのアンケート調査によると、「借入金・債務保証の引継ぎ」や「将来の経営不安」をおさえ、「自社株式に係る相続税、贈与税の負担」が一番の課題として挙げられた。こうした事業承継の際の税負担の軽減のため、平成21年より「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度」(以下「事業承継税制」という)が創設され、数度の改正を行ってきたところであるが、認定件数は年間400~500件にとどまっていた。
円滑な事業承継を強力に後押しし、大事業承継時代を乗り切るため、平成30年度税制改正において、10年間限定の事業承継税制の抜本的拡充が行われた。租税特別措置法とともに、税制適用の前提となる認定の要件を定める中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の改正が行われ、本年4月1日より新制度がスタートしている。本稿では、大きく改正された円滑化法施行規則の主なポイントについて解説を行う。
2.制度全体の改正ポイント
まず、今回の事業承継税制の抜本拡充について、全体像を確認しよう。今回の改正のポイントは、以下の5点である。
① 2027年12月までの10年間限定の特例措置であり、特例措置の適用を受けるためには2023年3月までの5年間に特例承継計画を提出することが必要。
② 議決権総数の2/3までという上限が撤廃され、さらに、相続税の納税猶予割合が80%から100%となり、議決権株式等に係る贈与税・相続税の全額が納税猶予の対象となった。
③ これまでは先代経営者から後継者の一対一の関係における贈与・相続のみが対象となっていたが、親族外を含むすべての株主から、複数後継者(最大3人まで)の承継が対象になった。後継者については、代表権を有している必要(※)があるので注意してほしい。
(※)贈与税の納税猶予の場合、当該贈与時点で代表権を有している必要がある。相続税の納税猶予の場合、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日時点で代表権を有している必要がある。
④ 認定後、5年間平均で雇用の8割を維持しなければならない雇用要件を見直し、雇用が8割を下回っても、その理由について報告を行えば猶予継続が可能になった。ただし、その理由が経営悪化等の場合には、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要がある。
⑤ 廃業時・売却時に、株式の評価額・売却額が事業承継時に比べて下落している場合は、その評価額・売却額に基づいて税額を再計算し、贈与・相続時の税額との差額を免除できるようになった。
次節以降では、事業承継税制適用の前提となる認定の要件等を定める、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という)について解説を行う。
3.特例承継計画について
事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年の間に、都道府県に特例承継計画(様式第21)を提出する必要がある。特例措置は10年間限定であるので、5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内(2027年12月31日まで)に実際に株式の承継を行った事業者が特例の認定の対象となる。特例承継計画を提出しても事業承継が義務づけられるわけではないので、この10年の間に事業承継を行う可能性が少しでもある場合は、作成・提出をおすすめしたい。
特例承継計画には「1.会社について」「2.特例代表者について」「3.特例後継者について」「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」を記載する。それぞれの項目について確認しよう。
まず、「1.会社について」だが、こちらには事業内容、資本金の額、従業員数といった会社の基本情報を記載する。事業承継税制の認定要件の中には「資産保有型会社ではないこと」等の要件があるが、これらの要件を満たしていなくても特例承継計画の提出は可能であり、実際に事業承継税制の認定の申請を行う段階で必要な要件を満たしていればよい。ただし、特例承継計画の提出の際に中小企業者であることが必要だ。
「2.特例代表者について」「3.特例後継者について」では、株式を承継する予定の先代経営者と、後継者の氏名を記載する。先代経営者は、現に代表権を有している者又は過去に代表権を有していた者を記載する。特例後継者については、3人まで記載可能だ。ただし、特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできない。そのため、後継者の変更や追加があった場合は、後述の変更申請書による変更手続きを行う必要がある。今回の改正で複数人からの贈与・相続を認定することが可能になったため、後継者ごとに贈与者・被相続人や承継のタイミングが異なる場合もある。その場合の取扱については、第7節で詳しく解説する。
「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」では、株式を承継する予定の時期、当該時期までの経営上の課題、当該課題への対処方針について記載する。株式等の贈与後・相続後に本計画を作成する場合(後述)や、すでに先代経営者が役員を退任している場合には記載不要だ。なお、当該会社がいわゆる持株会社である場合には、その子会社等における取組を記載することになる。
「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」では、特例後継者が実際に事業承継を行った後の5年間でどのような経営を行っていく予定かについて、具体的な取組内容を記載する。この事業計画は必ずしも設備投資・新事業展開や、売上目標・利益目標についての記載を求めるものではなく、後継者が事業の持続・発展に必要と考える内容を自由に記載して構わない。なお、すでに後継者が代表権を有している場合であっても、株式等の取得により経営権が安定したあとの取組について記載する。また、当該会社がいわゆる持株会社である場合には、4と同様に、その子会社等における取組を記載する。
「(別紙)認定経営革新等支援機関による所見等」については、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という)が記載することになる。認定支援機関の名称等、基本的な情報に加え、指導及び助言を行った年月日、指導及び助言の内容を記載する。事業者の所在する都道府県内の認定支援機関である必要はなく、どの認定支援機関でも指導及び助言を行うことができる。認定支援機関では、事業者の記載した「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」及び「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画について」について、なぜその取組を行うのか、その取組の結果、どのような効果が期待されるかが記載されているかを確認する。「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」においては、必ずしも各年の取組すべてが新しい取組である必要はないが、各年において取組が記載されていることが必要だ。中小企業庁ホームページで公開している記載例を参考に、可能な限り具体的に記載することが望ましい。
なお、計画作成の数年後に株式の承継を行うことを予定しているなど、この計画の作成段階では承継後の具体的な経営計画を記載することが困難である場合には、大まかな記載にとどめ、実際に株式を承継しようとする前に具体的な計画を定めることも可能だ。その場合には、特例承継計画の変更手続を行うことが求められる。
特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更があった場合は、変更申請書(様式第24)を都道府県に提出し確認を受けることができる。変更申請書には、変更事項を反映した計画を記載し、再度認定支援機関による指導及び助言を受けることが必要だ。
計画の作成や変更にあたっては、以下の点にご注意いただきたい。
・ 特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、当該特例後継者を変更することはできない。ただし、特例後継者を二人又は三人記載した場合であって、まだ株の贈与・相続を受けていない者がいる場合は、当該特例後継者に限って変更することが可能だ。当初の計画に記載した特例後継者が三人未満だった場合、追加も可能である。例えば、当初の計画では特例後継者にA,Bの二名を記載していたが、Aへ株式の承継を行った後に特例後継者BをCに変更したり、A,Bへの承継後にさらに三人目の特例後継者Cを追加することもできる。
・事業承継後5年間の事業計画を変更した場合(より詳細な計画を策定する場合を含む)も、計画の変更の手続きを行うことができる。特に、当初の特例承継計画においては具体的な経営計画が記載されてなかった場合は、認定支援機関の指導及び助言を受けた上で、それを具体化するための計画の変更の手続を行うことが求められる。
特例承継計画を都道府県に提出できる期間は、2018年4月1日から2023年3月31日の5年間だ(ただし、一度提出した計画の変更はそれ以降でも可能)。事業承継の計画であるため、特例承継計画の提出のタイミングは原則株式の承継を行う前になるが、計画を作成する前に先代経営者の相続等が発生してしまうことも考えられる。そのため、前述したとおり計画には株式を承継した後5年間の事業計画についても記載を求めていることも踏まえ、贈与・相続問わず株式の承継が行われた後でも、遅くとも事業承継税制の認定の申請の際に併せて計画を提出すれば、特例の認定を受けることができるようになっている。
4.認定の類型について
今般の改正により、複数株主から複数後継者への株式の承継が認定の対象となり、対象者が大きく拡充された。また、制度上これまでの事業承継税制(以下「一般措置」という)は存置され、今般の特例措置が10年間限定で併走することになった。それに伴い、これまで「特別贈与認定中小企業者」、「特別相続認定中小企業者」の2種類であった認定の類型が8種類に増えている。改正後の施行規則では、一般措置による認定の類型が「第一種特別贈与認定中小企業者」、「第一種特別相続認定中小企業者」、「第二種特別贈与認定中小企業者」、「第二種特別相続認定中小企業者」の4種類、特例による認定の類型が「第一種特例贈与認定中小企業者」、「第一種特例相続認定中小企業者」、「第二種特例贈与認定中小企業者」、「第二種特例相続認定中小企業者」の4種類となっている。類型が多く混乱を招いてしまうかもしれないが、名称を分解して解説すると、「第一種」・「第二種」が「先代経営者からの承継か」・「先代経営者以外からの承継か」、「特別」・「特例」が「一般措置を受けるための認定か」・「特例措置を受けるための認定か」、「贈与」・「相続」が「贈与による承継か」・「相続による承継か」を意味している。図表1に認定の類型を、該当する施行規則の条文と、認定申請の際に用いる様式番号とともに整理した。
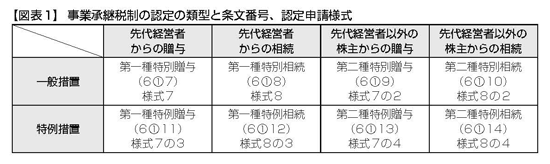
2017年以前の株式の承継について認定を受けた中小企業者は、施行規則の附則により自動的に第一種特別贈与中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者とみなされる。なお、一般措置の認定を受けている場合は当該認定を特例措置へ切り替えることはできないが、今般の改正により、一般措置でも先代経営者以外の株主からの贈与・相続について第二種認定を受けることができるようになった。
複数株主からの承継や、複数後継者への承継を行う場合は、認定に必要な要件を満たしているかをそれぞれ確認する必要があるため、申請書は贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)ごとに作成し、認定書もそれぞれ別個に交付される。例えば、先代Xから後継者A,Bに株式を贈与、その後先代の配偶者Yから後継者A,Cに株式を相続する場合は、X-A、X-B、Y-A、Y-Cのそれぞれの関係において申請書を提出し認定を行う。その後の認定の管理も別々になるため、年次報告などもそれぞれ行う必要がある。また、認定を受けた後継者を「第一種特例経営承継受贈者」や「第二種特例経営承継相続人」などと定義しているが、そちらは贈与者・被相続人との関係で定義される。そのため、上記の例でいえば、後継者AはX-Aの関係では第一種特例経営承継受贈者であり、Y-Aの関係では第二種特例経営承継相続人でもある。後継者Bは第一種特例経営承継受贈者、後継者Cは第二種特例経営承継相続人となる(図表2)。
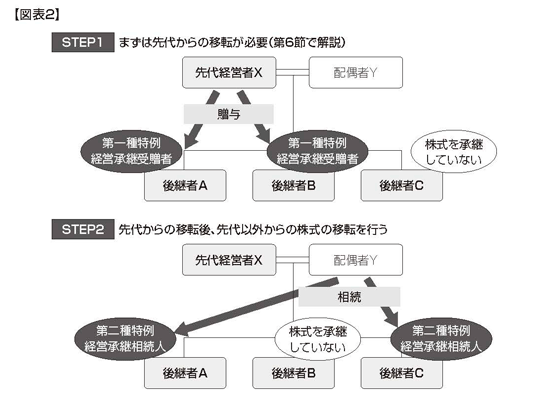
5.認定の要件について
以下、特例措置の適用を受けるための認定を前提に、先代経営者からの贈与・相続に係る認定を「第一種認定」、先代経営者以外からの贈与・相続に係る認定を「第二種認定」として解説を進める。
認定を受けるためには、会社の要件、先代経営者の要件(第二種認定の場合は先代経営者以外の株主の要件)、後継者の要件を満たす必要がある。
会社の要件については、一般措置と特例措置で変更はない。非上場の中小企業者であること、風俗営業会社に該当しないこと、資産管理会社に該当しないこと、常時使用する従業員数が一人以上いること、などが必要だ。黄金株発行会社の場合には、経営の安定の観点から後継者以外が黄金株を保有していないことが必要とされている。
後継者は、前述の通りまず特例承継計画に氏名を記載された者でなければならない。その他の後継者の要件については、基本的には一般措置と変更はない。贈与時(相続開始時)において同族で総議決権数の過半数を保有していること、代表者になっていること(相続の場合には、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日時点で代表権を有していること)、承継した株を継続して保有していること、贈与の場合は役員に就任してから3年以上経過していること、といった要件を満たす必要がある。受贈者・相続人が一人の場合は、一般措置と同様に、当該贈与後・相続開始後において同族関係者の中で筆頭株主になる必要があるが、受贈者・被相続人が複数いる場合は、それぞれが贈与後・相続開始後において10%以上の議決権を有し、同族関係者の中で上位2位(後継者二人の場合)又は上位3位(後継者三人の場合)となることが必要だ。また、その会社の株式について一般措置の適用を受けている場合は、特例の適用を受けることはできない。
後継者要件の判定において注意すべき点を紹介する。まず、同族過半数要件については、後継者ごとに判断される。例えば後継者A,Bの二人が受贈者である場合、後継者Aとその同族関係者で同族過半数を満たしている場合でも、後継者Bとその同族関係者で同族過半数を満たさない場合、後継者Bについては認定を受けることができない。次に、後継者の人数については、当該贈与・相続の時点で判断する。特例承継計画に特例後継者がA,B,Cの三人記載されていたとしても、先代Xから後継者Aに贈与、Xの配偶者Yから後継者Bに贈与、さらに伯父Zから後継者B,Cに贈与した場合は、X-A、Y-Bの贈与については後継者一人、Z-B,Cの贈与は後継者二人への贈与として要件を確認する。なお、贈与後・相続開始後の筆頭株主要件(複数の後継者への承継の場合は、それぞれ10%以上で、同族内で上位2位(後継者二人の場合)又は上位3位(後継者三人の場合)以内となっていること)については、直接保有している議決権数で判定し、間接保有分は含まれないので注意が必要だ。例えば後継者一人の場合、後継者が40%の株式を保有し、後継者が100%株式を保有する会社が60%の株式を保有するような場合は、筆頭株主は後継者ではなくその会社となってしまい、筆頭要件を満たさない(なお、先代経営者の要件においても述べるとおり、先代経営者の筆頭要件も同様に直接保有で判定する)。複数後継者への承継の場合も同様で、後継者A,B,Cの三人に贈与した場合、株主順位が1位:A、2位:B、3位:同族会社D、4位:C、となっていると、D社の株式を100%Cが保有していたとしても、Cが直接保有する株式だけで数えると4位のためCは認定の対象にならない。
次に、先代経営者の要件である。特例承継計画に氏名を記載された者であることを前提に、一般措置と同様、会社の代表者であったこと、つまり、贈与時には代表者を退任していること、先代経営者とその同族関係者で総議決権数の過半数を有し、その中で後継者を除いて筆頭株主であったこと(直接保有する株式に係る議決権数で判定)、一定数以上の株式を贈与すること、などが必要である。既に事業承継税制に係る贈与をしている場合は、二度目の認定を受けることはできない。例えば同一人物から後継者一人に対して複数年に分けて贈与をしたり、長男に贈与をした後、別の年に次男にも贈与を行った場合などには、どちらかの贈与についてしか認定を受けられないので注意が必要である。
最後に、先代経営者以外の株主から贈与・相続を行う場合の要件についてである。先代経営者以外の株主ということで、先代経営者の要件にあった、代表者を経験していたことや同族関係者で総議決権数の過半数を保有、といった要件はない。第二種贈与・相続のポイントとして、先代経営者からの贈与又は相続以後に、贈与を行う又は相続が発生することが必要である。すなわち、必ず第一種贈与・相続が先に発生した後、第二種贈与・相続を行わなければならず、先代経営者から株式を承継する前に、その配偶者などから株式の承継を行った場合、その贈与・相続については認定の対象とはならない。加えて、第二種贈与・相続は、先代経営者からの贈与・相続に係る認定の有効期間内に申告期限の到来する贈与・相続である必要がある。認定のタイミングや有効期間については次節で詳しく解説する。
なお、親族外の第三者からの贈与も対象になるが、その贈与者が死亡し相続が発生した際、税法上は当該株式を相続によって取得したものとみなすこととされている(租税特別措置法第70条の7の7)ため、推定相続人ではない後継者もその贈与者の相続税申告をしなければならないことに注意が必要だ。
6.認定の有効期間や報告について
認定を受けた中小企業者は、贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年間の有効期間中、毎年年次報告を行わなければならない。また、特例措置において雇用要件は弾力化されたものの、雇用が5年間の平均で事業承継時の8割を下回った場合は、その理由について報告を行う必要がある(第8節で解説)。今般の改正による対象者の拡大により、一人の後継者が複数のタイミングで株式を承継したり、複数の後継者が別々のタイミングで株式を承継するケースが発生することになるが、本節ではそうした場合の報告基準期間・従業員数確認期間について、場合分けをしながら具体的に解説する。基本的な考え方は、当該受贈者・相続人が最初に事業承継税制の適用を受けた際の有効期間を基準にする、というものである。
まずは、第二種贈与・相続の対象期間について確認しよう。先代経営者以外の株主からの承継については、「第一種贈与の日・相続開始の日(=先代経営者からの贈与の日・相続開始の日)」から「第一種認定の有効期間の末日までに申告期限が到来する贈与・相続」が認定の対象となる。例えば、2018年4月1日に先代から贈与(第一種特例経営承継贈与)があった場合に、対象となる先代以外からの贈与・相続(第二種特例経営承継贈与・相続)は、2018年4月1日から2023年12月31日までに行われた贈与、又は2018年4月1日から2023年5月15日までに発生した相続となる(図表3)。
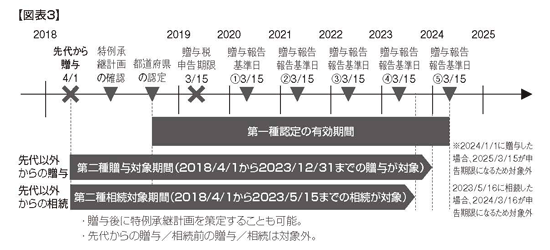
それでは、後継者が一人で、複数の株主から別々のタイミングで株式を承継し認定を受けるケースを検討する。2018年4月1日に先代経営者Xが後継者Aに株式を贈与し第一種認定を受け、3年後にXの配偶者YからAに株式を相続した場合を考えてみよう。この場合、Yからの相続に係る第二種認定の報告基準期間・従業員数確認期間は、Xからの贈与に係る第一種認定の報告基準期間・従業員数確認期間と合わせることになる。すなわち、第二種認定の年次報告は第一種認定の年次報告と併せて行い、第二種認定の有効期限は第一種認定の有効期間の末日と同日になる(=第二種認定の年次報告は5回ではなく、第一種認定の残りの報告回数である2回で終了する)。従業員数の確認についても、第一種贈与に係る申告期限から5年間における雇用人数を基に行う(図表4)。
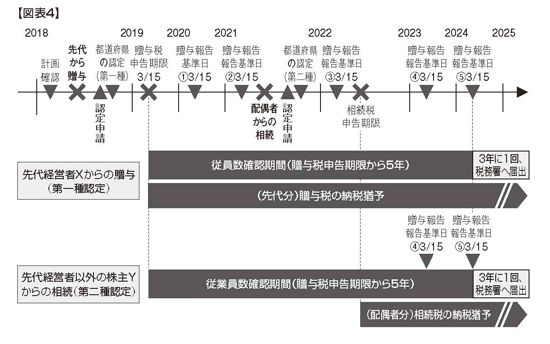
次に、後継者が複数で、複数の株主から別々のタイミングで株式を承継するケースを検討する。特例後継者としてA,B,Cの3名が記載されている状態で、先代経営者XからAが株式を贈与され第一種認定を受けた後、先代経営者の配偶者YからB,Cに株式を相続して第二種認定を受けるケースを考えてみよう。この場合、AとB,Cで最初に事業承継税制の認定を受けたタイミングが異なるため、AとB,Cで報告基準期間・従業員数確認期間が異なる。Aの認定に係る報告基準期間や従業員数確認期間については、Xからの贈与に係る申告期限を基準に5年間、B,Cの認定に係る期間は、Yからの相続に係る申告期限を基準に5年間となる(図表5)。なお、今回のケースに重ねて、さらに他の株主ZからA,B,Cのいずれかに株式の承継があった場合は、前述の通り当該受贈者・相続人にとっての最初の認定に係る報告基準期間・従業員数確認期間(AであればXからの贈与に係る認定、B,CであればYからの相続に係る認定に係る期間)と合わせて報告や雇用判定を行う。
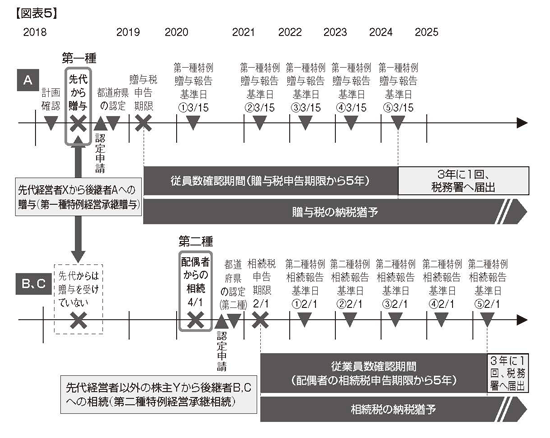
7.臨時報告・切替確認及び随時報告について
贈与認定に係る株式等の贈与者の相続が開始した場合において、相続税の納税猶予の適用を受けるためには切替確認の手続きが必要になる。また、贈与税申告期限の翌日から5年の間に贈与者の相続が開始した場合にあっては、臨時報告書を併せて提出しなければならない。臨時報告と切替確認については、贈与者ごとに手続きが必要だ。先代経営者Xが後継者A,Bに、Xの配偶者Yが後継者Bのみに株式を贈与し認定を受けているケースでは、Xに相続が発生した場合はXから贈与を受けたA,Bがそれぞれ手続きをする。Yに相続が発生した場合はYから贈与を受けたBが手続きをすることになる。
認定の取消事由に該当した場合、随時報告を行う必要があるが、こちらも受贈者・相続人ごとに手続きが必要だ。上記のケースにおいて、Xが代表者に復帰した場合取消事由に該当するが、その場合はA,Bがそれぞれ手続きを行う。有効期間中の株式の譲渡も取消事由となっているが、こちらは先入れ先出しで判定を行う。XがBに30株贈与した後、さらにYがBに20株贈与しているケースを考えてみよう。Bが40株を売却した場合、先入れ先出しにより、Xからの30株とYからの10株を売却したことになるため、第一種認定、第二種認定ともに取消となる。一方、Bが20株を売却した場合は、Xからの30株のうち20株のみを売却しYからの20株は保有し続けていることになるため、第一種認定は取消だが第二種認定は継続できる。どちらのケースも、Aの認定には影響はない。
8.従業員数が5年間平均で8割を下回った場合の報告について
最後に、今回の改正の大きなポイントの一つである、雇用要件の抜本的な見直しについて解説する。一般措置の認定では、従業員数が5年間の平均で認定時の8割を下回った場合には猶予打ち切りとなっていたが、改正後は8割を下回っても、その理由について報告を行い、当該理由が経営悪化又は正当でない理由と認められるときは、認定支援機関の指導及び助言を受ければ、猶予を継続できることになった。
従業員数が減少した場合の雇用実績報告は、5年間の有効期間後に行い、様式第27を利用する。報告書には、5年間の各報告基準日の従業員数とその平均人数を記載し、従業員数が8割を下回った理由について、「①高齢化が進み後を引き継ぐ者を確保できなかった」「②採用活動を行ったが、人手不足から採用に至らなかった」「③設備投資等、生産性が向上したため人手が不要となった」「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」「⑤その他(具体的に理由を記載)」といった選択肢から該当するものを事業者が選択する。
併せて、特例承継計画と同様に、認定支援機関による所見の記載が必要になる。さらに、雇用が減少した理由について「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」を選択した場合か、「⑤その他」を選択しその具体的理由が認定支援機関として正当でないと判断する場合は、認定支援機関が指導及び助言を行いその内容を記載しなければならない。認定支援機関では雇用が減少した理由について、その理由が事実であるかどうか状況を確認し、まずは所見を記載することになる。チェックポイントとして、「①高齢化が進み後を引き継ぐ者を確保できなかった」を選択した場合は退職理由の確認(高齢化によるものであるかどうか)、「②採用活動を行ったが、人手不足から採用に至らなかった」の場合は過去の求人状況(人材紹介会社やハローワーク等での求人、自社広告等)、「③設備投資等、生産性が向上したため人手が不要となった」の場合は会社の設備投資や生産性向上の状況、などを確認する。「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」を選択した場合は経営悪化の理由についての確認にくわえ、当該事業者が事業を継続していくための経営改善等に関する指導及び助言を行い、その内容を「4.指導及び助言の内容」の欄に記載する。「⑤その他(具体的に理由を記載)」の場合は、雇用減少の主たる原因が当該具体的理由であるかどうかを確認し、具体的理由が認定支援機関として正当でないと判断する場合には、その理由を記載した上で、事業継続のために必要な指導及び助言を行い、その内容を「4.指導及び助言の内容」の欄に記載する。
実績報告書については、特例承継計画と同様、中小企業庁のホームページでマニュアルを公表しているので、ご覧いただきたい。
9.おわりに
本稿では、円滑化法施行規則の主要な改正のポイントについて解説した。特例の認定に当たっては、特例承継計画の確認や、複数人から複数人への承継など従前の事業承継税制と手続きが異なる部分が多いため、十分に注意されたい。なお、円滑化法施行規則は納税猶予の前提となる円滑化法認定の要件を定めるものであるため、今回の事業承継税制抜本拡充の目玉である将来の売却・廃業時の差額免除など、税務上の取扱については、別途租税特別措置法の条文を確認されたい。
中小企業庁としては、この特例措置が早期・計画的な事業承継の促進に少しでもつながることを期待したい。税理士の皆様等、日頃中小企業を支える支援機関においては、ぜひこの「10年間限定の特例措置」を、事業承継に向けた経営者との対話の一つのきっかけとしていただければ幸いである。
経営承継円滑化法施行規則の改正について
中小企業庁 事業環境部財務課 田沢大地
1.事業承継税制改正の背景
人口の高齢化とともに、中小企業経営者の高齢化が進んでいる。1995年には経営者の年齢のピークは47歳だったが、2015年には66歳にまで高齢化した。今後10年間で、平均引退年齢とされる70歳を越える経営者の数は、約245万人にのぼると推計される。中小企業の数が現在約380万者であるところ、実にその約2/3の会社の経営者が引退年齢を迎える計算だ。それにもかかわらず、経営者の約半数が事業承継の準備を終えていない、という調査もある。現状を放置すれば、日本経済の基盤である中小企業の多くが円滑な事業承継を行うことができず、廃業の危機に瀕する恐れがある。
事業承継において経営者が直面する問題は様々だ。会社の経営状態を改善することはもちろん、状況によってはM&Aを検討することもあるだろう。一方、親族内承継を検討する企業における、「事業承継を行う上での課題」についてのアンケート調査によると、「借入金・債務保証の引継ぎ」や「将来の経営不安」をおさえ、「自社株式に係る相続税、贈与税の負担」が一番の課題として挙げられた。こうした事業承継の際の税負担の軽減のため、平成21年より「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度」(以下「事業承継税制」という)が創設され、数度の改正を行ってきたところであるが、認定件数は年間400~500件にとどまっていた。
円滑な事業承継を強力に後押しし、大事業承継時代を乗り切るため、平成30年度税制改正において、10年間限定の事業承継税制の抜本的拡充が行われた。租税特別措置法とともに、税制適用の前提となる認定の要件を定める中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の改正が行われ、本年4月1日より新制度がスタートしている。本稿では、大きく改正された円滑化法施行規則の主なポイントについて解説を行う。
2.制度全体の改正ポイント
まず、今回の事業承継税制の抜本拡充について、全体像を確認しよう。今回の改正のポイントは、以下の5点である。
① 2027年12月までの10年間限定の特例措置であり、特例措置の適用を受けるためには2023年3月までの5年間に特例承継計画を提出することが必要。
② 議決権総数の2/3までという上限が撤廃され、さらに、相続税の納税猶予割合が80%から100%となり、議決権株式等に係る贈与税・相続税の全額が納税猶予の対象となった。
③ これまでは先代経営者から後継者の一対一の関係における贈与・相続のみが対象となっていたが、親族外を含むすべての株主から、複数後継者(最大3人まで)の承継が対象になった。後継者については、代表権を有している必要(※)があるので注意してほしい。
(※)贈与税の納税猶予の場合、当該贈与時点で代表権を有している必要がある。相続税の納税猶予の場合、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日時点で代表権を有している必要がある。
④ 認定後、5年間平均で雇用の8割を維持しなければならない雇用要件を見直し、雇用が8割を下回っても、その理由について報告を行えば猶予継続が可能になった。ただし、その理由が経営悪化等の場合には、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要がある。
⑤ 廃業時・売却時に、株式の評価額・売却額が事業承継時に比べて下落している場合は、その評価額・売却額に基づいて税額を再計算し、贈与・相続時の税額との差額を免除できるようになった。
次節以降では、事業承継税制適用の前提となる認定の要件等を定める、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「施行規則」という)について解説を行う。
3.特例承継計画について
事業承継税制の特例措置の適用を受けるためには、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年の間に、都道府県に特例承継計画(様式第21)を提出する必要がある。特例措置は10年間限定であるので、5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内(2027年12月31日まで)に実際に株式の承継を行った事業者が特例の認定の対象となる。特例承継計画を提出しても事業承継が義務づけられるわけではないので、この10年の間に事業承継を行う可能性が少しでもある場合は、作成・提出をおすすめしたい。
特例承継計画には「1.会社について」「2.特例代表者について」「3.特例後継者について」「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」を記載する。それぞれの項目について確認しよう。
まず、「1.会社について」だが、こちらには事業内容、資本金の額、従業員数といった会社の基本情報を記載する。事業承継税制の認定要件の中には「資産保有型会社ではないこと」等の要件があるが、これらの要件を満たしていなくても特例承継計画の提出は可能であり、実際に事業承継税制の認定の申請を行う段階で必要な要件を満たしていればよい。ただし、特例承継計画の提出の際に中小企業者であることが必要だ。
「2.特例代表者について」「3.特例後継者について」では、株式を承継する予定の先代経営者と、後継者の氏名を記載する。先代経営者は、現に代表権を有している者又は過去に代表権を有していた者を記載する。特例後継者については、3人まで記載可能だ。ただし、特例後継者として氏名を記載された者でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできない。そのため、後継者の変更や追加があった場合は、後述の変更申請書による変更手続きを行う必要がある。今回の改正で複数人からの贈与・相続を認定することが可能になったため、後継者ごとに贈与者・被相続人や承継のタイミングが異なる場合もある。その場合の取扱については、第7節で詳しく解説する。
「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」では、株式を承継する予定の時期、当該時期までの経営上の課題、当該課題への対処方針について記載する。株式等の贈与後・相続後に本計画を作成する場合(後述)や、すでに先代経営者が役員を退任している場合には記載不要だ。なお、当該会社がいわゆる持株会社である場合には、その子会社等における取組を記載することになる。
「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」では、特例後継者が実際に事業承継を行った後の5年間でどのような経営を行っていく予定かについて、具体的な取組内容を記載する。この事業計画は必ずしも設備投資・新事業展開や、売上目標・利益目標についての記載を求めるものではなく、後継者が事業の持続・発展に必要と考える内容を自由に記載して構わない。なお、すでに後継者が代表権を有している場合であっても、株式等の取得により経営権が安定したあとの取組について記載する。また、当該会社がいわゆる持株会社である場合には、4と同様に、その子会社等における取組を記載する。
「(別紙)認定経営革新等支援機関による所見等」については、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という)が記載することになる。認定支援機関の名称等、基本的な情報に加え、指導及び助言を行った年月日、指導及び助言の内容を記載する。事業者の所在する都道府県内の認定支援機関である必要はなく、どの認定支援機関でも指導及び助言を行うことができる。認定支援機関では、事業者の記載した「4.特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について」及び「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画について」について、なぜその取組を行うのか、その取組の結果、どのような効果が期待されるかが記載されているかを確認する。「5.特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」においては、必ずしも各年の取組すべてが新しい取組である必要はないが、各年において取組が記載されていることが必要だ。中小企業庁ホームページで公開している記載例を参考に、可能な限り具体的に記載することが望ましい。
なお、計画作成の数年後に株式の承継を行うことを予定しているなど、この計画の作成段階では承継後の具体的な経営計画を記載することが困難である場合には、大まかな記載にとどめ、実際に株式を承継しようとする前に具体的な計画を定めることも可能だ。その場合には、特例承継計画の変更手続を行うことが求められる。
特例承継計画の確認を受けた後に、計画の内容に変更があった場合は、変更申請書(様式第24)を都道府県に提出し確認を受けることができる。変更申請書には、変更事項を反映した計画を記載し、再度認定支援機関による指導及び助言を受けることが必要だ。
計画の作成や変更にあたっては、以下の点にご注意いただきたい。
・ 特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、当該特例後継者を変更することはできない。ただし、特例後継者を二人又は三人記載した場合であって、まだ株の贈与・相続を受けていない者がいる場合は、当該特例後継者に限って変更することが可能だ。当初の計画に記載した特例後継者が三人未満だった場合、追加も可能である。例えば、当初の計画では特例後継者にA,Bの二名を記載していたが、Aへ株式の承継を行った後に特例後継者BをCに変更したり、A,Bへの承継後にさらに三人目の特例後継者Cを追加することもできる。
・事業承継後5年間の事業計画を変更した場合(より詳細な計画を策定する場合を含む)も、計画の変更の手続きを行うことができる。特に、当初の特例承継計画においては具体的な経営計画が記載されてなかった場合は、認定支援機関の指導及び助言を受けた上で、それを具体化するための計画の変更の手続を行うことが求められる。
特例承継計画を都道府県に提出できる期間は、2018年4月1日から2023年3月31日の5年間だ(ただし、一度提出した計画の変更はそれ以降でも可能)。事業承継の計画であるため、特例承継計画の提出のタイミングは原則株式の承継を行う前になるが、計画を作成する前に先代経営者の相続等が発生してしまうことも考えられる。そのため、前述したとおり計画には株式を承継した後5年間の事業計画についても記載を求めていることも踏まえ、贈与・相続問わず株式の承継が行われた後でも、遅くとも事業承継税制の認定の申請の際に併せて計画を提出すれば、特例の認定を受けることができるようになっている。
4.認定の類型について
今般の改正により、複数株主から複数後継者への株式の承継が認定の対象となり、対象者が大きく拡充された。また、制度上これまでの事業承継税制(以下「一般措置」という)は存置され、今般の特例措置が10年間限定で併走することになった。それに伴い、これまで「特別贈与認定中小企業者」、「特別相続認定中小企業者」の2種類であった認定の類型が8種類に増えている。改正後の施行規則では、一般措置による認定の類型が「第一種特別贈与認定中小企業者」、「第一種特別相続認定中小企業者」、「第二種特別贈与認定中小企業者」、「第二種特別相続認定中小企業者」の4種類、特例による認定の類型が「第一種特例贈与認定中小企業者」、「第一種特例相続認定中小企業者」、「第二種特例贈与認定中小企業者」、「第二種特例相続認定中小企業者」の4種類となっている。類型が多く混乱を招いてしまうかもしれないが、名称を分解して解説すると、「第一種」・「第二種」が「先代経営者からの承継か」・「先代経営者以外からの承継か」、「特別」・「特例」が「一般措置を受けるための認定か」・「特例措置を受けるための認定か」、「贈与」・「相続」が「贈与による承継か」・「相続による承継か」を意味している。図表1に認定の類型を、該当する施行規則の条文と、認定申請の際に用いる様式番号とともに整理した。
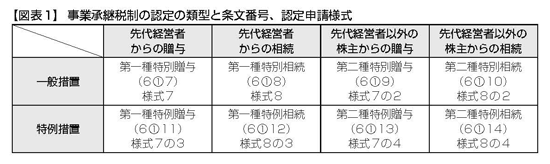
2017年以前の株式の承継について認定を受けた中小企業者は、施行規則の附則により自動的に第一種特別贈与中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者とみなされる。なお、一般措置の認定を受けている場合は当該認定を特例措置へ切り替えることはできないが、今般の改正により、一般措置でも先代経営者以外の株主からの贈与・相続について第二種認定を受けることができるようになった。
複数株主からの承継や、複数後継者への承継を行う場合は、認定に必要な要件を満たしているかをそれぞれ確認する必要があるため、申請書は贈与者(被相続人)と受贈者(相続人)ごとに作成し、認定書もそれぞれ別個に交付される。例えば、先代Xから後継者A,Bに株式を贈与、その後先代の配偶者Yから後継者A,Cに株式を相続する場合は、X-A、X-B、Y-A、Y-Cのそれぞれの関係において申請書を提出し認定を行う。その後の認定の管理も別々になるため、年次報告などもそれぞれ行う必要がある。また、認定を受けた後継者を「第一種特例経営承継受贈者」や「第二種特例経営承継相続人」などと定義しているが、そちらは贈与者・被相続人との関係で定義される。そのため、上記の例でいえば、後継者AはX-Aの関係では第一種特例経営承継受贈者であり、Y-Aの関係では第二種特例経営承継相続人でもある。後継者Bは第一種特例経営承継受贈者、後継者Cは第二種特例経営承継相続人となる(図表2)。
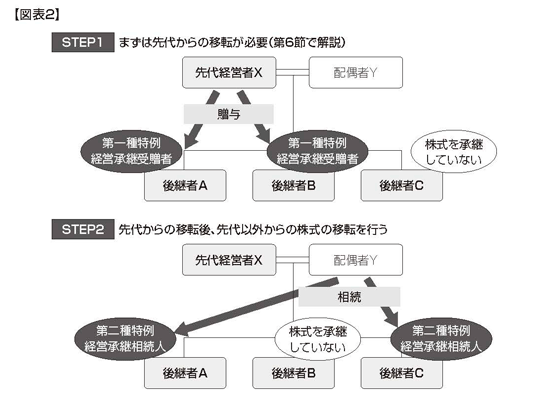
5.認定の要件について
以下、特例措置の適用を受けるための認定を前提に、先代経営者からの贈与・相続に係る認定を「第一種認定」、先代経営者以外からの贈与・相続に係る認定を「第二種認定」として解説を進める。
認定を受けるためには、会社の要件、先代経営者の要件(第二種認定の場合は先代経営者以外の株主の要件)、後継者の要件を満たす必要がある。
会社の要件については、一般措置と特例措置で変更はない。非上場の中小企業者であること、風俗営業会社に該当しないこと、資産管理会社に該当しないこと、常時使用する従業員数が一人以上いること、などが必要だ。黄金株発行会社の場合には、経営の安定の観点から後継者以外が黄金株を保有していないことが必要とされている。
後継者は、前述の通りまず特例承継計画に氏名を記載された者でなければならない。その他の後継者の要件については、基本的には一般措置と変更はない。贈与時(相続開始時)において同族で総議決権数の過半数を保有していること、代表者になっていること(相続の場合には、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日時点で代表権を有していること)、承継した株を継続して保有していること、贈与の場合は役員に就任してから3年以上経過していること、といった要件を満たす必要がある。受贈者・相続人が一人の場合は、一般措置と同様に、当該贈与後・相続開始後において同族関係者の中で筆頭株主になる必要があるが、受贈者・被相続人が複数いる場合は、それぞれが贈与後・相続開始後において10%以上の議決権を有し、同族関係者の中で上位2位(後継者二人の場合)又は上位3位(後継者三人の場合)となることが必要だ。また、その会社の株式について一般措置の適用を受けている場合は、特例の適用を受けることはできない。
後継者要件の判定において注意すべき点を紹介する。まず、同族過半数要件については、後継者ごとに判断される。例えば後継者A,Bの二人が受贈者である場合、後継者Aとその同族関係者で同族過半数を満たしている場合でも、後継者Bとその同族関係者で同族過半数を満たさない場合、後継者Bについては認定を受けることができない。次に、後継者の人数については、当該贈与・相続の時点で判断する。特例承継計画に特例後継者がA,B,Cの三人記載されていたとしても、先代Xから後継者Aに贈与、Xの配偶者Yから後継者Bに贈与、さらに伯父Zから後継者B,Cに贈与した場合は、X-A、Y-Bの贈与については後継者一人、Z-B,Cの贈与は後継者二人への贈与として要件を確認する。なお、贈与後・相続開始後の筆頭株主要件(複数の後継者への承継の場合は、それぞれ10%以上で、同族内で上位2位(後継者二人の場合)又は上位3位(後継者三人の場合)以内となっていること)については、直接保有している議決権数で判定し、間接保有分は含まれないので注意が必要だ。例えば後継者一人の場合、後継者が40%の株式を保有し、後継者が100%株式を保有する会社が60%の株式を保有するような場合は、筆頭株主は後継者ではなくその会社となってしまい、筆頭要件を満たさない(なお、先代経営者の要件においても述べるとおり、先代経営者の筆頭要件も同様に直接保有で判定する)。複数後継者への承継の場合も同様で、後継者A,B,Cの三人に贈与した場合、株主順位が1位:A、2位:B、3位:同族会社D、4位:C、となっていると、D社の株式を100%Cが保有していたとしても、Cが直接保有する株式だけで数えると4位のためCは認定の対象にならない。
次に、先代経営者の要件である。特例承継計画に氏名を記載された者であることを前提に、一般措置と同様、会社の代表者であったこと、つまり、贈与時には代表者を退任していること、先代経営者とその同族関係者で総議決権数の過半数を有し、その中で後継者を除いて筆頭株主であったこと(直接保有する株式に係る議決権数で判定)、一定数以上の株式を贈与すること、などが必要である。既に事業承継税制に係る贈与をしている場合は、二度目の認定を受けることはできない。例えば同一人物から後継者一人に対して複数年に分けて贈与をしたり、長男に贈与をした後、別の年に次男にも贈与を行った場合などには、どちらかの贈与についてしか認定を受けられないので注意が必要である。
最後に、先代経営者以外の株主から贈与・相続を行う場合の要件についてである。先代経営者以外の株主ということで、先代経営者の要件にあった、代表者を経験していたことや同族関係者で総議決権数の過半数を保有、といった要件はない。第二種贈与・相続のポイントとして、先代経営者からの贈与又は相続以後に、贈与を行う又は相続が発生することが必要である。すなわち、必ず第一種贈与・相続が先に発生した後、第二種贈与・相続を行わなければならず、先代経営者から株式を承継する前に、その配偶者などから株式の承継を行った場合、その贈与・相続については認定の対象とはならない。加えて、第二種贈与・相続は、先代経営者からの贈与・相続に係る認定の有効期間内に申告期限の到来する贈与・相続である必要がある。認定のタイミングや有効期間については次節で詳しく解説する。
なお、親族外の第三者からの贈与も対象になるが、その贈与者が死亡し相続が発生した際、税法上は当該株式を相続によって取得したものとみなすこととされている(租税特別措置法第70条の7の7)ため、推定相続人ではない後継者もその贈与者の相続税申告をしなければならないことに注意が必要だ。
6.認定の有効期間や報告について
認定を受けた中小企業者は、贈与税・相続税の申告期限の翌日から5年間の有効期間中、毎年年次報告を行わなければならない。また、特例措置において雇用要件は弾力化されたものの、雇用が5年間の平均で事業承継時の8割を下回った場合は、その理由について報告を行う必要がある(第8節で解説)。今般の改正による対象者の拡大により、一人の後継者が複数のタイミングで株式を承継したり、複数の後継者が別々のタイミングで株式を承継するケースが発生することになるが、本節ではそうした場合の報告基準期間・従業員数確認期間について、場合分けをしながら具体的に解説する。基本的な考え方は、当該受贈者・相続人が最初に事業承継税制の適用を受けた際の有効期間を基準にする、というものである。
まずは、第二種贈与・相続の対象期間について確認しよう。先代経営者以外の株主からの承継については、「第一種贈与の日・相続開始の日(=先代経営者からの贈与の日・相続開始の日)」から「第一種認定の有効期間の末日までに申告期限が到来する贈与・相続」が認定の対象となる。例えば、2018年4月1日に先代から贈与(第一種特例経営承継贈与)があった場合に、対象となる先代以外からの贈与・相続(第二種特例経営承継贈与・相続)は、2018年4月1日から2023年12月31日までに行われた贈与、又は2018年4月1日から2023年5月15日までに発生した相続となる(図表3)。
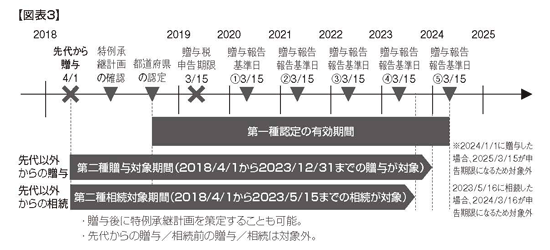
それでは、後継者が一人で、複数の株主から別々のタイミングで株式を承継し認定を受けるケースを検討する。2018年4月1日に先代経営者Xが後継者Aに株式を贈与し第一種認定を受け、3年後にXの配偶者YからAに株式を相続した場合を考えてみよう。この場合、Yからの相続に係る第二種認定の報告基準期間・従業員数確認期間は、Xからの贈与に係る第一種認定の報告基準期間・従業員数確認期間と合わせることになる。すなわち、第二種認定の年次報告は第一種認定の年次報告と併せて行い、第二種認定の有効期限は第一種認定の有効期間の末日と同日になる(=第二種認定の年次報告は5回ではなく、第一種認定の残りの報告回数である2回で終了する)。従業員数の確認についても、第一種贈与に係る申告期限から5年間における雇用人数を基に行う(図表4)。
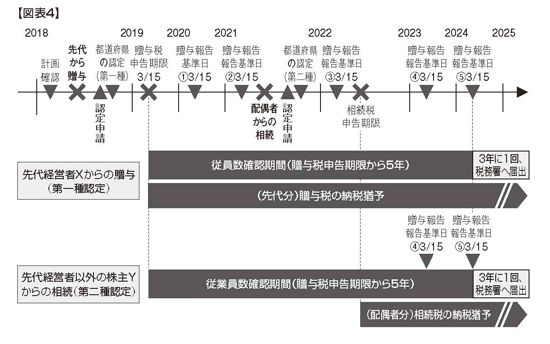
次に、後継者が複数で、複数の株主から別々のタイミングで株式を承継するケースを検討する。特例後継者としてA,B,Cの3名が記載されている状態で、先代経営者XからAが株式を贈与され第一種認定を受けた後、先代経営者の配偶者YからB,Cに株式を相続して第二種認定を受けるケースを考えてみよう。この場合、AとB,Cで最初に事業承継税制の認定を受けたタイミングが異なるため、AとB,Cで報告基準期間・従業員数確認期間が異なる。Aの認定に係る報告基準期間や従業員数確認期間については、Xからの贈与に係る申告期限を基準に5年間、B,Cの認定に係る期間は、Yからの相続に係る申告期限を基準に5年間となる(図表5)。なお、今回のケースに重ねて、さらに他の株主ZからA,B,Cのいずれかに株式の承継があった場合は、前述の通り当該受贈者・相続人にとっての最初の認定に係る報告基準期間・従業員数確認期間(AであればXからの贈与に係る認定、B,CであればYからの相続に係る認定に係る期間)と合わせて報告や雇用判定を行う。
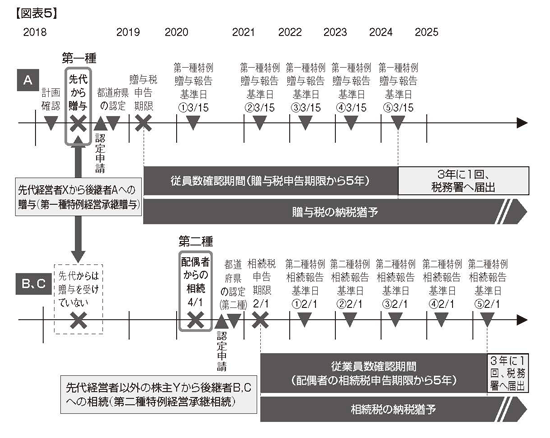
7.臨時報告・切替確認及び随時報告について
贈与認定に係る株式等の贈与者の相続が開始した場合において、相続税の納税猶予の適用を受けるためには切替確認の手続きが必要になる。また、贈与税申告期限の翌日から5年の間に贈与者の相続が開始した場合にあっては、臨時報告書を併せて提出しなければならない。臨時報告と切替確認については、贈与者ごとに手続きが必要だ。先代経営者Xが後継者A,Bに、Xの配偶者Yが後継者Bのみに株式を贈与し認定を受けているケースでは、Xに相続が発生した場合はXから贈与を受けたA,Bがそれぞれ手続きをする。Yに相続が発生した場合はYから贈与を受けたBが手続きをすることになる。
認定の取消事由に該当した場合、随時報告を行う必要があるが、こちらも受贈者・相続人ごとに手続きが必要だ。上記のケースにおいて、Xが代表者に復帰した場合取消事由に該当するが、その場合はA,Bがそれぞれ手続きを行う。有効期間中の株式の譲渡も取消事由となっているが、こちらは先入れ先出しで判定を行う。XがBに30株贈与した後、さらにYがBに20株贈与しているケースを考えてみよう。Bが40株を売却した場合、先入れ先出しにより、Xからの30株とYからの10株を売却したことになるため、第一種認定、第二種認定ともに取消となる。一方、Bが20株を売却した場合は、Xからの30株のうち20株のみを売却しYからの20株は保有し続けていることになるため、第一種認定は取消だが第二種認定は継続できる。どちらのケースも、Aの認定には影響はない。
8.従業員数が5年間平均で8割を下回った場合の報告について
最後に、今回の改正の大きなポイントの一つである、雇用要件の抜本的な見直しについて解説する。一般措置の認定では、従業員数が5年間の平均で認定時の8割を下回った場合には猶予打ち切りとなっていたが、改正後は8割を下回っても、その理由について報告を行い、当該理由が経営悪化又は正当でない理由と認められるときは、認定支援機関の指導及び助言を受ければ、猶予を継続できることになった。
従業員数が減少した場合の雇用実績報告は、5年間の有効期間後に行い、様式第27を利用する。報告書には、5年間の各報告基準日の従業員数とその平均人数を記載し、従業員数が8割を下回った理由について、「①高齢化が進み後を引き継ぐ者を確保できなかった」「②採用活動を行ったが、人手不足から採用に至らなかった」「③設備投資等、生産性が向上したため人手が不要となった」「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」「⑤その他(具体的に理由を記載)」といった選択肢から該当するものを事業者が選択する。
併せて、特例承継計画と同様に、認定支援機関による所見の記載が必要になる。さらに、雇用が減少した理由について「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」を選択した場合か、「⑤その他」を選択しその具体的理由が認定支援機関として正当でないと判断する場合は、認定支援機関が指導及び助言を行いその内容を記載しなければならない。認定支援機関では雇用が減少した理由について、その理由が事実であるかどうか状況を確認し、まずは所見を記載することになる。チェックポイントとして、「①高齢化が進み後を引き継ぐ者を確保できなかった」を選択した場合は退職理由の確認(高齢化によるものであるかどうか)、「②採用活動を行ったが、人手不足から採用に至らなかった」の場合は過去の求人状況(人材紹介会社やハローワーク等での求人、自社広告等)、「③設備投資等、生産性が向上したため人手が不要となった」の場合は会社の設備投資や生産性向上の状況、などを確認する。「④経営状況の悪化により、雇用を継続できなくなった」を選択した場合は経営悪化の理由についての確認にくわえ、当該事業者が事業を継続していくための経営改善等に関する指導及び助言を行い、その内容を「4.指導及び助言の内容」の欄に記載する。「⑤その他(具体的に理由を記載)」の場合は、雇用減少の主たる原因が当該具体的理由であるかどうかを確認し、具体的理由が認定支援機関として正当でないと判断する場合には、その理由を記載した上で、事業継続のために必要な指導及び助言を行い、その内容を「4.指導及び助言の内容」の欄に記載する。
実績報告書については、特例承継計画と同様、中小企業庁のホームページでマニュアルを公表しているので、ご覧いただきたい。
9.おわりに
本稿では、円滑化法施行規則の主要な改正のポイントについて解説した。特例の認定に当たっては、特例承継計画の確認や、複数人から複数人への承継など従前の事業承継税制と手続きが異なる部分が多いため、十分に注意されたい。なお、円滑化法施行規則は納税猶予の前提となる円滑化法認定の要件を定めるものであるため、今回の事業承継税制抜本拡充の目玉である将来の売却・廃業時の差額免除など、税務上の取扱については、別途租税特別措置法の条文を確認されたい。
中小企業庁としては、この特例措置が早期・計画的な事業承継の促進に少しでもつながることを期待したい。税理士の皆様等、日頃中小企業を支える支援機関においては、ぜひこの「10年間限定の特例措置」を、事業承継に向けた経営者との対話の一つのきっかけとしていただければ幸いである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























