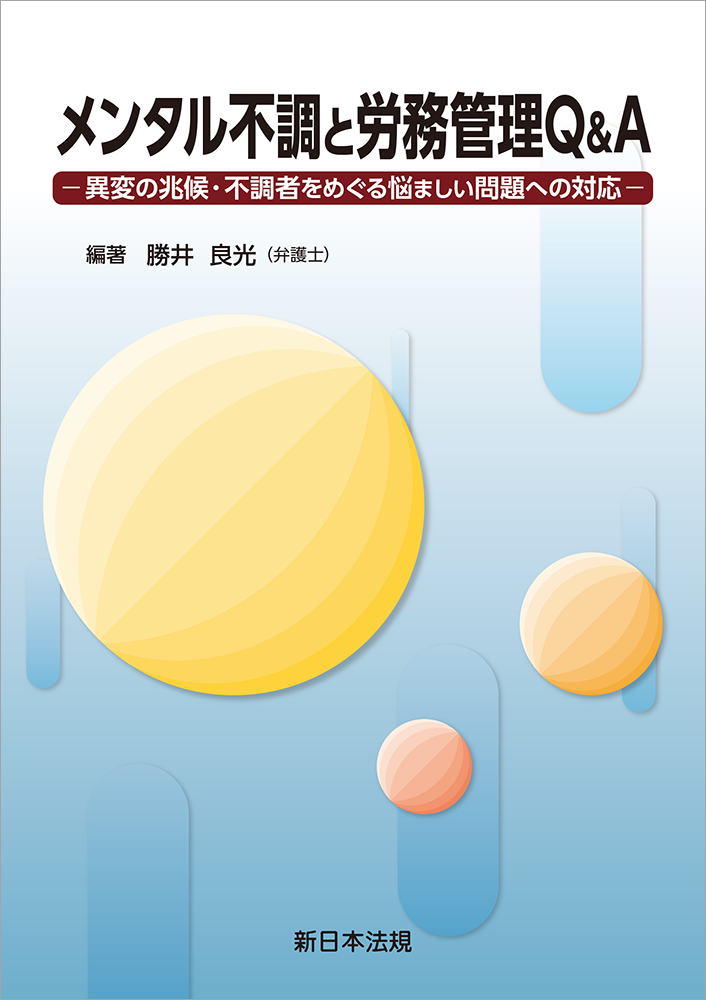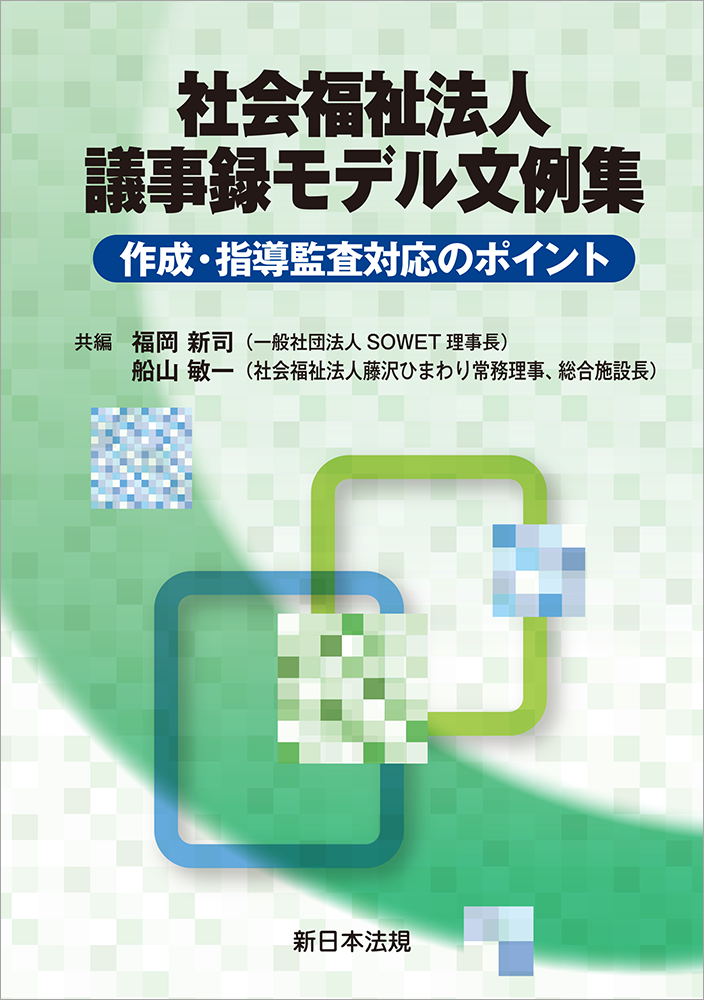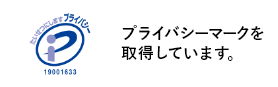解説記事2018年10月15日 【税制改正解説】 平成31年度税制改正に関する経団連の提言について(2018年10月15日号・№759)
税制改正解説
平成31年度税制改正に関する経団連の提言について
一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦
はじめに 経団連では2018年9月18日に、平成31年度税制改正に関する提言を公表した。
平成30年度税制改正では、個人所得課税における給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替や給与所得控除および公的年金等控除、基礎控除の見直し、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税および森林環境税等の創設、法人課税における賃上げ及び投資の促進に係る税制(所得拡大促進税制の改組)や情報連携投資等の促進に係る税制の創設、税務手続の電子化等の推進などの改正がなされた。この点、平成31年度税制改正では、研究開発税制の延長・拡充、消費税率の引き上げに伴う需要平準化の対応、自動車関係諸税の負担軽減・簡素化、中小企業の投資促進に関する税制の延長等が主要な課題などとなる見通しである。
なお、本稿の内容は当方の私見であり、必ずしも組織全体の意見を代表するものではない。
政府の成長戦略等の動向 提言では、「日本経済が、デフレから完全に脱却し、GDP600兆円経済に向け、さらに飛躍するためには、税制や規制等の諸改革により社会全体でイノベーションを起こし、生産性を向上させ、グローバル市場における日本企業の競争力を強化するとともに、経済全体を持続的に発展させていくことが重要である」との認識を示している。
政府の「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)では、2020年までの3年間を生産性革命・集中投資期間とし、大胆な税制、予算、規制改革などあらゆる施策を総動員するとされている。また、「未来投資戦略2018」(2018年6月15日閣議決定)では、「生産性革命」に取り組むとともに、AI、ビッグデータ、IoTなどの技術革新によって、「Society 5.0」を実現し、これによりSDGsの達成に寄与するとされている。
この点を踏まえ、経団連の提言では、Society5.0を本格的に実現する税制措置の整備を重要な課題として掲げている。具体的には、研究開発税制の拡充及び税務分野におけるデジタル・ガバメントのさらなる推進等を求めている。あわせてグローバル市場における日本企業の競争力強化の観点から法人実効税率の引き下げについても求めている。それぞれ詳細は以下のとおりである。
法人実効税率の引き下げ 提言では、法人実効税率について、「平成28年度税制改正により標準税率ベースで法人実効税率20%台への引き下げが実現した」としたうえで、主要先進国等における法人実効税率の引き下げの動向を踏まえ、「日本の法人税率は主要先進国のなかでもっとも高い水準となるおそれがある」ことから、「さらにグローバル市場における日本企業の競争力をより高めていく観点から、法人実効税率について、実質的な税負担の軽減を伴うかたちで早期にOECD主要国平均・アジア近隣諸国並みの25%程度を目指すべきである」としている。
2017年には米国でTax Cut and Jobs Act 2017(TCJA)が成立し、米国で連邦法人税率が35%から21%へと引き下げられた。また、フランスでもマクロン政権のもと、法人税率の引き下げについて深堀りがなされている。わが国おいてもこれらの動向や他の先進諸国の動きも踏まえつつ、今後、実質的な税負担の軽減を伴うかたちで議論が進展することを期待する(図2参照)。
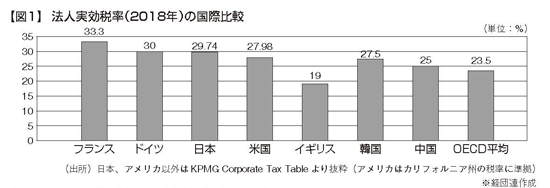
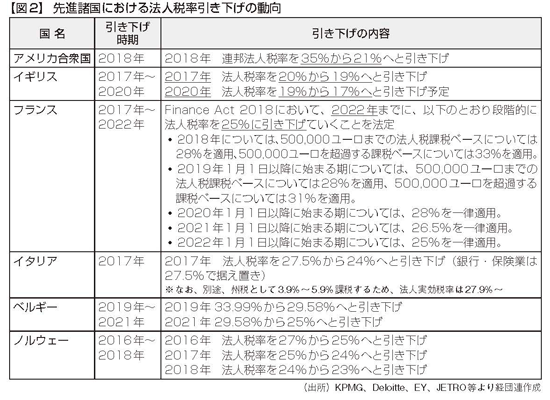
研究開発税制の拡充 Society5.0を本格的に実現するためには、イノベーションを起こすことが不可欠である。イノベーションの実現のためには、ICTとの連携やAI、ビッグデータ、IoTの新しい技術を積極的に活用するとともに、日本がこれまで行ってきた基礎研究や技術改良研究を推し進めることが重要となる。
「経済財政運営と改革の基本方針2018(以下、「骨太の方針2018」)」(2018年6月15日閣議決定)及び「未来投資戦略2018」では、「2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比4パーセント以上にする」ことを掲げていることから、研究開発投資の増大は日本にとって急務の課題である。
これらの点を踏まえ、提言では「上乗せ措置などの期限切れを迎えるが、より一層イノベーションに資する研究開発を促進すべく、研究開発税制を抜本的に拡充する必要がある」としている。具体的には以下のとおりである。
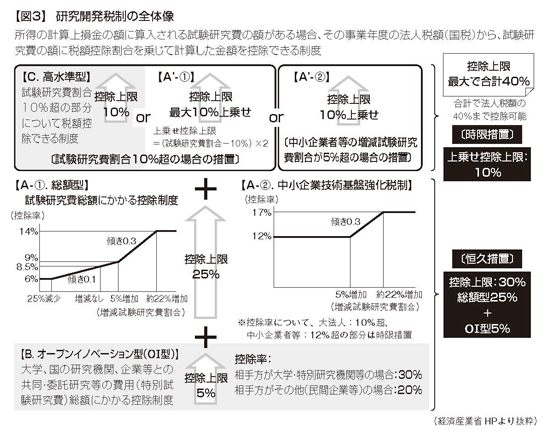
総額型の拡充等 総額型については日本の研究開発税制を支える根幹であることから、「控除上限を法人税額の25%から30%へ引き上げるべき」としている。また、「期限切れを迎える控除率10%~14%の部分について延長・拡充することが必要である」、「総額型上乗せ措置(試験研究費割合10%超の場合)及び高水準型については、延長すべきである」としている。
オープンイノベーション型(OI型)研究開発税制 特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究やそれらのものに委託して行う試験研究にかかる費用について控除できるオープンイノベーション型(OI型)については、企業などから共同研究を行う意欲は高いものの、制度の使いにくさについて多く指摘がなされている。大学との間で共同研究を行う場合、国の研究機関や国立研究開発法人と共同研究を行う場合と比べ、契約書で細目の記載が求められることや専門家の監査が必要となることなど厳しい要件が課されており、大学側の協力を得にくい等の課題が生じている(図4参照)。
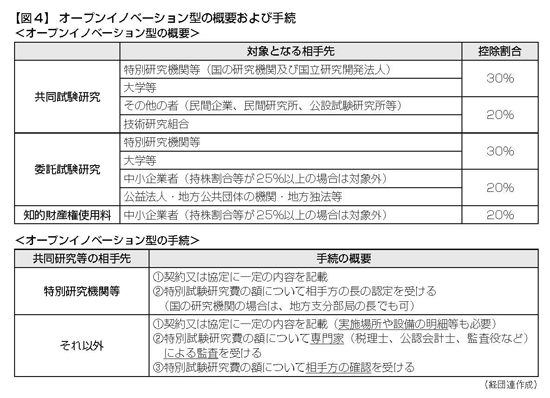
このため、提言では『「未来投資戦略2018」で「2025年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を3倍増とする」とされているなかで、少なくとも、大学との共同研究については、国立研究開発法人と同等の要件で共同研究を可能とするよう、契約書記載事項や相手先確認事項、監査要件を緩和すべき』としている。また、「その他の者との共同研究や委託研究についても、契約書記載事項や相手先確認事項を簡素化するとともに、監査要件を緩和することを検討すべき」としている。
また、Society5.0を実現する観点からは、大胆なイノベーションを生み出す研究開発型ベンチャービジネスを支援する観点から、「OI型について、研究開発型ベンチャービジネス及び中小企業者との共同研究について控除率を20%から30%に引き上げるとともに、研究開発型ベンチャービジネスに出資した場合に、投資額等に係る優遇措置を創設することを検討すべき」としている。
サービス開発に係る研究開発 平成29年度税制改正で研究開発税制の対象範囲に加えられたサービス開発に関しても、サービス開発の現場に適応しておらず、実際にサービス開発を行っている企業からはハードルが高く適用が難しいという声が多く出ている。
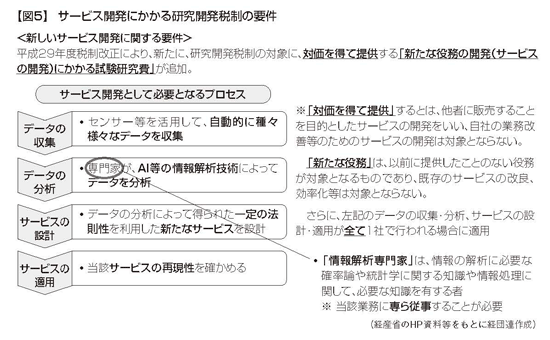
このため、提言では、「サービス開発に関し、対象となる範囲を広げるなどして要件を緩和すべき」としている。具体的には、『他社への販売だけではなく、自社の業務改善の目的を兼ねる場合でも「対価を得て」の要件を満たすことを明確化すべき』ことや、「1社でデータの収集・分析、サービスの設計・適用を行う場合だけではなく、企業の共同によるサービス開発を行う場合も対象に含める」ことを提言している。また、情報解析専門家について、当該業務に「専ら従事」することが求められているなかで、顧客との間の打ち合わせや設計の前段階での顧客の要望のヒアリングなど、データの収集やサービスの設計にあたって不可欠となる活動がサービス開発に係る活動と判断されずに、「専ら従事」とする要件を満たさないおそれがある。このため、「顧客における課題を発見し、新たなサービスを企画する活動に関与した場合でも、データの収集・分析等のサービス開発に係る活動に含まれるよう要件を見直す」ことを提言している。
税務分野におけるデジタル・ガバメントのさらなる推進 平成30年度税制改正では、円滑・適正な納税のための環境整備として、大法人について法人税等の電子申告が義務化されるとともに、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう環境整備が進められた。また、地方税の電子納税についても全地方公共団体が共同で収納を行う仕組みが整備されることとなった。
他方、「骨太の方針2018」にも「社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点から、税務手続の電子化を一層推進する」とあるとおり、企業の事務負担軽減の観点も踏まえつつ、労働生産性を向上させるという視点から、税務手続の電子化について、変えるべきところは変えるというかたちで引き続き見直しを行っていくことが重要となる。
このため、経団連の提言では、「行政手続コスト削減のための基本計画」(2018年3月改定)の内容について着実な実現を図ることなど、さらに取り組みを進展させることを求めるとともに、とりわけ以下の項目について、早期に取り組みを進めるべきとしている。
・連結納税に係る各種手続の緩和(例:連結子法人に係る異動届出書の連結親法人所轄税務署への一括送信)
・固定資産税の納税通知書・課税明細書等の書式統一・電子化
・事業者の実務負担に配慮した個人住民税特徴税額通知(納税義務者用)の電子化
あわせて、「電子帳簿保存法における承認申請やスキャナ保存に関し、企業内情報のデジタル化の推進及び保存義務者の負担軽減等の観点から見直しの検討を進めることが必要」と提言している。具体的には、「システム・製品単位のベンダーによる承認申請の容認(市販、カスタマイズ)や、過去分の重要文書の保存の容認を含むスキャナ保存の対象書類の拡大、グレースケールでの保存対象書類の拡大等のスキャナ保存要件の緩和、タイムスタンプ要件の緩和」等を求めている。
消費税 平成31年度税制改正において、もっとも大きく取り上げられる可能性があるのは、消費税であろう。まず、2019年10月の消費税率10%への引き上げについては、「骨太の方針2018」にもあるとおり、持続可能な全世代型社会保障制度を確立しつつ、財政健全化を実現するため、消費税率の8%から10%への引き上げを確実に実現すべきであると提言している。
消費税率の引き上げについては、5%から8%への引き上げの際に、駆け込み・反動減の動きが強く見られたことから、「骨太の方針2018」でも「需要に応じて事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要・反動減が抑制されるようその方策について、具体的に検討する」とされている。このため、経団連としても「販売価格の設定という企業の最も基本的な経済活動を制約しないことを前提としつつ、中小企業等による適正転嫁や小売の既存実務に配慮した制度設計を行うべき」としている。あわせて、「骨太の方針2018」で「2019年10月1日の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の自動車や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討する」とされていることを踏まえ、自動車及び住宅に関する対策を提言している。具体的には以下のとおりである。
自動車関係諸税 自動車関係諸税については、制度の見直しのタイミングと重なっているため、本年度は制度全体について議論が行われる見通しである。
平成29年度税制改正大綱において、「消費税率10%への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減対策に万全を期す必要があり、自動車をめぐるグローバルな環境、自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、グリーン化、登録車と軽自動車との課税のバランスを図る観点から、平成31年度税制改正までに、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる」とされている。この記述も踏まえつつ、平成31年度税制改正において見直しがなされる予定である。
近時、通商問題が先行き不透明な中で、自動車関係諸税については、需要変動の平準化に止まらない抜本的な改革が必要となる。最も重要なのは、保有課税の簡素化・負担軽減である。このため、経団連の提言では、「自動車の保有を促進する観点から、自動車税の税率を国際水準である現行の軽自動車税を起点に引き下げるとともに、自動車重量税の「当分の間税率」を廃止すべき」としている。あわせて、消費税率引き上げに係る需要平準化の対策という観点も踏まえつつ、取得時課税の簡素化・負担軽減を実現することが必要である。具体的には、「税率引き上げ後の自動車の取得時の税については、現行の税負担より十分な軽減を図るべきである。加えて、自動車税の初年度月割課税は廃止すべき」としている。また、期限切れとなるエコカー減税、グリーン化特例の租税特別措置についても、「技術開発の促進や次世代自動車普及促進の観点から延長すべき」としている。
また、中長期的には、負担軽減に加え、極めて複雑な自動車関係諸税を納税者にとって分かり易くなるよう抜本的に簡素化すべきとしている。
住宅・土地・都市税制 住宅に関しては、すでに、平成25年度税制改正等で住宅ローン減税や住宅取得等資金の贈与税特例等が措置されているところである(図6参照)。もっとも、2回の消費税率引き上げ延期の間に、住宅価格の上昇や借入金増加に伴う利息負担増、一次取得者の純貯蓄の減少等、住宅取得環境に大きな変化が生じている。このため、提言では、「消費税率引き上げによる経済の停滞を引き起こさないよう、駆け込み・反動減の平準化を万全のものとする観点から以下の措置を追加的に講ずるべき」としている。具体的な措置は以下のとおりである。
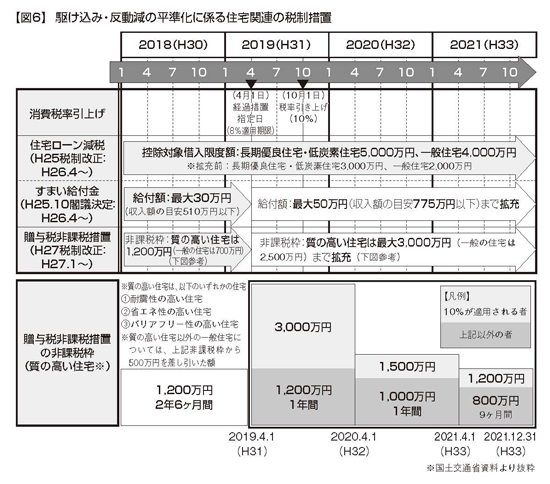
・住宅ローン減税の拡充(控除期間の延長等)
・住宅取得資金等の贈与特例の拡充
・住宅取得支援税制に係る床面積要件の緩和
このうち、住宅ローン減税の拡充については、現在の控除対象借入限度額が最大5,000万円であることから、控除対象借入限度額の引き上げよりも、控除期間(現行制度:10年)の延長を求めている。
また、提言では「予算措置(すまい給付金の拡充や省エネ住宅ポイント等)もあわせて講じ、万全の対応を行う必要がある」としている。
国際課税 次に国際課税の関係では、外国子会社合算税制の関係や、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの最終報告書の内容に係る国内法制化など、大きなテーマが議論となる見込みである。
外国子会社合算税制 外国子会社合算税制(CFC税制)は、外国子会社を利用した租税回避を防止するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度である。外国子会社合算税制は、平成29年度税制改正の見直しにより、所得の性質に着目し、一定の配当、利子、有価証券譲渡損益や無形資産等の使用料など、一定の受動的所得について合算課税の対象とするとともに、事業所等の固定施設を持たず、かつ、その本店所在地国において事業の管理、支配、運営を自ら行っていない会社(ペーパーカンパニー)や、総資産の額に対する受動的所得の合計額の割合が30%を超える企業で、総資産の額に対する金融資産等の割合が50%を超える会社(事実上のキャッシュボックス)、租税に関する情報の交換に非協力的な国(ブラックリスト国)等の租税回避のおそれが強い類型となる特定の外国子会社の所得について、合算課税の対象としている(図7参照)。
また、平成30年度税制改正では、ペーパーカンパニーの解消を促進する観点から、M&Aにより傘下に入った特定外国関係会社又は対象外国関係会社(ペーパーカンパニー等)を整理するにあたり、当該ペーパーカンパニー等が有する一定の外国関係会社の株式等を一定期間内に所定の要件のもとで譲渡した場合に、その譲渡により生ずる利益の額を、当該ペーパーカンパニー等の適用対象金額の計算上控除することを可能とする制度が創設された。
他方、米国における税制改正(Tax Cut and Jobs Act 2017(TCJA))により、新たな問題が生じている。具体的には、税制改革により連邦法人税率が35%から21%に引き下げられ、州税も含めた法人実効税率も多くの場合、30%未満にまで低下したことにより、米国に所在するLLC(Limited Liability Company、有限責任会社)・LPS(Limited Partnership、投資事業有限責任組合)や米国内で納税申告を完結させるために存在するブロッカー会社が、制度免除適用基準の30%より低い水準となることでペーパーカンパニー等にあたるとして合算課税の対象となるおそれが生じている。こうした事業体は、現地において実体ある事業活動を行うために必要なもので、租税回避の目的で設立されるものではないため、そもそも合算課税の対象とすべきものではない。
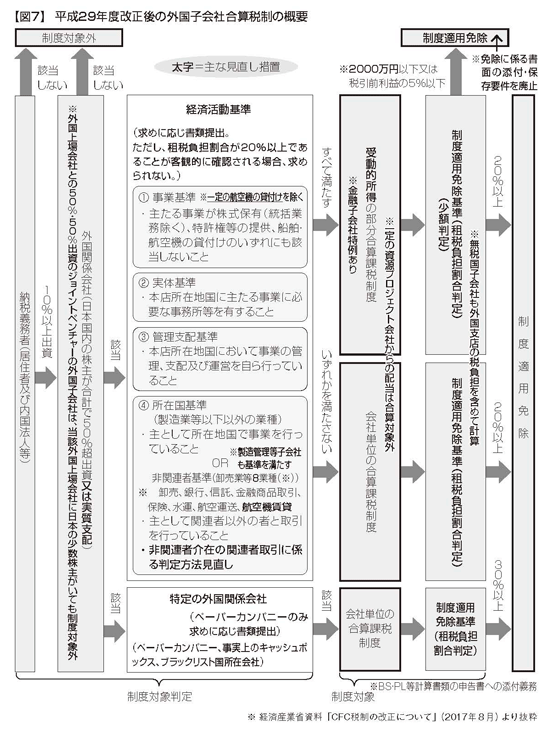
また、合算課税が行われる場合には、例えば、米国でLLC・LPSなどパススルー事業体が合算課税の対象となれば、米国における取り扱いでは、パススルー事業体の構成員に課税がなされる一方、日本における取り扱いでは、パススルー事業体も外国関係会社として扱われるため、日米で重畳的な課税がなされるおそれがある。加えて、パススルー事業体の所得・税額計算も困難となっており、さらに、米国で連結納税を行っている場合、わが国のCFC税制の適用の有無を判定するためだけに、各連結法人の個別の所得及び税額を計算する必要が生じることとなる。
このため、提言では、制度適用免除基準の引き下げやホワイトリストの適用を検討すべきとするとともに、これらを実施することが難しい場合、「パススルー事業体と構成員を一体として、CFC税制の判定を行う基準を導入すべき」と提言している。また、連結納税についても、「連結グループ全体を一体判定する仕組みを検討することが必要である」としている。あわせて、「個々の事業体について租税負担割合の計算が必要となる場合には、仮定的な所得や仮定的な税率によって簡便に計算することを許容すべき」としたうえで、外国税額控除の計算方法についても配慮すべきとしている。
BEPSプロジェクトの国内法制化 BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトに関しては、平成27年度税制改正による電子経済の課税上の課題への対応および平成28年度税制改正における移転価格税制に係る文書化制度の改正、平成29年度税制改正による外国子会社合算税制の改正、平成30年度税制改正における恒久的施設に関する規定の見直しなど、順次、OECDにおける検討状況を踏まえて、国内法制化が進められてきた。
この点、中長期的に取り組むべき課題については、平成29年度与党税制改正大綱の補論において、以下のとおり整理されている。
また、平成30年度与党税制改正大綱でも『今後も国際協調において主導的な役割を果たすため、わが国も引き続き国際合意に則った制度の整備を進める必要がある。特に、平成29年度税制改正大綱において中期的に取り組むべき事項として掲げた、移転価格税制、過大支払利子税制及び義務的開示制度については、「BEPSプロジェクト」における勧告や諸外国の制度・運用実態等を踏まえて検討を進める』とされている。
これらの与党税制改正大綱で示された課題について、「移転価格税制」は、BEPS行動8-10に、「過大支払利子税制」はBEPS行動4に、「義務的開示制度」はBEPS行動12に、それぞれ対応している。2019年にわが国でG20の開催を控えていることもあり、平成31年度税制改正では、特に、過大支払利子税制および評価困難な無形資産に関する移転価格税制の適用(所得相応性基準)について、制度の具体的な見直しがなされる可能性が高い状況にある。
あわせて、2019年にはBEPS行動1と関連する電子経済に関する議論についても進展が見られる可能性が高い。
利子控除制限 利子控除制限については、いよいよ本年度に制度の本格的な見直しの議論が行われる見込みである。わが国における過大支払利子税制は関連者への純支払利子等の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度である(※関連者とは、直接・間接の持分割合50%以上又は実質支配・被支配関係にある者)。もっとも、現行の過大支払利子税制では、利子等の受領者側でわが国の法人税の課税所得に算入されるもの等を除くとされているため、国内の関連者・非関連者との取引における支払利子は対象外とされている。また、ベースとなる調整所得金額についても受取配当益金不算入額が含まれている。
この点、BEPS行動4の最終報告書では、①BEPSの勧告では損金不算入となる利子の範囲が国外関連者に対する利子のみならず、国外の非関連者および国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となること、②固定比率の水準が異なること(BEPS行動4ではEBITDAの10%~30%とされている)、③過大支払利子税制の調整所得金額に対応するEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれない(なお、このEBITDAはBEPS行動4の最終報告書では、税務上のEBITDAとされている)こととされている(図8参照)。このため、BEPS行動4の最終報告書で勧告された内容に基づいて過大支払利子税制の見直しを行った場合損金不算入額が増大するおそれが大きい。とりわけ、構造的に借入額の大きい可能性がある業態やM&Aなどを実施したことにより借入額の大きい企業、単体納税を行っているホールディングス会社など子会社等からの配当が利益のほとんどを占める企業などでは、これまで過大支払利子税制のリスクについてまったく意識してこなかった場合でもあっても、思わぬかたちで損金不算入額が生じるおそれがある。
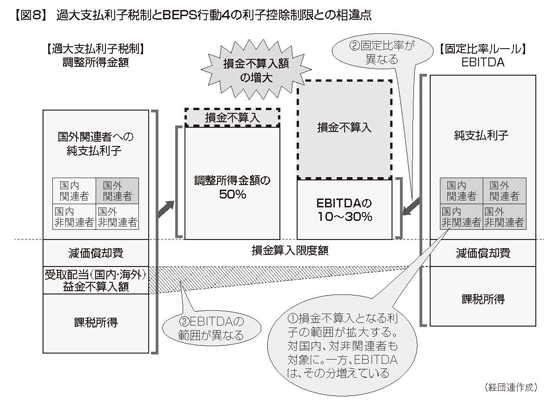
そのため、提言では、「対象とする利子の範囲は、現行制度と同様に、実質的に国外関連者に対する支払利子に限るべきである」ことや、「現在の金利が歴史的低水準にあることも十分に踏まえる必要がある」こと、「免税配当については、EBITDAから除外すべきではない」こと、「グループ比率ルールについては、各国における利子の数値の正確な把握など、事務負担が増加し、労働生産性の改善に支障を来たす恐れがあるため、導入は好ましくない」こと、「損金不算入額の繰越制度を拡充すべきである」ことを提言している。
所得相応性基準 移転価格税制により、海外の関連者との取引は、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し課税されるが、開発途上の無形資産を譲渡した場合、類似の取引が無い等の理由により、独立企業間価格を算定することは容易ではない。このため、BEPS行動8では、開発途上だが今後多額の利益を生みそうな無形資産などについて、十分にその価値が生じていない段階で低課税国等へ移転し、租税回避を図るスキームを防止するため、評価困難な無形資産(HTVI:Hard-to-Value Intangibles)について、税務当局が事後の実現値に基づき当初の譲渡価格を調整することを認めるアプローチ(所得相応性基準・HTVIアプローチ)を導入することを勧告している。
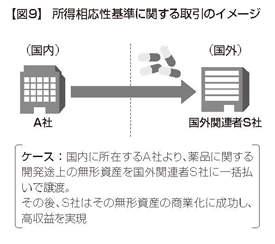
この点、提言では、「評価困難な無形資産(HTVI)の譲渡等に対する所得相応性基準の導入については、後知恵課税となるおそれがあり、平成31年度税制改正で拙速に導入すべきではない」として導入に反対している。具体的には、HTVIの定義が曖昧であるために、「仮に二重課税が発生した場合には、相互協議(MAP)に進んでも、HTVIに対する見解の相違等により二重課税が解消しないケースが増加するおそれがある」こと等の理由もあり、「まずはHTVIを利用した租税回避が日本においても存在するのか検討し、導入の必要性を検証すべきである」としている。さらに「万が一、導入が不可避な場合でも、所得相応性基準については、例えば事前の予測に関する信頼に足る証拠の意義等につきガイダンスを整備するなど、適用対象となる基準を明確化するとともに、実際に適用する局面は極めて限定する方向で検討すべきである」としている。加えて、「納税者の取引時点での予測に当局が修正を求める場合の立証責任は、課税当局にある点を明確化すべきである」としている。
電子経済 経済の電子化(デジタル化)に伴い、企業は各国において物理的な拠点を伴わなくとも大きな経済活動を行うことが可能となったため、自国において経済活動に見合った納税がなされていないのではないかという懸念を持つ国が現れている。この点、とりわけ、欧州の一部の国などでは、GAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)などのデジタル分野における多国籍企業がターゲットとなって、課税を強化すべきという声が出てきている。
この課題に包括的に対処すべく、2018年3月にOECDから電子経済に対する課税に関する中間報告書が公表されている。そこでは、電子経済のビジネスをグローバル規模で展開する高度に電子化された企業(highly digitalized businesses: HDBs)の存在を指摘し、複数国に亘る物理的進出を伴わない大規模事業展開、無形資産への依存、データ及びユーザーの参加という共通の特徴があるとする一方、データ及びユーザーの参加と価値創造との関係については各国で見解の相違があるため、具体的な課税手法は勧告していない。今後、ネクサス(課税の根拠となる利得の源泉地との結びつき)及び利得配分に関する議論を継続し、OECDでは電子経済に対する課税について2020年までに最終的なとりまとめを行うとしている。
この点、日本が2019年にG20の議長国となることもあり、日本政府としては電子経済の問題に主体的に関与していく必要がある。電子経済の問題は、単に特定の企業・業種の問題ではなく、PEや移転価格税制などの国際的なルール・枠組みにも影響を与えうる射程の広い議論となるおそれがあり、今後議論の行方を注視する必要がある。経団連としては、「仮にデータやユーザーの参加にネクサス性を認めるとしても、利得配分については既存の移転価格税制やPE帰属利得との整合性を踏まえた、別途の慎重な議論が必要」としたうえで、「不明確な定義による課税や経済活動の実態にそぐわない課税がなされること、また、諸外国において電子経済の議論に乗じた安易な源泉地国課税の強化の議論に結びつく可能性があること」への懸念を示している。また、各国・地域で異なった制度に基づいて課税がなされれば、経済的な実態として二重課税が発生するおそれや、紛争解決手段が有効に機能しないおそれがあるため、「各国・地域におけるユニラテラルな課税は避けるべき」としたうえで「電子経済取引の実態を踏まえ、OECD/G20におけるマルチラテラルな解決に期待する」と提言している。
役員給与税制の見直し 業績連動給与は平成29年度税制改正で算定指標の範囲拡大など拡充が行われた。一方、適正手続要件については抜本的な見直しは行われておらず、例えば、指名委員会等設置会社の場合、報酬委員会の構成員がすべて非業務執行役員であることが求められているなど、活用の阻害となる状況が引き続き残されている(参考1参照)。この点、改訂版コーポレートガバナンス・コードでは、中長期的な業績と連動する報酬の割合を適切に設定すべきことや報酬委員会の活用が要求されており、金融庁のディスクロージャーワーキンググループ報告でも企業価値の向上に向けた経営陣のインセンティブとして業績連動報酬の重要性が再認識されていることから、より一層、業績連動報酬の導入を推進していくことが重要となっている。
このため、指名委員会等設置会社における適正手続要件に関しては、「報酬委員会について非業務執行役員のみで構成されることという要件について、業務執行役員が委員であることの合理性等にかんがみ、非業務執行役員による過半数の賛成で足りる」こととすべきとしている。また、業績連動指標にキャッシュフローや定性的指標を盛り込むことや開示要件について緩和を検討すべきである。
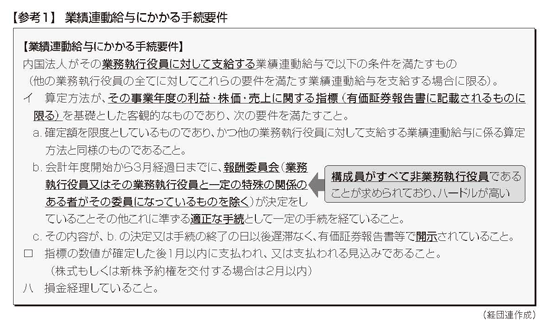
その他の課題 また、提言では、償却資産に係る固定資産税の抜本的見直し、印紙税の廃止・負担軽減、火災保険等に関する異常危険準備金制度の延長・拡充、減耗控除制度の延長・拡充、外航船舶に係る特別償却制度の延長等、地球温暖化対策税の抜本的な見直し、原料用途免税の本則非課税化、NISAの投資可能期間及び非課税保有期間の恒久化、上場株式等の相続税評価額の見直し、教育資金及び結婚子育て資金に係る贈与税の特例の延長、生命保険料控除制度の拡充についても実現を求めている。
平成31年度税制改正に関する経団連の提言について
一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦
はじめに 経団連では2018年9月18日に、平成31年度税制改正に関する提言を公表した。
平成30年度税制改正では、個人所得課税における給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替や給与所得控除および公的年金等控除、基礎控除の見直し、事業承継税制の拡充、国際観光旅客税および森林環境税等の創設、法人課税における賃上げ及び投資の促進に係る税制(所得拡大促進税制の改組)や情報連携投資等の促進に係る税制の創設、税務手続の電子化等の推進などの改正がなされた。この点、平成31年度税制改正では、研究開発税制の延長・拡充、消費税率の引き上げに伴う需要平準化の対応、自動車関係諸税の負担軽減・簡素化、中小企業の投資促進に関する税制の延長等が主要な課題などとなる見通しである。
なお、本稿の内容は当方の私見であり、必ずしも組織全体の意見を代表するものではない。
政府の成長戦略等の動向 提言では、「日本経済が、デフレから完全に脱却し、GDP600兆円経済に向け、さらに飛躍するためには、税制や規制等の諸改革により社会全体でイノベーションを起こし、生産性を向上させ、グローバル市場における日本企業の競争力を強化するとともに、経済全体を持続的に発展させていくことが重要である」との認識を示している。
政府の「新しい経済政策パッケージ」(2017年12月8日閣議決定)では、2020年までの3年間を生産性革命・集中投資期間とし、大胆な税制、予算、規制改革などあらゆる施策を総動員するとされている。また、「未来投資戦略2018」(2018年6月15日閣議決定)では、「生産性革命」に取り組むとともに、AI、ビッグデータ、IoTなどの技術革新によって、「Society 5.0」を実現し、これによりSDGsの達成に寄与するとされている。
この点を踏まえ、経団連の提言では、Society5.0を本格的に実現する税制措置の整備を重要な課題として掲げている。具体的には、研究開発税制の拡充及び税務分野におけるデジタル・ガバメントのさらなる推進等を求めている。あわせてグローバル市場における日本企業の競争力強化の観点から法人実効税率の引き下げについても求めている。それぞれ詳細は以下のとおりである。
法人実効税率の引き下げ 提言では、法人実効税率について、「平成28年度税制改正により標準税率ベースで法人実効税率20%台への引き下げが実現した」としたうえで、主要先進国等における法人実効税率の引き下げの動向を踏まえ、「日本の法人税率は主要先進国のなかでもっとも高い水準となるおそれがある」ことから、「さらにグローバル市場における日本企業の競争力をより高めていく観点から、法人実効税率について、実質的な税負担の軽減を伴うかたちで早期にOECD主要国平均・アジア近隣諸国並みの25%程度を目指すべきである」としている。
2017年には米国でTax Cut and Jobs Act 2017(TCJA)が成立し、米国で連邦法人税率が35%から21%へと引き下げられた。また、フランスでもマクロン政権のもと、法人税率の引き下げについて深堀りがなされている。わが国おいてもこれらの動向や他の先進諸国の動きも踏まえつつ、今後、実質的な税負担の軽減を伴うかたちで議論が進展することを期待する(図2参照)。
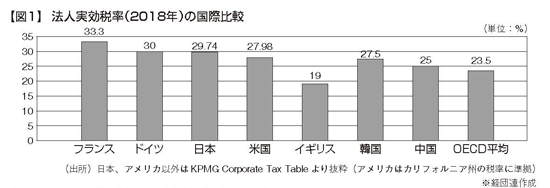
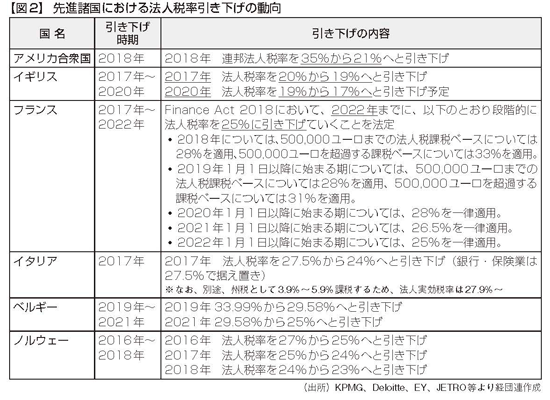
研究開発税制の拡充 Society5.0を本格的に実現するためには、イノベーションを起こすことが不可欠である。イノベーションの実現のためには、ICTとの連携やAI、ビッグデータ、IoTの新しい技術を積極的に活用するとともに、日本がこれまで行ってきた基礎研究や技術改良研究を推し進めることが重要となる。
「経済財政運営と改革の基本方針2018(以下、「骨太の方針2018」)」(2018年6月15日閣議決定)及び「未来投資戦略2018」では、「2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比4パーセント以上にする」ことを掲げていることから、研究開発投資の増大は日本にとって急務の課題である。
これらの点を踏まえ、提言では「上乗せ措置などの期限切れを迎えるが、より一層イノベーションに資する研究開発を促進すべく、研究開発税制を抜本的に拡充する必要がある」としている。具体的には以下のとおりである。
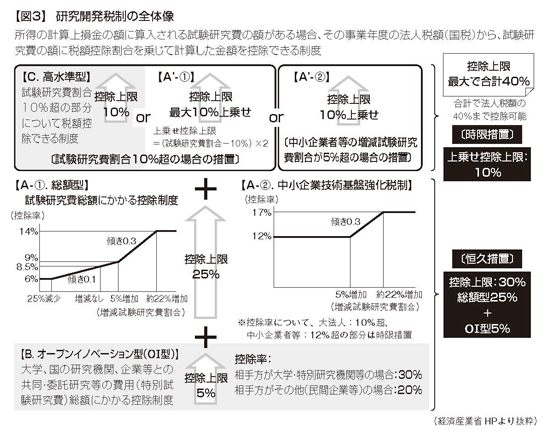
総額型の拡充等 総額型については日本の研究開発税制を支える根幹であることから、「控除上限を法人税額の25%から30%へ引き上げるべき」としている。また、「期限切れを迎える控除率10%~14%の部分について延長・拡充することが必要である」、「総額型上乗せ措置(試験研究費割合10%超の場合)及び高水準型については、延長すべきである」としている。
オープンイノベーション型(OI型)研究開発税制 特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究やそれらのものに委託して行う試験研究にかかる費用について控除できるオープンイノベーション型(OI型)については、企業などから共同研究を行う意欲は高いものの、制度の使いにくさについて多く指摘がなされている。大学との間で共同研究を行う場合、国の研究機関や国立研究開発法人と共同研究を行う場合と比べ、契約書で細目の記載が求められることや専門家の監査が必要となることなど厳しい要件が課されており、大学側の協力を得にくい等の課題が生じている(図4参照)。
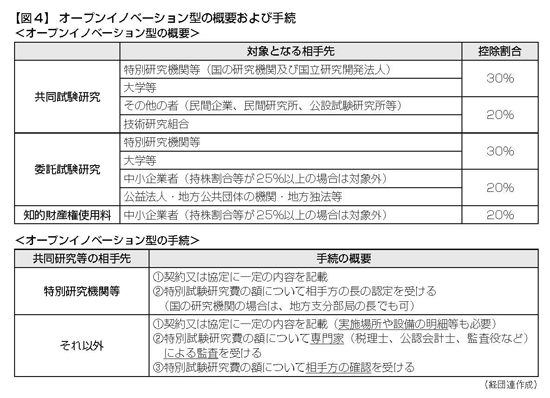
このため、提言では『「未来投資戦略2018」で「2025年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を3倍増とする」とされているなかで、少なくとも、大学との共同研究については、国立研究開発法人と同等の要件で共同研究を可能とするよう、契約書記載事項や相手先確認事項、監査要件を緩和すべき』としている。また、「その他の者との共同研究や委託研究についても、契約書記載事項や相手先確認事項を簡素化するとともに、監査要件を緩和することを検討すべき」としている。
また、Society5.0を実現する観点からは、大胆なイノベーションを生み出す研究開発型ベンチャービジネスを支援する観点から、「OI型について、研究開発型ベンチャービジネス及び中小企業者との共同研究について控除率を20%から30%に引き上げるとともに、研究開発型ベンチャービジネスに出資した場合に、投資額等に係る優遇措置を創設することを検討すべき」としている。
サービス開発に係る研究開発 平成29年度税制改正で研究開発税制の対象範囲に加えられたサービス開発に関しても、サービス開発の現場に適応しておらず、実際にサービス開発を行っている企業からはハードルが高く適用が難しいという声が多く出ている。
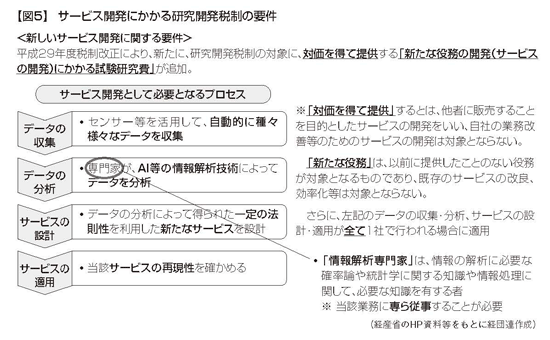
このため、提言では、「サービス開発に関し、対象となる範囲を広げるなどして要件を緩和すべき」としている。具体的には、『他社への販売だけではなく、自社の業務改善の目的を兼ねる場合でも「対価を得て」の要件を満たすことを明確化すべき』ことや、「1社でデータの収集・分析、サービスの設計・適用を行う場合だけではなく、企業の共同によるサービス開発を行う場合も対象に含める」ことを提言している。また、情報解析専門家について、当該業務に「専ら従事」することが求められているなかで、顧客との間の打ち合わせや設計の前段階での顧客の要望のヒアリングなど、データの収集やサービスの設計にあたって不可欠となる活動がサービス開発に係る活動と判断されずに、「専ら従事」とする要件を満たさないおそれがある。このため、「顧客における課題を発見し、新たなサービスを企画する活動に関与した場合でも、データの収集・分析等のサービス開発に係る活動に含まれるよう要件を見直す」ことを提言している。
税務分野におけるデジタル・ガバメントのさらなる推進 平成30年度税制改正では、円滑・適正な納税のための環境整備として、大法人について法人税等の電子申告が義務化されるとともに、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう環境整備が進められた。また、地方税の電子納税についても全地方公共団体が共同で収納を行う仕組みが整備されることとなった。
他方、「骨太の方針2018」にも「社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点から、税務手続の電子化を一層推進する」とあるとおり、企業の事務負担軽減の観点も踏まえつつ、労働生産性を向上させるという視点から、税務手続の電子化について、変えるべきところは変えるというかたちで引き続き見直しを行っていくことが重要となる。
このため、経団連の提言では、「行政手続コスト削減のための基本計画」(2018年3月改定)の内容について着実な実現を図ることなど、さらに取り組みを進展させることを求めるとともに、とりわけ以下の項目について、早期に取り組みを進めるべきとしている。
・連結納税に係る各種手続の緩和(例:連結子法人に係る異動届出書の連結親法人所轄税務署への一括送信)
・固定資産税の納税通知書・課税明細書等の書式統一・電子化
・事業者の実務負担に配慮した個人住民税特徴税額通知(納税義務者用)の電子化
あわせて、「電子帳簿保存法における承認申請やスキャナ保存に関し、企業内情報のデジタル化の推進及び保存義務者の負担軽減等の観点から見直しの検討を進めることが必要」と提言している。具体的には、「システム・製品単位のベンダーによる承認申請の容認(市販、カスタマイズ)や、過去分の重要文書の保存の容認を含むスキャナ保存の対象書類の拡大、グレースケールでの保存対象書類の拡大等のスキャナ保存要件の緩和、タイムスタンプ要件の緩和」等を求めている。
消費税 平成31年度税制改正において、もっとも大きく取り上げられる可能性があるのは、消費税であろう。まず、2019年10月の消費税率10%への引き上げについては、「骨太の方針2018」にもあるとおり、持続可能な全世代型社会保障制度を確立しつつ、財政健全化を実現するため、消費税率の8%から10%への引き上げを確実に実現すべきであると提言している。
消費税率の引き上げについては、5%から8%への引き上げの際に、駆け込み・反動減の動きが強く見られたことから、「骨太の方針2018」でも「需要に応じて事業者のそれぞれの判断によって価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要・反動減が抑制されるようその方策について、具体的に検討する」とされている。このため、経団連としても「販売価格の設定という企業の最も基本的な経済活動を制約しないことを前提としつつ、中小企業等による適正転嫁や小売の既存実務に配慮した制度設計を行うべき」としている。あわせて、「骨太の方針2018」で「2019年10月1日の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の自動車や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討する」とされていることを踏まえ、自動車及び住宅に関する対策を提言している。具体的には以下のとおりである。
自動車関係諸税 自動車関係諸税については、制度の見直しのタイミングと重なっているため、本年度は制度全体について議論が行われる見通しである。
平成29年度税制改正大綱において、「消費税率10%への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減対策に万全を期す必要があり、自動車をめぐるグローバルな環境、自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、グリーン化、登録車と軽自動車との課税のバランスを図る観点から、平成31年度税制改正までに、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる」とされている。この記述も踏まえつつ、平成31年度税制改正において見直しがなされる予定である。
近時、通商問題が先行き不透明な中で、自動車関係諸税については、需要変動の平準化に止まらない抜本的な改革が必要となる。最も重要なのは、保有課税の簡素化・負担軽減である。このため、経団連の提言では、「自動車の保有を促進する観点から、自動車税の税率を国際水準である現行の軽自動車税を起点に引き下げるとともに、自動車重量税の「当分の間税率」を廃止すべき」としている。あわせて、消費税率引き上げに係る需要平準化の対策という観点も踏まえつつ、取得時課税の簡素化・負担軽減を実現することが必要である。具体的には、「税率引き上げ後の自動車の取得時の税については、現行の税負担より十分な軽減を図るべきである。加えて、自動車税の初年度月割課税は廃止すべき」としている。また、期限切れとなるエコカー減税、グリーン化特例の租税特別措置についても、「技術開発の促進や次世代自動車普及促進の観点から延長すべき」としている。
また、中長期的には、負担軽減に加え、極めて複雑な自動車関係諸税を納税者にとって分かり易くなるよう抜本的に簡素化すべきとしている。
住宅・土地・都市税制 住宅に関しては、すでに、平成25年度税制改正等で住宅ローン減税や住宅取得等資金の贈与税特例等が措置されているところである(図6参照)。もっとも、2回の消費税率引き上げ延期の間に、住宅価格の上昇や借入金増加に伴う利息負担増、一次取得者の純貯蓄の減少等、住宅取得環境に大きな変化が生じている。このため、提言では、「消費税率引き上げによる経済の停滞を引き起こさないよう、駆け込み・反動減の平準化を万全のものとする観点から以下の措置を追加的に講ずるべき」としている。具体的な措置は以下のとおりである。
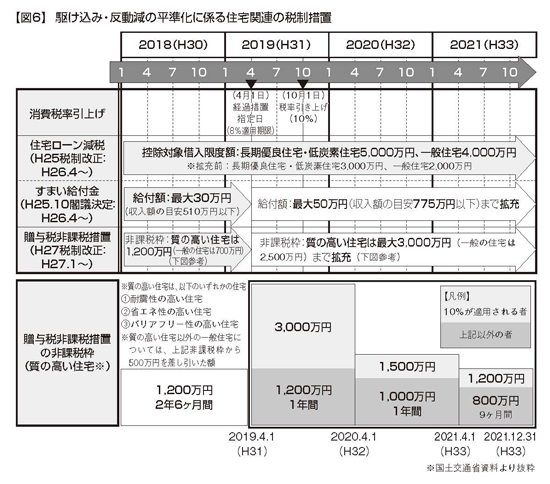
・住宅ローン減税の拡充(控除期間の延長等)
・住宅取得資金等の贈与特例の拡充
・住宅取得支援税制に係る床面積要件の緩和
このうち、住宅ローン減税の拡充については、現在の控除対象借入限度額が最大5,000万円であることから、控除対象借入限度額の引き上げよりも、控除期間(現行制度:10年)の延長を求めている。
また、提言では「予算措置(すまい給付金の拡充や省エネ住宅ポイント等)もあわせて講じ、万全の対応を行う必要がある」としている。
国際課税 次に国際課税の関係では、外国子会社合算税制の関係や、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの最終報告書の内容に係る国内法制化など、大きなテーマが議論となる見込みである。
外国子会社合算税制 外国子会社合算税制(CFC税制)は、外国子会社を利用した租税回避を防止するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度である。外国子会社合算税制は、平成29年度税制改正の見直しにより、所得の性質に着目し、一定の配当、利子、有価証券譲渡損益や無形資産等の使用料など、一定の受動的所得について合算課税の対象とするとともに、事業所等の固定施設を持たず、かつ、その本店所在地国において事業の管理、支配、運営を自ら行っていない会社(ペーパーカンパニー)や、総資産の額に対する受動的所得の合計額の割合が30%を超える企業で、総資産の額に対する金融資産等の割合が50%を超える会社(事実上のキャッシュボックス)、租税に関する情報の交換に非協力的な国(ブラックリスト国)等の租税回避のおそれが強い類型となる特定の外国子会社の所得について、合算課税の対象としている(図7参照)。
また、平成30年度税制改正では、ペーパーカンパニーの解消を促進する観点から、M&Aにより傘下に入った特定外国関係会社又は対象外国関係会社(ペーパーカンパニー等)を整理するにあたり、当該ペーパーカンパニー等が有する一定の外国関係会社の株式等を一定期間内に所定の要件のもとで譲渡した場合に、その譲渡により生ずる利益の額を、当該ペーパーカンパニー等の適用対象金額の計算上控除することを可能とする制度が創設された。
他方、米国における税制改正(Tax Cut and Jobs Act 2017(TCJA))により、新たな問題が生じている。具体的には、税制改革により連邦法人税率が35%から21%に引き下げられ、州税も含めた法人実効税率も多くの場合、30%未満にまで低下したことにより、米国に所在するLLC(Limited Liability Company、有限責任会社)・LPS(Limited Partnership、投資事業有限責任組合)や米国内で納税申告を完結させるために存在するブロッカー会社が、制度免除適用基準の30%より低い水準となることでペーパーカンパニー等にあたるとして合算課税の対象となるおそれが生じている。こうした事業体は、現地において実体ある事業活動を行うために必要なもので、租税回避の目的で設立されるものではないため、そもそも合算課税の対象とすべきものではない。
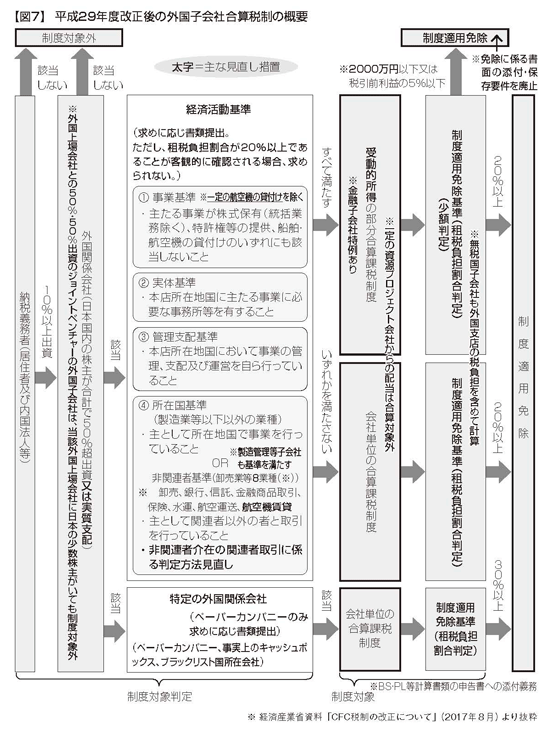
また、合算課税が行われる場合には、例えば、米国でLLC・LPSなどパススルー事業体が合算課税の対象となれば、米国における取り扱いでは、パススルー事業体の構成員に課税がなされる一方、日本における取り扱いでは、パススルー事業体も外国関係会社として扱われるため、日米で重畳的な課税がなされるおそれがある。加えて、パススルー事業体の所得・税額計算も困難となっており、さらに、米国で連結納税を行っている場合、わが国のCFC税制の適用の有無を判定するためだけに、各連結法人の個別の所得及び税額を計算する必要が生じることとなる。
このため、提言では、制度適用免除基準の引き下げやホワイトリストの適用を検討すべきとするとともに、これらを実施することが難しい場合、「パススルー事業体と構成員を一体として、CFC税制の判定を行う基準を導入すべき」と提言している。また、連結納税についても、「連結グループ全体を一体判定する仕組みを検討することが必要である」としている。あわせて、「個々の事業体について租税負担割合の計算が必要となる場合には、仮定的な所得や仮定的な税率によって簡便に計算することを許容すべき」としたうえで、外国税額控除の計算方法についても配慮すべきとしている。
BEPSプロジェクトの国内法制化 BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトに関しては、平成27年度税制改正による電子経済の課税上の課題への対応および平成28年度税制改正における移転価格税制に係る文書化制度の改正、平成29年度税制改正による外国子会社合算税制の改正、平成30年度税制改正における恒久的施設に関する規定の見直しなど、順次、OECDにおける検討状況を踏まえて、国内法制化が進められてきた。
この点、中長期的に取り組むべき課題については、平成29年度与党税制改正大綱の補論において、以下のとおり整理されている。
| 今後、「移転価格税制」についても、知的財産等の無形資産を、税負担を軽減する目的で海外へと移転する行為等に対応すべく、「BEPSプロジェクト」で勧告された「所得相応性基準」の導入を含め、必要な見直しを検討する。また、「過大支払利子税制」についても、「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた見直しを検討する。更に、国税当局が租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定し、法制面・執行面で適切に対応できるよう、その開発・販売者あるいは利用者に税務当局へのスキーム情報の報告を義務付ける「義務的開示制度」について、「BEPSプロジェクト」の最終報告書、諸外国の制度や運用実態及び租税法律主義に基づくわが国の税法体系との関係等も踏まえ、わが国での制度導入の可否を検討する。その際、国税当局が効果的かつ適時に必要な情報を入手するための最適な既存・新規制度の組み合わせも検討する |
これらの与党税制改正大綱で示された課題について、「移転価格税制」は、BEPS行動8-10に、「過大支払利子税制」はBEPS行動4に、「義務的開示制度」はBEPS行動12に、それぞれ対応している。2019年にわが国でG20の開催を控えていることもあり、平成31年度税制改正では、特に、過大支払利子税制および評価困難な無形資産に関する移転価格税制の適用(所得相応性基準)について、制度の具体的な見直しがなされる可能性が高い状況にある。
あわせて、2019年にはBEPS行動1と関連する電子経済に関する議論についても進展が見られる可能性が高い。
利子控除制限 利子控除制限については、いよいよ本年度に制度の本格的な見直しの議論が行われる見込みである。わが国における過大支払利子税制は関連者への純支払利子等の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度である(※関連者とは、直接・間接の持分割合50%以上又は実質支配・被支配関係にある者)。もっとも、現行の過大支払利子税制では、利子等の受領者側でわが国の法人税の課税所得に算入されるもの等を除くとされているため、国内の関連者・非関連者との取引における支払利子は対象外とされている。また、ベースとなる調整所得金額についても受取配当益金不算入額が含まれている。
この点、BEPS行動4の最終報告書では、①BEPSの勧告では損金不算入となる利子の範囲が国外関連者に対する利子のみならず、国外の非関連者および国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となること、②固定比率の水準が異なること(BEPS行動4ではEBITDAの10%~30%とされている)、③過大支払利子税制の調整所得金額に対応するEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれない(なお、このEBITDAはBEPS行動4の最終報告書では、税務上のEBITDAとされている)こととされている(図8参照)。このため、BEPS行動4の最終報告書で勧告された内容に基づいて過大支払利子税制の見直しを行った場合損金不算入額が増大するおそれが大きい。とりわけ、構造的に借入額の大きい可能性がある業態やM&Aなどを実施したことにより借入額の大きい企業、単体納税を行っているホールディングス会社など子会社等からの配当が利益のほとんどを占める企業などでは、これまで過大支払利子税制のリスクについてまったく意識してこなかった場合でもあっても、思わぬかたちで損金不算入額が生じるおそれがある。
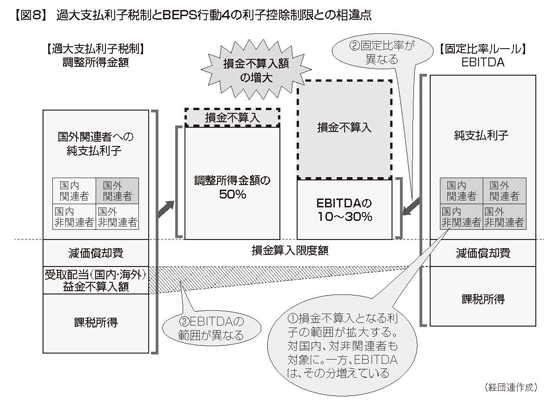
そのため、提言では、「対象とする利子の範囲は、現行制度と同様に、実質的に国外関連者に対する支払利子に限るべきである」ことや、「現在の金利が歴史的低水準にあることも十分に踏まえる必要がある」こと、「免税配当については、EBITDAから除外すべきではない」こと、「グループ比率ルールについては、各国における利子の数値の正確な把握など、事務負担が増加し、労働生産性の改善に支障を来たす恐れがあるため、導入は好ましくない」こと、「損金不算入額の繰越制度を拡充すべきである」ことを提言している。
所得相応性基準 移転価格税制により、海外の関連者との取引は、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し課税されるが、開発途上の無形資産を譲渡した場合、類似の取引が無い等の理由により、独立企業間価格を算定することは容易ではない。このため、BEPS行動8では、開発途上だが今後多額の利益を生みそうな無形資産などについて、十分にその価値が生じていない段階で低課税国等へ移転し、租税回避を図るスキームを防止するため、評価困難な無形資産(HTVI:Hard-to-Value Intangibles)について、税務当局が事後の実現値に基づき当初の譲渡価格を調整することを認めるアプローチ(所得相応性基準・HTVIアプローチ)を導入することを勧告している。
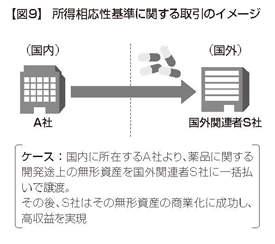
この点、提言では、「評価困難な無形資産(HTVI)の譲渡等に対する所得相応性基準の導入については、後知恵課税となるおそれがあり、平成31年度税制改正で拙速に導入すべきではない」として導入に反対している。具体的には、HTVIの定義が曖昧であるために、「仮に二重課税が発生した場合には、相互協議(MAP)に進んでも、HTVIに対する見解の相違等により二重課税が解消しないケースが増加するおそれがある」こと等の理由もあり、「まずはHTVIを利用した租税回避が日本においても存在するのか検討し、導入の必要性を検証すべきである」としている。さらに「万が一、導入が不可避な場合でも、所得相応性基準については、例えば事前の予測に関する信頼に足る証拠の意義等につきガイダンスを整備するなど、適用対象となる基準を明確化するとともに、実際に適用する局面は極めて限定する方向で検討すべきである」としている。加えて、「納税者の取引時点での予測に当局が修正を求める場合の立証責任は、課税当局にある点を明確化すべきである」としている。
電子経済 経済の電子化(デジタル化)に伴い、企業は各国において物理的な拠点を伴わなくとも大きな経済活動を行うことが可能となったため、自国において経済活動に見合った納税がなされていないのではないかという懸念を持つ国が現れている。この点、とりわけ、欧州の一部の国などでは、GAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)などのデジタル分野における多国籍企業がターゲットとなって、課税を強化すべきという声が出てきている。
この課題に包括的に対処すべく、2018年3月にOECDから電子経済に対する課税に関する中間報告書が公表されている。そこでは、電子経済のビジネスをグローバル規模で展開する高度に電子化された企業(highly digitalized businesses: HDBs)の存在を指摘し、複数国に亘る物理的進出を伴わない大規模事業展開、無形資産への依存、データ及びユーザーの参加という共通の特徴があるとする一方、データ及びユーザーの参加と価値創造との関係については各国で見解の相違があるため、具体的な課税手法は勧告していない。今後、ネクサス(課税の根拠となる利得の源泉地との結びつき)及び利得配分に関する議論を継続し、OECDでは電子経済に対する課税について2020年までに最終的なとりまとめを行うとしている。
この点、日本が2019年にG20の議長国となることもあり、日本政府としては電子経済の問題に主体的に関与していく必要がある。電子経済の問題は、単に特定の企業・業種の問題ではなく、PEや移転価格税制などの国際的なルール・枠組みにも影響を与えうる射程の広い議論となるおそれがあり、今後議論の行方を注視する必要がある。経団連としては、「仮にデータやユーザーの参加にネクサス性を認めるとしても、利得配分については既存の移転価格税制やPE帰属利得との整合性を踏まえた、別途の慎重な議論が必要」としたうえで、「不明確な定義による課税や経済活動の実態にそぐわない課税がなされること、また、諸外国において電子経済の議論に乗じた安易な源泉地国課税の強化の議論に結びつく可能性があること」への懸念を示している。また、各国・地域で異なった制度に基づいて課税がなされれば、経済的な実態として二重課税が発生するおそれや、紛争解決手段が有効に機能しないおそれがあるため、「各国・地域におけるユニラテラルな課税は避けるべき」としたうえで「電子経済取引の実態を踏まえ、OECD/G20におけるマルチラテラルな解決に期待する」と提言している。
役員給与税制の見直し 業績連動給与は平成29年度税制改正で算定指標の範囲拡大など拡充が行われた。一方、適正手続要件については抜本的な見直しは行われておらず、例えば、指名委員会等設置会社の場合、報酬委員会の構成員がすべて非業務執行役員であることが求められているなど、活用の阻害となる状況が引き続き残されている(参考1参照)。この点、改訂版コーポレートガバナンス・コードでは、中長期的な業績と連動する報酬の割合を適切に設定すべきことや報酬委員会の活用が要求されており、金融庁のディスクロージャーワーキンググループ報告でも企業価値の向上に向けた経営陣のインセンティブとして業績連動報酬の重要性が再認識されていることから、より一層、業績連動報酬の導入を推進していくことが重要となっている。
このため、指名委員会等設置会社における適正手続要件に関しては、「報酬委員会について非業務執行役員のみで構成されることという要件について、業務執行役員が委員であることの合理性等にかんがみ、非業務執行役員による過半数の賛成で足りる」こととすべきとしている。また、業績連動指標にキャッシュフローや定性的指標を盛り込むことや開示要件について緩和を検討すべきである。
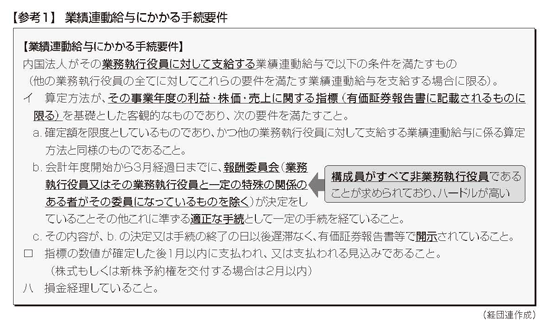
その他の課題 また、提言では、償却資産に係る固定資産税の抜本的見直し、印紙税の廃止・負担軽減、火災保険等に関する異常危険準備金制度の延長・拡充、減耗控除制度の延長・拡充、外航船舶に係る特別償却制度の延長等、地球温暖化対策税の抜本的な見直し、原料用途免税の本則非課税化、NISAの投資可能期間及び非課税保有期間の恒久化、上場株式等の相続税評価額の見直し、教育資金及び結婚子育て資金に係る贈与税の特例の延長、生命保険料控除制度の拡充についても実現を求めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -