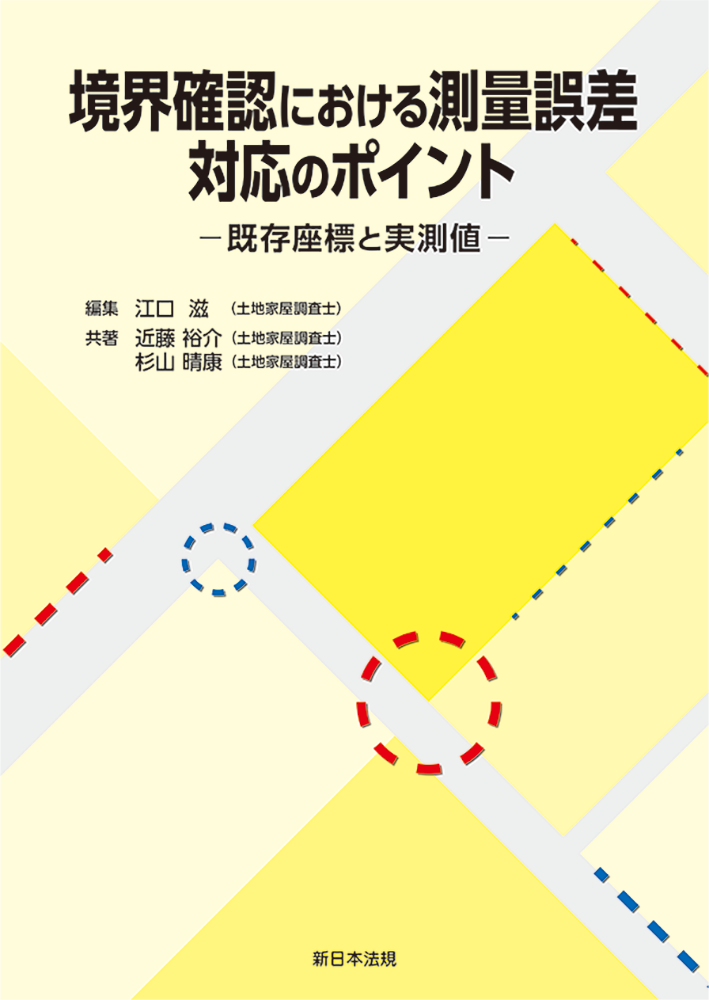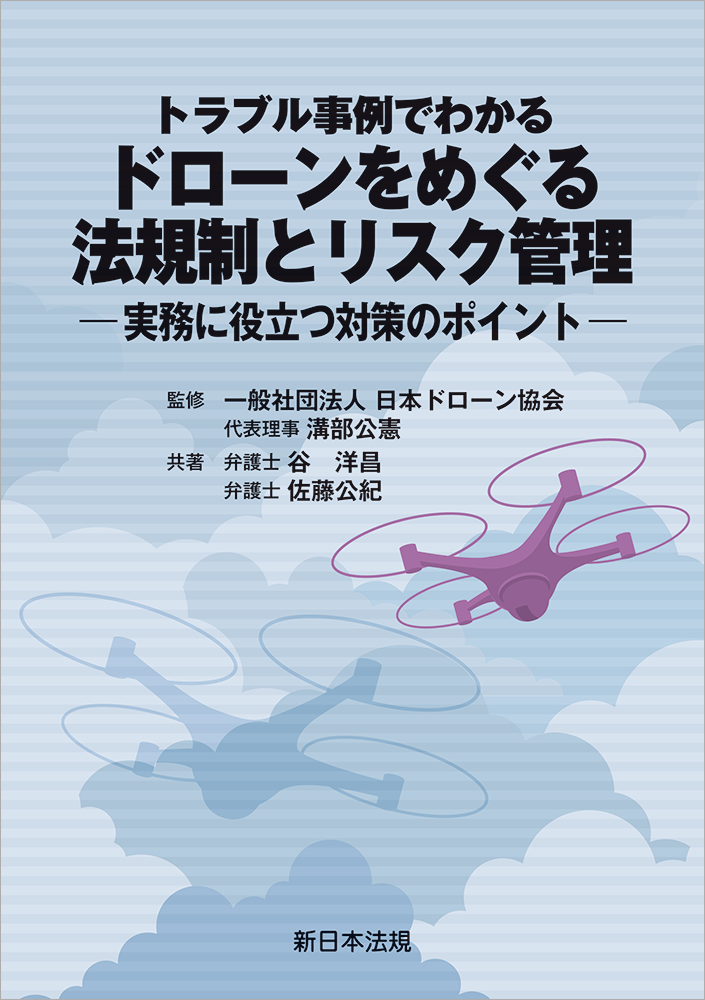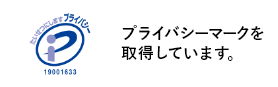解説記事2019年10月21日 ニュース特集 速報 デジタル課税「第1の柱」に関する公開討議草案(2019年10月21日号・№808)
ニュース特集
営業利益率が一定以下でも「基礎的な経済活動」行う現地販社あれば対象も
速報 デジタル課税「第1の柱」に関する公開討議草案
OECDは10月9日、デジタル課税のうちネクサス及び利益配分に関する国際課税原則の見直しを取り扱う「第1の柱」に関する公開討議草案(ディスカッション・ドラフト=DD)を公表した。
5月に公表された作業計画(本誌793号4頁~参照)の段階では、修正残余利益分割法、定式配分法、distribution based approaches(市場国におけるマーケティング・販売・ユーザ関連活動に対し、一定の「ベースライン利益」を配分する手法)が提案されていたが、今回はそれらの統合アプローチが提案されている。
DDでは、課税対象をGAFAに限定せず、採掘、コモディティ、金融業などを除く消費者向けビジネスを行う一定規模以上の多国籍企業グループとすることが明らかになったが、GAFA以外も課税対象となることは日本企業も想定済みだったと言える。注意しなければならないのは、今回提案された3つのアプローチのうち、1つ目のアプローチでは「営業利益率が一定以下」として適用除外とされたとしても、「基礎的な経済活動」を行っている現地販社がある場合には2つ目のアプローチで課税対象となる可能性があるということだ。
本特集では、今回のDDで示された3つのアプローチを解説しつつ、企業にとって留意すべき点、現時点で答えが出ていない注目論点を整理する。
なお、本DDへの意見募集は11月12日に締め切られ、11月初旬には軽課税国への利益移転に対抗する措置である「第2の柱」に関するDDが公表される見込みとなっている。
「消費者向けビジネス」をいかに定義付けるかが焦点に
周知のとおりデジタル課税議論のきっかけとなったのはGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)だが、今回公表されたデジタル課税のうちネクサス及び利益配分に関する国際課税原則の見直しを取り扱う「第1の柱」に関する公開討議草案(ディスカッション・ドラフト=DD)では、GAFAに限定せず、消費者向けビジネス(consumer facing businesses)を行う一定規模以上の多国籍企業グループ(CbCR=国別報告事項を念頭に、連結総収入金額750百万?の閾値を設けることも検討)を課税対象とする方向性が示されている。
もっとも、デジタル課税という新たなルールがGAFA以外にも及ぶことは、日本企業にとって想定内と言える。日本企業の関心事は既に「消費者向けビジネス」の具体的な範囲に移っている。採掘、コモディティ、金融業などは事業の性質上、「市場国への利益配分」との今回の改革の趣旨に馴染まないため、適用除外となる可能性がある模様だが、例えば「消費者向けビジネス」と「事業者向けビジネス」を両方とも行っている企業の場合、両ビジネスをどのように切り分け、新たな課税ルールを適用するのかといった点に対する明確な答えは今のところ示されていない。OECDが「消費者向けビジネス」をいかに定義付けるのかは今後の注目点の一つとなろう。
物理的拠点の有無問わずネクサスを認定、販社経由の販売にも適用
また、新たなルールの下では、市場国における売上高が一定以上の場合、物理的拠点の有無にかかわらずネクサスが認定されることになる。その際、いわゆる小国でも課税ができるよう、市場国の経済規模も考慮される。
企業にとって重要なのは、このルールが、遠隔地からの販売のみならず、市場国の(関連・非関連の)販社経由での販売にも適用されるということだ。この点についてDDでは、ビジネスモデルに中立的な制度と説明されている。
ネクサス
課税の根拠となる結びつきのこと。例えば従来のPE(Permanent Establishment=恒久的施設)では、ネクサスを基本的に「物理的拠点」と捉えているが、デジタルエコノミー(電子経済)は物理的拠点を要しないことから、デジタルエコノミー課税においては、ネクサスの概念そのものが変わる可能性がある。
DDで示された3つの利益配分の方法
公開討議草案では、利益配分の方法としてAmount A,B,Cが一体的に提案されている。具体的には以下の通り。
Amount A
みなし利益率は「10%」が有力
以下の4つのステップで市場国に利益配分を行う。
Step1:トータル利益の特定
多国籍企業グループの連結財務諸表をベースに、利益配分計算の基礎となる「トータル利益」を特定する。
トータル利益というと、企業にとっては「営業利益」が頭に浮かぶところだろう。しかし、現時点ではトータル利益の具体的な定義は確定しているわけではなく、今後の議論となる。
また、会計基準の違いという問題もある。IFRSやUS・GAAPなど各企業が様々な会計基準を採用している中、採用している会計基準によって「トータル利益」の額が異なる可能性もある。また、会計上のトータル利益と税務上のトータル利益が異なることもあろう。DDでは、会計基準の違いに起因する差異等については一定の調整が必要になる可能性が指摘されている。
このほか、多国籍企業グループ全体の利益とするのか、あるいは特定のビジネスラインごとの利益とするのかについても今後検討が必要とされている。これに対し企業からは、仮に後者が採用された場合、セグメント損益の切り出しが容易ではないのではないかとの懸念の声が上がっている。
Step2:みなし通常利益の除外(みなし残余利益の抽出)
Step1で特定したトータル利益から「みなし通常利益」を除外し、「みなし残余利益」を抽出する。
「みなし通常利益」の算定にあたっては、一定の「みなし利益率」を設定する。先進国では10%とする案が有力視されているが、途上国等はまだこれに合意していない模様。仮にみなし利益率を10%とすると、例えば利益率が25%の多国籍企業グループであれば、利益率10%の部分までが通常利益、それを除外した15%部分が残余利益となる。利益率が10%以下であれば、残余利益はゼロとなる。
みなし利益率が営業利益の10%に設定された場合、日本企業では、自動車メーカーや一部の電機メーカーが適用除外となる可能性がある一方、多くの製薬会社、一部のIT企業、建機メーカー、化粧品会社など、適用対象となる日本企業も出てくる模様。適用対象となる可能性が高い企業からは、「唐突」との声も聞かれる。
Step3:みなし残余利益のうち一定部分の配分
残余利益といっても、それがすべてマーケティング無形資産(商標、顧客データ、独自の市場など、商品やサービスの販売・マーケティングに使用されたり、その一助となる無形資産)に起因するものではない。研究開発活動などに関連する営業上の無形資産(trade intangible)等の貢献もある。
そこで、みなし残余利益のうち市場国に実際に配分すべき金額としては、みなし残余利益の一定割合とする案が検討されている。例えばこれを残余利益の10%とした場合、「15%×10%=1.5%」相当分が市場国に配分されるべき額となる。
研究開発活動に熱心な日本企業としては、この一定割合はできるだけ低くしたいところ(税収の逸失を防ぎたい日本政府も同じ立場のはずである)。一方、市場国側としては、できるだけ自国に税収が入るよう割合を高く設定したいのは言うまでもない。この「一定割合」を巡っては激しい議論が予想される。
Step4:みなし残余利益を「売上」に基づき市場国に配分
Step2によって計算されたみなし残余利益の一定部分を「売上」に基づいて市場国に配分する案が検討されている。もっとも、一口に「売上」と言っても何をもって売上とするかは議論が必要になる。製品等の最終ユーザの所在地も踏まえたところで売上を決定するとなると、数値を追い切れない企業が出てくることが予想される。
途上国による源泉徴収に不安を抱く企業
このようにAmount Aは、残余利益に着目するという意味で修正残余利益分割法の要素を有していると言え、また、割り切りで計算するという意味では定式配分の要素を有していると言えよう。
また、Amount Aでは、執行の方法として源泉徴収に言及しているが、ひとたび源泉徴収されると、途上国は還付をしない、または還付に時間がかかる等の問題がある。DDでは、源泉徴収を行う場合のルールを定めておく必要性を指摘しているものの、企業としては気になる点であろう。
このほか、各市場国に配分されるべき額が特定されたとして、それを「誰が」申告・納付するのかは今後の課題となる。この点については、親会社、高収益企業、重要な知的財産(IP=intellectual property)を有する企業など様々なオプションが浮上している。加えて、「誰に」申告・納付するのかについては、既に現地に子会社等を有する場合は、追加的に親会社等のネクサスを認定する必要性は乏しいのではないかとの意見もある。
Amount B
地域統括会社が商流・物流に関与する場合の利益配分など異論噴出
この提案は、要するに「基礎的な経済活動(baseline activity)」を行っている現地販社に対して利益の一定保証(例えば売上×固定比率)を行おうというもの。現地販社の利益率の適正性を巡っては、課税当局と企業の間で常に争いがあるだけに、税の安定性を高めるための提案とも説明されている。Distribution Based Approaches(市場国におけるマーケティング・販売・ユーザ関連活動に対し、一定の「ベースライン利益」を配分する手法)の発想に近いものと言える。
要注意なのは、Amount Aにおいて適用除外となる企業(利益率が一定以下の企業)であっても、Amount Bでは捕捉される可能性があるという点だ。
今後は、「基礎的な経済活動」の意義が論点となる見込みだが、日本企業からは戸惑いの声も聞かれる。具体的には、「子会社(現地販社)が仕事に不熱心でも利益の最低保証ということになると、子会社は業績を上げるインセンティブがなくなり、いかがなものか」「そもそも利益率1パーセント以下のコンマの世界で営業している子会社もある中で(売り上げの数パーセント等の)利益率保証を行えば、ビジネスをかなり歪ませることになる」「親会社と販社という単純なビジネスモデルだけではない。その間に地域統括会社が商流・物流に関与している場合は、それぞれどのように利益を分け合うのか」「最低保証を行うとした場合、誰が面倒を見るのか。親会社か」といったものだ。
このようにAmount Aで適用除外となる企業が捕捉される可能性がある上に様々な意見が渦巻くAmount Bも、日本企業にとっては無視できない重要な論点となる。
Amount C
基礎的活動以上の経済活動がなされれば追加的な利益配分も
Amount Cでは、市場国でAmount Bの基礎的活動以上の経済活動がなされている場合、その市場国が課税権を行使できるよう担保することとなる。
Amount Bで利益の最低保証を行って終わりということではなく、当該販社の機能によっては、追加的な利益を配分することがあり得るということである。
多国間の紛争解決メカニズムは不可欠
Amount Cを含め、上記提案におけるすべての要素に関係した紛争は、適切、かつ強力な二重課税防止及び紛争解決策に服することとなる。DDではICAP(本誌789号9頁参照)や仲裁の有用性が問われている。企業からも、仲裁はもとより、多国間の紛争解決メカニズムが不可欠との声が上がっている。
なお、今回公表されたDDは「第1の柱」に関するものであり、軽課税国への利益移転に対抗する措置である「第2の柱」に関するDDは11月初旬に公表される予定となっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -