解説記事2021年09月06日 税務マエストロ 日本型インボイス制度(1)(2021年9月6日号・№896)
税務マエストロ
日本型インボイス制度(1)
#264
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間中に、仕入税額控除の適用要件として保存が義務付けられる「区分記載請求書等」には、従来の請求書等の記載事項に加え、「軽減税率対象品目である旨」と「税率区分ごとの合計請求額」の追加記載が義務付けられている。これに加え、令和5年10月1日以後に保存と発行が義務付けられる「適格請求書等」には、さらに「登録番号」と「税率区分ごとの消費税額等」を記載することとされている。
今月からは、いよいよ本番を迎える適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)について実務上のポイントを確認する。
※ 表記する条文番号は、令和5年10月1日施行の法令通達に基づいている。
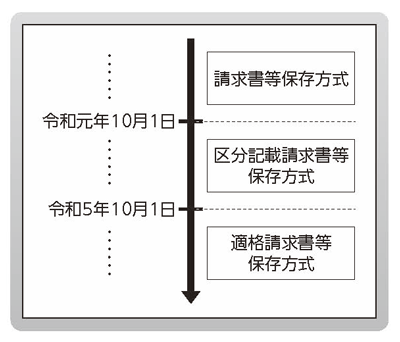
1 適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者登録制度を創設し、令和5年10月1日以降の取引については、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となる(消法30⑦〜⑨)。
(1)適格請求書発行事業者とは?
「適格請求書発行事業者」とは、納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいう(消法2①七の二)。
なお、e-Taxを利用して登録申請書を提出した場合には、登録の通知もe-Taxにより行われることになる(インボイスQ&A問2)。
(2)登録申請
適格請求書発行事業者の登録は、令和3年10月1日からその申請を受け付けることとしているので、令和5年10月1日前であっても申請書を提出することができる(平成28年改正法附則1八)。
事業者は、登録をしなければ適格請求書を発行することはできない。したがって、適格請求書の記載事項を確認したうえで、オリジナルの適格請求書の雛形を決定するなどの事前の準備が必要となる。
課税事業者であっても登録をしなければ適格請求書発行事業者になることはできない。よって、適格請求書を発行する必要がない課税事業者は、あえて登録する必要はない。
ただし、課税事業者が適格請求書の登録をしなかったからといって、納税義務が免除されるわけではないので注意が必要だ。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となったうえで登録申請をする必要がある。
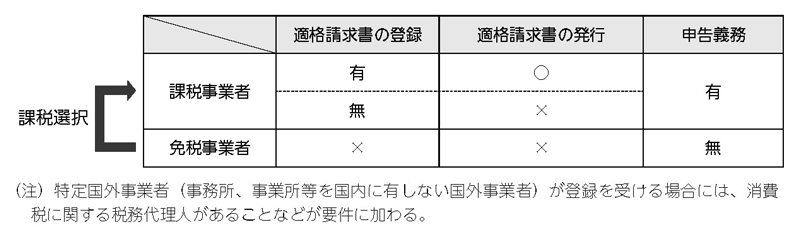
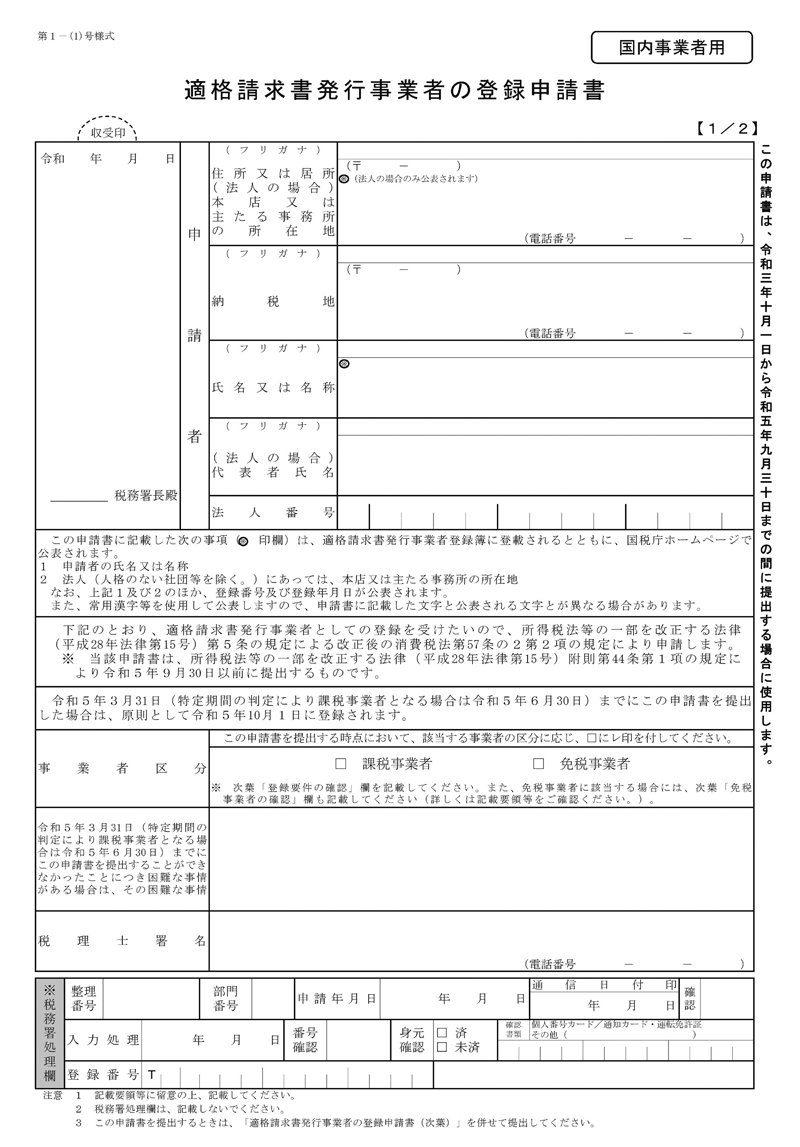
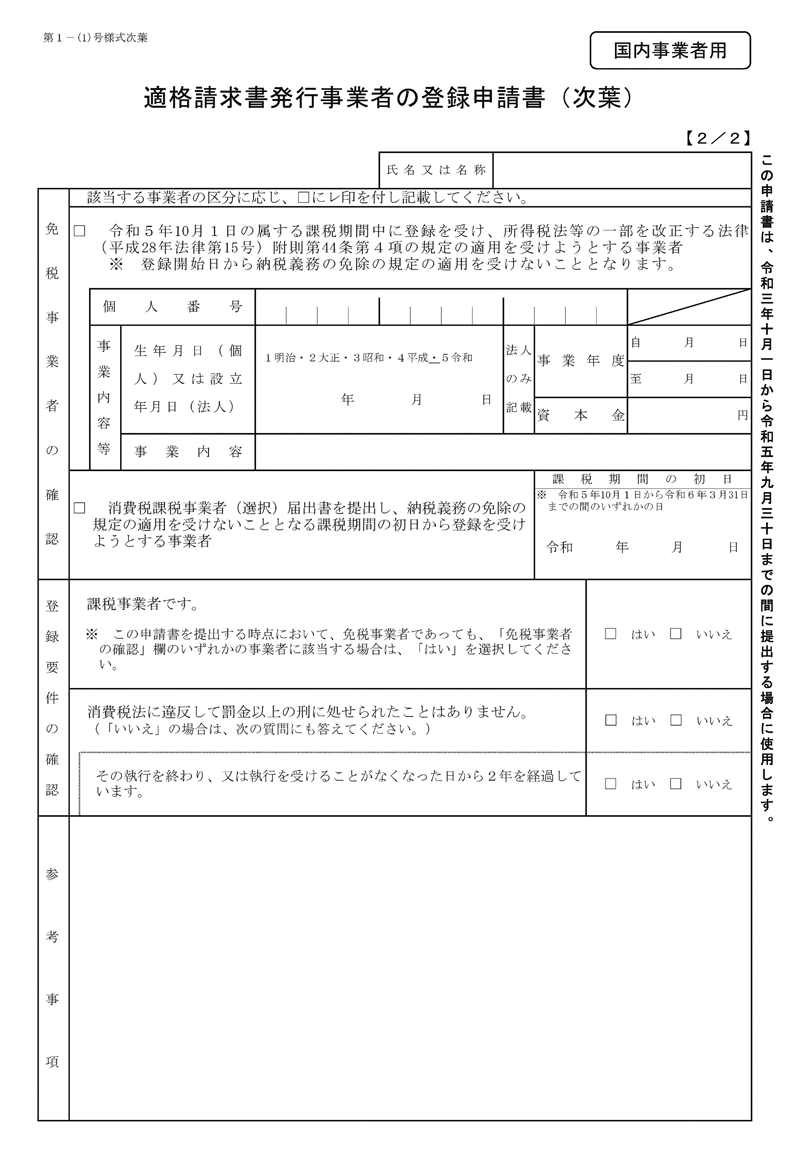
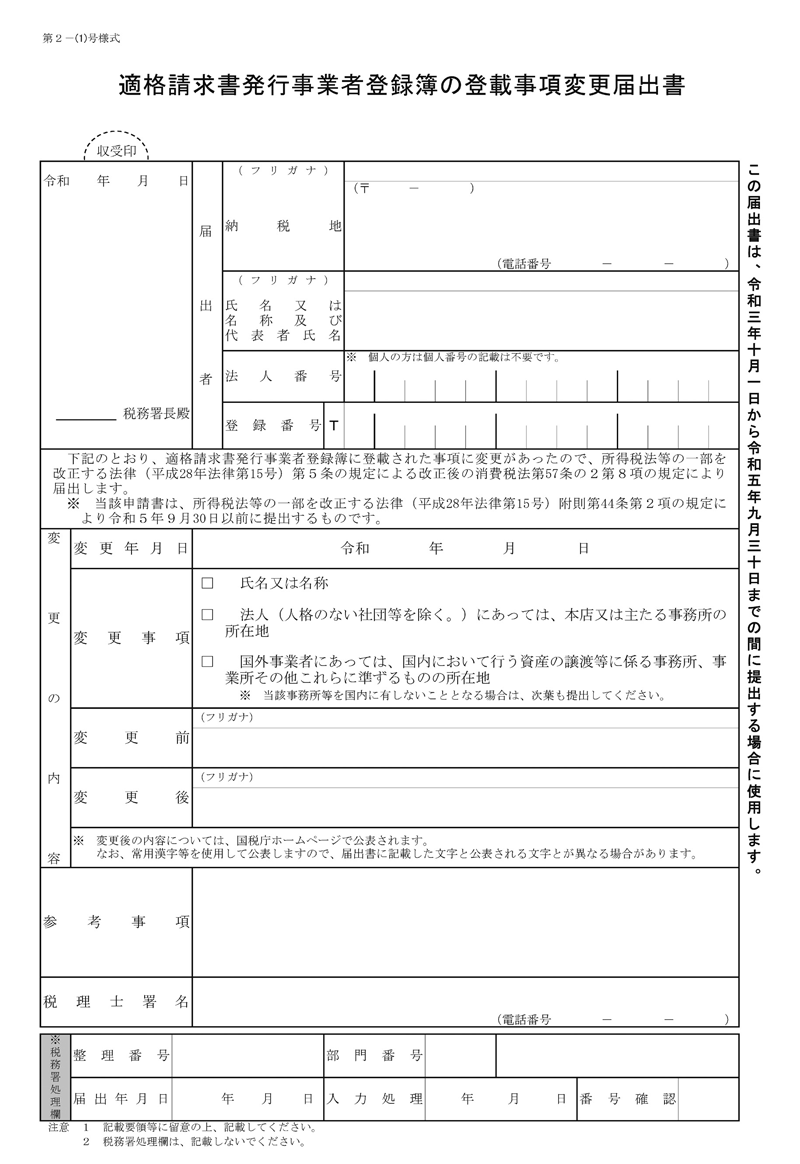
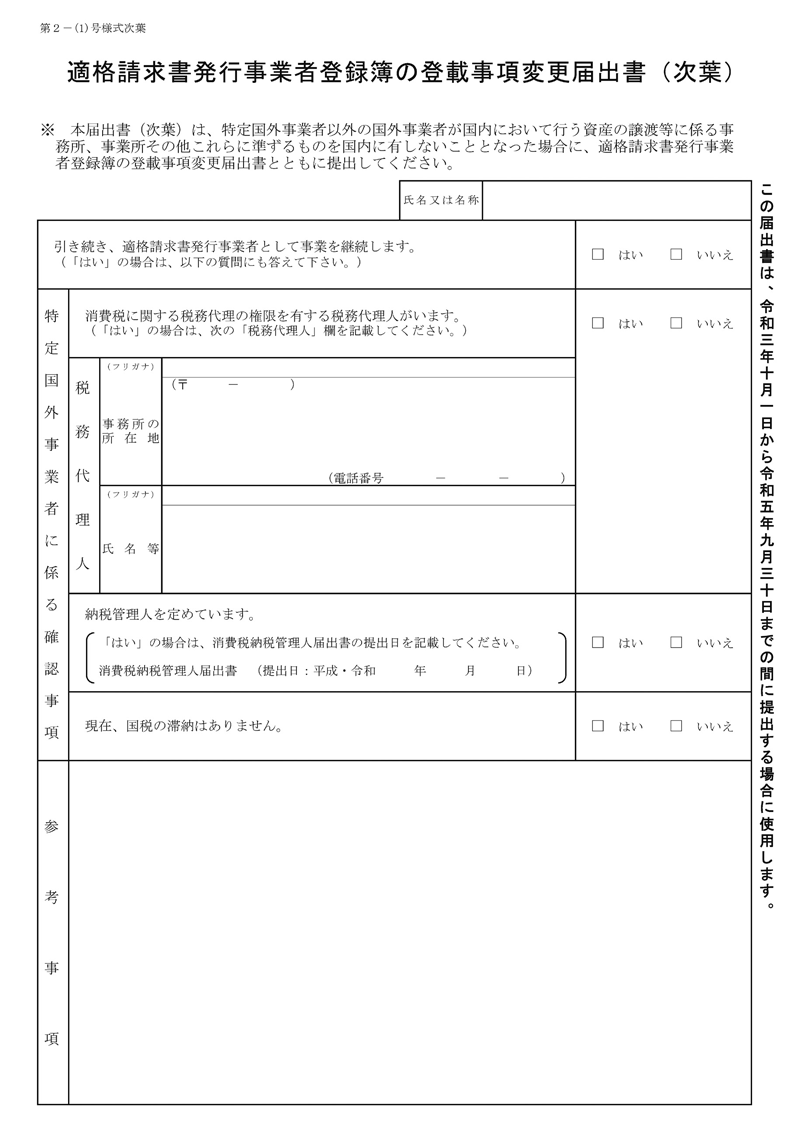
2 登録期限と登録の効力(消法57の2、平成28年改正法附則44②)
登録申請がされた場合には、税務署長は、法律違反などの理由により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく登録し、書面により通知することが義務付けられている。また、「適格請求書発行事業者」は、「適格請求書発行事業者登録簿」に登載された事項に変更があった場合には、速やかに「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出することとされている。
(1)課税事業者が登録申請をした場合
課税事業者が登録申請書を税務署長に提出し、登録申請をした場合には、登録後の期間について、適格請求書発行事業者として適格請求書を発行することが認められる。したがって、通知がされるまでの間は登録番号がないので、当然のことながら「適格請求書発行事業者」となることはできない。
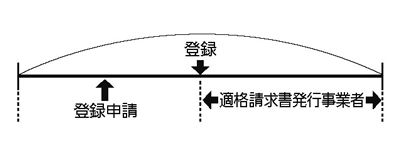
(2)登録の効力(インボイス通達2−4・インボイスQ&A問5、31)
適格請求書発行事業者の登録の効力は登録日から発生する。そこで、登録日から登録の通知を受けるまでの間に交付した請求書等について、後日、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載した書面等を取引先に通知することにより、適格請求書の記載事項を満たす書類とすることができる。
なお、後から通知する書面の内容は、既に交付した書類との相互の関連が明確であり、取引先が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限られる。
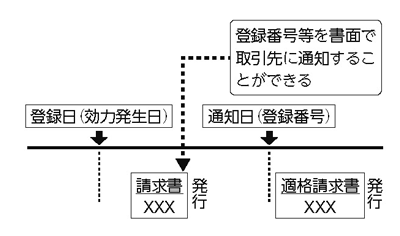
(3)免税事業者が課税事業者になる場合(消法57の2②、消令70の2)
免税事業者が課税事業者を選択する場合には、期限までに「課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要がある。
また、基準期間(特定期間)中の課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者は、「課税事業者届出書」の提出が義務付けられている。このようなケースにおいて、免税事業者が、課税事業者となる課税期間の初日から「適格請求書発行事業者」になろうとするときは、課税期間の初日の1か月前の日までに登録申請書を税務署長に提出する必要がある。
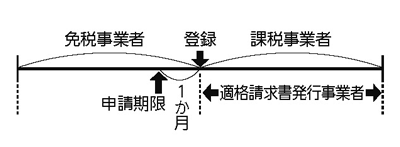
(4)新規開業等の場合(消令70の4、平成30年改正令附則13、消規26の4)
下記①〜③の課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、登録申請書を課税期間の末日までに提出することにより、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなされる。
① 新規に開業した日の属する課税期間
ただし、相続により適格請求書発行事業者である被相続人の事業を承継した相続人は対象とならない。
② 吸収合併により、 適格請求書発行事業者である被合併法人の事業を承継した合併法人の合併があった日の属する課税期間
③ 吸収分割により、適格請求書発行事業者である分割法人の事業を承継した分割承継法人の吸収分割があった日の属する課税期間
この場合において、上記①〜③の課税期間の初日が令和5年10月1日の前日以前であるときは、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる。
3 相続による事業承継
適格請求書発行事業者である個人事業者が死亡した場合には、相続人は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を税務署長に提出することが義務付けられている。また、被相続人の適格請求書の登録の効力は、事業を承継した相続人がいる場合といない場合に区分して前頁下のように取り扱うこととされている(消法57の3①〜④)。
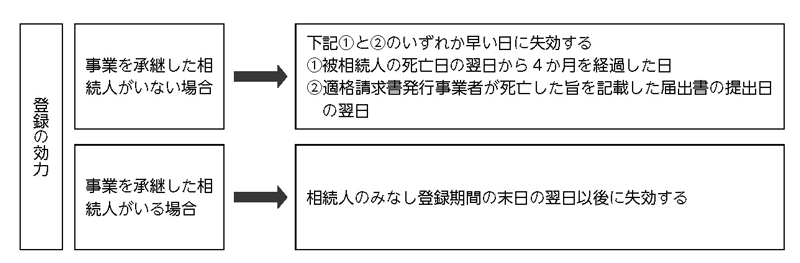
なお、被合併法人や分割法人が受けた適格請求書発行事業者の登録の効力は、合併法人や分割承継法人には引き継がれない。したがって、合併法人や分割承継法人が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするときは、新たに登録申請書を提出する必要がある(インボイス通達2−7)。
(1)事業を承継した相続人がいる場合の取扱い
事業を承継した相続人がいる場合には、みなし登録期間中は、相続人を適格請求書発行事業者とみなし、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなす(消法57の3③④)。
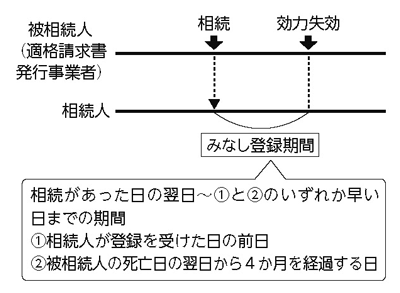
この場合において、相続人がみなし登録期間経過後も適格請求書を交付しようとするときは、新たに登録申請書を提出して登録を受ける必要がある。
また、相続人がみなし登録期間中に登録申請書を提出した場合において、みなし登録期間の末日までに登録または処分の通知がないときは、通知が相続人に到達するまでの期間はみなし登録期間とされ、適格請求書の交付は被相続人の登録番号によることとなる(消令70の6②、インボイス通達2−6)。
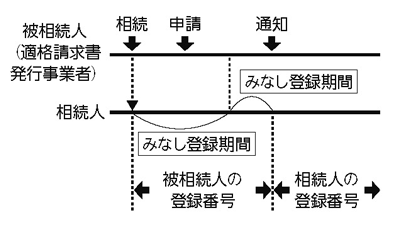
(2)被相続人が登録取り消しの届出書を提出後に死亡した場合の取扱い
被相続人が登録取り消しの届出書を提出後に死亡した場合には、みなし登録期間中は、相続人を適格請求書発行事業者とみなし、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなす(消令70の7)。
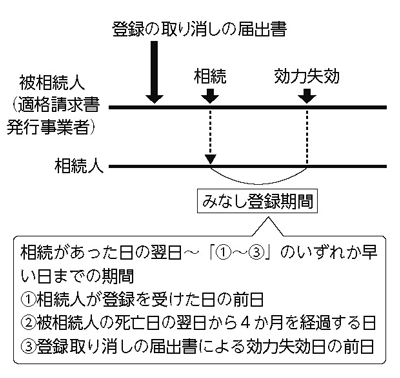
(3)相続人が免税事業者の場合の棚卸資産の税額調整
相続人が免税事業者の場合には、みなし登録期間の初日の前日において保有する棚卸資産に係る消費税額を課税仕入れ等の税額に加算することができる(消令70の8①)。
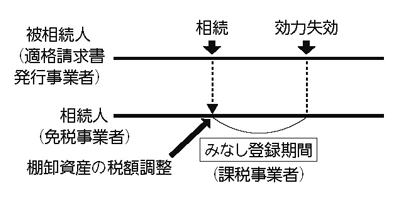
(4)相続人が免税事業者になる場合の棚卸資産の税額調整
相続人がみなし登録期間の末日の翌日から免税事業者となる場合には、みなし登録期間の末日において保有する棚卸資産のうち、みなし登録期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、課税仕入れ等の税額から控除することとされている(消令70の8②)。
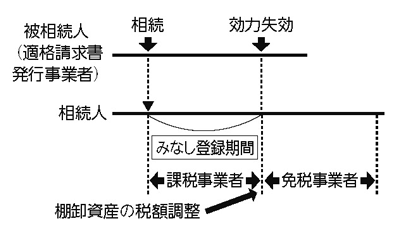
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























