解説記事2021年11月01日 税務マエストロ 日本型インボイス制度(3)(2021年11月1日号・№904)
税務マエストロ
日本型インボイス制度(3)
#266
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
今回は、インボイスの記載事項や消費税額等の端数処理、ケース別の表示方法などについて確認する。
1 適格請求書
(1)適格請求書の記載事項(消法57の4①、消令70の10)
「適格請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう(太字が追加項目)。
(記載事項)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
⑤ 税抜(税込)取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥ ⑤に対する消費税額等及び適用税率
⑦ 請求書等受領者の氏名又は名称
<注意>
上記⑥の「消費税額等」とは、消費税額及び地方消費税額の合計額をいい、次のいずれかの方法で計算した金額とし、消費税額等の計算において1円未満の端数が生じた場合には、税率の異なるごとに当該端数を処理する。
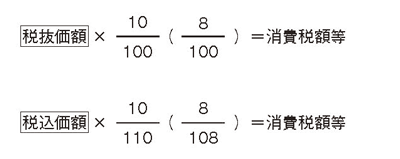
※ 消費税額等の端数処理は請求書単位で行うので、複数の商品の販売につき、一の商品ごとに端数処理をした上で合計することはできないが、端数処理の方法は、切上げ、切捨て、四捨五入などの任意の方法によることができる(インボイス通達3-12・インボイスQ&A問37)。
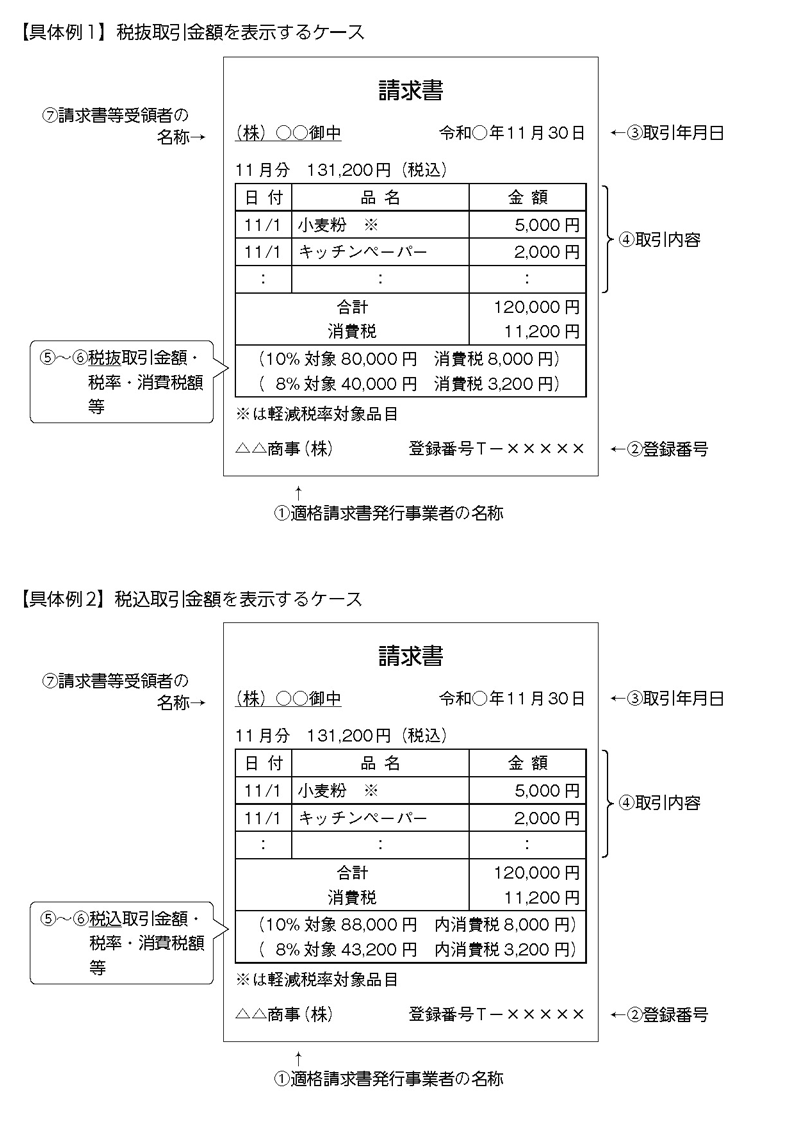
(2)適格請求書の名称と記載方法等(インボイス通達3-1、3-3・インボイスQ&A問25、26、44、45)
「適格請求書」とは、登録番号などの法定事項が記載された書類の法律上の名称であり、実務で使用する書類にまでこの名称を用いる必要はない。
中小企業であれば、手書きの領収書を交付しても何ら問題ないし、電話番号などで事業者が特定できる場合には、屋号や省略した名称を記載しても構わない。
また、一の書類に全ての事項を記載する必要もないので、納品書や請求書など、複数の書類全体で記載事項を満たしていれば適格請求書として認められることになる。
適格請求書に記載する売手(買手)の名称や登録番号、取引内容などについては、取引先コード、商品コード等の記号、番号等による表示によることもできるが、下記の①と②に注意する必要がある。
① 売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合のコード表の修正
② 売手が適格請求書発行事業者である期間の確認などの措置
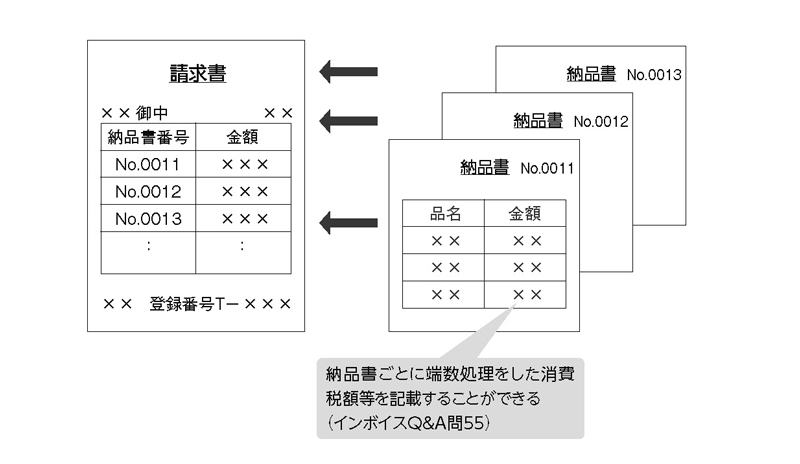
2 適格簡易請求書(消法57の4②、消令70の11)
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等のように不特定多数を取引先とする事業を営む場合には、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」を交付することができる。
「適格簡易請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう(太字が追加項目)。
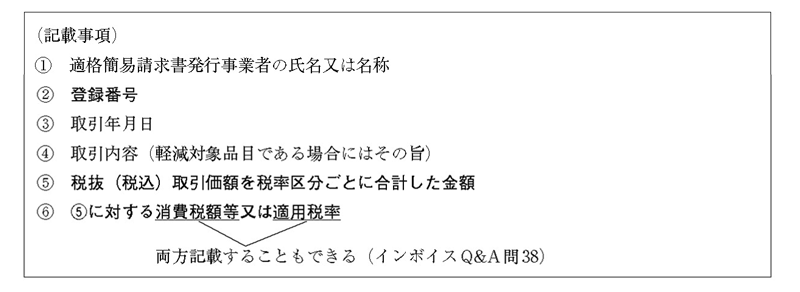
「適格簡易請求書」には、「請求書等受領者の名称」を記載する必要がない。また、消費税額等又は適用税率のいずれかの記載でよいこととされているので、スーパーやタクシーなどのレシートに登録番号、税率などを記載して、適格簡易請求書として利用することができる。
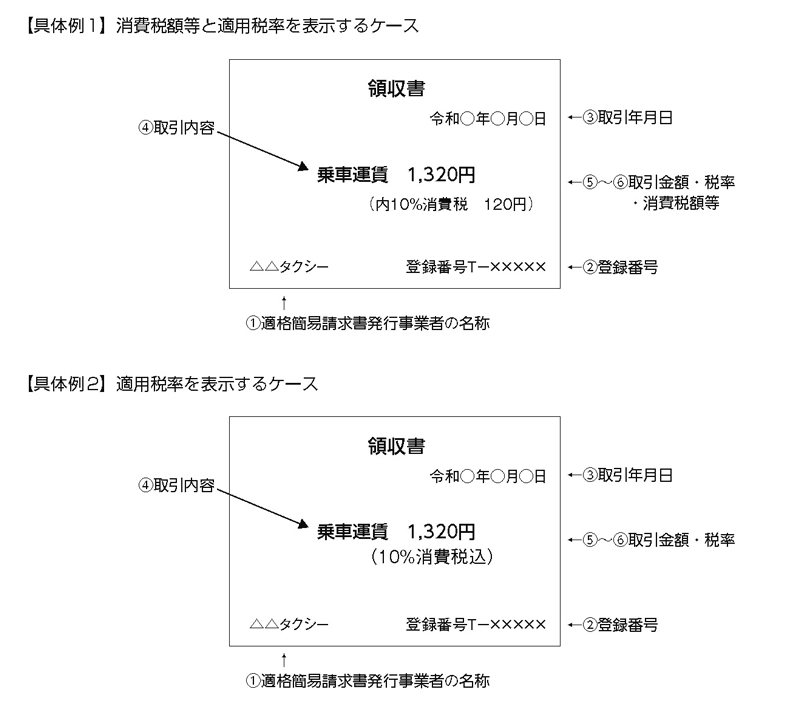
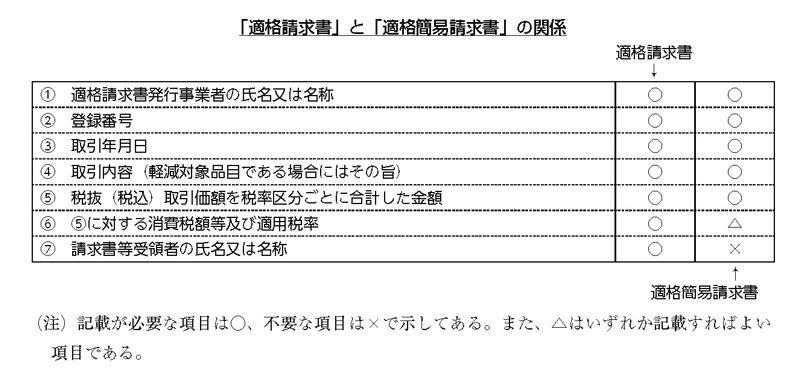
□税込価額と税抜価額が混在するレシートの表記方法
消費税額等の端数処理は、領収証単位で行うこととされている。よって、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在する場合には、税抜価額か税込価額に統一して代金を記載するとともに、これに基づいて算出した消費税額等を記載する必要がある。
なお、税抜(税込)価額を税込(税抜)価額に修正する場合の端数処理については特段の定めはないことから、事業者が任意に算出することが認められている(インボイスQ&A 問48)。
【具体例】
税込600円のたばこを税抜価額にする場合には、円未満の端数を切り捨て又は四捨五入にすると545円、切り上げにすると546円となるが、どちらの表記も認められることになる。
600円×100 / 110≒545.45……
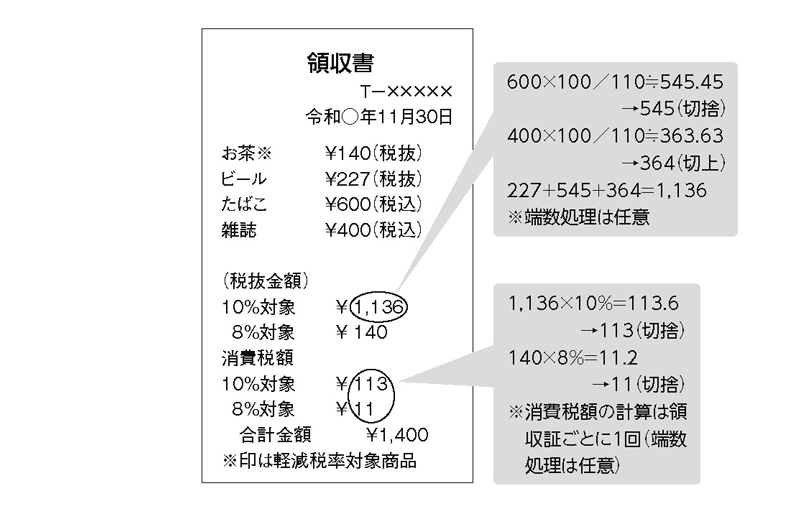
□一括値引がある場合の計算方法(1)
割引券等による一括値引をした場合において、適用税率ごとの値引額が明らかでないときは、値引前の価額によりあん分計算する(インボイスQ&A問56)。
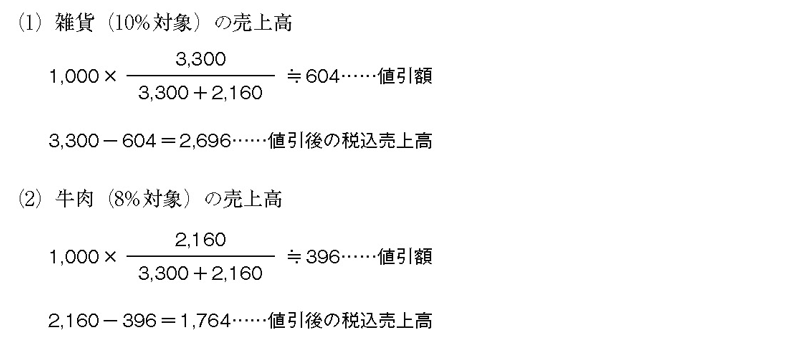
レシート(簡易インボイス)には、値引後の適用税率ごとの売上高を表示する必要があるので、表示方法としては、例えば次のようなものが想定される(インボイスQ&A問56)。
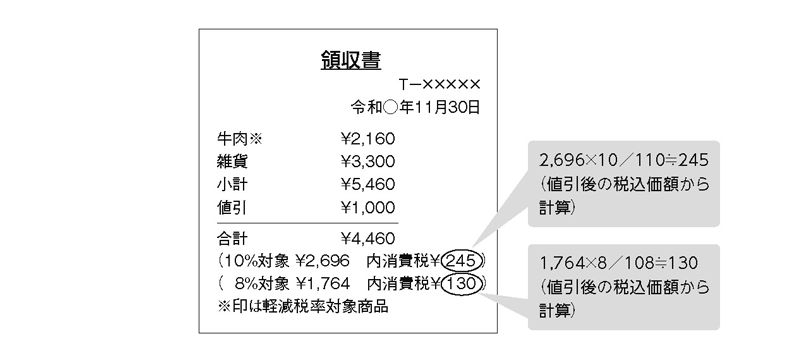
また、上記の記載方法では値引額の内訳がわからないので、税率ごとの値引前の税込(税抜)売上高と値引額を記載することもできる。
この場合の値引額は、次の算式により計算する。
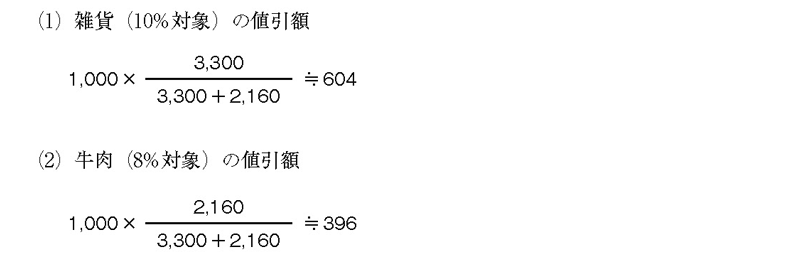
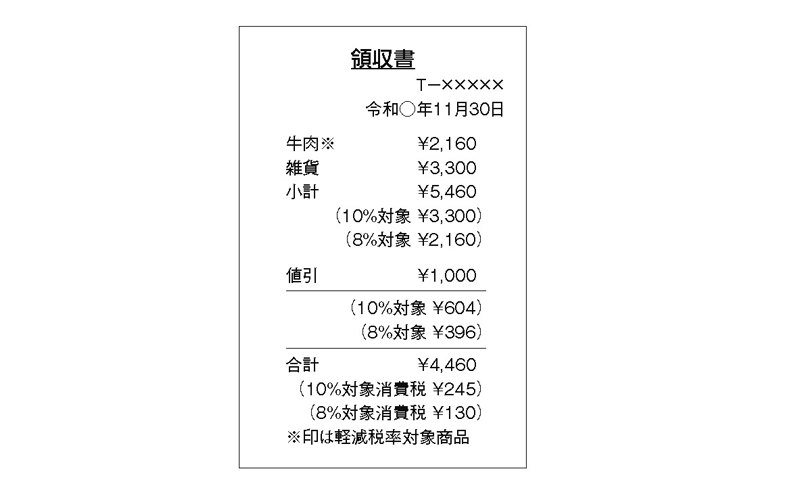
□一括値引がある場合の計算方法(2)
顧客から割引券をすべて雑貨の購入代金に使用したいと申出があった場合のレシートの記載方法
は、値引後の価額が明らかにされているので次のような表示になる。
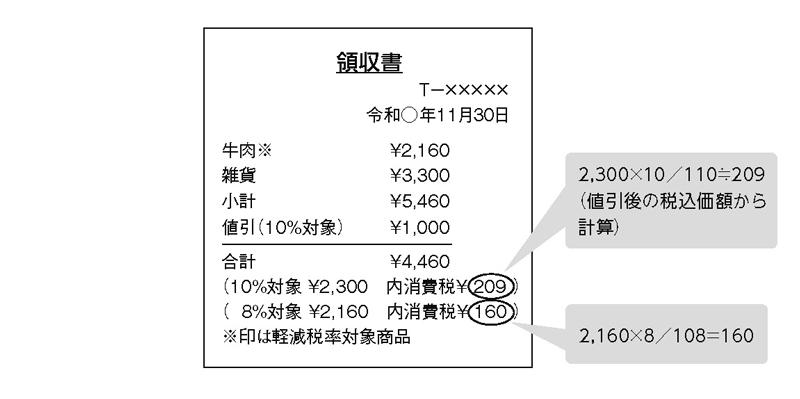
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























