解説記事2022年01月31日 巻頭特集 令和4年度税制改正(2022年1月31日号・№916) ウィズコロナ・ポストコロナ時代における企業変革に向けて
巻頭特集
令和4年度税制改正
ウィズコロナ・ポストコロナ時代における企業変革に向けて
一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 秋本潤一郞
岸田政権発足後初となる税制改正が行われる。「新しい資本主義」、「成長と分配の好循環」の実現という政権の大目標の下で、令和4年度税制改正の動向は、政権・与党の政策の方向性をうらなう試金石として、例年にも増して耳目を集めた。本稿においては、主に法人税制関係の見直し事項を解説しながら、それらに散りばめられた「メッセージ」を紐解いた上で、来年度改正以降を展望していくこととしたい。なお、本稿の記載事項は、2022年1月19日時点の情報に基づいており、今後法令等により変更が生じうる。全ては筆者個人の見解であり、所属組織を代表したものではないことを予めお断りしておく。
1.異例の「期待」
令和4年度与党税制改正大綱(2021年12月10日)における「未来への投資等に向けた経済界への期待」と題する一節は、法人税制をフォローする者にとって、大変な驚きをもって受け止められた。それは、わが国の賃金水準や、人的資本や無形資産への投資の状況等に対する指摘が行われた後に、「近年の累次の法人税改革も、意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ない」と断じられているためである。同節では、更に企業がアニマルスピリッツを取り戻し、イノベーションに挑戦することへの期待が述べられた上で、次のように締めくくられている。
来年以降、経済界の取組状況等も見極めつつ、積極的に未来への投資に取り組む企業に対しては真に有効な支援を行うとともに、十分な投資余力があるにもかかわらず活用されていない場合に、企業の行動変容を促すためにどのような対応を講ずるべきかといった視点からも、幅広く検討を行う。
こうした与党税調からのメッセージは、法人税制と企業行動、あるいは自由経済と産業政策の関係性にも根源的な疑問を投げかけているように思われる。与党からの宿題事項を真摯に受け止めた上で、企業・経済界が、税負担・事務負担の軽減を通じて、何を実現したいのかをより説得力のある形で訴求していくことが来年度改正以降においても重要なポイントとなるだろう。
2.賃上げ促進税制の抜本的強化
(1)改正の背景
新政権下の「成長と分配の好循環」の実現に向けた重要施策として、賃上げ促進税制のデザインを巡る議論が急ピッチで行われた。とりわけ、大企業向けの現行措置である「人材確保等促進税制」の拡充のあり方が今回の改正の大きな焦点となった。
もともと、「人材確保等促進税制」は、令和2年度までの中堅・大企業向け賃上げ税制の適用期限を延長した上で、適用要件及び税額控除対象額を新規雇用者(新卒・中途双方を含む)に着目した形で、令和3年度税制改正で縮小改組したものだった。これには、同改正におけるカーボンニュートラル(CN)、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制や、欠損金の繰越控除制度の特例措置の創設に伴う財源確保という意味合いもあった。
このため、「人材確保等促進税制」について、財源見合いで、どのように拡充するのかという点に当初注目が集まった。大きな方向性を決定づけたのは、政府の新しい資本主義実現会議の「緊急提言〜未来を切り拓く『新しい資本主義』とその起動に向けて〜」(2021年11月8日)であろう。同提言では、賃上げに積極的な企業への税制措置について、次の方向性が示された。
・新規雇用者ではなく、継続雇用者の1人当たり給与の増加を要件とすること
・非正規雇用を含めて全雇用者の給与総額の増加を対象とすること
・賃上げに積極的な企業に対する税額控除率を引き上げること
これを受けて、11月中旬より本格化した与党税制調査会での議論では、①継続雇用者の一人当たり給与は基本給のみを見るべきか、賞与も含めるべきか、②大企業の適用に対し、更なる要件設定を行うべきかという点に力点が置かれるようになった。とりわけ、②は水面下において最も議論が集中した点である。より具体的には、仮に大企業が税制措置を利用するならば、当該企業が従業員や取引先を含むマルチステークホルダーへの配慮を行うことを「宣言」し、世の中に示すことが必要ではないかという強い問題意識が存在した。後述の通り、給与等の引き上げ方針及び取引先との適切な関係構築等に係る「宣言」を公表し、かつ経済産業大臣に届出を行う要件設定を巡っては、当該要件の要否を含めて、関係企業・団体の調整が続けられた後、一定の決着を見た。
(2)改正後の制度の概要
以下では、国税に焦点を当てて、中堅・大企業、中小企業別の見直し内容を解説する。
① 「人材確保等促進税制」の改組・拡充(中堅・大企業向け)
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である場合には、控除対象雇用者給与等支給額の15%の税額控除が可能な制度とされた。各用語の定義について、現時点では次の通りとなる。
継続雇用者給与等支給額:
継続雇用者(前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者であり、かつ前事業年度及び適用年度の全て又は一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者を指す。)に対する給与等支給額を指す。
継続雇用者比較給与等支給額:
前期の継続雇用者給与等支給額
給与等支給額:
国内雇用者(法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指す。パート、アルバイト、日雇い労働者は含まれるが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれず。)に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与所得)を指す。退職金等、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当せず。)の支給額を指す。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除する。
控除対象雇用者給与等支給額:
全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、適用年度の給与等支給額から前年度の給与等支給額を控除した額を指す。
仮に、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、税額控除率に10%を加算し、教育訓練費(外部講師謝金、外部施設使用料等、研修委託費等、外部研修参加費等が該当)の額の比較教育訓練費の増加割合が20%以上であるときは、税額控除率に5%を加算する。なお、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存が不可欠となる。
上記から、税額控除率は最大で30%となるものの、控除税額自体の上限は当期法人税額の20%のままであることには留意が必要である。
これに加えて、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、更なる要件が課される。すなわち、給与等の支給額の引き上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出なければいけない。
当該要件の詳細自体は、本稿執筆時点においても調整が続けられているものの、手続き自体は、概ね次の通りと考えられる。
・税制利用企業は、自社のウェブサイト上に「宣言」を掲載し、その旨を経済産業省に届出
・経済産業省は、ウェブサイト掲載の事実を確認の上、受理通知書を企業に発行
・企業が受理通知書を確定申告時に添付
「宣言」に関しては、数値目標等の定量的事項の記載までは求められない見通しである。その一方で、その公表時期に加えて、ひな型を設ける場合にはどの程度記載内容の自由度があるのか等の重要論点が依然として残っていると見られる。とりわけ、前者の公表時期が税制の適用年度中のみとなった場合に、当該税制の適用有無を判断できないままに、「宣言」の公表を決定する必要が生じうる。なお、経済産業省のウェブサイトによれば、詳細情報は、租税特別措置法等が成立し、制度内容が確定次第、本年5月頃に同省ウェブサイトに公表される見込みである。
② 所得拡大促進税制の延長・拡充(中小企業向け)
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上である場合に、控除対象雇用者給与等支給額の15%を税額控除する枠組みを維持した上で、適用期限を1年間延長することとなった。その上で、税額控除率の上乗せ措置は、次の通り拡充された。
・雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算。
・教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算。
これにより、税額控除率は最大40%となる。なお、控除上限は、大企業向けと同様に当期法人税額の20%となる。
上記①、②の見直し後の制度の全体像は、図表1の通りとなる。
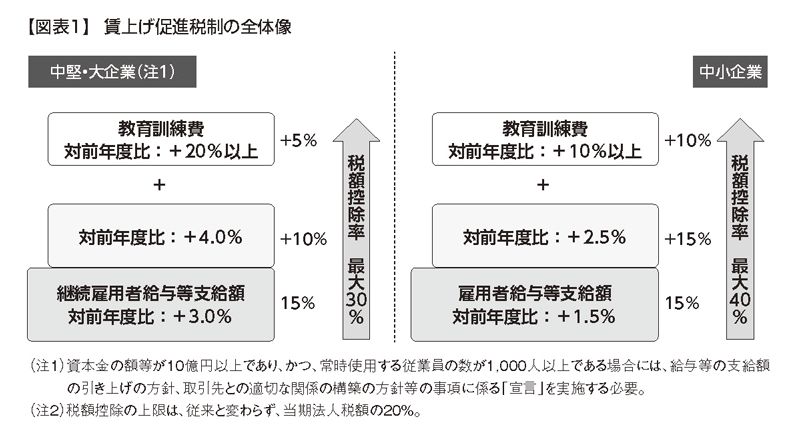
なお、地方税において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できる措置等が講じられる。その一方で、大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率について、年400万円以下の所得部分及び年400万円超800万円以下の所得部分の見直しも行われる。
(3)ムチ税制(特定税額控除規定の不適用措置)の一部強化
収益が向上しているにもかかわらず賃上げにも投資にも積極的ではない大企業は研究開発税制等の一定の租税特別措置(特定税額控除規定)を利用することができず、ムチ税制と呼称される。
具体的には、大企業(研究開発税制における中小企業者等に該当しない法人)は、次の要件の全てに該当する場合、特定税額控除の規定(研究開発税制、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制等)を適用することができない。
① 所得金額が前年度の所得金額を上回ること
② その大企業の継続雇用者の給与総額が前事業年度の継続雇用者の給与総額以下であること
③ その大企業の国内設備投資額が当期減価償却費の3割の金額以下にとどまること
上述の賃上げ促進税制の抜本的強化により、インセンティブを拡充する一方で、賃上げに積極的ではない企業のディスインセンティブの強化として、一部要件が厳格化されることとなった。
すなわち、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、継続雇用者給与等支給額に係る要件(上記②の要件)を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(令和4年度は0.5%以上)に達していないこととした。なお、一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含む。
図表2の【要件1】及び【要件2】のいずれにも該当する場合には、上記②の要件が強化される。
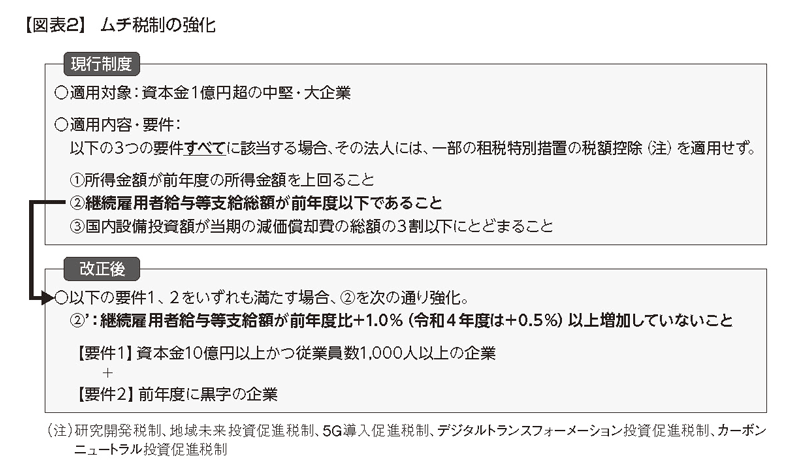
【要件1】は、賃上げ促進税制において、「宣言」の公表・届出を要する企業と同様の定義であり、いわゆる大企業に対象が絞り込まれている。
【要件2】は、赤字から黒字へと転換したばかりの企業にムチ税制を適用するのは避けるべきとの判断から設けられたものである。
ムチ税制が発動され得るのは、上記①〜③の全てに該当する場合であるため、今回の要件厳格化により②に該当した場合でも、③に該当しない場合は影響を受けない。なお、今回の改正においても、①の取り扱いは変わっていないため、前期黒字であっても今期の黒字幅が減少している場合にも、やはりムチ税制は適用されない。
なお、グループ通算制度における適用判定については今後法令を確認する必要がある。
3.期限切れ重要租税特別措置
(1)オープンイノベーション促進税制
① 改正の背景
令和2年度税制改正では、与党大綱に「極めて異例の措置」と明記される形で、オープンイノベーション促進税制が創設された。当該税制措置は、事業会社による一定のベンチャー企業への出資に対し、出資の一定額の所得控除を認めるものである。
令和2年度から本税制措置の適用が開始したところ、ヘルスケア・バイオ・宇宙・AI・モビリティ等の分野において、出資企業とスタートアップ企業のオープンイノベーションの新規案件の成立が見られるようになった。
これに加えて、新政権の「成長と分配の好循環」の実現という大目標の下、スタートアップの徹底支援や、既存企業の事業革新の促進を通じた、企業の付加価値の向上も重点課題となった。
これらが追い風となり、当該税制の延長・拡充に向けた議論が進展することとなった。
② 改正後の制度の概要
適用期限を2年間延長した上で、次の拡充が行われる(図表3参照)。
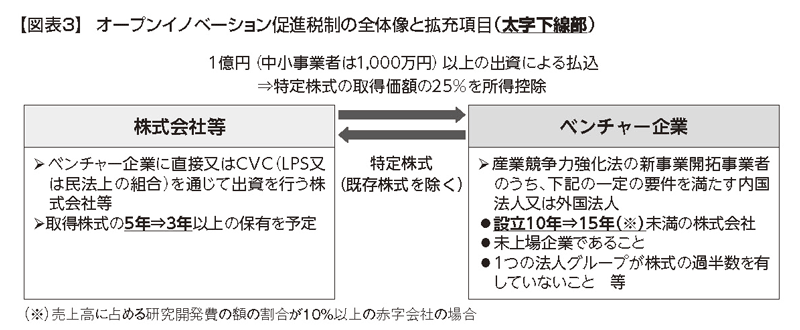
【拡充項目①】
・(a)対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び(b)取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を、特定株式の取得の日から3年(現行:5年)とする。
【拡充項目②】
・出資対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち、設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社について、設立の日以後の期間を15年未満(現行:10年未満)とする。
【拡充項目①】については、出資法人側がより機動的にオープンイノベーションに取り組むことを可能とする観点からの拡充となる。なお、改正時の議論においては、出資金額の下限(現行:1件当たり1億円以上)の引下げについて、出資の受け手となるベンチャー企業のニーズ等も踏まえ、検討の俎上に上っていた模様である。これは、ベンチャー企業としても、大企業から1億円以上の出資を受けて、経営の自由度が損なわれたくないという考えもあったと思われる。しかしながら、大企業の資金余力等に鑑み、出資金額の下限の見直しが実現することはなかった。
【拡充項目②】については、設立10年以上が経過しても、事業拡大のために事業会社が有する資金・技術・販路等が必要なケースも存在することに対応した拡充である。バイオ・素材・宇宙等、事業化までに長期の研究開発期間を要する分野のスタートアップ企業や、未上場の間に積極的な成長投資を行うスタートアップ企業等が存在することが念頭にあると思われる、なお、「売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社」の具体的な定義については、現時点でも調整中と見られ、今後法令等を確認する必要がある。
この他、出資要件に発行済株式の取得をはじめとして、資本金額の増加を伴う株式の取得以外の一定の取得の対象の追加等を行うことも議論された。しかしながら、当該税制措置の創設時の要件設定に係る議論でも、発行済株式の取得まで対象にしてしまうと、スタートアップ創業者を過度に利することになりかねないという懸念が与党税調幹部・税務当局に存在していた。今回の改正においても、こうしたハードルを突破することはかなわなかったようである。
(2)5G導入促進税制
① 改正の背景
令和2年度改正において、安全で信頼できる5Gの導入を促進し、5Gを活用して地域が抱える様々な社会課題の解決を図るとともに、わが国経済の国際競争力を強化するため、5G導入促進税制が2年間の時限措置として創設された。
国税については、主務大臣の認定に基づく特定高度情報通信技術活用システム導入のための5G設備(全国キャリアは、開設計画前倒し分で高度な全国基地局等、ローカル5G免許人は、送受信装置等)について、15%の税額控除又は30%の特別償却を選択することが可能とされた。
新政権の「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けて、5G全国ネットワークについて、高度なインフラを都市・地方で一体的に整備する重要性が一層高まっている。とりわけ、過疎地域等の条件不利地域における整備の加速が必要となっている。これに加えて、企業等の多様な主体が自らシステムを構築するローカル5Gについても、社会課題解決や、事業革新等に向けて、導入の後押しが求められる状況である。
② 改正後の制度の概要
適用期間を3年間に限り延長した上で、対象設備に係る基準・要件の見直しを行うとともに、税額控除率については、事業供用年度に応じて、次の通り段階的縮小が行われる。なお、控除税額の上限は、当期法人税額の20%が維持される。
<全国キャリア:現行15%>
イ 令和4年度:9%(条件不利地域は15%)
ロ 令和5年度:5%(条件不利地域は9%)
ハ 令和6年度:3%(条件不利地域は3%)
<ローカル5G免許人:現行15%>
イ 令和4年度:15%
ロ 令和5年度:9%
ハ 令和6年度:3%
なお、特別償却については、全国キャリア、ローカル5G免許人にかかわりなく、令和6年度にかけて30%が維持される。
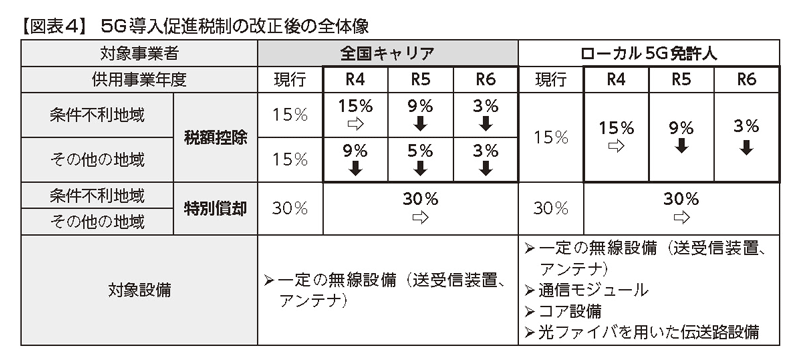
4.グループ通算制度投資簿価修正制度等
(1)改正の背景
グループ通算制度においては、①通算子法人の株式の評価損益・譲渡損益の不計上を通じた租税回避の防止、②グループ通算制度への加入及び離脱を組織再編における合併及び分割と擬制することを通じた、組織再編税制との整合性の確保が目指された。
これを踏まえ、グループ通算制度の投資簿価修正は、連結納税制度とは大きく変化することとなった。すなわち、離脱通算子法人の株式の離脱直前の帳簿価額は、離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額とされた。その帰結として、買収プレミアム付きで買収を行った場合、買収企業を譲渡する際に、譲渡原価に買収プレミアムを算入することができず、単体納税の場合との比較において、譲渡益の過大計上、譲渡損の過少計上が生じることとなった。
令和2年度改正以降、「離脱通算子法人の株式の離脱直前の帳簿価額は、離脱法人の簿価純資産価額に相当する金額とする」という投資簿価修正制度のあり方について、企業の買収・売却を通じた機動的な事業再編を行う企業・関係団体からは、その見直しを求める声が聞かれるようになった。すなわち、買収プレミアムを当該通算法人の株式の譲渡原価に算入できないことに伴い、単体納税はもちろんのこと、従前の連結納税制度と比較しても、譲渡時に課税が発生しうることについての懸念が強まった。
令和4年度税制改正に向けては、企業・関係団体からは投資簿価修正制度の見直しを求める意見が出されたものの、租税回避行為の防止という観点もさることながら、組織再編税制との整合性を確保しつつ、どのように「買収プレミアム相当額」を算定するのかという点が大きなハードルとなった。
(2)改正の概要
現行の投資簿価修正の計算方法を使用することも可能としつつ、一定の要件を満たす場合には、離脱時の通算子法人の株式の譲渡原価に「買収プレミアム相当額」を加算する特例的な取り扱い(以下、特例措置)が認められることとなった。
以下では、本特例措置の対象及び「買収プレミアム相当額」の計算方法を述べた後に、適用要件を見ていく。
まず、対象法人には、連結納税制度からグループ通算制度に移行したグループの連結開始・加入子法人も含まれる。また、対象となる通算子法人からは、主要な事業の継続が見込まれないことにより離脱時時価評価の適用を受ける法人が除かれる。なお、本特例措置は、離脱する通算子法人株式ごとに適用有無を判断することが認められている。
次に、「買収プレミアム相当額」は、「資産調整勘定等対応金額」と呼称され、売却(譲渡)される通算子法人の通算開始・加入前に、通算グループ内の他の法人が時価取得した当該通算子法人株式の取得価額(買収対価)のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時に当該通算子法人を被合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定として計算される金額に相当する金額として定義される。ここで、非適格合併時の資産調整勘定の概念が参照されるのは、組織再編税制との整合性の確保が念頭にあるものと考えられる。他方で、資産調整勘定自体は5年間の均等償却により損金算入されていくのに対し、「資産調整勘定等対応金額」は償却が行われず、残存し続けるという特徴がある。これにより、納税者は、後述の要件を満たすことさえできれば、特に期限を設けることなく「買収プレミアム相当額」を譲渡原価に加算できる。上記は、前頁の図表5の通り、表される。
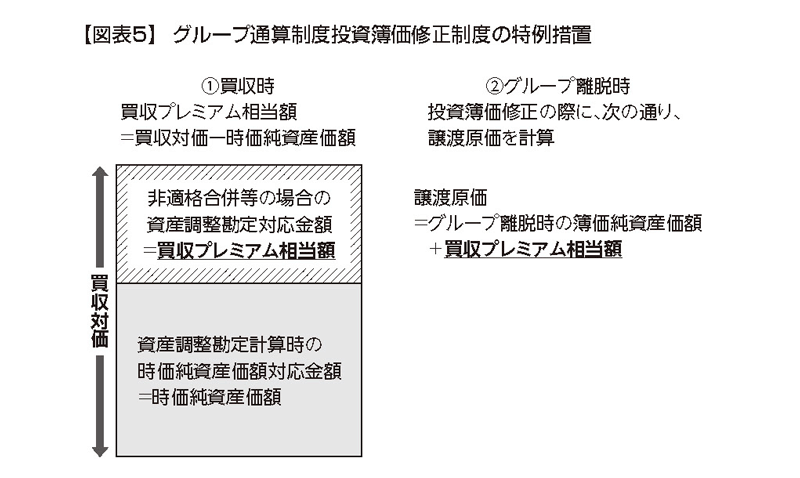
なお、子法人株式の時価取得が段階的に行われる場合又は通算グループ内の複数の法人により行われる場合には、各法人の各取得時における調整勘定として計算される金額に対応する金額に取得株式数割合を乗じて計算した金額の合計額とされる。これは、次の例の通り、計算されると考えられる。
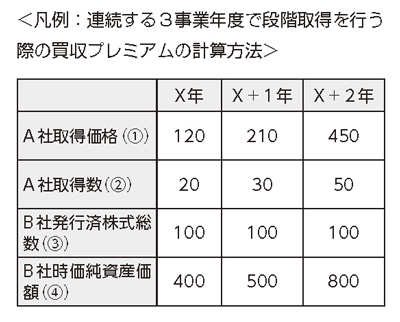
【買収プレミアム(資産調整勘定等対応金額)の計算方法】
・X年(A社がB社の株式の20%を取得)
1株当たり買収対価:120(①)/20(②)=6(⑤)
発行済株式の全てを取得した場合の買収対価:
100(③)×6(⑤)=600(⑥)
買収プレミアム=(600(⑥)-400(④))×20%=40(α)
・X+1年(A社がB社の株式の30%を追加取得)
1株当たり買収対価:210(①)/30(②)=7(⑤)
発行済株式の全てを取得した場合の買収対価:
100(③)×7(⑤)=700(⑥)
買収プレミアム=(700(⑥)-500(④))×30%=60(β)
・X+2年(A社がB社の株式の50%を追加取得)
1株当たり買収対価:450(①)/50(②)=9(⑤)
発行済株式の全てを取得した場合の買収対価:
100(③)×9(⑤)=900(⑥)
買収プレミアム=(900(⑥)-800(④))×50%=50(γ)
【B社の買収に係る買収プレミアム相当額(資産調整勘定等対応金額)】
40(α)+60(β)+50(γ)=150
本特例措置の適用に際しては、通算子法人の株式に係る買収プレミアム相当額(資産調整勘定等対応金額)について、離脱時の属する事業年度の確定申告書に明細を添付し、かつ、その計算の基礎を保存していることが要件とされる。
各時価取得時の買収対価等を明らかにする書類の他、引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例についての書類の保存(法令113②、法規26の2の4①一二)と同様に、当該離脱通算子法人取得時の資産及び負債の価額を明らかにする書類を保存している場合が想定される。
前述の通り、本特例措置は、連結納税制度から通算制度に移行したグループの連結開始・加入子法人や、段階取得時も対象となるが、上記書類の添付、保存に係る要件は必須となる見通しである。すなわち、例えば、連結納税制度への加入が相当程度前であるケースや、50%支配には至らないマイナー取得から始めるケース等において、必要書類の保存がない場合は、買収プレミアム相当額に係る例外的な計算はもちろんのこと、本特例措置の適用自体が認められないと見られる。
これを前提とすると、本特例措置の適用には、大きく次の2点が実務上の課題となると考えられる。
1点目に、既存の連結子法人が段階取得された場合には、段階取得時の関係書類が保存されている必要がある。仮に、当該連結子法人の段階取得が帳簿保存期間である7年間を超える時点で行われた場合には、関係書類の保存の有無を確認することが必須となる。
2点目に、グループ通算制度施行後にグループに加入する通算子法人取得時の関係書類についても、やはり帳簿保存期間である7年間を超えて保存しておく必要が生じる。加えて、マイナー取得から始める場合においても、本特例措置の適用を見据えるのであれば、被買収企業に対して、段階取得時点ごとに必要書類を求めなければならない。
なお、本改正と連動して、通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度について、時価評価資産から除外される資産から帳簿価額1,000万円未満の営業権が除外される。離脱時時価評価は、次のいずれかの場合に該当する際に行われるが、当該見直しは、a)を対象として行われる見通しである。
a)主要な事業を継続することが見込まれていない場合(法法64の13①一)
b)帳簿価額が10億円を超える資産の譲渡等による損失を計上することが見込まれ、かつ、その法人の株式の譲渡等による損失が計算されることが見込まれている場合(法法64の13①二)
前述の通り、事業継続の見込みがない離脱通算子法人は、本特例措置の適用は認められていないが、当該離脱通算子法人は、帳簿価額1,000万円未満の営業権を離脱時に時価評価することが新たに求められる。当該改正の趣旨については、今後の税務当局の解説が待たれるが、実務上は営業権を時価評価する対象法人自体はさほど多くないと考えられる。
5.土地・住宅税制
(1)土地に係る固定資産税等の負担調整措置
令和3年度税制改正では、令和2年1月1日の公示地価とコロナ禍を受けた実勢価格の乖離が予期される下で、地価上昇による税負担の増加が懸念された。これを踏まえ、令和3年度限りの措置として、商業地、住宅用地、農地の区別なく、地価上昇により税額の上昇が見込まれる全ての土地について、令和3年度の課税標準額を令和2年度と同額にする措置が講じられた。
令和4年度税制改正では、商業地等の地価の動向が全国的に不均一、すなわち「まだら模様」であることを踏まえつつ、令和4年度における土地の固定資産税の増加をどの程度許容できるかが大きな焦点となった。与党税調においても、政治的な綱引きが最後まで続いた分野である。
結果として、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行:5%)とすることで決着した(図表6参照)。ただし、令和3年度の課税評価額と当該上昇幅の合計額が、令和4年度の評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とすることとされた。
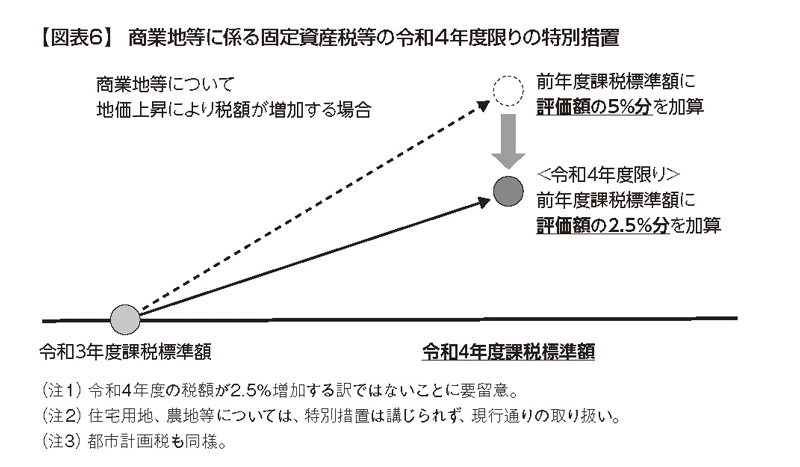
なお、今回の見直しを前提とすれば、令和4年度の課税標準額の上昇幅が半減する商業地も、令和5年度には原則通り令和4年度の課税標準額から上昇することは避けられない。今後の経済情勢等に照らしつつ、税負担のあり方に係る議論の動向に注視が必要である。
(2)住宅ローン控除
令和3年度与党税制改正大綱で触れられている通り、住宅ローン減税については、超低金利環境が続く一方で、控除率が借入残高に対して1%に設定されていることで「逆ざや」が生じていることが会計検査院から指摘がなされていた。
これに加えて、住宅ストックについても、「2050年カーボンニュートラル」目標の実現に向けて、より高い省エネ性能等を有することが目指されるようになった。
こうした背景の下で、住宅ローン控除は、適用期限が4年間延長された上で、次の見直しが行われる(図表7参照)。
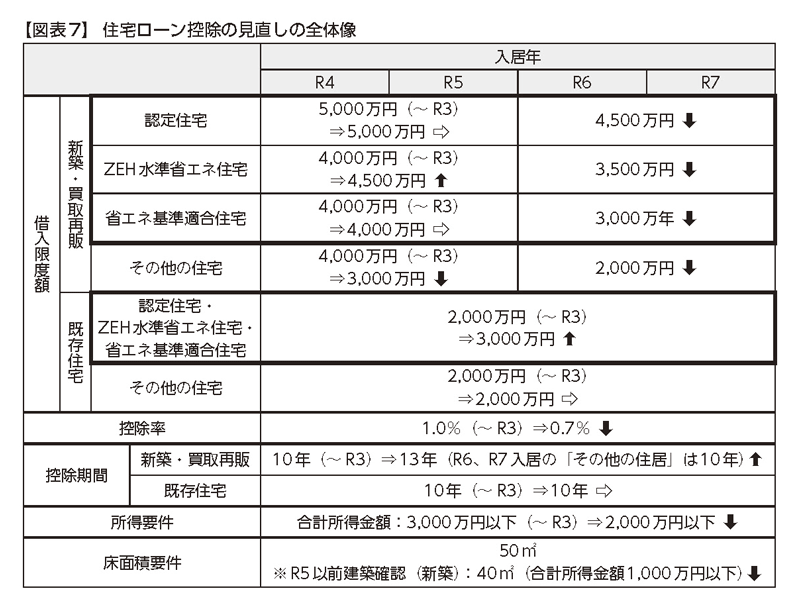
a)2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
・省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
・令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
b)「逆ざや問題」への対応
・控除率を1%から0.7%としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ
c)その他見直し事項
・住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額を3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ(いわゆる富裕層の節税利用の適正化のため)
・合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平米以上に緩和
6.税務手続き関係
(1)電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置
令和3年度税制改正において、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続を定めた電子帳簿保存法が抜本的に見直された。この際、従前は認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止された。
しかしながら、令和4年度税制改正において、その電磁的記録の保存要件への対応が困難である事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられることとなった。
具体的には、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データは、保存要件にしたがって保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面による保存が可能とされた。なお、この2年間の宥恕措置の適用にあたって、納税者から税務署長への手続等は不要である。
(2)地方税における納税環境整備
eLTAXは、インターネットを利用して地方税に係る手続を電子的に行うシステムであり、複数団体に対する電子申告・電子納税を一括で行うことができる他、地方団体と国税当局間の情報連携に活用されている。
令和4年度税制改正では、納税者等が地方団体に対して行う全ての申告・申請手続について、実務的な準備が整ったものから順次eLTAXを利用して行うことができるよう所要の措置を講じることとされた。
また、地方税統一QRコードを活用した納付に係る仕組みの構築に目途がついたことを背景として、eLTAXを通じた電子納付の対象を全税目に拡大するため、所要の措置を講じることとされた。併せて、電子納付に係る納付手段として、納税者が地方税共同機構が指定する者を経由してスマートフォン決済アプリ、クレジットカード等による納付を行うことができるよう所要の措置も講じられる。
7.令和5年度税制改正以降を見据えて
(1)法人税制上の重要租税特別措置
令和5年度税制改正を展望した際に、研究開発税制が大きな目玉となるだろう。当該税制措置の適用総額(財務省「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(令和3年1月国会提出)」に基づくと約5,600億円)に鑑みても、控除上限及び控除率の上乗せ等に係る時限措置については厳しい議論が想定されよう。
他方で、わが国企業のイノベーション創出の観点からは、政府の「第6次科学技術・イノベーション基本計画」(令和3年3月26日閣議決定)での民間企業等の研究開発費に係る目標の達成に向けた取り組みも必要不可欠である。上記の控除上限及び控除率を巡る「伝統的な」議論に加えて、ビジネスモデルの変化に即した試験研究費の範囲のあり方等に係る「先進的な」議論も行われるだろう。
この他、令和3年度税制改正で創設されたDX投資促進税制や、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が令和4年度末に到来することとなり、改正時にも議論が行われると見られる。
更に、自動車関係諸税については、自動車重量税のエコカー減税、種別割のグリーン化特例の適用期限が到来する。令和4年度与党税制改正大綱の検討事項では、前年度に引き続き「(各種技術革新や経済社会の変化への対応に向けて)受益と負担の関係も含め、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う」と記載されている。引き続き注視が必要な分野であろう。
(2)中期課題
与党大綱での記載ぶりが注目された事項は大きく3点ある。
1点目は、カーボンプライシングである。各種調整の上に、「検討事項」においてカーボンプライシングという文言は明記されなかった。カーボンプライシングの枠組みを巡って議論が十分に煮詰まってないことを反映したものと思われる。他方で、カーボンニュートラルの実現に向けた世界的な潮流はとどまることを知らない。OECD事務局においても、デジタル課税の次なる課題は“Environmental Taxation”と目されており、わが国として今後も議論自体を避けることはできないと思われる。
2点目は、金融所得課税である。「検討事項」への記載はなく、前文において、「一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う」とされた。①対象となる所得階層、②税率のあり方に照らして、どの程度の見直しが社会的に許容されるのか、そして政治的コストを払うことができるかが焦点となるだろう。
3点目は、国際課税である。デジタル経済に対する国際課税の枠組みについては、昨年10月に国際的な政治的合意がなされた。これを踏まえ、「第1の柱(国家間の利益の再配分ルール)」、「第2の柱(ミニマム課税)」の詳細なルール設計に向けた各種調整が続けられている。わが国企業に対して、より広範な影響をもたらしうるのは、「第2の柱」となり、その国内法制化が令和5年度税制改正以降の大きな課題となる。これを踏まえ、既存のわが国の外国子会社合算税制(CFC税制)の抜本的な簡素化を求める声が企業側から強まりを見せているが、制度趣旨等に鑑み、どのような簡素化の「青写真」を描けるかが今後の重要な検討課題と言えよう。
(3)法人税収と企業の創出する付加価値を巡って
本稿の締めくくりとして、令和4年度税制改正による増減収見込額に言及したい。国税については、初年度約740億円の減収、平年度約1,640億円の減収見込みである。内訳を見れば、賃上げ促進税制の抜本的な強化による減収幅が相当程度に大きいと言える。他方で、本稿では触れなかったが、完全子会社株式等の配当に係る源泉徴収の見直しに伴う「期ずれ」により、所得税及び法人税あわせて、令和5年度に約8,000億円の減収が生じ、令和7年度に同額の増収が見込まれる。
上記の税収を取り巻く状況、今後のマクロ経済環境、そして冒頭の与党大綱における「経済界への期待」を踏まえれば、令和5年度税制改正においては、法人税制全般において、税源見合いでの「適正化」が検討の俎上に上る可能性は決して低くないだろう。その一方で、与党税調においても、持続的な賃金引上げに向けて、その原資となる付加価値の向上に向けた税制措置の必要性が言及されている模様である。
法人税収の増加と企業の創出する付加価値の拡大の両立を巡って、来年度税制改正においても激しい綱引きが行われるだろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















