解説記事2022年10月03日 巻頭特集 経産省・R5税制改正要望“深読み” 第二弾(2022年10月3日号・№948)
巻頭特集
個人の株式税制が論点に 譲渡益を14億円まで非課税、適格SOも拡充
経産省・R5税制改正要望“深読み” 第二弾
前号の特集では、経済産業省の令和5年度税制改正要望のうち、外国子会社合算税制の事務負担軽減、研究開発税制における「サービス開発の要件の見直し」「一般型のインセンティブ強化」、「一部持分を残したスピンオフ」に対するスピンオフ税制など企業税制についてお伝えしたが、今回は、岸田政権の政策の柱である「スタートアップ」を後押しする個人の株式税制を取り上げる。
なかでも、実現すればインパクトが大きいのが、“日本版QSBS”の導入だ。経産省の税制改正要望では「エンジェル税制についての必要な見直しも含め、個人のリスクマネーがスタートアップ・エコシステムに循環することを促す税制措置」との記述にとどまっているが、本誌取材により、この要望が米国で導入されているキャピタルゲインの非課税制度(QSBS)を念頭に置いていることが判明した。米国では、起業家や従業員を対象に、5年以上保有する自社株式を売却して発生した譲渡益を年間1,000万ドル(約14億円)まで非課税とし、さらに当該売却益をスタートアップに再投資する場合、課税の繰り延べを可能としている。日本のエンジェル税制がスタートアップ投資について所得控除や株式譲渡益控除等しか認めていないことを考えると、かなり大胆な提案と言えるだろう。
また、経産省は現行税制適格ストックオプションの拡充も視野に入れている。本誌取材によると、最長10年間とされている権利行使期間を「15年」に延長するほか、年間合計額1,200万円以下とされる現行の権利行使価額要件を引き上げる案も浮上している。
株式売却益への課税
個人が自社株売却益をスタートアップに再投資なら課税繰延べ
「スタートアップ」が岸田政権の政策のキーワードとなる中、経済産業省は令和5年度税制改正で「我が国のスタートアップ・エコシステムの抜本強化のための個人によるスタートアップ投資を促進する税制措置の検討」を要望している。財務省のWEBサイトで公開されている要望の詳細版にも、「エンジェル税制についての必要な見直しも含め、個人のリスクマネーがスタートアップ・エコシステムに循環することを促す税制措置」を検討するとある(30−1参照)。
周知の通り、エンジェル税制は優遇措置A・B(Aが所得控除、Bが株式譲渡益控除)などからなる個人のスタートアップ投資を支援する特例措置であるが、経産省の税制改正要望にある現行制度に対する「必要な見直し」という記述のみからは、それが具体的に何を指しているのかは見えにくい。
これを読み解くカギを握るのが、内閣府の動きだ。財務省WEBサイトに掲載された各省庁の要望のラインナップを見ると、内閣府は「我が国のスタートアップ・エコシステムの抜本強化のための個人によるスタートアップ投資を促進する税制措置の検討」という経産省と全く同じ要望を提出している(6−1参照)。要望の担当課は「科学技術・イノベーション推進事務局」となっている。同事務局に設置された総合科学技術・イノベーション会議の「イノベーション・エコシステム専門調査会」が6月にとりまとめたのが、「世界に伍するスタートアップ・エコシテムの形成について」と題する報告書だ。
この報告書を読むと、米国のQSBSというキャピタルゲイン非課税制度(図1、下記の報告書抜粋参照)に関する記述がある。同趣旨の制度は、英国やベルギーなどでも導入されているという。「一定額」とは年間1,000万ドルであり、日本円では約14億円(1$=140円)にものぼる。
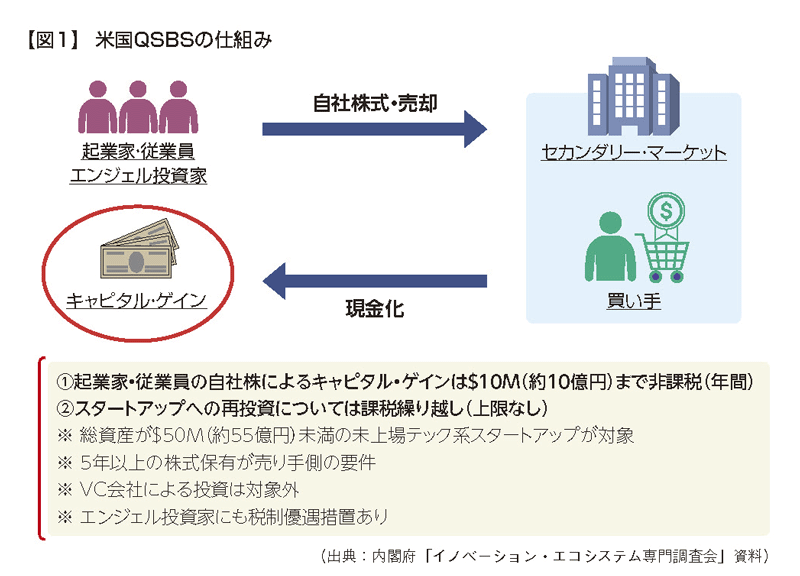
| 米国では、リスクを取って挑戦する起業家や従業員に対し、5年以上保有する自社株式(QSBS:Qualified Small Business Stock)を売却して発生した譲渡益(長期的キャピタルゲイン)に対し一定額まで非課税とし、さらにQSBSの売却によって得た利益をスタートアップに再投資する場合に、課税の繰り延べが可能となっている。これにより、起業家・従業員の現金化の機会を与え、生活の安定化や未上場段階での長期にわたる成長とともに、エンジェルになって次の若い起業家を支援する好循環につながっているとの指摘がある。 |
財務省の“1億円の壁”論とは逆方向、与党内にも免税には慎重な声
内閣府の狙いは、端的にいえば、“日本版QSBS”の創設にある。現行のエンジェル税制では、スタートアップ投資について所得控除や株式譲渡益控除等を認めるにとどまっており、米国のような規模の免税までは認められていないため、かなり大胆な提案と言える。
要するに、経産省の税制改正要望は“内閣府発の共同戦線”と見てよいだろう。一方で、財務省サイドは、かねてから“1億円の壁”問題(分離課税となっている金融所得の多い富裕層の所得税負担率が、所得1億円を境に大きく減少していること)を背景に、高額所得者を念頭に金融所得課税の見直しが必要ではないかと主張してきたところ(図2、本誌919号4頁〜参照)。
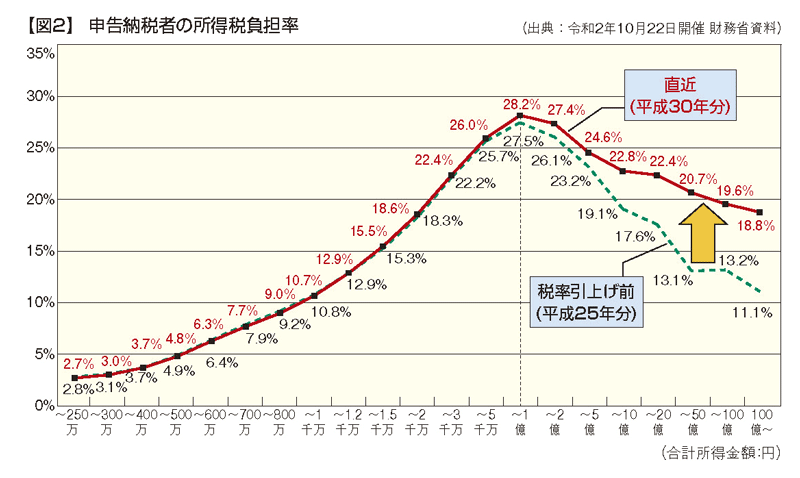
これは内閣府とは逆方向の意見であるが、金融所得が多い富裕層への課税強化は財務省の念願とも言える。また、与党内からも「ツイッターでお金を配る者がいる。創業期等はともかく、あのような功成り名を遂げた者がキャピタルゲイン免税を安易に享受するような税制でよいのか」との声が聞こえてくる。
スタートアップ振興税制が令和5年度税制改正の中心課題の1つとなることは間違いないが、議論はかなり紆余曲折するだろう。
税制適格ストックオプション
権利行使期間延長、権利行使価額要件の引上げも
同じくスタートアップを支援する改正として、ストックオプション税制の拡充が盛り込まれた(財務省WEBサイトの経産省要望06−1参照)。
周知の通り、ストックオプション税制とは、取締役や従業員に付与される新株予約権の一種であるストックオプションについて一定の要件を満たす場合、権利行使時における取得株式の時価と権利行使価額との差額に対する所得課税を株式売却時まで繰り延べる仕組みであり(措法29の2)、株式売却時には売却価格と権利行使価額との差額が譲渡所得として課税されることになる。
平成31年度税制改正では、スタートアップによる外部高度人材の確保の観点からストックオプション税制が拡充され、外部協力者(弁護士、会計士、プログラマー、エンジニア等)を活用して行う事業計画について主務大臣の認定を受けた場合には、当該外部協力者へ付与したストックオプションについても取締役や従業員と同様、課税の繰り延べを適用することとされたところ。企業はこの改正を評価する一方、スタートアップの成長を後押しするという観点からはまだ不十分として、ストックオプション税制のさらなる拡充を求める声も根強い。
その一つが、権利行使期間要件の延長だ。現状、「付与決議日の2年後から10年後まで」とされているが、創業から上場までの期間が長いスタートアップにあっては、創業当初に付与したストックオプションが上場前に税制上、失効してしまう恐れがあることから、「短すぎる」との指摘がある。令和5年度税制改正議論ではこれをどこまで延ばせるかが焦点となる。令和4年度税制改正では、オープンイノベーション促進税制を延長するとともに、大規模な研究開発を行うディープテック企業を想定し、出資先のスタートアップの要件が「設立後10年未満」から「15年未満」に延長されたことを踏まえると、この改正を前例として、ストックオプション税制についても、権利行使期間を「15年」等へと大幅に延長する案が検討される可能性がありそうだ。この場合、研究開発型等の要件を付すべきではないとの意見も出ている。
“新しい資本主義”の追い風、総理も決意表明
権利行使価額要件の引上げについては、「権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと」という現行の権利行使価額要件に対し、「高度人材にとって魅力的ではない」との指摘が多い。ただ、(1)複数年に渡って権利行使をすれば上限に突破するわけではないこと、(2)米国のストックオプション税制でも上限が10万$とされており、殊更に日本の制度が見劣りしているわけではないことを踏まえると、要望の実現に向けたハードルは低くないが、企業サイドは少なくとも議論の俎上に載せることを期待している。
岸田政権が「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」でスタートアップ振興を掲げたことは本稿で取り上げた要望の追い風になろう。つい最近、岸田総理はニューヨーク証券取引所において、「大切なのは、スタートアップを生み育てるエコシステムを日本に作り上げること。そのために、株の売却益を元手にスタートアップ投資を行う場合の税優遇措置や、ストックオプション税制の拡充が必要だ」と明言している。総理が決意表明した以上、何らかの税制改正があることは確実だろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























