解説記事2023年04月17日 実務解説 有価証券報告書 作成上の留意点(2023年3月期提出用)(2023年4月17日号・№975)
実務解説
有価証券報告書 作成上の留意点(2023年3月期提出用)
財務会計基準機構 桐島雄太
財務会計基準機構 曽根由香里
《まとめ》
・「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、「管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」、「サステナビリティに関する考え方及び取組」、「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況」及び「株式の保有状況」について開示の新設及び拡充が行われている。
・改正「時価の算定に関する会計基準の適用指針」、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を中心とした項目に注意が必要。
・このほか、「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」についても留意が必要。
Ⅰ はじめに
本稿は、2023年3月期の有価証券報告書(以下「有報」という。)における作成上の留意点についてまとめたものであり、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)の改正を踏まえた有報の開示に関する留意点、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「実務対応報告第42号」という。)等に関する主な留意点を中心に解説する。
なお、文中において意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添えておく。
Ⅱ 開示府令の改正を踏まえた有報の開示に関する留意点
1 概 要
2022年6月13日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告における「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」及び「コーポレート・ガバナンスに関する開示」についての提言を受けて、2023年1月31日付で「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第11号)が公表された。
2 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
改正開示府令により、提出会社及びその連結子会社それぞれについて、当事業年度における管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金の差異(以下「女性管理職比率等」という。)を記載することとされた(開示府令第三号様式が準用する第二号様式記載上の注意(以下「記載上の注意」という。)(29)d~f)。
これら3つの指標は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)又は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づき公表されるものを有報においても開示対象とするものとされている。そのため、女性活躍推進法又は育児・介護休業法の規定に基づき女性管理職比率等の公表を行わない会社については、その記載を省略することができるとされている(記載上の注意(29)d~f)。また、例えば、女性活躍推進法に基づき雇用管理区分ごとの男性労働者の育児休業取得率を公表している場合には、有報で報告する男性労働者の育児休業取得率についても、女性活躍推進法に基づいて実際に公表している雇用管理区分ごとの実績を記載することになる。
記載事例1では、管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異について、提出会社と連結子会社に分けてそれぞれ表形式で記載している。
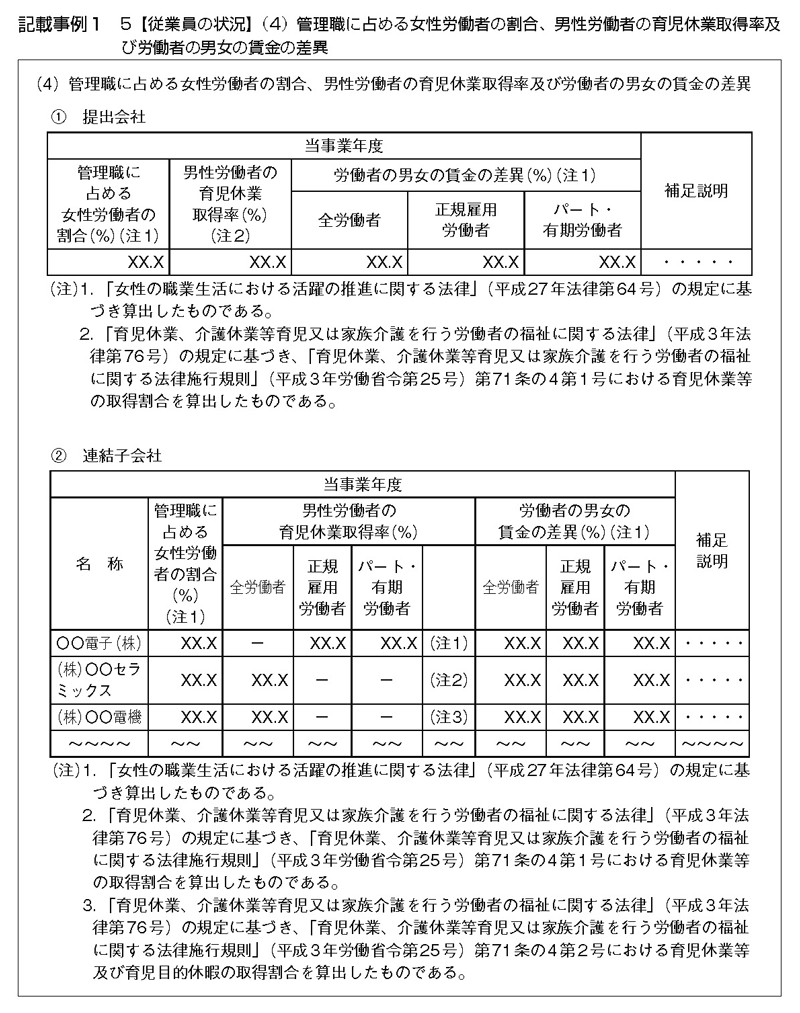
管理職に占める女性労働者の割合については、女性活躍推進法の規定に基づき算出した比率を記載することとされている。男性労働者の育児休業取得率については、同じグループ会社であったとしても、どの法律に基づいて公表しているか、また、どの割合を算出しているかが会社ごとに異なっている場合があるため、注意が必要である。すなわち、①女性活躍推進法に基づき雇用管理区分ごとの育児休業取得率を開示する会社、②育児・介護休業法に基づき育児休業等の取得割合を開示する会社、③育児・介護休業法に基づき育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を開示する会社の3つのケースが想定される。
記載事例1では、
・連結子会社〇〇電子(株)については、①女性活躍推進法に基づき雇用管理区分ごとの育児休業取得率を開示するケース
・提出会社及び連結子会社(株)〇〇セラミックスについては、②育児・介護休業法に基づき育児休業等の取得割合を開示するケース
・連結子会社(株)〇〇電機については、③育児・介護休業法に基づき育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を開示するケース
を想定している。
労働者の男女の賃金の差異については、女性活躍推進法の規定に基づき算出した比率を、全労働者及び雇用管理区分ごとに記載することとされている。また、投資者の理解に資するように、任意でより詳細な情報や補足的な情報を記載することも可能とされており、補足説明欄において記載することが考えられる。
改正開示府令では、提出会社及びすべての連結子会社についてそれぞれ3つの指標を開示することが求められているが、主要な連結子会社以外については、「第一部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「2 その他の参考情報」に記載することができるとされている(記載上の注意(29)g)。この場合、記載事例2脚注4で示しているように、その箇所を参照する旨を記載することとされている。なお、参照先である「第一部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「2 その他の参考情報」においても、提出会社及び主要な連結子会社については、「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「5 従業員の状況」の「(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」を参照する旨を記載することが考えられる。
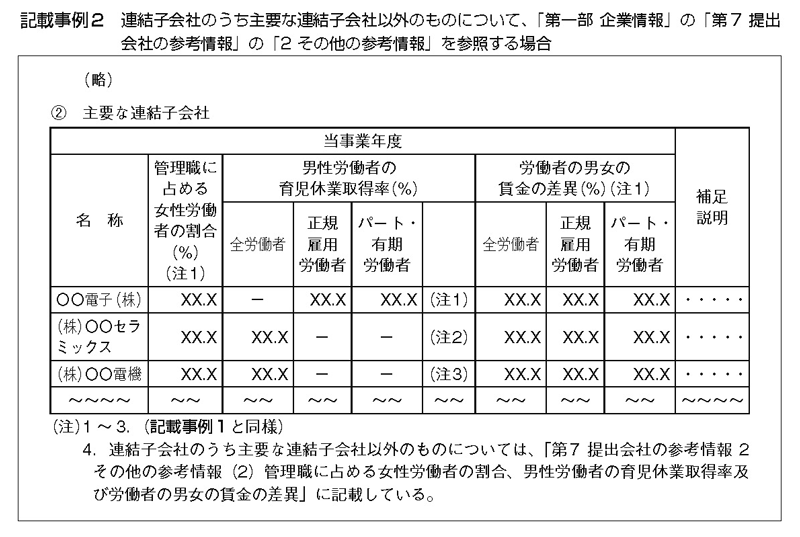
改正開示府令と同時に公表された、「記述情報の開示に関する原則」(別添)−サステナビリティ情報の開示について−(金融庁 2023年1月31日公表)(以下「開示原則(別添)」という。)によれば、(望ましい開示に向けた取組み)(注2)として、3つの指標については、投資判断に有用である連結ベースでの開示に努めるべきであるとされた。記載事例3は、改正開示府令で求められる開示ではないが、提出会社及び連結子会社についての開示に加えて、連結ベースでの状況についても開示を行う場合を示している。
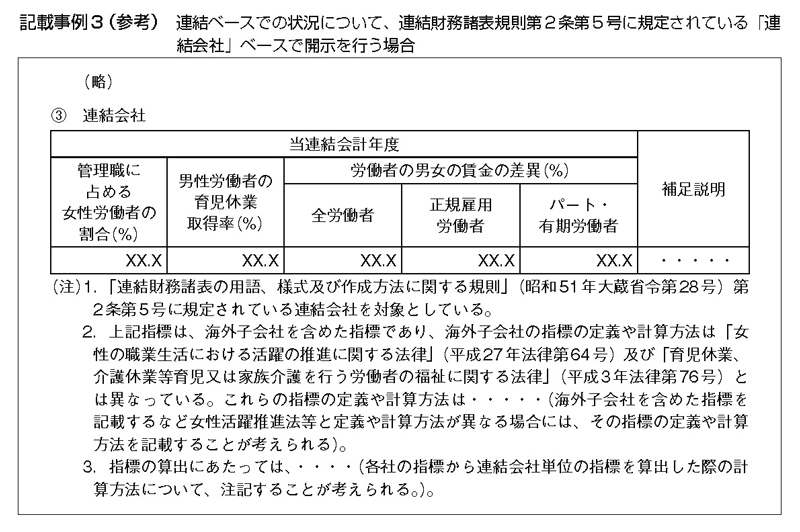
連結ベースでの状況の記載については、連結グループをどう捉えて開示するかがポイントとなる。記載事例3は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている「連結会社」ベース、すなわち、会計上の連結範囲で集計する場合を想定しているが、それ以外の独自のグループベースでの開示を行うことも可能である。
独自のグループベースで開示を行う場合については、会計上の連結範囲で集計していると誤解されないように、以下のようにすることが考えられる。
・「連結会社」及び「当連結会計年度」の表記は使用しない。
・投資家に有用な情報を提供する観点から、提出会社グループのうち、より適切な範囲を開示対象とする場合には、開示対象とした範囲について記載する。
・提出会社グループに含まれる各社の事業年度が提出会社と異なり、各指標の数値についても、当該異なる事業年度ベースで集計している場合、そのことがわかるよう、各社の事業年度ごとに集計している旨を注記する。
3 サステナビリティに関する考え方及び取組
(1)概 要
改正開示府令により、当連結会計年度末における連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組について記載することとされた。このサステナビリティに関する考え方及び取組の記載は、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」の4つが構成要素とされている。このうち、「ガバナンス」及び「リスク管理」については、重要性にかかわらず、すべての提出会社において記載が求められる。一方で、「戦略」並びに「指標及び目標」については、重要なものについて記載することとされている。このほか、人的資本(人材の多様性を含む。)に関する「戦略」並びに「指標及び目標」については、重要性にかかわらず、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針を「戦略」の構成要素として記載し、当該方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績を「指標及び目標」の構成要素として記載することとされている(記載上の注意(30−2))。
サステナビリティに関する考え方及び取組の記載は、具体的な記載方法については詳細に規定されておらず、また、現時点においては我が国における開示基準は定められていないところ、2023年3月期は各社の取組状況に応じて柔軟に開示を行い、その後、投資家との対話を踏まえ、自社のサステナビリティに関する取組の進展とともに開示を充実させていくことが考えられるとされている。
そのため、2023年3月期の有報におけるサステナビリティに関する考え方及び取組の記載については、各社の取組状況に応じて、さまざまな方法が考えられる。例えば、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」の各構成要素に分けた記載を行わず、一体として記載することも考えられる。この場合には、投資家が理解しやすいよう、4つの構成要素のどれについての記載なのかがわかるようにすることも有用と考えられる。
本稿では、参考として2例の記載事例(記載事例4、記載事例5)を示しているが、サステナビリティに関する考え方及び取組の記載についてはさまざまな方法が考えられるため、各社の取組状況に応じて柔軟に開示を行うことが考えられる点、改めてご留意いただきたい。
記載事例4は、サステナビリティ情報全体について、サステナビリティに関する考え方及び取組の記載を行う場合を想定している。記載事例4では「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」の4つの構成要素を分けているが、一体として記載することも可能である。「戦略」及び「指標及び目標」については、重要性を判断したうえで、記載しないことが認められているが、開示原則(別添)(望ましい開示に向けた取組み)によれば、その場合でも、当該判断やその根拠の開示を行うことが期待されるとされている。人的資本(人材の多様性を含む。)に関する開示は、重要性にかかわらず、すべての会社で「戦略」並びに「指標及び目標」に関して開示が必要である。本稿では、人的資本(人材の多様性を含む。)に関する「指標及び目標」について、連結グループベースでの目標及び実績を記載する方法で記載している。一方で、人材育成等がすべての会社では行われてはいないなど、連結グループにおける記載が困難である場合には、その旨を記載した上で、例えば、連結グループにおける主要な事業を営む会社単体(主要な事業を営む会社が複数ある場合にはそれぞれ)又はこれらを含む一定のグループ単位の指標及び指標の開示を行うことも考えられる。
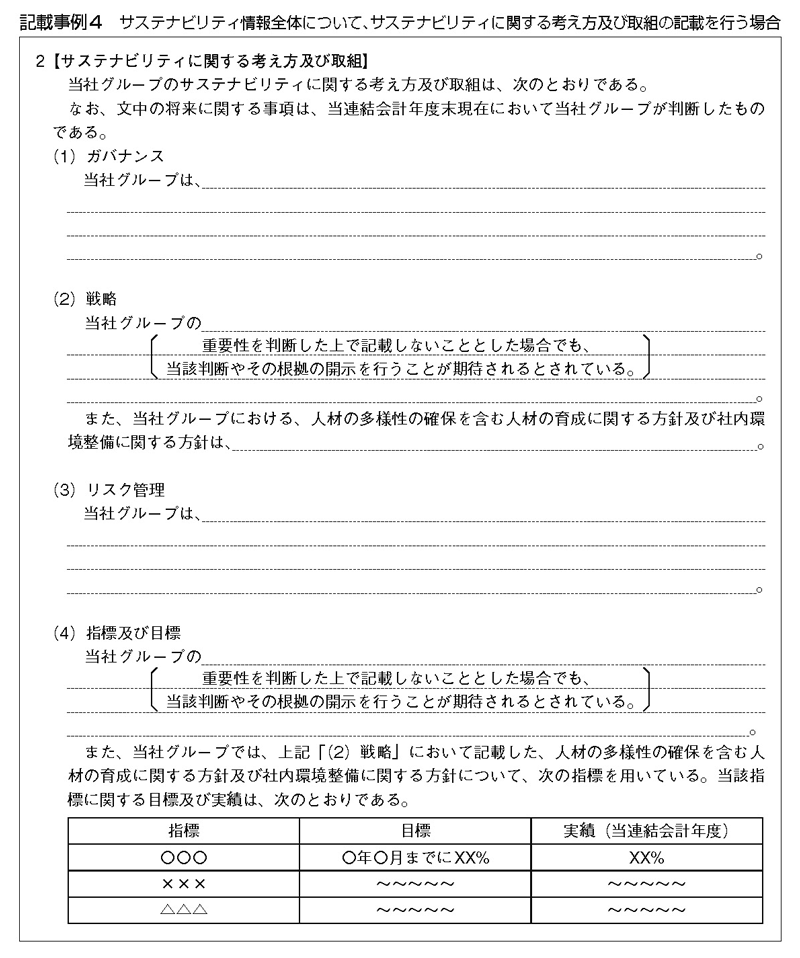
記載事例5は、重要なサステナビリティ項目ごとに、サステナビリティに関する考え方及び取組の記載を行う場合を想定している。(1)において、サステナビリティ全般に関するガバナンス及びリスク管理を記載し、(2)として、その枠組みを通じて識別された重要なサステナビリティ項目を示し、それぞれの項目別に4つの構成要素に関する記載を行うことを想定している。
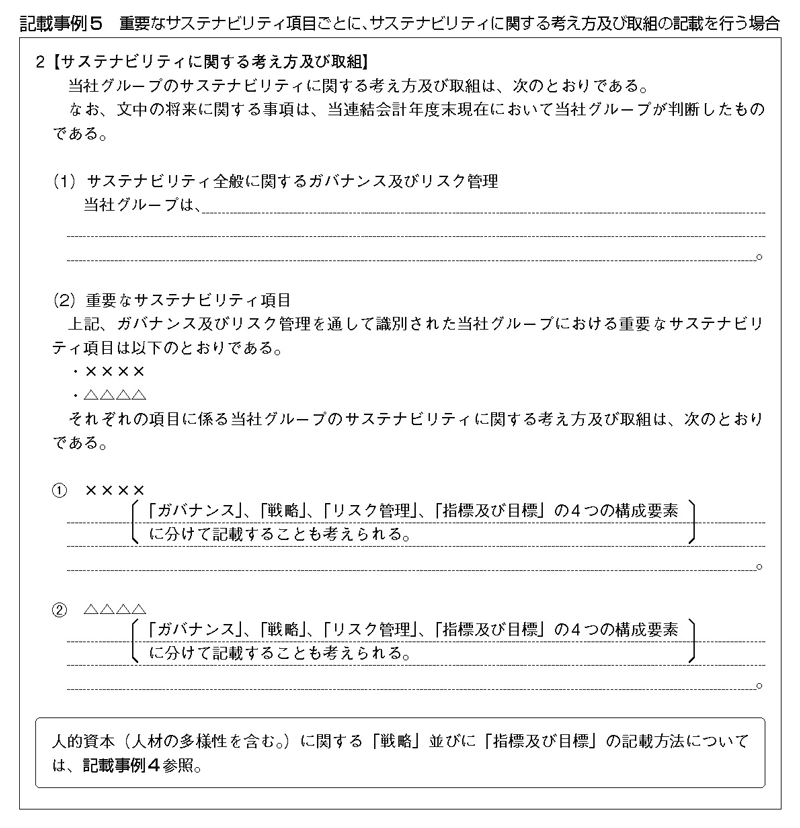
(2)留意点
改正開示府令では、記載すべき事項の全部又は一部を有報の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができるとされている(記載上の注意(30−2)ただし書き)。これに関して、2023年に改正された「企業内容等の開示に関する留意事項について」(以下「開示ガイドライン」という。)5−16−5では、例えば、サステナビリティに関する考え方及び取組に記載する人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針(人材の多様性の確保を含む。)に関する指標を用いた目標及び実績として、女性管理職比率等を「従業員の状況」において記載している場合が含まれることに留意するとされている。ただし、サステナビリティに関する考え方及び取組については、基本的には連結ベースでの「指標及び目標」を開示することが想定されている。「従業員の状況」における女性管理職比率等に関する開示は、提出会社及び連結子会社それぞれについて記載することとされているため、参照する場合には留意が必要である。
改正開示ガイドライン5−16−4において、他の公表書類を参照する場合の取扱いについて規定された。すなわち、有報に記載したサステナビリティに関する考え方及び取組を補完する詳細な情報については、提出会社が公表した他の書類を参照することができる旨、また、他の公表書類に明らかに重要な虚偽があることを知りながら参照する等、当該書類を参照する旨を記載したこと自体が有報の虚偽記載等になり得る場合を除き、直ちに有報に係る虚偽記載の責任を負うものではない旨が示された。
また、改正開示ガイドライン5−16−2において、将来情報の記述と虚偽表示の責任について規定された。すなわち、将来に関する事項で有報に記載すべき重要な事項について、一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、有報に記載した内容と実際に生じた結果が異なる場合であっても、直ちに虚偽記載等の責任を負うものではないと考えられる旨が示された。また、説明を記載するに当たっては、例えば、当該将来情報について社内で合理的な根拠に基づく適切な検討を経たものである場合には、その旨を、検討された内容の概要とともに記載することが考えられるとされている。なお、この改正開示ガイドライン5−16−2は、「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」までの将来情報について規定されている。
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの概要
改正開示府令により、提出会社の取締役会等の活動状況として、開催頻度、具体的な検討内容、個々の取締役又は委員の出席状況等について記載することとされた。ここでいう「取締役会等」には「提出会社の取締役会」、「指名委員会等設置会社における指名委員会及び報酬委員会」及び「企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するもの」が含まれる。ただし、「企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するもの」のうち、「指名委員会等設置会社における指名委員会又は報酬委員会に相当するもの」以外のものについては、記載を省略することができるとされている(記載上の注意(54)i)。
(2)監査の状況
改正開示府令により、「監査役監査の状況」については、「主な検討事項」の記載から「具体的な検討内容」の記載に用語の見直しがされた(記載上の注意(56)a(b))。これは、単に規定された検討事項ではなく、実際に監査役会において検討された内容の開示を求める趣旨を明確化するために行われたものであり、開示事項を実質的に変更するものではないと考えられる。
また、「内部監査の状況」については、改正開示府令により、内部監査の実効性を確保するための取組を具体的にかつ分かりやすく記載することとされた(記載上の注意(56)b(c))。この改正の趣旨は、2021年6月のコーポレートガバナンス・コード再改訂において、上場企業は、デュアルレポーティングラインを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保することが求められ、2022年6月13日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、「デュアルレポーティングラインの有無を含む内部監査の実効性の説明を開示項目とすべきである」と提言されたことを受けたものと考えられる。
(3)株式の保有状況
改正開示府令により、政策保有株式について、保有目的が提出会社と当該株式の発行者との間の営業上の取引、業務上の提携その他これらに類する事項を目的とするものである場合には、当該事項の概要を記載することとされた(記載上の注意(58)d(e))。
Ⅲ 財務情報に係る留意点
1 時価の算定に関する会計基準の適用指針に係る留意点
2021年6月に企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から公表された改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「改正適用指針」という。)は、投資信託の時価の算定に関する取扱い及び貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いについて明らかにするものであり、適用時期は、2022年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされている。その詳細は、山田哲也「改正企業会計基準適用指針第31号『時価の算定に関する会計基準の適用指針』の概要」(No.895)を参照いただきたい。
(1)会計方針の変更に関する注記
改正適用指針の適用初年度においては、当該適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとされている。この場合、その変更の内容について注記することとされている。
(2)金融商品関係注記
連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、金融商品の時価等に関する事項の記載を要しないとされている。ただし、この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならないとされている。
投資信託等については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、金融商品の時価等に関する事項の記載については、その記載にあたり、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
また、投資信託等については、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の記載を要しないとされているが、この場合には、当該事項を注記していない旨、当該投資信託等の連結貸借対照表計上額及び当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)等を注記しなければならない。
2 グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いに係る留意点
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、連結納税制度の適用対象となる企業は、2022年度からグループ通算制度に移行することとなった。そのため、ASBJは、2021年8月に実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表し、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた。当実務対応報告は、2022年4月1日以後に開始する年度の期首から適用することとされている。その詳細は、宗延智也「実務対応報告第42号『グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い』の概要」(No.900)を参照いただきたい。
税効果会計関係
当実務対応報告第42号に従って法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理を行っている場合には、その旨を税効果会計に関する注記の内容とあわせて注記するものとされている。
3 その他の留意点
(1)「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」に係る留意点
2022年8月26日にASBJから実務対応報告第43号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」が公表された。当該実務対応報告は2023年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用することとされている。ただし、当該実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができるとされている。その詳細は、若尾健二「実務対応報告第43号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い』の解説」(No.949)を参照いただきたい。
(2)「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」に係る留意点
2023年3月31日にASBJから実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」が公表された(以下「実務対応報告第44号」という。)。実務対応報告第44号は、公表日以後適用することとされている。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立している(以下、改正法人税法が成立した2023年3月28日を「改正法人税法の成立日」という。)。
実務対応報告第44号では、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、当面の間、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととされている。また、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計については、現行の枠組みにおいて適用すべきか否かが明らかではないと考えられること、さらに、仮に税効果会計を適用する場合、グローバル・ミニマム課税制度に基づく税効果会計の会計処理については明らかではないと考えられる点があることを踏まえ、原則的な取扱いの適用を認めず、当該特例的な取扱いを一律に適用することとされている。
また、その範囲については、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後その適用が見込まれるか否かの判断について、企業が適時にかつ適切に行えるか懸念があるとの意見が聞かれたことを踏まえ、一律に、企業会計審議会が1998年10月に公表した「税効果会計に係る会計基準」が適用される連結財務諸表及び個別財務諸表に適用することとされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























